デジタル技術を基礎から実践まで幅広く学べる「さくらのクラウド検定」
>>無料で学ぶ

神奈川県立横須賀高校は、2016年に文部科学省のスーパーサイエンスハイスクール(以下、SSH)の指定を受け、理数教育の強化と未来の科学技術を担う人材育成に力を入れています。その取り組みの一環として、さくらインターネットとの連携が始まりました。2025年9月から、同校の1年生が「クラウド」と「衛星データ」の活用をテーマにした課題研究に取り組んでいます。
今回は、横須賀高校の龍見玄太郎先生と、さくらインターネットの戸倉大輔に、連携の経緯や横須賀高校の目指す理数教育の在り方、今後の展望などについてインタビューしました。
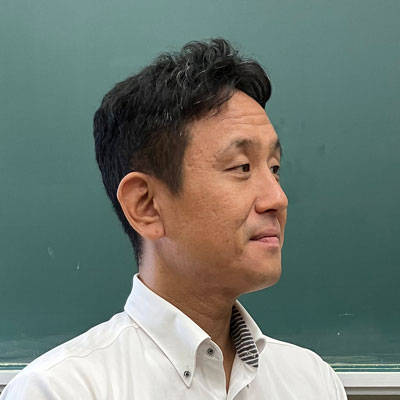
龍見 玄太郎(たつみ げんたろう)先生 プロフィール
国際物流の民間企業勤務を経て2012年に教育の道に進み、現在は横須賀高校の英語教員として授業や学習指導を担当している。実践的な英語力の育成を重視し、アクティブラーニングやICTを活用した教育スタイルを推進。剣道四段の資格を持ち、部活動指導にも力を注いでいる。戸倉とは高校時代からの剣道仲間。
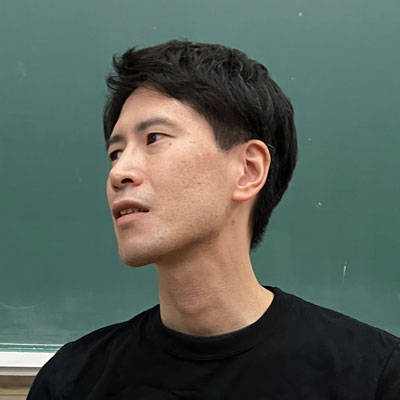
戸倉 大輔(とくら だいすけ) プロフィール
SIerでの勤務を経て、2021年にさくらインターネットに入社。現在はテクニカルソリューション本部 ラーニングサポート部に所属し、全国の高等専門学校への出前授業や「さくらのクラウド検定」を通じた次世代教育支援などを担当する。
SSH指定校の「課題研究」をさくらのクラウドで支援
横須賀高校とさくらインターネットの連携の経緯についてお聞かせください。

私と戸倉さんは、高校時代、同じ剣道部に所属していました。その縁で、卒業後も連絡をとったり、話をしたりする機会があり「さくらインターネットで次世代教育支援に取り組んでいる」と聞いて興味を持ったのが始まりです。
横須賀高校は、SSHの課題研究で、文理を問わずさまざまな外部機関と連携しています。たとえば金沢文庫さんと連携した古文書の読解や、防衛大学校さんと連携した宇宙工学分野の取り組みなどです。しかしこれまで、アプリやICTサービスの開発に関する分野は不十分で、生徒の需要がある一方で、なかなか連携先を見つけられずにいました。
また、通年での指導が必要な活動になるため、企業側の負担が大きいという課題があります。そのため、引き受けていただけるかは心配だったのですが、当校の取り組みを紹介したところ、「ぜひチャレンジしたい」と言っていただきました。

さくらインターネットは、これまでも高専との連携や、小学生向けのIT教育支援をおこなっています。龍見先生からお話を聞いて、SSHの高校生に対しても、将来を見据えた実践的な学習に触れるお手伝いができるのではないか、と考えました。
ICT分野であれば、ガバメントクラウドにも選ばれている「さくらのクラウド」(※条件付き認定)を活用して、生徒さんの研究をサポートできる。また、同時期に高専生向けの授業を検討していた衛星データについても、グループ会社(Tellus)を通じてテーマとして扱えると提案させていただきました。
課題研究は「社会で生きるためのスキル」を得るトレーニング
横須賀高校が指定されている「SSH(スーパーサイエンスハイスクール)」とは、どのようなものなのでしょうか。

本校のSSH指定は、ただ理数教育を強化するだけではない、「課題を見つけて、解決する能力」や、それを支える論理的思考力、コミュニケーション力などの汎用的な能力の育成をねらいとしています。
その取り組みの中核にあるのが、課題研究科目「Principia(プリンキピア)」です。ニュートンの著書『プリンキピア』に由来した名前で、生徒はこのプログラムのなかで自ら課題を設定し、検証を重ね、成果を振り返るという一連の研究プロセスを経験します。
「研究」と聞くと、どうしても基礎研究の印象が強くなりますが、研究プロセスのなかで求められる力は、社会で起こるトラブルや業務上の課題に取り組むにあたっても重要なものです。生徒たちは研究を通して、しっかりとしたエビデンスに基づいた状況分析と、現実的かつ持続可能性のあるソリューションを導き出す力を伸ばしています。
ありがたいことに、SSHの取り組みは、受験生にも浸透し始めています。現在は入学希望者のうち、約1割の生徒がSSHの取り組みに期待して当校を選んでくれているようです。
高校1年生の研究課題、その意外な難しさ
さくらインターネットが提供している支援について、具体的にお聞かせください。

今年の9月から、クラウドチームに5人、衛星データチームに4人の生徒さんが配属され、それぞれのテーマに沿った課題研究を進めています。
まず、クラウドチームの目標は、「身近にあるアナログ課題をデジタル化すること」に設定しています。具体的には「学校のプリント配布」や「食券を現金で購入する」といった、生徒さんたちが生活のなかで「面倒だな」と感じるものを課題として設定し、それを、クラウドを活用したWebアプリケーション制作につなぐような進め方をしています。
ただ、クラウドは、さまざまなサービスやシステムの土台となる存在であるため、活かし方が幅広く、自由度が高いからこその難しさがあるな、と感じています。
SSHの取り組みとしては、生徒さんの自主的な探究活動を重視すべきなので、われわれが一足飛びで答えを教えてはいけません。生徒さんが自分で方向性を決められるように誘導するのが役目になります。これが予想以上に大変で。「黙って見守る」のは、とても難しいですね。
衛星データチームは、グループ会社である株式会社Tellusの社員にも講師として参画してもらい、衛星データを使った社会課題の解決に取り組んでいます。衛星データは「宇宙から地球を撮ったデータ」という性質上、できることが比較的明確なので、マクロな社会課題に紐づきやすいな、と感じています。生徒さんたちは、すでに災害対策をテーマに設定し、どの衛星のデータを使えば課題が見えるのかを調べ始めています。
両チームとも、生徒さんの事前知識には驚かされました。われわれが想定していたよりもずっと専門的な知識を持っている生徒さんがいます。YouTubeなどから情報を得ているようで、デジタルネイティブ世代だなあ、と感じます。この知識と、生成AIなどのツールを組み合わせれば、Webアプリケーション制作までいけるかもしれません。

企業の方々との関わりは、生徒たちにとって、とても大きな経験になっていると思います。実社会との接点ができ、自分が勉強していることの延長線上に大人の社会があることを実感できているように見えます。教室のなかだけでは得られないリアルな学びの経験は、将来の進路を考えるきっかけにもなっているようです。

「何のためにこのツールを使うのか」を取捨選択できる力を手に入れてほしい
今回の連携を通じて、さくらインターネットと横須賀高校は、何を目指していますか?

生徒さんには、ぜひデジタル時代を生き抜くための本質的な力を身につけてほしいと考えています。
いまの高校1年生が社会に出るころには、いまよりもさらにデジタル、宇宙産業、AIネイティブが進んでいるでしょう。これらを当然のようにツールとして扱えるようになってほしい。さらに、そのツールを「何のために使うのか」を判断して取捨選択できるようになってほしいと思います。そのための、基礎的なデジタル技術についての理解を深めてもらえたらうれしいですね。

私が期待するのは、SSHの活動を通じて、生徒に「自ら考え、問いを立て、答えを探し続ける力」を身につけてもらうことです。
Principiaの活動では、教員は答えを与えず、生徒自身が探究のプロセスを主体的に進めなければなりません。その過程で、失敗や行き詰まりを経験することも、本当の意味での「学び」につながるでしょう。力を伸ばし、自分の言葉で、自分の考えを語れる人になってほしいですね。
つい数か月前まで中学生だった子どもたちが、急に大人の世界に加わるのは、とても大変なはずです。生徒たちはよく食い下がって、ぐんぐん能力を伸ばしていると思います。
短期的な成果と、発展的な学習への進化を目指す
今後の展望についてお聞かせください。

まず、短期的な成果を目指したいと考えています。研究が過度な成果主義に走るのは避けるべきですが、自分が取り組んだ研究が客観的に評価される経験は、生徒たちの学びの意欲や能力向上に必ず繋がります。大学入試への影響もあるため、いわゆる学会発表や科学コンテストなどへの参加は進めていくつもりです。
また、長期的には「持続可能性の高い、発展的な取り組み」を進めたいですね。SSH指定は5年区切りで継続の審査があり、指定がなくなると、予算が削られてしまいます。予算不足で研究活動に制限がかかるのは、あまりにももったいない。次回の審査でもSSH指定を受け、いま生徒たちが進めている一歩一歩の成果を、後輩たちの、より発展的なステップへと繋げていきたいと考えています。

まずは、一人ひとりの生徒にしっかり向き合い、横須賀高校の求める取り組みができるかを見ていただきたいと考えています。われわれは次世代教育支援に携われることに大きなやりがいを感じています。日本のデジタル化は、先進国のなかでも高い水準にはありません。日本のデジタル化を進めるには、今回の連携のような取り組みを何でもやっていくことが重要だと考えています。
学生のみなさん・学校教員の方へ
さくらインターネットではデジタル技術を基礎から実践まで幅広く学べる「さくらのクラウド検定」、および無料の学習教材を提供しています。将来エンジニアやIT業界でのキャリアを考えている学生のみなさんにもおすすめです。ぜひ活用してみてくださいね。


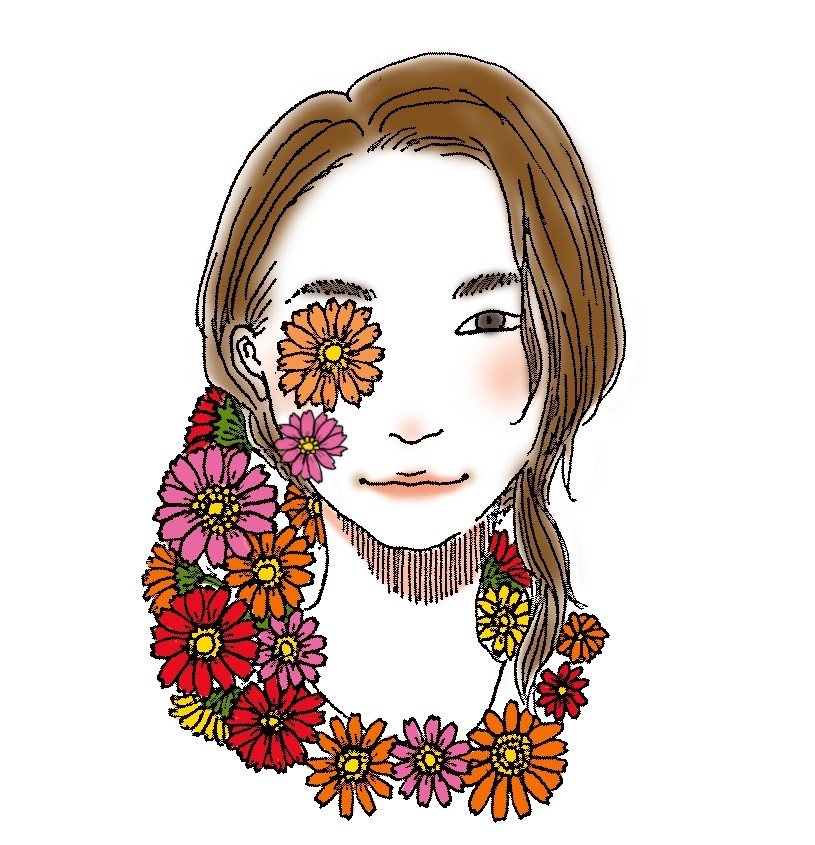
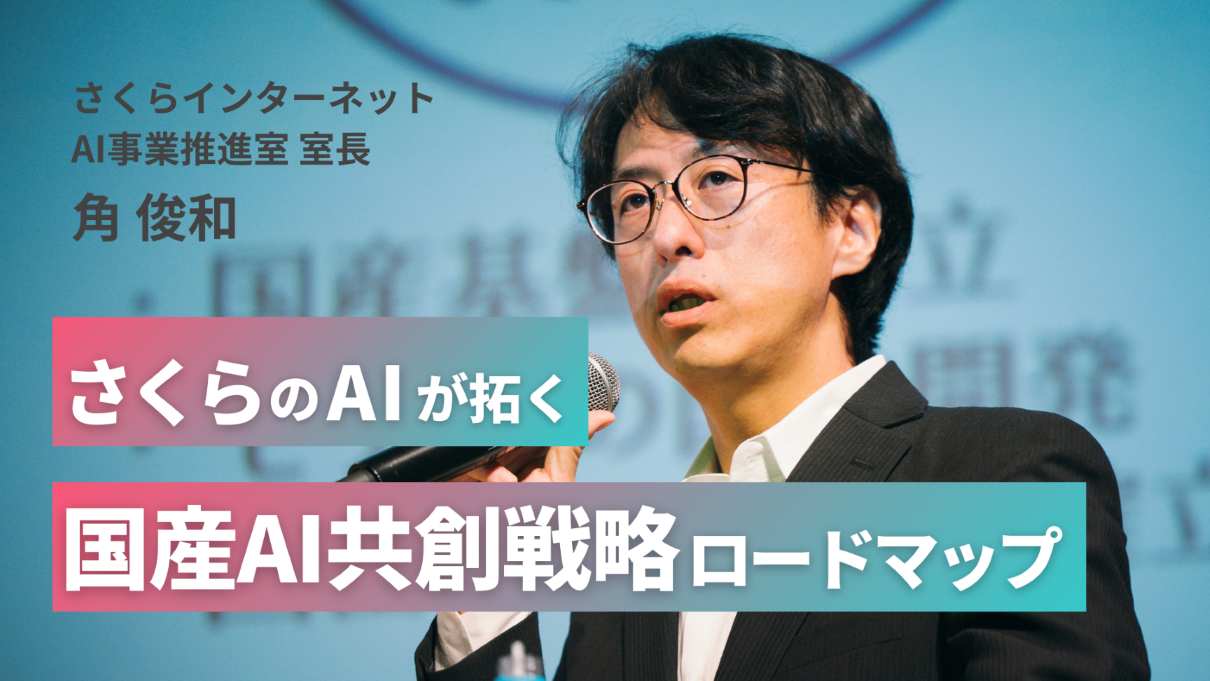

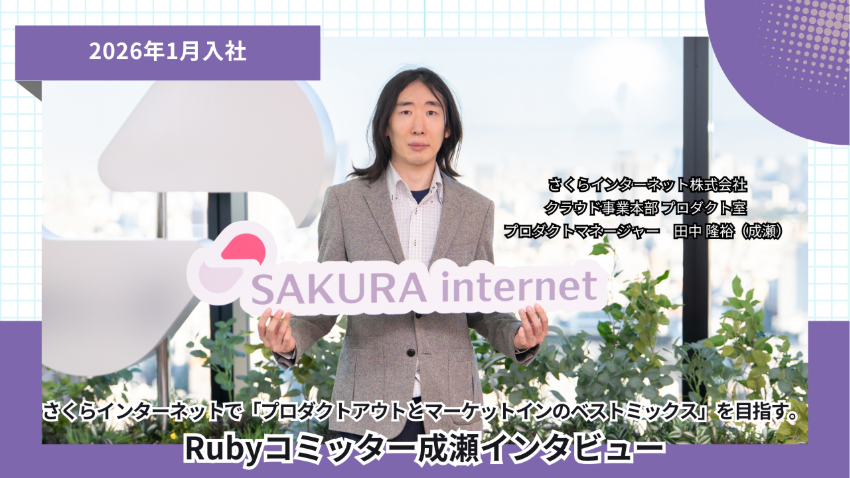
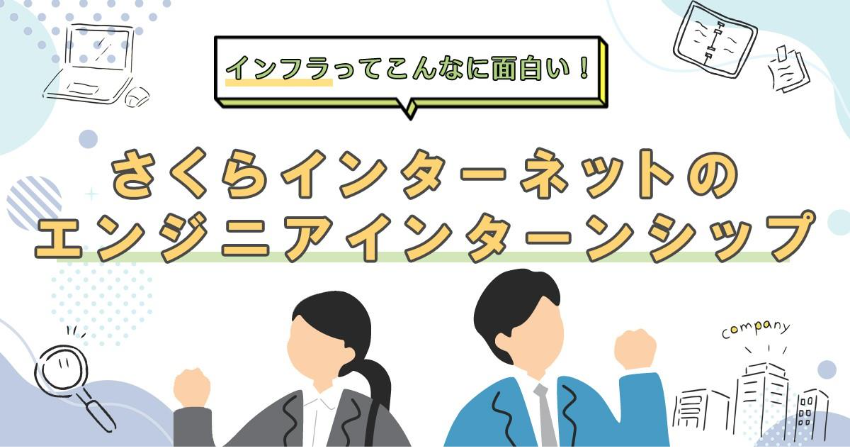

 特集
特集




