>>さくらインターネットのスタートアップ共創プログラム「Link up」とは?
“「やりたいこと」を「できる」に変える”。
さくらインターネットはこのビジョンのもと、多くの人がやりたいことを叶えられるような社会をインターネットとともに作っていくことを目指しています。近年注力している取り組みの1つとして「スタートアップとの共創」があり、さくらインターネットの拠点のある北海道、東京、大阪、福岡、沖縄、それぞれの地域に根差した活動をおこなっています。
そのなかで今回は、おもに北海道を担当する社長室 イノベーション共創グループ 新発田 大地にインタビュー。2024年4月、新発田は、北海道から継続的にスタートアップが生まれ、グローバルに発展していくことを目指す組織「STARTUP HOKKAIDO実行委員会(以下、STARTUP HOKKAIDO)」のオープンイノベーション 領域マネージャーに就任しました。 STARTUP HOKKAIDOに参画することになった経緯や具体的な取り組み内容、今後の展望などを聞きました。

新発田 大地(しばた だいち) プロフィール
さくらインターネット 社長室 イノベーション共創グループ スタートアップチーム 北海道担当。
札幌の音楽専門学校を卒業後、インターネットサービスプロバイダや通信回線事業者のテクニカルサポートなどを経て、さくらインターネットに入社。データセンター運用チームにて、収容サービスの構築‧保守業務に携わった後、石狩データセンターの入退管理責任者や、業務移管プロジェクトのPMなどを務める。2022年からスタートアップ支援・共創業務を担当。2024年4月からSTARTUP HOKKAIDOに参画し、オープンイノベーション 領域マネージャーを務める。
STARTUP HOKKAIDOの仕事とは
新発田さんがオープンイノベーション 領域マネージャーに就任された「STARTUP HOKKAIDO」とは、どういった組織なのでしょうか。
STARTUP HOKKAIDOは、北海道、札幌市、北海道経済産業局が連携し、2023年7月に設立された組織です。北海道から継続的にスタートアップが生み出され、世界的な企業となるまで成長させていくエコシステムの構築を目指しています。
おもに、どのような活動をしていますか。
STARTUP HOKKAIDOは前述の3行政のほか、北海道大学と、私のような民間出身のメンバーで構成されています。それぞれが連携し、北海道内のスタートアップの創出やグロース支援、アントレプレナーシップ教育やアクセラレータプログラムの運営など、幅広い活動をおこなっています。
また道外・海外のスタートアップの誘致にも積極的に取り組んでいます。北海道の広大なフィールドをスタートアップの成長に存分に活かしていただきたいと考えているんです。
新発田さんの、STARTUP HOKKAIDOにおける担当業務はどのようなものでしょうか。
STARTUP HOKKAIDOでは、2024年10月に、 注力領域に掲げる「一次産業・食」「宇宙」「環境・エネルギー」でのスタートアップ創出、道内におけるスタートアップと自治体や事業会社との「オープンイノベーション推進」、道外のスタートアップの「北海道進出サポート」、それぞれに専門マネージャーを配置しました。そのなかで私はオープンイノベーション推進を担当するマネージャーに就いています。
おもな役割はスタートアップと自治体や事業会社のマッチングです。そのため、日頃からスタートアップだけではなく、さまざまな方々と積極的にコミュニケーションを取るよう心がけています。
ほかにも、STARTUP HOKKAIDOへのお問い合わせに対する窓口も担っています。日頃からさまざまなお問い合わせが寄せられるのですが、内部で適切なマッチング先が見つからない場合もあります。その際は、「札幌・北海道オープンイノベーションチーム」という団体に相談をします。札幌・北海道オープンイノベーションチームは、STARTUP HOKKAIDOを含め全8機関が参画し、それぞれの組織が独自の機能とネットワークを持っています。そして横連携ができているので、マッチング先の選択肢を広げることができます。
このように「面」でサポートができるのは強みであり、STARTUP HOKKAIDOの重要な存在意義でもあります。

マッチングは、道内の企業同士でおこなうことが多いのでしょうか?
いえ、そんなことはありません。STARTUP HOKKAIDOは道内外問わずスタートアップの方々を支援していますので、道内の企業同士もあれば、道外のスタートアップと道内の企業、あるいはその反対といった組み合わせもありました。今後は、道内で成長した企業が道外に進出するためのマッチングを増やしていけるよう、さらにネットワークを広げていきたいですね。
また、自治体とのマッチングを希望するスタートアップがとても多いので、スタートアップとの連携に前向きな自治体の方とのつながりはとても大切にしています。スタートアップからの要望をもとに個別にマッチングするケースが多いですが、自治体が独自でおこなっている事業の公募情報をスタートアップにご紹介した結果、マッチングが成立したという事例もありました。昨年度、石狩市が実施した「令和6年度地域イノベーション連携石狩モデル事業」では、お声がけしたスタートアップのなかから1社が採択されました。公募の情報をキャッチアップしてスタートアップに展開するのも、STARTUP HOKKAIDOとして重要な役割です。
STARTUP HOKKAIDOでの活動をして、手応えはいかがですか。
STARTUP HOKKAIDOに参加してまだ1年未満ですが、私がスタートアップ支援の活動をはじめてからは2年ほど経ちました。さくらインターネットだけではできない価値提供ができるようになり、マッチングから商談に発展したり、実証実験が実現した事例も出てきたりと、少しずつ手応えを感じはじめています。STARTUP HOKKAIDOが主催するオープンイノベーションプログラムに応募のあったスタートアップとさくらインターネットをマッチングし、石狩データセンターで実証実験をおこなっている事例もあります。
また、私は基本的にスタートアップから要望がなければ、自分からさくらインターネットのサービスをお勧めはしないんです。でも、支援させていただいたスタートアップのなかには、そのまわりにさくらインターネットを勧めてくれたり、「絶対にさくらインターネットに切り替えます!」と言ってくださる方もいらして、本当にうれしい限りです。
>>さくらインターネットのスタートアップ共創プログラム「Link up」とは?
地元にゆかりがあるからこそ、できる支援もある

新発田さんは音楽の学校を出たあとにIT業界に入り、その後もデータセンター勤務などさまざまな仕事を経験して現在の仕事に就いたという、なかなか異色の経歴ですよね。なぜスタートアップとの連携を担当されるようになったのでしょうか。
さくらインターネットのデータセンター運用のチームで働いていたとき、先輩社員から「札幌でスタートアップ支援に関する事業が始まるので担当を社内公募するらしい」と聞いて、興味を持ったんです。それが、STARTUP HOKKAIDOの前身である「STARTUP CITY SAPPORO」の仕事でした。
ちょうどそのころ、データセンター運用のチームでの大きなプロジェクトをやり切って、キャリアチェンジを真剣に考えていた時期でしたから、ぜひ挑戦したいと思って手をあげたんです。私自身が北海道出身なので、地元を盛り上げる仕事ができたらと考えていたことも後押しになりました。
日頃の業務に、いままでの経験が活きていると感じることはありますか?
データセンター運用チーム時代に心がけていた、議事録をしっかり書くということや、マニュアルを作るスキル(テクニカルライティング)は、役に立っていると思います。STARTUP HOKKAIDOは多くの組織のメンバーが集まって構成されているので、決定事項を記録したり、そこからルールをマニュアル化して、非同期で共通認識を持てる状態をつくるのは、とても重要なんです。また、KGIやKPIの達成度合いをしっかり記録する必要もあるので、細かなことでも逐一記録する自分の習慣は、あってよかったと感じています。
さくらインターネットだからできる、北海道でのスタートアップ支援・共創としてはどういうものがあるでしょうか。
これは活動をはじめたばかりの頃に、私がとても悩んだ点でした。「さくらインターネットといえばクラウドなどのインフラサービス」というイメージがあると思いますし、実際に当社のスタートアップ向けの施策のなかには「サーバーの無料提供」というメニューがあります。
しかし、スタートアップは事業成長が最優先であり、仮にコストダウンが見込めたとしても、それだけではインフラサービス切り替えの優先度は低く、とくに北海道のスタートアップは「シード」「アーリー」と呼ばれる若いスタートアップが多いので、インフラ関連のご提案をしたところであまり響きません。
そこで考えたのは、データセンターをはじめとするさくらインターネットのアセットを活用した実証実験機会の提供、スタートアップを起用したイベント企画、さくらインターネットとスタートアップの協業です。そしてなにより、スタートアップの製品・サービスをさくらインターネットで使うことができないか、社内に積極的に働きかけることです。
ほかにもさくらインターネットが持つネットワークからのマッチングなども提供できる価値の1つです。とくにさくらインターネットのデータセンターがある石狩市とは長年親しくさせていただいていることもあり、スタートアップに関することもいろいろとご相談しています。
これらの支援もスタートアップの方々と話すなかで、見出したものでした。当たり前のように思えて、いざ実践してみるとそう簡単ではありません。それでも諦めずに挑戦し続けるのが、とても重要だと考えています。
たしかに、若いスタートアップへのそういったサポートは喜ばれそうですね。ところでほかの都市と比較して、北海道の企業にはどういった特徴があると感じていますか。
北海道はとても広くて沢山の市町村がありますが、札幌のような都市部以外は企業の数が少なく、地域ごとのビジネスプレイヤーも少ない。そのため、経済圏がかたまりがちかもしれません。広い分、地理的な分断もあるので「いつもお願いしているところに頼む」という発想になりがちなのだと思います。付き合いの長い取引先を大切にすることはもちろん良いことですが、新しいものを受け入れるのに時間がかかるともいえるので、そこに苦労していると若い起業家の方から聞くことがあります。
そういった環境の北海道に道外の企業がやってくると、大きな変化がもたらされそうですね。
そうですね。北海道の企業や自治体に、スタートアップが受け入れられるよう働きかけていくのが、オープンイノベーションの領域マネージャーである私の役割の1つでもあります。
やはりいきなりよそ者がきてスタートアップがどうこう言っても、そんなに簡単に受け入れてはもらえません。そのため、STARTUP HOKKAIDOでは、道内の自治体を巡って、直接会ってお話するという活動も積極的におこなっています。直接会って、どういう活動をしているかを知ってもらい、その地域の強みや課題を聞いたうえで、どんな連携ができそうかを話し合います。そうすることで一定の信頼関係ができて、次回以降の相談もしやすくなるので、なるべく会いに行くという地道な活動はとても大切にしています。
>>さくらインターネットのスタートアップ共創プログラム「Link up」とは?
道内・道外のスタートアップをもっと盛り上げたい

今後の展望を教えてください。
私の役割はスタートアップだけでなく、スタートアップと連携してくれる事業会社や自治体とつながり、マッチングしていくこと。今後もさらにそのネットワークを広げていきたいと考えています。STARTUP HOKKAIDOは、北海道の地の利や産業の強みを活かした「一次産業・食」「宇宙」「環境・エネルギー」という3つの分野を注力領域として定めています。それぞれに専門の領域マネージャーがいるので、内部の横連携もさらに強化したいですね。
新発田さん個人としては、なにか目標はありますか。
私個人としては、スタートアップに関する取り組みを通じて、北海道にある沢山の市町村の地域経済を活性化させたいと考えています。
いま、全国でスタートアップは増えてきてはいますが、やはり東京のスタートアップが一強なのはゆるぎません。それは大学の数や、ライバルとなる企業の多さ、資金調達のしやすさなどさまざまな要因が考えられます。北海道で東京を超える数のスタートアップを生み出すというのはあまり現実的ではないでしょう。なので、北海道発のスタートアップを全力でご支援しつつも、課題先進地である北海道の広大なフィールドを、道外の強いスタートアップにも大いに活用いただく。その結果、北海道の各地域や企業が刺激を受けたり、それを見た道内の学生が起業を考えたりという変化が、少しずつ生まれてくればいいなと思います。
いま、STARTUP HOKKAIDOでの活動は、さくらインターネットでは新発田さんが中心となっておこなっていますね。どういった人が、スタートアップとの連携業務には向いていそうですか?
「さくらインターネットとして、スタートアップとこんなことがしたい!」という強い想いを持っている人ですね。「ビジネスで地域をよくしたい」と考えている方も合っていると思います。既定路線のないことばかりなので、自分で考えてどんどん動けること、トライアンドエラーを楽しめることは重要だと思います。私も当初は迷いながら活動していましたが、最近ようやく自分の軸ができ、自分らしく活動できるようになってきました。
新発田さんの「軸」は、どういったものなのでしょうか。
「『さくらインターネットやSTARTUP HOKKAIDOの新発田』ではなく、『一個人の新発田』として動く」ことです。これはある方の受け売りなのですが、どこかの会社や組織の人ではなく、個人として認識されないとスタートアップからは相談されないし、本質的な話ができないと。
ですから、どんな相談もなるべく「一個人の新発田」として、フラットな目線で聞くように意識しています。そのうえで、自分にできる支援を考えて、それはSTARTUP HOKKAIDOとさくらインターネットのどちらとして対応するのが適しているのかを判断していますね。
最近は、仲良くなったスタートアップのオフィスづくりを手伝ったりもしています。さくらインターネットでもSTARTUP HOKKAIDOでもなく、まさに個人でやっていることですね。会社同士ではなく「人」と「人」という関係性だからこそ聞くことができる、スタートアップの考え方やリアルな悩みもあるので、無理のない範囲で個としてのサポートも継続していきたいと考えています。
自分の軸が固まったことが、大きな転機になったのですね。
そうですね。それから、私個人のSNSアカウントの更新にも力を入れ始めました。
きっかけは、いまのお仕事をはじめてから、本質的な支援とはいったいなんだろう?自分に何ができるんだろう?と悩んでいたときに、スタートアップの方から「自分たちの製品・サービスや、自分と一緒に撮った写真をSNSに上げてくださるだけでも充分ありがたいです!」と言われたことでした。
正直最初は自撮りにとても抵抗があったのですが、最近はもう慣れました(笑)。つながった方々に顔を忘れられないようにするという効果もあり、やってみると案外メリットがたくさんあるなと感じています。
そういった一見些細なことでも、自分だからこそできる細やかな支援は、どんどんやっていきたいですね。
>>STARTUP HOKKAIDOへのお問い合せ窓口はこちら
さくらインターネットの最新の取り組みや社風を知る
>>さくマガのメールマガジンに登録する






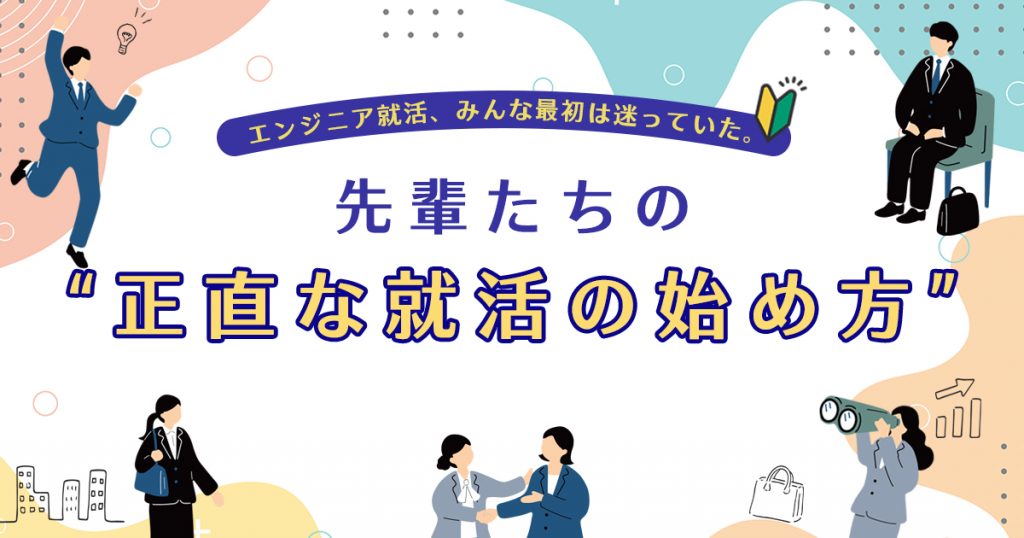 New
New
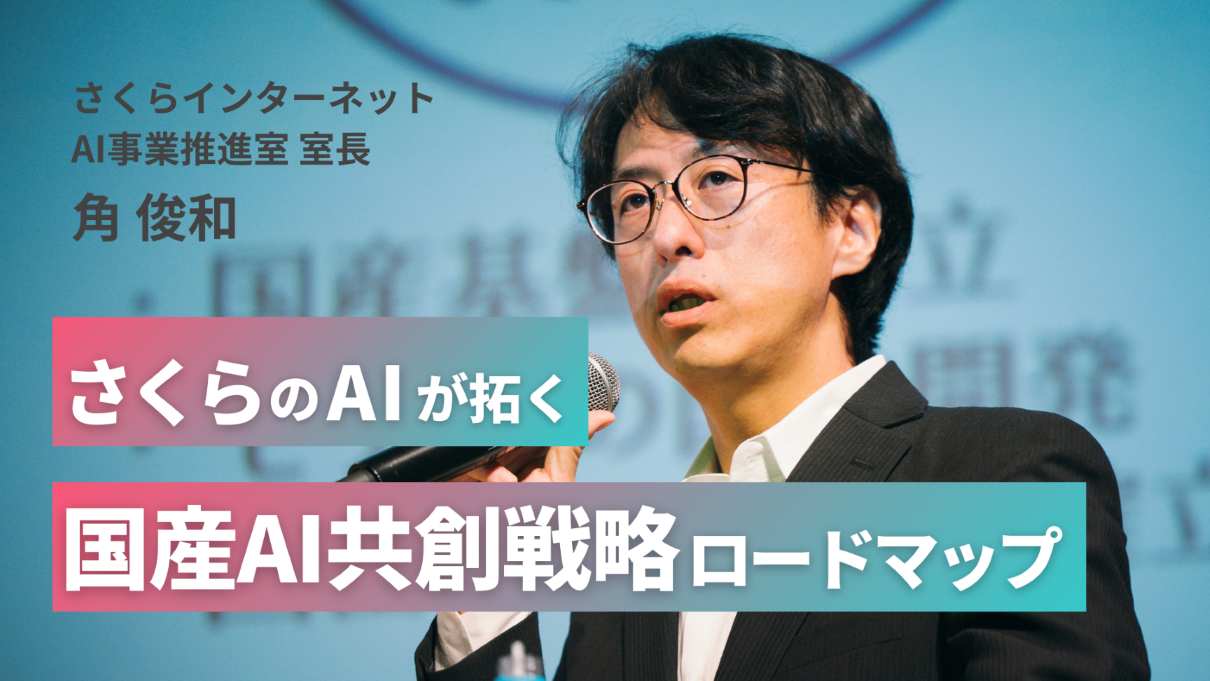
 特集
特集




