さくらのクラウドの概要やセキュリティ機能や導入事例をまとめてご紹介
>>「さくらのクラウド」入門資料セットをダウンロードする
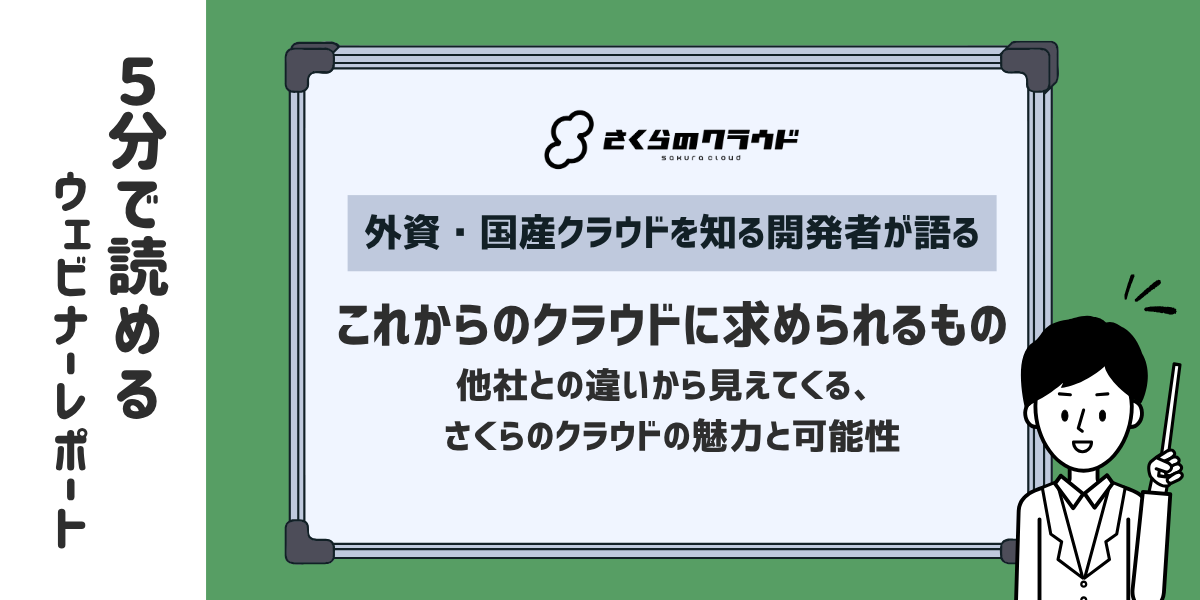
2025年5月28日に開催されたウェビナー「外資・国産クラウドを知る開発者が語る、これからのクラウドに求められるもの ~他社との違いから見えてくる、さくらのクラウドの魅力と可能性~」では、さくらインターネットの荒木靖宏と川又幸恵が登壇。
2人のこれまでのキャリアを振り返りつつ、「さくらのクラウド」が提供する独自の価値や、日本市場に最適化されたインフラ構築の哲学について語りました。
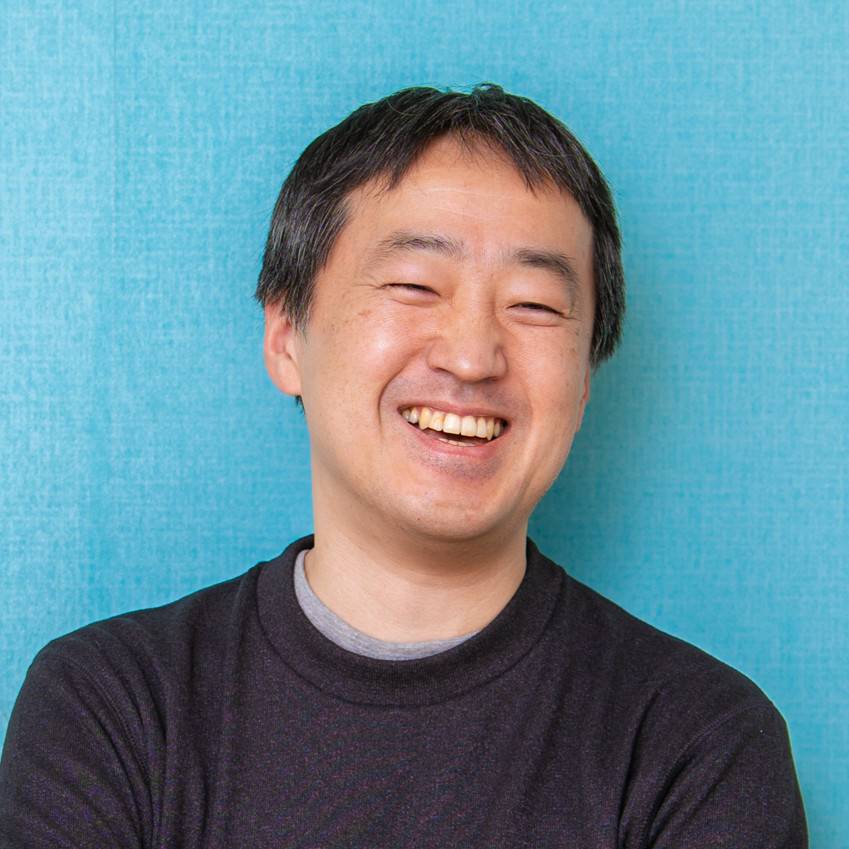
荒木 靖宏(あらき やすひろ) プロフィール
さくらインターネット クラウド事業本部
国内3社、外資2社を経て、2024年にさくらインターネット入社。現在は、クラウドサービスの設計・企画を担当。ガバメントクラウド間接続サービス「GCAS Connect」の設計開発技術責任者。AWS、Google Cloud、さくらのクラウドなど複数のクラウド認定資格を保有。

川又 幸恵(かわまた ゆきえ) プロフィール
さくらインターネット クラウド事業本部 プラットフォーム部
ネットワークエンジニアとして、おもに自社サービスのプラットフォーム基盤の設計・運用に従事。ハイブリッドクラウドサービスや産業IoTプラットフォームサービスなどの基盤開発を経て、2025年4月にさくらインターネット入社。ネットワークアーキテクトとして、自社サービスネットワーク全体におけるスケーラビリティ向上のための課題解決業務を担当。

ファシリテーター:天野 貴洋(あまの たかひろ)
さくらインターネット CS本部 アカウントマーケティング部 デマンドセンターグループ リードマネジメントユニット リーダー
これまでの経歴と入社のきっかけ

これまでの経歴とさくらインターネットへの入社のきっかけを教えてください。

大学院生のときにインターネットの研究をしていた流れで、この世界に入りました。最初はIIJ(株式会社インターネットイニシアティブ)、その後数社を経て、昨年の秋にさくらインターネットに入社しました。「いろいろなことをしたいです」と言って入社したところクラウド事業本部で仕事をすることになり、基本的にはサービスを作って提供する仕事をしています。

これまでは、ハイブリッドクラウドサービスのリージョンの立ち上げやパブリッククラウドを利用した産業IoT プラットフォームサービス基盤開発など、クラウドを作る側にも使う側にも携わってきました。国内の産業やサービス業をIT インフラで支えていきたいという想いをずっと持っており、転職をしました。

入社前、さくらインターネットにどんな印象を持っていましたか?

サーバーのリソースを提供することに長けている老舗の会社だというイメージでした。のちにクラウドのサービスができたので、日々進化している会社だなという印象を持ちましたね。また、すごくメッセージ性が強く、ビジョンが明確な会社だと思います。

メッセージ性が強い会社だというのは、私も同じ印象です。あと、一言で言うと「手作り感」がある会社だと思っていたのですが、あながち間違っていなかったようです。
社会を支えるパプリッククラウドを一緒に作りませんか?
>>さくらインターネットのエンジニア採用情報を見る
現在の仕事内容について

現在具体的にどのような取り組みに携わっていますか。

1つ大きな仕事を挙げると、昨年12月からGCAS Connectというデジタル庁が企画したネットワークサービスの設計開発技術責任者をしています。それ以外にもさくらインターネットを強くするためになんでもやるぞという感じで、いろいろな仕事に関わっています。

ネットワークアーキテクトとして、さくらインターネットのクラウドサービスを中心にそのほかのサービスも含め、要件に応じてどのような技術を選定したらよいか、また選択した技術の検証をしながらネットワークを全体的に設計し、既存のものと組み合わせてアーキテクトしていく仕事をしています。

今後さくらのクラウドを通じてどんな価値を届けていきたいですか?

お客さまの企業価値向上に貢献できるサービスでありたいです。大手のパブリッククラウドが備えているような機能は備えつつ、さくらインターネットらしい機能を引き続き提供できるクラウドでありたいですし、要件を受け止められる柔軟性や、太い帯域、可用性を持ちたいです。

さくらインターネットは基本的にはITインフラをお届けする会社ですが、グループ企業もありますし、さまざまなサービスを提供していますので、お客さまの多様な要望に沿ったサービスを提案することができます。それをお客さまに理解していただくとともに、私たちもサービスをどんどん増やしていきたいです。
外から入ってきてわかった、さくらインターネットの強み

ここがさくらインターネットの強みだと感じる部分はありますか。

実際にクラウドを使っている方やソフトウェアのデベロッパーの方と近いところで仕事をすることによって、細かなニーズにも対応してインフラを作っていけるところです。

外資系の大手のサービスプロバイダではやっていないような、ニッチな日本のリクエストに応えられるのはさくらインターネットのおもしろいところだし、これからも続けていきたいです。リクエストしていただければ、ほかではできないようなサービスも作れるかもしれません。

今後サービスが増えていくと、どう選べばよいのか悩まれるお客さまも出てくるかもしれませんね。

それに対しては、9月末を目途に、サービスの組み合わせ方を包括的に案内したWebページを作る予定です。11月ごろには本も出せるように準備をしていますので、ぜひご期待ください。
参加者からの質問に回答
続いて質疑応答タイムに。ウェビナー参加者から2人に対してたくさんの質問が届きました。

さくらインターネットと外資系製品の違いや製品設計思想の違いなどは感じますか?

外資系には多くのユーザーがいてコンピューティングリソースが集まっているので、それを活かして広帯域のサービスがなされていますが、さくらインターネットでは国内に特化し、国内のユーザーの方が求めているものをサービスとして展開しているところが違う点ですね。

外から入ってきて強く感じるのが、「良いものを届けたい!」という気持ちで作っている点です。これは設計思想としてすごく違うなと思いました。

今後サーバーレスの分野の拡充や検討していることはありますか?

コンテナ技術を使った「AppRun β版」を2月に発表しました。その周辺のものをこれからどんどん出していきます。それから「高火力 DOK」というサービスでは、1秒単位の課金でコンテナをGPUで使えるのですごく便利です。
さくらインターネットのサーバーレスは強みもあると思うので、とくにGPUにはご注目ください。

為替の影響を受けない点で競合サービスに十分優位だと感じています。願わくはサポートにもっとつながりやすくなるととても安心です。

外資系のクラウドサービスは為替の影響や従量課金によって、見積もりや原価率が変動します。一方当社の場合は、為替の影響がなく、ルータ+スイッチといって帯域を選択することで定額になりますので、見積もりがしやすいというお声をいただいています。
また、サポートに関しては、人材を採用して強化していくと聞いています。

Webフォームで問い合わせをする際に、時間を指定して電話でのコールバックをリクエストすることもできます。さくらのクラウドに関しては、最初から電話で問い合わせができるようになる予定もあり、今後もっとスムーズにつながるサービスを考えていきます。

お二人の所属するクラウド事業本部において、現在注目されている技術やホットワードがあれば教えてください。

オーバーレイの技術などは注目されていますし、あとはAIインフラに関わる部分でしょうか。通信量が増えてラックが空気では冷やしきれなくなってきているので、液冷の技術が注目されています。

光電変換や熱の冷却技術、発電技術といったところは、大きなホットワードだと思います。

国外から要望などが来ることもあるのでしょうか。

あります。GPU関連が多いですね。

今後クラウドサービスの海外リージョン展開の計画はありますか。引き続き国内リージョンの数やリソース拡充に注力するのでしょうか。

決まっている計画はないです。ただ、日本が最優先であることは間違いないし、現在ガバメントクラウドの正式認定のために全力を注いでいるのは事実です。
日本のコンテンツを海外に持っていきたい、逆に海外から日本のサービスにアクセスしたいといった要望はありますね。

海外のリージョンは必要なので、やっていかなければいけないと感じています。

世の中の企業では「オフィス回帰」と言われ始めていますが、一方で多様な働き方を認める動きもあります。さくらインターネットの採用において、求められる人物像や働き方についての展望や考え方があれば教えてください。

さくらインターネットはリモートワークを前提とした働き方になっています。また、「肯定ファースト」「リード&フォロー」「伝わるまで話そう」という3つのバリューがしっかりと実践されているので、このバリューに共感できる方には働きやすい会社だと思います。

さくらインターネットではリモートの人が置いてきぼりになるようなことが全然ないんです。それは非常によいところだし、それを続けていけば、いままでどおりリモートで仕事ができると思っています。
100%リモートで働くことは不可能な部門も、可能な範囲でリモートで働けるようにチャレンジしています。

環境に優しいサービスであることも期待します。

グリーンITと言われるような、使わないときにうまく節約し、なるべく電力を効率よく使うといった技術も検討しながら環境への配慮をしていきたいと思っています。

本質的に電力を使う事業体ではあるのですが、再生可能エネルギーの利用など、工夫できるところがまだまだあると思っています。

石狩データセンターがある理由も、北海道の冷たい自然の空気を間接的に使って光熱費を抑え、クラウドを低価格で提供するところにあります。そういった点もIR情報で公開しておりますので、ぜひご覧ください。

現在推進されている自治体のガバメントクラウド利用はAWSが9割を超えるシェアを持っています。そんななかで、ここからさくらインターネットのクラウドが自治体をマーケットシェアしていくために、どのような戦略や展望をお持ちでしょうか。

どんな自治体にも企業にも言えることですが、さくらインターネットのサービスだけを使う組織はあまりないと思うんです。オンプレミスのデータセンターや他社のクラウドも含めてマルチで使っていくのが当たり前になっています。
いま、私はほかのクラウド同士をつなぐ仕事をしていますが、その後「まずさくらインターネットのクラウドにつなげば、ほかのクラウドにも入っていける」というシステムを作ろうと思っています。ですので、さくらインターネットのクラウドを最初に選んでいただくようにするのが、大きな意味での戦略なのかなと思います。
さくらのクラウドの概要やセキュリティ機能や導入事例をまとめてご紹介
>>「さくらのクラウド」入門資料セットをダウンロードする
社員インタビュー記事や求人情報をお届け!
>>さくマガのメールマガジンに登録する



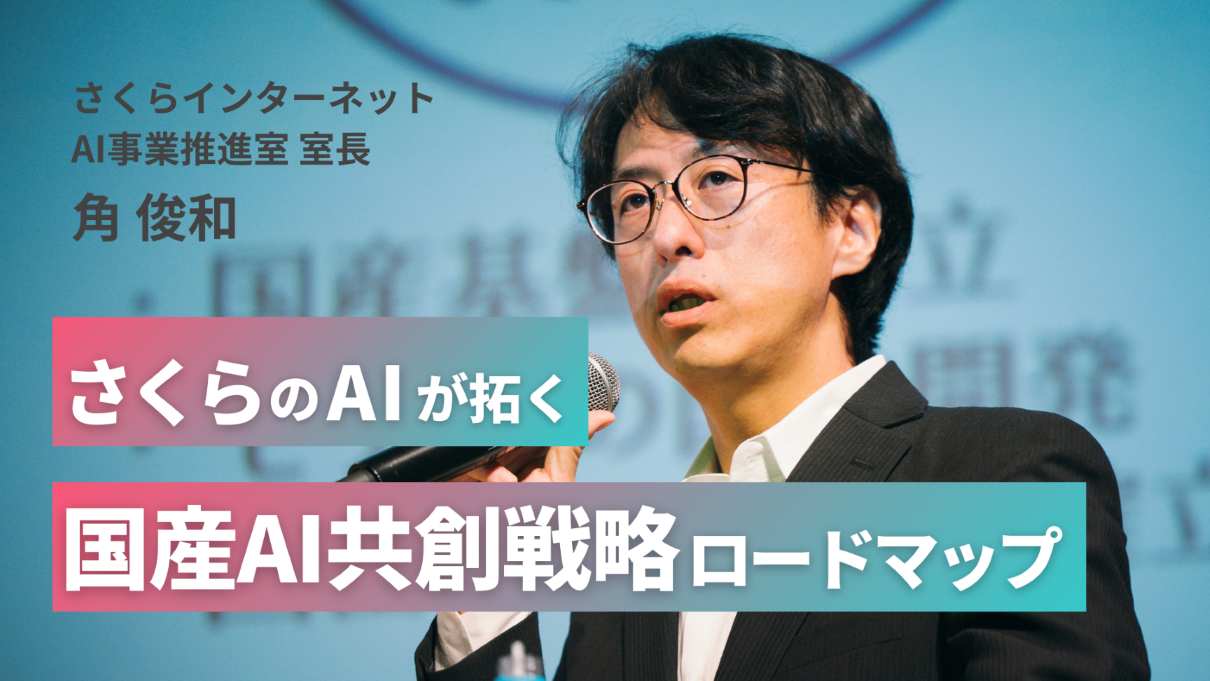

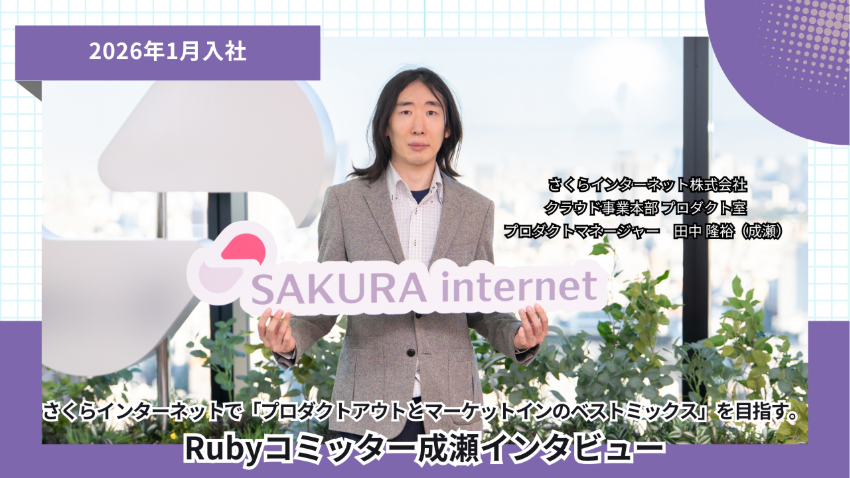
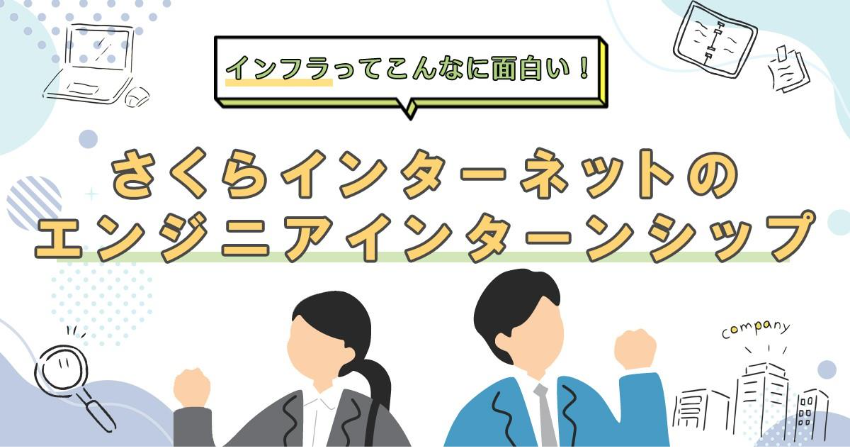

 特集
特集




