社会を支えるパプリッククラウドを一緒に作りませんか?
>>さくらインターネットのエンジニア採用情報を見る

エンジニアとして成長するには、どんな力を身につけるべきか。仕事をスムーズに進めるためには、何を意識しておくとよいのか。
本記事は、2025年に入社した新卒エンジニアたちが、社内で活躍するベテランエンジニア7名にインタビューした内容をもとに、さくマガ編集部が一部抜粋してまとめました。 働くうえで大切にしていることや、情報との向き合い方、キャリアの築き方など、多岐にわたるテーマで語られています。
未来の自分たちに向けた問いかけと、その答え。7人の言葉のなかには、エンジニアとして働くうえでの実践的なヒントが詰まっていました。
エンジニアに求められる「技術力」とは?
エンジニアとして必要な能力や、仕事をするうえで意識したほうがいいことは何でしょうか?
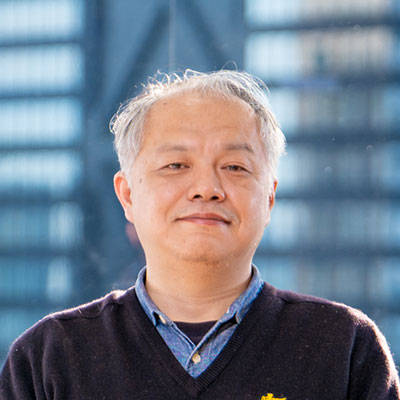
プログラミング言語をたくさん知っていることも大事ですが、僕個人的には「マニュアルをちゃんと読める能力」が重要だと思います。
たとえば、ハードウェアのドライバ実装の場合はマニュアルを読み込む必要がありますし、通信を実装する場合はプロトコルの規格を理解しないといけない。マニュアルをきちんと読んで理解し、実装に活かせる力こそが「技術力」だと思います。この能力は身につけておいて損はありません。
もうひとつ、重要なのは「段取り」です。仕事をスムーズに進めるための準備や設計ができるかどうか。これは、社会人として非常に大事なスキルです。
たとえば開発においては、ある機能をつくって終わりではなく、社内外への説明、デプロイ、モニタリングまで含めて何度も高速に回していく必要があります。力技や運でなんとかなる場面もありますが、このような段取りを丁寧にできると結局あとが楽になると思います。
■亀澤 寛之の過去インタビューはこちら
>> 「チャレンジングな環境って楽しい」。元Linuxカーネル エンジニア亀澤寛之に聞く、さくらインターネット転職の決め手とは?
経験を積むことで確かな実力になる
エンジニアとして成長するには何が必要でしょうか?
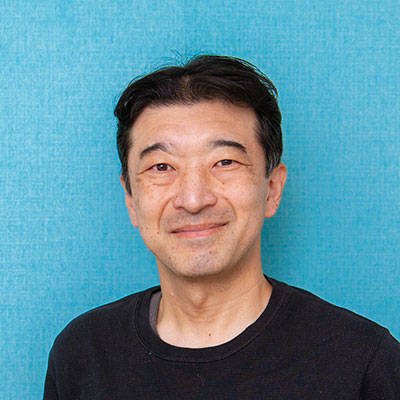
最近は簡単な実装ならLLMがある程度やってくれるので、「これからは設計力が大事」とよく言われます。しかし、設計力は実装の裏付けがあってこそ。実装を知らない人が設計だけやっても、現実離れしたものになってしまう。「この処理、重くない?」「速すぎて逆に不安……」という感覚は、コードを書いて体感しないと得られないと思います。
ただ、実務では設計から自由にできる機会は少ないので、自由につくって壊して試せる環境があるといいですね。OSSでも個人開発でもいいので、失敗しても迷惑がかからない場所で設計から実装・検証までやりきる経験を積むと、確かな実力になります。
逆に、仕事において「僕の最強の〇〇」をいきなり導入して中途半端に残してしまうと、あとでプロダクトの足を引っ張る「残骸」になってしまう可能性があります。未完成の技術や仕組みは、後任が対応に苦労するし、代替も必要になるので非常に厄介。まずは安全な場所で力をつけてから、現場に貢献する。この順番を意識すると、周囲の信頼や成果につながると思います。
■藤原 俊一郎の過去インタビューはこちら
>> 便利なOSSを多数開発。“隙間家具職人”の開発モットーとは? 藤原俊一郎(fujiwara)インタビュー【前編】
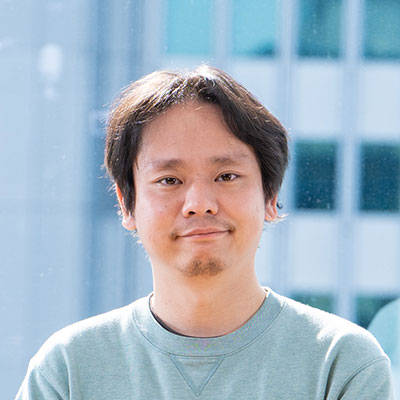
成長するにあたっては、仕事の量をこなして成果を出すことが大事。その積み重ねで、面白い仕事や成長できる案件に関われる機会が増えていくと思います。
私が一緒に働きたいと感じるエンジニア像は、積極性がある人、そしてプロダクトやお客さまのことをちゃんと考えられる人。とくにクラウド系プロダクトに関わるなら、同業他社の動向や最新技術をキャッチアップする習慣も必要でしょう。
また、社内の人とだけ話していると視点が偏りがちなので、社外の人と話す場に出るのもおすすめです。Platform Engineering MeetupやSRE Kaigiのような社外イベントに参加して、外から見たさくらインターネットのサービスの印象を知ることも、すごく大事だと思います。
■松野 徳大の過去インタビューはこちら
>> 国内最大級サービスからパブリッククラウド開発へ。エンジニア 松野徳大(tokuhirom)の転職理由とは?
情報は“集める”だけで終わらせない
情報収集や、発信について工夫していることを教えてください。
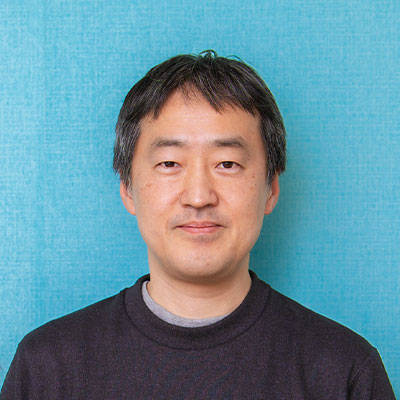
情報収集について、まずは社内のSlackでニュースを共有してくれているチャンネルを見ておくといいかもしれません。そうすると、さくらインターネットで働くうえで知っておいたほうがいいことは、自然と入ってきます。
次のステップは、自分からリアルタイムの情報を取りにいくこと。ほかの人がまだ知らないことを知ろうと思ったら、早起きして朝に情報を集めるのがおすすめです。日本の朝は、アメリカではちょうど夕方にあたる時間帯。アメリカで発信された最新情報をいち早くキャッチできるので、朝の情報収集はタイミング的にもとても理にかなっています。
QiitaやZennで気になるキーワードをいくつか登録して、そこに流れてくるものは全部見る。そして、そのなかで面白かったものを誰かにひとつ紹介してみる。そうやって発信すると、今度は逆に情報をくれる人が現れるので、自然と情報が集まってくるようになります。
■荒木 靖宏の過去はこちら
>> 外資系クラウドから国産クラウド開発へ。荒木靖宏に聞くさくらインターネットへの転職理由

私は2008年から個人ブログ「すぎゃーんメモ」を運営しています。当初は、「未来の自分」が忘れてしまうかもしれない知識をあとで参照できるようにするメモのようなものでした。
基本的に読者は自分という想定ですから、インターネットに公開する必要はないんですよね。ただ、公開するためと意識して書くと、きちんと調べるようになるので知識として身につくんです。こうした積み重ねが、意外と自分の知識整理に役立ちました。10年前の自分が書いていたことを振り返ると面白いです。また、結果的に自分はこういうことをしている人間であるというポートフォリオ的なものにもなっているかもしれません。
■杉 義宏の過去インタビューはこちら
>> 「安心・信頼して使えるサービスを」。クラウド事業本部SRE室 新メンバー、杉 義宏(sugyan)にインタビュー
新卒エンジニアへ、いまだからこそやってほしいこと
新卒エンジニアへ、「これはやっておいたほうがいい」といったアドバイスがあればお願いします。
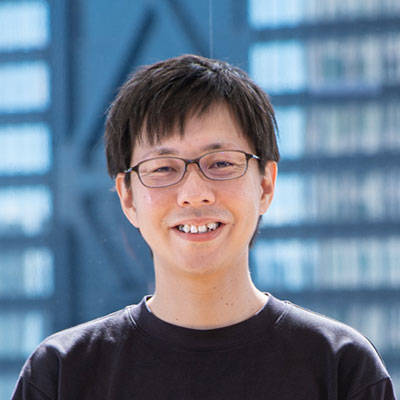
楽しいと思えることをやってほしいですね。結局、「なんか面白そうだからやってみた」がきっかけで、スキルが身につくことって多いと思うんです。ときにはつまらない仕事もありますが、もしかするとその「つまらない仕事」を経て、それをしなくて済むようにする、自分で変えていくという選択肢もあるかもしれない。エンジニアはそういうことを比較的やりやすい仕事だと思うんです。
僕の場合も、ネットワークを自動化するというアイデアを勝手にやってみた結果、いまの自分の強みとして活かせるスキルに繋がりました。好きでやってみた結果、気づいたら10年後にはほかの人にはできない、自分の強みになっているかもしれません。「面白そう」「好きだな」「興味が持てそう」と思えることをとにかくなんでもやってみてください。それに尽きますね。
■土屋 太二の過去インタビューはこちら
>> 「まるでシリコンバレー企業のような自由度」。ネットワークエンジニア 土屋太二に聞く、やりたいことを叶えられるさくらインターネットの環境
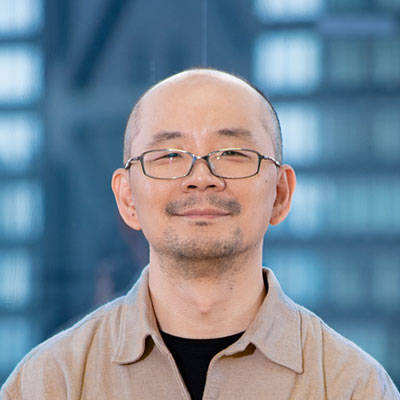
普段一緒に仕事をしていない人とも積極的にコミュニケーションをとるようにするといいと思います。
仕事のやり方に「これが正解」というものはなくて、チームごとに考え方や進め方が全然違うのが普通です。でも、ひとつのチームの中だけでずっとやりとりをしていると、そこでのやり方が唯一絶対の正解に見えてしまう。実際には、ほかのチームではまったく違うスタイルでうまく回っていることもあるし、「このやり方、正直ちょっと合わないな」って思うのも自然なことです。
だからこそ、いろいろな人と話して「さまざまなやり方がある」と気づけることが大事。それが、自分を追い詰めすぎないための助けにもなると思います。
■田籠 聡の過去インタビュー
>> 幅広くコンピューティングに関われる。プロダクト担当 田籠聡に聞く、さくらの魅力とは?
重要なのは人や仕事との向き合い方
技術力はもちろん大切。でも、ベテランエンジニアたちの言葉からは、それ以上に人や仕事との関わりのなかで「どう学ぶか」「どう行動するか」といった仕事との向き合い方が重要であることが伝わってきました。
今回のインタビューは、さくらインターネットで働く新卒エンジニアを対象に実施されたものですが、そこで語られた言葉は、日々の仕事に向き合うすべての人にとって、成長や働き方のヒントになるのではないでしょうか。



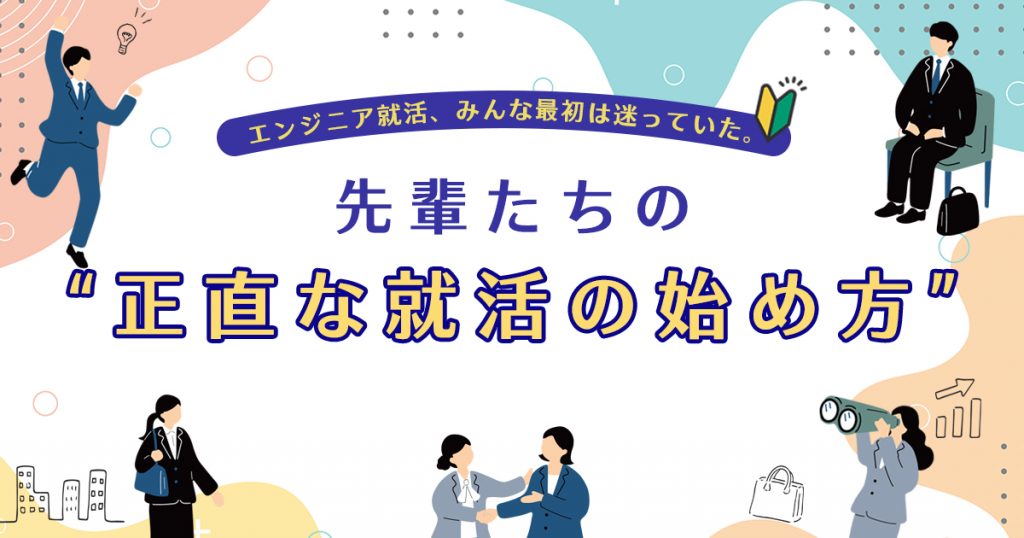 New
New
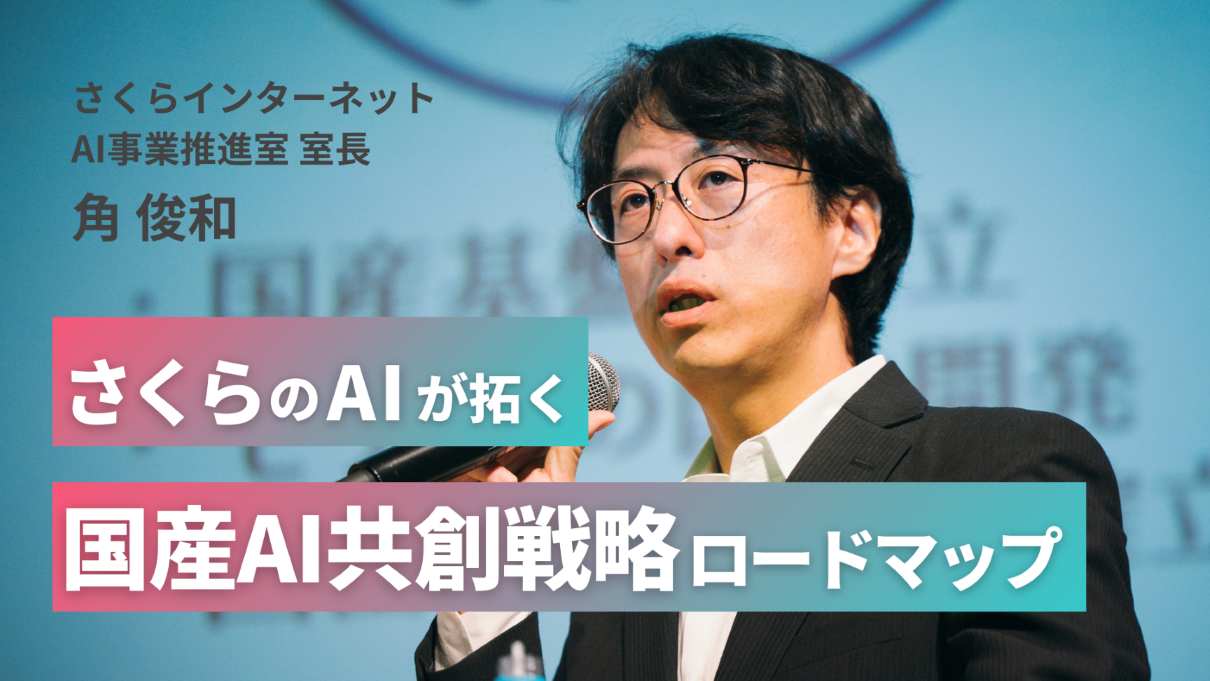

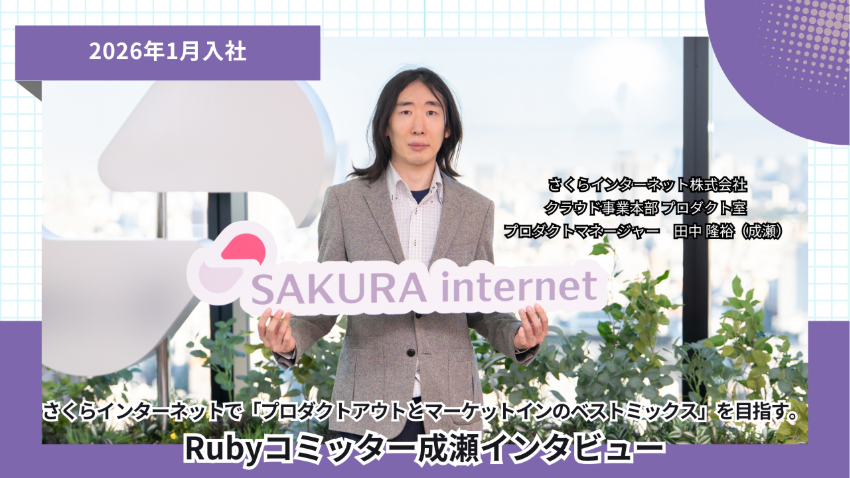
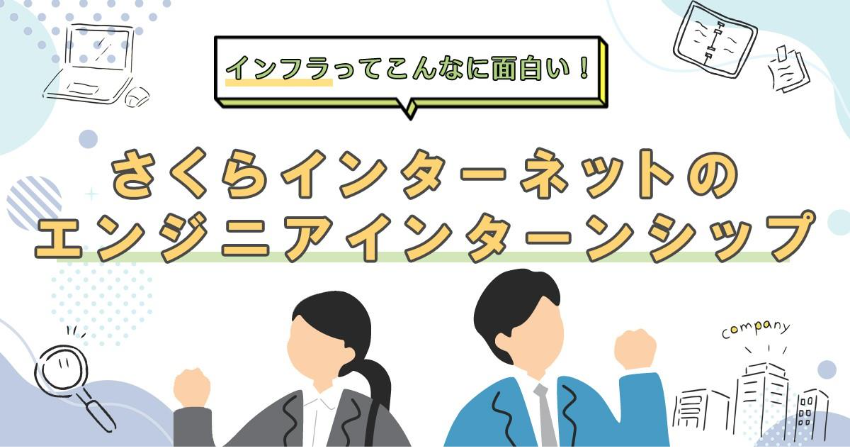
 特集
特集




