デジタル技術を基礎から実践まで幅広く学べる「さくらのクラウド検定」。そんなさくらのクラウド検定には、「さくマス!」という学習アプリがあります。このアプリを作ったのは、2025年にさくらインターネットに入社した熊谷雄汰。入社前の大学生時代にさくらのクラウド検定を受検した際、「自分に合った学習ツールがあればいいな」と考えたことから、個人的に「さくマス!」を開発・リリースしました。そして入社後は同期のエンジニア3人を加え、引き続き「さくマス!」の開発に取り組んでいます。そんな熊谷と同期メンバーに、「さくマス!」開発の経緯や裏側を聞きました。
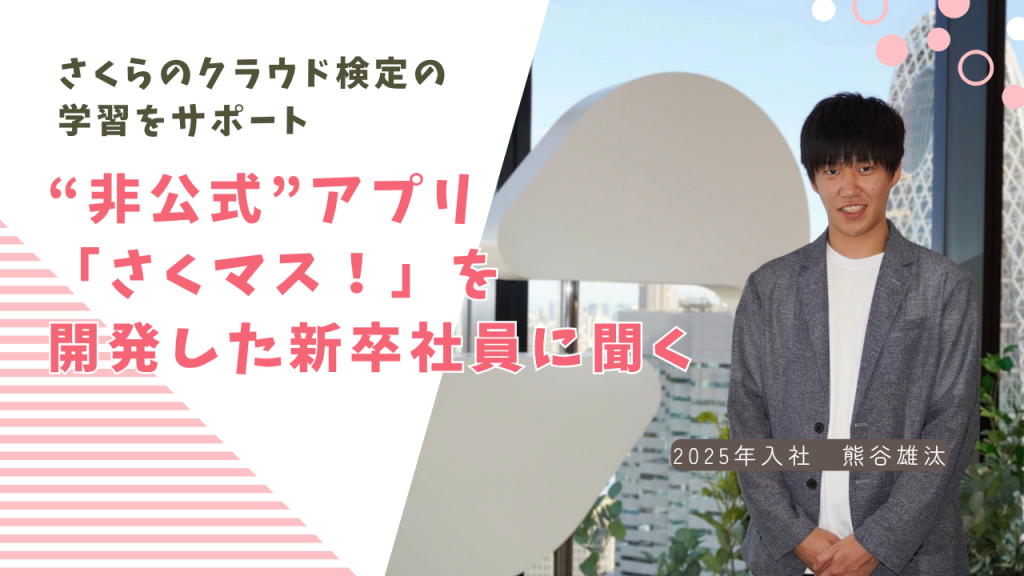
>>(関連記事)デジタル人材育成の新たな一歩。「さくらのクラウド検定」担当者インタビュー
熊谷 雄汰(くまがや ゆうた)
2025年、新卒でさくらインターネットに入社(ビジネス職)。大学では情報系学部に所属し、ビジネス領域(マーケティング・事業立案など)を専攻。在学中に「さくらのクラウド検定」に合格、「さくマス!」を自主的に開発、リリースする。
菊池 兼矢(きくち けんや)、鈴木 進太郎(すずき しんたろう)、山下 亮輔(やました りょうすけ)
2025年、新卒でさくらインターネットに入社(エンジニア職)。同期の熊谷に声をかけられたことがきっかけで、「さくマス!」の開発に携わる。
問題を大量に解けるサービスがほしかった
熊谷さんは第1回「さくらのクラウド検定」(2024年9月)を受検し、見事合格したそうですね。検定を受けようと思ったきっかけを教えてください。

第1回試験の1か月くらい前に、SNSでさくらのクラウド検定の存在を知りました。当時は大学生で、すでにさくらインターネットに入社することが決まっていたので、「じゃあ受けてみるか」と。
学習してみて、どのような印象を持ちましたか?

単にさくらのクラウドに特化した知識だけでなく、ITに関する基礎知識をしっかり学べる内容だと思いました! 僕は、学生時代にITの基礎については学んでいたところもあったので、スムーズに学習を進められました。
ただ、さくらのクラウドについて深い知識があったわけではないので、新たに覚えないといけないことも多かったですね。そういった点では、難しいなと感じることもありましたが、教材が無料で公開されているので、初心者や学生でも取り組みやすい工夫がされていると思います。
山下さんはいかがですか。熊谷さん同様、さくらのクラウド検定に合格したそうですね。

はい。さくらのクラウド検定のことを知ったとき、「さくらインターネットもついに大手外資系クラウドサービスと同様に資格制度を取り入れたんだ!」とワクワクしましたね。 入社後にさくらのクラウドに携わるうえでよい勉強になるだろうなと考え、すぐに受検することを決めました。
こういった資格は受検費用が高いことがネックだと思いますが、さくらのクラウド検定は学割があったので、心理的ハードルは低かったです。
どういった方法で学習していたのでしょう?

僕は過去問をたくさん解いて解説を見て学ぶ学習スタイルが好きなんですが、公式の学習ツールだけだと個人的には心もとなくて……。たとえば、ほかのIT系資格だと、過去問をひたすら解くアプリケーションがあるんです。さくらのクラウド検定はまだできたばかりということもあって、そういうサービスがなかったんですよね。だから、問題を繰り返し解くために、AIを利用して、学習用のローカルアプリのようなものをつくりました。それが、「さくマス!」の原型になっています。
個人で開発した「さくマス!」がさくら社内で話題に
さくらのクラウド検定に合格したのち、「さくマス!」を開発・公開されたそうですね。「さくマス!」をつくろうと思ったきっかけを教えてください。

僕自身が大量の過去問を解く学習スタイルだからこそ、同じように「さくらのクラウド検定の問題をたくさん解きたい」という需要があると思いました。あと、僕は数字を追いかけることが好きなので、「サービスをつくったうえで、どうやってユーザーを増やしていくかを楽しみたい」という動機も大きかったです。ニッチなサービスだからこそ、解像度を高めることができるし、僕もさくらのクラウド検定を受けたのでユーザーが求めているものがわかる。きっと多くの受検者たちが求めているような、よいものがつくれると思いました。
開発するときに大変だったことはなんでしょうか?

開発がスピード勝負だったことです。というのも、当時、僕のほかにも「さくらのクラウド検定の例題をつくってみたので解いてみてください」と問題を公開しているサイトがあったんですよ。早く動かないと同様のサービスが登場してしまうと思い、急いで開発をしました。さくらのクラウド検定に合格した2024年10月から開発を進めて、1か月後には「さくマス!」をリリースしました。
開発はどのように進めたのでしょうか?

「Claude」というコーディングに長けたAIを使いました。AIと共同でコーディングすることで、とても効率よく作業を進めることができました。体力無限なスーパーエンジニアと一緒に開発しているような感覚です。
開発をするうえでこだわったポイントは?

収録問題数の多さです。「どれだけ問題演習できるか」というところにユーザーのニーズがあると思ったので、そこに目をつけて、初期リリースでは500問収録すると決めていました。
問題はAIで作成したんですが、僕は高度なプロンプトが書けるわけではありません。最初のうちはAIに100問出力してもらって、そのうちの20問が使える問題、みたいなペースでした。だから500問作成するのはけっこう大変でしたね。ボツになった問題もすごく多かったです。
「さくマス!」を公開したときの反応はどうでしたか?

第2回試験(2024年12月)の1か月くらい前に公開したのですが、第2回試験前日のDAU(Daily Active Users、サービスを1日1回以上利用したユーザーの数)が99人でした。その全員が受検したと仮定すると、受検者数が200人弱だったので、およそ半数の方に利用してもらえたことになります。また、平均エンゲージメント時間は55分でした。
それはすごいですね!どのような方法で利用者数を増やしたのでしょうか?

Xで「さくマス!さくらのクラウド検定対策」というアカウントをつくり、運用していました。さくらのクラウド検定のタグをつけまくったり、「さくらのクラウド検定」と投稿している人のポストにいいねをつけたり。もう1つはブログです。SEOを意識したうえで、ITのトレンドについてなど、さくらのクラウド検定の受検者層が見るような話題の記事をどんどん書きました。
当時、さくらインターネットの社員は「さくマス!」の中の人が熊谷さんであることは知らなかったんですよね?

そうなんです。入社後にテクニカルソリューション本部のさくらのクラウド検定に関わる方々とお話する機会があって、「僕が『さくマス!』をつくっています」とお伝えしたんです。「熊谷さんだったんですか!」と驚かれましたね。そのほかにも「さくマス!」の存在を知ってくれていた社員の方、実際に使ったことがあるという方もいて、すごくうれしかったです。
個人よりもチームで開発するほうが圧倒的に楽しい!
入社後、「さくマス!」を同期の4人で共同開発することになったそうですね。

2025年4月に入社後、大阪研修中に僕、菊池さん、鈴木さん、山下さんの4人でお好み焼き屋さんに行ったんです。このメンバーはそれぞれ学生時代にインターンや個人で開発をした経験があり、その話で盛り上がりました。それで、「何か一緒につくりたいね」という流れになって、「じゃあ『さくマス!』を一緒にやらない?」と声をかけました。2週間の大阪研修が終わってオンライン研修が始まったタイミングで「さくマス!」の開発をスタートした感じです。
研修期間中、どのように時間を捻出していたのでしょうか?

研修中はみんな同じ時間に昼休みがあるので、その間に30分間のミーティングをしていました。それが週に1、2回で、開発は終業後や週末に各自でおこなっていましたね。
個人で開発したものをチームで開発することになって、一番大きな変化はなんでしたか?

チームで開発するほうが圧倒的に楽しいです。このメンバーって、山下さんはフロントエンド、鈴木さんはバックエンド、菊池さんはインフラというように、それぞれ得意分野が違うんですよ。だからそれぞれの専門的な知識を取り込むことで、「さくマス!」をより良いものにすることができていると思います。
あと、4人の性格のバランスもいいですね。僕と菊池さんは、スピード感を持ってどんどん開発を進めたいタイプ。一方で、山下さんと鈴木さんは慎重なので、「そのまま進めて大丈夫?」「会社側に確認したほうがいいんじゃない?」と言ってくれる。だから安心感があります。


学生時代もアプリ開発をやってきましたが、熊谷さんのようなマーケティングやビジネス側の考え方をもっている人と組むのは面白いです。メンバーそれぞれが得意なことを活かしているので、すごいスピード感で「さくマス!」が形になっていって。こんな体験は初めてなので、すごく楽しいですね。

さきほど熊谷さんが言っていたように、僕は「慎重なタイプ」だったのですが、熊谷さんが「こういう機能がほしい」などのアイデアを次々と出してくるので、それに応えているうちにスピード感をもって取り組めるようになってきたと実感しています。いまはやればやるほど機能が増えていく段階なので、僕らとしてもかなりおもしろいですね。

このメンバーで開発に取り組むことで、非常に良い勉強になっています。僕はフロントエンドを担当していて、ユーザーが触れる、目に見えてわかりやすい部分をつくっているので、それがやりがいになっています。仲間から「これいいね!」とポジティブなフィードバックがあったときはすごくうれしいですね。
「さくマス!」は「非公式」。しかし将来的には……?
最初は熊谷さんが個人的につくりはじめた「さくマス!」ですが、現在、さくらインターネットのなかではどういった位置づけなのでしょう?

いまのところ「非公式」の存在で、さくらインターネット公式のものではありません。もちろん僕らが「さくマス!」をつくっていることを知っているので、公認ではあるんですけれど。僕らとしても、いまの段階では、公式になることを望んではいないんです。テクニカルソリューション本部のみなさんも、「自分たちのペースで開発したほうが楽しいよ」と言ってくれていて。ただ、いつかは公式になったらいいなとは思います。
今後、検討している「さくマス!」のユーザーを増やすための施策はありますか?

ユーザーが自分の学習進度を把握できる機能をつくりたいと思っています。「今日は〇問解きました。この分野が弱いようです」と教えてくれるような機能を考えています。
今後、さくらインターネットでやりたいことはありますか?

もっと世の中にさくらのクラウド検定を普及させたいです。取得することのメリットがまだ世間にあまり知られていないので、「検定を取るとこんなにいいことがあるよ!」と身をもって発信できたらいいですね。
僕個人としての夢は、「さくマス!」よりずっと大きなサービスをつくって提供することです。さくらインターネットでたくさん吸収して、将来的にはそれを活かしてより多くの方に届けられる、社会に貢献できるような事業に携われたらと考えています。
最後に、さくらのクラウド検定や「さくマス!」に興味を持っている方へのメッセージをお願いします。

IT技術、クラウドの基礎知識、さくらのクラウドなど、ここまで幅広く学べる検定はなかなかないのではないでしょうか。とくに、IT初学者はクラウドの理解に時間がかかると思いますので、そういった方がクラウド検定を受検してどう感じるのか気になります。よかったらご意見をいただければと思います。

「さくマス!」はあくまで有志で開発したものであり、公式サービスではないのですが、ユーザーにとって、さくらのクラウドに興味を持つきっかけになればうれしいですね。

「さくマス!」は、さくらインターネットが提供する「AppRun」というインフラ管理不要のアプリケーション実行基盤を使用して開発しています。そういった技術的な内容は「さくらのナレッジ」に掲載されていますので、ぜひご覧ください! さくらのクラウドを使ったアプリケーション開発のモデルケースとして少しでも参考にしていただけたらうれしいです。
「さくらのナレッジ」の記事はこちら
>>さくらのクラウド検定学習アプリ「さくマス!」リニューアルの裏側

「さくマス!」は現在、1,000問以上の問題を収録しているので、さくらのクラウド検定を受ける方はぜひ学習に使ってみてください! 「さくマス!」はまだ開発途中で、UI・UXもどんどんアップデートしていきます。そういう変化も楽しんで見守っていただけるとありがたいです。




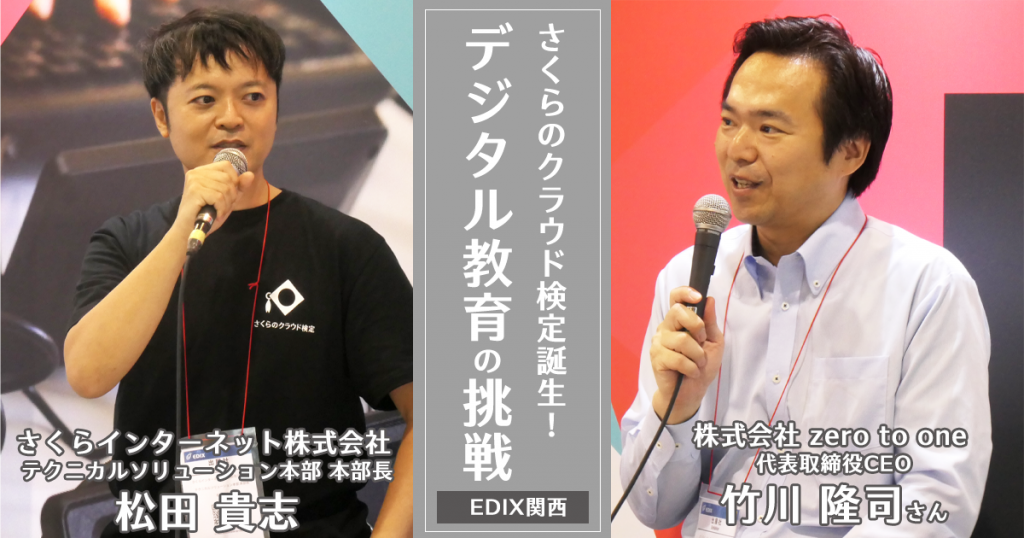
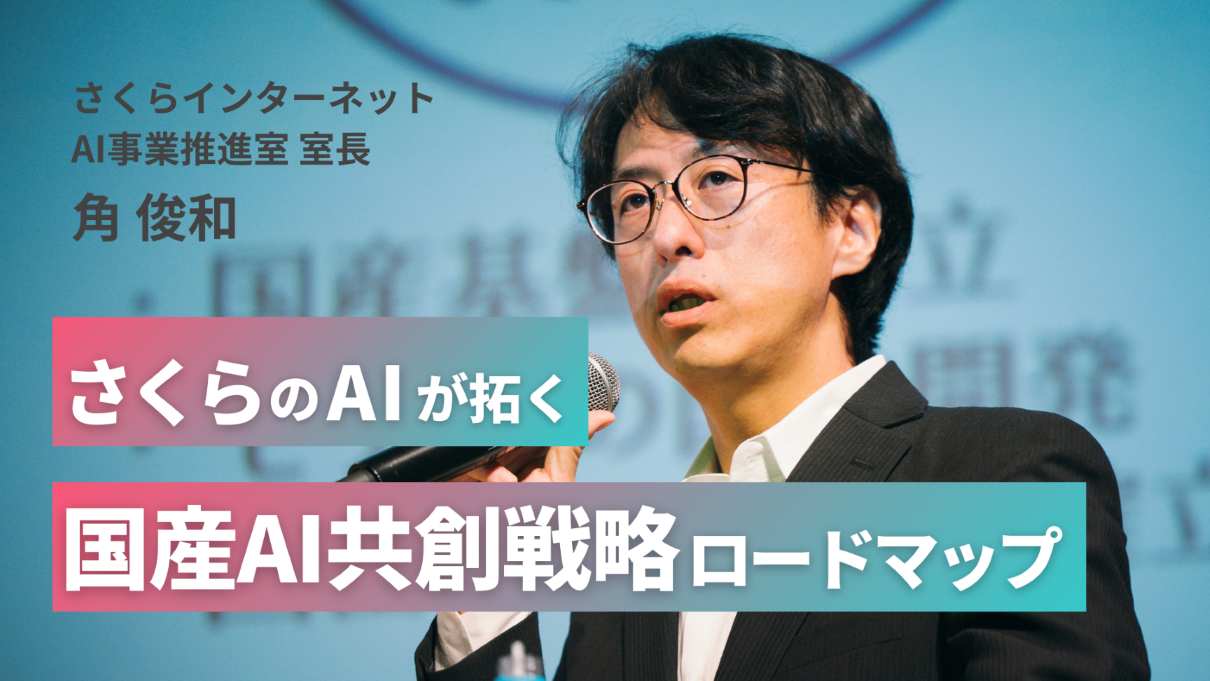

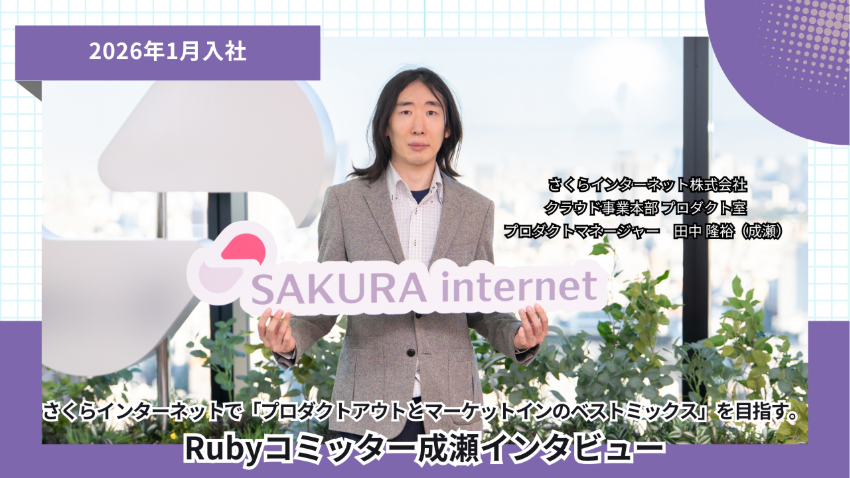
 特集
特集




