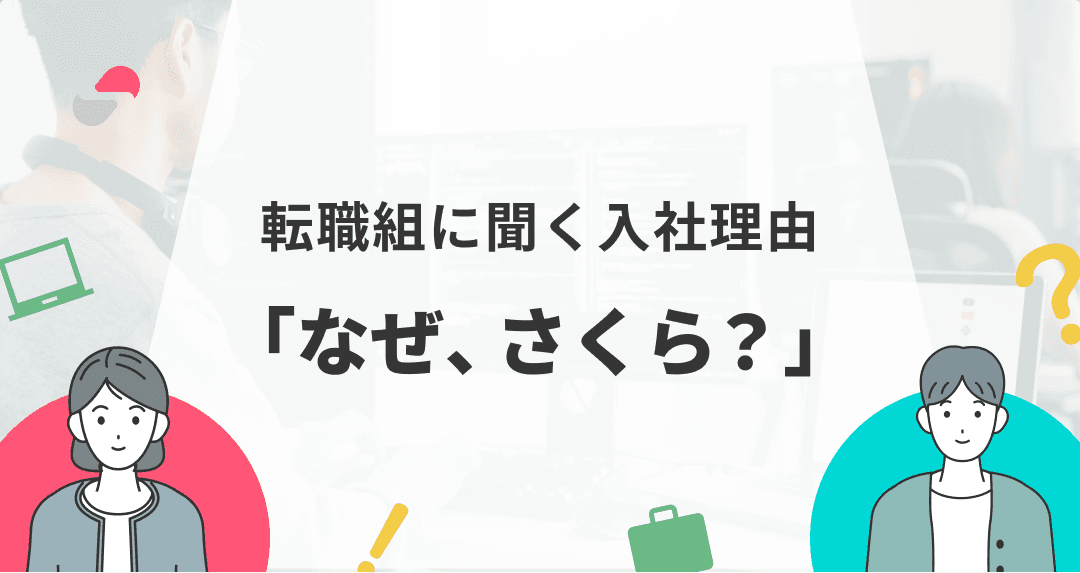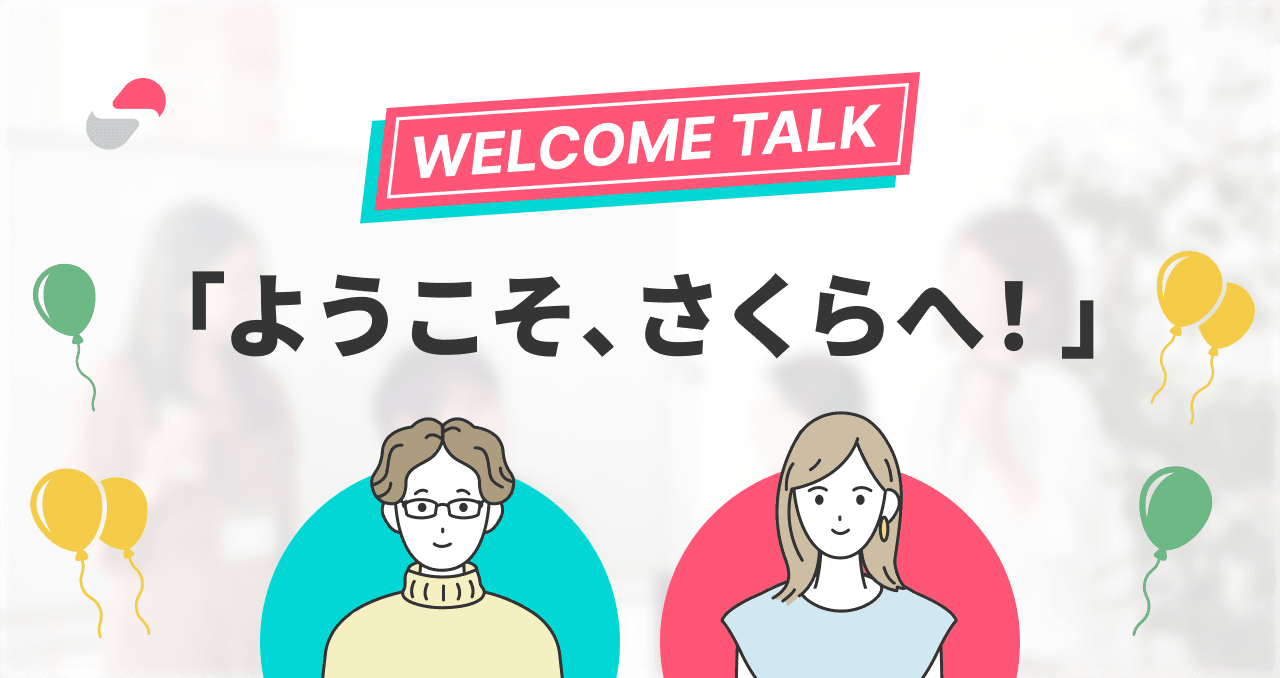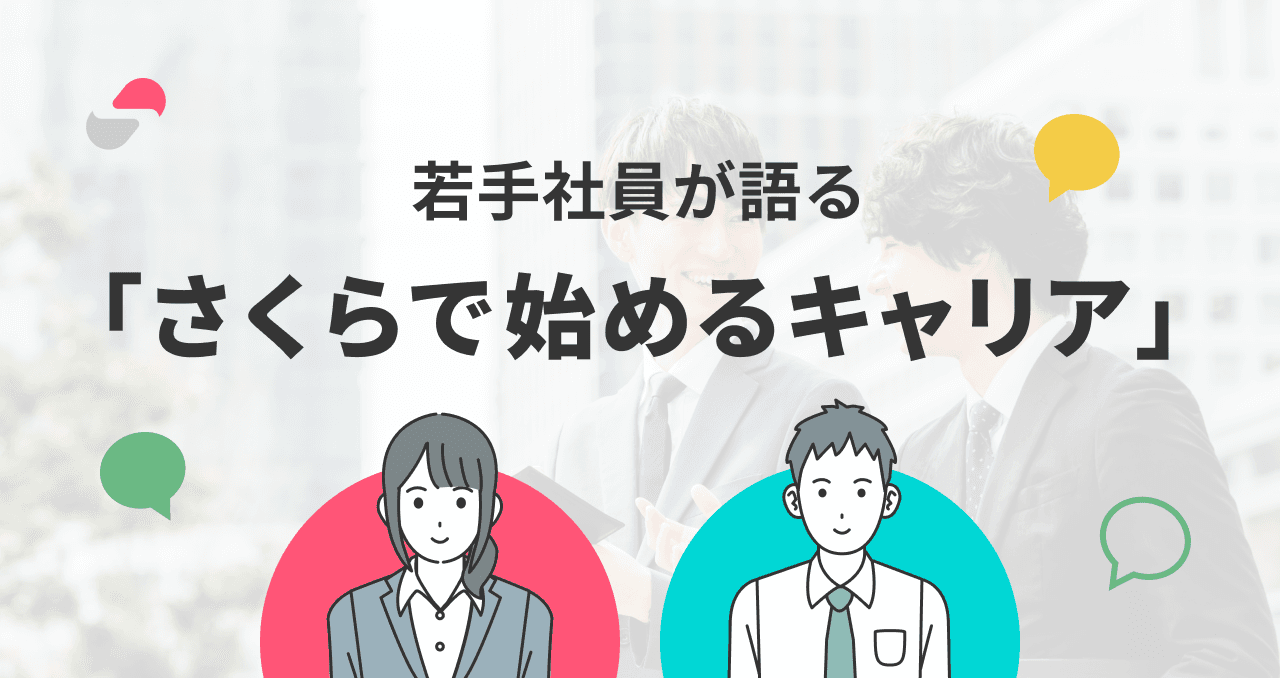皇居をのぞむ東京都千代田区大手町。オフィスビルが燦然と輝くビジネス街に、なんと野菜が育っている。2022年5月、プランティオ株式会社(以下プランティオ)は、大手町ビルの屋上に、IoT農園「The Edible Park OTEMACHI」をオープンした。オフィスワーカーが野菜を手入れし、ダイニングのシェフが採れた野菜を調理する。大手町の地産地消だ。なぜ、郊外でなくビジネス街のど真ん中なのか。アーバンファーマーを名乗るプランティオの代表取締役 芹澤 孝悦さんに話を聞いた。

芹澤 孝悦 (せりざわ たかよし)さん プロフィール
エンターテインメント系コンテンツプロデューサーを経て、日本で初めて“プランター”という和製英語を発案・開発し世に広めた家業であるセロン工業に入社。2015年、祖父が発明した元祖プランターを再定義・再発明すべくプランティオ株式会社を創業。祖父の発明の本質は「高性能なプランターを開発したことではなく、”農”に触れる機会を創出したこと」と捉え2020年”grow”ブランドを発足、食と農の民主化を目指す。アーバンファーマー、プランティオ株式会社 代表取締役 共同創業者CEO(現職)。
皇居から徒歩3分、ビジネス街のど真ん中で野菜が育つ
「都市でおこなう農業を”アーバンファーミング”といいます。世界ではアーバンファーミングが台頭しています。ニューヨークのブルックリンでは3、4棟に1棟のマンションに農園があるのが当たり前。ロンドン市内には3,000ヶ所以上の農園があるんです。ないのは日本くらいです」芹澤さんはそう話す。
一般的なマクロな農業に対して、ベランダや屋内の限られたスペースでおこなう農業を「マイクロファーミング」という。「マイクロファーミング」を都心部でおこなうのが「アーバンファーミング」だ。
芹澤さんの祖父は日本で初めて“プランター”を作った。芹澤さんは「祖父の発明の本質は、人が”農”に触れる機会を作ったこと」だと話す。家庭のベランダだけでなく、ビルの屋上に農園があってもいい。時代に合わせ、プラットフォーム化してもいいはずだ。IoTと掛け算し、スマホを利用した野菜栽培が始まった。育てるのは農家ではなくオフィスワーカーや子育て世代のファミリーだ。
「野菜は買うものという常識をアップデートしたい。育てる選択肢があっても良いんです。土と種子があれば、誰にでもできる食糧生産。大手町という最も象徴的な場所に農園をオープンしたのは、身近で”農”に触れる世界を知ってほしいから」芹澤さんはそう話す。

IoTで野菜の生育状況がわかる
「じつは日本人の約半分が何かしらの野菜栽培にトライした経験があるといわれています。しかし約60%の人たちが途中で挫折してしまう、非常に離脱率が高い体験なんです。理由はタイミングの問題。水やりとか間引きとか、手入れのタイミングがわからない。ネットで調べても、地域ごとに条件やタイミングが違います」
トマトは、開花してから積算温度が1,000度を超えると赤くなるといわれている。単純計算で気温20度の日が50日続くと赤くなって収穫できる。バジルは土中の温度の累積が100度になると発芽する。
「北海道と沖縄では気候条件や生育環境が違います。同じ野菜を育てるにも、手入れのタイミングが異なります」
プランティオでは、デジタルテクノロジーで課題解決を図った。「grow CONNECT」と呼ばれるIoTセンサーだ。大きさは片手に載るほど。土に挿すことで野菜の成長の状態をタイムリーにナビゲーションしてくれる。日照量・土壌水分量・土壌温度・外気温の推移など栽培に重要なデータを日照センサーやカメラが集め、データを肉付けして、野菜の生育状況をスマホ専用アプリ「grow GO」に知らせてくれるのだ。

GPSとも連動している。挿した場所の位置情報にもとづいて、手入れのタイミングを教えてくれる。たとえば、沖縄は気温が高いので3日で芽がでる。北海道は気温が低いので7日。「そろそろ発芽します」といった案内がスマホに届く。「そろそろ間引きのタイミングです」など、成長する野菜の無言のメッセージを「grow CONNECT」のセンサーやカメラが集めてくれる。クラウド上のデータと掛け合わせ、スマホのアプリに届けてくれる。野菜栽培のDXが実現した。
「大事なのは、指示通りに育ててほしいということではなく、テクノロジーを介して野菜が成長の状態を呼びかけてくれること。そのようなイメージです」
多忙な都会人に野菜が呼びかけ、人をつなぐ
「都市生活者の方はとても忙しい。忙しさの上にコミュニケーションが発生すると思っています。野菜栽培をハブにして、そこから生まれるコミュニケーションを楽しんでほしい。野菜栽培を持続可能なエンターテイメントにしたいですね」
芹澤さんが目指しているのは、楽しいからこそみんなが野菜のお手入れをする、ひいては持続可能な食と農が実装される世界だ。
都市農園の会員のスマホにはタイムリーに「そろそろ間引きですよ」といった野菜からの呼びかけが全員に共有される。それがコミュニケーションの醸成につながっていく。
「プランティオが手がける都市農園は、会員の自発的な活動で成り立っています。共助、共同、共有の、助け合えるような仕組みです。たとえば、一部の人だけが『水やりします』というのは持続可能ではないと思います。一部の人だけでコミュニティが固定化し、もしその人たちがいなくなったら終わってしまう。一部のコミュニティの人ではなく、野菜のほうから呼びかけることで持続可能になると考えています」

エコな江戸の伝統野菜が都市農園で育つ
プランティオがこだわっているのが江戸の伝統野菜の栽培。種子のライセンスがフリーだからだ。農業用の種子は、特定の方法、農法、特定の農薬や肥料で大量生産できるように設計されている。大量生産型の野菜は、プランティオが手がけるようなマイクロファーミングには向かない。大量生産の枠組みを外れるためには、江戸の伝統野菜やもともと固定種・在来種と呼ばれている種類の野菜が適している。芹澤さんはそう説明する。
「”種子を鍛える”という言葉があります。3世代育てると種子が学習して3世代目から強く育つという特性があります。もともとあった伝統野菜を地域の特色に合わせて育てる。農薬などは使わずに、育つ場所の形質や気候に合わせて強く育ってほしい。伝統野菜にこだわるのはそういった想いがあるからです」
芹澤さんがモデルにするのは江戸時代の野菜栽培。環境負荷を下げつつ、地域に適正化させること。伝統的な江戸野菜は、農業という産業ベースにのせるには無理がある。たとえば伝統的な日本小松菜は、とても柔らかくすぐにしおれてしまう。流通に向かないので中国原産のチンゲン菜と交配している。産業化するためのテクニックだ。
「たとえば、江戸時代の新宿には”内藤唐辛子”という唐辛子がありました。当時、内藤新宿と呼ばれた一帯を領地としていた内藤家に由来します。天保の大飢饉や天明の大飢饉を救った”のらぼう菜”という野菜も江戸全域にありました。江戸時代には地域に根ざした地産地消のエコシステムがありました」
芹澤さんが目指すのは”農”への原点回帰。それは農業という産業ではなく”農”といったもともとの姿。そのために、いまの大量生産の農業のシステムをアンラーン(学びほぐし)してアップデートする必要があるという。
皇居・江戸城に隣接する大手町。象徴的なビジネス街にIoT農園をオープンしたのは、原点回帰へのメッセージだ。
「高度経済成長期を支えたのは農業という産業で、そのおかげで日本は成長できました。しかし、農が産業になる前に、一般の人たちの農的な活動がありました。その活動はオフグリッドで環境負荷も低かった。世界では農業から農にシフトしています。ニューヨークやロンドンの都市の人たちが野菜を育てているのにはそういった背景があります。日本の江戸時代には、すでにそのようなエコシステムがあったんです」

芹澤さんは、都市で育てるアーバンファーミングには大きく4つのメリットがあると話す。
1つめは地域の活性化。野菜を育てることを通じてコミュニティーが活性化する。
2つめは環境貢献。地産地消でフードマイレージが短くCO2を排出しない。生ゴミが堆肥になり、緑化でヒートアイランド現象にも貢献できる。
3つめは食農教育。種の蒔き方がわからない子供たちに、食と農に接する機会を提供できる。
4つめは食料自給。自宅のそばに食料が育っているのだ。
野菜栽培が地域通貨になる未来
野菜を育てることが価値になる。すでに大手町での活動は丸の内ポイントアプリに連携している。
「将来的にはスマートシティと連携させていきたいですね。野菜を育てたらポイントがもらえて、スマートシティOSを介してポイントをクーポンなどに交換できる。将来的にそれが暗号通貨やトークンになるかもしれませんね」
芹澤さんは続ける。
「そもそも人類は、古今東西5,000年以上にわたって植物を育ててきました。江戸時代、年貢が米で納められていたように、貨幣の機能がありました。育てるという行為が地域のローカル通貨や暗号通貨の礎になるのは自然だと思っています」

祖父は植物(plant)に人という意味で er をつけプランター(planter)と名づけた。芹澤さんは「plant」にデータのInput、Outputの「io」をつけ「プランティオ(PLANTIO)」という社名にした。プランティオは、都市農園を展開しながら、デジタルプラットフォーマーとなることがコアバリューだという。
芹澤さんの祖父は戦争に出征した。特攻の部隊で生き残ったのは祖父1人だったそうだ。戦後、焼け野原の渋谷で小さな商売を始め、日本で初めて高性能なプランターを開発した。誰もが家庭で野菜を育てられるようになった。
「農に触れる機会を作った」祖父の想いをアップデートし、芹澤さんは未来を目指す。描く世界はSX(サステナビリティ・トランスフォーメーション)。持続的だった江戸時代のエコシステムと現代のテクノロジーを掛け算した農の原点回帰。それは新しい形のコミュニティーとなるかもしれない。
PLANTIO|持続可能な食と農をアグリテインメントな世界へ



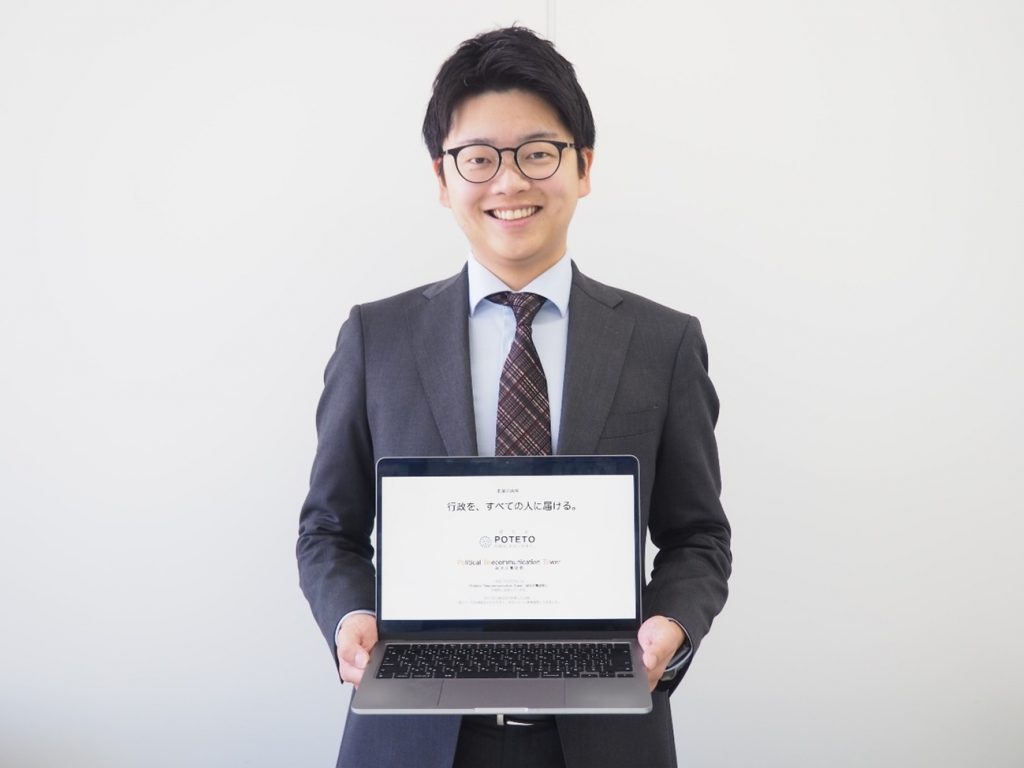 New
New
 New
New
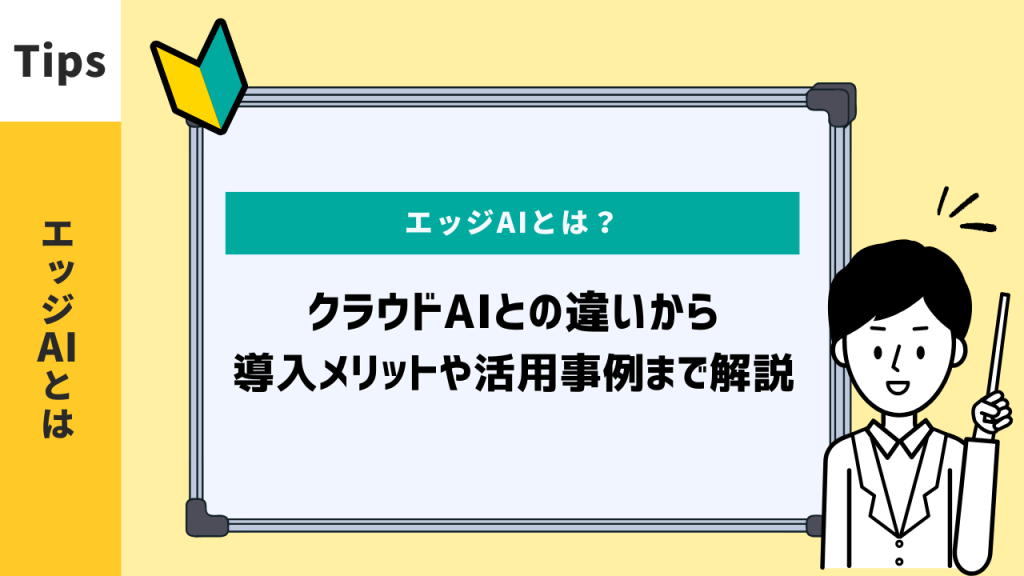
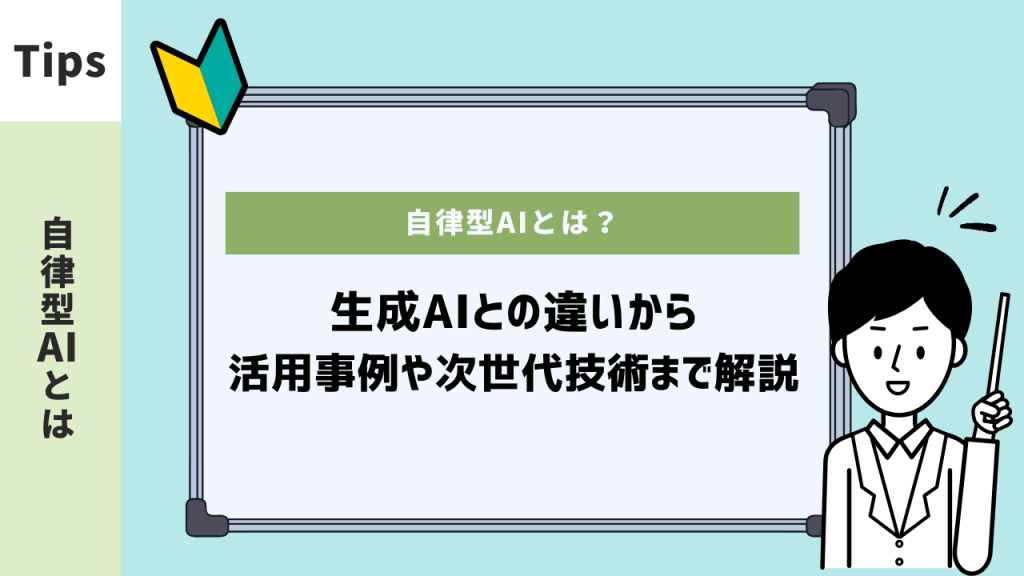
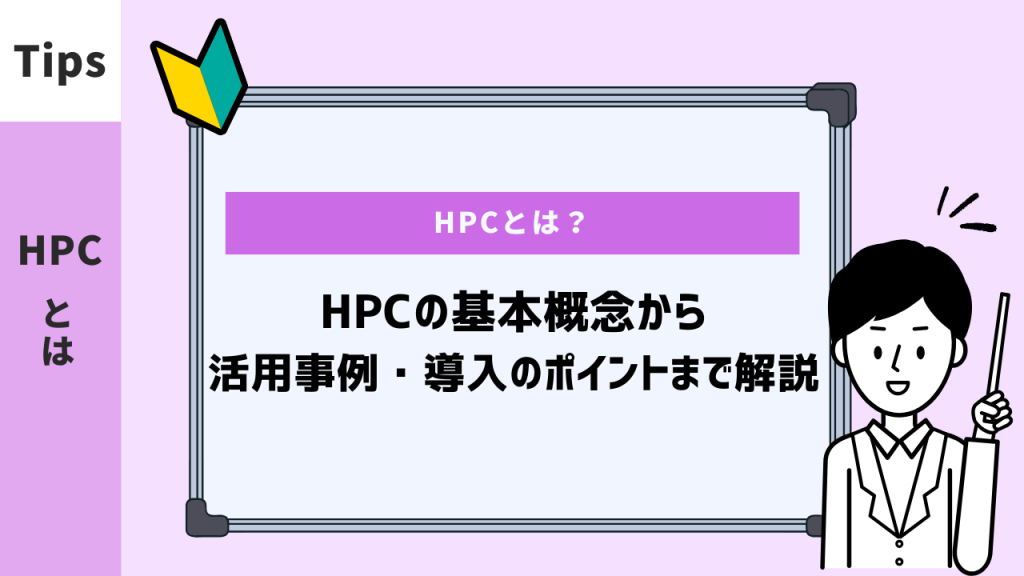
 特集
特集