>>5分でさくらインターネットのサービスがわかる!サービス紹介資料をダウンロードする
「課題先進国」とも呼ばれる日本において、企業経営に紐づけた社会課題の解決は意識すべきものとなっている。その方法や手段はさまざまであるものの、しっかりと利益を生み出しながら、社会により大きなインパクトをもたらす施策が企業には求められている。そのようななか、自社事業と社会課題の解決に綿密な関係を持たせ、地域社会の発展に寄与するとともに成長曲線を描いているのが、沖縄県にあるオリオンビール株式会社(以下、オリオンビール)だ。沖縄の戦後復興期に創業し、今なお沖縄の人々の未来を共創する同社の取り組みについて、サステイナビリティ・広報部長の丁野 良太さんに聞いた。

丁野良太(ちょうの りょうた)さん プロフィール
2021年6月オリオンビール株式会社入社。現在、経営管理本部サステイナビリティ・広報部部長として、オリオングループのサステイナビリティ/ESG対応全般、企業広報、CSR事業、行政対応、産官学民連携事業を統括するほか、「オリオングループ・サステイナビリティ委員会 事務局長」を兼務。
創業の意志を守り、沖縄の「未来」を育むビール会社

オリオンビールの創業は、まだ沖縄県がアメリカ統治下にあった1957年。創業時の資本金もB円(アメリカ軍発行の軍票)で用意された。まさに戦後復興の時代、沖縄の未来をつくるためには、地元経済復興のエンジンとなる製造業の立ち上げが求められた。
「弊社は沖縄の若者の働き口、夢を応援することを理念に創業されました。当時の沖縄には製造業が少なかったため、沖縄県内に産業を育むということで創業者の具志堅宗精を中心として立ち上げられたビール工場(当時:沖縄ビール株式会社)がはじまりです」
現社名であり、ブランド名を冠する「オリオン」の名称も公募によって生まれた。沖縄の夜に燦然と輝くオリオン座を、そして夢とあこがれを象徴する星のイメージは、未来をつくろうとしている沖縄の人々を表現するものであった。オリオンビールの歴史は、まさに沖縄の人々に託された夢とともに育まれてきたものだ。
「創業当時から現在に至る67年間、沖縄のビールとしてオリオンビールが存続している最大の理由は、沖縄県民の方々から応援し続けていただいていることです。だからこそ、オリオンビールのコアバリューのひとつに『報恩感謝』と『共存共栄』を掲げて営業してきました。私たち、そして私たちがつくるお酒は県民の方々に育てていただきました。その想いは今も変わらず、沖縄県自体のこれからの成長に、オリオンビールが貢献していきたいと考えています」
丁野さんが語るように、オリオンビールが事業成長において志向するのは、自社とともに地域社会が発展していく未来を描くことだ。「報恩感謝」「共存共栄」の言葉通り、創業以来根付く持続可能性の追求は、オリオンビールだけではなく沖縄県全体の発展を見据える。
「具体的には、県内素材の活用です。たとえば、ビールづくりの原材料は大まかにいえば酵母に水、大麦とホップです。当然、水は県内のやんばる地方を水源とする『やんばるの水』を使うわけですが、近年では琉球大学や民間企業との産学連携での研究によって、沖縄での大麦の栽培に成功しました。これにより県内の農家で栽培する品目の選択肢を広げるとともに、栽培した大麦は弊社で買い取りさせていただいておりますので、地域の第一次産業の支援に繋がっています。
加えて、挑戦しているのは県産ホップの栽培です。じつはすでに栽培自体には成功しており、現在はオリオンビールのクオリティスタンダードにマッチするかどうかの試験を進めているところです。これがうまくいけばホップも沖縄県内で栽培できることになりますので、さらに農家の方々の選択肢を広げることに貢献できます」
沖縄県産の大麦を使ったビールはすでに製造され、旗艦製品である「オリオン ザ・ドラフト」のほか、同社のクラフトビール『75BEER』など、同社のビール製品の副原材料として採用されている。加えて、オリオンビールは沖縄県産のビール酵母「OB-001」を発見、こちらも『オリオン ザ・プレミアム』の醸造で活用されている。

「ホップについては試験段階ですが、うまくいけば、酵母から水、大麦、ホップすべてが沖縄県産のビールをつくることができます。ただ、大麦でいえばその収量はまだ少なく、海外産と比較して価格も高いので、現在生産しているビールすべてを沖縄県産で賄うのは現段階では困難です。しかし、いずれは純沖縄県産ビールを製造したいと考えています」
そのほか、ビールのほかにも『WATTA』シリーズをはじめとする酎ハイ、今年に入ってからはフルーツワイン『Southern Cross Winery パッションフルーツ』の発売も開始した。酎ハイではシークワーサーのほか沖縄原産のみかん品種「カブーチー」などの果実を使用。フルーツワインでも沖縄県糸満市で収穫されたパッションフルーツを使用するなど、地元で収穫された素材を活かした製品開発を志向している。

「地元で収穫された産物をそのままお酒にすることで、沖縄の魅力を前面に出していることが他社との差別化につながっています。同時に、沖縄の素材を使わせていただくことで地元産業にも還元していく。これが私たちオリオングループの製品開発における、ぶれない想いです」
>>5分でさくらインターネットのサービスがわかる!サービス紹介資料をダウンロードする
地域に根差した企業だからこそ迅速な経営判断ができる

地域の素材を活用し、また栽培可能にすることで農業へと貢献していく。まさに酒類製造メーカーだからこそ実現できるアプローチだ。しかし、事業を持続的に成長させていくためには、県内だけでなく県外、さらには海外を視野に入れる必要がある。沖縄県はこれまで人口増を維持していたが、2022年時点で人口減に転じている。県内外でのファン獲得は事業継続の要ともいえる。
そのようななかで、オリオンビールではコロナ禍を機にECサイトやSNSの強化など、D2C戦略で売上を伸ばしてきたという。その背景にはなにがあったのだろうか。
「2019年に株主が変わったのがひとつの契機であったと思います。そこから注力をし始めた主な取り組みが酎ハイの製造開始とECサイト、そして海外展開です。正直にいえば、これまでECサイトに関してはほぼ手付かずの状態から、一気に注力したことが功を奏したといえます。コロナ禍において沖縄に来ることができない方が大勢いらっしゃったときにECサイトが立ち上がりましたので、よいタイミングでアピールできました。
コロナ禍で沖縄に来ていただくのが難しい状況でしたが、せめて製品を通じて沖縄の雰囲気を楽しんでいただきたいという想いがありました。そのため、ECサイトでは、酒類のほかにも食品、飲料などの沖縄県産品や、オリジナルグッズも販売しています。このようなコンセプトを喜んでくださり、今でも定期購入をされる方が増えています。
海外展開も同じですね。沖縄は非常に有名な観光地です。とくに中国や台湾、韓国の方によく来ていただくのですが、現在では各国・各地域で本格的に海外展開を進めていて、 観光客のみなさまが帰国後もご自身のふるさとでオリオンビールの製品を楽しんでいただけるようになりました」
また、オリオンビールでは、より市場とのコミュニケーションを重視した経営判断、製品開発に注力しているという。なかでも、近年大きな話題を呼んだのが、ストロング系酎ハイの終売だ。2024年現在でこそ、ストロング系酎ハイは健康への悪影響などの要因から終売となるケースも増えてきたが、オリオンビールが終売を決めたのは2020年。業界に先立つ英断ともいえるが、経営の観点ではストロング系酎ハイは利益率の高い商品でもある。なぜこのような迅速な判断ができたのだろうか。
「実際、ストロング系酎ハイはよく売れていましたが、当時から沖縄における適正飲酒の在り方について懸念する声があったことも事実です。沖縄に根差し、コアバリューに沖縄との『共存共栄』を掲げる弊社としては、沖縄県民の皆さまに末長く弊社製品を愛飲いただきたいという想いもあって、このような経営判断に至ったのだと考えています」
丁野さんが語るように、オリオンビールはまさに「共存共栄」の理念に基づき、迅速な経営判断を下した。沖縄というバックグラウンドと、県民全体への想いがあるからこそ、ストロング系酎ハイの終売を決断し、結果的に、この経営判断は沖縄だけでなく、日本全国でポジティブな反響を呼んだ。

「しかし、お酒をつくる企業としていくら『健康に配慮している』と対外的に発信しても、社員自身が健康でなくては説得力がありません。そのため、2020年から健康経営を推進していくことを決めました。2023年は、国内の製薬メーカーと連携し、週2日の休肝日の設定と運動を継続的におこなうことで、血糖値の改善を目指すプロジェクトを実施し、その結果、各参加者の数値を改善させることができました。ひとつだけ残念だったのは、健康診断の前日に弊社主催のビアフェストが開催されたのが影響したのか、私の尿酸値の改善が芳しくなかった点です(笑)。ただ、社内を巻き込んで健康促進に取り組み、内外で発信してきたことで、対外的にもオリオンビールに共感してくださる方々が増えてきた実感があります。同時に、社内のエンゲージメント向上にも効果があったと思います」
健康経営の推進とともに、より働きやすく生産性の高い環境の構築にも努めている。具体的には、バックオフィス業務のクラウド移行や全社的なRPAの導入など、社内で発生する事務作業やサプライチェーンマネジメントのうえで発生する煩雑な業務の自動化などを推進しているという。これにより従業員の負荷を下げ、健康と生産性の向上を両立した企業環境の整備を進めている。
環境を守り、新たな産業・雇用を創出するサステイナビリティの推進

オリオンビールは地域社会に貢献しつつ、その活動そのものが事業成長のエンジンともなっている。子会社の「オリオンホテル 那覇」「オリオンホテル モトブ リゾート&スパ」が、それを体現している拠点だ。オリオンビールが掲げる「共存共栄」には、沖縄の観光資源でもある豊かな「美ら海の自然」も含まれる。沖縄の環境が守られることで、県民の生活や雇用にもよい影響を与え、観光客の増加によって宿泊施設などの観光事業者にも恩恵をもたらす。そしてなにより、オリオンビールの売上増にもつながる。一つひとつが沖縄の発展に貢献するものでありながら、循環するように自社の利益と成長に寄与するのだ。
そのほか、同社ではサーキュラーエコノミーに着目した取り組みも進めている。さまざまな共同研究を進めている琉球大学とは、ビール製造で発生する麦芽粕のアップサイクルについても連携しているという。ビール製造では毎日約10トンもの麦芽粕が発生するが、大量の水分を含むため焼却処分には適さず、また、ただ埋立処理をしただけでは土壌への悪影響が懸念される。
「そこで、最初に目指したのは麦芽粕の肥料化です。琉球大学などと連携して栽培に成功した沖縄県産大麦の肥料にこの麦芽粕を使い、そこで育てた大麦でビールを製造するという完全循環を研究し、成功しています。2021年6月には、初めて完全循環で栽培した大麦を副原料として採用した『オリオン ザ・ドラフト』を発売しました。現在では大麦畑のほかにも、近隣のフルーツ畑や野菜畑のほか、休耕地の土壌改良にも使っていただいています。
もうひとつのアプローチは飼料化です。これは30年ほど前から実現できていたことで、沖縄県のブランド牛「もとぶ牛」を飼育する酪農家さんが、弊社のビール粕を配合した飼料を採用いただいています。麦芽粕は乳酸菌を多く含んでいる副産物なので、牛の腸内環境を整えていると好評いただいています。
さらに、近年は琉球大学が主導して進めている魚の陸上養殖でも活用いただいています。陸海にかかわらず、養殖でもっとも課題となるのは餌のコストです。飼料自体のコスト高に加え、県外からの調達で輸送費がかかるところ、県内で発生する麦芽粕を活用できればコスト低下を実現できます。この取り組みは国の支援事業にも採択され、2022年から10年間助成をいただきながら研究を進めることになりました」

同社で発生したビール粕は肥料や飼料として活用され、より環境にやさしいやり方へ、より元気な作物・家畜が育つ資源へと変わっている。さらに、同社のビール粕で育った野菜や肉は各オリオンホテルにおいてもホテルの求めるクオリティを満たす食材として採用され、宿泊客の食事として提供されている。オリオンビールと麦芽粕で育った食材を使った食事によって、同社のサーキュラーエコノミーを味覚で追体験できる。
一方で、オリオンビールが注力するのは一次産業だけではない。沖縄での雇用創出、人材育成そのものにも注力し、未来への投資もおこなっている。その一例が、同社が創業60周年のタイミングで立ち上げた「公益財団法人オリオンビール奨学財団」だ。同財団は経済的事情から進学や学びの機会を得ることが困難な人材に、給付型奨学金を助成している。その支援の対象は、学生だけに限らず、シングルマザーなども含まれる。
「創業者の具志堅は『県民のみなさまを幸せにする福祉政策は、”救貧”ではなく”防貧”の視点が重要である』と熱心に話していたと聞きます。つまり、貧しくならないための方法や経済的に自立できる方法を学ぶ必要があるということです。そういった背景で設立したのがオリオンビール奨学財団です。返済不要の奨学金を付与するほか、シングルマザーのキャリアアップを支援する団体等への助成などに取り組みました」
そのようななか、オリオンビールは2024年3月にある発表をおこなった。丁野さんも携わる、オリオンビールのサステイナビリティ活動など非財務情報を公開する特設ページの制作を、株式会社レキサス(うるま市)に委託するというものだ。レキサスは、オリオンビール奨学財団を通じたシングルマザー支援プロジェクトにより、デジタルデザイン人材14人を育成している会社だ。財団としてただ助成をするだけなく、自社としても雇用を創出する姿勢は反響を呼んだ。しかし、丁野さんは「レキサスを選定したのは、あくまでも提案とデザインのクオリティが高かったから」だという。

「オリオンビールは営利団体であり、現在はIPOを目指していますので、非財務情報を公開する特設サイトの存在は非常に重要です。そのため、選定はシビアかつドライに進めていました。コンペには全国的に展開されている大手企業にも参加してもらっています。そのようなプロセスを踏まえて、技術的にも体制としても他社に遜色ないと判断し、委託を決めました。
オリオンビール奨学財団が支援させていただいた方々がさまざまなご事情があるなかで懸命に努力して得られた結果であると考えています。わたしたちとしても、ぜひお仕事をお願いしたいと思えるものでした」
偶然にも、特設サイト制作で選定されたのは、「さくらのレンタルサーバ」だ。サーバーの選定にはレキサスからの提案があったというが、決定理由はどのようなものだったのだろうか。
「総合的に判断してさくらのレンタルサーバにしました。運用コストについても念頭にありましたが、重視したのはセキュリティです。国内企業という安心感もありますが、もしものときにすぐに相談ができる窓口など、リスク対策としてもさくらインターネットが魅力的でした」
なお、さくらインターネットは2023年9月から、沖縄にDX拠点「SAKURA innobase Okinawa」(沖縄県那覇市松山1丁目2番13号 長谷工那覇ビル1F)を開設している。同拠点の開設により、沖縄の新たな産業・事業創出やデジタル人材の育成など、さまざまなコラボレーションから沖縄発のイノベーション創出を支援していく。
沖縄の自然と産業、そして人を守り、新たな未来を描くオリオンビール。その取り組みは決して「社会貢献」だけにとどまらず、まさに持続可能性を維持しながら産業を創出する経営を推進している。最後に、今後の展望について丁野さんに聞いた。
「オリオングループ全体としては、先ほど申し上げたサステイナビリティの取り組みで、5つのマテリアリティを重要なテーマに設定しています。それは、『環境保全』『地域貢献』『ガバナンス』『顧客への責任』『人財の活用』です。
このうち、環境保全を最上位にあげています。 オリオングループにはホテルが2社あり、製造業と同時に観光業を営んでおりますし、沖縄にこられる非常に多くの方にオリオンビールを飲んでいただいています。沖縄のもっとも重要な観光資源である美しい自然の保全に取り組み、沖縄の持続可能性を強化することは、結果、沖縄の魅力を差別化要素としているオリオングループの持続可能性を強化することにほかならないと考えています。
それを踏まえて、今後は沖縄に関心を向けていただいたお客さまに沖縄の良さが伝わるよう、オリオングループだけではなく沖縄全体の価値を発信していこうと考えています。それはECサイトや海外への販売にも反映されていますが、オリオングループだけの独り勝ちはありえないのです。
すべてのステークホルダーの成長があって、初めて沖縄の成長があります。オリオンビールは、それを推し進めるエンジンのひとつとしてあり続けたいですね」
>>5分でさくらインターネットのサービスがわかる!サービス紹介資料をダウンロードする



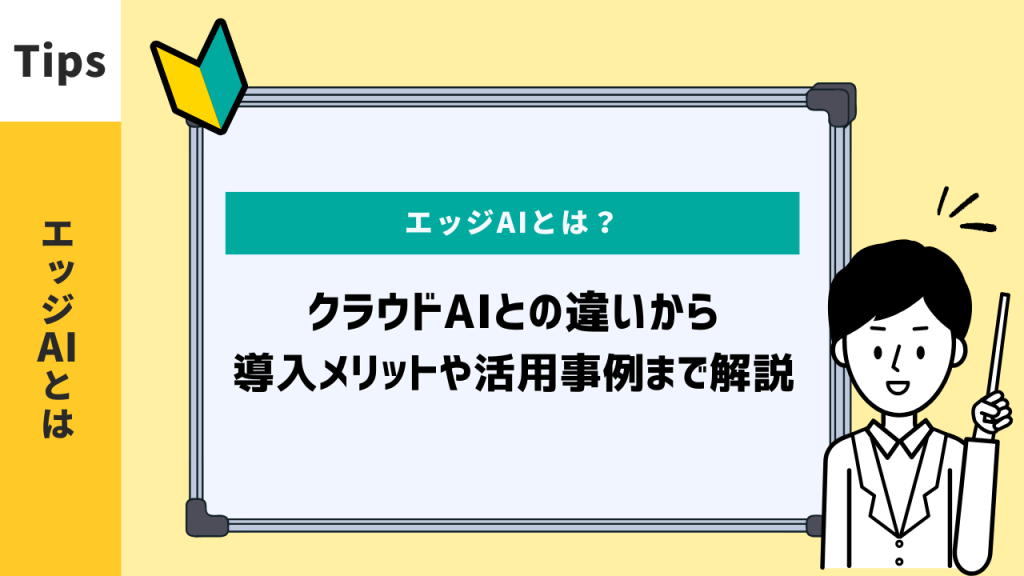

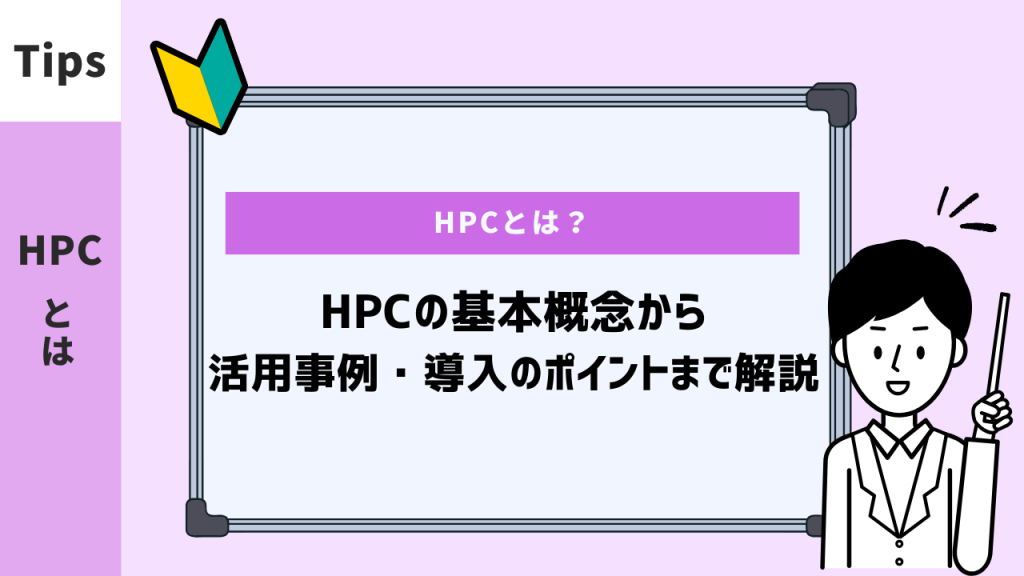
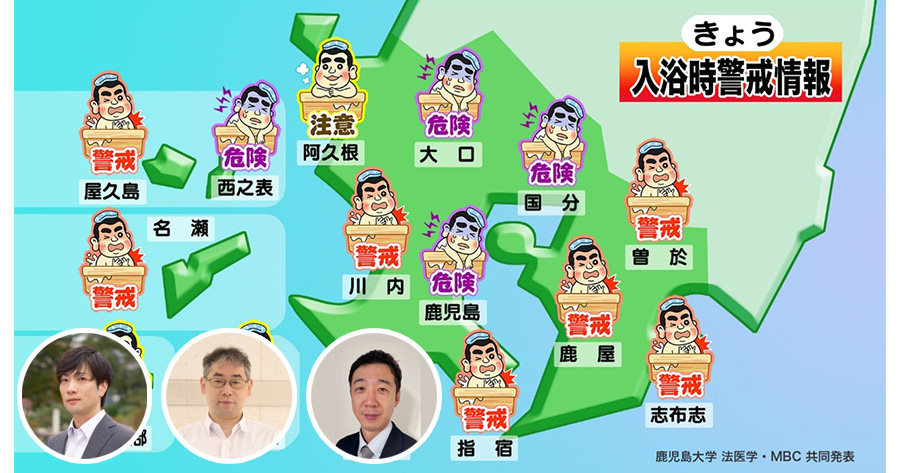

 特集
特集




