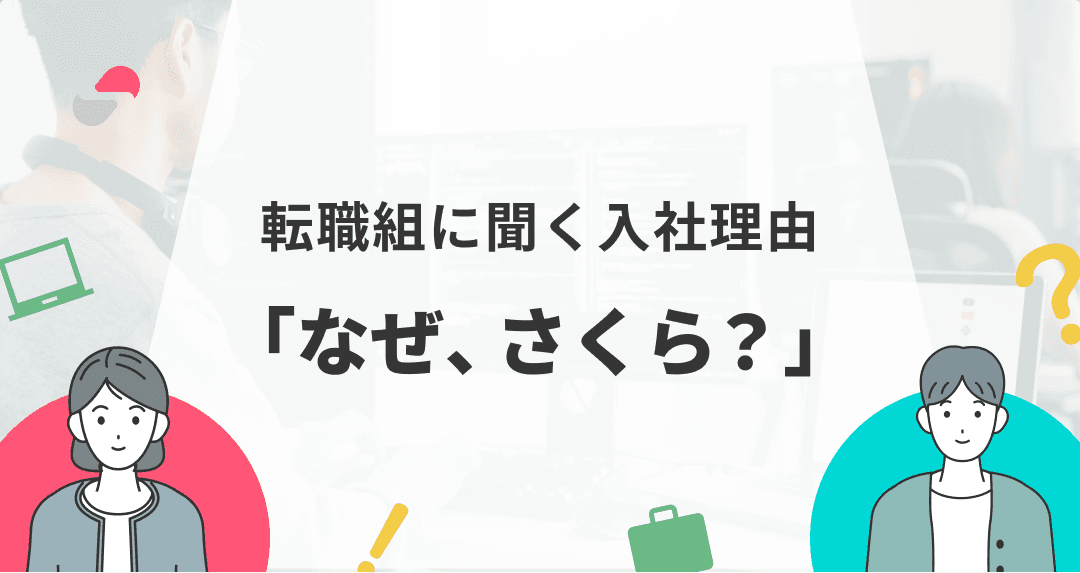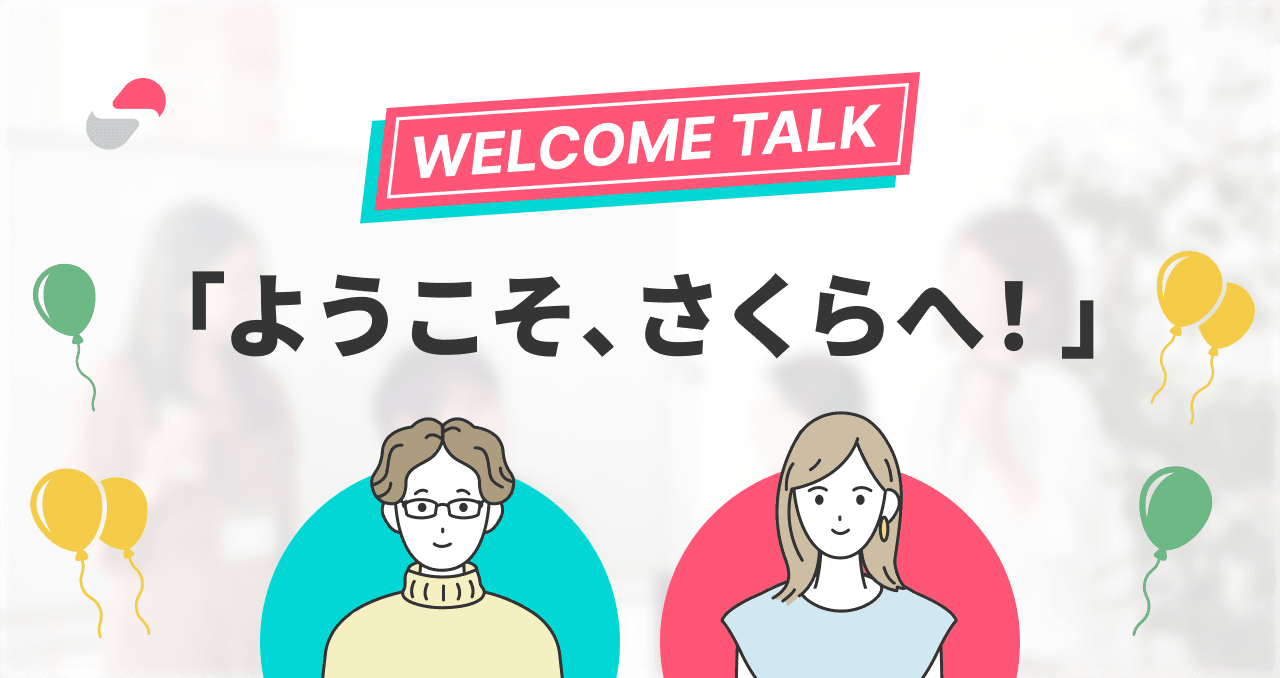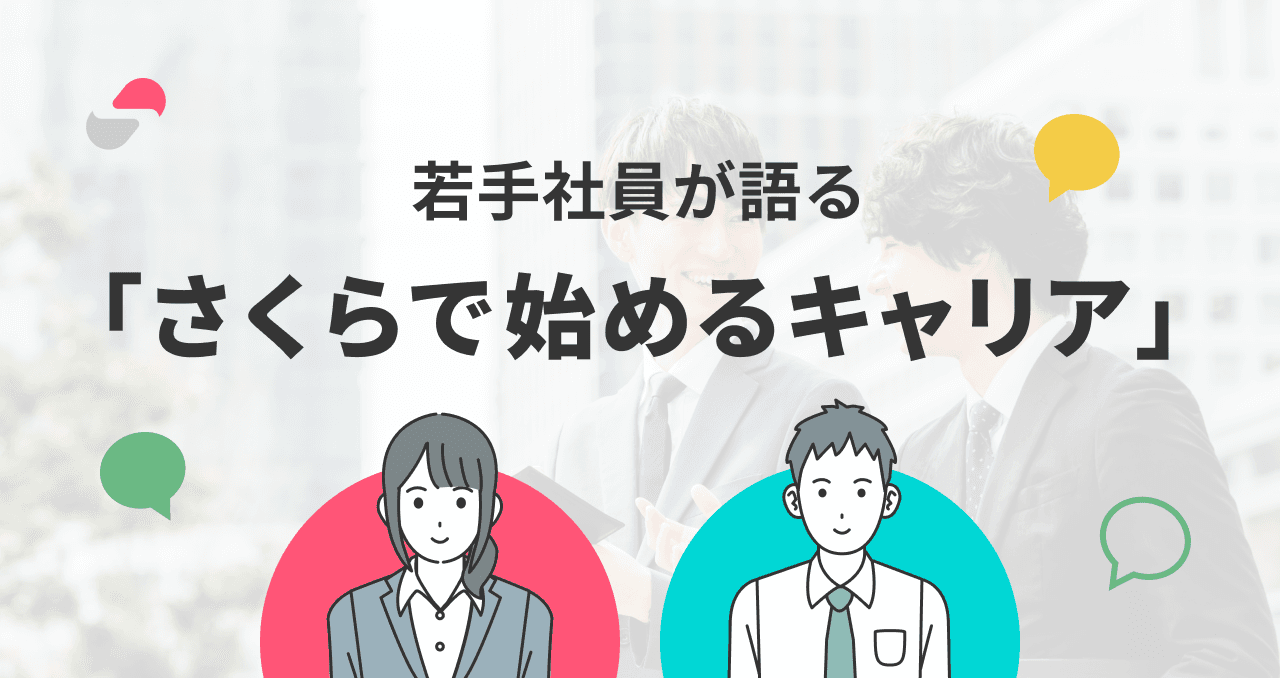大橋 太郎(おおはし たろう)さん プロフィール
1948年、東京生まれ。1971年「電波新聞社」に入社。 電子工作マガジン/マイコンBASICマガジン初代編集長。現在は電波新聞社 メディア事業本部 特別顧問、コラムニスト、電子ホビー入門アドバイザー、「日刊電波新聞」特任ライター。子ども向けの電子工作・プログラミング教室を運営するKidsVentureの特別顧問も務める。叔父はアニメ映画『AKIRA』の劇伴音楽で世界に衝撃を与えた山城祥二(本名:大橋力)さん。

2022年4月、取材場所は都内にある大橋さんのご自宅。表札にはアマチュア無線局の識別信号が書かれている。
大橋さんは小学1、2年生のころに叔父の山城祥二(本名:大橋力)さんに秋葉原へ連れて行ってもらい、スピーカーや部品の買い物を見ていた。いま思うと、叔父の影響をものすごく受けたという。73歳となったいまでも秋葉原に通い続けている。自宅には、アマチュア無線の無線機や最新の放送機材が同居している。

さくらインターネットとの関わり
大橋さんがさくらインターネットの存在を知るきっかけとなったのが「ロボット連絡会」だ。人とものづくり技術の交流の場として、大阪の日本橋で毎月第3火曜日に開催されている。
「ロボット連絡会には時間の許す限り参加していました。そこには、電子工作マガジンなどに記事を書いている久保幸夫先生も参加されていました。その主要メンバーに元さくらインターネット創設メンバーの方がいらっしゃり、存在を知りました」
7年ほど前、大橋さんは通い続ける秋葉原で「IchigoJam※」を発見し、電子工作マガジンに紹介記事とプログラムを掲載した。
※jig.jp創業者の福野 泰介さんが開発したこどもパソコン
2015年、さくらインターネットは、IchigoJamの生みの親である福野さん達と共同で、子ども向けの電子工作とプログラミング教室を運営する非営利団体「KidsVenture」を設立した。大橋さんはKidsVentureの特別顧問に就任し、子ども達にプログラミングや電子工作の楽しさを伝えている。
電波新聞社一筋半世紀超
大橋さんは、エレクトロニクス産業を基盤とした『電波新聞』やエレクトロニクス関連雑誌・書籍などを発行する電波新聞社へ1971年に入社。現在も特別顧問として働いている。両耳が難聴になってしまったが、音声自動文字起こしツールなどのテクノロジーを使って、現在も毎日仕事をしている。大橋さんが電波新聞社に入社した当時を振り返ってくれた。
「電波新聞社に入社して、1か月で出版部の配属となりました。僕はアマチュア無線にものすごく凝っていて、無線業界では結構有名でした。ちょうど『Hamライフ』というアマチュア無線の月刊誌を創刊する時期で、当時の出版部長が僕のことを知っていて、すぐ来るように言われました」

当時の大橋さんは『Hamライフ』と『ラジオの製作』を兼任していた。とくに『Hamライフ』の創刊は、はじめて関わった雑誌の仕事で印象に残っているという。続けて印象に残っているエピソードについて、語ってくれた。
「皆川隆行先生という、週刊誌のトップ屋※として名を馳せた方がいました。彼もアマチュア無線に夢中になっていました。その皆川先生が電波新聞社に乗り込んできて『Hamライフを読んでみたが、なかなかいいじゃないか。私も参画させろ。OKするまで動かんぞ』と言うわけです。先輩から『太郎ちゃん、担当しろよ』と言われ、私が担当編集者になりました」
※出版社の依頼で週刊誌の記事を書くフリーランスのジャーナリストやライター
昭和ならではのやり方で『Hamライフ』に関わることになった皆川さんだが、大橋さんとは意気投合した。皆川さんから編集のいろはを教えてもらい、新宿のゴールデン街で一緒によく飲ませてもらった。皆川さんは、主要の週刊誌には毎週目を通し、世の中がどうなっているか学ぶことの大切さを教えてくれたという。
「記事や小説などを読めば読むほど、良い原稿というのは生まれる。”うんこ”みたいなものだと教わりました。スーパースターである皆川先生と一緒に仕事ができ、当時の若い私は発奮しました」

無線コンテストの賞状も貼ってある
読者は誰か?
『Hamライフ』は4年ほどで終了し、『ラジオの製作』専任となった大橋さん。ただ、当時は競合雑誌に後れを取っていた。
「『初歩のラジオ』という雑誌に、発行部数も広告掲載数も完全に負けていました。僕は一等賞が好きなので、一等を目指しました」
『ラジオの製作』専任となり、編集長からBCL※の第一人者、山田 耕嗣先生を担当するように言われた大橋さん。しかし、当初はBCLを少し馬鹿にしていたという。
※海外放送の聴取、または聴取者
「アマチュア無線で世界中の人と交信をして友人もいましたから、海外の放送を聴くだけの何が面白いのか、と思っていました。正直に言うと、少し下に見ていた思いもありました」
ある日、山田さんからBCLの原稿を受け取った大橋さんは、原稿を手直しした。ゲラを見た山田さんから、初めてとても怒られたという。
「山田先生から『太郎ちゃん、何であたしの原稿に手を入れたの?』と言われました。僕は、山田先生の原稿は理論的ではないし曖昧だ、と答えたんです。まるで子どもが書いたと感じていました。すると山田先生が『太郎ちゃん、君は記事を誰に読んでもらおうと思ってるの?』と言われたので、読者に決まっているじゃないですか、と答えました。でも『どういう読者だ?』と聞かれ、詰まってしまったんです」
山田さんは、小学5年生でも分かるように書くことを意識していると教えてくれた。自分の知識をひけらかす記事は、初心者が読んでもさっぱり分からないし、面白くない。裾野を広げるためには、子どものような初心者でも読めるようにしたほうがいいと考えてのことだ。
大橋さんは「そうか…」と腹落ちした。その後は山田さんと協力して、各国語での受信報告書の書き方の雛形を作って雑誌に載せるなど、子どもでもBCLを楽しめるように編集した。

電波新聞社創立70周年・創刊65周年を記念し、2020年に記念特大号が発売された
皆川 隆行さんからは編集のいろはを、山田 耕嗣さんからは読者について考えることを教わった。結果『ラジオの製作』は大ヒットし、入門誌として業界トップに躍り出た。当時はオイルショックで大不況の時代。社長からは「太郎さんのおかげで、社員にボーナス払えたよ」と言われた。会社からは、ご褒美も出た。

「『ラジオの製作』の表紙は、電波新聞社の写真部長が年に1回、世界中で撮影しています。その運転手をさせてもらいました。1か月ほどヨーロッパ中をまわり、現地のアマチュア無線のイベントや放送局にも訪問しました。現地の放送にも出演したりして、楽しかったですね」
マイコンブームが到来
1970年代、マイコンブームが到来。1977年に創刊された電波新聞社の『月刊マイコン』は発行部数が多く広告掲載量も多かった。広告掲載依頼が多すぎて、掲載を断るほどだったという。子ども向けのマイコン情報誌を作りたいという声が各所から上がり、大橋さんに話が来た。
「無線やオーディオはくわしかったのですが、マイコンはまったく分かりませんでした。でも、新しいもの好きなのでやってみるか! と考え、1年間『ラジオの製作』にマイコンに関する情報を付録として載せました。それが『マイコンBASICマガジン』のはじまりです」
当時、マイコンは「何でもできる」という触れ込みだった。その中でも何が読者にウケるかを探るため、1年間さまざまな企画を考え、テストをしていた大橋さん。そんな中、当時、北海道でアマチュア無線ショップ「CQハドソン」を営んでいたハドソンの工藤裕司さんから東京進出の相談を受けた。
「工藤さんもマイコンを広げたいと考えていました。彼は北海道大学の優秀な学生を集めて、ゲームプログラミングをカセットテープに入れて売っていたんです。その注文が多すぎてどうしようもない、と相談を受けました。それで電波新聞社の支局網を使って売ることになりました」
それと同時に、大橋さんからも工藤さんに相談したことがある。付録としてテストランしていた『マイコンBASICマガジン』を単独で立ち上げるために、テーマを何にしたらいいのか悩んでいたのだ。
「『そりゃ太郎ちゃん、ゲームだよ。読者からゲームプログラムの投稿を集めたらどうだ』と工藤さんが言うわけです。実際に投稿を呼びかけたら、バンバン来るんです。編集部でやってみて、面白いと思ったものから順に載せました」
子ども達は『マイコンBASICマガジン』に載っているゲームのプログラムを自分で打ち込み、ゲームを楽しんだ。『マイコンBASICマガジン』は大ヒットし、最終的には工学系雑誌のトップになり、18万部の発行部数になった。

「やりたいこと」を「できる」に変えるには?
好きなアマチュア無線に関わる仕事を続けてきたが、マイコンについては「やりたいことではなかった」と大橋さんは語る。それでも続けられたのは何故だろうか?
「どうせやるんだったら一等賞になろうと思って、一生懸命勉強をしてきました。僕の場合、やりたいことでなくても、やってみたらハマっちゃうんです」
大橋さんは出版部で数々の雑誌を成功させ、出版部長となっていた。しかし、50歳のときにまったくの未経験である新聞記者への異動を命じられる。
「異動となって、5年間は黙って言うことを聞こうと思っていました。職人ばかりの職場でしたね。『ダラダラ書いてんじゃねえよ。新聞は月に1冊出せばいい商売じゃないんだ』などと言われました。やりたいことではなかったけど、新聞記者の仕事にものめり込んで、コラムを書けるくらいの記者になろうと思って仕事をしました」
この経験もあり、大橋さんはいまでも毎日コラムを書いている。やりたいことではなくても前向きに捉え、やっているうちにのめり込んで「やりたいこと」に変わっていった。
「いまは73歳で両耳難聴です。それでも記事がかける仕組みづくりをしています。自分が難聴になって気づいたことがたくさんあるので、ここ2年くらいは難聴の体験談や便利なツールの紹介をしています。益々頑張りますから、よろしくです」
大橋さんの”難聴記”は、日本オーディオ協会の『JAS JOURNAL』に掲載された。
大橋さんはサービス精神旺盛で、取材後に手料理を振る舞ってくれた。帰り際には事前に買っておいたパンをお土産として持たせてくれるほどだ。いまでも多くの人に慕われるのは、こうした思いやりがあるからだろう。









 特集
特集