IT・デジタル関連の最新情報や企業事例をいち早くキャッチ
>>さくマガのメールマガジンに登録する
年に数度は目にする、悲しい交通事故のニュース。自動車本体にも安全機能が次々と搭載されているが、それでもなくならないのが自動車による交通事故だ。トラックやタクシー、社用車による事故がニュースで取り上げられることもあり、社用車を有する企業にとっては、会社を守るためにも事故削減、リスク運転の軽減は大きな関心ごとなのではないだろうか。
GOドライブ株式会社(以下、GOドライブ)が提供する「DRIVE CHART(以下、ドライブチャート)」は、AIを搭載したドライブレコーダーが運転状況をつねに解析し、従業員の運転による事故やリスク運転の削減を実現する次世代のサービスだ。同サービスの開発経緯や特徴、導入企業の反響について、ビジネス本部 マーケティング部 部長の岡田 拓也さんに聞いた。

岡田 拓也(おかだ たくや)さん プロフィール
企業のブランド戦略の構築や業務設計、人事制度構築などを支援するコンサルティング会社を経て、2019年に株式会社ディー・エヌ・エーに入社。以後、「DRIVE CHART」の営業・マーケティングに従事。現在は、事業移管に伴いGOドライブ株式会社に移り、マーケティング領域の責任者を務める。
リスク運転・事故の削減に確実につなげるサービス
次世代AIドラレコサービス ドライブチャートは、名前のとおり、AIを搭載したドライブレコーダーだ。一般的なドライブレコーダーは、SDカードに映像を録画して保存していく仕組みだが、AIドラレコは録画するだけでなく映像を分析することができる。ドライブチャートは車外と車内を映す2種類のカメラを搭載。映像や加速度センサーなどさまざまなデータをAIが分析し、脇見や一時不停止などの危険な運転シーンを検出する。分析したデータはクラウド上にアップロード、レポート化されるため、見たいシーンを容易に確認可能だ。
また、ドライブチャートの特徴として、運転の振り返りを促す機能やカスタマーサクセスチームによる伴走支援が挙げられる。導入するだけで終わってしまうことのないよう、週次サマリーメールの送信、カスタマーサクセスチームによる運用方法の改善アドバイスなど、「リスク運転・事故の削減にきちんとつなげられる」サービスとなっている。実際、導入企業のなかには「一時不停止が100%削減された」「事故件数が導入後3分の1まで減った」など、目に見えて効果が表れているという。

契約台数は10万台を突破(公開日現在)。反響の大きさについて、岡田さんの見解では、「法規制の改正の影響などで、社用車を有する企業の事故防止や安全運転への意識が高まっている」のだという。
「たとえば、以前は『緑ナンバー』の運送業にのみ義務付けられていたアルコールチェックですが、2022年の法改正後は、いわゆる『白ナンバー』の社用車や、営業車を一定台数以上使用している企業にも義務付けられています。アルコールチェックの記録管理はアナログでおこなわれていることが多いのですが、ドライブチャートを導入いただければ、自動で上がってくる走行データと紐づけることで、帳票の作成をWeb上でおこなえるようになるため、効率化にもつなげられるのです」
車両管理業務は、会社だけではなくドライバーである社員自身が対応しなければならないものも多い。そのため、管理業務の負担軽減・効率化はドライバーにもメリットのある機能だといえる。
「社用車を有する企業にとって、従業員や社会の安全を守るために、安全運転を徹底し交通事故を未然に防ぐことは重要な課題となっています。それだけではなく、法改正などによって厳格さが求められるようになっている車両管理業務を効率化し、現場のドライバー・管理者の負担を軽減していくことも重要です。そのような状況下で、事故削減と業務の効率化を両立して実現できるドライブチャートは、導入するメリットがあると判断していただいているのではないかと思います」
さくらインターネットの「さくらのクラウド」とは?
>>サービス資料をダウンロードする
AIを活用して社会課題の解決に貢献したい
ドライブチャートのサービス提供を始めたのは2019年。サービス開始当時はDeNA(株式会社ディー・エヌ・エー)から提供されていた。AIを使ってできることを考えていたなかで、「技術的にも世の中の課題にもマッチする」という発想から開発を開始したという。その後、DeNAのオートモーティブ事業とJapanTaxi株式会社が統合して生まれたGO株式会社での提供となり、8月1日に設立したGOドライブで事業を承継することとなった。
「社用車が関係する交通事故は全体の事故件数に一定のインパクトを与えています。もちろん、一般車による事故も発生してはいるのですが、まずは社用車による事故を減らしていくことで、社会全体への貢献につながるのではと考えました。AIやIoTといった技術を活用し、社会課題の解決に貢献したい。この方針は当時も今も変わりません」
交通事故の原因の90%以上はヒューマンエラーと言われているという。いずれは自動運転化による事故削減も可能となるかもしれない。しかし、いま起きている事故を少しでも早く減らすには、運転をサポートし、ミスを未然に防ぐことが重要だ。そこで、まずはタクシー事業者などを訪問し、事故削減のために企業がどのような指導をしているのかヒアリングを進めたという。
「聞いていくと、交通事故を防ぐために、多くの企業がかなりの時間と労力をかけているとわかりました。具体的には、座学での研修や、事故を起こした人がいれば、教習所で再度運転を見直す機会を設けるといった取り組みが挙げられます。さらに、『事故が起きていないシーンも含めて管理者がドライブレコーダーの映像を見て、危険運転やドライバーの癖を人力で分析し、指導する』という、時間も手間も非常にかかる対策を取られている会社もありました。そもそも、何人もドライバーを抱えている会社が人力ですべての映像を見るのは現実的に不可能ですから、どうしても一部の映像をピックアップして確認することになってしまいます。AIを活用すれば、全映像データから危険運転を洗い出せるようになり、より正確なデータを収集できるうえ、作業を効率化できると考えました」

すでにAI領域の土台が会社にあったと岡田さんはいうが、それでも開発は「容易ではなかった」という。開発チームが直面したのは、ドライブレコーダーという特殊な機器のなかで、AIによる解析処理をできるようにしなければならないという課題だった。
「ドライブレコーダーという限られたスペックで『効率的に計算するための工夫が必要だった』と開発チームから聞きました。限られた計算リソースの中で精度を向上させるため、エッジ(ドライブチャート本体)と、データの移行先であるサーバーでの2段階の映像解析をおこなっています。精度が低いと、誤ったシーンがリスク運転と判定されてしまい、ドライバーや管理者の不信感につながってしまいます。そうした誤検知が起こらないような精度を担保する必要があったんです」
サービス提供開始からこれまでに分析したデータ量は、約50億km分の走行データになるという。リスク運転を検知するには、その道路の速度制限や一時停止の位置といった交通ルールデータと照らし合わせることも必要だ。車内外カメラ、加速度センサー、GPSや地図データ、道路情報などをすべて照合し、処理スピードも担保したうえでAI解析をおこなえるのがドライブチャートの強みだ。ドライブレコーダーは真夏、真冬にも車内に設置されたままとなる機器のため、ハードウェアの耐久性という点でも限界があるなか、多くの工夫を重ねたという。
「類似サービスもありますが、我々は精度の高さ、安定性に自信を持っています」
安全対策への取り組み実績を自社のブランディングにもつなげる
提供を開始した直後から問い合わせを受けるなど、企業からの反響は大きかったというドライブチャート。「社用車を抱える企業の、事故軽減やリスク運転の防止に対して意識の高さを感じた」と岡田さんは語る。
「じつは、企画段階では『そこまでニーズは多くないのでは』という意見も出ていたようです。しかし、蓋を開けてみるとそんなことはまったくなく、多くの企業さまに導入いただきました。一度事故を起こしてしまうと、企業のブランディングに傷がつきますし、事故が重なるとそれだけ車両保険もかさむというコスト的な影響もあるため、企業側の課題意識が高かったのでしょう。
ドライブチャートを導入してくださった会社がプレスリリースなどで、対外的に発表してくださったことで、新たに他社の導入にもつながるという流れも生まれています。ある運送会社さまの導入をきっかけに、同業他社さまも導入してくださるという、横のつながりも大きな後押しとなりましたね。交通事故の削減に向けた取り組みは、企業や業界の壁を超えて真似できるものです。導入企業が増えるほど、さらに導入が広がるというよい循環につなげられてのではないかと思います」

ドライブチャートの導入で初めてAIドラレコを利用した企業も多いが、戸惑う声は少ない という。Web画面の使いやすさを評価するコメントもあるといい、「開発段階で注力した部分を評価していただけていてうれしい」と岡田さんは語る。
また、導入会社内での新たな工夫も見られるという。そのひとつが、リスク運転の少ない「優良ドライバー」の表彰制度だ。こうした取り組みはGOドライブでも同様で、「ドライブチャートアワード」を毎年開催し、安全運転に貢献した会社を表彰している。
「受賞した会社さまには、ぜひ自社のブランディングにもつなげていっていただきたいですね。また、ランキング上位の会社の施策をWebでの勉強会などで共有していくことで、事故削減につなげる活用方法のヒントにしていただけたらという想いもあります。さらに2024年からは『ドライブチャート交通安全運動』というイベントも始めました。日々実施する安全施策はどうしてもマンネリ化してしまいがちなので、定期的にイベントなどで盛り上げる機会をつくっていくことが重要だと思っています」
なお、2024年の「ドライブチャート交通安全運動」には111社、4万5,000人以上の管理者、ドライバーが参画し、リスク運転を前年比25%削減という結果が出たという。
「多くの企業に参画いただけたという点で成功したと考えています。今後もイベントを通じて企業の活用度を上げ、成果につなげていっていただきたいと思っています」
GOドライブでは、開発を社内で完結できる体制が整っている。そのため、導入企業が増えることで機能的な改善ポイントが見えてきた際、すぐに開発チームにフィードバックし、アップデートにつなげられる点も強みだ。過去には、危険運転などの指導すべき映像を一旦保存してコメントを残しておける機能を追加実装した。これにより、管理者同士で情報を共有しやすくなり、ドライバーに声をかけられるタイミングで漏れなく指導できるようになったという。
「事故防止対策」は企業の義務。啓蒙活動にも注力
まずは「社用車を持つすべての企業に、事故を未然に防ぐ努力をしなければならないという意識を持っていただきたい」と語る岡田さん。
「シンプルにドライブチャートの導入数を増やしたいという想いは当然ありますが、『社用車を持つ企業は、安全管理、事故の未然防止対策に取り組むことが当たり前である』という世界にしていくことが重要だと感じています。そのためにも、啓蒙活動に力を入れていきたいですね。ドライブチャート以外にも対策方法はありますが、AI活用は取り組みやすい方法だと思います。ぜひ関心を持っていただけた企業には、ドライブチャートの導入をご検討いただけたらうれしいですね」
ゆくゆくは一般ドライバーも使えるよう、機能拡張やサービス開発にも取り組んでいきたいと語る岡田さん。交通事故件数が限りなくゼロになる世界を目指し、今後も働きかけを続けていく。
GOドライブ株式会社
会社設立時のメールアドレス作成なら「さくらのメールボックス」
>>サービスの詳細を見てみる

執筆
卯岡 若菜
さいたま市在住フリーライター。企業HP掲載用の社員インタビュー記事、顧客事例インタビュー記事を始めとしたWEB用の記事制作を多く手掛ける。取材先はベンチャー・大企業・自治体や教育機関など多岐に渡る。温泉・サウナ・岩盤浴好き。
※『さくマガ』に掲載の記事内容・情報は執筆時点のものです。
- SHARE


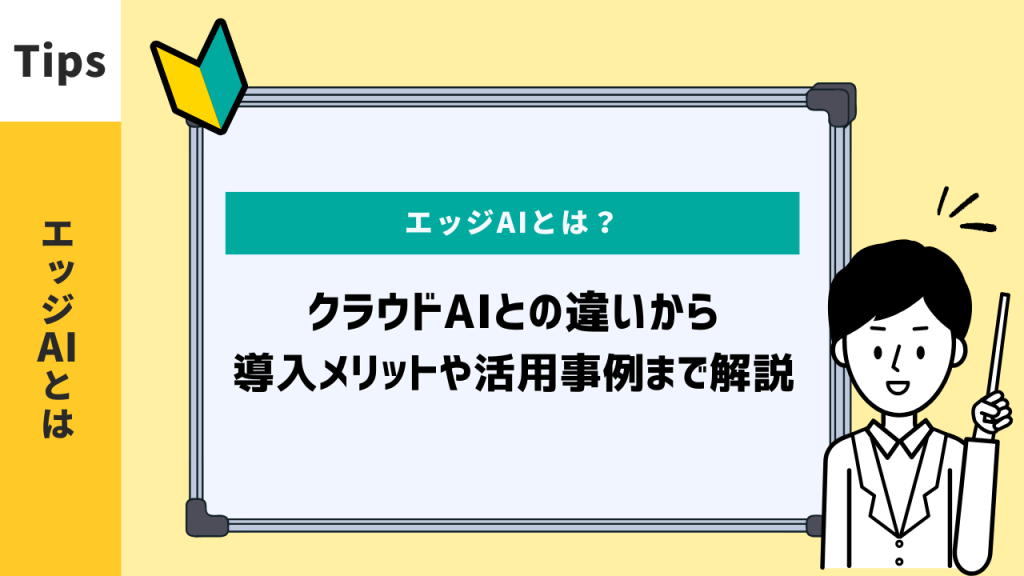 New
New

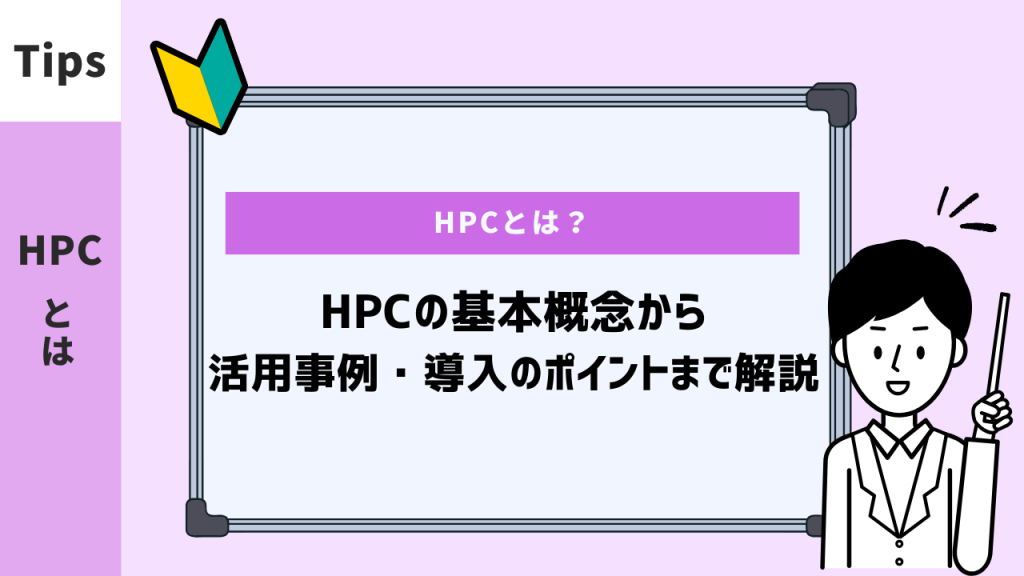
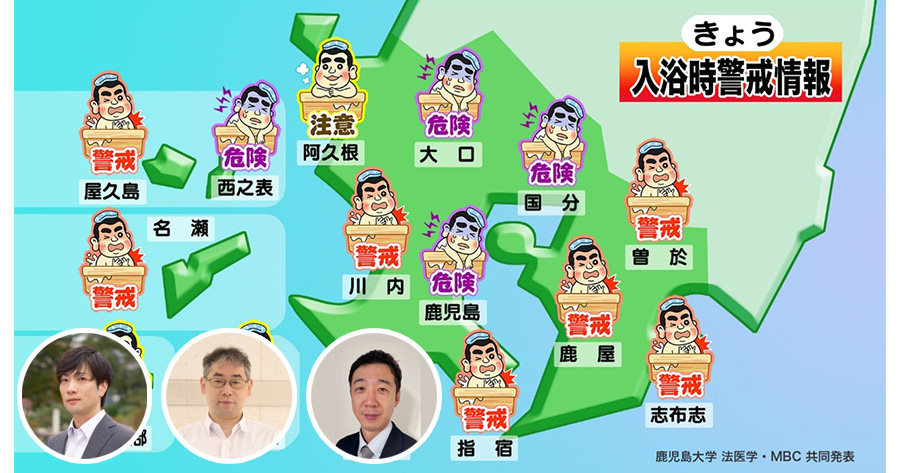

 特集
特集




