ビジネスパーソンに役立つコラムを読んでスキルアップ&隙間時間を有効活用
>>さくマガのメールマガジンに登録する
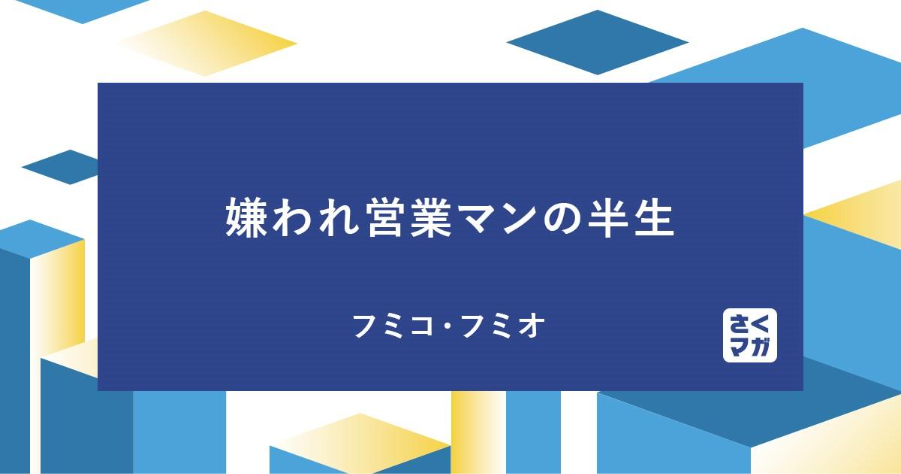
「営業」は嫌われてオッケー!
営業マンは嫌われてオッケー。これが僕の30年近い営業人生で到達した営業職像である。開き直りと思われるかもしれない。あるいは「無理な仕事(契約)を取ってくる」「強引な手法を使う」といった、営業マンに対するマイナスイメージを思い浮かべて「何をいまさら」とイラっとする人もいるかもしれない。
そういう反応は想定内だ。長い間、営業という仕事に携わってきて、さまざまな営業マンと付き合い、自分自身がいろいろな営業のやり方を実践するなど、紆余曲折を経て、嫌われてオッケーという結論に到達したのである。思いつきや自己弁護ではないのだ。
ビジネスパーソンに役立つコラムを読んでスキルアップ&隙間時間を有効活用
>>さくマガのメールマガジンに登録する
営業が何をしても許された時代があった。
僕が営業人生をスタートしたのは1990年代中ごろ、まだまだ昭和の名残が残る仕事の進め方をしていた時代だ。僕は営業部に属していた。上司や先輩営業マンは変な人が多かった。営業部全体がギスギスしていて、最悪な職場環境だった。
新人の僕から見ても営業部は暴走しているように見えた。「会社に売上(お金)をもたらせばよい」「契約を取るためなら無茶は許される」。そういう、売上至上主義があった。それらが「営業は会社の看板を背負っている」という無駄に高いプライドに支えられていたのが厄介だった。「会社にお金をもたらす営業がなければ会社は成立しない」という傲慢につながっていたのだ。結果が出ているから許されていた。僕が働いていた会社だけでなく、世間一般の会社の営業部門は多かれ少なかれそんな感じだった。
そのため、営業部は会社内のほかの部署からは露骨に嫌われていた。表向きには営業をリスペクトしていても、裏では「こんな契約を持って来やがって」「営業は現場知らない」という陰口は叩かれていたし、部署間の打合せではバチバチにぶつかり合っていた。僕はもっと要領のいいやり方、うまい方法はないものかと思ったけれども、売上や利益という数字で押し切るやり方、他部署に向かって「じゃあ自分たちで同じ売上のある仕事を取ってきてみろ」と恫喝するような手法は有効で、営業以外の部署は文句をいいつつ、営業部に従わざるをえなかった。
先輩営業マンは利益をもたらしていなかった。
営業部の先輩たちは、普段、何をしているかわからない人ばかりだった。会社から出ていくと帰ってこないのは当たり前だった。上司もそれを黙認していた。数字を出していれば何をしてもオッケーな雰囲気だった。そのため、仕事を進めるうえで必要な社内コンセンサスを取りつけるようなこともなく、コンセンサスは後回しになっていた。実際に仕事をするほかの部署から見ればたまったものではない。聞かされていない条件を相談もなしで決めてきて押し付けるのだからね。調整不足が原因の社内トラブルも多かった。いまでは信じられないような話だ。
当時の僕は、荒っぽい仕事の進め方が営業の仕事のやり方だと思っていた。多少のトラブルは仕事を進めるうえではつきものだと考えていたのだ。考え方が変わったのは、諸事情により、現場に飛ばされたことがきっかけだった。湾岸エリアの物流倉庫で現場仕事をさせられたのだ。僕の任された仕事は所長代理という名のなんでも屋で、フォークリフトでの荷受け管理と日雇い労働者への賃金支払いがおもな仕事だった。
倉庫の業務は営業部が契約してきた仕事が投影されていた。営業マンの配慮のなさが現場に負荷をかけていた。僕は作業員さんたちとデタラメなスケジュールと行程の作業と格闘した。デタラメの原因は営業部の現場への配慮のなさにあった。「荷物の出し入れはいつでもできる」「とある顧客の荷物は小口であっても優先して対応」等々、営業部が軽い気持ちから客先で話したことは現場の重荷になっていた。現場はきつかった。残業は当たり前。休憩も取れないこともあった。
現場での不平は仕事のきつさより、これだけの仕事をこなしているのに、金になっていないことに対してのものが大きかった。めちゃくちゃな条件の仕事を押し付けてくる営業部は、売上や利益をもたらしていることを免罪符にしていたが、実際に現場で働いてみると、業務の忙しさのわりには合わない金額で仕事を受けていることがわかった。
社内調整を重視しすぎると仕事は小さくなる。
結局のところ、営業部の先輩たちが口にしていた「売上や利益をもたらす」というのはイメージだけだった。実際には、いいかげんな金額提示をしてどんぶり勘定で仕事を受けてきただけだった。条件の良くない仕事、つまりおいしくない仕事を取ってきていたのだった。なぜこんなことが起きたかといえば、コンセンサスを取っていないこと、チェック体制がなかったことと、営業マン個人任せの営業部の体制のせいだろう。ガバナンスがなっていなかった。
30歳でその会社を辞め、別の業界に移り、いまもまだ営業職として働いている。転職したころから営業は、コンセンサスやコンプライアンスやガバナンスに重きを置くような仕事になっていった。世の中が変わったのだ。営業部門は社内コンセンサスを重視するようになり、案件を進めている途中であっても、関係部署との情報共有や社内調整を求められるようになった。
営業部門は仕事や契約を取ってくる部署ではなく、会社とお客様の橋渡しをするような存在に変わった。社内会議も変わった。関係部署間のギリギリした、喧嘩のような話し合いはなくなった。穏やかな雰囲気の打合せになった。
営業部門より、実際に現場を抱えている部署の意見が通るようになった。無理やチャレンジなどは論外で、守りの営業になってしまった。「いまできること」に重きを置く体制になってしまったからだ。チャレンジがなくなってしまったため、仕事の規模は小さくなりがちになった。守りの体勢になったため、過去の仕事の焼き直しが多くなり、仕事自体が退屈になってしまった。活気が失われていた。関係各署の意見を聞き、配慮をしすぎると営業部門は消極的になり、結果として会社にはマイナスになることがわかった。
営業は嫌われるくらいでちょうどいい。
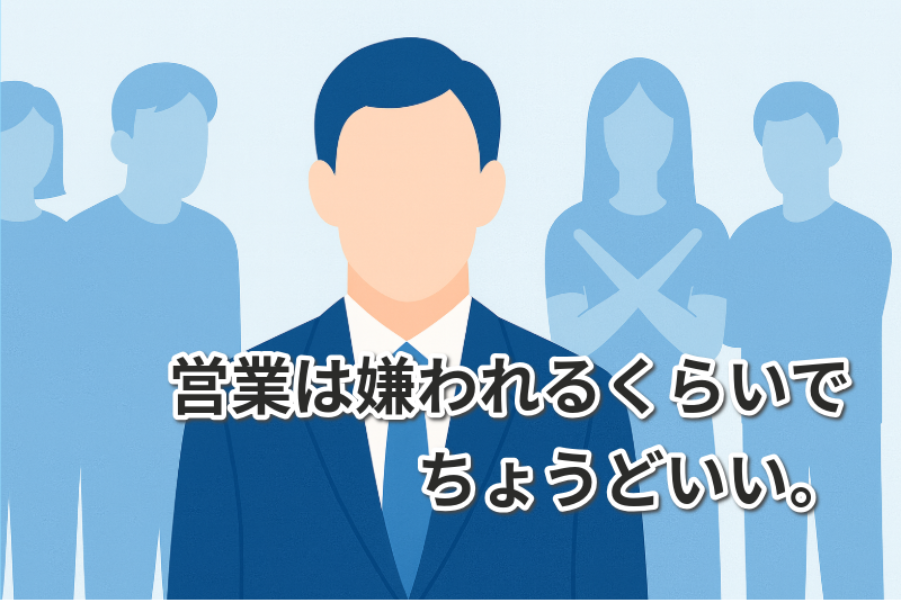
このような経緯から僕は、営業は社内から嫌われるくらいでいいと考えるようになった。営業部が、破滅をもたらさない程度の安全な無茶をしても許容されるような組織が一番いいのだと考えている。喧嘩は論外だが、関係各署や現場の声を聞きすぎて守りの体制にならないように、つまり営業部が独立しながら孤立しない程度の距離感をうまく保っていくことが、あるべき姿だろう。
営業部が力を持つことも、関係各署との関係を重視した結果、現場サイドの声が強くなることも、いいかえれば、もっとも声の大きい者を誰にするのか程度の主導権争いにすぎない。顧客不在でくだらない。そして、過度に仕事に感情を持ち込みすぎなのだ。仕事の主導権を握りたいという雑念を捨て、関係各署に配慮しすぎないような関係性を作ることがこれからの営業部にとって必要なことだろう。
とはいえ人間から感情を排除することは不可能だ。仕事をしているうえでは、「あいつの仕事は遅い」「あいつむかつく」「あいつの顔を見たくない」といった、どうしようもない負の感情が芽生えてくる。「有益な情報をあえて社内のライバルに教えたくない」という負の感情から情報共有がなされないこともある。AIやDXといったテクノロジーを使って、過度に感情が入らない情報共有や工程管理体制を構築すれば、営業部と関係各署それぞれがある程度独立しつつ、距離感を保った仕事ができるようになるはずだ。
社内で仲良しである必要はない。とくに営業は嫌われるくらいでちょうどよい。かつての先輩たちのようにただ忌み嫌われるのではなく、ある程度敬意を持った嫌われかたをされるような営業が理想だろう。そんなふうに考えながら、僕はこれからも嫌われていきたいと考えている。
ビジネスパーソンに役立つコラムを読んでスキルアップ&隙間時間を有効活用
>>さくマガのメールマガジンに登録する

執筆
フミコ・フミオ
大学卒業後、営業職として働き続けるサラリーマン。
食品会社の営業部長サンという表の顔とは別に、20世紀末よりネット上に「日記」を公開して以来約20年間ウェブに文章を吐き続けている裏の顔を持つ。
現在は、はてなブログEverything you’ve
ever Dreamedを主戦場に行き恥をさらす
Everything you've ever Dreamed : https://delete-all.hatenablog.com/
2021年12月にKADOKAWAより『神・文章術』を発売。
※『さくマガ』に掲載の記事内容・情報は執筆時点のものです。
- SHARE



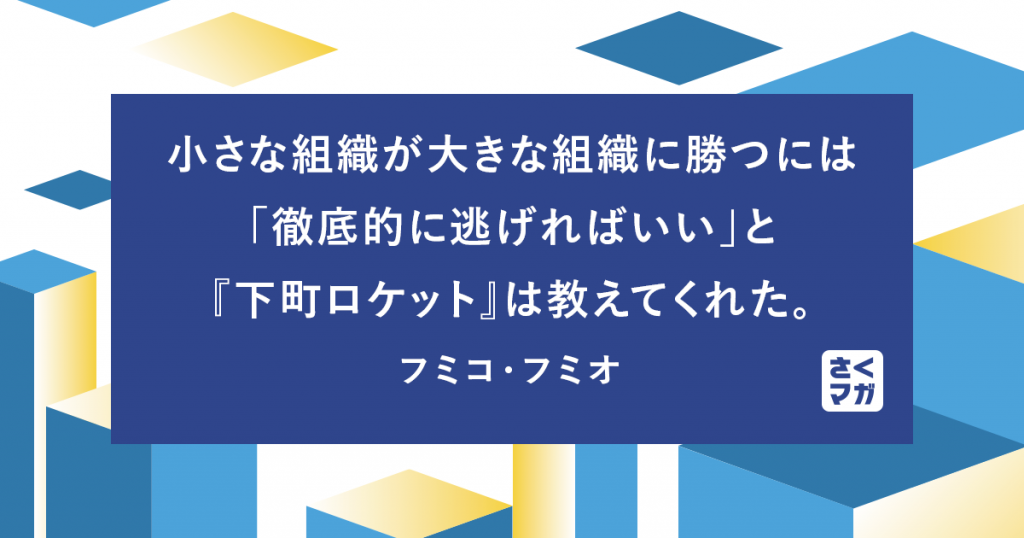
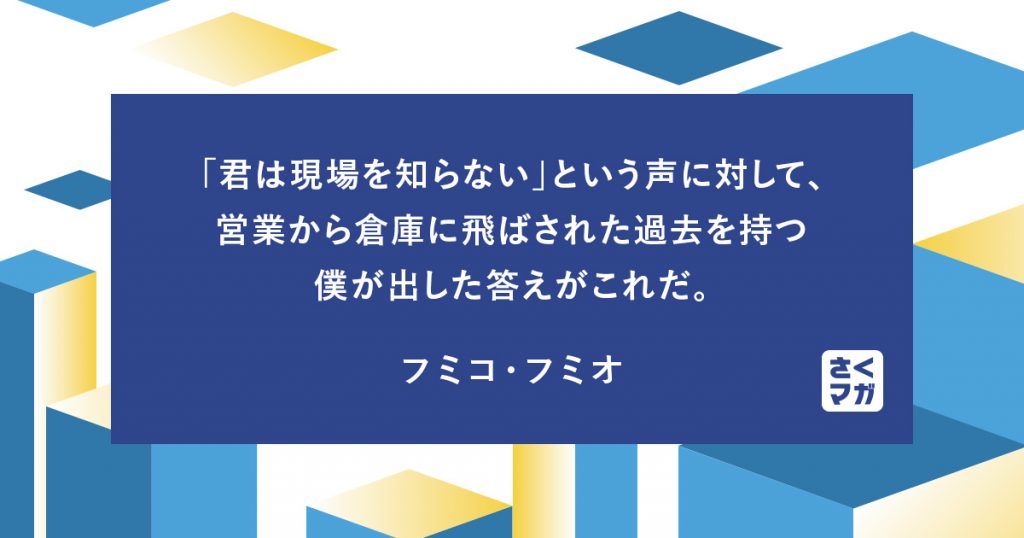
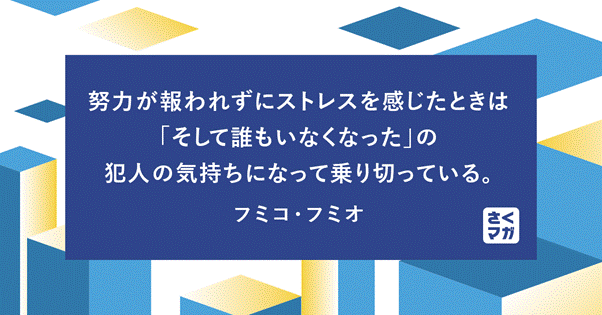
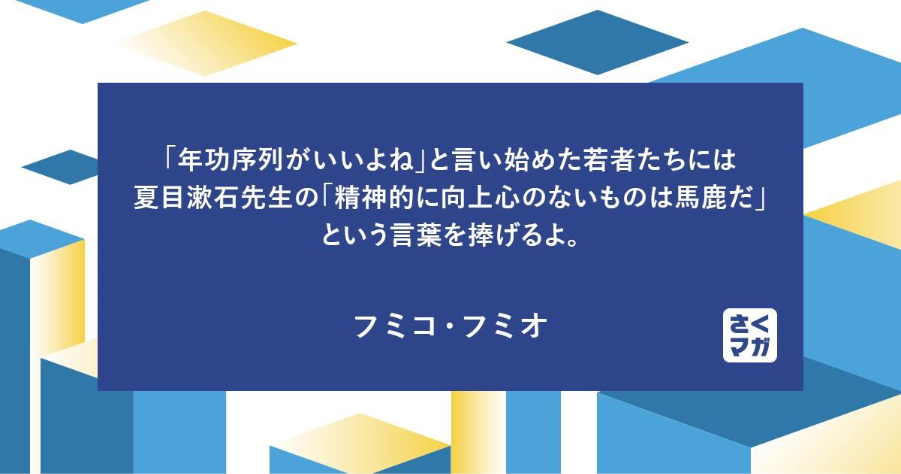
 特集
特集




