ビジネスパーソンに役立つコラムを読んでスキルアップ&隙間時間を有効活用
>>さくマガのメールマガジンに登録する
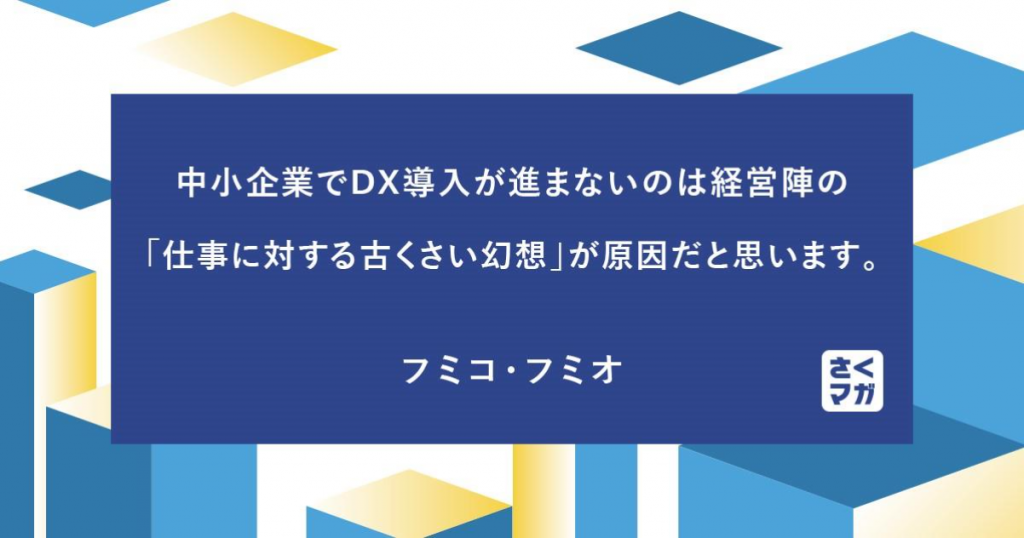
中小企業におけるDXやAIの導入が予想よりも進んでいない(ように見える)。その原因として、経営陣の理解不足が挙げられるが、それだけではない。経営陣は、DXやAIをくわしくは理解していないものの、業務効率化やスピード化といった効果は十分に理解している。僕は、経営陣がDXやAIの導入に躊躇しているのは、(彼らが考える)「仕事の価値」が下がることを危惧しているからだと考えている。
DXやAIによって企業が受ける恩恵は大きい。とりわけ中小企業が受ける恩恵は大きい。DXやAIの活用で、マンパワー不足が解消され、競合する大企業との差を一気に縮められる可能性があるからだ。経営陣は、その可能性を理解している。僕が勤めている会社の上層部も、DXやAIを正しく理解しているか怪しいが、業績を伸ばす可能性があるものと理解はしている。
経営陣は、業績を伸ばすものに対してのアンテナを持っている。たとえばGoogle。仕組みや意義を理解していないが、「Googleで検索すれば一発で入手したい情報にアクセスできる。昔なら、一日がかりで図書館や役所へ足を運んで調べなきゃいけなかった……」と理解している。Googleが何かよくわかってはいないが、「仕事を便利にしてくれるもの」と理解している。
もっとも、僕の会社の場合、経営陣からAIがどういうものかわかりやすく説明するよう求められたとき、「ドラえもん」と答えたのが悪かった。「思い通りに動かない」「わがまま」「ポンコツ」といった取り扱いが難しい印象を持たれてしまった。反省している。
経営陣は「DXやAIが人間のやる仕事の価値を下げる」と考えている。
経営陣は、DXやAIの活用で仕事の価値が下がると真剣に考えている。仕事とは、人間が汗水たらし努力をして成し遂げるものだと考えているのだ。DXやAIを活用して効率的に成果を出すことは仕事ではないとさえ考えている。汗をかいていないからだ。
新卒で働き始めたとき、上司や先輩から「営業は足で稼げ」「靴底が擦り切れるまで歩け」と教えられた。営業は契約を取ることが目的だ。契約を多く取るためには多くの見込み客に接触する必要がある。そのために自らの足で、靴が擦り切れるくらい多く訪問することが当時は必要だった。時代は変わった。多くの見込み客と接触するためには、ネットで情報を入手してターゲットを絞ってからコンタクトするほうが、地図を片手に足で歩き回るよりもはるか効率的で、早く、多くの成果を出せる。ところが汗をかいて苦労していない仕事を経営陣は仕事と認めない。楽をしているからだ。
先日もこんなことがあった。ネットに出した広告を見て問い合わせがあり、そこから何も苦労もなく、成約に至った案件があった。ラッキーだ。コストも手間も時間もかかっていない。経営陣の立場からでもローコストで成約に至ったのだから万々歳のはずだ。ところが経営陣は「ネットの問い合わせで取った楽な仕事」と低く評価している。経営陣は、仕事を「汗を流し苦労して成し遂げること」と考えていて、そこに価値があると考えている。成果ではなく過程においてどれだけ労力をかけたかが評価ポイントになっている。
つまり経営陣は、DXやAIを活用した効率的な仕事を、どれだけ成果や結果を出そうとも、仕事として認めたくないのだ。僕が勤める会社の上層部には、DXやAIを、人間がやる仕事の意義や価値を下げるものと評価していて、価値や意義を下げるものをわざわざ導入する必要はないと結論づけている人までいる。導入へのハードルは高い。
ビジネスパーソンに役立つコラムを読んでスキルアップ&隙間時間を有効活用
>>さくマガのメールマガジンに登録する
経営陣は人を育てることが仕事だと考えている。
経営陣はDXやAIによって人材が育たなくなると考えている。人材育成をはばみ将来的に企業にマイナスをもたらすと真剣に考えている。DXやAIによって業務が革命的に効率化とハイスピード化が実現することはわかっている。だが、面倒な業務をDXやAIに任せることにより、人材教育の機会が損なわれると考えている。
たとえば営業職なら、企画書の作成はAIを活用してさくっと作って、いくつかの例からベストなものを選んでブラッシュアップしていく方向性にシフトしている。だが経営陣からみれば、企画書をゼロから作って上司から先輩からの厳しいダメ出しを経て完成するものであり、さくっと作成することは、すなわち成長の機会を奪うものだと認識しているのだ。
わからないではない。経験のない新人がいきなりプロ仕様の企画提案書をもって「確認してもらえますか」といわれてもダメ出しするところがないのだから。上司の面目丸つぶれである。
しかし、中小企業の場合、人材の確保は困難だ。今後、もっと厳しくなることが予想されている。さらに人材の流動化も進むので、人材を育てる余裕はなくなる。従来の属人化した仕事のやり方では、置いていかれてしまう。DXやAIの導入で「この人しかできない」みたいな属人化された部分を少なくするしかない。
経営陣はバカではない。この問題をわかっている。しかしながら、それでも経営陣は人材を育てて、優秀な人材を抱えなければならないという固定概念が捨てられない。そのため、DXやAIによる効率化・省人化を受け入れられない。これについては、人材確保の難しさや、属人化した仕事の問題点を粘り強く説明していくしかない。ハードルは高い。
経営陣はテクノロジーで余裕ができた社員を許せない。

経営陣は、DXやAIで効率化高速化が進むことで、社員の労力が減るのを問題視している。つまり、効率化によってた余裕に何をさせればいいのかわからない。先ほどの足で稼ぐ営業のエピソードのように、手段が目的化してしまっているため、労力が削減されたとき、どんな仕事を与えればいいのかイメージできない。実際に体を動かし頭を使い試行錯誤を繰り返すことが、価値のある仕事という認識があるからだ。僕も会社上層部から「社員の仕事を軽減させてどうするの? 楽になったぶん給与は減らしていいの?」と質問されたことがある。労基案件だ。
営業職なら、外回り営業や案件掘り起こし作業が軽減されたぶんを、企画提案のビルドアップや、新たな企画の創造へ向ければよい。ところが創造や創作といった新しいものを考える行為が、経営陣の目には仕事とは映らない。企画やアイデアは、過去の実績からコピ-するか、執拗な試行錯誤とやり直しによって作り上げるものだと考えている。
中小企業が生き残るためには、大企業ができないような尖った企画で勝負をしなければ勝てなくなる。また、かぎりある人材や労力を重要な事案へ集中投下する必要がある。DXやAIの導入で業務を効率化・スピード化して人材と労力の余裕をつくっていくしか道はない。しかし、経営陣は、社員やスタッフが汗をかかないことに抵抗感がある。自分たちが過去にやってきた仕事、経験、実績に縛られている。三つ子の魂百までというわけだ。
経営陣はDXやAIの利点がわかっていることが問題。
以上のように列挙していくと、DXやAIの導入が進まないのは、理解不足というよりも、ある程度理解したうえで、DXやAIを取り入れた仕事のやり方が、彼らの考える仕事像から乖離しているからだとわかる。体を使わないのは楽をしている、つまり仕事をしていないという思い込みがある。
言い換えれば、経営陣は、DXやAIの意義や効果についてほぼ正確に理解できているということになる。理解したうえで、これまで自分たちがやってきた仕事の意味合いが変わることに対する抵抗感があるため、導入に二の足を踏んでいるのである。DXやAIを導入した仕事が想像できないのではなく、想像できているからこそ、導入に抵抗している。厄介だ。
ウチの会社では経営陣が「ドラえもんは便利だけれどトラブルを起こす。トラブルを起こす存在はいらない」という感じでDXやAIを認識しているので、「劇場版ではドラえもんは立派に活躍して世界を救っています」と説得してきた。この説得によって、DXやAIの導入へ着実に進んでいるので、真似していただけたら幸いである。いずれにせよハードルは高い。地道にやっていくことが肝心だ。
ビジネスパーソンに役立つコラムを読んでスキルアップ&隙間時間を有効活用
>>さくマガのメールマガジンに登録する

執筆
フミコ・フミオ
大学卒業後、営業職として働き続けるサラリーマン。
食品会社の営業部長サンという表の顔とは別に、20世紀末よりネット上に「日記」を公開して以来約20年間ウェブに文章を吐き続けている裏の顔を持つ。
現在は、はてなブログEverything you’ve
ever Dreamedを主戦場に行き恥をさらす
Everything you've ever Dreamed : https://delete-all.hatenablog.com/
2021年12月にKADOKAWAより『神・文章術』を発売。
※『さくマガ』に掲載の記事内容・情報は執筆時点のものです。
- SHARE



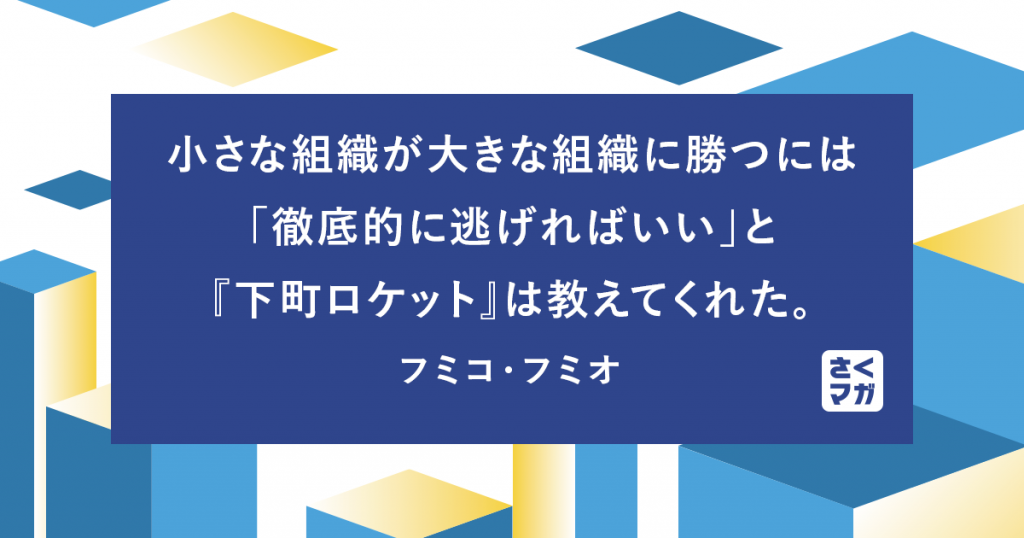
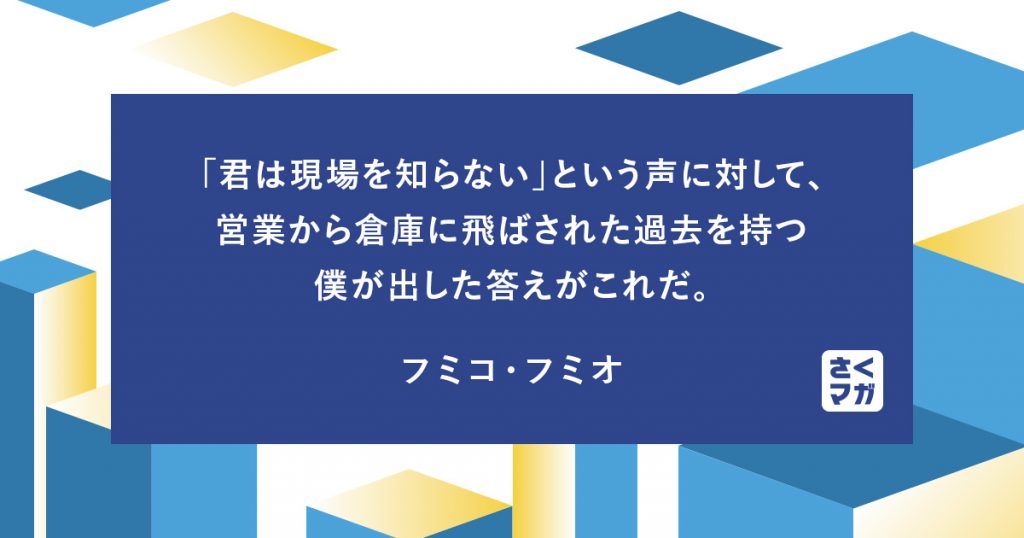
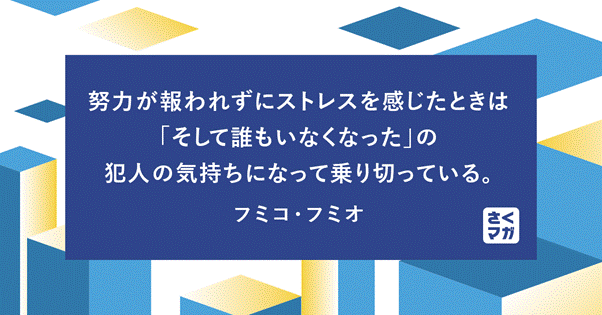
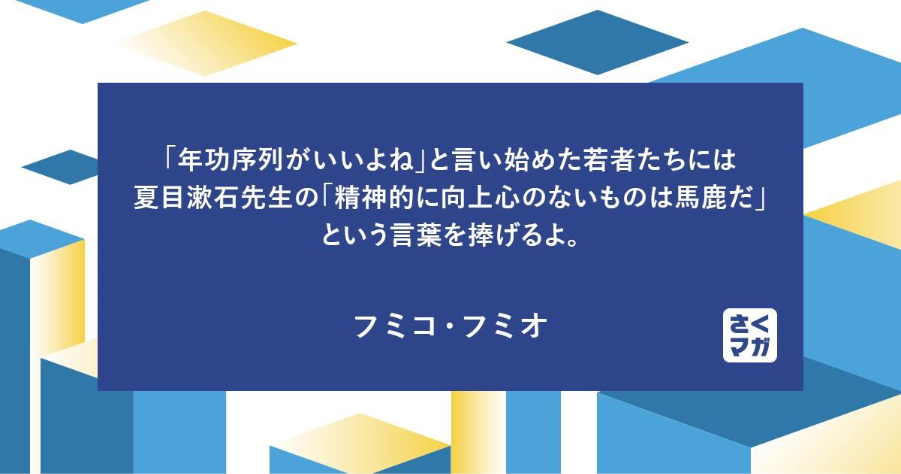
 特集
特集




