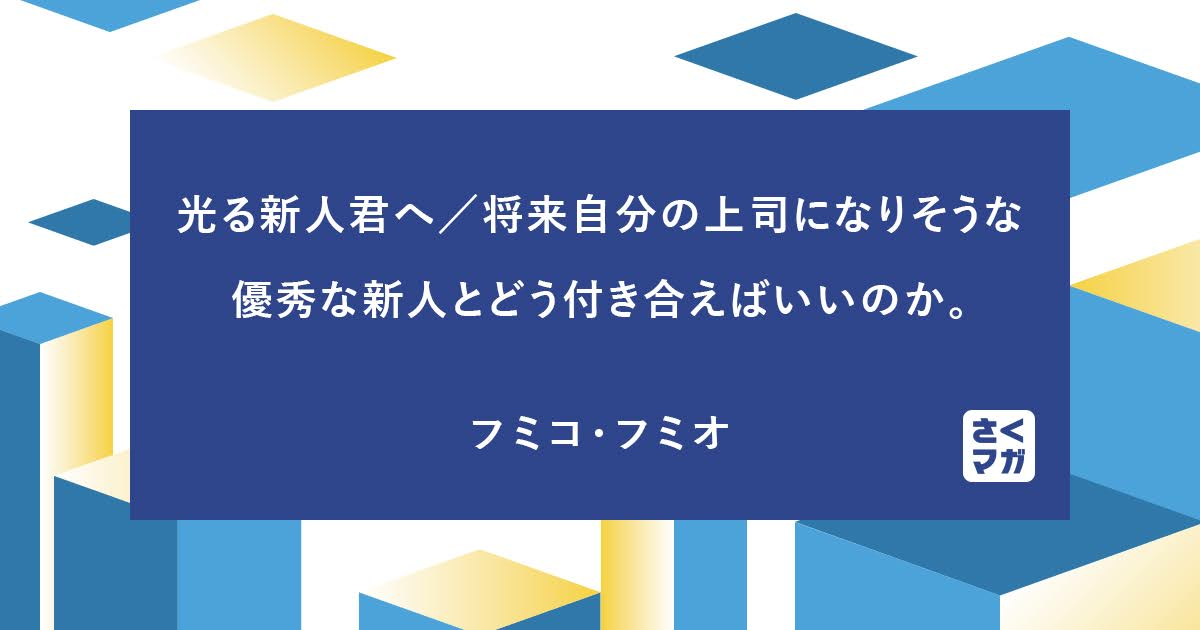
ビジネスパーソンに役立つコラムを読んでスキルアップ&隙間時間を有効活用
>>さくマガのメールマガジンに登録する
新人が配属されるハードな季節のはじまり
この文章がアップされるのは6月。春の終わり、夏のはじまりである。清少納言が「枕草子」で「春は、あけぼの。やうやう白くなりゆく山ぎは、すこしあかりて、紫だちたる雲のほそくたなびきたる」、要するに「春って夜明けがいいよね」と歌っていた春が終わった。現代社会において春は、「夜明けがいいよね」などと長閑なことを言っていられる季節ではない。なぜなら、春は新卒社員の入社、人事異動、組織改編のある慌ただしい季節だから。そして、本格的な夏にかけて、新人研修を終えた新人が配属され、能力や性格が次第に明らかになっていく油断ならない季節が続く。今年の新人が有望な「光る君」なのか、あるいはまあまあよくやってくれそうな平均的な人なのか、それとも、時間と手間がかかる育てがいのある「かわいいヤツ」なのか、判明するのである。
僕の28年の会社員経験では、「光る君」が10パーセント、「まあまあ」が60パーセント、「かわいいヤツ」が残り30パーセントくらいだろう。本人の努力次第で当初の評価を覆してエース級に育った人もいるので、新人のみなさんは各自頑張ってもらいたい。一方、初見の評価というのはだいたい正しい。メジャーリーグで大活躍している大谷選手やダルビッシュ選手は、ドラフト1位で日本ハムに入団している。つまり新人時代の評価もめちゃくちゃ高かったということ。会社も同じ。そして光り輝く新人は、そのまま順調にエースに成長して役職につくのも早い(例外はあるけれど)。なぜかというとエース候補はエース候補として大切に育てられるからである。
優秀な新人に対して警戒心を抱いてしまうのはなぜか

ここ数年、会社関連でニュースやネットの話題になるのは、新人たちのありえない言動である。つい先日も「配属ガチャを理由に入社当日に退職した新人」が話題になっていた。僕自身はずっと会社勤めを続けている関係上、「会社勤めはそんなに悪くない」という立場を取らざるをえないが、会社を光の速さでやめてしまう新人たちに対して「それは間違っている」と非難するつもりはまったくない。それぞれが自由に自分で選んだ道を進めばよいだけのことなのだ。
実際、上記のようなありえない言動をする新人はレアな珍種。それより、仕事をしているうえでわれわれが気にしなければならないのは、配属されてきた新人である。まあまあな新人や手のかかる新人については、おもしろおかしく語られているし、僕自身もブログや寄稿記事で取り扱ってきた。一方で、エース級に育つ素質を持っている優秀な新人にはあまり触れられない。なぜかというと仕事をそつなくこなし、上司や先輩や同僚と良好な関係を築き、同期たちのリーダー的なポジションにはまるような優秀な新人の話は、なんかムカついておもしろくないからだ。
優秀な新人は、将来、自分の立場を脅かしかねない存在でもある。つまり、自分より若く優秀な新人が入ってくることは、危機なのだ。若さだけでも大きなアドバンテージがあるのに、見かけも爽やかで歯が白く、学生時代にスポーツをやっていて体格も細マッチョだったりしたら、歯槽膿漏と尿漏れと体力の低下に悩む中年に勝ち目はないのである。そんな素晴らしい人材をブログなどインターネットで取り上げることは、自分を卑下することにほかならない。そんな記事は書きたくない、という嫉妬が、手のかかる新人の話が記事のネタになりがちな理由なのではないだろうか。
卒業のない会社生活はビーチフラッグ競技のようなものである。
優秀な新人に僕らはどう対応すればいいのだろう。彼らを目の当たりにしたときに覚える嫉妬や焦りから完全に自由にはなれない。とはいえ優秀な新人を粗末に扱うと「人間としてどうなの?」「みじめな奴だ」と周囲から見られる。また、優秀な新人は我々先輩に対しての気遣いまで万全なので、それがまた己の人間の小ささを突き付けられる。きっつー。
会社で生き残るということは、限られたポストを大勢で争うビーチフラッグ競技のようなものだ。日本の職場は、まだまだ年功序列が残っているけれども、それでも実力主義を採り入れてきている。つまり力のある新人がわれわれ先輩を追い越していくことが、以前よりも容易にできるようになってきている。若く能力が高く柔軟な発想のできる若者と争って会社ビーチフラッグで勝てるだろうか。勝てない。
また、一昔前と比べて経験がアドバンテージになりにくくなった。インターネット上に経験や知識が公開されているからだ。そのうえ、対話型AIの発達で今後は相談役としての需要も失われていく。ますます先輩社員の優位性は失われていくだろう。
優秀な新人が現れたとき、1ミリも嫉妬や痛みを感じず、危機感を覚えることなく受け入れることができるだろうか。聖人ならできるかもしれない。会社は学校のように卒業がない。能力と実績によって飛び級がたびたび起こる。こいつは、将来自分の立場を脅かすのではないか、自分を追い抜くのではないか、という危機感を覚えないほうが不自然である。
その危機感をどうやって消化するか、あるいはプラスに転換していくか、それが、会社を生き抜くための大きなポイントだと思う。なぜなら、優秀な新人は毎年出現する可能性があるからだ。そして受け入れる側は毎年、体力や気力を失っていくからだ。
光る新人とどう付き合えばいいのか。

優秀な新人との付き合い方はいくつかのパターンに分類できる。もっともやってはいけないのは、排除することだ。将来、自分の敵となりえるものは事前に排除するという考えだ。これはマジで最悪。優秀な人材は会社の宝。宝を失うことは会社にとって大きな損失であり、巡り巡って、得られたであろう売上や利益を損失するため、未来の自分の給与や賞与が下がるという事態になりかねない。また、超優秀な新人を排除しようとしても、彼らを一時的に劣勢に追い込んだところで、最終的にはその圧倒的な能力で反撃をしてくるだろう。十数年後、上司に乗った新人くんから呼ばれて「あのときは参りましたよ」と無人島への異動の辞令を渡されるのである。
かといって、「この優秀な新人は将来、自分の上司になる大人物だ」と見込んで、当初から部下的なマインドをもってご機嫌を損ねないように付き合うのも考えものである。最近の若者はドライでビジネスライクなので「この先輩ペコペコして使えないな」と評価されたらやはりリストラ肩たたきで無人島行きとなるだろう。
以前勤めていた会社で経営者一族の長男が新卒で入ってきたとき、一部の人たちは「この人物は将来上司になることが確定しているから」と丁重に扱ったことがある。結果から言えばお互いにとって最悪だった。長男は能力的には平凡であったが、周りからの丁重な扱いを受けて「自分はすごい人物だ」と勘違いして入社まもなくしてスーツにバスケットシューズで出勤するなどアホムーブをかまし、アホを丁重に待遇した者たちはアホの取り扱いを間違えたことで周りからアホ扱いされたのである。新人を特別視することがよい結果をもたらさない好例だと思う。
優秀な新人に媚びずに普通に付き合うのがベスト
結局のところ優秀な新人に対しても卑屈にならずに毅然とした態度で接するのがベストになる。優秀な新人、スーパールーキーと比べたら、全体的な能力は劣っているところがあるかもしれない。けれども、卑屈にならずに付き合うこと、そのなかでキラリと光るところを示せればよいのではないか。そして優秀な新人に引っ張ってもらい、追随すればよい。新人はたまたま生まれたのが後だっただけのこと。特別視せず、卑屈にならず、同僚の1人として付き合えばいい、という無難な結論になる。それがなかなか難しいのは、年配先輩としての意地、嫉妬という感情があるからだ。仕事は仕事と割り切ってつまらない感情を捨ててしまおう。
僕は会社員生活を長く続けている。幸い、後輩に立場で追い抜かれたことはない。一度だけ教育担当をした後輩と課長職で並んだことはある。当該後輩について僕は特段厳しくしたつもりはなかったけれども、立場で並んだときに「先輩には厳しく教えてもらって感謝していますよ」と本音なのか嫌味なのかわからぬことを言われた。その後は、同僚として友好的に協力しあって業務に従事した……という美しい話にはならなかった。ライバルとして切磋琢磨して競争した。その競争のなかで実力がついた。売上も伸びた。よいことづくめだった。
このように、優秀な新人が入ってきても、平常心とリスペクト精神を持って特別視せずに付き合っていくこと、それが将来その新人が自分の上司になったときにもよい結果に繋がるのだと思っている。

執筆
フミコ・フミオ
大学卒業後、営業職として働き続けるサラリーマン。
食品会社の営業部長サンという表の顔とは別に、20世紀末よりネット上に「日記」を公開して以来約20年間ウェブに文章を吐き続けている裏の顔を持つ。
現在は、はてなブログEverything you’ve
ever Dreamedを主戦場に行き恥をさらす
Everything you've ever Dreamed : https://delete-all.hatenablog.com/
2021年12月にKADOKAWAより『神・文章術』を発売。
※『さくマガ』に掲載の記事内容・情報は執筆時点のものです。
- SHARE


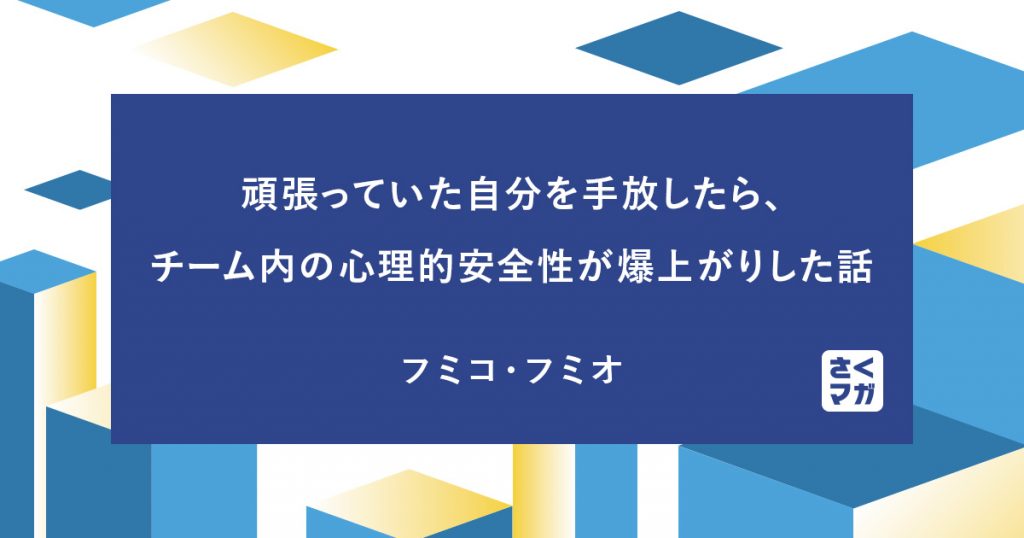 New
New

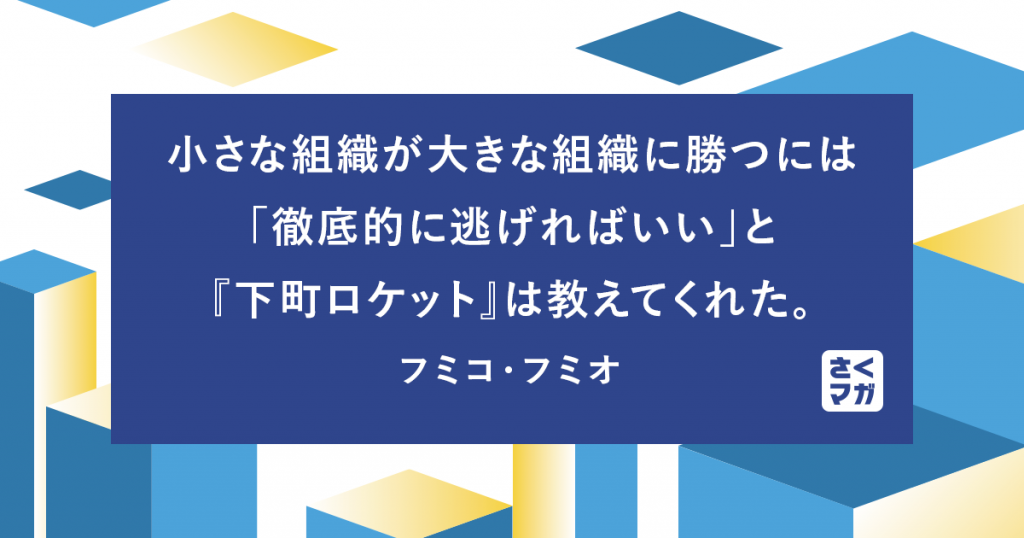
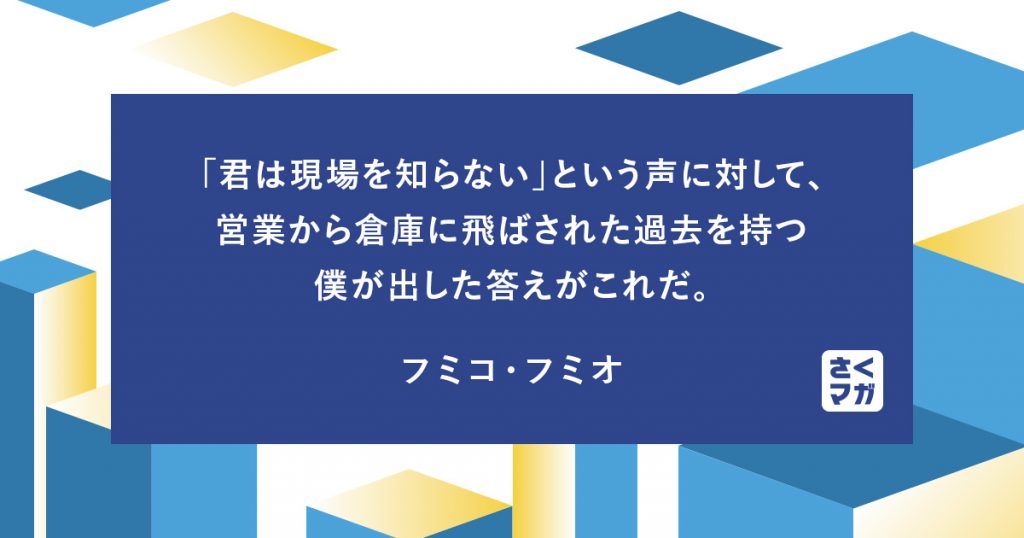
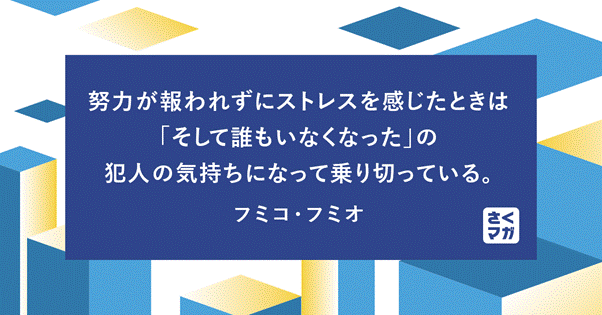
 特集
特集




