デジタル庁が運営するデジタルマーケットプレイス(以下、DMP)をご存じだろうか。Web上でクラウドソフトウェア(SaaS)の情報が公開され、国の行政機関・自治体が検索結果からサービスの比較・検討、調達選定をおこなえるサービスのことだ。行政・自治体がITサービスを調達する際はこれまで一般競争入札が基本だったが、DMPを活用すれば、時間や手間を大幅に削減できるだろう。
今回は、DMP開発の中心メンバーで、デジタル庁戦略・組織グループ 企画官の吉田泰己さんにインタビューを実施。DMPのくわしい機能、開発背景や今後の展望までを聞いた。

吉田 泰己(よしだ ひろき)さん プロフィール
デジタル庁戦略・組織グループ 企画官
2008年経済産業省入省。2015年から17年までシンガポールに留学。2017年から2021年まで経済産業省情報プロジェクト室で事業者向け行政サービスのデジタル化を推進。2021年からデジタル庁企画官としてデジタルマーケットプレイスを担当。2023年から内閣官房デジタル行財政事務局企画官。著書に『行政をハックしよう』(2021年、ぎょうせい)、『行政組織をアップデートしよう』(2024年、ぎょうせい)。
従来の入札方法では選定までの長さや官民双方の手続きの手間が課題に
まず、DMPとはどのような仕組みか教えてください。
クラウドベースのパッケージソフトウェアであるSaaSや、その販売サービスが掲載されたカタログサイトから、各行政機関・自治体が検索を通じて最適なソフトウェア・サービスを選定し、調達が行える新しい手法のことです。DMPを活用することで、従来の入札方式で課題となっていた調達時間の長さや煩雑な手続きを解消することができます。
いまお話のあった調達時間の長さなど、従来の入札方式ではどのような課題があったのか、くわしく教えてください。
これまでは、行政機関が用意した調達仕様書に対して複数社が提案と価格を提示し、そのなかから優れた事業者を選定するというのが一般的な入札方式でした。しかし、この方式だと選定まで長ければ3か月~半年ほどかかっていました。また、行政・自治体は調達仕様書の作成、事業者は提案書の作成やプロポーザル用のプレゼン準備など双方で手続きが負担となっていました。
ほかに、行政機関や自治体ではいちからソフトウェアの構築を委託する調達契約が多かったのですが、近年はクラウドベースで開発されたパッケージのソフトウェアであるSaaSが市場でも多く普及しています。これらを調達しやすくすることで、行政機関・各自治体の費用・時間のコスト面は大きく改善されると考え、英国の事例なども参考にしながらDMPの導入を進めました。
通常の入札方式だと、新規参入しにくいという課題もありそうですね。
はい。これまではどうしても行政機関と長年取引してきたベンダーからの調達が多く、SaaSを提供する中小企業やITベンチャー/スタートアップ企業(販売代理店も含む)は、そもそも行政機関や自治体にどうアクセスしたらよいのかわからない、調達のプロセスがわからないなどの理由で、参入障壁が高かったと思われます。
DMPでは、デジタル庁と基本契約を結ぶことでカタログサイトにソフトウェア・販売サービスを掲載できるため、市場の透明性が高まることはもちろん、行政機関や自治体といままで取引のなかった事業者も簡単に参入できるというメリットもあります。また、これまで特定のベンダーとしか付き合いのなかった自治体もこのサイトを閲覧することで、どのようなソフトウェアが市場にあるのか比較できるようになりました。DMPを活用することで、各行政機関・自治体のニーズに合ったSaaSの導入が進むことを期待しています。
掲載する事業者・サービスに条件などはありますか。
基本契約を結ぶ前に、まず全省庁統一資格とGビズIDプライムのアカウントを取得する必要があります。その後、DMPカタログサイトに掲載されている基本契約を確認の上事業者登録をしてもらいます。その後、提供するソフトウェア情報を登録いただくとデジタル庁で登録内容を確認します。確認といっても複雑なものではなく「行政の業務目的で使用できるものか(ゲーム関連などは除く)」、セキュリティの観点から「委託開発している場合、その委託先の所在地国や開発・運用場所」「ソフトウェアが動くクラウドサービスの種類やリージョン」などを確認させていただきます。8営業日ほどで確認は終わり、問題なければ登録いただいたソフトウェアがカタログサイトに掲載されます。
留意点として、SaaSの中にはハードウェアの調達を伴うものもありますが、ハードウェアの調達は今回のDMPでは対象外です。SaaSの中でもローコード開発ツールなどで受託開発を伴う場合は、ライセンスはDMPで調達可能ですが、開発委託部分について、従来と同じ入札プロセスを取っていただく形になります。
また、SaaSの中には直販だけでなく販売会社を経由して提供されるものもあり、こうした会社がセットアップ支援やユーザーサポートを実施していることも多くあります。そうした付帯サービスも登録いただければ、ソフトウェアとセットで調達が可能です。
重要な点として、ソフトウェア会社による直販がなく、販売会社のみを経由してソフトウェアを提供している場合は、ソフトウェア会社だけでなく販売会社にも登録いただかないと行政側が調達できないので、ぜひ注意してください。
調達仕様チェックシートと調達モードで、仕様書作成の負担を軽減
「調達仕様書の作成が負担になっている」との声も各自治体からよく聞かれます。その点に関してはいかがでしょうか。
そのとおりだと思います。調達仕様書は、必要とする機能・仕様などを綿密に記載する必要がありますが、記載すべき内容の粒度や、項目について整理すべき点が多くあり、記載の手間・煩雑さが行政・自治体職員を悩ませています。
そこで、DMPでは調達仕様チェックシートを用意しました。従来のようにいちから仕様書の構成を検討する必要はなく、項目に沿って内容を記載・選択することで作成できます。自由記載できる箇所もありますので、項目にないものや個別の要望はそこに記載することも可能です。
仕様書作成後、行政利用者はDMPカタログサイトのアカウントを取得し、ログインすることで調達に利用する機能が活用可能です。その際に使用する「調達モード」という機能も用意しました。
調達モードとはどのような機能でしょうか。
調達における公平性を保つために、フリーワード検索のような特定のキーワード・会社名・販売方式での検索項目が制限されたモードのことです。行政利用者は、調達モードをオンにすることであらかじめ記載した調達仕様チェックシートの仕様に沿って検索することになります。
調達の際、行政利用者は、調達モードで検索項目を設定して検索したあと、絞り込まれたソフトウェアの詳細画面を確認して仕様にあったソフトウェアかどうかを確認します。不明点がある場合にはソフトウェア会社に問い合わせ、詳細仕様を確認します。ソフトウェアが選定されたら、システム上で選定理由を記載し、その後、販売会社による販売サービス検索などを進めていきます。最後はDMPカタログサイトでの選定結果をPDFで出力します。
調達仕様チェックシートと、出力された選定結果のPDFを示すことで、公平に選定をおこなった証左となり、これを根拠として調達契約まで進んでいけます。
契約方法について教えてください。
選定をおこなった結果、1社が選定された場合であればそのまま特命随意契約を通じて調達します。複数社であれば、予算規模に応じて、少額髄契、指名競争入札に進みます。指名競争入札ではソフトウェアの仕様、付帯サービスなどはあらかじめ確認していますので、もっとも低い価格で入札をした事業者と契約します。
調達に関しては、企画立案、仕様策定、予算要求、調達など各フェーズがあると思いますが、DMPカタログサイトはどういったフェーズから使えるのでしょうか。
結論から言うと、すべてのフェーズで活用できます。たとえば、企画の段階では、カタログサイトに掲載されたさまざまなソフトウェアを自由に検索してもらうことで、導入したいソフトウェアのおぼろげだったイメージの解像度を上げられます。仕様策定や予算要求のフェーズであれば、各ソフトウェアに関する仕様の記載を参考にしたり、実際に提供するソフトウェア会社に詳細仕様を問い合わせたり、見積もりを依頼したりすることができます。
登録なしで利用できる一般向け検索機能もありますので、もしDMPの利用を迷っている行政関係者がいれば、とりあえずカタログサイトを見て回って「使えそうだ」と感じたら本登録をするという使い方で問題ございません。事業者側も、カタログサイトを見てもらい、自社と同じカテゴリーのソフトウェアの登録状況や、掲載の少ない領域に絞った製品を掲載するなどの使い方もできるでしょう。
DMPカタログサイトのα版を2023年にリリース。ユーザーの声を聞き、より使いやすいプラットフォームを目指す
今回の正式版リリースの前に、2023年にDMPα版カタログサイトをリリースされていますよね。どのような意図があったのでしょうか。
正式版を出す前にα版を提供することで、事業者・行政機関、双方のユーザーから直接フィードバックを得たいと考えました。また、双方のユーザーの方々にDMPがどのようなものになるかのイメージを持っていただきたいという意図もありました。DMPα版カタログサイトのリリース後には、事業者向け、行政利用者向けにワークショップを開催するとともに、問い合わせフォームを通じてさまざまなフィードバックを得ました。
たとえば、α版の段階では、ソフトウェア製品の価格情報に関してログインしなくても誰でも閲覧できるようにすることを想定していました。しかし、ワークショップ開催時に、事業者から自社の価格情報を競合に見られたくないといった声も多く聞かれましたので、そうした声を踏まえて、正式版ではアカウント登録した行政事業者だけが閲覧できるようにしました。
また、行政利用者向けの検索結果の比較表の生成や、その保存機能などもワークショップでいただいた意見を踏まえて追加開発を実施しました。今後も利用者の声を聞きながらカタログサイトの機能は改善していきたいと思います。
掲載企業・ソフトウェア数は急伸長。今後はAPI連携によるアクセス解析も可能に
現在のDMPカタログサイトの登録状況を教えてください。
事業者の皆様によるソフトウェア登録は2024年10月末から正式版サイトで受付を開始しましたが、2025年2月9日現在、178社の事業会社が登録されており、136のソフトウェアが掲載されています。審査中のものを含めると年度内には掲載ソフトウェア数は200以上に増えていく見込みです。
2025年1月30日からはこれまで事業者の皆様に登録いただいたソフトウェア、販売サービスの検索機能の提供を開始しました。行政関係者の登録や調達に利用する機能の提供に関しては、3月末までを目途に進めていきます。
今後、機能拡張などは検討していますか。
実際にDMPを通じて行政機関、自治体から調達があった場合は、調達契約を行った企業から調達実績を報告してもらうことを想定しています。具体的には、デジタル庁が用意するフォームを通じて実績を登録いただきます。調達実績については他の行政機関・自治体や事業者の参考になるよう公開する予定です。どこまでの粒度の情報で掲載するかは検討中ですが、どういった政策目的で、その機能があるSaaSが調達されたのか、また金額規模や、ライセンス数の規模などについて掲載することを考えています。こうした情報はDMPの有効性を訴求することにもつながると思います。
ほかには、DMPカタログサイトの情報についてオープンAPIを通じて提供予定です。どういった検索項目で何回検索されたかといったデータや、登録されているソフトウェアの一般公開範囲のデータなどについてAPIを通じて提供することを考えています。事業者の皆様にはこうしたデータを活用することで、行政ではどういったソフトウェアの関心が高いのか、どういった領域のSaaSはまだ提供されていないのかということもわかるので、そうした領域のソフトウェアを持つ事業者の参入が促進されることを期待しています。
また、政府から「新しい地方経済・生活環境創生交付金」が発表されました。この交付金の対象事業の1つであるデジタル実装型のタイプⅠにおいて、DMPを活用して調達することを計画に含めた場合、加点措置を実施します。100点満点中の1点が加算されますので、今後交付金の活用を検討している自治体関係者の方がいれば、ぜひDMPを活用していただけますと幸いです。
(撮影:ナカムラヨシノーブ)



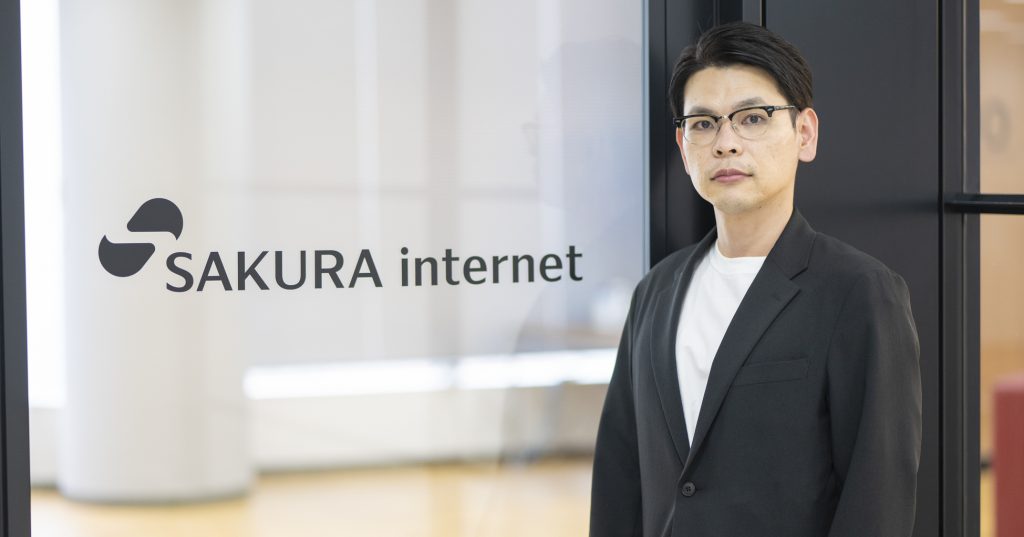



 特集
特集




