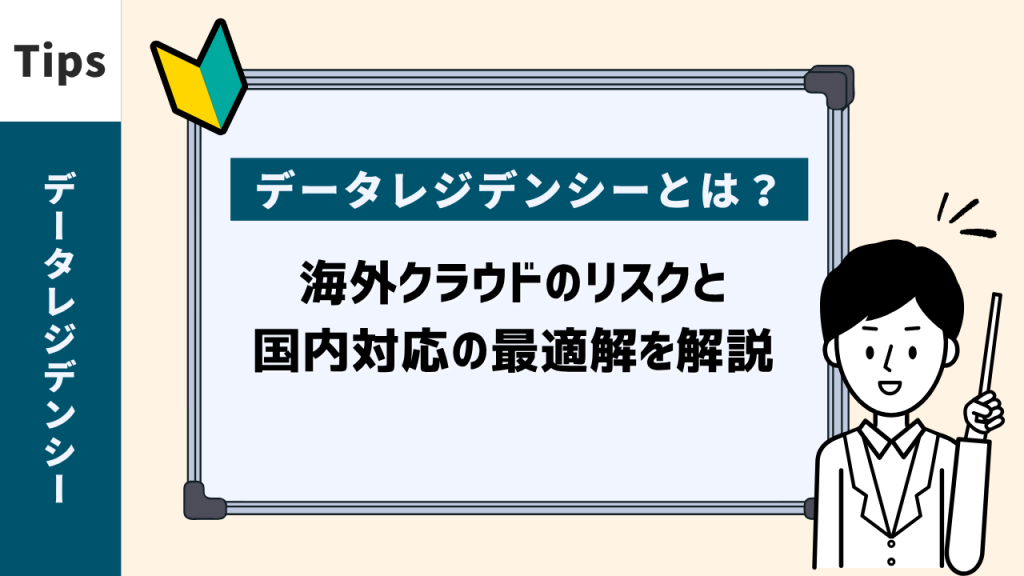
AI開発やデータサイエンスの現場でクラウドサービスの利用が急速に拡大するなか、データがどこに保存されるかという「データレジデンシー」への関心が高まっています。
GDPR(EU一般データ保護規則)や個人情報保護法の改正、助成金や共同研究での条件変化など、データの保管場所を取り巻く環境は大きく変化しています。とくに、スタートアップやベンチャー企業がAIサービスを提供する際、顧客から預かるデータの取り扱いは重要な検討事項です。
本記事では、データレジデンシーの基本概念から、海外クラウド利用時の課題、適切なサービス選定のポイント、実践的な対応策まで、技術者から経営層まで幅広い読者に向けて解説します。

さくらインターネットが提供している高火力シリーズ「PHY」「VRT」「DOK」を横断的に紹介する資料です。お客様の課題に合わせて最適なサービスを選んでいただけるよう、それぞれのサービスの特色の紹介や、比較表を掲載しています。
1. データレジデンシーとは?
まず、データレジデンシーの定義とその重要性、そしてよく混同される関連概念との違いを明確にしましょう。
1-1. データレジデンシーの定義と重要性
データレジデンシー(Data Residency)とは、デジタルデータが物理的に保存される地理的な場所を指します。つまり、利用するクラウドサービスのデータが、どの国のどのデータセンターに保管されているかということです。
この概念が重要とされるのは、データが存在する場所によって適用される法律や規制が異なるためです。たとえば、日本企業が顧客の個人情報を処理する場合、そのデータがアメリカのサーバーに保存されていれば、日本の個人情報保護法に加え、アメリカの法律も考慮する必要があります。このように、データの保存場所により企業が遵守すべき法的義務が大きく変わってくるのです。近年では、法規制の強化や企業のコンプライアンス意識の高まりにより、データレジデンシーへの関心が急速に高まっています。
1-2.データ主権/データローカライゼーションとの違い
混同されやすい概念に「データ主権(Data Sovereignty)」と「データローカライゼーション(Data Localization)」があります。
- データ主権:国家がその領域内のデータに対して法的権限を持つという考え方です。データが生成された国や、データ主体(個人)が属する国の法律が、そのデータの取り扱いを規制します。
- データローカライゼーション:特定の法域内でデータを保存・処理することを求める法的要件です。これは、データレジデンシー要件に準拠するための具体的な措置といえます。
- データレジデンシー:単純にデータの物理的な保存場所を指します。
整理すると、データ主権は「法的概念」、データローカライゼーションは「法的要件」、データレジデンシーは「物理的場所」という違いがあります。
1-3. 研究開発分野でデータレジデンシーが重視される理由
とくに研究開発やスタートアップ企業でデータレジデンシーが注目される背景には、以下のような要因があります。
AI開発におけるセンシティブデータの増加
機械学習や生成AIモデルの学習、および推論時に参照するRAG には大量のデータが必要ですが、そのなかには個人情報や企業の機密情報といったセンシティブデータが含まれていることが多くなっています。顧客向けAIサービスを提供する企業では、機密データが漏えいすれば企業の信用が失われ、事業存続に影響がおよぶおそれがあります。
共同研究や産学連携での契約条件
大手企業との共同研究では、機密情報保護の観点からデータの保存場所に厳格な制限を設ける契約が一般的です。違反が発覚すれば、研究の中断や損害賠償のリスクもあります。
助成金や公的資金の条件変化
政府系の研究資金や補助金では、データの国内保管を条件とするケースが増えています。技術流出の防止や安全保障上の理由から、重要データの海外流出を防ぐ目的があります。
2.海外クラウド利用で起こりうる問題
海外クラウドサービスは機能面やコスト面で魅力的ですが、データレジデンシーの観点からは複数の課題が存在します。
2-1. 法的・契約的リスク
法的コンプライアンス違反
GDPR(EU一般データ保護規則)では、EU域外へのデータ移転に厳格な制限が設けられています。適切な保護措置なしにデータを移転した場合、2,000万ユーロを上限として制裁金が科される可能性があります。
参考:
個人情報保護委員会「EU一般データ保護規則(GDPR)」
契約上のトラブル
共同研究契約や助成金の条件として「国内でのデータ保管」が求められているにもかかわらず、海外クラウドサービスを使用していた場合は契約違反とみなされ、資金の返還や契約の解除を求められる可能性があります。
レピュテーションリスク
AIサービス提供企業が顧客データを海外で管理していることが判明した場合、データ保護に対する信頼が損なわれ、顧客離れや新規顧客の獲得が困難になるおそれがあります。
2-2. 運用・技術的リスク
サービスの利用制限リスク
海外クラウドサービスでは、地政学的リスクや外国企業への規制強化の影響により、サービスの利用が制限される可能性があります。
レスポンス時間の問題
海外にデータがあることで物理的な距離による通信遅延が発生し、AIモデルの推論速度やデータ処理速度に影響をおよぼす可能性があります。
サポート体制の違い
海外クラウドサービスでは、時差の影響で緊急時の対応が遅れることがあります。また、言語の壁によって技術的な問題の詳細な共有や対応が困難になる場合もあります。
3. データレジデンシー対策:国内でのクラウドサービス選択ポイント
データレジデンシーの要件を満たしたうえでコストと機能の両立を図るために、国内クラウドサービス選定時のポイントを紹介します。
3-1. 日本国内リージョン選択のメリット
クラウドサービスでの「日本国内リージョン」とは、AWS東京リージョンやAzure東日本リージョンなど、海外クラウド事業者が日本国内に設置したデータセンターで提供されるサービス領域を指します。
データの物理的な保管場所を日本国内にすることで、以下のようなメリットが得られます。
日本の法制度に基づいたデータ管理が可能
日本の法律が適用されるため、データ保護や個人情報の取り扱いについて、日本の個人情報保護法に基づいた対応が可能です。
ネットワーク性能の向上による開発・運用効率の改善
物理的距離が近いため、ネットワークのレスポンスが向上し、AIモデルの推論や大量データ処理の効率化が図れます。
災害時の迅速な復旧と安定運用が可能
日本国内にデータセンターが分散配置されている場合、災害時の復旧作業において、物理的距離の近さや言語・時差の問題がないことから、海外リージョンに比べて迅速かつ確実な対応が期待できます。
3-2. 国産サービスのメリットと選定時の注意点
国産のクラウドサービス(さくらのクラウド、ニフクラ、GMOクラウドなど)には、海外企業のクラウドサービスとは異なる特徴があります。
たとえば、国内企業ならではの手厚いサポート体制が整っています。技術的な問題が発生した際に迅速かつ詳細な対応を受けられ、緊急時の対応で大きなアドバンテージとなります。また、個人情報保護法や業界固有の規制について、サービス設計の段階から日本の法制度を理解したうえで考慮されているため、ユーザー側の対応負荷が軽減されます。
一方で、機能や課金体系で基準となりがちな海外の大手クラウドサービスとは異なる特徴があり、グローバル展開を考えている企業の場合は海外でのサービス提供に制約が生じる場合がある点に注意が必要です。将来的な事業計画も含めて、総合的に判断することが重要です。
3-3. データレジデンシー重視のサービス比較方法
データレジデンシーを重視したクラウドサービス比較の重要なポイントを紹介します。
データ保管場所の確認項目
- プライマリデータの保管場所(明確に日本国内と明記されているか)
- バックアップデータの保管場所
- データ処理時の一時的な移転の有無
契約・コンプライアンス関連
- データ移転に関する契約条項の内容
- 法執行機関からの情報開示要求への対応方針
運用・サポート体制
- 24時間365日の日本語サポート対応
- 障害時の目標復旧時間(RTO)
これらの項目を事前に整理し、複数のサービスを同じ基準で比較することで、自社の要件に最適なサービスを選定できます。とくにデータレジデンシーが重要な企業では、価格や機能だけでなく、データ保管場所の透明性とコンプライアンス対応力を重視した選定が求められます。
4. 安心して使えるインフラ環境とは?開発現場での工夫例
データレジデンシーの要件を満たし、効率的な開発環境を構築するための実践的なアプローチを紹介します。
4-1. チームメンバーと安全にデータを扱う
とりわけスタートアップ企業やベンチャー企業では、社内外のメンバーや外部パートナーと安全にデータを共有することが重要な課題です。
階層的なアクセス権限設計
データの機密度に応じて、閲覧専用、編集可能、管理者権限といった段階的なアクセス権限を設定し、プロジェクトメンバーの役割に応じて適切に割り当てることが重要です。
監査ログの活用
誰がいつどのデータにアクセスしたかを記録・確認することで、不正アクセスや情報漏えいのリスクを低減できます。
データの仮名化・匿名化
開発やテスト環境では、実際の個人情報や機密データを使わずにすむよう、仮名化・匿名化技術を活用すると効果的です。
4-2. クラウドとローカルを使い分けるハイブリッド運用
データの性質や用途に応じて、クラウドとオンプレミスを組み合わせた「ハイブリッド運用」をおこなうことで、データレジデンシーの遵守とコスト効率の両立が可能です。
機密度による使い分け
個人情報や機密情報など高いセキュリティを求められるデータはオンプレミスや国産クラウドサービス上で管理し、一般的な開発データはコストパフォーマンスの高い海外クラウドサービスを活用するなどの使い分けが有効です。
処理段階による使い分け
AIモデルの訓練には容量の大きいクラウドストレージを用い、訓練済みモデルの推論処理は社内システムで実行することで、データ流出リスクを抑制しながら開発効率を向上できます。
4-3. 国内サービスの充実したサポート体制
国産クラウドサービスの大きな魅力は、サポート体制の手厚さと、日本国内での迅速な対応です。
緊急時の対応力
言語や時差の壁がないため、トラブル発生時にも日本語で詳細な説明が可能で、早期解決につながります。
コンプライアンス相談の容易さ
法規制の解釈や業界固有の要件について、日本の法制度を理解したサポート担当者に相談できるため、迅速かつ的確な対応策を導き出せます。
さくらインターネットのクラウドサービス「高火力シリーズ」では、これらの利点を活かし、高性能なGPUインスタンスをはじめとするAI開発向けのサービスを日本国内で提供しています。データレジデンシーを担保して、安心かつ効率的なインフラ環境を実現します。
まとめ
データレジデンシーは、現代のクラウド活用には欠かせない重要な概念です。とくに、AI開発やデータサイエンスに取り組むスタートアップ企業やベンチャー企業にとって、顧客から預かる機密データの適切な管理は、法的コンプライアンスと企業の信頼性の両面から、事業の根幹にかかわる要素といえます。
海外クラウドサービスの利用には法的・契約的・運用面でのリスクが伴いますが、日本国内のクラウドサービスや国産サービスを選択することで、これらのリスクを大きく軽減できます。重要なのは、自社の事業特性や取り扱うデータの性質を正確に把握したうえで、最適なサービス選択と運用設計をおこなうことです。
さくらインターネットの高火力シリーズでは、データレジデンシー要件を満たす国内インフラ環境のもと、高性能なGPUリソースを安全に利用できます。日本語での手厚いサポートや、ソブリンクラウドの思想に基づいた設計により、開発効率とデータ保護を両立する最適な環境を提供します。
データの置き場所に対する正しい知識を持ち、安全かつ効果的なクラウド活用を実現しましょう。

さくらインターネットが提供している高火力シリーズ「PHY」「VRT」「DOK」を横断的に紹介する資料です。お客様の課題に合わせて最適なサービスを選んでいただけるよう、それぞれのサービスの特色の紹介や、比較表を掲載しています。



 New
New

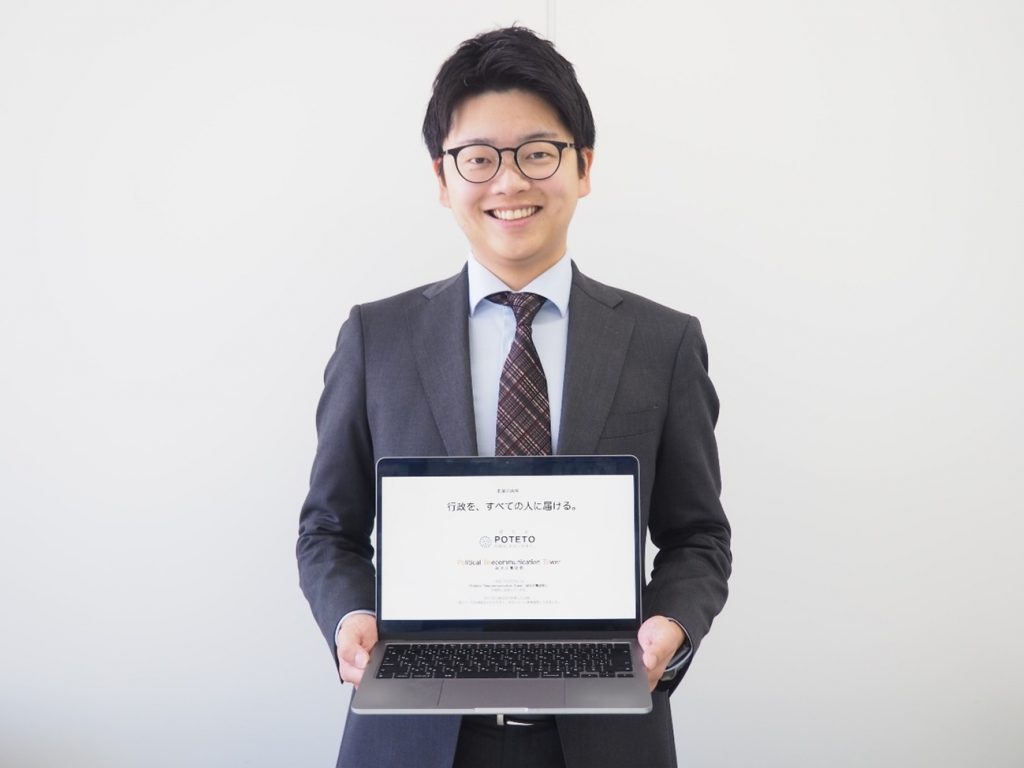
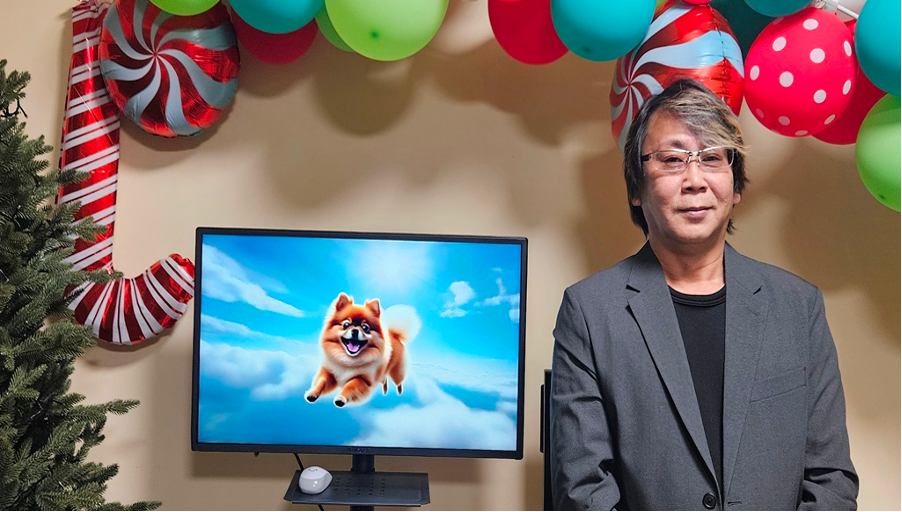
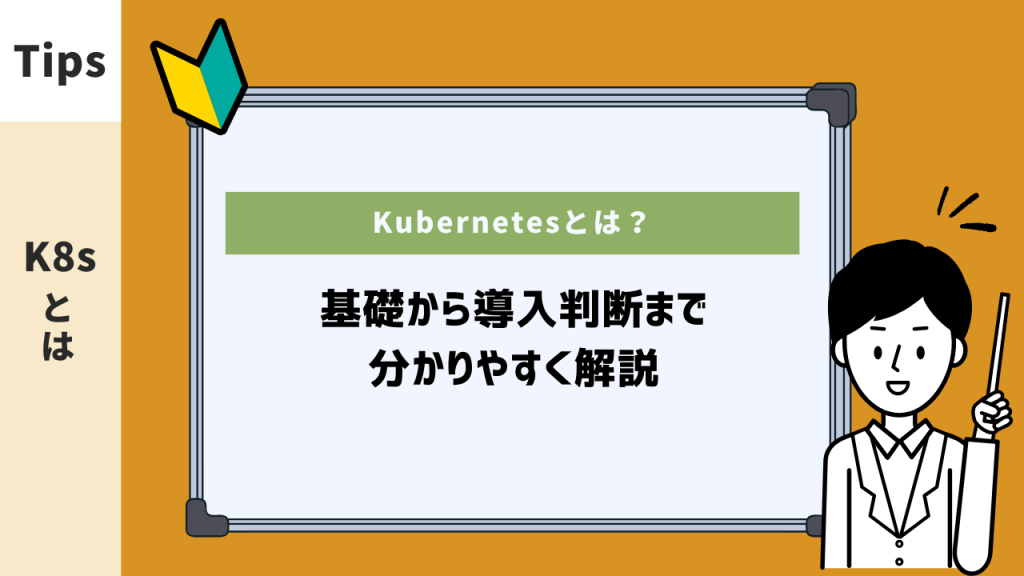
 特集
特集




