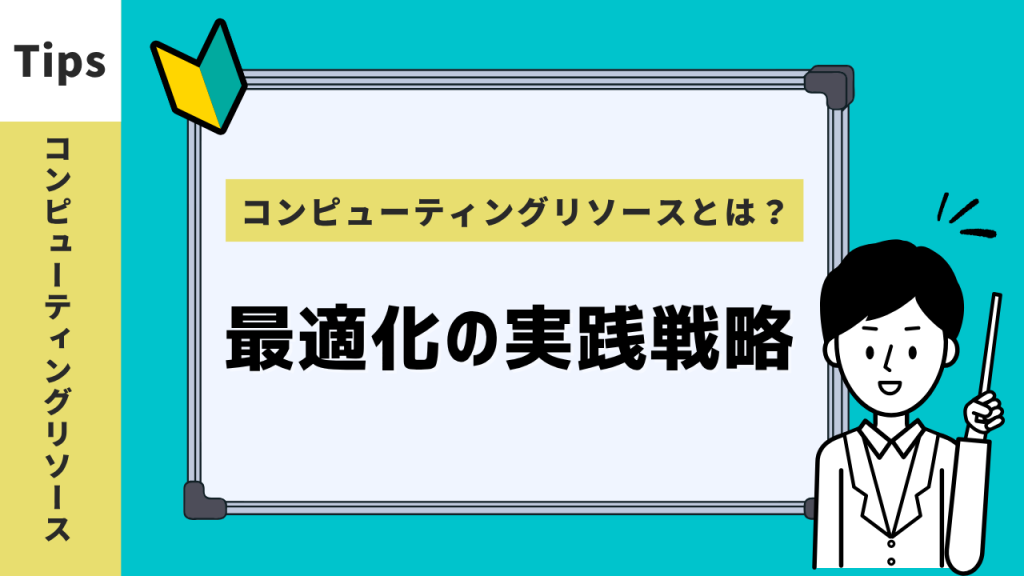
システムの複雑化とクラウド環境の普及により、コンピューティングリソースの効率的な管理はインフラエンジニアやクラウドアーキテクトにとって重要な課題となっています。リソースの過剰配分によるコスト増加と、不足によるパフォーマンス低下の間で適切なバランスを見つけることは容易ではありません。本記事では、コンピューティングリソースの基本概念、クラウド環境での管理方法、実践的な最適化戦略、そして効果的な活用事例について解説します。

さくらインターネットが提供している高火力シリーズ「PHY」「VRT」「DOK」を横断的に紹介する資料です。お客様の課題に合わせて最適なサービスを選んでいただけるよう、それぞれのサービスの特色の紹介や、比較表を掲載しています。
コンピューティングリソースとは何か
まずは基本的な概念を整理しながら、クラウド時代におけるコンピューティングリソースの重要性について見ていきましょう。
コンピューティングリソースの要素と役割
コンピューティングリソースの中心となるのは、以下の4つの要素です。
- CPU(中央処理装置): システムの計算処理を実行する頭脳の役割。データの演算や論理処理を担当し、処理性能はコア数や動作周波数で決まります。
- メモリ: 一時的なデータ保存と高速アクセスを実現する作業領域。CPUが処理するデータを一時的に保持し、アクセス速度がシステム全体の応答性に影響します。
- ストレージ: データを永続的に保存する保管庫の役割。HDDやSSDなど種類によって速度、容量、耐久性が異なり、システムの用途に応じた選択が必要です。
- ネットワーク: 各コンポーネント間やユーザーとの通信を担当。帯域幅とレイテンシがデータ転送速度とアプリケーション応答性を決定づけます。
これらの要素のバランスが取れたリソース配分が、システムのパフォーマンスとコスト効率を左右するため、システムが処理する作業(ワークロード)の特性に合わせた適切な設計が重要です。
クラウドでのリソース管理の新しい考え方
クラウド環境では、リソースが抽象化され、仮想的に管理されるようになりました。オンプレミス環境では将来の需要を見越した「余裕を持った」設計が一般的でしたが、クラウドでは「必要なときに必要なだけ」という考え方が基本です。
クラウドのリソース管理では、設備投資から使用量に応じた課金体系へと変わり、細かなコスト管理が必要になっています。また、地理的な分散やレイテンシなど、新たな考慮点も加わっています。
クラウド環境の主要コンピューティングリソース
クラウド環境では、さまざまなタイプのコンピューティングリソースが提供されています。
仮想マシン(VM):最も基本的なコンピューティングリソースで、物理サーバーを仮想化したものです。クラウドのVMは物理サーバー上に構築され、インスタンスタイプによってCPU、メモリ、ストレージなどの組み合わせが定義されており、用途に応じて選択できます。
コンテナーサービス:アプリケーションとその実行環境を軽量なパッケージとして提供します。VMより起動が速く、リソース効率も高いため、マイクロサービスアーキテクチャとの相性がよいです。
サーバーレスコンピューティング:関数単位でコードを実行するサービスで、利用時のみリソースが割り当てられます。インフラ管理の負担がなく、イベント駆動型の処理に適しています。
システムに合ったリソース設計の方法
ここでは、ワークロードの特性に応じた最適なリソース設計のアプローチについて解説します。
ワークロードに合わせたリソース配分
ワークロードに最適なリソース配分をするには、まず処理の特性を分析し、適切なリソースタイプを選択することがポイントです。
トランザクション処理システムでは、CPUコア数とI/O性能がパフォーマンスのカギを握ります。データベースへの頻繁なアクセスが発生するため、低レイテンシのストレージとネットワーク接続がシステムの応答性を左右します。
データ分析処理においては、メモリ容量と処理能力のバランスが効率的な処理の基盤となります。とくにデータウェアハウスや機械学習処理では、大量のデータを高速に処理できるメモリ最適化型インスタンスの活用が効果的です。
マイクロサービスアーキテクチャの場合、各サービスの負荷特性に応じた柔軟なリソース配分が求められます。サービスごとに最適なリソース制限を設定することで、リソースの無駄を減らしながらシステム全体のパフォーマンスを向上させることが可能になります。
コンテナーとサーバーレスのリソース設計
コンテナー環境でのリソース設計では、各コンテナーの役割に応じて適切な制限値を設定します。コンテナーのオーケストレーションツールであるKubernetesでは、「リソース要求」(最低保証量)と「リソース制限」(最大使用量)を指定し、コンテナー間の競合を防ぎながら効率的なリソース活用を図ります。
サーバーレス環境では、関数ごとに最適なメモリ割り当てを決定することが設計の鍵です。処理内容の複雑さと実行時間のバランスを測定し、コスト効率の良いメモリ設定を探りましょう。コールドスタート問題も考慮に入れた設計が重要です。
ハイブリッド環境でのリソース連携
複数環境間のリソース管理統合には、一貫した監視と管理のフレームワークが効果的です。クラウド管理プラットフォームやInfrastructure as Codeツールを活用すれば、環境間の違いを抽象化できます。
データの所在とネットワーク接続も検討すべき要素です。頻繁にアクセスされるデータは、処理を実行する環境に近い場所に配置するなど、戦略的なデータ配置が有効です。
リソースの最適化とコスト削減の実践方法
パフォーマンスとコストのバランスを取りながら、ビジネス要件を満たすための最適な方法を見ていきましょう。
自動スケーリングの選択
自動スケーリングとは、負荷の変動に応じてリソースを自動的に増減させる仕組みです。適切なスケーリング方法を選択することで、パフォーマンスを維持しながらコストを最適化できます。おもに垂直と水平の2種類のスケーリング方法があります。
垂直スケーリング(スケールアップ・ダウン)はインスタンスのサイズを変更する方法で、データベースなど状態を保持するシステムに適しています。水平スケーリング(スケールアウト・イン)はインスタンス数を増減する方法で、過去の状態に依存せず、それぞれのリクエストを独立して処理するステートレスなWebアプリケーションに効果的です。
自動スケーリングの設定では、CPU使用率やメモリ消費量だけでなく、リクエスト数やレスポンスタイムなど、アプリケーションの特性に合ったメトリクスを選択するとよいでしょう。
クラウドコストの最適化
クラウドコスト最適化の基本は、ワークロードパターンに合った料金モデルの選択と、不要リソースの削減です。長期的に安定した使用が見込まれるワークロードと変動が激しいワークロードでは、異なるアプローチが効果的です。
リザーブドインスタンスは、長期利用をコミットすることで通常より低コストでリソースを利用できる契約形態です。常時稼働システムには、このようなコミットメント型の料金体系が有利です。
スポットインスタンスは、余剰キャパシティを変動料金で利用できるサービスです。バッチ処理など、中断が許容されるワークロードに向いていますが、可用性は保証されません。
リソースのライフサイクル管理も大切です。不要なリソースの削除や、開発環境の自動停止などで無駄を省けます。リソースにタグ付けしてコスト帰属を明確にすることも有効な手段です。
高性能コンピューティングの効率的な使い方
AI開発や機械学習などの高負荷ワークロード(生成AI、画像処理、HPCなど)では、GPUなどの特殊なリソースを活用できます。トレーニングには高性能GPUが不可欠ですが、インファレンス(推論)では比較的軽量なGPUで十分な場合が多いです。
バッチサイズやモデルパラメータの最適化もパフォーマンスに直結します。モデルの量子化や圧縮技術により、リソース要件を削減できるケースもあります。ジョブスケジューリングを工夫し、GPUの遊休時間を減らすことで費用対効果を高められます。
アーキテクチャ別のリソース活用例
代表的なアーキテクチャパターンごとのリソース活用アプローチを紹介します。
マイクロサービスのリソース管理
各マイクロサービスの処理特性に応じた異なるリソースプロファイルの設定が望ましいです。負荷テストを通じて、サービスごとに最適なリソース要件を見極めましょう。
サービスメッシュ環境では、プロキシコンテナーのリソースも考慮が必要です。またマイクロサービス間の依存関係も踏まえ、リクエストのエラー数に応じて挙動を変えるようなサーキットブレーカーパターンを採用するとリソース問題の連鎖を防止できます。
データ処理システムのリソース配分
バッチ処理は短時間で高いコンピューティング能力を要しますが、常時稼働は不要です。スポットインスタンスや自動スケーリングでコスト効率を上げられます。
ストリーム処理には安定したリソース割り当てが望ましいです。データ量の変動に応じたスケーリングポリシーの設定がポイントです。データウェアハウスではストレージとコンピューティングの分離がコスト削減に貢献します。
高可用性システムのリソース設計
マルチリージョン構成では、リージョンごとに適切な容量配分をおこない、障害時のサービス継続性を確保します。アクティブ-アクティブ構成では複数リージョンでトラフィックを分散し、リソース効率を向上できます。
災害復旧計画では、RTO(目標復旧時間)とRPO(目標復旧時点)に基づくリソース配置を検討しましょう。CDNやエッジコンピューティングの活用はレスポンス時間短縮とバックエンド負荷軽減の一石二鳥の効果があります。
まとめ
本記事では、基本概念から実践的な最適化戦略、そしてアーキテクチャ別の活用方法まで解説しました。クラウド環境でのリソース管理は継続的な改善プロセスであり、ワークロード特性の理解と適切なツール選択が成功への道筋となります。とくに高性能コンピューティングが求められるAI開発や機械学習では、専用リソース構成の恩恵が大きいでしょう。
さくらインターネットの高火力 DOKは、GPUインスタンスなどの高性能リソースを効率的に提供し、高負荷ワークロードに最適なソリューションです。リソースの柔軟な拡張性と高コストパフォーマンスを両立させたクラウドアーキテクチャの構築に、ぜひさくらの高火力 DOKをご検討ください。
さくらインターネットの高火力シリーズはこちら
さくらのGPUクラウドサービス|最新GPUで開発・AI学習・研究開発を加速!

さくらインターネットが提供している高火力シリーズ「PHY」「VRT」「DOK」を横断的に紹介する資料です。お客様の課題に合わせて最適なサービスを選んでいただけるよう、それぞれのサービスの特色の紹介や、比較表を掲載しています。



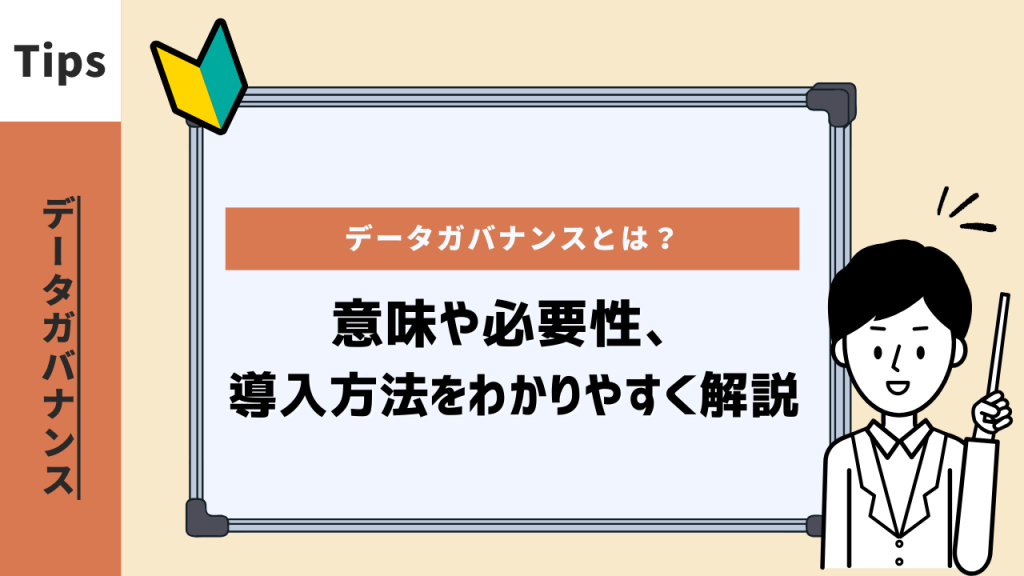 New
New
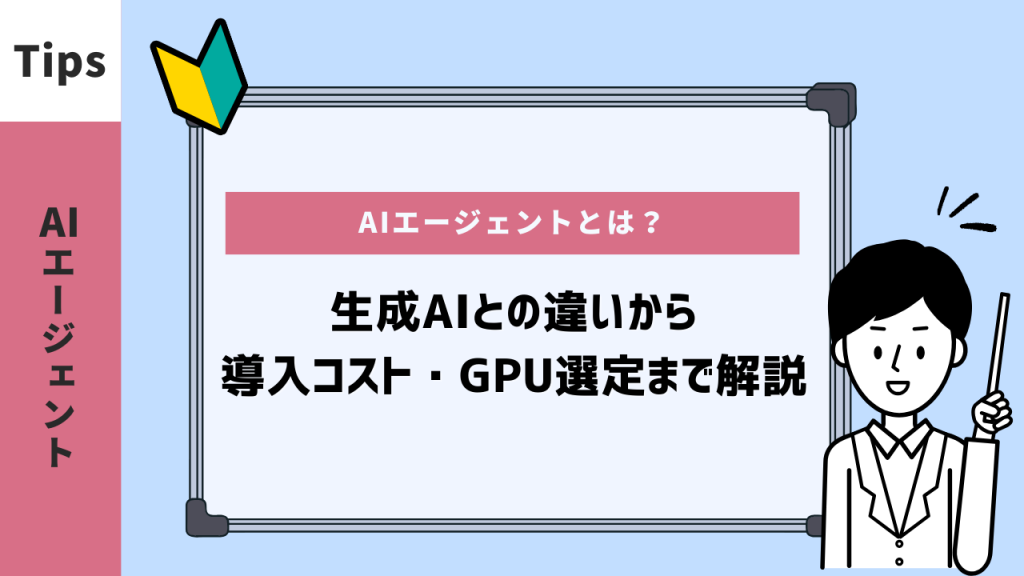 New
New



 特集
特集




