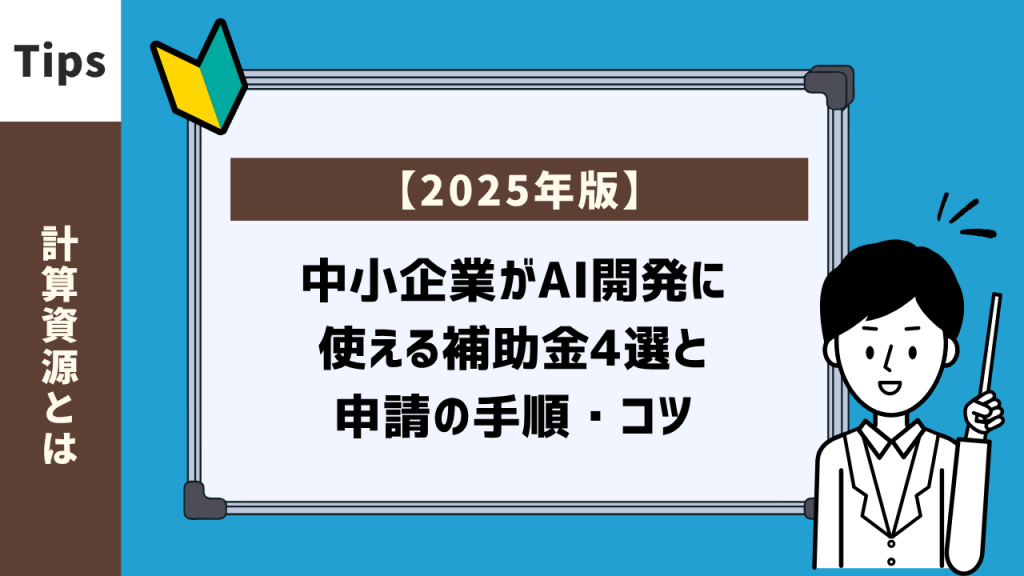
AI技術の活用が企業の競争力を左右する時代となった現在、中小企業にとって開発コストは大きな課題です。AIシステムの構築には数百万円から数千万円の投資が必要となるケースが多く、資金面での不安から導入に踏みきれない企業も少なくありません。
しかし、国や自治体が提供する補助金制度を活用すれば、開発費用の負担を大幅に軽減できます。昨今では「ものづくり補助金」や「中小企業新事業進出補助金」など、AI開発に適した制度が充実しており、適切に活用することで資金調達の課題を解消できます。
本記事では、AI開発に活用できる代表的な4つの補助金制度の概要と、申請の手順やポイントを解説します。

さくらインターネットが提供している高火力シリーズ「PHY」「VRT」「DOK」を横断的に紹介する資料です。お客様の課題に合わせて最適なサービスを選んでいただけるよう、それぞれのサービスの特色の紹介や、比較表を掲載しています。
1. AI開発で補助金を活用するための基本知識
AI開発で補助金の活用を考える場合、まずは制度の基本的な特徴や仕組みを理解しましょう。
1-1. 「補助金」と「助成金」の違いとAI開発での使い分け
補助金と助成金はいずれも国や自治体から支給される返済不要の資金ですが、制度の目的や申請条件に違いがあります。
補助金は主に経済産業省や地方自治体が所管し、新規事業や設備投資、技術開発といった企業の成長を後押しすることを目的としています。審査を経て採択される仕組みで、申請すれば必ず受給できるわけではありません。競争率が高い一方で、採択されれば多額の資金を得られる可能性があります。
一方、助成金は厚生労働省が所管し、雇用促進や働き方改革など、労働環境の改善を目的としています。一定の条件を満たせば受給しやすい点が特徴です。
AI開発のようなシステム構築や技術開発には補助金制度が適しているケースが多く、開発費や外注費などが補助対象となることが一般的です。一方で、AI人材の研修や育成には助成金の活用が有効です。
1-2. AI開発で補助金の対象となる経費の例と注意点
AI開発プロジェクトで補助対象となる主な経費は以下のとおりです。
- システム開発費・ソフトウェア開発費
- クラウドサービス利用料(AWS、Azureなど)
- 外注費(開発会社への委託費用)
- 専門家経費(AI技術者のコンサルティング費用)
- 機械装置費(AI開発に必要なハードウェア)
一方、以下のような経費は多くの補助金制度で対象外とされています。
- 汎用的なパソコンの購入費
- オフィス賃料
- 既存設備の維持費
また、補助金の交付決定前に発生した経費は原則として補助対象外となるため、申請のタイミングには注意が必要です。
補助金は基本的に後払い方式のため、企業が一時的に費用を立て替える必要があります。実施期間中の資金繰りについても事前に計画しておくことが求められます。
AI開発にかかる費用の詳細や予算設計については、以下の記事で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。
AI開発の費用はいくらかかる?相場・内訳・予算設計ガイド【IT責任者向け】
2. AI開発に使える主要な補助金4選
2025年現在、AI開発に活用できる補助金制度のなかでも、特に中小企業に適している4つの制度を紹介します。それぞれ対象となる事業者や補助金額、適用要件が異なるため、自社のプロジェクト規模や目的に応じて適切な制度を選びましょう。
2-1. ものづくり補助金
「ものづくり補助金」は、中小企業による革新的な製品・サービスの開発や、生産性向上を支援する制度で、AI開発に最も適した補助金のひとつです。
正式名称は「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」で、全国中小企業団体中央会が運営しています。補助対象事業枠のうち、「製品・サービス高付加価値化枠」では、従業員数に応じて750万円から2,500万円の補助上限額が設定されています。補助率は中小企業で1/2、小規模事業者で2/3です。
対象経費には、機械装置・システム構築費、技術導入費、専門家経費、クラウドサービス利用費などが含まれ、AI開発にかかる費用の大部分をカバーできます。採択事例としては、製造業の品質管理システムの構築や、サービス業における顧客対応の自動化などが挙げられます。
申請時には3~5年の事業計画書の策定が求められ、付加価値額の年平均成長率3%以上を目指す必要があります。年間を通じて複数回の公募があるため、準備が整い次第申請できる点が利点です。
2-2. 中小企業新事業進出補助金
「中小企業新事業進出補助金」は2025年度から開始された新制度で、事業再構築補助金の後継として位置づけられています。既存事業とは異なる新市場や高付加価値事業への進出を支援することを目的としています。
補助上限額は従業員数に応じて異なり、20人以下で2,500万円、21〜50人で4,000万円、51〜100人で5,500万円、101人以上で7,000万円と設定されています。大幅賃上げ特例を適用する場合は、それぞれ3,000万円、5,000万円、7,000万円、9,000万円まで引き上げられます。
AI技術を活用した新規事業の立ち上げや、既存サービスのAI化による高付加価値化などが対象となります。補助率は原則1/2で、補助下限額は750万円です。
申請時には新事業進出要件を満たす事業計画の策定が求められ、付加価値額の年平均成長率4%以上を目指す必要があります。従来の事業再構築補助金に比べて要件が明確化され、申請しやすくなった点が特徴です。
2-3. 中小企業省力化投資補助金
「中小企業省力化投資補助金」は、人手不足に直面する中小企業の業務自動化・省力化を目的とした投資を支援する制度です。AIの活用が前提となるケースも多くあります。
申請方式は「カタログ注文型」と「一般型」の2種類があります。カタログ注文型は、省力化効果が認められた汎用製品を「製品カタログ」から選択して導入する形式です。従業員数5人以下で200万円、6〜20人で500万円、21人以上で1,000万円の補助上限が設定されています。製品選定が比較的簡単で、スムーズに申請できるのが利点です。
一方、一般型では、個別の現場ニーズに応じてカスタマイズした設備・システムの導入が可能です。補助上限額は従業員数5人以下の750万円から、101人以上の8,000万円(大幅賃上げ特例適用時は1億円)まで設定されています。
対象例としては、AIによるデータ分析システム、自動化ロボット、画像認識による検査システムなどがあります。製造業の品質検査や、サービス業の受付業務の自動化などでの活用が進んでいます。
2-4. 小規模事業者持続化補助金
「小規模事業者持続化補助金」は、小規模事業者等(従業員数20人以下)の生産性向上と持続的発展を図ることを目的とする制度です。比較的小規模のAI活用プロジェクトに適しています。
通常枠では補助上限50万円、特別枠では最大250万円までの補助が受けられます。補助率は原則2/3で、対象経費には機械装置費、開発費、委託費、広報費などが含まれます。たとえば、AIを活用したマーケティングや顧客管理システムの導入などが対象になります。
補助金額は限定的ですが、申請書類が比較的簡易であるため、初めて補助金を申請する小規模事業者でも取り組みやすい点が魅力です。既存業務の効率化や販路拡大を目的とした小規模なAI導入に適しています。
3. AI開発補助金の選び方と申請手順
補助金を活用するには、自社に最適な制度の選択と、申請プロセスの理解が重要です。
3-1. 企業規模・目的別の補助金の選び方
補助金を選ぶ際は、企業規模や開発目的に応じて最適な制度を見極めましょう。
企業規模別の選び方
従業員数20人以下の小規模事業者
小規模事業者持続化補助金が適しています。補助額は小さいものの、申請手続きが簡易で初めての申請にも向いています。
従業員数21〜100人の中規模事業者
ものづくり補助金や中小企業省力化投資補助金が有力候補です。補助上限が高く、より本格的なAI開発にも対応可能です。
開発目的別の選び方
新たなAIサービスを立ち上げる場合
中小企業新事業進出補助金が適しています。新市場への展開や業態転換を伴う挑戦的な事業に対応します。
既存業務の効率化・自動化が目的の場合
中小企業省力化投資補助金が最適です。人手不足の解消や生産性向上を目的とした設備投資に対応しています。
技術的な新規性のある開発を行いたい場合
ものづくり補助金が有力です。独自技術の活用や製品開発など、技術開発を重視するプロジェクトに適しています。
なお、採択の難易度も考慮しましょう。ものづくり補助金や中小企業新事業進出補助金は競争率が高いため、詳細な事業計画や差別化ポイントの明示が求められます。一方、中小企業省力化投資補助金のカタログ注文型は対象製品があらかじめ登録されており、比較的採択されやすい傾向があります。
3-2. 補助金申請の基本的な流れ
本記事でご紹介した4つの補助金を含む、多くの制度で共通する申請手順を解説します。なお、詳細な手続きや必要書類は制度ごとに異なるため、実際に申請する際は必ず各補助金の公募要領を必ず確認してください。
■ 申請準備フェーズ
1. GビズIDプライム取得(1~2週間)
↓
2. 申請書類準備(事業計画書・経費明細書等)
↓
3. 見積書取得・支援機関相談
↓
4. 電子申請システムで提出
■ 審査フェーズ
5. 審査・結果通知待ち
■ 採択後フェーズ
6. 採択決定後:交付申請手続き
↓
7. 事業開始承認後:プロジェクト開始
↓
8. 事業完了後:実績報告書提出
↓
9. 審査完了:補助金支給
このフローの各ステップについて、重要なポイントを解説します。
申請準備フェーズ(ステップ1~4)
まず、GビズIDプライムアカウントの取得が必要です。これは政府の電子申請システムを利用するために必須のアカウントで、取得には1~2週間程度かかるため、早めの申請が推奨されます。
次に、申請書類の準備を行います。事業計画書、経費明細書、決算書などの提出書類を揃え、公募要領に従って正確に記載しましょう。この段階で、補助対象経費の見積書を取得し、必要に応じて認定経営革新等支援機関から支援を受けることも重要です。特に、事業計画書の作成では専門家の助言を受けることで採択率が向上します。
電子申請システムで申請書類を提出する際は、締切間際のアクセス集中を避けるため、余裕を持ったスケジュールで手続きを完了させましょう。
審査フェーズ(ステップ5)
申請後は、審査結果の通知を待ちます。審査期間は補助金の種類によって異なりますが、一般的に1~3か月程度かかります。審査基準には、事業の実現性・革新性・地域経済への波及効果などが含まれる場合が多いです。
採択後フェーズ(ステップ6~9)
採択決定後は、交付申請手続きを行い、事業開始の承認を得てからプロジェクトを開始します。補助金の交付決定前に契約・発注した経費は補助対象外となるため、必ず承認後に着手してください。
事業完了後は、成果物や支出をまとめた実績報告書を提出します。報告内容は審査を経て確定し、問題がなければ補助金が支給されます。補助金は基本的に「後払い方式」であるため、事業期間中の資金繰りについても事前に計画しておくことが重要です。
4. 補助金を申請する際のポイント
採択率を高め、申請時のミスを避けるためには、いくつかの重要なポイントを押さえておく必要があります。
4-1. 採択率を上げる申請書作成のコツ
補助金の採択率を高めるには、審査員に評価されやすい申請書を作成することが不可欠です。
技術的独自性と革新性を明確にする
単なるAIツールの導入ではなく、自社独自の課題解決や新たな価値創出につながる点を具体的に示しましょう。市場分析や競合との差別化要素もあせて説明すると効果的です。
実現可能性の高い事業計画を示す
開発スケジュール、必要な人材や設備、リスクとその対策などを具体的に記載し、計画の信頼性を高めましょう。特にAI開発における技術的課題と解決方法は、専門的な観点からの説明が求められます。
定量的な経済効果を提示する
売上の増加、コスト削減、生産性の向上などを定量的に示すことが重要です。たとえば、「AI導入により作業時間が〇〇時間短縮され、年間〇〇万円のコスト削減が見込まれる」といった具体的な数値があると説得力が増します。
4-2. 申請時によくある失敗例と対策
補助金申請では、次のような失敗がよく見られます。事前に把握して回避策を講じましょう。
対象外経費の計上
汎用的なパソコンやオフィス家具など、AI開発に直接関係しない費用を補助対象として申請してしまうと、減額や不採択の原因になります。交付決定前に発生した費用も対象外です。自社の従業員給与は対象外とされることが多く、外部専門家への報酬のみが対象になる点も注意しましょう。
事業計画の妥当性が不十分
根拠のない楽観的な予測(例:「売上が3倍になる」)や、非現実的なスケジュール(例:「3か月で高度なAIシステムを完成」)は、計画の信頼性を損ないます。業界データや過去実績に基づいた計画を立て、リスクへの備えも盛り込むことが重要です。
5. AI開発補助金以外の資金調達手段
補助金以外にも、融資や助成金などの資金調達手段を組み合わせることで、より柔軟な資金計画が可能になります。補助金の採択結果を待たずに開発を進めたい場合や、補助対象外の経費をカバーしたい場合などに有効です。
5-1. 政策金融公庫・民間金融機関の技術開発向け融資
日本政策金融公庫では、AI導入に特化した「IT活用促進資金」を提供しています。中小企業事業では最大7億2,000万円の融資が可能で、一定の条件を満たすことで金利の優遇措置を受けられます。
補助金と異なり、融資は交付決定を待たずに資金を確保できる点が大きなメリットです。ただし返済義務があるため、事業の収益性や返済計画の妥当性が重要です。申請には「スマートSMEサポーター」など専門家の助言を受けることが条件となる場合があります。
民間金融機関でも、技術開発向けの設備資金融資や運転資金融資を用意しているケースがあります。地域金融機関では自治体と連携した特別融資制度が設けられていることもあるため、取引銀行に相談するのがよいでしょう。
5-2. クラウドファンディングによる資金調達
技術系クラウドファンディングは、革新的なAI技術やサービスに対して資金調達を行う手段として注目されています。
購入型クラウドファンディングでは、開発予定の製品やサービスを事前に販売することで資金を集められるほか、市場の反応を確かめながら開発を進めることができます。ニーズとのズレを抑える点でも有効です。
資金調達の方式には、目標金額に達しなければ資金を受け取れない「All or Nothing方式」と、目標未達でも集まった資金を受け取ることができる「All-in方式」があります。AI開発では初期投資や開発コストが固定的に発生するため、資金不足で赤字となるリスクを避けられる「All or Nothing方式」が選ばれることが多くなっています。
株式型クラウドファンディングであれば、より大規模な資金調達が可能ですが、株式発行に伴う経営上の影響にも注意が必要です。
5-3. 助成金制度の活用
助成金制度では、AI人材の育成に関連する支援が充実しています。たとえば「人材開発支援助成金」を活用すれば、外部研修や社内研修にかかる費用の一部の助成を受けることが可能です。
補助金がシステム構築費を対象とするのに対し、助成金は人材育成に特化しており、両者を組み合わせることで総合的な資金調達が可能になります。また「キャリアアップ助成金」を利用すれば、非正規社員を正社員化してAI人材として育成する際の支援を受けられます。
それぞれの制度には異なる要件や申請手続きがあるため、事前の情報収集と計画的な活用が重要です。
まとめ
本記事では、中小企業がAI開発に活用できる代表的な4つの補助金制度と、申請を成功させるための実践的なポイントを紹介しました。
「ものづくり補助金」「中小企業新事業進出補助金」など、それぞれの制度には特徴や適用条件があり、自社の規模や開発目的に合った補助金を選ぶことが重要です。また、補助金は採択率が高くないため、申請書の完成度や事業計画の妥当性が大きなカギを握ります。
さらに、補助金制度に加えて、政策金融公庫の融資やクラウドファンディング、助成金制度などの資金調達手段を組み合わせることで、より柔軟で実現可能なAI開発プロジェクトを実現できます。
AI開発を進める際には、資金調達とあわせて、開発環境の整備も重要な要素となります。さくらインターネットの高火力シリーズでは、AI開発に最適化されたGPUクラウドを提供しており、従量課金制で柔軟に利用できるのが特長です。初期費用を抑えて、必要なタイミングで高性能な環境を活用できます。
AIを活用した事業に取り組む皆さまにとって、本記事が資金調達や制度選びの一助となれば幸いです。

さくらインターネットが提供している高火力シリーズ「PHY」「VRT」「DOK」を横断的に紹介する資料です。お客様の課題に合わせて最適なサービスを選んでいただけるよう、それぞれのサービスの特色の紹介や、比較表を掲載しています。



 New
New

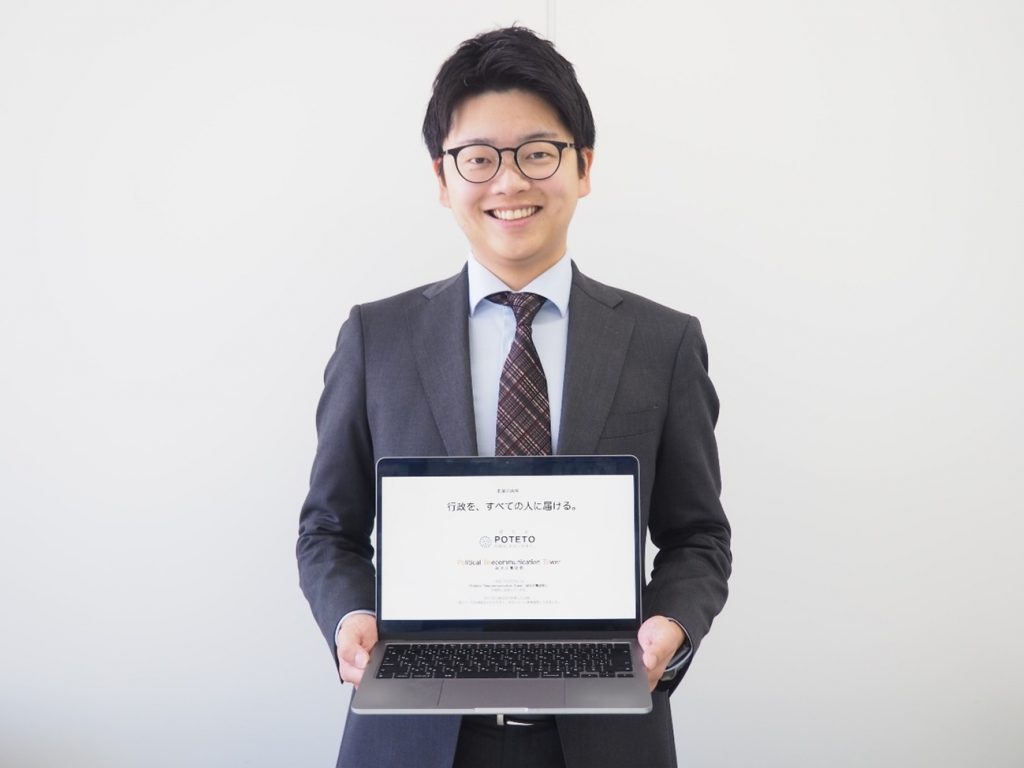
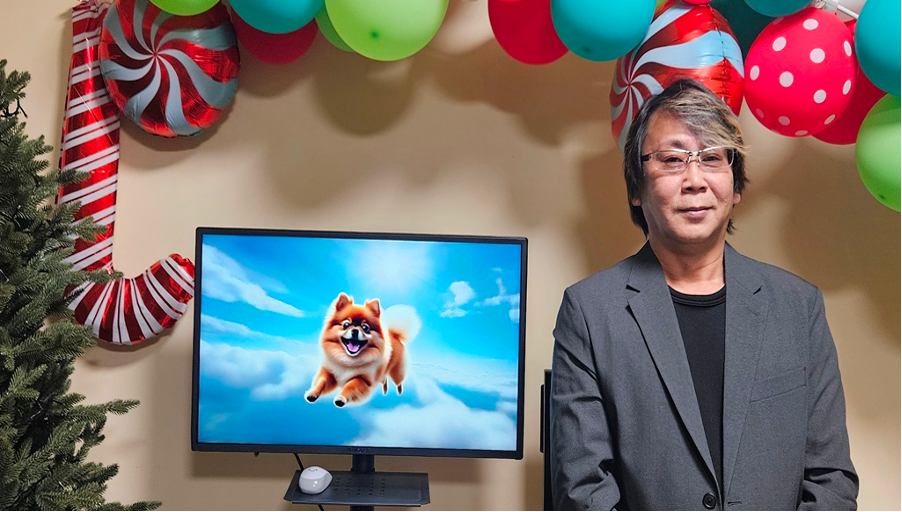
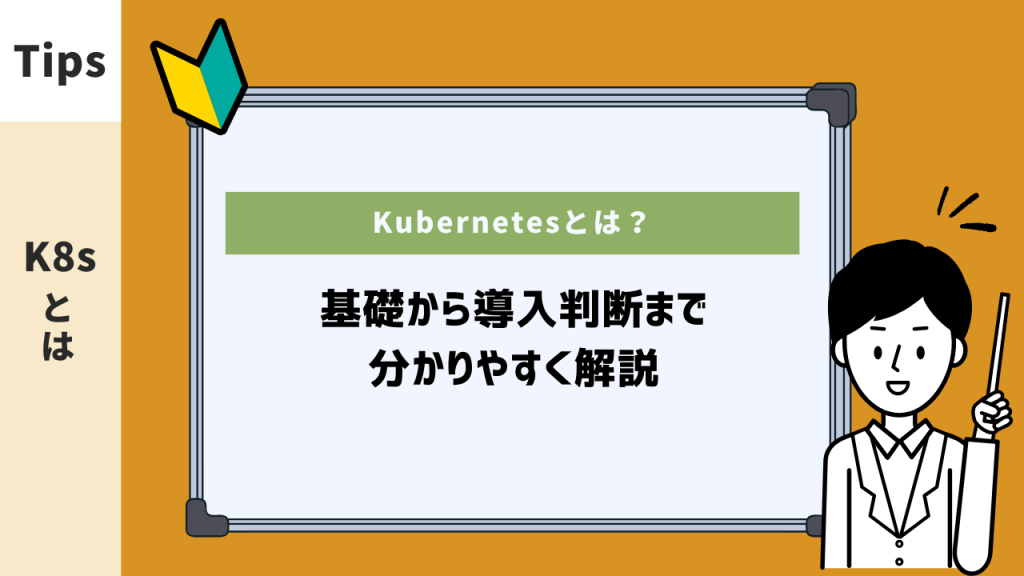
 特集
特集




