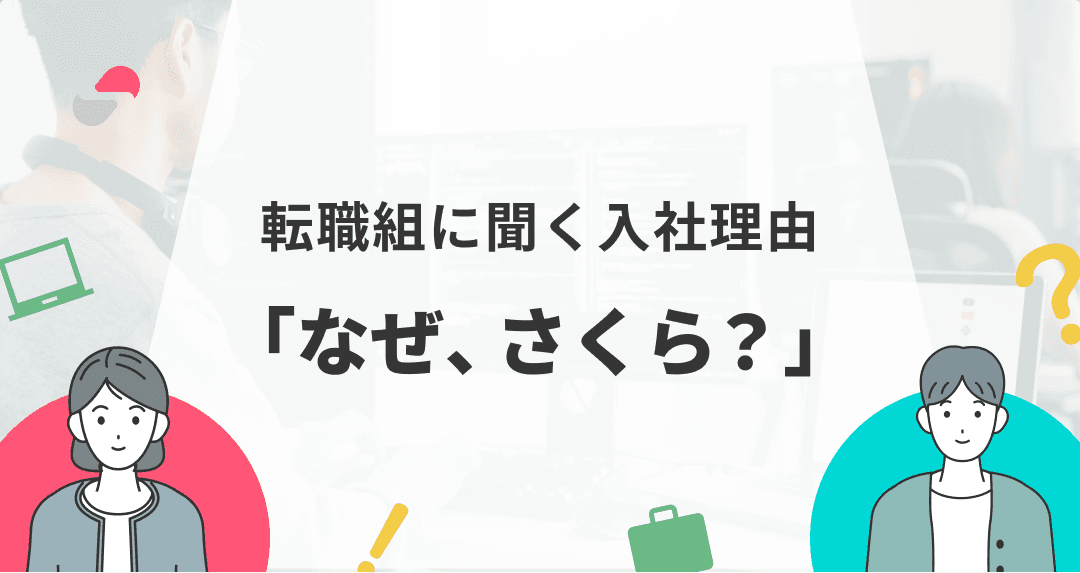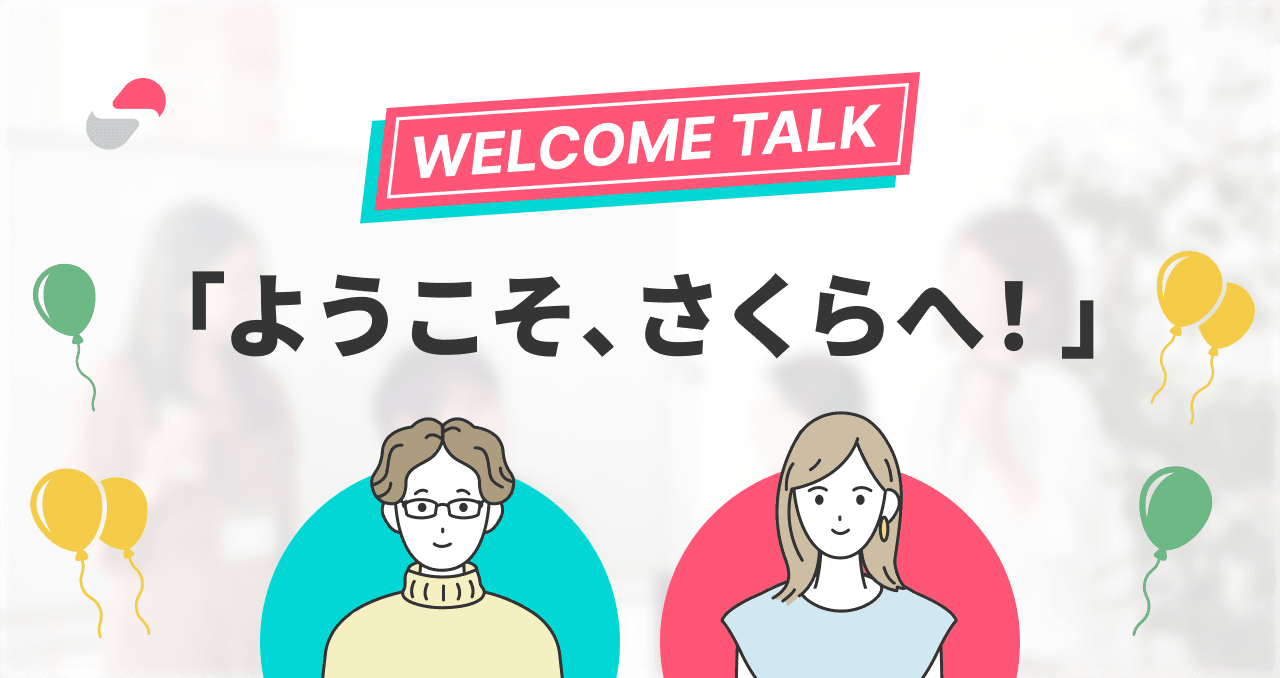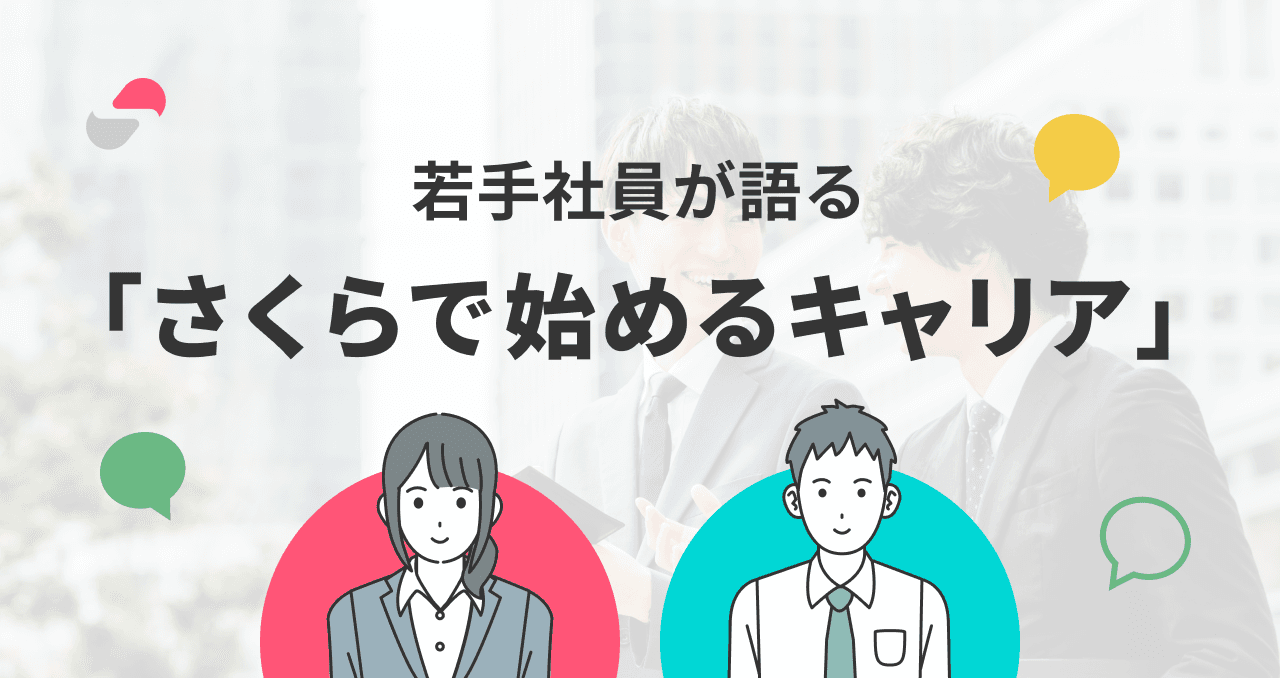IT・デジタル関連の最新情報や企業事例をいち早くキャッチ
>>さくマガのメールマガジンに登録する
日本酒の海外輸出量は年々増加している。しかし、生産総量や国内市場を加味すれば、そこにはまだポテンシャルによるものが大きく、國酒たる日本酒の存続・振興のために注力すべき課題だ。そういったなかで、日本酒のリブランディングや海外戦略をおこなうのが株式会社Agnavi(以下、Agnavi)だ。より手軽でスタイリッシュ、そして持続可能な日本酒のあり方を提案する同社の事業と今後の展望について、代表の玄 成秀さんに聞いた。

玄 成秀(げん せいしゅう)さんプロフィール
1992年生まれ、群馬県出身。私立函館ラ・サール中学・高校を卒業。2016年に東京農業大学を卒業後、2018年に同大学院 農芸化学専攻 修士課程を修了(首席)。在学中に米国コーネル大学留学、2019年に創業した株式会社アグリペイを代表取締役として事業譲渡、2020年2月に株式会社Agnavi を創業。2021年3月、東京農業大学大学院 農学研究科 農芸化学専攻 博士課程を修了。博士(農芸化学)の学位を取得。Agnavi を経営するかたわら、2021年4月より東京農業大学 客員准教授も務めている。
日本酒をめぐる国内・海外市場の課題

「日本酒を飲むシーン」は、時代とともに大きく変化している。今ほど酒類のバリエーションが多くなかった昭和の時代は、家庭に一升瓶があり、日常的に飲むお酒として日本酒が食卓に並んでいた。時代が移り変わり、スーパーマーケットで、あるいは飲食店でさまざまな酒類が販売されるようになると、そのシェアは徐々に奪われていった。かつてのような大量生産・大量消費の時代は終わったものの、それでも全国の酒蔵では純米酒や吟醸酒などの「特定名称酒」に注力。量から質へとシフトすることによってファン獲得に努めてきた。
しかし、それでも日本酒の国内市場シェアや製造量は減少を続けている。健康志向の高まりによる飲酒の需要減少も相まって、依然として苦しい状況が続いていることも事実だ。そこへさらに追い討ちをかけたのが、2019年末から始まったコロナ禍だった。自粛要請による飲食店の休業、アルコールの提供休止などは酒蔵にとって大きなダメージとなった。2020年時点の日本酒(清酒)の事業者数は 1,550。2010年度から 236 の酒蔵が統合や廃業によって姿を消した(※)。全国の日本酒は今、存続の危機に瀕すると同時に、新たな日本酒のあり方を模索している。
そのようななか、日本酒市場に「新たなスタイル」を提案する企業がある。2020年創業のスタートアップ、Agnavi だ。同社が提供する「ICHI-GO-CAN®」は、ちょうど 1合(180ml)サイズの缶に日本酒を充填および販売するサービスである。「ICHI-GO-CAN®」提供の背景を、代表の玄成秀さんに聞いた。
「Aganavi自体は 2社目で、その前にはアグリペイという会社をやっていました。ちょうど事業譲渡をおこない、心機一転スタートしていたときのことです。一番最初に『日本酒プロジェクト2020』という、Agnavi と母校の東京農業大学、そして日立キャピタルグループとの産学官連携のクラウドファンディングをはじめました。当時は緊急事態宣言で酒屋さんも在庫がダブついてしまい、酒蔵も出荷が止まってしまうような状況のときでした。プロジェクトは全国 56蔵の酒蔵を支援するもので、約2,600万円集めました。
ただ、プロジェクトをおこなうなかで感じたのは『日本酒を瓶で売る』ことへの難しさでした。消費者の生活スタイルが変化するなかで、日本酒販売の中心になっている一升瓶や四合瓶は量が多すぎると思う方が多くなってきているんです。『日本酒は好きだけど、あまり多くは飲めない。買っても品質が劣化してしまってもったいない』という声も聞きました。日本酒という市場が低迷しているなかで、新たな価値訴求のあり方が求められていると思いました」
国内市場のニーズへの対応に課題を感じる半面、日本酒のポテンシャルにも着目していた。海外への輸出だ。日本酒の海外輸出は増加を続けており、2021年の輸出金額は約400億円と、対前年比で 60%以上も増加している(※)。しかし、好調な伸びを見せている一方で、日本酒の輸出にも障壁が多いという。
「大きくわけて、輸出での課題は 2点あると考えています。まず 1つ目はリソースの問題。酒蔵のほとんどが必要最低限のリソースで日本酒をつくっているのが現状です。そのかたわらで輸出に関する業務をおこなうには限界があります。また、日本酒をただ輸出すればいいというわけでもない。各国に対してのブランディングやマーケティングなどがなければ売れるものも売れません。
2つ目は、品質と輸送コストの問題です。ワインも温度や湿度管理が重要なお酒ですが、日本酒はもっと繊細で風味が劣化しやすい。さらに、瓶での輸出は効率が悪く、その分一本あたりの輸出コストは高くなります。その結果、海外に行くと日本酒は非常に高価で品質管理のハードルも高いお酒になってしまいます。
こういった日本酒の国内・海外市場の課題を解決し、酒蔵の方々に寄り添ったサービスができないかと考えたのが『ICHI-GO-CAN®』のはじまりです」
>>5分でさくらインターネットのサービスがわかる!サービス紹介資料をダウンロードする
『ICHI-GO-CAN®』がもたらす「三方よし」のビジネスモデル

では、「ICHI-GO-CAN®」とは具体的にどのようなサービスなのか。1合サイズの缶という面では適量感はある。しかし、1合サイズの瓶や紙パックで販売されている日本酒はすでにある。「ICHI-GO-CAN®」にはどのような特性があるのだろうか。
「まず、『ICHI-GO-CAN®』は適量・持ち運びが便利・環境にもやさしいという 3点の特徴があります。それに加えてデザイン性にもこだわることで、1合瓶や紙パックの日本酒の購買層とは明確に棲み分けをしています。バリエーションが豊富なことも強みです。
サービス提供開始から 2年弱となった現在では、全国100弱の酒蔵と取引し、100種類以上の『ICHI-GO-CAN®』が展開されています。各銘柄もよりスタイリッシュなパッケージデザインを施すことで、おしゃれでほどよい飲酒体験が実現できるようなサービス設計となっています。
Agnavi では、このような『ICHI-GO-CAN®』に合わせたリブランディングのほか、自社工場で缶への充填委託をおこなっています」
多くの酒蔵では瓶詰めの充填装置はあるものの、缶に対応できるものは多くないため、新たに導入する場合は大きな設備投資となってしまう。そのような点からも、充填作業は Agnavi が請け負い、「ICHI-GO-CAN®」という共通ブランドのもと流通させたほうが効率的だ。しかし、いくらスタイリッシュなデザインを施したものでも、商流に乗らなければ意味がない。また、酒蔵主体での新製品のプロモーションや卸業者への営業活動は、負担が増すことになる。
「そういったデメリットを解消するためにも、私たちは各酒造の『ICHI-GO-CAN®』を一定数買い取り、国内市場での輸出やプロモーション、さらには輸出をおこなっています。Agnavi では、自社EC はもちろん、国内大手スーパーマーケットや大手百貨店と直接取引があるほか、ポップアップストアも展開しています。また、輸出では北米や欧州、南米、アジア圏などサンプル展開も含めて 約10か国への輸出をおこなっています。
先ほども話した通り、酒蔵が個社単位で海外輸出やマーケティングをおこなっていくのは非常に難しい。しかし、『ICHI-GO-CAN®』というブランドのもと、私たちがその役割を担うことで、大手ビールメーカーがおこなっているような海外ブランディングを展開できるようになるのです」
物流コストの面でも「ICHI-GO-CAN®」はメリットを発揮する。円筒状になっている缶は、四合瓶や一升瓶と違い積載ロスが少ないため、効率的な輸送が可能だ。また、アルミ缶を使っているため、輸送中に破損するリスクも比較的低い。コストが抑えられれば、輸出先の国でも日本酒はより手軽でカジュアルなお酒となる。また、物流の効率化は環境への配慮にもなる。さらに、瓶ではなくアルミ缶を採用している点もサステナビリティを意識しているという。
「従来、日本酒の酒瓶は『リターナル瓶』というものが使われています。これは空き瓶を回収して再利用するサイクルがあります。しかし、日本酒の生産本数も消費も減少しているなかで、そのサイクルが少しずつ機能しなくなっているのが現状です。そのため、酒瓶の価格が高騰していることも酒蔵の方々の悩みの種になっています。一方で、アルミは供給が非常に安定している素材であり、社会全体で再利用のサイクルが機能している。そのような点からもアルミ缶の採用はコストを抑えるとともに、持続可能性が高いと思っています。
また、輸出に目を向ければ、瓶であってもアルミ缶でもあっても、基本的には一方通行で日本には戻ってきません。しかし、世界的に見てもアルミ缶のほうが再利用の循環は確立されていて、循環効率もよいものです。そのような観点からも『ICHI-GO-CAN®』は環境にやさしいという点に特徴があると考えています」
日本酒産業のゲームチェンジャーになりたい

まだスタートから間もない Agnavi と「ICHI-GO-CAN®」だが、その評価は着実に高まっている。2023年4月、Agnavi はシード期の資金調達として累計1.2億円を調達した。金融機関だけでなく、東洋製罐グループや JR東日本スタートアップなど、同社のステークホルダーや地方創生に注力する企業やベンチャーキャピタルからの出資も目立つ「ICHI-GO-CAN®」の成長がもたらす地方経済へのインパクトに期待が寄せられての資金提供だ。
「Agnavi を設立した 2020年、日本酒産業は低迷の最中にありました。国全体での出荷は 2割減となっていますが、実勢での出荷売上ベースでは 5割以上減った酒蔵もあるでしょう。酒蔵という存在は、ただ日本酒をつくっているだけではなく、地域の観光資源でもあり、酒米の買付という点では国内農業への貢献も大きい。そのほか、経済活動だけではない地域貢献もしているため、地方経済にとって非常に重要なのです。地方創生において、そういった地域の担い手をまず盛り上げないことには活性化していかないと考えています」
一方で、国外からは「ICHI-GO-CAN®」のブランディング面での評価が高まっている。資金調達完了と同時期に、イギリスの経済・ライフスタイル誌「MONOCLE(Based in London, UK)」が主催するデザインアワードで日本唯一のトップ50に選出された。選出されたのは小田急グループとのコラボ缶であり、「ICHI-GO-CAN®」には小田急電鉄の車両がデザインされている。

資金調達完了、そして国内外での認知が高まるなか、Agnavi はどのような事業展望を持っているのだろうか。販路や輸出先の拡大とともに、玄さんが見据えるのは「日本酒を飲むシーン」の提案だという。
「日本酒はもともと、とても生活に根ざしたお酒であり、さまざまなシーンに日本酒があったと思います。Agnavi としては世界中でもっとさまざまなシーンで日本酒を飲んでいただけるような提案をしていきたいと考えています。たとえば、飛行機の中に日本酒を持ち込む際も、缶であれば場所を取らないので気軽に楽しむことができます。また、ホテルでのウェルカムドリンクとしても便利ですね。
また、海外では、やはり「日本酒は高価」というイメージがあります。品質管理が難しいこともあり、メニューに入れることを避ける飲食店もあります。そのようなお店でも「ICHI-GO-CAN®」の価格やバリエーション、鮮度管理のしやすさを訴求して、より気軽に出せてお店のお客さんにも美味しい日本酒を楽しんでいただける。そういった体験訴求をおこなっていきたいと考えています」
そのためにも、Agnavi に求められるのは「ICHI-GO-CAN®」の安定的な生産と供給体制の確立だ。とくに海外での認知が高まるなかで、輸出総量も増加しつつある。今後は酒蔵との連携や「ICHI-GO-CAN®」の生産体制への設備投資が求められてくるだろう。
「現状、『ICHI-GO-CAN®』の充填工場は埼玉にある 1か所のみで、最大で約200万本を生産できます。現状、工場が1か所だけでは地方の酒蔵さんとの輸送や連携に課題があります。今後は東北や関西、九州などに工場を増やしていく予定で、当面の目標として 1,000万本程度の生産体制をつくりたいと考えています。
また、海外に目を向けると、やはり各国の有力企業とのアライアンスを組んでいくことも重要ととらえています。現地に精通したノウハウを持った現地のパートナーと連携を強化しながら、まずは最短ルートで現地の日本酒市場を広げていくことが先決です」
日本酒産業はいま、変革の時を迎えている。先日紹介した西堀酒造の西堀哲也さんの取り組みのように、酒づくりそのものをアップデートしていき、日本酒産業の持続可能な未来をつくり出そうという動きがある。一方で、Agnavi は、飲酒スタイルの変化や輸出へのポテンシャルに着目して、その提供スタイルやブランディングのあり方の刷新にチャレンジしている。最後に、玄さんが目指す未来や、日本酒産業における Agnavi のあるべき姿を聞いた。
「日本酒産業にとってのゲームチェンジャーになりたいと考えています。たとえば、缶ビールの登場がビール市場の拡大を圧倒的に押し上げたように、日本酒における瓶から缶への流れは、日本酒市場を向上させると考えています。そのための事業展開としては、『ICHI-GO-CAN®』を中心として、より早いスピードで普及拡大を図っていくことが重要です。スタートアップとしても、そのようなスピード感とスケーラビリティを意識していきます」
「生産者に多様な選択肢を」。Agnavi が掲げるミッションだ。伝統産業である日本酒産業は、伝統と革新が共存しつつ、未来へと進もうとしている。その可能性はまさしく「多様な選択肢」によって生まれていく。新たなムーブメントがもたらす「新たな日本酒のあり方」に期待したい。








 特集
特集