
ブロックチェーン技術の応用によって生まれたNFT(non-fungible token=非代替性トークン)アートが巷で話題になっている。
我が国では政権与党がNFT関連の法整備に前向きで*1、成長戦略の柱とするのみならず、「岸田総理トークン」なるものを配布するほどの入れ込み具合*2。
「なぜそれを…」という問題はともかくとして、NFTがお上の目につくほどのホットワードのひとつとなっていることは確かだろう。
では、お隣中国ではどうかというと日本同様、もしくはより前のめりになっているのが現状だ。現地報道によれば、中国国内におけるNFTアートの交易プラットフォームは300を超え、その多くは今年1月から4月の間に誕生したものだという*3。
だが、そもそも中国はブロックチェーン資産に対して厳しい統制を加えており、暗号通貨の取引およびマイニングを禁止している。NFTアートは発行こそ認められているものの、転売はNGであり、そのうえ各プラットフォームは実名認証制のため匿名性も担保されない。
要するに、中国においてはいくらNFTアートを買い漁ろうが、値上がりや売り抜けが期待できるとは思えないのだが、どういうわけか発行即完売などというケースも見受けられるのである。
実のところ、NFTアートに関しては目下さまざまな問題が指摘されており*4、一部ではすでに伸びがピークに達したとする指摘もある*5。
そんな国外の潮流などおかまいなしに、爆発的な盛り上がりを見せる中国のNFTアートの世界とは、一体どのようなものなのか。
本稿はうっかり立ち入ると泥沼にはまりかねない技術的側面は横に置き、NFTアート熱を中国で起きている事象のひとつと捉え、このテーマについて私見混じりで分析を加えてみたい。
資産ではなくコレクションという位置付け
筆者は普段、中国発のさまざまなアナウンスに目を通し、それらを訳したり分析したりする作業に従事しているのだが、昨年から今年にかけて「数字收藏」「数字藏品」という言葉をやたらと目にするようになった。
それも中央だけでなく、地方都市が出しているプレスリリースなどの文章にも、この単語がやたらと登場するものだから、ブーム到来かと思ったわけだ。
さて、この「数字收藏」を日本語にそのまま訳せばNFTアートとなるのは確かなのだけれども、いろいろと調べ、さらに筆者などよりよっぽど詳しいライターの方による先行記事を参考にした結果*6、「デジタルコレクティブル」という言葉を使うのが正解という考えに至り、現在に至っている。
これはざっくり説明すれば、海外で一般に言われるNFTアートと中国の「数字収蔵」は、トークンによって唯一性を証明するという点は同じでも、似て非なるものということ。
中国の「数字収蔵」はあくまでコレクション、単に集めて悦に入るためのもので、資産価値があってはならない(ということになっている)のである。そもそもこれらを扱う中華プラットフォーム自体、NFTという言葉をあえて避けているフシがある。
中国におけるデジタル資産の管理

なぜそこまで気を使うかと言えば、中国は前述の通り、デジタル資産の管理について極めて敏感であり、法定通貨でない暗号通貨(暗号資産)がご法度の国であるからだ。ダメな理由としては投機の問題や実体経済重視の姿勢、中国が打ち出しているCO2排出削減計画への影響などさまざまな理由が挙げられる*7。
だが、根本にあるものは、デジタル人民元の普及に当たって他の暗号通貨が邪魔であること、何事も自国のコントロール下に置きたい中国にとって分散型・非中央集権的な金融ツールは危険視されること、そして何よりもマネー流出への懸念であろう。
中国の人々、とりわけ小金を持っている層がどれほど国外に資産を逃したいと考えているか、また同時に政府がいかにそれを阻止したいか。具体的には語らないが、この攻防は実にすさまじいものがある。
中国としてはブロックチェーン技術の恩恵は受けたいけれども、デジタル資産に関しては上記の理由からどうしてもガチガチの統制を敷かざるを得ない。
よって、中国の「数字収蔵」に資産価値や流動性が生まれることは当局として断じて容認できず、乱暴に言えばスマホの中の飾りという以上の意味を持たない存在となっているのである。
デジタルコレクティブルを買うのは大半が若者
では、中国では実際にどのようにしてデジタルコレクティブルが売られているのか。試しにアリババが運営している「鯨探」というプラットフォームを開いてみると、真っ先に目につくのは博物館の収蔵品や京劇など中国の伝統文化にまつわる品々だ。
それに加えてキャラクター系もあり、価格帯としてはいずれも18元から25元(1元=約19円)程度。数量は限定10000などとしているものが多く、予約で完売などというデジタルコレクティブルも珍しくない。
ちなみに、中国の伝統文化にまつわるものは全体の約7割を占めるそうで、これは政府が文化のデジタル化戦略*8を打ち出して後押ししている影響が大きい(数字は以下いずれも前出の「腾讯网」の記事より引用)。
実際、5月18日は国際博物館の日だったのだが、それに合わせて収蔵品に関連するデジタルコレクティブルを発行した美術館や博物館も多かった。
なぜデジタルコレクティブルが若者に人気なのか?
では、そういうものにお金を出す人は比較的年配の方が多いのだろうと思いきや、1990年以降生まれが71%と、不可思議な状況が生まれている。中国の代表的な官製メディアである『人民日報』の日本語サイトは、「なぜ若者に大人気なのか?」との問いについて、以下のように論じている。
「デジタルコレクションにこれほど人気があるのは、今の若者にとってこれが一種の社交の手段であり、人と違う目新しいものを求める若者にぴったりだからである」*9
一読して感じるのは「いや、そんなわけないだろう」という思い。百歩譲って言うならば、中国では「国潮」といって、自国の伝統的要素を取り入れたブランドカルチャーに勢いがあるのは確か。
だからといって若者が青銅器や玉器などのデジタルコレクティブを集めまくるというのは、事象としていかにも不自然だ。この論評のピントがズレているのは明らかであり、はっきり言って投機目的以外に理由など考えられないのである。
恐るべし! 中国人の投機スピリッツ
売り買いできないものが、どうして投機の対象となり得るのか。筆者の見立てでは、まずひとつにNFTアートならぬデジタルコレクティブルが中国ではまだまだ広く認知されていないこと、平たく言えばよく分かっていない人が多いことが大きい。
一例として挙げられるのは、今年2月に開催された北京冬季オリンピックのマスコットキャラ「氷墩墩」(ビン・ドゥンドゥン)のNFTアートに最高で約2000ドルの値段がついたというニュースである。
中国国内でも伝えられたこの報道をもって、「やっぱり儲かる」「実は売り買いできる」と勘違いした者は、きっと少なくないだろう。
だが、ここで使われたプラットフォームは海外のものであり、値段の高騰もしょせんはビン・ドゥンドゥングッズが売り切れになった開催期間中のあだ花に過ぎない、といったことに触れない中華メディアが多かった。
また、確かに中国国内のデジタルコレクティブル関連のプラットフォームでは売買不可ながら、一定の条件下で譲渡はできる。そこで、表向きはプレゼントだが、裏で金のやり取りをすればいいと考えた者も多かったに違いない。
実際、中国で最もメジャーな中古品売買アプリ「閑魚」では、デジタルコレクティブル関連の売買がおこなわれ、それに対する取り締まりもあったが、今でも「数字収蔵」で検索すると結構な数がヒットする。
さらに、投機目的の購入がなくならない理由を深読みすると、「中国国内のユーザー間のみ取引を可とする」といった将来的な方向転換の可能性に賭けて、今のうちに先行投資ならぬ先行投機を行っているユーザーもいるかもしれない。
中国ではさまざまなものが投機対象に

むろん、そのような変化が起きる確率はゼロではないし、自分の金をどう使おうが、極論すれば個人の勝手ではある。しかし、投機のために手を出す人々が、NFTアートもしくはデジタルコレクティブルについて言われる問題について、到底深く理解しているとは思えない。
ある日突然、プラットフォームが運営を止めたらどうするのか。購入した非代替性トークンはデジタルデータの唯一性を証明するものに過ぎず、紛失やコピーを防ぐものでもなければ、著作権や所有権を伴うものでもないことを分かっているのか。
こっそり売買していて捕まるリスクについて、真剣に考えているのかーー。
もっとも、中国人とは誰もが相場師の気質を大なり小なり持つと言ってもいいほどに、金への執着が強い人々。この国では理財商品や不動産にとどまらず、マオタイ酒にプーアル茶*10などさまざまなものが投機の対象とされ、その熱気たるや日本の比ではない。
暗号通貨の爆発的な値上がりを知る中国の人々がNFTに注目しないわけがなく、これからもアート以外のさまざまな分野を含め、この業界には投機マネーが流れ込むことだろう。
ちなみに筆者は根っからのビビリであり、一攫千金など信じないタイプ。でも、「岸田総理トークン」ならぬ「習近平総書記トークン」が発行されることがあったら、値上がりに賭けてひと勝負してみたいと思っている。
そのようなものがバラまかれることは、万が一にもないだろうがーー。
*1:自民党「『Web3.0』をわが国の成長戦略の柱にNFT政策検討PTが提言(案)を取りまとめ」
*2:デジタル「岸田トークン」を自民党が初配布へ NFTに本腰か|FNNプライムオンライン
*3:腾讯网「海外NFT缩水万倍,国内数字藏品平台激增,都在发行什么?」
*4:WIRED「NFTアートを巡る法的混乱は、アーティストのロイヤルティ条項を守れるか」
*5:Forbes「失速鮮明のNFT市場、売上もアプリDL数も90%減少」
*6:BRIDGE「NFTアートとは呼ばせない、中国のデジタルコレクティブル・プラットフォーム——主要プレーヤーを一挙紹介」
*7:WIRED「中国で仮想通貨が『全面禁止』になった理由と、矛盾もはらむ政府の思惑」
*8:中华人民共和国中央人民政府「中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于推进实施国家文化数字化战略的意见》」

執筆
御堂筋あかり
スポーツ新聞記者、出版社勤務を経て現在は中国にて編集・ライターおよび翻訳業を営む。趣味は中国の戦跡巡り。
※『さくマガ』に掲載の記事内容・情報は執筆時点のものです。
- SHARE


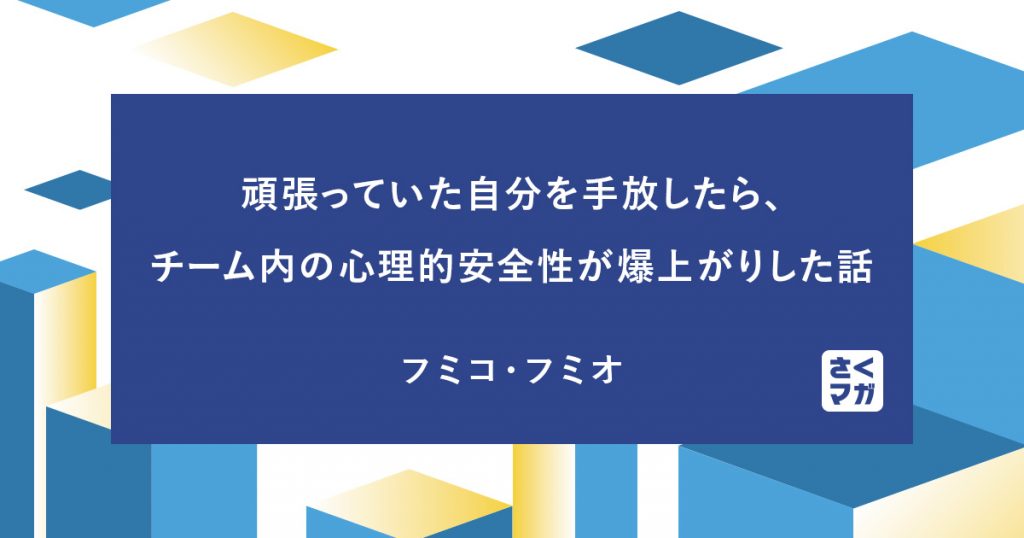

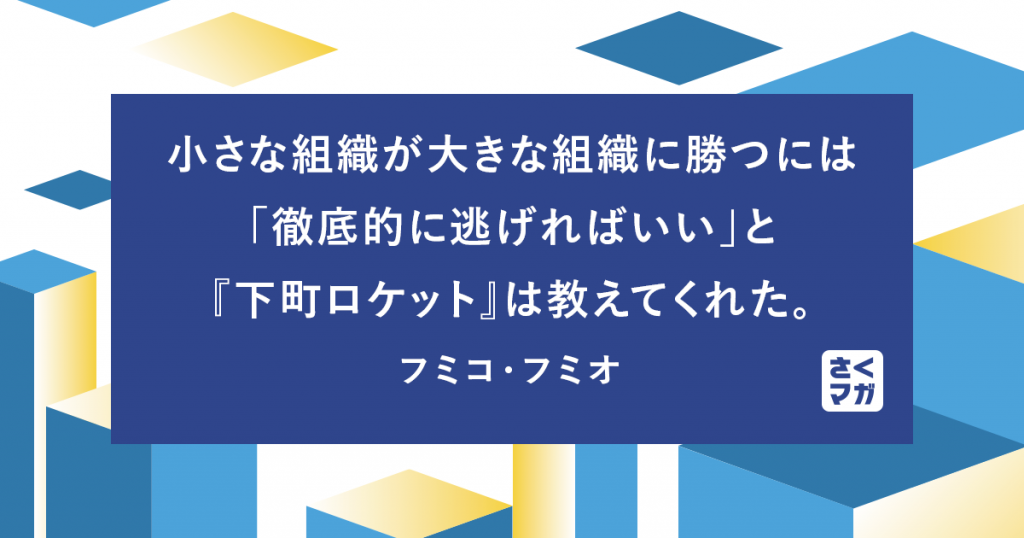
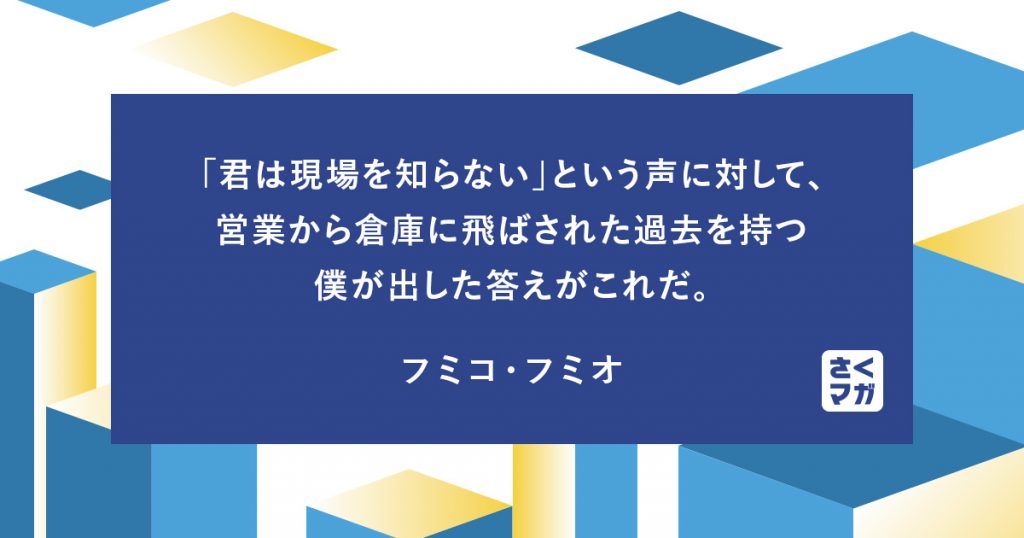
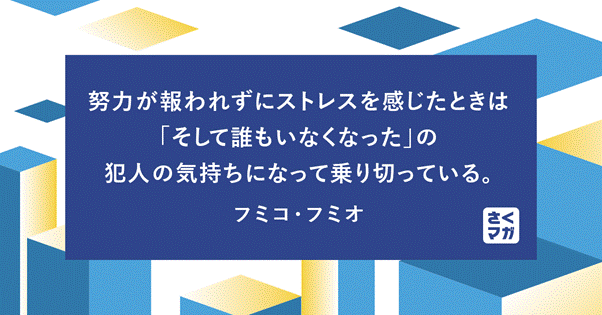
 特集
特集




