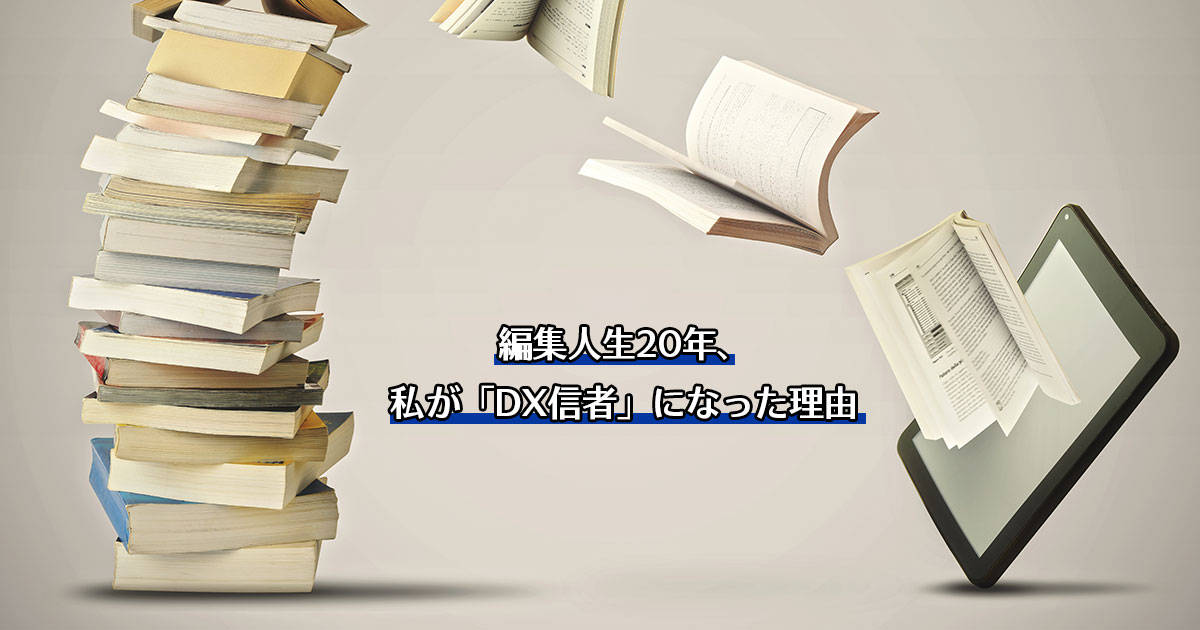
特定の何かを絶対的なものと信じ、疑わないことを「信仰」と呼ぶ。
論理的に説明できる事柄であっても、完全肯定するためには根っこの部分に「信じる」という行為が伴う。
自分は現在、中国に住んでいるのだが、周囲にいる党員の皆さんは自らのイデオロギーを科学的理論であると語り、無宗教を掲げる。しかし、そんな彼らもまた「共産主義は絶対的真理」と信じてやまない人々。
真理であるかどうか証明し得ない以上、そこにはやはり信仰が存在し、彼らが忌み嫌う宗教と割合近い部分がある。
さて、なぜそんな前フリで書き出したかといえば、自分はDX(デジタルトランスフォーメーション)の未来に揺るぎない「信仰」を抱いているからだ。
進化するテクノロジーは、本当に人々の暮らしを豊かにするのかーー。
これまでにさまざまな論証がなされ、裏付けとなる実例もごまんとある以上、この問いかけには一見疑いを挟む余地などなさそうに思える。
だが、厳密に言えば現時点における仮説であり、とどのつまりはそれを信じるかどうか。そこで自分としては、主の復活を信じるクリスチャンのごとく、DXがもたらす明るい未来への信仰を高らかに宣言したいのだ。
もっとも、そのような思いに至ったのは、神のお告げがあったわけでも何でもない。理由は簡単、出版業界に20年ほど携わる中でデジタル化の波をもろに受け、DXが生み出す変化とその不可逆性を目の当たりにしてきたからだ。
世の中には、いまこの瞬間も職場でのDX推進に取り組み、壁にぶつかっている人とていることだろう。そのような方々にDX=必然という筆者の篤い信仰心と、それが生じるに至った経験をお伝えすることで、何かの励みになるのではあるまいか。
狭い業界でのエピソードであり、論証というよりは信仰告白に近いかもしれないが、以下自分の思いを語ってみたい。
駆け出しの頃からあった「遅れてるよね」という感覚

出版とはそのものズバリ情報を扱う仕事であるにも関わらず、デジタル化が早い業種では決してなかった。自分が新卒でライターになったのは2000年、任されたのはスポーツ新聞の仕事である。
時すでに21世紀でありながら、職場で支給されたのはインクリボン式のワープロ。原稿を刷り出し、画像素材は紙焼き写真にして、地下鉄を乗り継ぎクライアントまで届けるのが日課だった。
いや、そんなのメールで送ればいいのでは……と思ったが、相手は大手スポーツ新聞社であり、デスクのジイさんは頑としてITを受け付けない。そのお人は、かつてスポーツ以外の話題を一面に持ってくるのはご法度とされていた時代に、社内の反対を押し切って社会記事を頭に持ってきたという伝説的存在。
いわば改革派であるにも関わらず、ことITに関しては何を提案しても「お前、なめとんのか」という対応で、話が通じない相手なのだった。いま考えれば実に無駄な時間を過ごしたものよと思うのだが、デザイナーを生業とする先輩からすれば自分はまだマシなほうらしい。
グラフィックデザインがまだアナログだった時代、レイアウト作成で使うのはPCではなく紙とカッターとピンセット。一体、切り貼り作業にどれだけの時間を費やしたことか……あの苦しい時代を知らないのは幸福以外の何物でもない、と先輩はしみじみ言っていた。
ちなみに出版業界におけるデザイナーとは、最もデジタル導入が早かった人々だ。
徹底した合理主義者で、「できれば100年後、もっと技術が進んだ時代に生まれたかった」と真顔で語るこの先輩もご多分に漏れず、アナログな人々とのバトルを経ていまがある。
「こちらがデジタル導入を進めたいと思っていても、結局は一番遅れているところに合わせなければ仕事が成り立たちません。しかも往々にして、その遅れているところが発注元であったりすることが多く、仕事をもらっている立場上、こちらからは物申しにくいのが悩みどころです」
とは言え、どれほど頑迷な人や組織であっても、最後はITが生み出す利便性の前に考えを改めるーーゆえに自分もこの先輩も、DXによってもたらされる未来に、大いなる希望を抱いている。
ただその時、まだ現役で働けているかどうか、お互い全く確信はないのだが。
出版界のデジタル化を阻んでいたファクターとは

さて、時代は下って自分が雑誌編集者となった2000年代前半。
原稿やデザインはさすがにデータ化したが、一番の金食い虫である写真は相当後になるまでアナログから抜け出すことができなかった。あの頃、グラビア誌を1冊出すとなると、撮り下ろし用のフィルムと現像費だけで毎月およそ50万円のコストがかかっていた。
撮った写真はラボに持っていき、上がったフィルムからセレクト写真を切り出すだけでも徹夜作業。マンパワーも含めて果てしない浪費で、デジタル移行すればそれらは節約できるのだが、頑として認めない人々がいた。
まず筆頭は当時の上司で、デジタルで人肌をきれいに表現できるわけがないという信念の持ち主。いま考えれば寝言のようだが、当時は印刷所がデジタルデータに慣れておらず、刷り上がったものを見てひっくり返るようなことは確かにあった。
それを変えていったのは「これからはデジタルの時代」と先を見据える目を持った一部の業界人。中には現状を変えるべく印刷所に怒鳴り込むカメラマンもいたほどだ。
さらに時代が下り、出版社が自前のサイトを持つべきだという話になった。
雑誌のコンテンツは、作ったら作りっぱなし。それをただ埋もれさせるのではなく、WEBマガジンを立ち上げてコンテンツにすれば無駄にならず、読者層の掘り起こしにも繋がるーー。
これもいまなら当たり前の思考とはいえ、最初は非難轟々だった。
「いい雑誌を作っていれば読者はおのずと増えていく」
「WEBに人を回す余裕はない」
「俺は紙の力を信じている」
そう言って協力しない編集が一定数おり、遅々として進まなかった。他にも例を挙げていけばキリがないが、これらをまとめると出版業界のデジタル化が遅れた要因として、以下の3点が大きかったのではと考えている。
(1)変化に対する忌避感
出版は厳しいと言われて久しいものの、いまと比較してみればデジタル化が始まった当時はまだまだ余裕いっぱい。
そこまで無理しなくても、いままで通りでいいのではーーそういう思考が何となく許される緩さがかなりの程度残っていた。むろん、現状に甘んじている限り、変革は起こらない。
「前時代的な成功体験にすがる編集者がイニシアチブを握りがちで、ITに対応できないベテラン勢が意識の有無に関わらず変化を拒否しがちだった。
その弊害はデジタル化の面だけに留まらず、出版をビジネスとしてマネジメントするという発想や、商売なら当たり前のマーケティング概念の取り入れも遅れる要因になった」
と語るのは、中堅出版社で管理職を務める筆者のかつての同僚である。
幸い、と言っていいのか分からないが、今日ではもはやアナログへの郷愁を抱えて仕事をするゆとりなど微塵もなくなり、誰もが自己革新を余儀なくされている。
「仕事は脚で稼ぐ!」みたいなノリで生きてきた営業のオッサンたちが、知らないうちにSNSで販促とか言っている……そんな時代がようやくやってきたわけだ。
他業種から見れば時遅しとなるかもしれないが、ITこそ生き残りの鍵であるとの信念を持ち、ベテラン勢も一体となった出版界のDX推進がおこなわれることを願ってやまない。
(2)デジタル化によって利益を損なう人々の存在
産業革命の時代からある「機械に職を奪われる!」というヒトとしての危機感というよりは、アナログ技術を生業とするスタッフや業者からのプレッシャー。これもまた、無視できないほど大きかった。
自分が現役時代、真っ先に無用の長物となったものとして写植屋がある。DTP*1に移行後、テキストの流し込みはデータ上でやればよく、毎月数十万(さらに昔はもっとかかった)も写植に金をかける必要性は理屈上消えたはずだった。
ところがオーナー社長の天の声で、あそこの会社も大変だから仕事を回してやれということになる。なかなかデジタル移行しない外注スタッフも、ベテラン勢から「ずっとウチの仕事を受けてくれた人だから」という声が出て、バッサリとは切れなかった。
また、さまざまなデータから雑誌の適正部数は明らかなのに、営業が取次*2の人から「今月売上少ないんだよね」などと酒の席で相談され、いきなり部数をバカ乗せしてきたなんてこともあった。
当然、余分に刷った分は返本となり、責任を負うのは編集長である自分。
合理性よりウェットな人間関係と浪花節が優先されるのかと、当時はそれなりに憤慨したものだ。
「そういう風潮が長く続いたせいで、いまでも数百ページの紙ゲラに写植屋の担当でないと読めないクセ字で書き込んで何度もやり取りする編集者や、データはあるのに全く分析をしない事務方がいるが、完全にオワコン。
また、人や取引先を切れず合理化が進まないのは、感性主導で仕事をしてきたのが大きい。
それを許しているのは、本を読む人が絶滅危惧種化し、現代人の可処分時間*3で『本を読む』という選択肢が限りなく小さくなっていることを理解していないせい」
こう話すのは前出の元同僚。要は「もっと危機感を持て」ということだろうが、できることならば追い込まれてようやく重い腰を上げるのではなく、デジタル化は一歩、いや半歩でも先を見て動きたいものだ。
(3)読者の利益に叶うDX意識の欠如
これは反省でもあるのだが、出版業界で働いていた頃のことを思い返してつくづく感じるのは、IT技術によるメリットを読者にもたらす意識が希薄だったということだ。
テクノロジーの進歩により編集実務は無駄が減り、かつて10人でやっていた作業を2〜3人、会社によっては1人でやるようにすらなった。では、それによって浮いたお金やマンパワーはどこにいったのかというと、少なくとも読者には還元されていない。
出版社の懐事情の関係上、雑誌・書籍の値段は下がるどころか部数と売上減を埋めるために上がる一方だ。せめて内容がよくなっていればまだマシとはいえ、実際にはむしろ逆。
とりわけ雑誌やムック本は、ネットで拾える程度の情報しか載っていない媒体がザラにある。
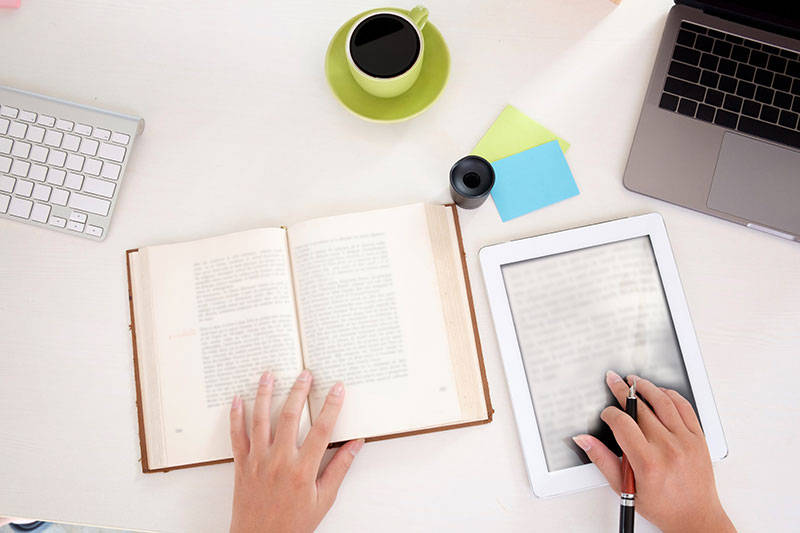
そもそも出版社がDXを進める上で、読者に利便性をもたらすという目的意識がどれくらい共有されているかというと、極めて疑問。電子書籍は紙やインク、配本、在庫管理に至るまで、あらゆる面でコストが削減できるはずなのに、「どういうわけか」紙の本と大して値段が変わらない。
電子書籍の市場規模はここ数年、毎年2〜3割程度の伸びを見せている*4とはいえ、前出のデザイナー氏の言葉を借りれば「オブジェとしての本という需要なのか、それともモノの所有欲なのか、日本では紙が予想よりも残っている」。
加えて言えば、手にとって読む本でないと内容が頭に入らないという方もいれば、本に書き込みを入れながら読書をするタイプの人だっているだろう。はたまた現在の電子書籍のシステムでは他人に貸せず、読み終わっても古本屋に持っていけないという問題も確かにある。
だが、情報を伝えるという行為の中で、印刷、製本、流通、そして実店舗での販売という煩雑な過程をより必要としているのは、読者ではなく作り手側。電子書籍が主流となれば存在意義を失う書店や取次は言うまでもなく、現状においては出版社もできれば紙のほうを買って欲しい(と考えているようにしか見えない)。
ゆえにコミックはやや事情が違うにしても、電子書籍は紙版の補助的な位置づけとなり、そうなるように値付けされる。
個人的な意見を言えば、読者は作り手の都合を押し付けられているのであり、そのことに怒っていいとさえ思うのだ。ただ、前向きに考えるならば、雑誌のサブスク化やオーディオブックの興隆など、昔では考えられなかった変化もまた起きつつある。
人間、一度便利なものに触れてしまえば、ノスタルジーを愛する人など例外を除けば基本、元には戻れない。IT導入の過程では、思わぬ混乱や反発を招くことは確かにある。
だが、それが本当に有用であるのなら、いつかきっと誰もが受け入れるものとなるーー。それこそが長年の編集業経験を通じ、自分が得た啓示である。
繰り返すが、これがあくまで筆者の「信仰」。
自分よりデジタルに通じているであろう本サイト読者の皆さまに、己の考えを押し付けるつもりは毛頭ない。ただ、DXを本気で推し進める上で、小難しい理屈を並べるだけではやはり上手くいかないこともある。頭の固いオヤジ上司や保守的なクライアントなどといった手強い相手にぶつかった時、信念はきっと貴方の力となる。
強い思いは、必ずや現実世界を動かす。
根拠はないが、自分はそう固く信じている。
≫ 【導入事例やサービス紹介も】さくらインターネット お役立ち資料ダウンロードページ
*1:
公益社団法人日本印刷技術協会「DTPは印刷を変えた(1)- 印刷100年の変革」
いまはかつてほどの力はないが、筆者が現役だった2020〜2010年代後半は事実上、雑誌部数や新規ムック本企画などの決定権を握っており、カミサマ的存在だった。

執筆
御堂筋あかり
スポーツ新聞記者、出版社勤務を経て現在は中国にて編集・ライターおよび翻訳業を営む。趣味は中国の戦跡巡り。
※『さくマガ』に掲載の記事内容・情報は執筆時点のものです。
- SHARE


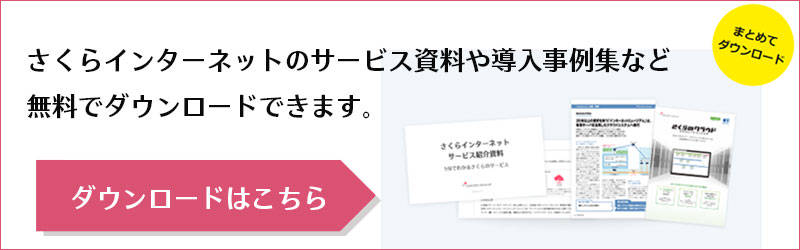
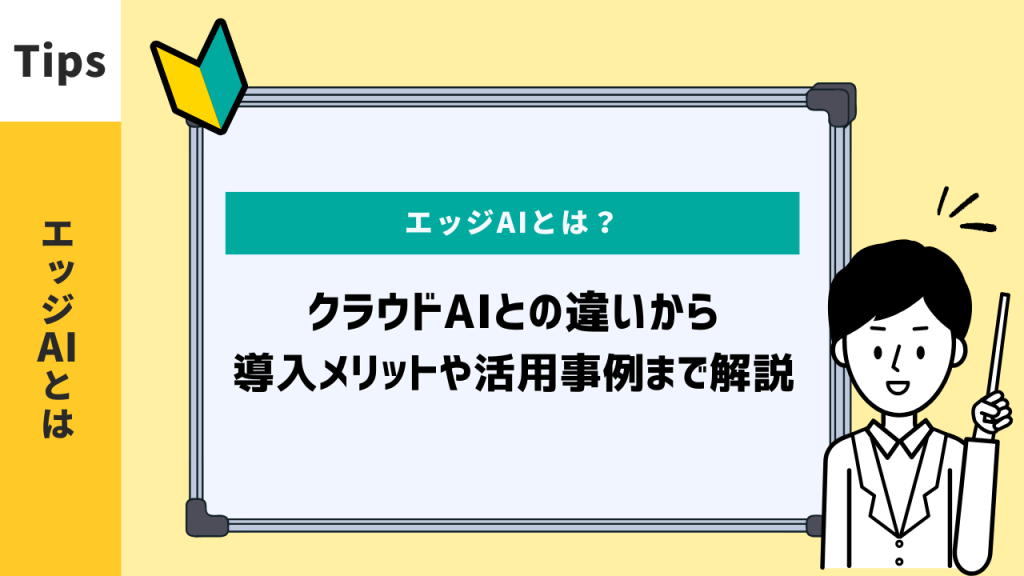 New
New

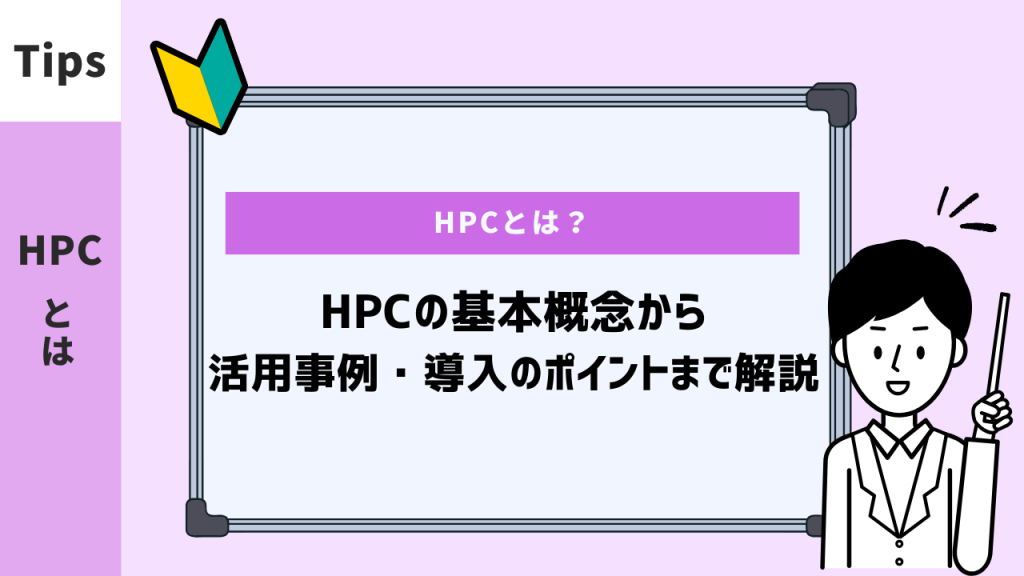
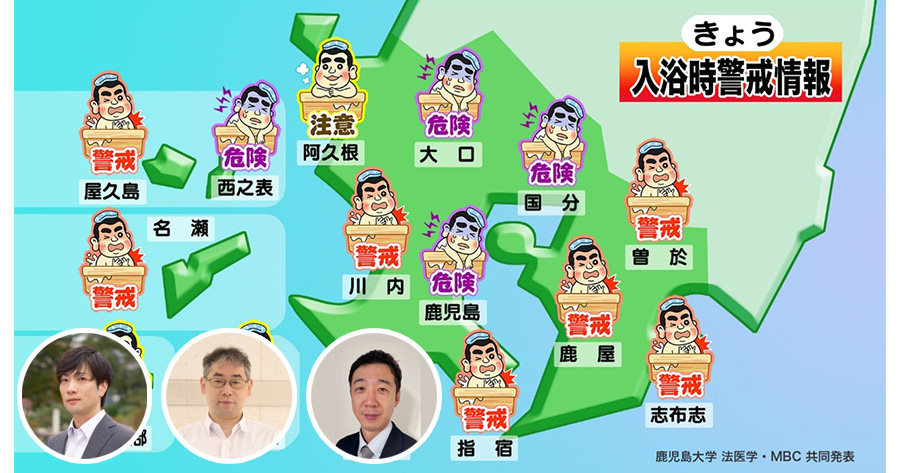

 特集
特集




