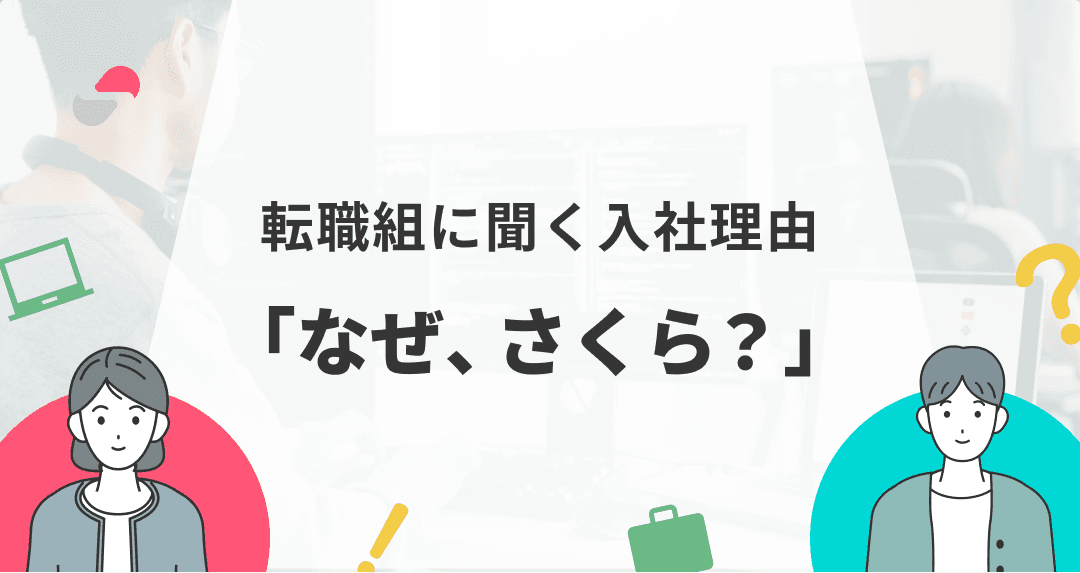2021年8月31日に経済産業省から「DXレポート」の最新版、「DXレポート2.1」が公表されました。筆者はこの公表を心待ちにしていました。
なぜなら一つ手前、去年12月に公表された「DXレポート2」では、”前回のレポートのメッセージが正しく伝わらなかった”と経済産業省自らの反省とも取れる記載があったからです。
今回こそ、的確に伝えてくれるのではないか。
興味深くレポートを読んでみました。しかし、今回もまたイマイチな発信になってしまうのではないか…と筆者は早くも心配しています。
「DXレポート2.1」とは
DXレポートとは、日本企業の「デジタルトランスフォーメーション(DX)」の進捗状況に危機感を持った経済産業省が2018年に公開したものです。
そこでは「2025年の崖問題」が指摘され、この言葉自体は話題になりました。
コロナ禍の2020年12月に、経済産業省は「DXレポート2(中間取りまとめ)」を公表しています。その中に、このような記述があります。
先般のDX レポートによるメッセージは正しく伝わっておらず、「DX=レガシーシステム刷新」、あるいは、現時点で競争優位性が確保できていればこれ以上のDXは不要である、等の本質ではない解釈が是となっていたとも言える。
(引用:経済産業省「DXレポート2(中間取りまとめ)」)
その理由にはさまざまなものがあるのでしょうが、そもそも「DX」という言葉の正しい意味が伝わっていないのだから仕方のないことです。
そして今年8月末に公表されたのが「DXレポート2.1」です。「2.1」というからには、「DXレポート2」の追補版です。
確かに一部の内容について補足的な部分はあるものの、レポートそのものは現場から少し遠ざかってしまったのではないかと、筆者としては心配してしまう節があるのです。
「DXレポート2.1」で強調されていること

「DXレポート2.1」には、「2025年の崖」のような強い言葉はありません。よって、最初に公表された「DXレポート」に比べれば少し地味な存在になってしまっていますが、大切なことが指摘されていますので、その点はご紹介したいと思います。
最大の論点は、システムやソフトを提供する「ベンダー企業」とそれを利用する「ユーザー企業」との間に存在する垣根の問題です。
DX実現のためには、両者がしっかりと手を組むことが必要です。ビジネスモデルや、デジタルを利用した新たな価値をどこに認めるかは、「ユーザー企業」ごとに異なります。むしろ多様化していく必要性があるでしょう。
よって、システムやソフトを提供する「ベンダー企業」は、システムの一方的な提供、あるいは単なる御用聞きにならないよう、「ユーザー企業」の変革に密に伴走していく必要性がある、というのが「DXレポート2.1」の大きな指摘のひとつです。
しかし、今度は「ベンダー企業」にこのようなジレンマが生まれるといいます。
- 受託型ビジネスを現業とするベンダー企業が、ユーザー企業のデジタル変革を伴走・支援する企業へと変革しようとすると、内製化への移行により、受託型ビジネスと比べて売上規模が縮小する
- ベンダー企業がユーザー企業をデジタル企業へ移行する支援を行うことにより、最終的には自分たちが不要になってしまう
(引用:経済産業省「DXレポート2.1(概要)」経済産業省)
現代の技術やビジネス変革のスピードについていくには、両者の垣根を取り払い、「ベンダー企業」は「ユーザー企業」をデジタル企業へと導いていかなければDXは成功しません。
しかしDXが「ユーザー企業」に浸透していくと、今度は自分たちでシステムを作ってしまう。つまり「ユーザー企業」がシステムを内製できるようになっていってしまいます。そうなると、「ベンダー企業」としてお金を稼いできた会社は困ってしまいます。
「ベンダー企業」としては自分たちの首を絞めてしまう道を歩むことになる。そこに大きなジレンマがあると指摘しています。
「DXレポート2.1」に物申したい

上記のような主張はもっともであり、多くの日本企業に欠けているものだと筆者も思います。ただ、「DXレポート2.1」が、その必要性をきちんと伝えられる読み物であるのかという点に筆者は首をかしげているのです。
例えば、DXの目指す姿としては、
つまり、DX の終着点における企業の姿とは、価値創出の全体にデジタルケイパビリティを活用し、デジタルケイパビリティを介して他社・顧客とつながり、エコシステムを形成している姿と考えられる。
(引用:経済産業省「DXレポート2.1」)
「ユーザー企業」と「ベンダー企業」の関係については、
(DXレポート2では)ユーザー企業とベンダー企業は「相互依存関係」にあるため、一足飛びでは変革を進めることが難しいことも示した。また、企業がラン・ザ・ビジネスからバリューアップへ軸足を移し、アジャイル型の開発等によって事業環境の変化への即応を追求すると、その結果として、ユーザー企業とベンダー企業の垣根がなくなっていくという究極的な産業の姿が実現されるとの方向性を示した。
(引用:経済産業省「DXレポート2.1」)
「ベンダー企業」が抱えるジレンマを解消するには、
こうしたジレンマを打破して DX を進めるためには、企業経営者のビジョンとコミットメントが必要不可欠である。一方で、ベンダー企業が取り組んできた IT 技術やシステム開発の能力は、最新技術がコモディティ化されたとしても、これからのデジタル産業において継続的に必要なものである。
(引用:経済産業省「DXレポート2.1」)
とあるのですが、いかがでしょうか。企業規模にかかわらずDXが必要というわけですが、これじゃあ何を言っているのかわからない、とは思いませんか?
イチャモンかよ、と思われるかもしれませんが、これは割と重要なことではないかと筆者は考えています。
DXとは経営そのものの変革でもあります。経営者の関与や決断なくして成り立たちません。しかし、まず「DX」という言葉の意味すら浸透していない状況の中、本当に危機を乗り越えるには、中小・小規模事業の経営者にも分かるような説明をしていかなければ、のれんに腕押し状態です。
実際、それが最初のDXレポートの公表後に起きたことです。「DXレポート」なるものの存在を知らない経営者も多いことでしょう。
何らかの方法で正しく経営者に伝えていかなければならないのですが、これではレポートと経営者の間にある垣根が大きくなるだけなのではないかなあ、と筆者は感じるのです。
「自分語」で会話する人たち
さて、文句ばかりを言っているわけにもいかないので、「DXレポート2.1」の内容についてはまたの機会にご紹介したいと思いますが、「自分語」でしか話をできない人に筆者は時々出会います。
いわゆる「業界言葉」、あるいは自分が使う「スラング」は、どんな相手にも通じると思い込んでしまっている人たちです。あとは過剰なカタカナ語の羅列で、短くて済むはずの話を長くしてしまう人です。
特にカタカナ語はやっかいです。時々、自分でもその意味を理解していないのに使っている人がいたりするからです。
最近ではマスコミでも、発表文に載っている言葉をそのまま転載しているだけで、読者には意味が分からないまま、というのも散見されます。
自分がそうならないよう、襟を正さねばとも思いました。
外来語ばかり輸入せずに、日本で生まれたビジネス用語が世界に広がるくらいになってほしいなあ、とはかない思いを抱きつつ……。


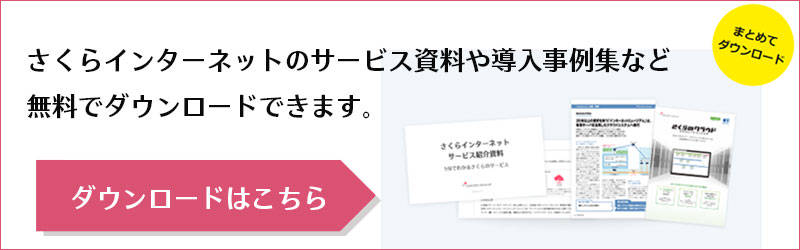

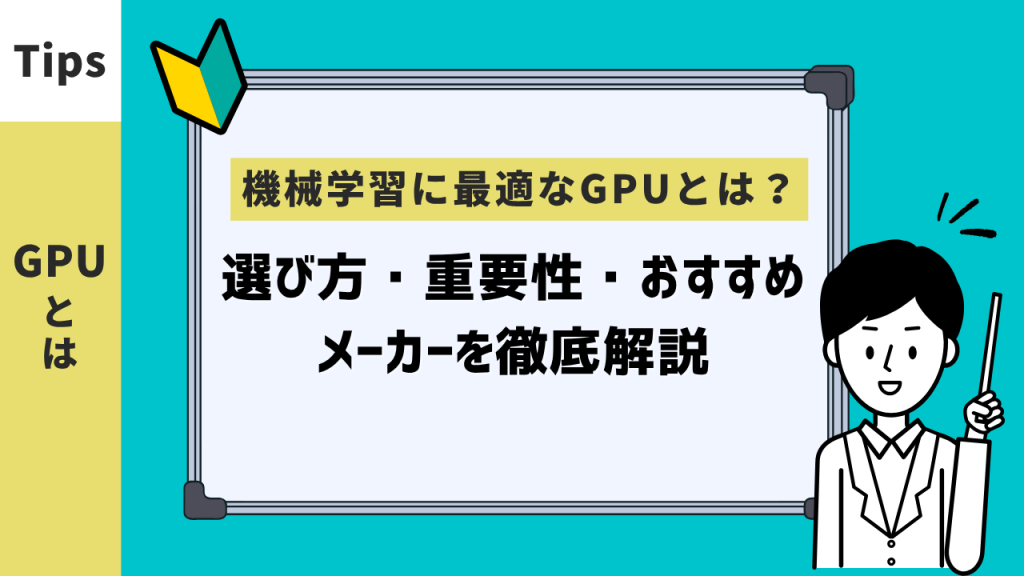 New
New




 特集
特集