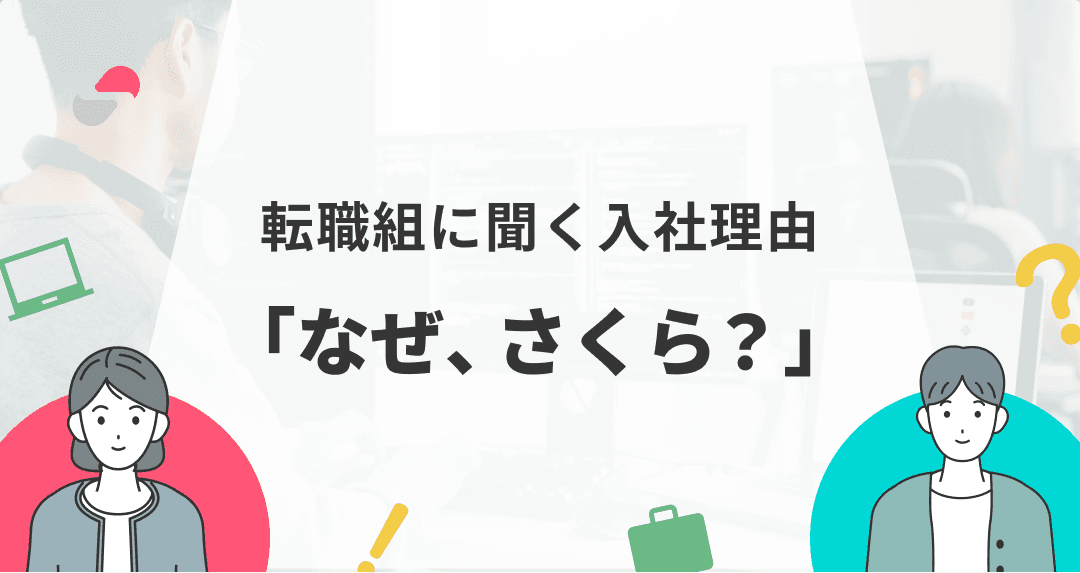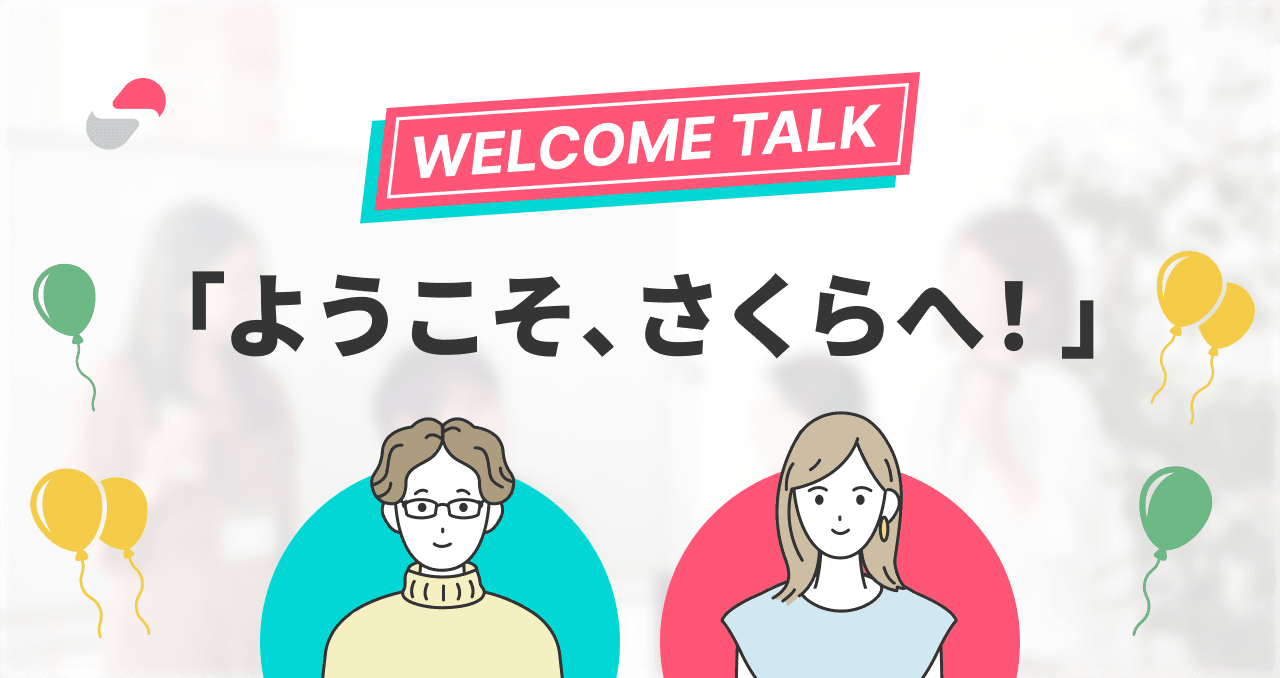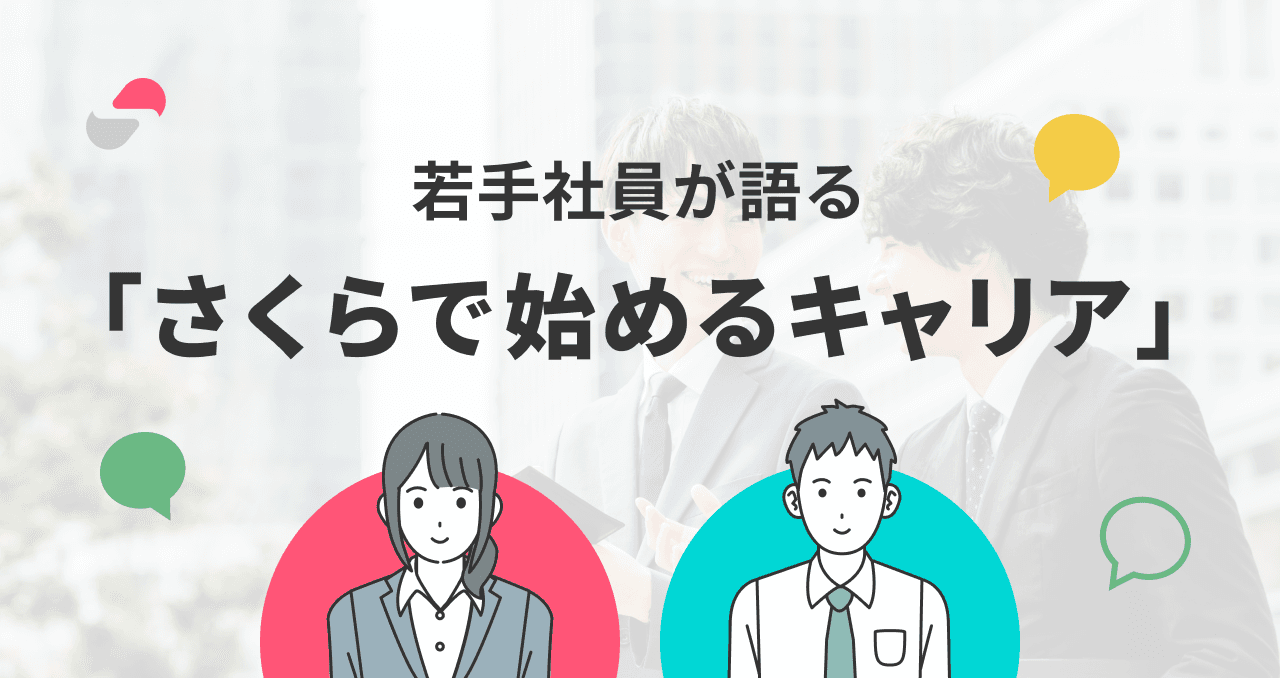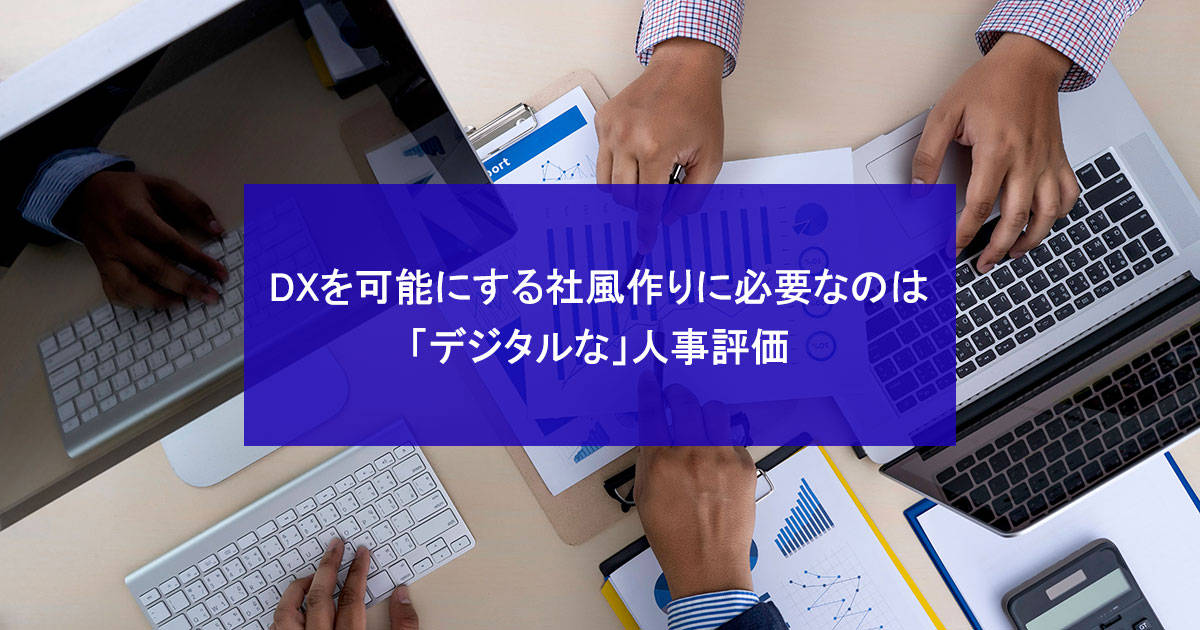
DXはいきなりIT化だと思っていませんか?
DX(デジタルトランスフォーメーション)といえばIT化、給与計算から社内会議まですべてをネットで管理すればいいんでしょ? くらいの理解を、私はしていた。DXがブームになってから、紙の契約書はオンライン署名になり、確認作業は印刷された紙面から画面越しとなった。
大手企業でも目まぐるしい変化が起きていたことから、私はてっきり「ITツールを導入すれば、DXなのだ」と思いこんでいたわけだ。
ところが、DXに苦戦している会社の話を聞くと「IT以前」の課題が大きいと気づいた。オンライン会議システムの画面で”上座”に自分がいないと言い出す上司や、あいまいすぎる評価基準しかない会社など、そもそもIT化できない仕事が多すぎたのだ。
結局、DXを進めるには前提としてDX可能な会社を作る必要がある。そのために外資系企業から人材が引き抜かれ、社風作りから手を入れるケースも増えてきた。
DXを可能にする社風作り

では「DXを可能にする社風」とはなにか。答えのひとつに、「実践可能なビジョン」の存在がある。ビジョンとは、会社がなにを目的としているか言葉に表したものだ。あなたも、企業のコーポレートサイトで「○○な未来へ」といったビジョンを目にしたことがあるだろう。
そして、こう思ったのではないか。「ふわふわした単語だけど、実現したいと思ってないんじゃないかな」と。実際、大手企業ですらビジョンは実現への明確なステップを欠いたものが多い。ひどいケースだと、人事部が独断でビジョンを策定し、他部署の社員はビジョンすら知らないことがある。
本来、ビジョンとは「人事評価のベース」になるものだ。ビジョンに沿っているとはすなわち会社がよしとする方針に従っていることであり、それが出世の条件になるべきだからである。
これまで、さまざまな企業のビジョンについてヒアリングしてきたが、社員はビジョンがそのまま出世要件につながっていると考えていなかった。なにより、「いま偉い人間」が、ビジョンに沿わない行動をしているケースも多くあった。
たとえば、「日本をDX先進国にする」的なことビジョンに掲げる企業のお偉いさんが、チャットシステムはおろかメールもろくに使えないなんてケースがあった。こういう事例を見てしまうと、社員は「なにがDXだ」と思ってしまう。そして、全社員がビジョンを蔑ろにしだす。
DXを可能にするならば、まずは「機械的に判断できるほど、クリアな出世要件」を決めなくてはいけない。そのためには、出世要件や人事評価をデジタル化する必要がある。その結果、こういった「なぜこの肩書かは分からないけれど、偉い人」を減らしていくこともDXに含まれる。
だから、DXを進めるためには社長判断が必須となる。社長が「これまで厚遇してきた人にも厳しくしていく」と腹を決めなければ、DXはスタートラインにすら立てないのである。私は数々の企業をヒアリングし、DXに必要なものは、予算より勇気だと痛感した。
DXを可能にするビジョンと実践

では、ビジョンを策定したのち、いかにしてDXを達成すればいいか。ここでAmazonの事例を紹介したい。Amazonの企業理念は「地球上で最もお客様を大切にする企業であること」だ。これだけなら、似たことを掲げる企業はいくらでもある。また、このビジョンだけでは要件が甘すぎて「どうすれば達成できたと言えるか」が分からない。
だが、Amazonが素晴らしいのはこのビジョンを具体的な人事評価へ落とし込んでいるプロセスである。Amazonは「地球上で最もお客様を大切にする企業」であるために、どういう社員であればそれを実現できるかを考え尽くした。そして、Amazonのビジョンに紐付いた、OLP(Our Leadership Principles)という人事評価基準が生まれた。
OLPには「リーダーシップ」「常に学ぶ」「倹約精神」など業務で活かしやすい評価基準が書かれている。これを実行していれば評価され、無視すれば出世に響く。だから社員はビジョンを意識し、OLPに従って働く。
さらに、採用基準もOLPに従って生まれる。5回を超える面接では、エントリーした人がOLPに沿った人材と言えるかを根掘り葉掘り聞いていく。そして合致した人間しか採用しない。その徹底した採用基準が、Amazon社員の質を担保している。
DXを可能にする「デジタルな」人事評価

日本企業でもOLPのようなものを作っているところは多いが「たやすく、どの現場でも実現できる」ポリシーであることを無視した基準が多い。言葉の意味がふわふわしすぎており、人事評価のタイミングで使えないのである。
こうしてふわふわの評価基準を採用すると、人は適当に人事評価を始める。そして結局、上司のお気に入り社員が出世する構造に戻ってしまう。
あるいは「労働時間」や「社外と接点を持った回数」のような、極端に数字で計測可能な指標を持ち出すケースも多々見られる。そうすると、従来の残業ばかりする社員が評価されてしまったり、営業先と飲んでばかりの社員が「よく取引先との接点を持っている」と高評価になったりする。実際には、飲んでばかりで契約率が低い社員かもしれないのに、である。
だから、DXを実現するためには最初に「ビジョンを実現するための評価基準」を作らねばならない。そして、評価基準へ取り組めば必然的にビジョンが達成されると社員が信じられるほど、ビジョンとの一貫性も求められる。
さらに、ビジョンに沿わない人間はたとえ幹部でも人事評価は厳しくしなければならない。そうしなければ、ビジョンはただの飾りとなるからだ。これが伝統的な企業では最も難しいことかもしれない。だからこそ、DXにおいてはトップダウンの大鉈を振るう必要があるのだ。
DXで評価基準を正しいKPIへ落とし込む
ここまでできたら、次に採用基準を「正しいKPI(数値目標)」へ落とし込む。正しくないKPIとは、先述の通り残業時間など、ビジョンに直結しない数値目標だ。やればやるほど会社のビジョン達成に近づくKPIでなければ、設定する意味がない。
ここで、架空のビジョンをもとに評価基準とKPIを作ってみた。正しいKPIを設定するうえで、参考になればと思う。
<ビジョンに紐づくKPIの落とし込み方>
仮にビジョンが「すべては消費者のために」だったとすると……
ビジョンに基づく採用・人事評価基準は以下のようなものが作れる
責任感ある行動
消費者へ最高の商品を届けるためには、社員に最後までやりとげる責任感が必要だから
KPIの例:最後まで終えられたプロジェクトの割合
コストパフォーマンスの追求
限られた予算で最良のものを消費者へ届けたいから
KPIの例:自社広告の費用対効果130%以上
……といったように、ビジョンからKPIへ一気通貫のシステムを策定するのがコツである。かつ、KPIは達成可能でありながら、やや背伸びしたものが望ましい。あまりに高すぎる、あるいはサボっても達成できるほど低い目標は、社員のやる気を削ぐからである。やりがいは、「達成が難しく、しかし不可能ではない」数字から生まれる。
デジタルツールを導入するタイミング

ここまで社内の評価基準を「人が決める」ものから「ビジョンに沿って決まる」ものへ変えられたら、ようやくデジタルツールを導入していい頃合いだろう。社内のやり方がハッキリ決まるまでは、ツールをむやみに導入しないほうがいい。各社員の主義主張で、要件がコロコロ変わってしまうからである。
DXに苦戦する企業には、早々にツールを導入した企業も多い。だが、それでは「早すぎる」こともあるのだ。まず、社内はDXに適した環境になっているだろうか。デジタルに切り分ける必要があるのは、まずしがらみと縁故に囚われた社内環境かもしれない。




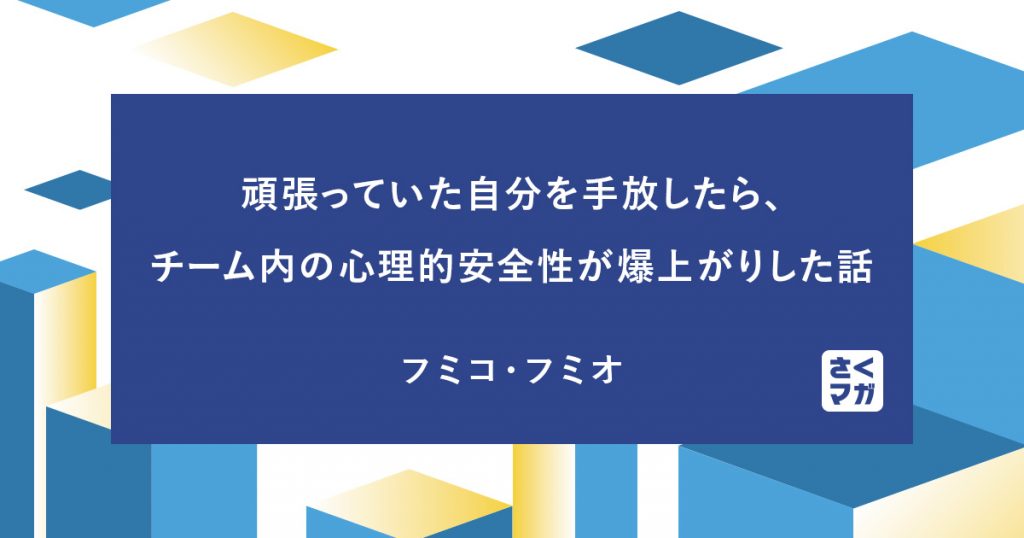

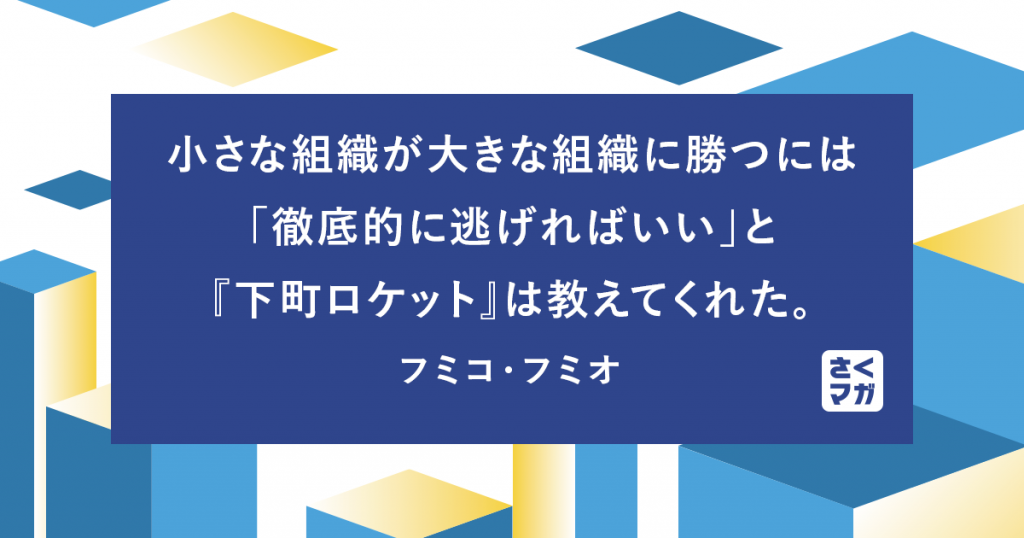
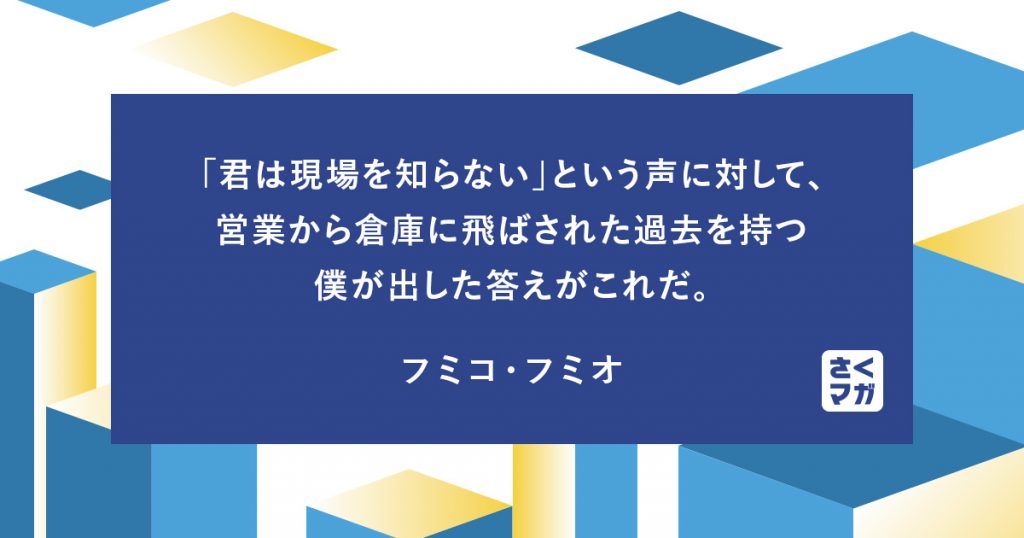
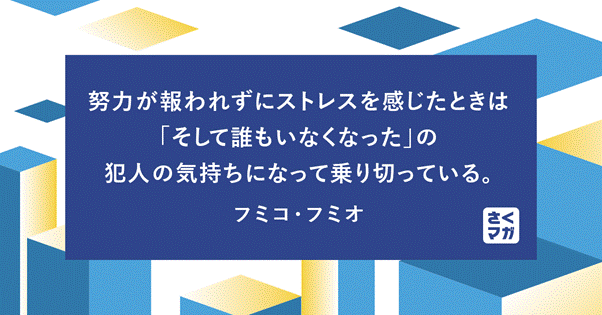
 特集
特集