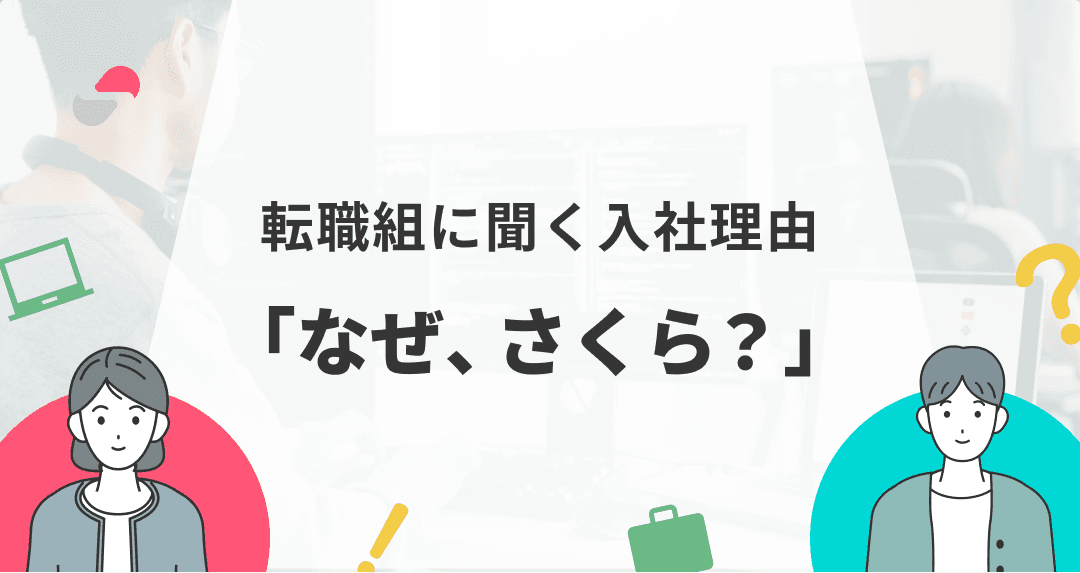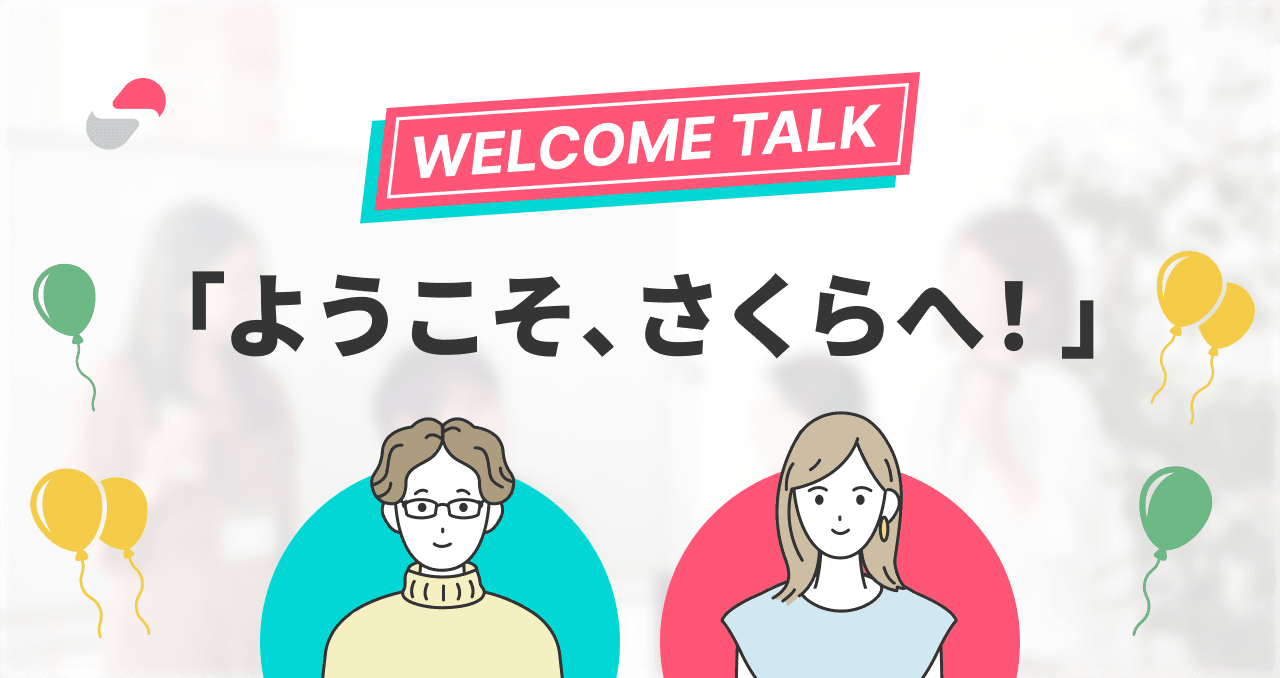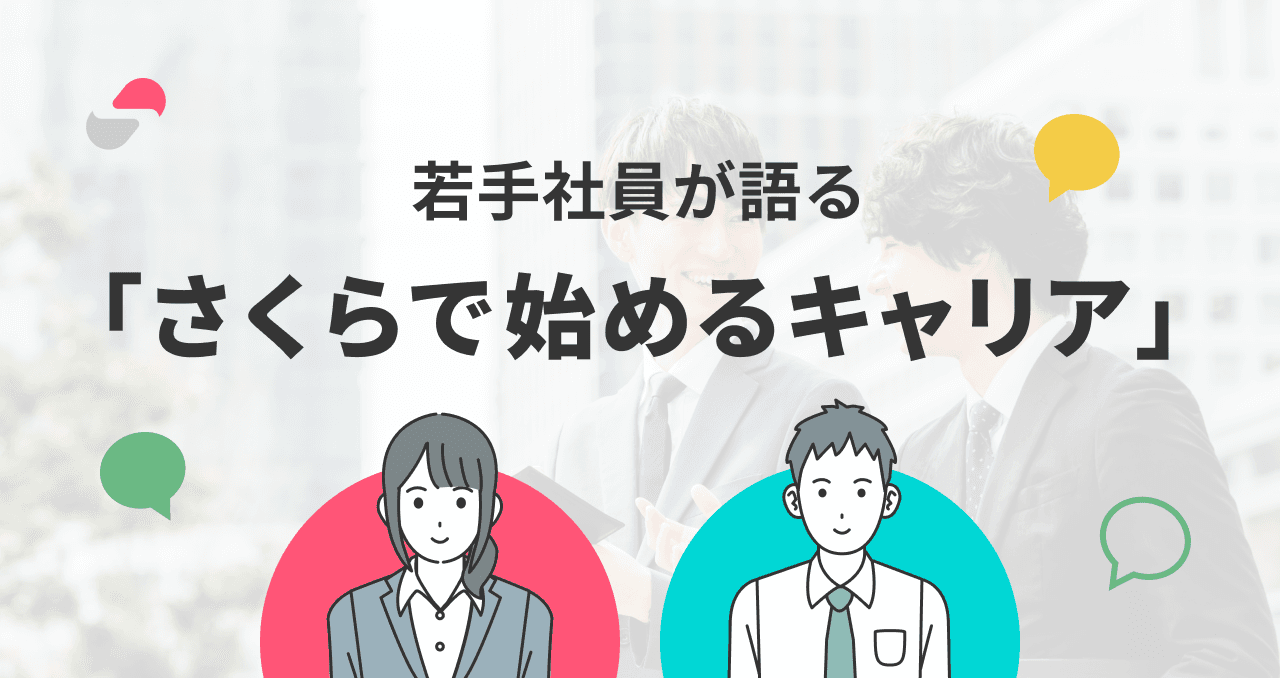あの日みた猫の名前を僕たちはまだ知らない

その猫の名前を知らなかった。
全身まっ黒な大人の猫で、くりくりと丸い黄色の目が特徴だった。妙に落ち着き払っていて、がっついておらず、毛並みだって艶々していたから、おそらくどこかの家で飼われていたのだろう。
日の落ちた公園で東屋に座り、ただ暗い空を見つめるなんでもない時間を過ごしていると、その猫がやってきて「ニャー」と鳴いてみせたのだ。
当時、中学生だった僕は“結果を見る”というものを異常に恐れていた。とにかく恐れていたのだ。ここで注意すべきは、”結果”が怖いわけではない。あくまで”結果を見る”という行為が怖くて嫌いなのだ。
例えば、何らかの合否を知らせるメールが来ていたとする。そこで合否の結果が怖いのではなく、あくまで“結果を見る”行為が嫌で怖く、メールを開けないのだ。
僕は徹底して“結果を見る”ことが嫌いだ。ドラマや映画などの創作物で、主人公が裏切られそうな不穏な感じがしてきたとする。
そうなると、裏切られ、傷つき、落ち込む主人公を鑑賞するという“結果を見る”行為が予想できてしまう。僕はそれがかなり心理的な負担になるので、そう思った瞬間に鑑賞できなくなってしまうのだ。別に裏切られる展開が嫌いというわけではない。あくまでも結果を見ることをしたくないのだ。
全てがこの調子で、幼いころからずっと“結果を見る”行為を避けて生き続けてきたように思う。徹底的に避けたという自信がある。
そんな僕の前に避けては通れない“結果”が立ちはだかった。将来の進路や高校受験は、やはり人生を決めてしまうレベルの結果イベントだと思えたし、なんとなく、避けては通れないのだろうと感じていた。これらのイベントでは“結果を見る”ことを強いられるのだろう、避けられない、と思った。
それでも僕は反抗して見せた。中学生という時期もあって思春期や反抗期ともあいまったのだと思う。親や社会に反抗して見せたのだ。この反抗こそが“結果を見る”行為を避けるものだった。
反抗といっても、普通なら親や社会に敵対して、夜の校舎窓ガラス壊して周ったかもしれないが、そんな度胸はなかった。夜の校舎はまあまあ怖いし、けっこうちゃんと戸締りされている。
普通なら家を飛び出して夜遊び、そのうち悪い仲間に誘われてどんどんと悪事に手を染めていったりするのだろうが、まあまあの田舎町でコンビニすらなかったので、そもそも夜遊びができなかった。
結果として、何かに反抗したくて夜に家を飛び出したのだけど、何もすることがないので公園の東屋(あずまや)にいる、というなんとも意味不明なことを繰り返していた。今でもたまに思う、あの当時の僕は本当に何を考えていたのだろうと。
手元には、実力テストの結果が印刷された紙があった。裏返されたこの紙をめくれば“結果を見る”ことになる。テストの点数に、順位、偏差値、ご丁寧に科目ごとに網羅された“結果を見る”ことは重荷でしかなかった。この先も何度もこういったことを繰り返すと思うと背筋に冷たいものが走った。
そのテスト用紙を紙飛行機にして飛ばす。それは反抗だった。まるでありきたりなJ-POPの歌詞のような場面だ。結果を乗せた飛行機は、スーッと音もなく暗闇へと消えていった。
「にゃー」
猫の鳴き声が聞こえた。視線を移すと、暗闇の中に漆黒の猫が東屋の脇のところに佇んでいた。その猫は近づいても逃げる様子がなく、それどころかゴロゴロと喉を鳴らしながらさらに近づいてきた。
「おまえ、名前は?」
訊ねてみたが、当然のことながら返事はない。名前のわからない猫はゴロゴロと喉をならしながらこちらに腹を見せ、コンクリートに背中を擦りつけていた。
「腹減ってんのかな。明日なんか持ってきてやろう」
なんとなくだけど、僕自身は明日も何かに反抗してこの場所に来ていて、この猫もこの場所に来るような気がした。本当になんとなくそう思ったのだ。
次の日も、日が落ちてから家を抜け出して公園に行くと、やはりそこには黒猫がいた。まるで待っていたかのように椅子の上に佇んでいて、ニャーと鳴いてみせた。僕は冷蔵庫から盗んできたソーセージを手土産にまた返事のない会話を楽しんだ。
「猫って高校受験とかないんだろ?」
「いや、でも猫の世界の高校みたいなものがあるのかもしれない」
「猫だって将来のことが漠然と不安になるかもしれないし」
「おれさ、結果を見たくないんだよ。わかんねえか、この感じ」
もちろん、返事が返ってくるわけではない。猫はムシャムシャとソーセージを食べている。よほど美味しかったのか、鳴き声を上げながら食べているので、ムンニャムンニャみたいな鳴き声になっていた。
猫との会話には“結果”がなかった。こちらが何を言っても答えは返ってこない。その結果が待ち受けない世界がなんとも心地良かった。
思えば、親との会話も、友人との会話も、教師との会話も、進路の選択もテストも、結果を見ることの連続だった。
こう言えば喜ぶだろう、こう言えば怒られないだろう、こう言えばいいんだろう、そんな意図をもって発言し、その結果が返ってくる。あの言い方はまずかったな、嫌われたかも、みたいに結果に思い悩む。人との関わり合いは思惑と結果が連綿と重なり合うようなものだった。いつも結果を見なくてはならなかった。それはちょっと僕にはきつかった。
だから、結果のない会話がなんとも心地よかったのだろう、名前も知らない猫とのソーセージを介した結果のない関係、これはしばらく続いた。不思議なことに、猫はいつ公園に行ってもそこにいたし、呼びかけると茂みの中から出てきた。

ある日のことだった。その日は結果が押し寄せてきた。
志望校の合格判定みたいな用紙が返却されてきたし、いい加減に第一希望を決めろと教師に怒られた。希望調査書はあいかわらず白紙だ。それを埋めると結果を見る必要があって怖かった。家に帰ると、ついにバレてしまったらしく、いつも夜中に抜け出してどこに行っているんだと怒られるし、ついでに夜な夜なソーセージを盗んでいることも咎められた。
ついでに紙飛行機にして飛ばしたテスト用紙は近所の婆さんが拾って届けてくれたらしく、そこでもまた怒られた。行動に対する結果が怒涛のように押し寄せ、それを見る必要があった。耐えられなかった。
すぐにでも公園に行きたかった。あの結果のない場所に行きたかった。結果のない猫に会いたかった。けれども、あまりに怒られたものだから、夜に抜け出すわけにもいかず、3日ほど行けない日が続いた。
それでも、なんだか義務のように感じていた僕は、4日目の夜にソーセージを盗み出し、寝静まった家をゆっくりと抜け出して公園に向かった。
「おい、きたぞ」
ソーセージを剥き身にし、いつものように茂みに話しかける。けれども、そこに猫の姿はなかった。公園内を徘徊し、あらゆる場所で呼びかけてみるが、その気配すら感じられなかった。
3日も空けてしまったのだ。もう来ないと思ってどこか別の場所に行ってしまったのだろうか。仲良くしていた猫がいなくなったという“結果”が僕に重くのしかかった。
「帰ろう」
また抜け出したことがばれたら大事になる。またスパイのように窓から侵入して、痕跡を消して、などと考えながら公園を出ると、そこに衝撃的な光景が待っていた。
この公園は、我が家から大きな幹線道路を隔てた場所にある。田舎町でありながらこの幹線道路だけは潤沢に整備されており、交通量もかなり多かった。昼間はひっきりなしに大型トラックが通る場所だ。ただ、もう夜も遅い時間で車通りはなく、昼間の騒音が嘘みたいに静まり返っていた。道路を照らす街灯と、点滅信号がアスファルトを照らしていた。
その幹線道路の歩道を歩く。特に理由もなく、ふと幹線道路の中央に視線を移した。
黒い塊があった。
車線の真ん中に黒い塊が横たわっていた。それは猫の死体のようでもあった。なんだか経験したことないくらいに心がざわついたのを覚えている。
「見たくない!」
とっさの判断で視線を逸らす。そして、問題の黒い塊がなるべく視界に入らないようにして移動し、脇道へと入った。呼吸を整える。
「もしかしてあの猫だったんじゃないだろうか。あの猫が轢かれてあそこに横たわっていたのではないだろうか」
そんな考えがグルグルと頭の中を回った。家に帰って布団に入ってもずっとあの黒い塊のことを考えていた。
「3日間、僕が行かなかったから僕を探して道路を渡ったんじゃないだろうか」
そう考えると、さらに心臓の鼓動が早くなるのを感じた。
見に行かなくてはならない。そう考えたが、同時にそれは無理なことだともわかっていた。黒い塊があの猫であるか、その“結果を見る”という行為はたぶん僕には無理だ。怖いんだ。
僕はずっと結果を見ることを避けてきたのだ。ここ一番の大切な場面で逃げ出す。その繰り返しだった。僕は臆病なのだ。卑怯なのだ。ダメなやつなのだ。結果を見ないこと、それはただ現実から逃げているだけだ。僕が見ようが見まいが結果はそこに結果として歴然と存在する。それを見ないことに本質的な意味はない。ただ逃げているだけだ。
「変わらなきゃ」
そう思った。あの猫を思い出す。結果を見ないことはあの猫と過ごした時間をも否定するような気がしたのだ。
布団から飛び出し、玄関へと向かう。悪いことに、トイレに起きてきた父親と鉢合わせてしまった。
「なんだ、また抜け出すのか?」
夜な夜な抜け出していることを咎められたばかりだったので、皮肉を込めてそう言われた。まさかもう抜け出していてもう1回、抜け出すつもりだなんて言えなかった。
「抜け出すのと違う。大切なものがそこにあるんだ。それを確認する必要がある。ちょっと外に行きたい」
そんなことを言ったと思う。とにかく、ここで確認しないと、僕はもう一生ダメになると思ったのだ。たぶん、ずっと逃げ続ける。だから確認しなくてはならない。その熱意をいろいろと語ったような気がする。
「そんなに言うなら一緒に行ってやる」
熱意が通じたのか、一緒に行くことを条件に家を出ることを承諾してくれた。外に出ると、また少しだけ夜が深まっていた。
父親と一緒に幹線道路へと向かう。
幹線道路は相変わらず静まり返っていた。黒い塊があった場所まで歩く間も一台も車は通らなかった。
「何があるっていうんだ」
父親は不思議そうに言った。
「大切なものがある。そう、今後の人生を左右するほどの大切なものだ」
僕はもう半ば覚悟していた。たぶん、あれはあの猫だ。亡骸だ。僕を探して道路を渡り、轢かれたのだろう。そこには悲しい結果が待っている。けれども、もう恐れない。僕は見届ける。向き合わなければならない。そして僕を励ましてくれた彼を弔ってあげるのだ。名前を知らない彼を。
「あそこ」
数十メートル先に黒い塊が見える。相変わらずピクリとも動かない。父親は何かを察したのか押し黙ってしまった。
「あれを確認しにきた」
そう言い残し、もう一度、車が来ないことを確認して黒い塊に駆け寄る。辛かったな。痛かったな。もう大丈夫だよ。俺、恐れていた。臆病だった。お前のおかげだよ。もう大丈夫。恐れない。だからせめて安らかに眠れる場所に埋めるから。黒い塊をそっと手に取った。
モモヒキだった。
ベローンと人の下半身の形をした黒い布がクシャクシャになって落ちているだけだった。
「それが大切なもの……」
父親が呟いた。
「そう、大切なもの。人生を左右するほど」
引っ込みがつかなくなった僕はそう呟いた。ベローンとなったモモヒキがなんとも哀愁漂う感じだった。
「これシゲって書いてあるな。あそこの角の爺さんのだわ。明日にでも届けてやろう」
タグにはサインペンで名前が書かれており、父親がすぐに持ち主を特定した。シゲさんは何をどうやって幹線道路のど真ん中にモモヒキを落とす事態になったのだろうか。
それから、あの猫に会うことはなかった。けれども、臆病な僕に大きな影響を残してくれたように思う。勇気を出して確認したからこそ、あれが死体ではなくモモヒキだと分かったのだ。
結果は常にそこにある。それを確認しようが確認しまいが、結果は変わらない。だから、確認することにそう意味はない。けれども、確認するからこそ、次の行動に繋がり、次の結果が変わるのかもしれないのだ。恐れていてはいけない。名前を知らないあの猫は、そんなことを教えてくれた。
「おれさ、〇〇を受験しようと思うわ」
「ええんじゃない」
モモヒキを手に家へと帰る幹線道路で父親とそんな会話をした。
さいごに
人間関係においても、ビジネスの世界でも、多くの“結果を見る”という行為が伴う。この世は結果が折り重なった世界だ。そしてその結果の多くは残酷で悲しく、届かないものだ。喜ばしい結果は相対的にそう多くはない。結果とは往々にして残酷なものなのだ。だから、“結果を見る”ことは怖い。
僕は、いまだに結果を見ることが苦手だ。原稿を送った後の編集部からの返信も開けないことがある。「ボツ」とか「死ね」とか書かれてそうで怖いのだ。できればサブジェクトを「最高でした!」にしておいてくれると開きやすいのでそれでお願いします。
ただ、そうやって結果を見ることを怖がるたびに、あの猫のことを思い出す。僕に少しの勇気を与えてくれたあの猫を想い、僕は結果を見るのだ。
あの日見た猫の名前を僕たちはまだ知らない。ただ、あの日、モモヒキを落とした角の爺さんの名前は知っている。モモヒキに「シゲ」と」書いてあったからだ。


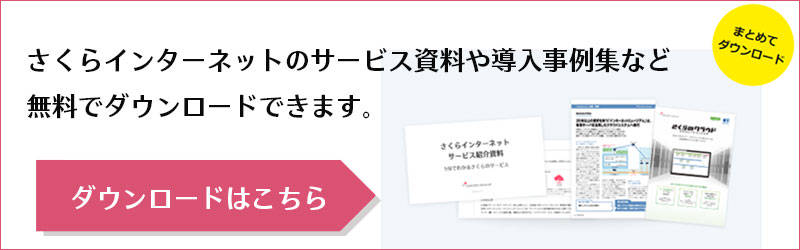


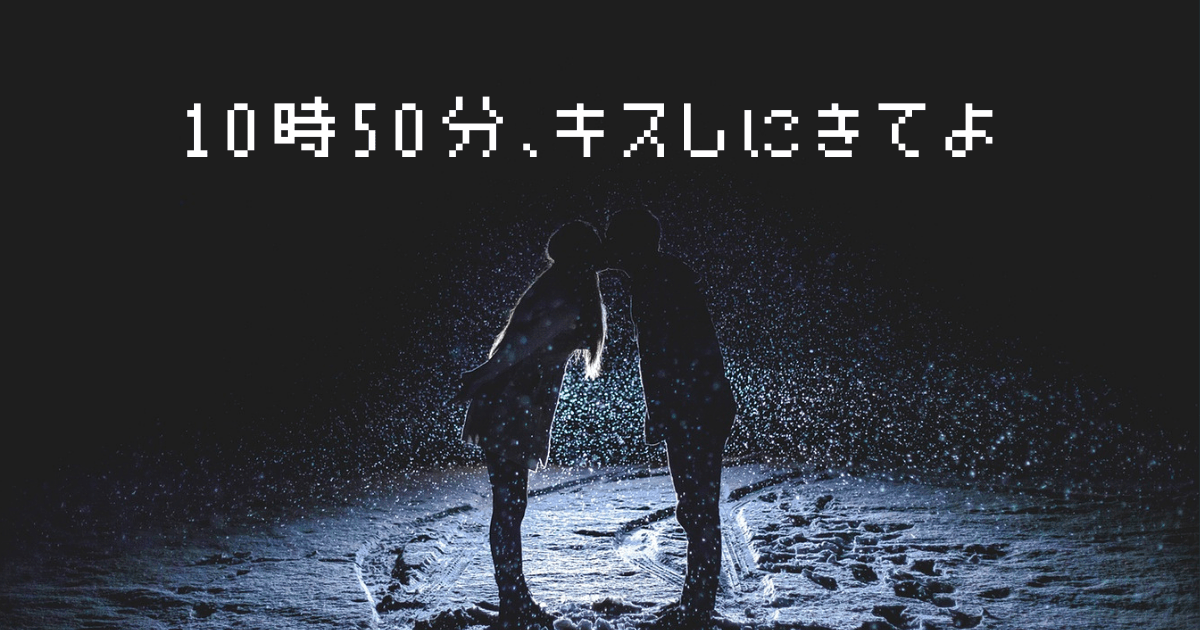

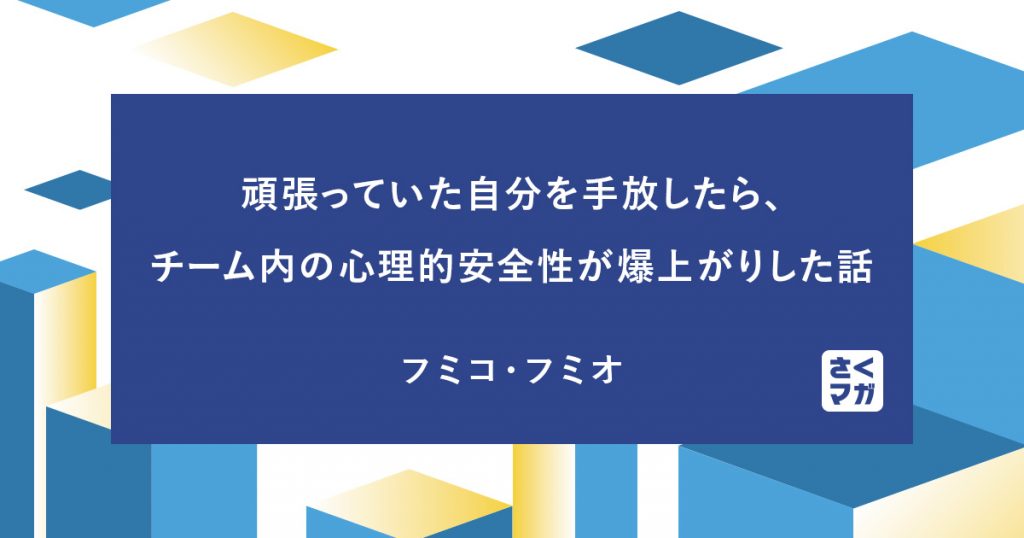

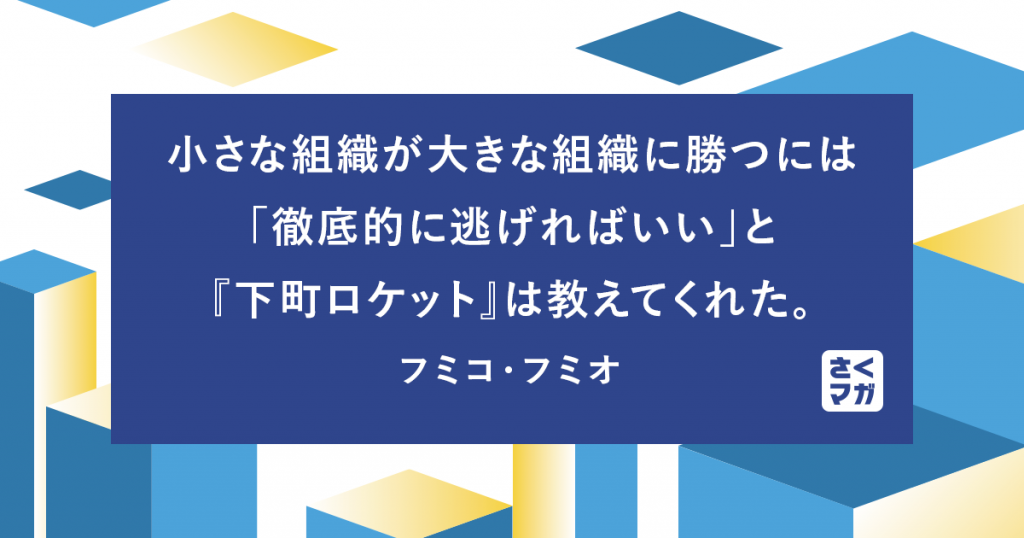
 特集
特集