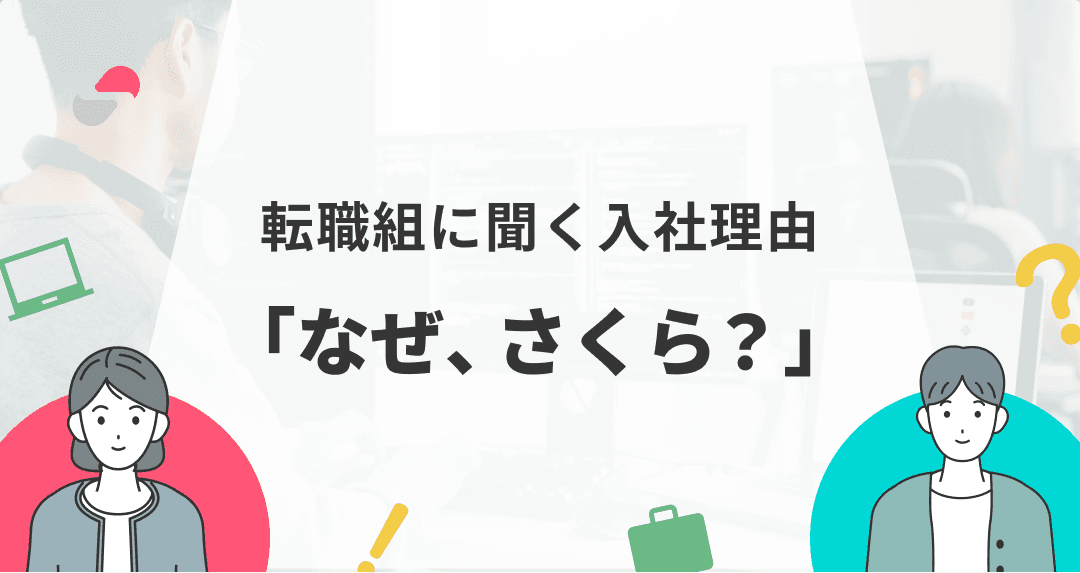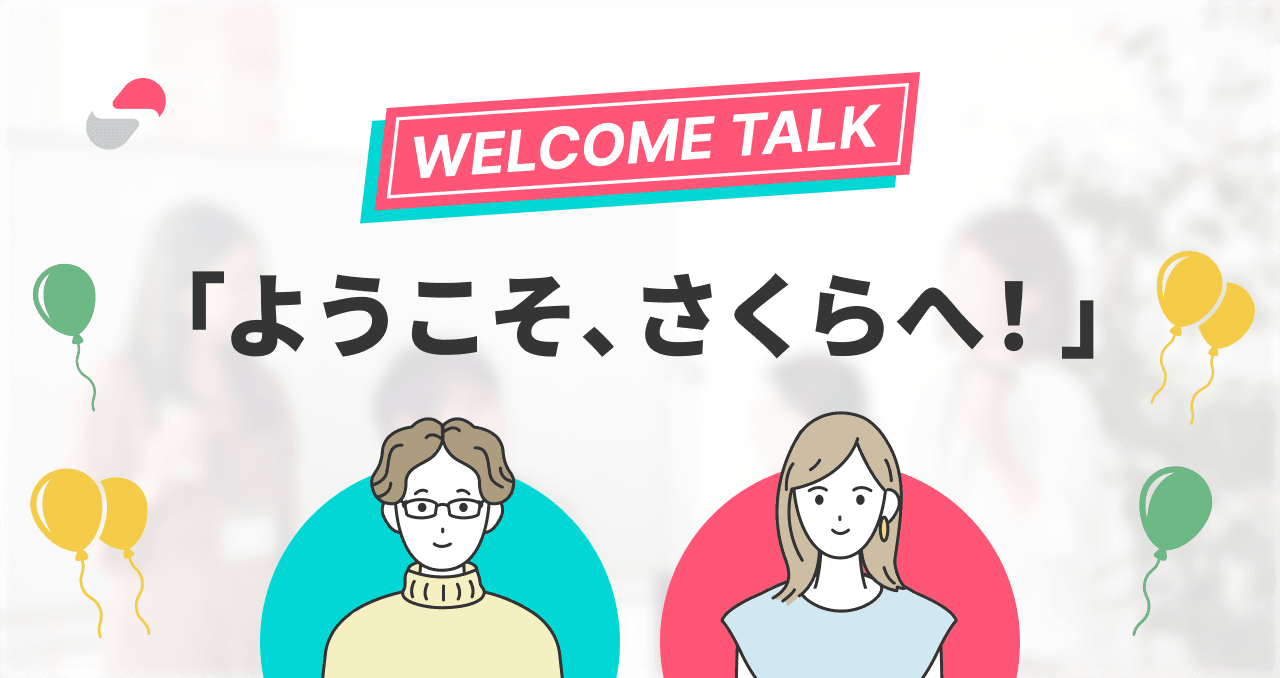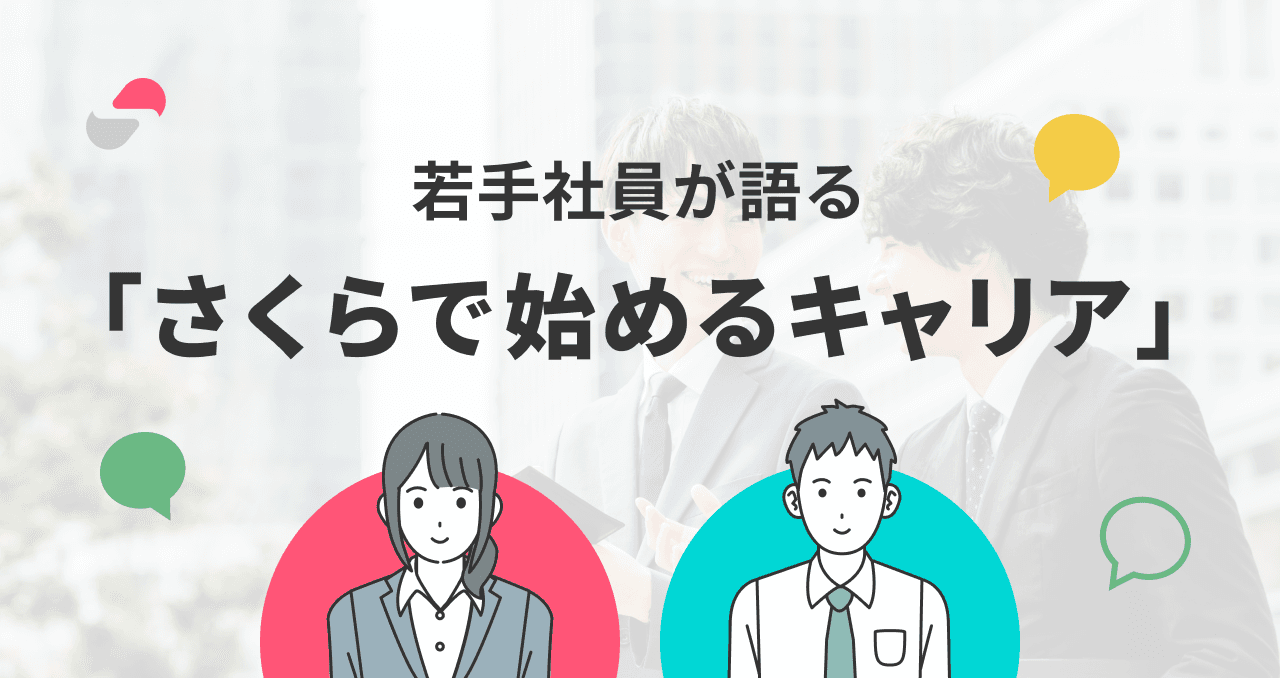日本サッカー界の転機の一つとなった1997年11月16日、1998年フランスワールドカップ出場をかけたアジア第3代表決定戦がマレーシア・ジョホールバルで開催された。日本は延長後半、岡野雅行のゴールデンゴール(Vゴール)でイランを3-2と破ってワールドカップ初出場を果たす。
その延長戦に入るとき、サッカー放送でも一つの壁が破られた。突き抜けたのはNHKアナウンサーの山本浩氏。そのときの時代背景はどうだったのか、そしてどんなブレイクスルーがおこなわれたのか、本人に語ってもらった。
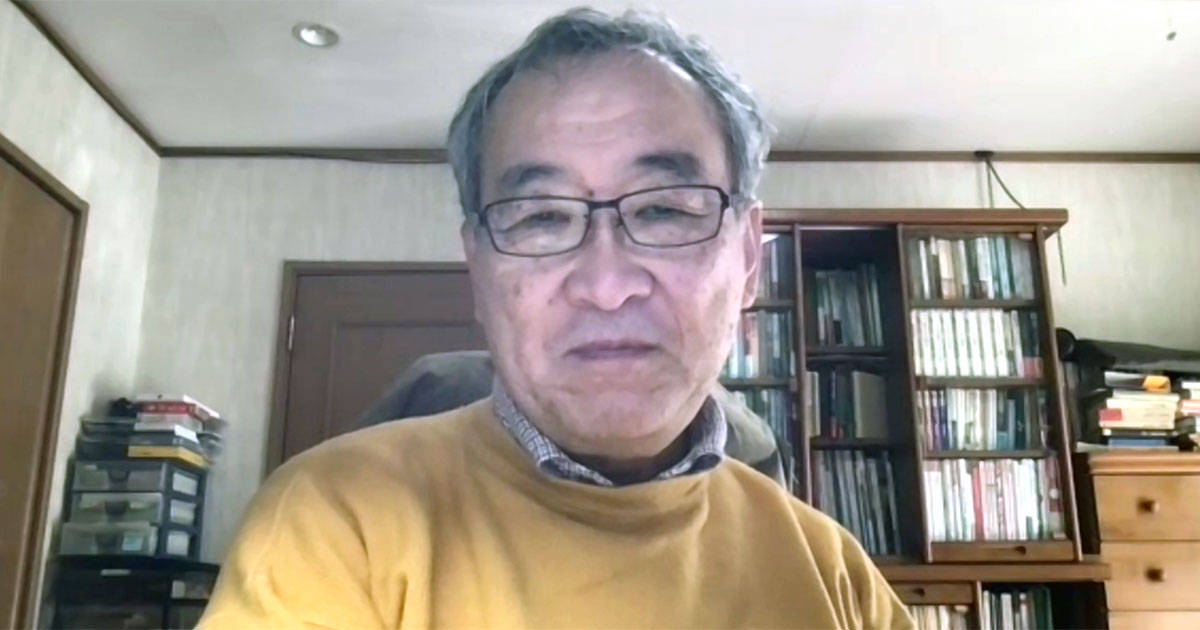
山本浩氏が語るジョホールバル
アジア第3代表決定戦がジョホールバルで開催されると聞いて、最初はあんまりありがたくないなって思っていたんですよ。
東南アジアで試合をすると、環境面で言ったらそれほどよくないですよね。いつもそう言われていましたし、選手たちに話を聞くと、例えばピッチの状態が日本と違うとか、役員が用意してくれているはずの練習場に行ったら鍵がかかっていて使えないとか、いろんなことが起こる。当時の日本は予定通りに動いて当たり前という感覚でやっていましたからね。
アレンジメントがうまくできていないと、作為があったのか無作為なのか分かりませんけれども、何か悪いことされているんじゃないかって、そういう気持になったこともありました。そういうところに対して非常にピュアだったもんですから、動揺が高じて。
例えば予選で東南アジアの試合になると、強いはずの日本代表がいきなり全然勝てないとか、そういう歴史的背景がたくさんありましたからね。それに関する話も、そのときに同行した人たちからちょっと聞いていましたんで。
あれは確か、西アジアでやるのか、それとも東南アジア、あるいは東アジアでやるのかという政治的な駆け引きがあったはずです。
日本はどちらかと言うと「政治的な駆け引きをするのはあざといことだ」と言ってやらないという、長い間のそういう方針もあったでしょうし、政治的な駆け引きが得意でない人がサッカーの現場に多かったところもあったと思うんです。
それがジョホールバルを境にして段々と日本のサッカーがある意味の、世界基準じゃないですけど、アジア基準になってきたと思います。
日本の国民性
当時の日本は放送に関しても、例えばあの当時日本国内では「サドンデス」という言葉がよくないから変えていこうと、「Vゴール」へ。
そして最終的には「ゴールデンゴール」っていうことになりましたけど、非常に神経質でいろんなことに気を配る、そういう国民性が表に出ていました。一方でイランのほうは、いかにしたら相手がひれ伏す状態に持っていけるかということを考えていて、ずいぶん役者としては違ったと思うんですよね。
幼子から少年になったばかりの日本と、長いこと大人をやっているイランとの違いみたいなものが、なんとなくあったんじゃないかという気がするんですよ。その意味で言ったら、ああいう大きな勝負を経験して日本も成長していったんでしょう。そういう過程でしたね。
ちょうどその4年前の「ドーハの悲劇」のときには、プロになった後のある種の浮かれた状態で戦って、体調もコンディションもよくないし、戦い方もよく分からないみたいなところがあった。それがその4年間で、周りがいろいろやっぱり大人になってきていたと思うんです。
「ずっと負ける試合しか放送してきていなかった」
私はずっと負ける試合しか放送してきていなかったんです。世界に出る経験をしていないわけですよ。大事な試合をやっても負けて帰ってくるっていう。昔から応援していた多くのサポーターの方もそうだったと思いますね。
だからジョホールバルのときも、どこかに「本当にフランスに行けるのか?」みたいなところがあって、勝って叫んだ後もよく分かっていないような感じでした。浮ついたフワフワした感じですよね。おそらくワールドカップの経験国だったらあんなにフワフワしていないと思うんですけどね。
放送というのはそのときの世論とか社会の熱にすごく影響を受けるんですよ。放送だけが熱くなって、社会が冷静でいると「あんな放送して」と後ろ指刺されてしまうわけです。分かりやすい例が、大差の試合になり始めたときにゴールを絶叫しても、みなさん白けて見てますよね。
けれど世論が熱いときは、その放送がどんなに熱くてもだいたいその温度に対してみなさん共感してくれるんですよ。ジョホールバルのときには4年前の出来事を記憶しているもんですから、本大会に何としても行くんだって非常に高い温度の状態が誰にもキープされていたわけですね。
ですから我々が熱に浮かれたようになっていても、視聴者のみなさんもソワソワしてるもんですから、その意味では世の中、社会と、放送あるいはメディアとの間の温度差があまりなかったと思うんです。みなさんの温度が高いぶん、我々がそれより高くても、そんなに離反されないというんですか、みなさんが背後からもう1回押してくれるような状況だったんですよね。
選手とメディアと視聴者を三位一体に
そんな心理状態で延長に入るときに「このピッチの上、円陣を組んで、今、散った日本代表は私たちにとっては『彼ら』ではありません。これは『私たち』そのものです」と口走ったんです。
これは後から名台詞と言ってくださる方もいましたけれど、でもあのころ「ナショナルナショナリズムを煽るために言っているんじゃないか」と、社会学者の間では、厳しい見方をする人もありましてね。
「日本をまとめよう」とするっていうんでしょうか、「日の丸中心主義」みたいに取る方も多分あったと思うんです。社会学系の先生の中でスポーツナショナリズムを専門にされている方には、そういう分析もありうると思いましたので、丁寧な説明をしたこともありました。
また「メディアが第三者的に放送するという壁を越えて、選手とメディアと視聴者を三位一体にした」というご意見もありました。それについてはそのとおりですね。
テレビ埼玉から始まった放送の変化
NHKという放送局は日本代表の試合だけじゃなくていろんな試合を放送しますから、スタンダードとして「AチームとBチームを横に置いて喋ってくれ」というのがすごく強いんですよ。「日本代表と他の国との試合になっても応援をするな」というのは長いこと言われてきたんです。
その応援放送をスポーツの中で正面切ってされたのは、テレビ埼玉が昔放送した西武ライオンズ戦ですね。「西武を応援する」って堂々と、多分社の方針としてされたと思うんです。そのあたりからじゃないかって気がします。
それまで会社の方針として、例えば日本テレビが読売ジャイアンツを応援放送するという形はなかったと思います。と言うのは、ジャイアンツの放送は日本全国の方に楽しんでもらっていたソフトです。当時の放送にはそういう商品価値がありましたよね。
どの地域の人が見ても不満が残らないように、ある程度ジャイアンツと対戦するチームと平等に扱おうとしていたわけですね。そう放送することでメディアの「野球放送」という商品をちゃんと買ってもらえるという感じだったと思うんです。
テレビ埼玉はその地理的な条件から、当然ライオンズは大事な地元球団だったわけですから、応援放送が出来たんです。つまりテレビ埼玉の特殊性は、北海道や九州ではその放送を見られないという前提ですね。それがまた地元の人たちにとっては大変心地のよいものだったわけですよ。「オラが放送局」みたいな感じです。
世間の寛容度が高くなった
この「オラが放送局」に感じてもらえるのは放送業者にとって大変ありがたいことなんです。放送エリアの中にいるプロチーム(球団)が、放送エリアの中の住民に応援されることでかけがえのない存在になる。地域のスポンサーを大切にする地元の放送局としてみれば、みんなで一緒に戦っている感覚でしょう。
それは、誰も彼もに受ける番組作りみたいな感じとはまた違うわけです。その意味で言うとテレビ埼玉はかなりの英断をしたと思います。
ライオンズを応援したのは、その地域とそのテレビ局との関係が背景にあってのことでした。ですがこれが時代を変えて、方向を変える、ベクトルを動かすのに大変大きな役割を果たしたんです。
そういうところに、たまたま日本代表も世界の中に割って入る、とにかく弱い日本代表が段々と大きくなっていくときに、「日本代表はオレたちのもの」という感覚でみなさん許してくれるようになるわけですね。
ですからその点から言うと、私がこういう放送をやっても、多分大きな批判は起こらなかった。それは世間的にある種の寛容度の高い状態が始まっていたんじゃないかという気もするんです。
そしてあの場に散っていた選手たち一人ひとりの個性を、たくさんの日本のファンの方がもうご存知だった。すごくよく分かっておられた。だから逆に言うと、放送がしやすかったという感じがあるんです。説明しなくていいことが多いんですよ。

ジョホールバルとドーハの違い
説明をするときには言葉が平板になって、どちらかと言うと硬い言葉や数字が増えたり、同じような表現にもなったりするのですが、誰もが多分もう分かっているとからと説明を省いて奔放にやれる、大胆に絵を描いてもよかったんです。筆を大胆に回すと言うんでしょうかね。
そうでないともう少しデッサンをしっかりやって、細かなところまで気を使ったタッチで絵を描かなきゃいけないんですけど、「岡野雅行」って言えばもうみなさんだいたい何を期待していいのか分かっている。
すごい勢いで走るけどボールが必ずしもゴールに向かっていかないと思われているから、私も「岡野はこういうタイプの選手で、持ち味は、苦手なところは」なんて描写をしなくていいわけですね。そうすると何か一言発するだけで岡野という人がみなさんのところに飛んでいくぐらいの感じだと思うんですよ。ある意味でこれはドーハのときに比べるとやりやすい感じでした。
一方で、これで負けたら終わるという感じもありました。どこか心の奥底では「負けてはいけない」というのが非常に強かったと思うんです。ところが空港でサポーターのみなさんと言葉を交わしたときには、どちらかと言うと楽しい感じで来てるんですよね。
ドーハのときとはちょっと違うんです。ゆとりがあると言うんですか。そうしたところにいるみなさんのに、サッカーに対して経験と、それから自信と分析力を持っていると感じましたね。昨日今日のサポーターじゃない人たちだと思ったんです。
ドーハのころの日本サッカー
ドーハのころはまだ日本は教わるサッカーでした。日本サッカー協会がオフトさんに教えてくださいって言って頼んだ代表ですよ。でもその4年後には、今度は加茂周監督を更迭して岡田武史監督に代える。監督を代えてしまうという組織になっているんですから、その点で言っても、サッカー協会はもちろん、サッカーを取り囲む人たち、メディア、それから多分スポンサーも、もっと代表の中心点から近いところにみんなひしめいている、そういう状況だったんだろうと思いますね。
日本サッカーのスタンダードの縮図、歴史がそこにあるような気がします。緩かったもの、ベタベタしたものがギューっと締まっていく過程、非常に大きな大事なトンネルって言うんでしょうかね、そこをくぐろうとしていたような気がします。
「横」から「縦」の放送に
日本代表の試合はNHKでも私だけじゃなく、いろいろな人間が放送して、そのたびに反省会をやるわけです。それに年に3、4回、解説者を含めて集まって、映像を見てああだこうだやります。
最初のころは、我々よりも20年先輩のアナウンサーの人たちが「あんまり日本を応援するんじゃないぞ」みたいなことを言ってるんです。けれど、だんだんそういう人たちが世代交代していなくなっていきます。
やがて、両チームを横に置いて放送するんじゃなくて、縦に見て放送することを是認する人たちが増えてくるわけですね。縦というのは一つのチームに対しての深さということです。日本イレブンの中に入って、その方向で放送するということで、攻めるときは「行く」、攻められているときは「来る」という感じですよ。
それまでは、攻めるときは右へ、守るときは左へというやり方だったわけです。なおかつボールを持っている側に主語を置きますから、相手チームが攻めてくると相手チームのことばかり話すわけですね。そして相手のチームのボールがシューティングレンジに入ったときに「ニッポン、危ない」と言ってるんですよ。
それが、「こんなに攻められているけれど、どうしたらいいんだ」という質問を続け様に出してもあたふたしなくていい、気が付かないうちにそんな時代が来ていたわけです。「イランのFWコダダド・アジジが来てる」「アジジをどう止めるか」と話を持っていくわけですから。
そうすると視聴者の見方も「どうやって止めるんだろう」という方向にちょっと重心が傾くわけです。そういう世の中の動きがあって、我々がプレーのさなかにそんな投げかけをしても反応は悪くない。
試合中に戦術的な話をしてもみなさんが受け止めてくれる、という流れのある時代だったと思うんですね。アナウンサーだけじゃなくてディレクターも、それから一緒にいる記者たちも、視点や関心の軸の方向を少し動かしていたんじゃないかと思うんですよね。
試合中、とっさに出た言葉
もしあの試合で日本代表が情けない戦いぶりをしたら、そうはならなかったでしょうね。あの戦いぶりだったらここまで言っても大丈夫っていう、多分そういう感じで自然に反射的にやっていると思うんです。計算しているんじゃなくて。
あのときの試合はもう何やっても押し切って勝とうという感じでしたよね。僕は後半、城彰二がイランのペナルティエリアで倒されたときに「もし痛くないんだったら早く立ってほしい」と言ってるんですよ。
倒れて時間を使ってる、そういう試合じゃないぞっていう想いなんですね。本人はすごく痛かったんだろうと想像するんですけどね。
「このピッチの上、円陣を組んで…」のあの言葉は延長の前に、何か知らないんですけど、自分の中でですね、「これ言わなきゃいかん」っていうのが出てきちゃったんです。
あのとき松木安太郎さんが解説されていて気合入ってるわけですよ。松木さんはああいう熱血的な解説をされる方ですからね。
目の前の選手が円陣を組んで、それから動き始める。試合再開までには時間がありましたからね、ほとばしるように話が長くなっていたんですが、聞いてるうちに、僕は「これは言わなきゃいかん」と。
他人事じゃないんだ。このピッチにいるのはオレじゃないか、みたいな。「これってオレの友達でサッカーの優秀なやつが、こいつらと一緒にしのぎを削って、オレの友達は負けていったけどそれで生き残ったのがここにいるんじゃないか」と。
つまり「オレたちのグループから勝ち上がってきた選手だから、全部オレと同じ血が流れているんじゃないか」ってこういうことを言わなきゃいかんという、どっかで後頭部を殴られるように感じたわけですよ。
松木さんが声を振り絞って話し続けているときに、そういうものが頭の中で醸造されたというか、醸成されたっていいますか。
それはそこに来るまで、例えばマレーシアの空港に降りたとき会った人たちがみんなすごく熱い人で、そういうものが何となく、記憶にしっかり残ってるわけじゃないですけど、多分どこか脳の中に残ってたんでしょうね。たくさんの人がこの一戦に自分の人生かけてる、みたいなね。
あの延長に入る前には、そういう何かが結晶となってムクムク出てきたって言うんですかね。多分そうだと思うんです。これはもう言わなきゃいかん、松木さんの話を断ち切ってでも言わなきゃいかんと。それで松木さんが話しているのを手で制するようにして発した言葉なんです。
全部出しきり、試合後には何も記憶に残らない
アナウンサーというのは自分の放送のことを人に聞いて回らないし、だいたい僕の場合は放送した自分の映像をほとんど見ないんですよ。なんか自分の言えなかったことが記憶に残っちゃって「これ失敗だったな」と思っちゃうから。
だから、どういうことを言ったかあまり覚えていないわけです。でもそのときに、そういうことを言わなきゃいかんと殴られたっていう記憶だけはあるわけです。自分で自分の頭を殴ったっていうね。
試合が終わった後っていうのは……何も記憶に残ってないんですよ。空白、色が抜けちゃってるって感じのフィルムですよね。
夜はずっと、翌日の朝方のリポートだとかラジオ用の原稿を書いたり、いろんなことをして猛然と働いていたはずですよ。FM放送も、それから当時のNHKの放送関連の雑誌の原稿とか、そういうものをダーッとやってるはずなんですけどね。
スポーツ系だけじゃなくて、いろいろな部門からも依頼がありましたので、今この時に全部出し切らんといかんぐらいの気持ちが、多分あらゆるメディアの人間にあったんじゃないかと思うんですよね。
気がついたら朝の5時ぐらいに松木さんと2人で、ホテルのピアノが置いてあるところにいて、ハイネケンの缶ビールがいっぱい置いてあったんです。
ダンボールの箱ごと3、4箱積んであったので、多分祝勝会用に買っていたんでしょうね。松木さんと2人でピアノの足にもたれかかって、足投げ出して缶ビールを話もそれほどせずに飲んだのは覚えてますよ。

即時描写が大事
私が話す言葉は、作家や文筆家のようにいろいろ考えながら自分の中で研ぎ澄ましたものを下ろしてくるのと違って、発作的ですからね。反射的に言ってるので、しかもほとんどが目の前の人や物の動きから言わされてるわけです。我々、ラジオの時代から「即時描写が大事だ」とずっと言われつづけてきたので。
なぜ即時描写が大事かというと、話がプレーに遅れると、見てる人、聞いてる人が、そのプレーの真性の楽しみ、本来の楽しみからずれてしまってサービスが低下するという考え方ですね。試合を目の前にしている君だけが先に楽しむのは、視聴者聴取者サービスとして許されないということ。それが一つ。
もう一つは、即時描写することによって、目の前でおこなわれてるスポーツが持つ素晴らしいリズムを伝えるためです。いいスポーツっていいリズムを持っているんですよ。そしていい戦いをしているチームって必ずいいリズムがあるんです。そのリズムを伝えるためにはもう即事描写しかないという考え方なんですね。
この即時描写をするためには「よく見ろ」と言われています。「よく見る」ということは自分の中にあるものを出すんじゃなくて、見たものを返す、そういうアクションですね。目の前に起こっていることで、その体の中に入ってきたものをそのまま言葉で返していくという仕事をしているんですよ。
用意したものは現場の温度と乖離する
言葉を迷うことはないです。表現しようとして迷うのはプレーが止まっているときですね。プレーが止まっているときには迷うんです。例えばシュートを打つときに「打つ」と言うのか「蹴る」と言うか迷うことはないわけですね。ポンと言っちゃう。
NHKは民放と違ってハーフタイムに、長時間の休みがありません。今でこそいろんなハイライトやドキュメンタリーみたいなものを作って出しますけれども、そういうことがまだ出来ない時代でした。だからそれだけの高い緊張感の中ではもう生で放送し通せという感じだったんですよ。
こっちもその緊張感を切らないで何か言えることをそばに置いておかないといけないんですけれど、そういう用意したものってほとんど駄目なんですよね。ああいうときに、あらかじめ用意したものでは勝負できないんです。用意したものは現場の温度と乖離してしまうんですよ。
あの延長に入るシーンはアウトオブプレーなんですけど、放送が続いていた私達にとってはずっとインプレーだったわけです。インプレーだったからこそ、「私に言え」と見えない何者かが指図してきたことをそのまま話した。それがあの言葉なんです。
その場で見たものに言葉をぶつけるだけ。あのときは後頭部を殴られるように「これを言え」っていう声が自分の中で聞こえたんで、あの言葉を言ったんですね。ただ、松木さんに少し遠慮してるもんですから、タイミングとしては円陣が解けた後、言っているはずなんです(笑)。
あれで円陣が解ける前に口にしていれば、いきなり「ここにいるのは私たちです」とだけ言っていたはずで、キックオフまでに時間ができてしまって却って説明くさくなっていたかも知れません。
マラドーナに言わされた名実況
1986年メキシコワールドカップの準々決勝、アルゼンチンvsイングランドで、ディエゴ・マラドーナ(故人)の5人抜きのときに「マラドーナ」と4回連続で名前を呼んでいるんですが、あのときはマラドーナに言わされてるわけですね。
もしアウトオブプレーでずっとマラドーナを繰り返していたら、うるさいだけでしょうもない話だと思うんですけど、インプレーのときにマラドーナに引っ張られて言っている分、見ている側には違和感がなかったんでしょう。
あのときラジオとテレビ合わせて160局ぐらいの放送局が来ていて、みんな同じようにマラドーナに引っ張られていたはずです。世界中みんなこの業界では即事描写がすごく大事だと分かっていますから。見てそれに反応するっていう行為だけなんですよ。そこに反応できない人はあの場に派遣されてはいないはずですからね。
アナウンサーの仕事
アナウンサーって、喋るのが仕事のように見られますが、本当はそれほど喋ってないはずなんです。元来は人に喋らせるのが仕事なんですよ。
経験を積んだ人となれば、自分が目立つことは考えませんし、そこばかりを重視するなんて人はまったくありません。私はJリーグの開幕当時40歳なんですけど、そのころからは「自分が表に出るようなことを第一にするな」と盛んに後輩に言っていたんです。
「お客さんは君の声を聞きたいんじゃないんだ。お客さんが見ているものに対して君はちょっと味付けをするだけ。そこにいる選手の味を知りたいのであって、君の味を知りたいんじゃないんだ」と。
もしアナウンサーが自分の味を出すとするならば、アウトオブプレーのときだけなんです。アウトオブプレーの話の作り方でアナウンサーの巧拙って決まってくるんですよ。一番分かりやすいのが相撲です。
相撲の勝負はだいたい数秒から10秒ぐらいですよね。その前には3分30秒を超える間があって、その時間をどう動かすかで相撲のアナウンサーの力量の違いが生まれます。
10秒はほとんど誰がやっても変わらないんですね。でも残りの2分50秒で上手い人と下手な人の差がはっきり出ます。本当に怖いですよ。
マラソンなんかも分かりやすいんですけど、例えば大集団がずっと一緒になって走ってると変化がなくて喋ることなくなってくるわけです。
そのときに過去のデータや、あるいはリポーターの話で「昨日こんなこと言っていました」みたいなもので繋いでるようでは、どうなのかなって感じですね。何をどう持ってくるか考えられていない。とにかく何か埋めなきゃいけないみたいに出していくという放送は、あまり商品価値が高くないわけです。
アナウンサーに瞬発力は必要だと思いますね。持続力も必要でしょうが、でもほとんどジョホールバルのときは松木さんが喋ってましたからね。
解説の方も興奮すると実況するんですよね。「ここだ!」とか言うわけで、それはそれでいいと思うんですけどね。
逆に言うと解説のしゃべる量が少ないとノっていない試合、あるいはノっていない放送という感じですからね。だから持っているものを出してもらえればと思います。
木村和司さんも、いいときは自分で「やった!」とか何とか言いますからね。そういうふうに持っていくのもアナウンサーの仕事の一つかと感じます。

山本浩の思い出に残る試合
私が喋った試合の中で、放送そのものがよかったと思うのは多分1999年1月1日、天皇杯決勝で横浜フリューゲルス(その後、横浜マリノスと合併し、現・横浜FM)が優勝した試合です。
気持ちが一番充実していた放送の一つですね。あとから見ると、その放送で私は「私たちは決して忘れないでしょう。横浜フリュ―ゲルスという、非常に強いチームがあったことを」と話したんです。
ただあれね、たしか時間が余っちゃったんでああいう風に言えたんですね。用意していたコメントじゃなかったんです。
大事な試合のとき、放送の最後の30秒ぐらいハイライト映像を出すということがよくあるんですよ。試合のハイライトのシーンを試合中に担当者が編集して作っておいて、映像のエンドから逆算して決勝点のシーンでスローモーションを止めて終わるんですけど、あのときは確かね、私の喋る時間を延ばしてくれって言われたんですよ。
通常だったら1分間スローモーションを入れるみたいなことをやるんですけど、喋りを長くすることになっちゃったんです。
多分、あの生の感動のシーンから、作った映像に移ることに対して、制作側に抵抗感もあったんじゃないかと思うんです。そういうことが起こりますから、何かコメントを準備しておくと意外にダメなんですね。
時間のコントロールが出来た
あのころは今から考えても不思議なぐらい自分で時間のコントロールが出来る状態だったんです。1秒間を4分の1に割って、文章を1秒の4分の3で終わるとか、その中に何を喋るかその場で決めることが出来るぐらいの感じだったんですね。
7秒で終わるコメントがあるとしますね。そうすると6秒と4分の3で止める、6秒と半分で止める、そういうことが出来るぐらいのコンディションだったんですよ。
調子のいいときは本当に1秒が長く使えるんです。3秒あればこういうコメントが言えるぞ、ということを喋りながら組み立てられるわけです。
調子が悪いときは全然駄目ですよ。言葉さえ出てこないんですけど、あの決勝ではそういう状態だったんですね。一つの理由はその場に解説の加茂周さんがおられたからです。
加茂さんにとって自分の育ててきたチームがなくなる瞬間ですよ。それを勝って終われた。加茂さん、多分泣いておられたと思うんです。
そして敗れた清水エスパルスも大変いいサッカーをして、あのサッカーで敗れてしまったのなら仕方がないと思うくらいでした。フリューゲルスのそういう意味での舞台設定と、そこでの戦いぶりですね。それからそこに揃った役者たちがある種非常に濃い印象に残ってるんですよ。あんなことありませんからね。普通じゃないですよね。
それに、いろいろな人間模様と経済界のバブル崩壊の後の非常に苦しい環境、経験のなさから来る非常に苦しい状況とか、そういった情報が全部一緒になって私の中にあったんです。
サッカーの試合の中で出す話ではないわけですから、何か胆嚢(たんのう)の辺りに、聞いた話が重い石となって残っているんです。それがあそこでいいサッカーをして勝つ。するとその石がどんどん溶けていくようで。
形の上で非常に印象の深い終わり方になりました。こっちもそれに付いて行くだけで済んだんですね。調子が良かったんで1秒を4分の1ずつ計りながら、最後は止めることができたんです。

山本浩の「やりたいこと」
「やりたいことができるようになる」ということは、「相手のやりたいことをやらせる」に繋がると思うんですね。
今、大学生を教えてるんですけど、学生はよくエントリーシートの書き方を教えてくれって言ってくるんですよ。エントリーシートを書いてオンラインで応募していると思うんですね。ところが、ほとんどの学生が読む側のことを全然考えないんですよ。
自分が4年間で何をやったか書けと指示されて書いているんでしょうけれど、そのエントリーシートを読んで会社側が何に、どういうふうに使って、どこのところを読もうとしてるかってことを一切考えていない。
「僕はこんなにインターンで頑張りました」「飲食店ではサービスの責任者を任されて頑張った」「体制改革をした」と書いているんですけれど、読み手のことが全く頭にないわけです。
お客さんがどこにいるのか、そのお客さんを大事にしてる雇い主がどこにいるのか、自分はどこに立ってるのか。そういう位置関係を知ることで、もう少し視野が広がって、主語が変わり、目的語の置き方も変わって、そうすると当然接続詞の使い方も変わります。
そしてやがて姿勢が変わってきて働きぶりもエネルギーも変わってくるんじゃないかと思うんです。
若い人へのアドバイス
若いうちは当然自分中心でいいと思うんです。自分を大事にして、自分が大きくなって、自分が強くなって、自分がスピードを上げて、テクニックも上がってきたというのでいいと思うんです。
けれどどこかで、自分を迎えてくれる人が、どこで何してるのかを考えるのが必要です。それに早く気がつくと、自分自身を曲げないで進める非常に大きな材料になるような気がします。そうしたら、やりたいことができるようになりますよね。
若いときに何が役立ったかというと、中学校のころ、やたらに落語の本を読んでいたことでしょうか。文学全集を読まないで落語の大きな全集をいろいろ読んでましたからね、ほとんど文学性がないんですよ。
自分の主張や哲学をストーリーで語ると言うより、お客さんが何で面白がるかを大切にしている落語の話。でも面白がって何かを読むって大事だと思いますね。
それに落語の言葉は書き言葉じゃないんですね。語る言葉なんです。中学校から高校にかけて落語の本をずっと読んでいましたから、そういう言葉が喋るっていう仕事のときには役に立ったかもしれないです。
年配の人といろんな話をするのもいいですね。我々がもう使わなくなっている言葉をたくさん知ってる方がおられて。その言葉の持っている硬さ、柔らかさ、それから広がりと言うんですか、押しつぶしたときにどのぐらいエキスが出てくるか、言葉がそれぞれ違いますから。
そういうもので何か疑問を持ったら、辞書を引いて、今だとスマホですぐに音声検索ができると思いますので、そうやって溜めていくっていうのは、一つの手だと思います。




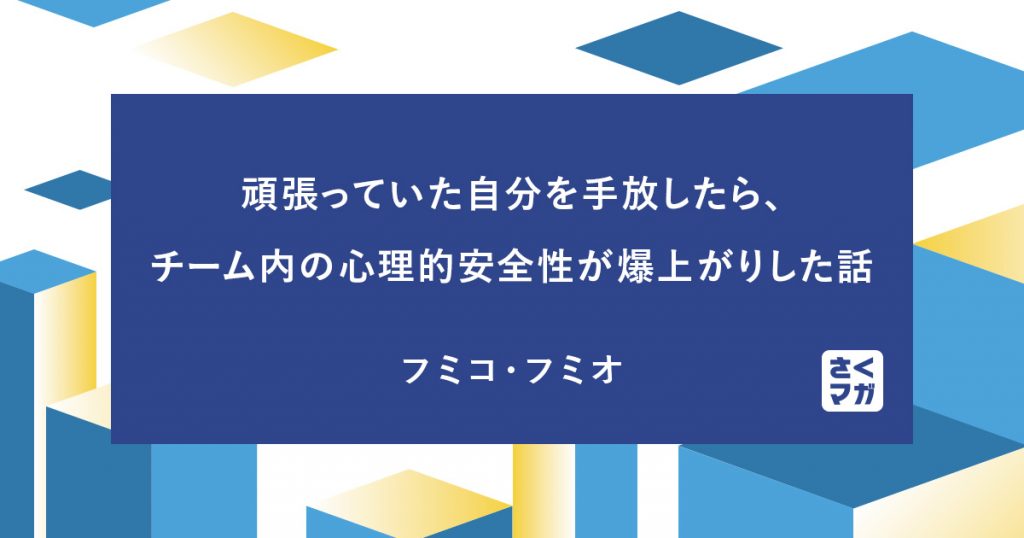

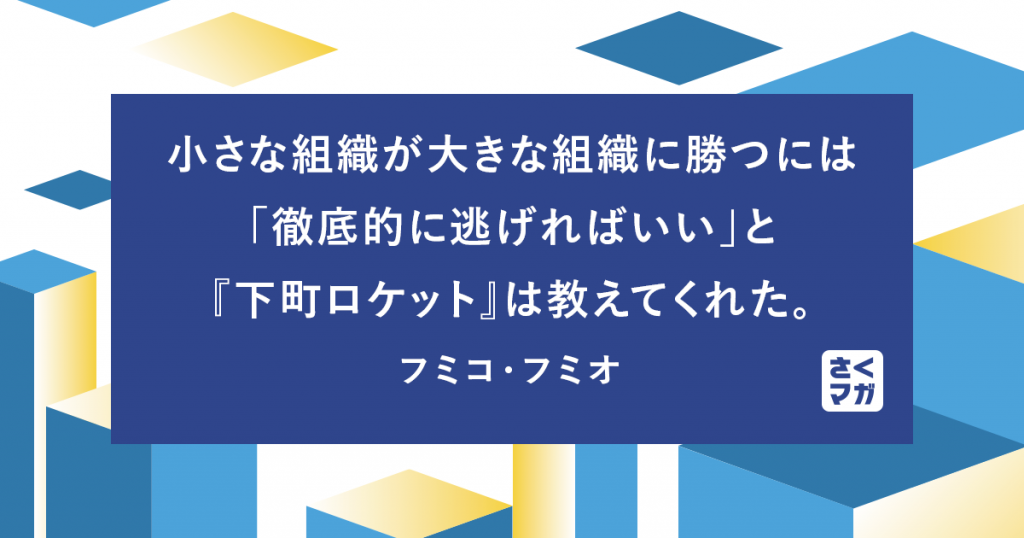
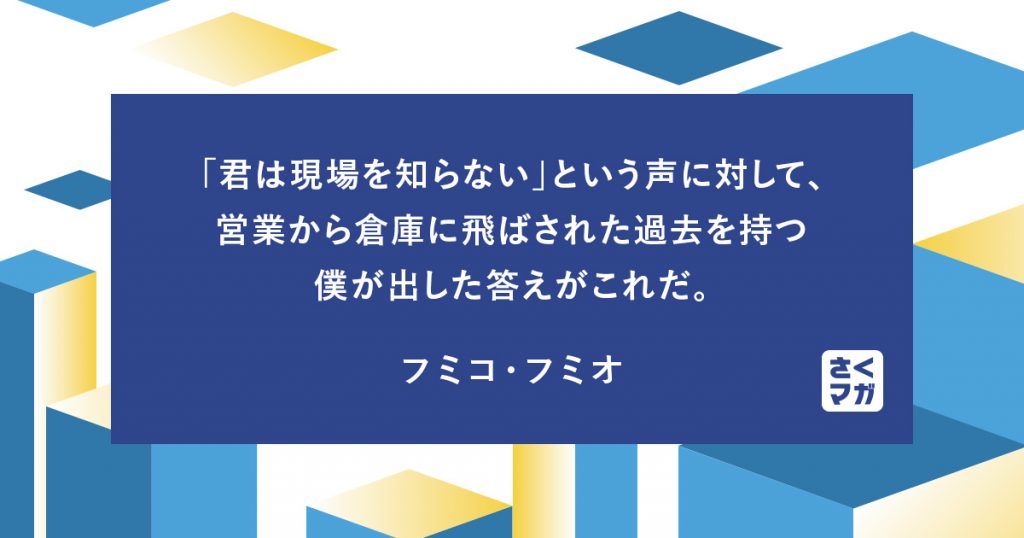
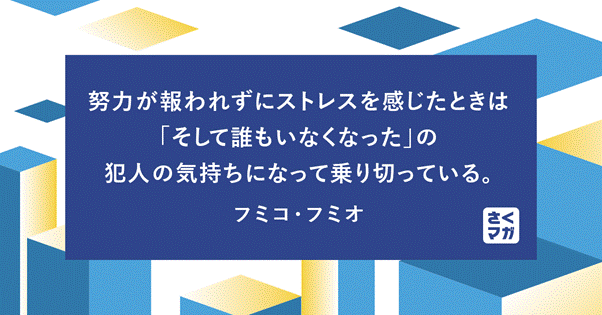
 特集
特集