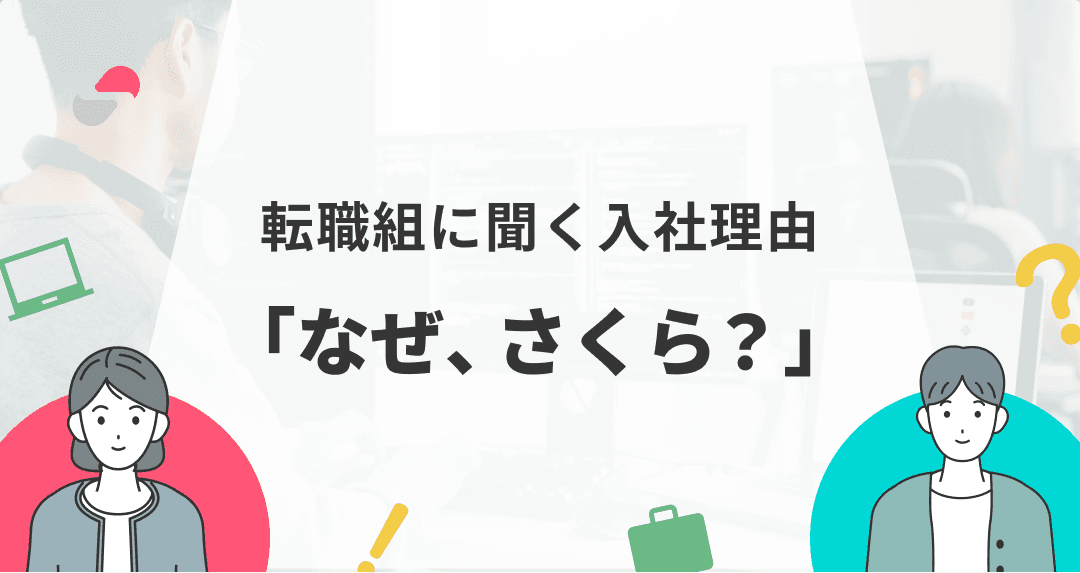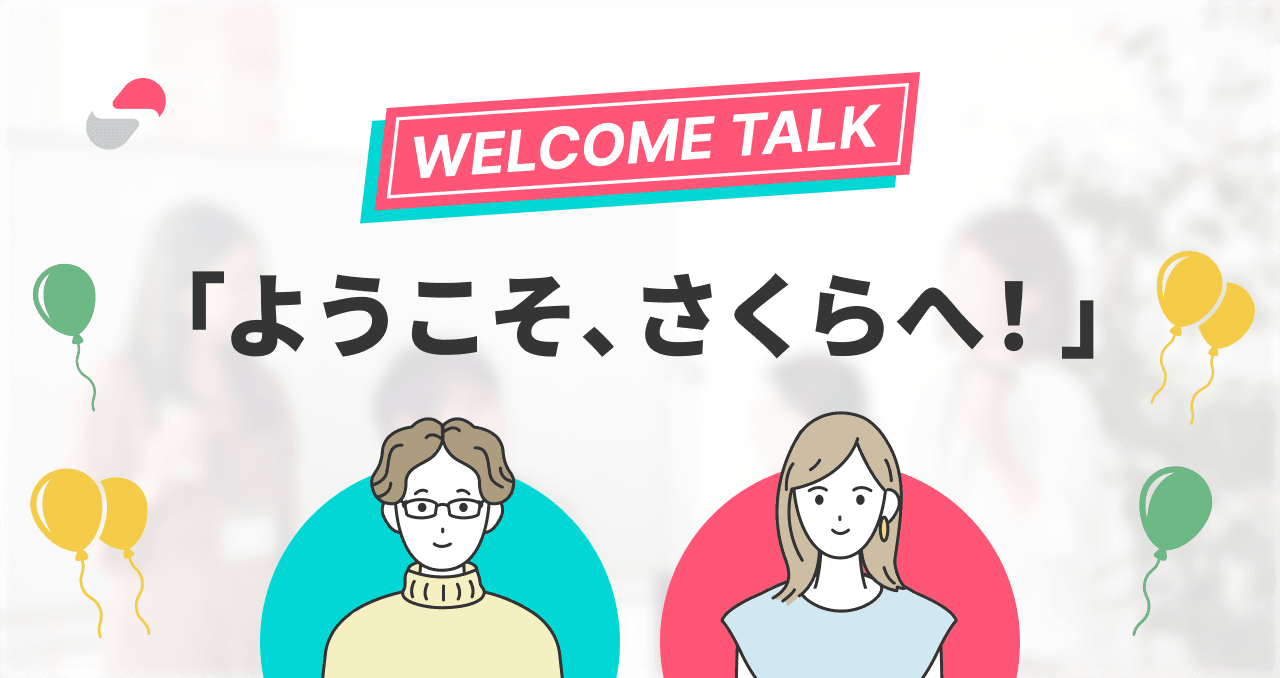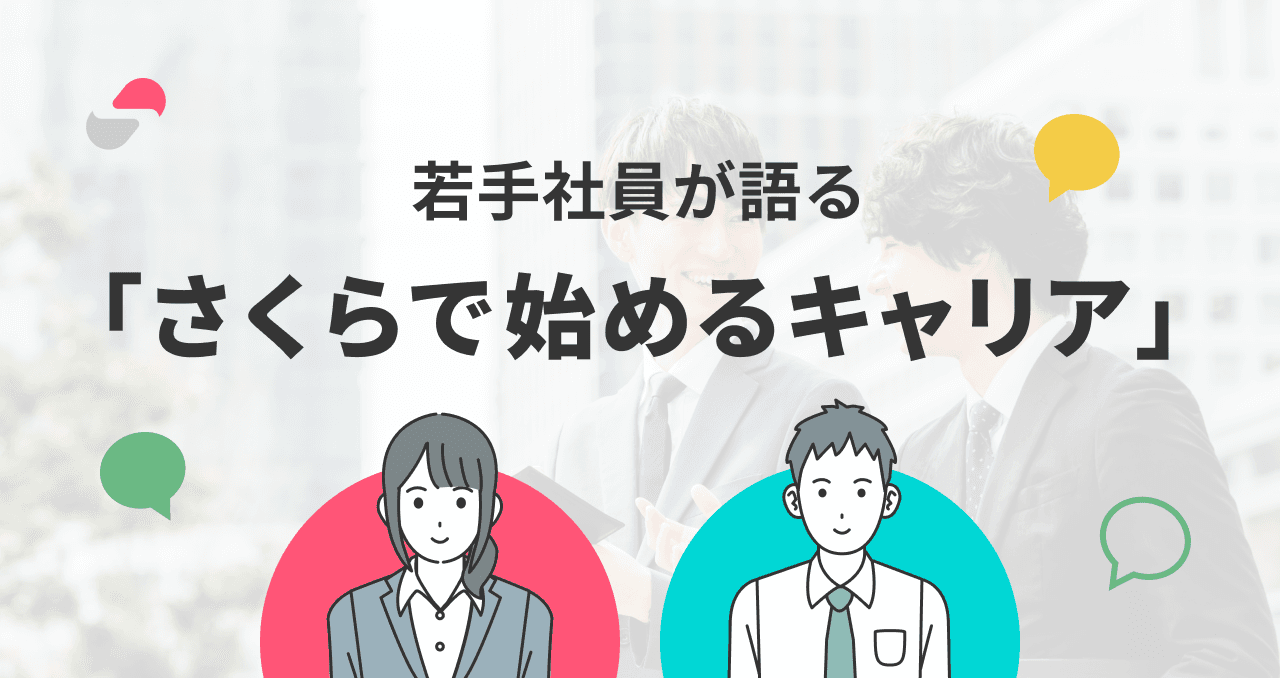東京都内で、「沼る」ワインバルがある。「vivo daily stand」という店名で、都内に 33店舗を展開する飲食チェーンだ。墨田区に本社・セントラルキッチンを構え、基本的なメニューは全店舗で統一されているにも関わらず、常連客は他店舗を「行脚」する。各店舗ごとに地域性を持たせた雰囲気があり、それぞれの「色」が異なるためだ。あえて統一感を持たないことでファンを獲得し、顧客を循環させる店づくりのあり方を、運営会社である VIVO PRODUCTION TOKYO株式会社の代表取締役 花本 朗さんに聞いた。

花本 朗(はなもと あきら)さんプロフィール
1975年、福岡県生まれ。大学を卒業後、福岡のホテル・レストランで働き、その後、フランスへ渡り 1年間修行。帰国後、東京のAUX BACCHANALES などを経て、2010年、VIVO PRODUCTION TOKYO株式会社に入社。2021年から代表取締役。
「コミュニティ機能を備えたバル」という店づくり
東京都内に 34店舗を構えるワインバルがある。「vivo daily stand」(以下「vivo」)だ。食事メニューはほぼ統一で500円程度、ワインも同価格帯とリーズナブル。常連客には女性も多く、1人でも通いやすい。しかし、vivo の特徴はそれだけではない。チェーン展開する多くの飲食店では、店舗デザインが統一され、マニュアルに基づいたオペレーションがおこなわれるが、実際に vivo に足を運ぶと、その対極のように感じる。スタッフの身のこなしや髪型などはバラバラだが、それぞれが居心地のいいサービスを提供してくれる。だからこそ各店舗が独自の魅力を持ち、常連客の多くが、各地の他店舗に足しげく通っているのだ。
このような店づくりの背景には、どのような仕組みがあるのか。vivo を運営する VIVO PRODUCTION TOKYO株式会社の 2代目社長である花本さんは、次のように語る。
「当社の理念は『コミュニティ機能を備えたバルをつくる』です。これは、創業者で前社長の鈴木 健太郎が、学生時代にスペインで出会ったバル文化に影響を受けています。朝に子どもが遊びにきて、昼間はお年寄りが集まってカードゲームをしたり、サッカーを観戦したりする。そして夜には仕事帰りの人々が飲みに来る。スペインには、年齢を問わず多くの人々の生活に根付いたバルが各地域に 1つはあるんです。
そういったコミュニティとしての役割を兼ね備えたお店をつくるのが、vivo の目標です。だからこそ、私たちは接客ルールを設けていないし、制服もありません。店長の人柄や、足を運んでくださるお客さまによってお店がつくられていく。そこが楽しさでもあるし、魅力でもあるのでしょう」

2023年2月1日から 3月末までの期間、スタンプラリー企画を実施した。各店舗の来店状況が QRコードによって記録され、6店舗を訪れると vivo オリジナルのステンレスボトルと交換できるというキャンペーンだ。結果として、約1,200名が参加し、400名ほどがステンレスボトルを獲得したという。2か月の間にこれほど多くの人数が同じチェーン店を行脚しているというのだから、驚きだ。
その理由を探るために、vivo の小竹向原店を訪れ、スタンプラリーに参加した常連客と話をした。不動産業で働くその男性は、スタンプラリー参加以前から都内の各店舗に行ったことがあるという。男性は「店によってそれぞれが持つ特徴が違うのがおもしろい」と語る。
「メニューが一緒だから安心するということもありますが、店によって微妙に違いがあるのが面白いんです。たとえば、この小竹向原店は落ち着いた雰囲気ですが、にぎやかで客同士の距離が近く楽しい雰囲気の店もある。共通しているのは、初めて行っても、1人で行っても、どの店舗でも歓迎してくれるんです」(常連客の男性)
仕入れから調理まで、店舗運営の徹底した効率化

低価格で普段使いができ、コミュニティ機能を備えたバル。顧客目線からすれば理想的な飲食店のあり方だが、一方で企業運営の視点では、どのようなビジネスモデルで収益を得ているのだろうか。とくに現在では、原材料である食品の価格高騰が同業他社の収益モデルに大きな影響をおよぼしている。そこで効果を発揮するのが、vivo の徹底したコスト管理だという。
「まず、私たちは酒飯免許を持っているので、ワインなどの酒類の仕入は卸業者を通さずに輸入業者やメーカーと直接取引ができるんです。当社が各店舗分を一括で買い上げるため、酒類の原価は低く抑えられています。また、セントラルキッチンを採用することで、店舗で調理にかける時間を削減。その分をオペレーションにあてて、顧客満足度の向上と調理にかける時間的コストの削減を実現しています」
花本さんはそういうと、セントラルキッチンの冷蔵庫を開く。大きなバットの中には、配達前のデリが並んでいる。
「フードに関しては、セントラルキッチンで 95パーセントほどを仕上げて、店舗ではそれをお皿に移すか、温め直すだけの状態にしているんです。当社はパンやチーズであっても、ここでカットした状態のものを各店舗に配達する。そうすることで、お店でのバックヤード業務を最低限にしています」
vivo の各店舗の広さは平均して 10坪程度。最低限の人数で店舗運営をおこなうため、敷地面積をあえて狭くし、駅から徒歩 3分ほどの場所でも、家賃を下げることで固定費を削減している。その代わり、セントラルキッチンを採用することで調理スペースや器具を省くことができる。また、東京 23区内に絞った出店計画により、店舗は余計な在庫を抱える必要のない仕組みにしているという。

「当社では受発注システムを導入し、各店舗からの発注情報を一元管理して、自社便を使ってフードを配達する仕組みを採用しています。朝までに発注すれば当日のオープン前には届けられるようになっているので、各店舗はその日必要な分だけ発注できる。そのため、在庫調整も容易で、発生するロス自体も最小限にできます」
このような店舗運営の仕組みは、フランチャイズへのメリットも大きい。現在、開店している 33店舗のうち、半分以上を占める 18店舗はフランチャイズ加盟店だ。
「もしも自力で飲食店を経営しようとすると、フードメニューを作るための仕込みに膨大な時間がかかります。現在の飲食店では慢性的な人手不足のため、店舗運営は最低限で回すしかない場合もある。そうなると、オーナーが抱える負担は膨大になります。当社の場合、フランチャイズ加盟店へは開店前に店舗運営のノウハウをトレーニングしたうえで、開店後は各フードメニューを低価格で販売しています。そうすることで、飲食業界以外からの参入障壁を下げると同時に、閉店リスクを可能な限り下げているのです」
社員の 8割がソムリエのスペシャリスト集団

徹底した店舗運営の効率化を図る一方で、同社が注力するのは人材育成だ。先述の通り、同社は比較的小規模なテナントに店舗を構えるため、原則は 1、2名でのオペレーションが求められる。そのため、同社では社員やアルバイト、フランチャイズのオーナーを含め、すべてのスタッフが 1か月の研修を受け、最終試験をクリアしなければ店舗に立てない。
「メニューにはワインだけなくカクテル、そしてコーヒーもあります。それに加えてデリがありますので、幅広い知識が求められます。研修では商品知識や接客などをしっかりとトレーニングしたうえで、最終試験では筆記とロールプレイングをおこない、 1人でも店が回せるかを確認しています。それを通過してはじめて vivo の店頭に立つことができるのです。フランチャイズ加盟希望の方にも、この研修はマストで受けていただきますが、なかにはこの研修で諦めてしまう方もいます。しかし、これがなければ vivo の理念『コミュニティ機能を備えたバル』を実現できません」
vivo の店づくりを支えるのは各店舗の人材。だからこそ、スタッフには徹底したトレーニングをおこなうことで、スペシャリストとして店舗に送り出す。さらに、同社では直営店以外の社員にもソムリエ資格の取得を奨励しており、現在では 8割ほどがソムリエ資格を取得している。こうすることで、店舗に立つ社員にはより高い質の接客、デリや仕入れを担当する商品部の社員には、より顧客目線の商品への意識を向けているという。
「vivo のメニューは 500円程度のものがほとんどです。それを『ただ出すだけ』になってしまっては、ただの安さを求めた飲食店になってしまいます。しかし、私たちがセントラルキッチンでつくるデリは手作りであり、提供するワインも上質です。一人ひとりがプロフェッショナルでなければ、vivo という存在が成り立たなくなってしまうと考えているんです」
同社の特筆すべき点は、離職率の低さにもある。飲食業界は離職率が高く、人材の定着が大きな課題となっている。しかし、vivo で働くスタッフの多くは数年以上定着し、のれん分けのような形で社員が店を買い取り、フランチャイズオーナーになる場合も多い。現在では高田馬場店と下高井戸店のほか、大森店や東十条店がのれん分けをした店舗だ。
「人材の定着は業界全体の課題であり、当社でも以前は高い離職率が問題になっていました。しかし、のれん分けする店舗などが増えたことによって、独立を目指して働いているスタッフのなかには、将来的には vivo を買い取りたいという店長も増えてきました。さらに、新たに入ってくるスタッフ自身が元々 vivo の常連客である場合も多く、当社の理念に賛同して働いてくれる人が増えたということが大きな理由かもしれません」
2057年までに 600店舗を目指す

花本さんは 2021年に代表取締役に就任。コロナ禍が長引き、飲食業界に向かい風が吹くなかでの就任だった。飲食店経営の舵取りが難しいなかで、vivo をオープンし続ける選択をとったのも、花本さんだった。
「当時はお酒の提供もできなかったので、店舗のスタッフにとっては歯がゆい時期であったと思います。しかし、『コミュニティ機能を備えたバル』という当社の理念があるうえでは、店を休業してしまえば人との接点がなくなる人もいる。難しい決断でしたが、vivo はコロナ禍の中でも店を開け続けました」
九州で生まれ育った花本さんは、元々は音楽を志していたが、音楽活動のかたわらで飲食業界と出会い、調理の道へと進むことにした。その後、単身フランスに飛び、ミシュラン星つきのレストランで修行。東京へと戻ってからも、フレンチの腕を磨いた。花本さんが vivo に入社したのは 2010年。東京での修行の仕上げとして、1年間だけ働こうという気持ちだったという。
「福岡の博多で自分のお店を出すことを目標にしていたので、東京での就業は 5年と決めていたんです。 それで、4年間はほかのレストランやビストロで働いて、最後の 1年間はどこで働くかを考えていました。高級レストランで働くか、それとも自分が今まで学んできたことをアウトプットできるお店で働くか、という選択に迷っていました。
そんなときに、立ち上げ前の高田馬場店の募集が出ていました。そこで、入社から 1年間で立ち上げから携わっていくことにしたんです」
高田馬場店は中野店、代々木店に次ぐ vivo の 3店舗目。当時はまだセントラルキッチンもなく、現在のようにシステム化されていない状態だった。創業者の鈴木さんから裁量を与えられたこともあり、立ち上げからの 1年間は必死に働いた。
「結構やりたいようにやらせてもらって、お店もすごく繁盛しました。しかし、ふとわれに返ったときに『福岡に帰っても、多分これと同じようなことをやるのだろうな』と思ったんです。 そう思った瞬間に、自分で店をやることにまったく魅力を感じなくなりました。1人で店を経営して、成功したとしても、たかが知れている。
そこで、もう一度当社の理念を思い出したんです。東京にコミュニティや文化をつくるという考えは、料理人からはなかなか生まれません。そうなった未来は素晴らしいだろうと思いました」
花本さんは同社に残る決心をした。その後間もなく取締役に就任し、ワインなどの商品回りを管轄、セントラルキッチンができてからは、全店のデリのメニューの考案も任されるようになった。そして 2021年、花本さんは同社 2代目の社長に就任する。
「これまで vivo の運営面については熟知していましたが、経営に関してはまったく知らない状態でした。なので、就任後に明治大学で MBA(経営学修士)を取りに行きました。私は鈴木と違い、0 から 1 を生み出す能力はありませんが、いまあるものを改善し、伸ばしていくことには適性がある。そういった面からも、現在の vivo をより魅力的な場にすることに注力していきたいと考えています」
同社では「2057年までに 600店舗を目指す」という目標を掲げている。そのような具体的な目標設定にはどのような意図があるのだろうか。
「飲食店が社会貢献できる方法はいろいろあると思いますが、多店舗展開というのはその 1番わかりやすい方法だと思っています。2057年は vivo の創業 50年の年です。それまでに 23区内にある 1つの駅に 1店舗 vivoがあり、それぞれの地域でコミュニティとして貢献できるようにしたいと考えています」
2023年中にも新たな店舗のオープンが計画されているが、現在はフランチャイズの問い合わせも多い。スタッフやフランチャイズ加盟希望者とのグリーティングを実施し、自社の理念を丁寧に説明しながら、着実な成長を目指している。最後に、花本さんに今後の展望を聞いた。
「創業した 2007年には、都内の単身世帯の割合が初めて家族世帯を上回りました。以来、当社では人が日常的につながれる場が必要だという想いを持ち、店舗を運営してきました。仕事帰りの疲れたときに 1杯飲んで、店長と他愛のない話をして、気心知れた近所の人がいる。それだけでも、日常生活は本当に豊かになると思います。そのためには価格や店の雰囲気も大切であり、そういった場をつくる人も重要です。店舗を増やしていくと同時に、理念に通貫した運営と店づくり、そして人づくりをしていきたいと考えています」
(撮影:ナカムラヨシノーブ)



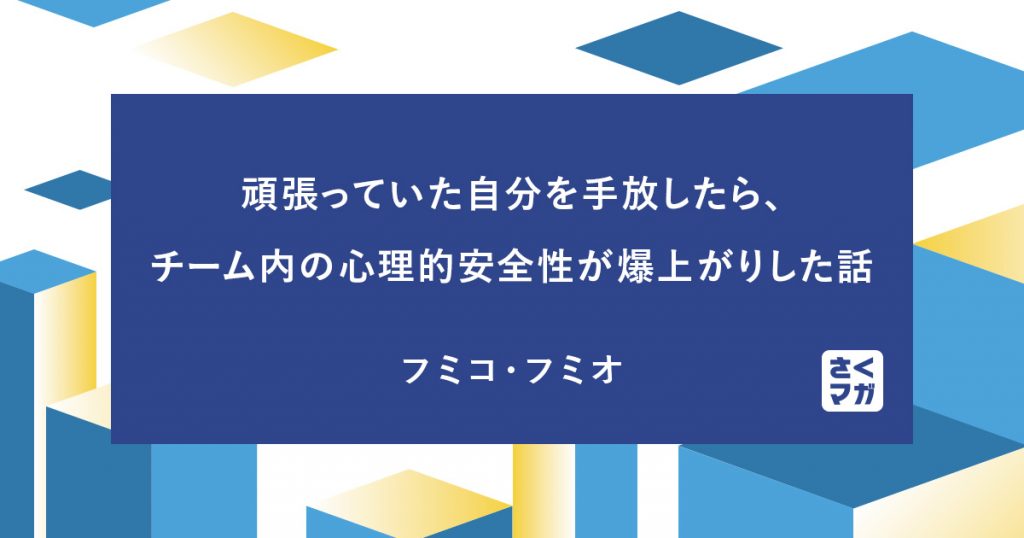

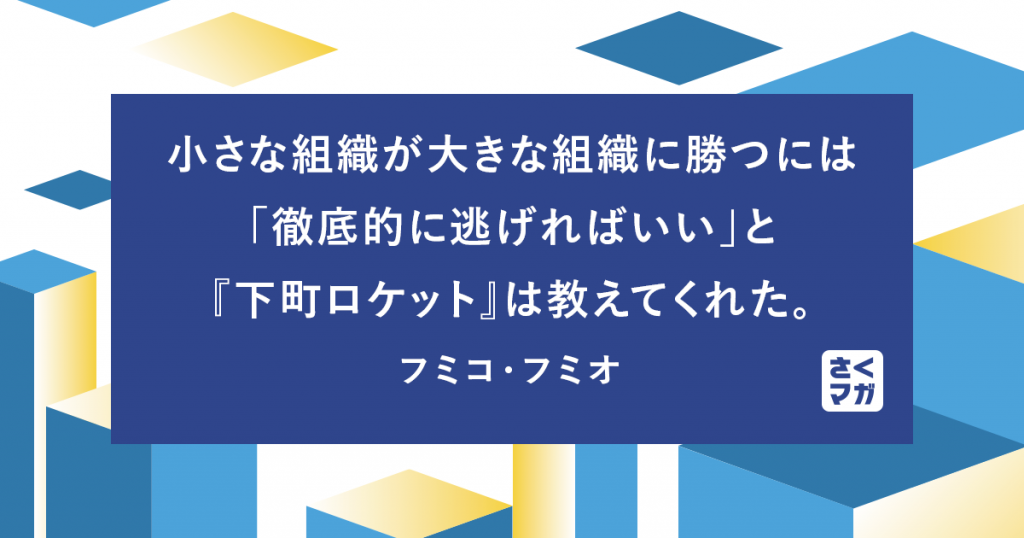
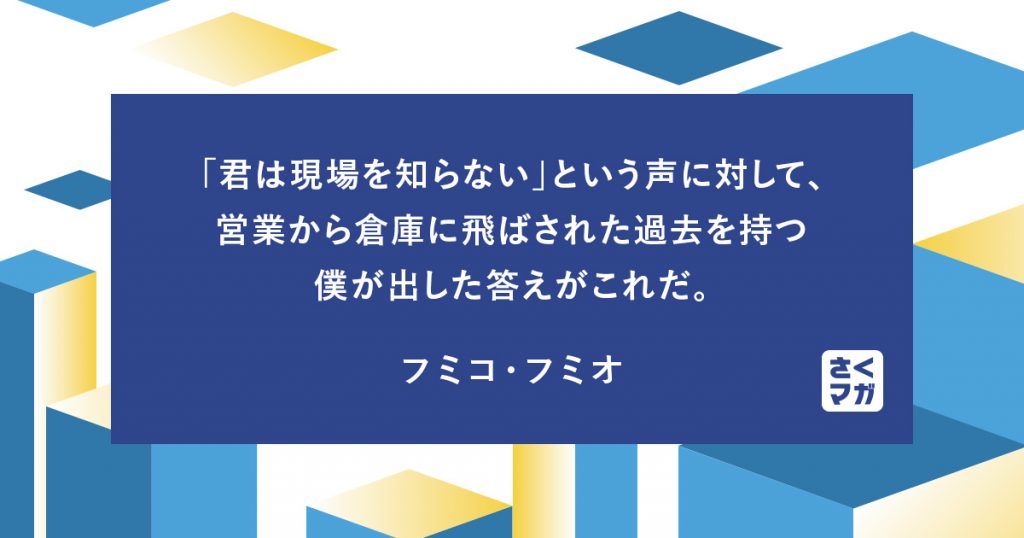
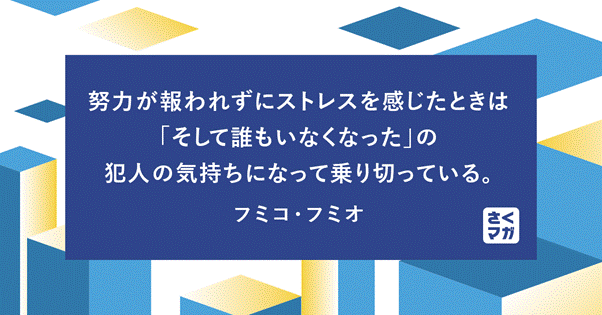
 特集
特集