
さくらインターネットがこれから成長していくための注力テーマの1つとして掲げている「教育」。クラウド事業者としてどうすれば次世代に貢献できるか、試行錯誤しながら活動を広げています。高等専門学校(高専)の学生向けに教育支援活動をおこなう「高専支援プロジェクト」はその取り組みの一貫です。2023年3月には、独立行政法人国立高等専門学校機構(以下、高専機構)と包括連携協定を締結。現在、日本の多くの高専で出前授業などをおこなっています。
そしてこのたび「高専支援プロジェクト」は海外にも活動の場を広げ、モンゴルで「高専式の技術教育」を実践する新モンゴル高専技術カレッジ(以下、新モンゴル高専)と連携。学習環境の整備や出前授業などを通じてモンゴルの技術者教育を支援しています。2025年2月から始まった出前授業のタイミングに合わせ、新モンゴル高専のオユンジャルガル・ツムルバルタル先生(校長)、ソロンゾンボルド・ナチン先生(コンピュータサイエンス学科 学科長)、バチュルーン・バトナサン先生(同科 担当教員)の3名と、連携を進めた田川 真理子さん(JICA海外 ボランティア)、そしてさくらインターネット 執行役員 髙橋 隆行に、モンゴルにおける技術教育の現状や課題、今後の展望などについてインタビューしました。
日本のIT企業を連携先に選んだきっかけとは

新モンゴル高専とさくらインターネットが連携をすることになったきっかけを教えてください。

現在、モンゴルではデジタル化が急速に進んでおり、とくにサイバーセキュリティ、AI、ビッグデータなどの分野に注力しています。政府はIT系スタートアップ企業のイノベーションを積極的に支援する方針を打ち出しており、法整備も進めています。それらの取り組みのなかで、新モンゴル高専は「技術者の教育」を担っています。
Soronzonbold Nachin(ソロンゾンボルド・ナチン)先生 プロフィール
新モンゴル高専技術カレッジ コンピュータサイエンス学科 学科長。モンゴル科学技術大学にてソフトウェア工学を専攻。卒業後、同大学で10年間コンピューターソフトウェア科の教員を務める。その後、起業やITの私立大学設立などを経験。2021年9月に新モンゴル高専技術カレッジにて勤務開始し、コンピュータサイエンス学科立ち上げを担う。

モンゴルは国として豊富な資源を持つ一方で、それを十分に活用しきれていないという現状があります。自国の資源を自国で活かすには、科学技術レベルの向上が不可欠です。そこで、新モンゴル高専は日本の高専式教育を取り入れ、「機械・電気電子・建築・物質工学」の学科を運営していました。そこに、近年の世界的なデジタル化を取り入れるために「コンピュータサイエンス学科」を新設することにしたんです。
Oyunjargal Tumurbaatar(オユンジャルガル・ツムルバタル)先生 プロフィール
新モンゴル高専技術カレッジ 校長。医療工学を専攻し、日本の北海道国立大学機構 北見工業大学に3年間留学。花王株式会社で1年間のインターンシップと、卒業後に北見工大で研究員としての勤務を経験し、約7年間の日本生活を終えて2018年4月に教師を目指しモンゴルに帰国。新モンゴル高専技術カレッジの物質工学科の教師、学科長を経て2024年8月より現職。

私は2023年からJICA海外ボランティアとしてモンゴルに赴任し、長年、ITエンジニアとして企業で働いた経験を活かし「モンゴル技術カレッジ連盟」において、日本の高専モデルを取り入れた教育の技術支援をおこなっています。その活動の一環として、新モンゴル高専からコンピュータサイエンス学科の新規に開講する授業のカリキュラムの相談などを受けました。
ちょうどその時期に、さくらインターネットのメールマガジンで高知高専との連携事例を知って、連絡をしてみたんです。私自身はさくらインターネットのサービスユーザーだったので、よく存じ上げていました。
田川 真理子(たがわ まりこ)さん プロフィール
JICA海外ボランティア。大学卒業後、日本企業および外資企業でITエンジニアとしてのキャリアを積む。その後、モンゴルの高専で次世代のITエンジニア育成を支援するボランティアの募集を知り、応募。2023年10月より2年間の契約でモンゴルに赴任し、複数の高専のIT関連学科でカリキュラムの改善や授業の実施などの技術支援活動をおこなっている。

田川さんからご連絡をいただいてすぐにオンラインで会議をしました。新モンゴル高専の先生方にも参加いただき、その場で「やりましょう」という話になったんです。すごく良いタイミングでしたね。
髙橋 隆行(たかはし たかゆき) プロフィール
さくらインターネット株式会社 執行役員。カスタマーサポート、プリセールスエンジニア経験を経て2006年にさくらインターネットに入社。運用現場業務に従事したのち、2011年に運用執行役員に就任。2016年に営業管掌として異動、子ども向けプログラミング教室を運営する非営利団体「KidsVenture」の立ち上げ、グループ会社代表取締役を経験。現在は「高専支援プロジェクト」を担うテクニカルソリューション本部を管掌し、パートナー戦略策定やユーザーへの教育支援に従事。
モンゴルにおける「高専式の技術教育」の現状と課題
モンゴルの技術教育の現状についてお聞かせください。新モンゴル高専では、どのように日本の高専教育を取り入れているのでしょうか。

現在、カリキュラムの約7割は日本の高専モデルを導入しています。ただし設備や機材が日本ほど揃っていないため、実験・実習の時間数は日本の高専と比較するとまだ少な目です。

技術者を目指す学生たちにとって、実践的な学びの機会は非常に貴重です。私自身、モンゴルで技術者を目指し、日本へ留学して日本企業のシステムエンジニアとして働いた経験があります。そのなかで、モンゴルではIT分野の実践的な学習機会が限られていることを悔しく思っていました。
コンピュータサイエンス学科が新設されるにあたって、私とソロンゾンボルド先生が新モンゴル高専の教員に就任しましたが、体系的な学習のためには計算資源やクラウドインフラが不可欠です。どうカリキュラムを組むべきか悩んでいたところにさくらインターネットと連携できることになり、とても助かりました。
Batchuluun Batnasan(バチュルーン・バトナサン)先生 プロフィール
新モンゴル高専技術カレッジ コンピュータサイエンス学科 教員。日本式の高校教育をおこなう新モンゴル高等学校の第一期生。日本に興味を持ち、日本の大学・大学院に6年間留学。卒業後、モンゴル国立教育大学にて教員として勤務。2017年に再来日し、研究生として研究に取り組んだ後、システムエンジニアとして勤務。その後、コンピュータサイエンス学科の立ち上げに伴い、2022年より現職。

さくらインターネットがおこなう教育支援では、クラウドエンジニアが学習する際に「特定のプラットフォームに依存しすぎないこと」を重要視しています。特定のシステムの使い方を職業訓練的に学ぶだけでは、エンジニアとしての視野は広がりません。そのため、学生には、インフラの基礎をしっかり学び、特定のサービスにロックインされない普遍的な知識を身に着けてほしいと考えています。そこで私たちは、クラウドサービスの利用方法だけでなく、インフラのより低いレイヤーから教えることを大切にしています。たとえば「サーバーとは何か」「スイッチとは何か」「ルーターとは何か」といった、物理的な仕組みから学ぶことで、学生たちに幅広い選択肢を提供したいんです。
さくらのクラウド検定で国産クラウドの技術を身につけよう
>>詳細を見る
2025年2月から授業開始。学生の反応は?

具体的に、現在はどのような支援をしているのでしょうか。

さくらインターネットは大きく分けて、2つの支援をしています。
まず1つ目は、インフラの提供です。日本の現役高専生向けと同様に、新モンゴル高専にもクラウド環境や計算資源を無料で提供しています。これは、「学生が月額費用を負担してクラウドを利用するのは実質的に難しい」という課題に対応するためです。ただし現在は、海外向けの約款整備が未了のため、新モンゴル高専への提供は、授業やコンテストなどの期間限定にとどめています。
2つ目は、出前授業です。出前授業では、全16コマのカリキュラムで、基礎から実践までを体系的に学びます。まずは2025年2月に現地で3コマの授業を実施します。その後5コマのリモート授業をおこない、後半は3月~4月にかけて現地で2コマ、その後6コマのリモート授業を実施します。最終回は5月下旬を予定しています。講師陣が再度現地を訪問して、学生の発表会に立ち会います。まだ検討中ですが、発表会だけではなく、懇親会やデータセンターを中心とした特別講義、高専卒の起業家をお招きしたパネルディスカッションなど、学生が今後のキャリアを考えるうえでもプラスになるようなコンテンツを考えたいですね。
言葉の壁もあるかと思いますが、新モンゴル高専の学生たちの反応はどうですか?

現在(2025年2月4日時点)、1回目の現地授業が完了したところですが、学生たちは非常にモチベーションが高く、技術を習得する意欲もすごいです。モンゴル語への通訳が必要になるため授業のペースを少し落とすつもりでいたのですが、学生の理解が速く、質問も積極的にしてくれます。

新モンゴル高専では、1年生から週2コマの日本語授業を実施し、4年生からは技術用語を重点的に学ぶカリキュラムに移行します。とくにIT分野の専門用語は英語と日本語で共通するものが多く、学生たちの理解もスムーズに進んでいるようです。
技術者の挑戦を支える環境づくりへ
今後の展望についてお聞かせください。

モンゴルでは技術者を目指す若者が多い一方で、彼らを指導できる人材や環境はまだまだ不足しています。私がITエンジニアを目指していた頃は実践的な学習の機会がいま以上に限られていたので、ITセンターをつくるのが夢でした。いま、さくらインターネットの協力で、その夢の一部が実現できているように感じています。この環境を整備して将来的な学びの場を充実させたいです。そのためには、自分自身も技術者として成長していく必要があると考えています。

もし私がいまの環境で学生だったら、モンゴルの国をデジタル化する事業に力を入れていたでしょう。そして、ITだけに限らず、他の専門の学生たちと一緒にチームを組んで、ITを使ってイノベーションを起こしていたと思います。言語、インフラ、産学連携、AIなどなど、学生たちにはどんどん新しいものに触れてほしいし、何でもつくってみてほしい。その環境を整備していくことが私たちの役割だと考えています。

モンゴルと日本の技術連携をもっと進めて、広げていきたいと考えています。とくにこれからの4・5年生には、自由に挑戦する機会を与えたいと思っています。過去の卒業研究で発表された製品に、とても良い健康的な発酵食品の研究があるのです。あれを形にして、事業化まで持っていけるような環境を整えていきたいですね。

最新技術のなかでも、とくにAI、IoT、ビッグデータなどの分野で教員が足りず、カリキュラムも十分に整備されていません。クラウド基盤や学習教材などを充実させる必要もあります。こういった分野での継続的支援や連携が、今後さらに重要になってくると考えていますので、今回の出前授業を皮切りに、さくらインターネットに引き続きご支援いただければ幸いです。

ぜひよろしくお願いいたします。さくらインターネットは、高専出身者が創業した会社です。私自身も現役高専生の保護者であるため、会社としても、私個人としても、高専を応援したい熱意があります。まずは今回の授業が、学生にとって、そして新モンゴル高専にとって実り多きものになるよう、尽力していきます!
さくらインターネットの最新の取り組みや社風を知る
>>さくマガのメールマガジンに登録する


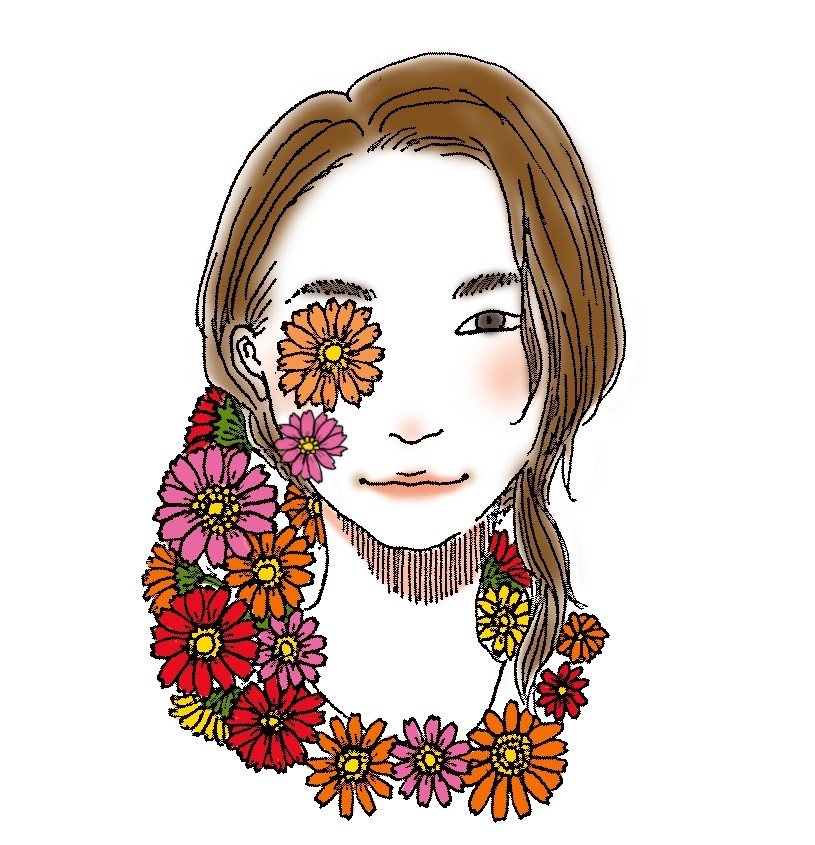

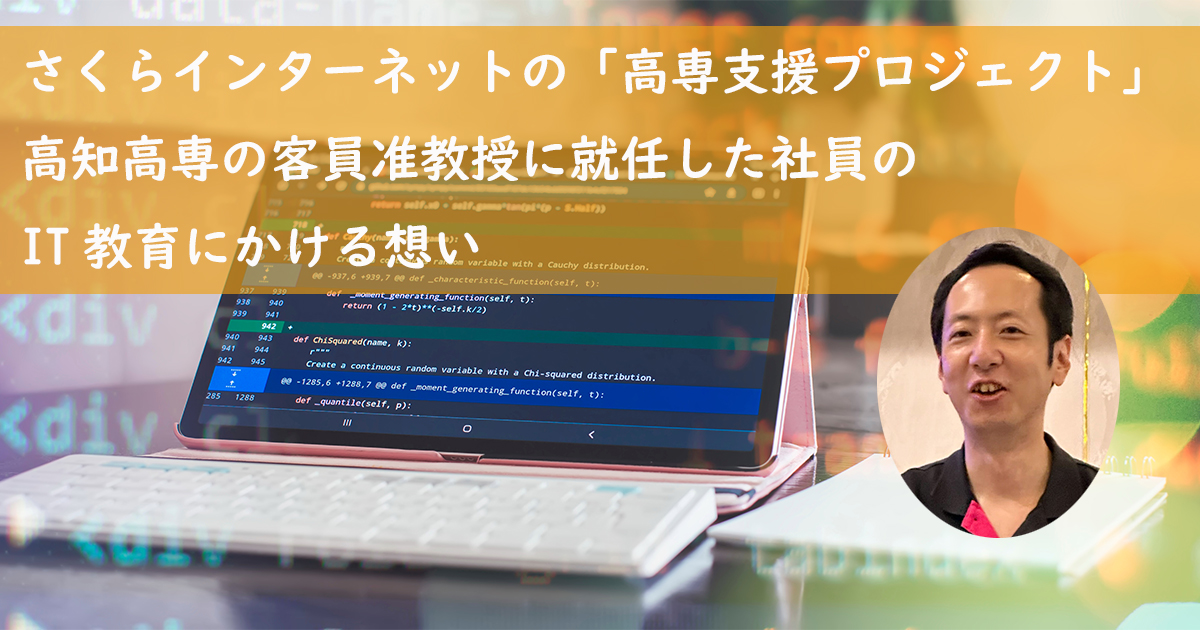

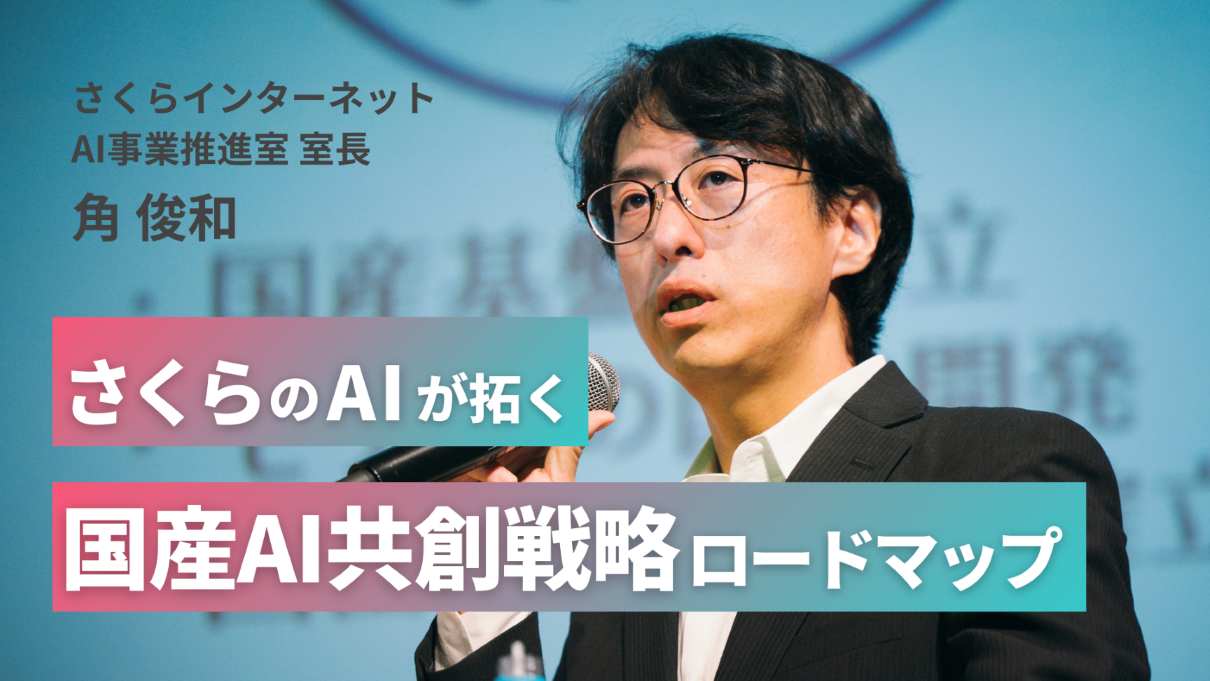 New
New
 New
New
 特集
特集




