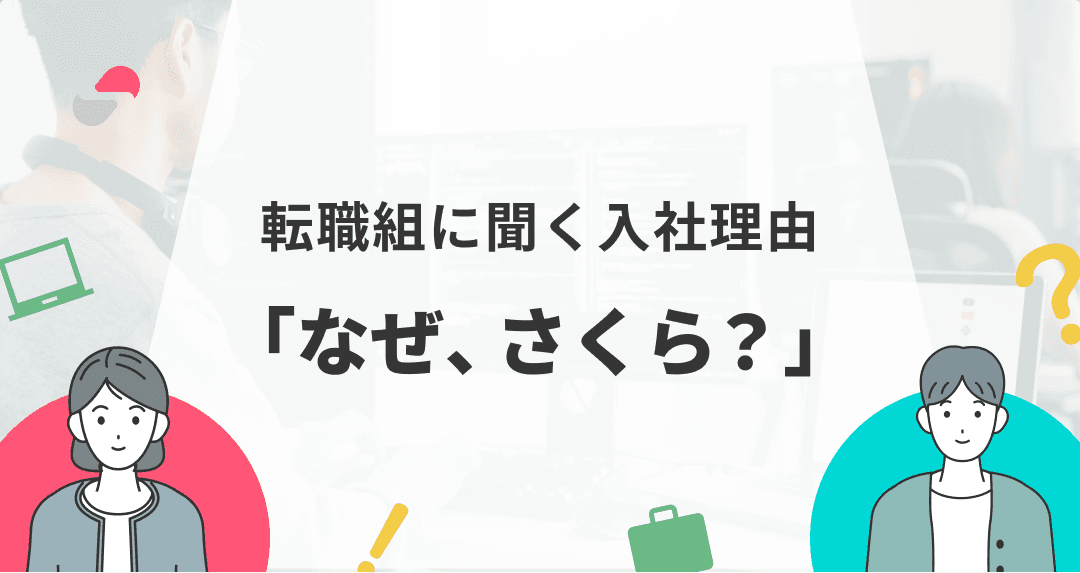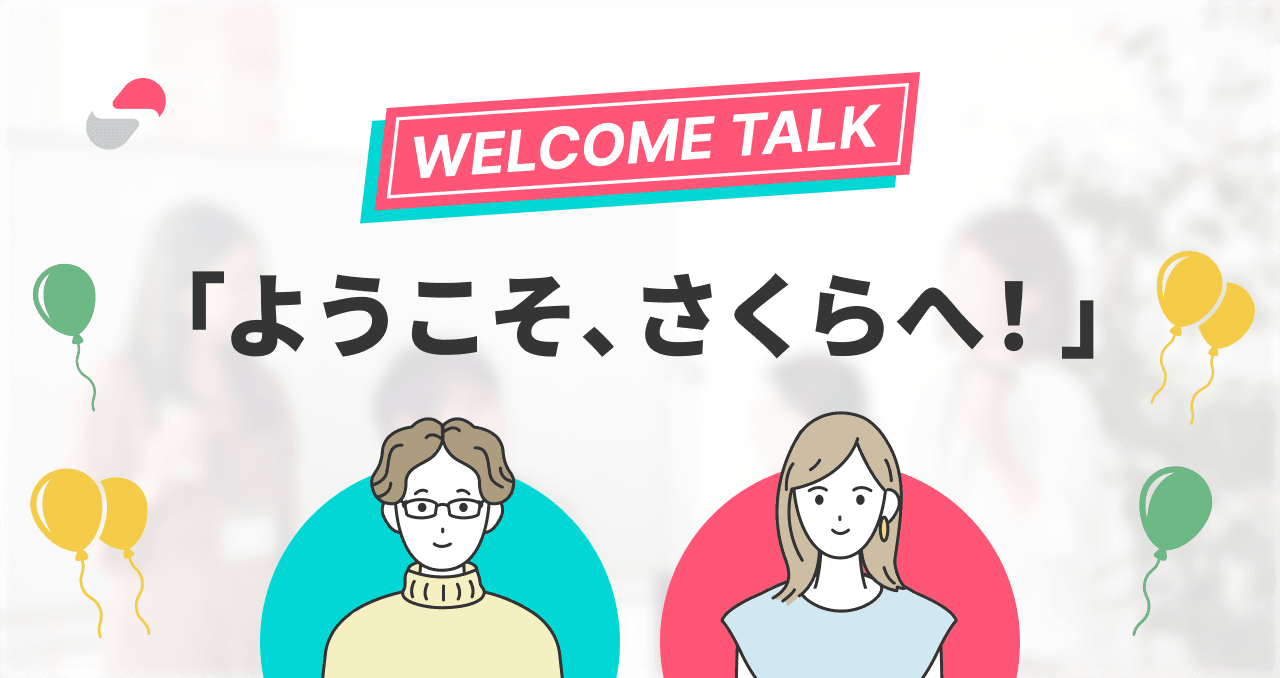書籍の執筆。それはあまりにも属人化された世界である。
私は書籍を執筆し始めてもう数年経っているが、どうやってほかの著者たちが書籍を執筆しているのか、本当にわからない。まったくわからない。どんなふうに目次をつくり、前から順に、10万字も生産しているのか。謎すぎる。
そして最近、「いや、自分の書籍執筆もあまりに漠然とやりすぎでは?」と強く感じていたのだ。
とにかく書く、とにかく着地を目指す、というスタイルで今までやってきていたのだが。それは正直、私の本がこれまで章立てが細かい「〇〇集」ばかりだったから成立するスタイルなのだ。
書評集、エッセイ集、コラム集。それらは章のなかの構成は考えなくてはいけないが、本全体の流れのようなもの、つまり本全体の構成は曖昧で良い(気がする)。もちろん私なりに構成は作っていたつもり、というか読者の方にこんな流れで読んでもらえたらいいなというぼんやりした実感はあった。とはいえそれはぼんやりしたものにすぎず、基本はどこから読んでも大丈夫スタイルでやってきてしまった。
が、それではうまくいかない時がやってきてしまった。今である。
困った。なんか今までと同じやり方ではうまくいかない。
前置きが長くなったけれど、そんなとき手に取ったのが、今回紹介する『メイキング・オブ・勉強の哲学』(千葉雅也著、文藝春秋)である。
「本を執筆する仕事」について語る仕事論の本
本書は『 勉強の哲学 来るべきバカのために』という書籍をどうやって作っていったか、対談や講義を通して語る本である。『勉強の哲学 来るべきバカのために』は「勉強」を問う哲学書でありながらベストセラーにもなった書籍である。
さまざまな話題や方法論を通過しながら「勉強」の意味や技術を綴るこの本が、どうやって作られていったのか、たしかに気になる。あわよくば自分の書籍執筆の参考にもしたい。そう思って手に取ったのだった。
本書をビジネス本と呼んでいいのかはわからない。普通に考えたら人文書の範疇に入るのかもしれない。が、私は本書をれっきとしたビジネス書だと感じた。それはなぜなら、この本が描き出すものが、「本を執筆するという仕事」についてひたすら語る、仕事論だからである。
執筆スタイルそのものを探究する

作者の千葉雅也さんは、『勉強の哲学』を口頭で話してそれを書き起こしてもらう形で作ろうとしていたらしい。だがそれではうまくいかないことに気づく。そして、アウトライナーというツールを使った執筆スタイルを構築していったのだと語る。
私がこの話を読んで、そもそも「そこまで執筆スタイルそのものを探究するのか」という点に驚いた。というのも「書く」という行為は基本的にものすごくシンプルな行動の集積で、Word さえあればこれまで本一冊書けちゃっていたからである。
もちろんこれまでも、たとえばデスク周りを快適にしようとしたり、キーボードを変えてみたり、椅子を模索したりしたことはある。だが執筆ソフトそのものを模索したことがなかったのだ。
しかし考えてみれば、執筆ソフトもまた、あきらかに書ける原稿の量や質にかかわる話だ。書くことだって、ツールを使っている行為なのだから。楽器を使う人が楽器にこだわるのと同じで、たしかに書くこともまた、ツールをあれこれ使ってみるべきではないかと、本書を読んで心底思ったのである。
本書をきっかけにツールを模索
結果的に、書くことは Word一択だった以前に比べ、いまは Google ドキュメントや、WorkFlowy、Scrivener を駆使してみている。
私は以前からスマートフォンで原稿を書けるようになってきたので、外出先ではスマートフォンでまず書き出しを模索できたり、あるいは本の執筆の目次を WorkFlowy で模索できたりするのが良い点だ。まだ始めたばかりだから続くかわからないけれど、ツールを模索すると、たしかに書くことそのものの楽しさを思い出せる気がする。そういえば小さい頃は、自由帳や真っ白なノートをひとりで使えることそのものが嬉しかったのだ。
書籍の執筆は属人化した、ひとりで模索する世界だ。しかしだからこそ、ひとりであれこれ試し、いろんなツールを使ってみたい。その模索のわくわくする感じを思い出せたことが、本書を読んで一番良かったことである。



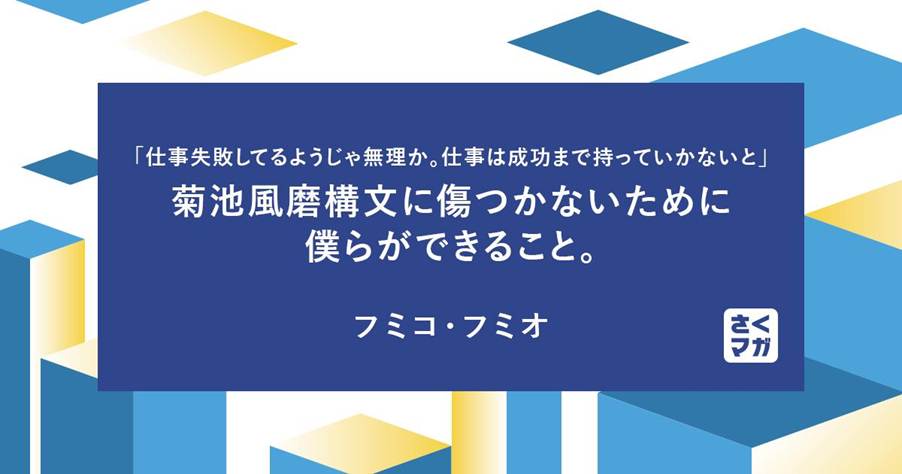
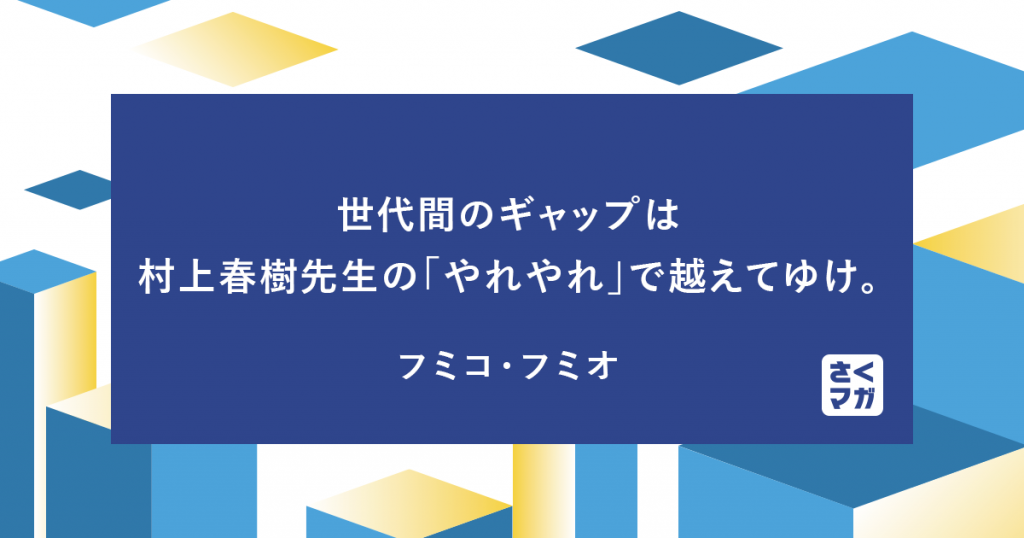
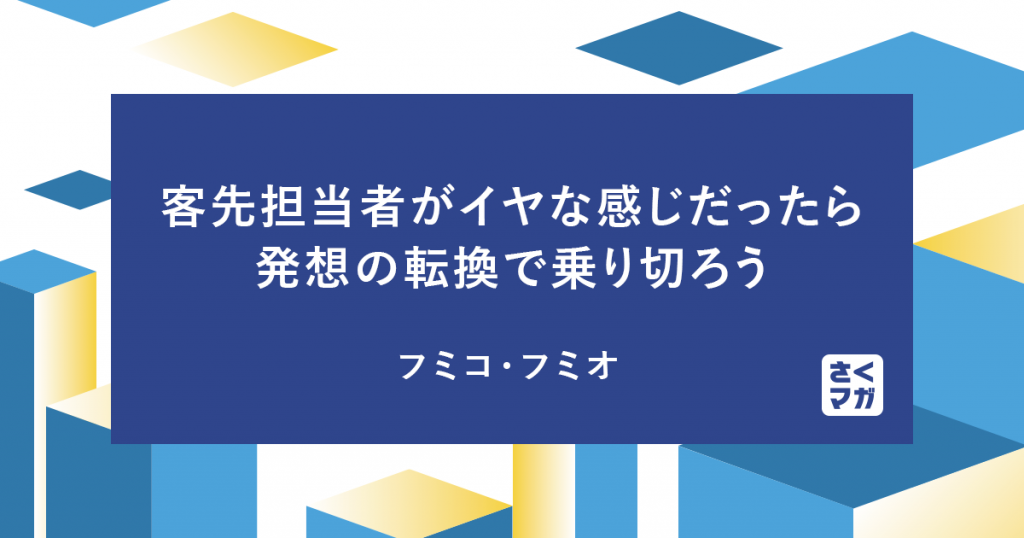
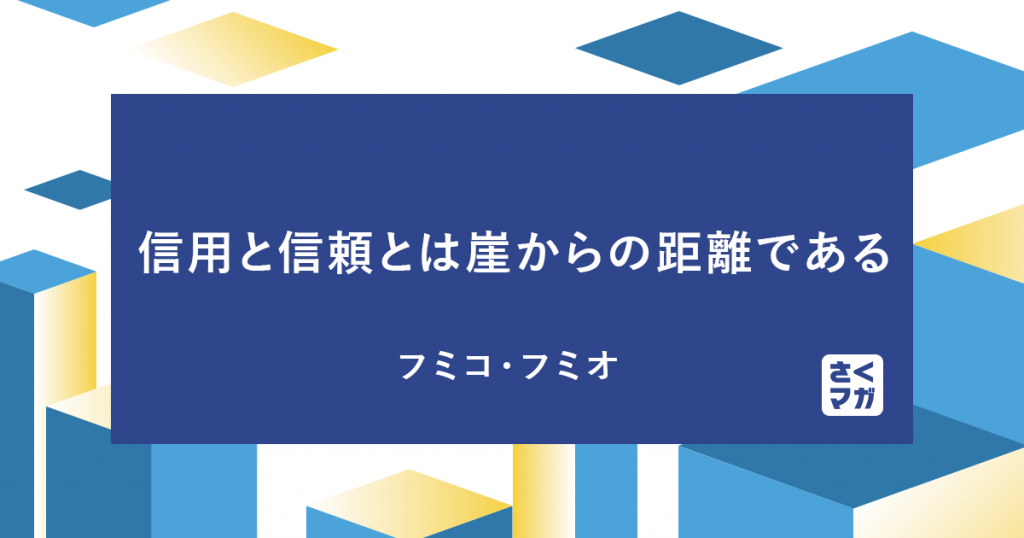
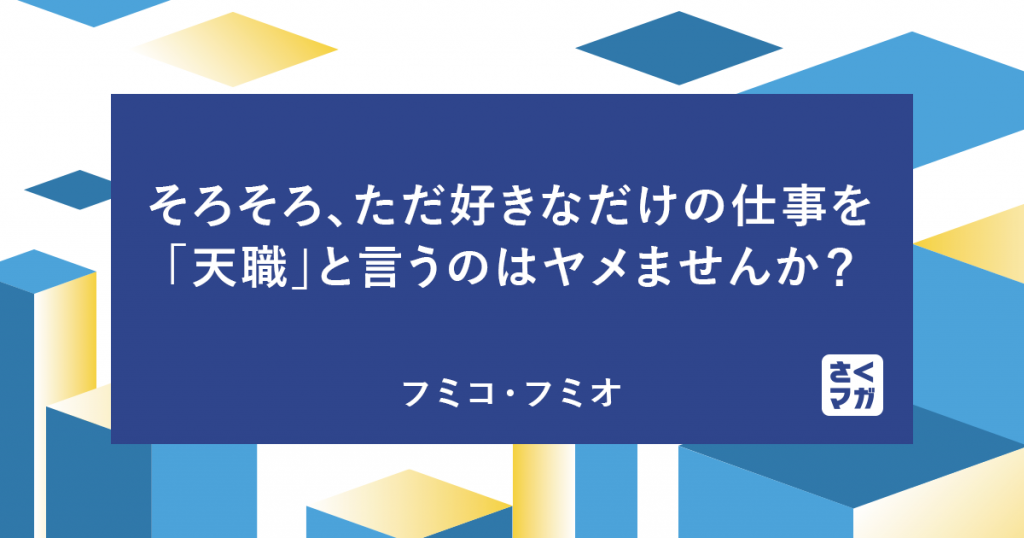
 特集
特集