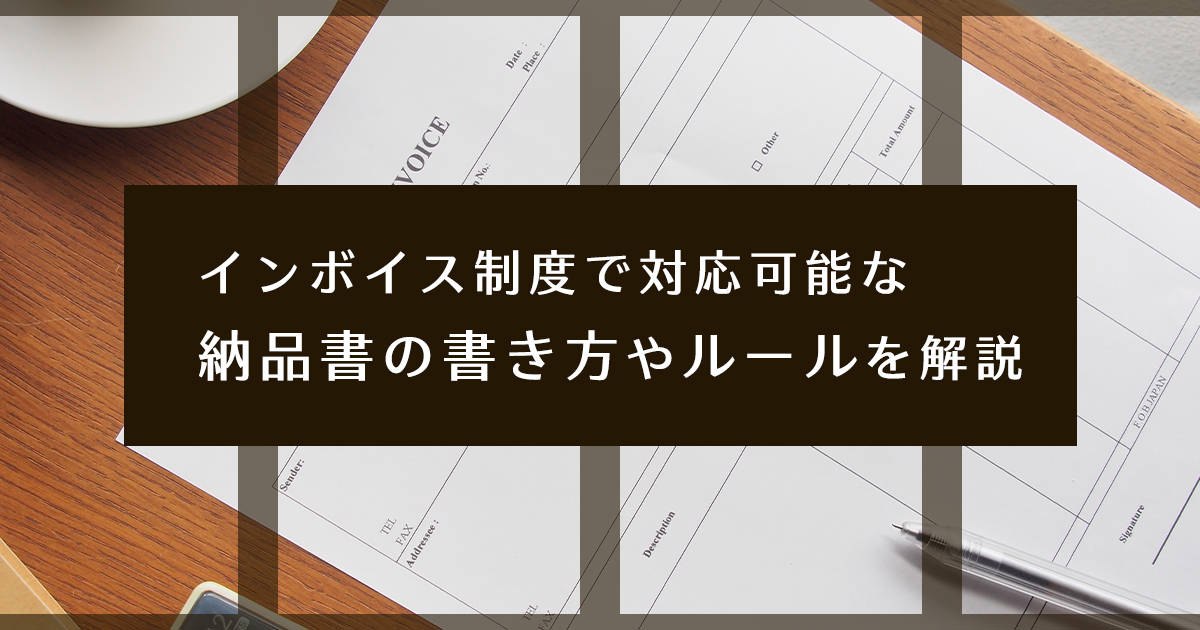
>>5分でさくらインターネットのサービスがわかる!サービス紹介資料をダウンロードする
重複した徴税をなくすための仕入税額控除を受けるために、適格請求書を証拠の資料として保存しておく制度のことを「インボイス制度」といいます。インボイス制度では、証拠資料となる適格請求書のほかにも、納品書での対応も可能です。
ただし、納品書を証拠資料とする際には、書き方や注意点、納品書のルールを理解し、正しく保存しておく必要があります。
本記事では、株式会社SoLabo 代表取締役 田原 広一が、インボイス制度に対応するための納品書の書き方や注意点について解説します。
インボイス制度に対応する納品書の書き方とルール
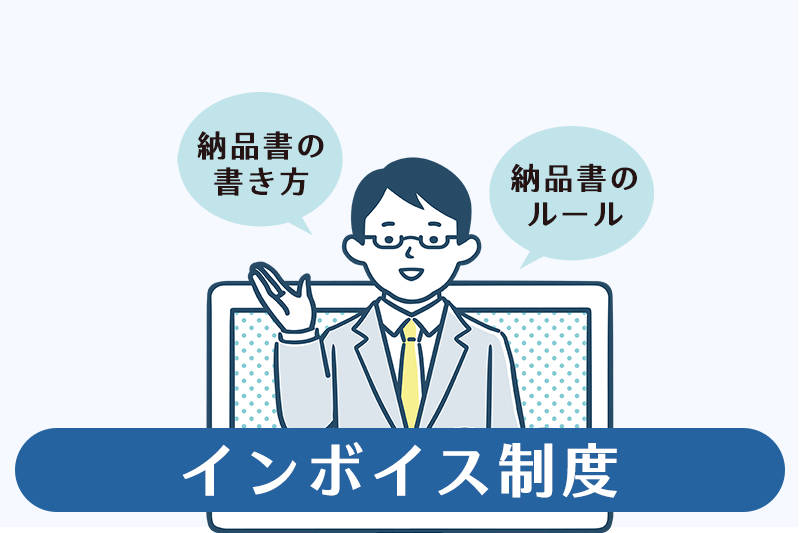
インボイス制度に対応した納品書を作成するためには、インボイス制度を理解し、納品書に入れるべき記載項目を知る必要があります。インボイス制度では、受け取り側が納品書に追記することは認められていないため、作成側が理解しておくことがもっとも重要です。
納品書の書き方
必要な記載項目が網羅されていればインボイス制度に対応できますが、従来のテンプレートに追記するだけでは、見やすい納品書にはなりません。
まずは、現段階の 適格請求書等保存方式 の両方で、必要となる記載項目を洗い出します。それらをもとに、新しい納品書のテンプレートを作成していきましょう。
【納品書の書き方】
|
(1)納品書発行元の氏名もしくは名称 納品書を作成する事業者の氏名は必ず記載してください。取引先によっては担当者の氏名を求めることもあるため、あらかじめ取引をおこなう際に確認しましょう。 |
|
(2)取引がおこなわれた年月日 納品書を作成した日付を記載します。この日付があることで、複数の資料を適格請求書として対応させる場合に、同じ取引に関しての資料ということが明確になります。 |
|
(3)取引をおこなった内容 取引をおこなった内容や品物名・数量・単価・金額を記載します。具体的な数量の記載が難しい場合は、「一式」という文言でも問題ありません。 金額は 「数量 × 単価」で計算されますが、金額の記載も任意となります。ただし、金額を記載しておいたほうが合計額を計算しやすくなるため、項目の 1つに入れておくといいでしょう。 |
|
(4)税率別に分けて合計した対価の額 現在の税率は、8%(野菜・肉・魚・テイクアウト・一体資産など)と、10%(酒・外食・イートイン・例外の一体資産など)の 2種類です。これらの税率にそれぞれ対象となる内容を分け、合計した対価の額を記載します。 |
|
(5)軽減税率の対象内容であることがわかる主旨 軽減税率の対象となる内容には、〈*/◆/※〉などの印を記載し、どの取引内容が軽減税率として計算されているのかを明確にしましょう。 |
|
(6)発注者の氏名もしくは名称 納品書を渡す相手、発注事業者の氏名を記載します。(1) と同様に、担当者氏名の記載を希望することもあるため、あらかじめ取引先に確認しておきましょう。 |
|
(7)登録番号 税務署にて、適格請求書登録事業者の登録手続きをおこなったあとに、税務署から割り当てられた登録番号を記載します。この登録番号がないと、納品書が証拠資料として対応できなくなってしまうため、必ず記載しましょう。 登録番号は、アルファベットの T と 13桁の半角数字で構成されています。 |
|
(8)適用税率 (4)で分けた内容に、適用する税率を記載します。税率は、8% と 10% に分けられるため、この税率を忘れずに明記しましょう。 |
|
(9)それぞれの消費税額 適用税率ごとに分け、合計した際の消費税を記載します。 |
納品書のルール
インボイス制度が施行されることにより、これまでの納品書の記載事項に加えて、下記 3点の記載が必要です。記載事項が明記されていれば、インボイス制度に対応した納品書となります。
【インボイス制度の施行で記載が必要な項目】
・納品書の発行元の登録番号
・対価の額に対する適用税率
・適用税率ごとに分けた消費税額
インボイス制度を知り、上記のルールを守って正しく納品書を作成しましょう。
Web制作の機能が充実している法人向けレンタルサーバー
>>サービスの詳細を見てみる
納品書作成・発行時の注意点
納品書の作成や発行にあたって、注意するべきポイントは4つあります。
- 発送商品の日付は「出荷日」
- 納品書は出荷・発送する商品に同封する
- 納品書への印鑑はなくてもいい
- 電子データがおすすめ
上記について、1つずつ解説します。
発送商品の日付は「出荷日」
商品を発送する際の日付は、一般的に「出荷日を記載する」とされています。
配送で商品を届ける場合、配達業者や交通状況、また受け取る側の不在などによって、予定していた納品日から遅延が生じることもあります。
発送元が到着日を正確に把握するのは難しく、到着日に合わせて納品書を発行することはできません。そのため、商品を発送する場合の納品書の日付は、商品の出荷日を記載するようにしましょう。
納品書は出荷・発送する商品に同封する
納品書は、商品を出荷・発送する際に同封しましょう。注文側が、納品書の内容を見ながら、注文内容の不備などがないかを確認できるようにするためです。
また、納品するタイミングによって、注文側へ発行する請求書を併せた「納品書兼請求書」や、納品の際に入金が済んでいるものであれば 「納品書兼領収書」など、納品書と請求書または領収書をあわせて発行することもあります。
1枚にまとめることで、後日発送する手間がなくなることやコストが削減できるというメリットがありますが、その際には、記載事項に漏れがないように注意しましょう。
納品書への印鑑はなくてもいい
納品書への印鑑は、基本的になくても問題ありません。ただし、日本においては、注文側や取引先のルールとして「印鑑が押されていない納品書は認めない」としていることも多くあります。
納品書の発行は電子データがおすすめ
現在では、アプリやシステムの発達により、PDF などの電子データで納品書を作成することができます。紙を使わないため、コストの削減や紙による保管スペースが不要となるなどのメリットから、電子データを利用している会社も少なくありません。
しかし、取引先によっては紙での発行を希望されることもあるかもしれません。
納品書を自社で保管するときは電子データを利用し、取引先の希望によっては紙を発行するなどの柔軟な対応をおこないましょう。
【インボイスに関するほかの記事はこちら】
インボイス制度は副業をしている人にどう影響するのか
会社設立時のメールアドレス作成なら「さくらのメールボックス」
>>サービスの詳細を見てみる



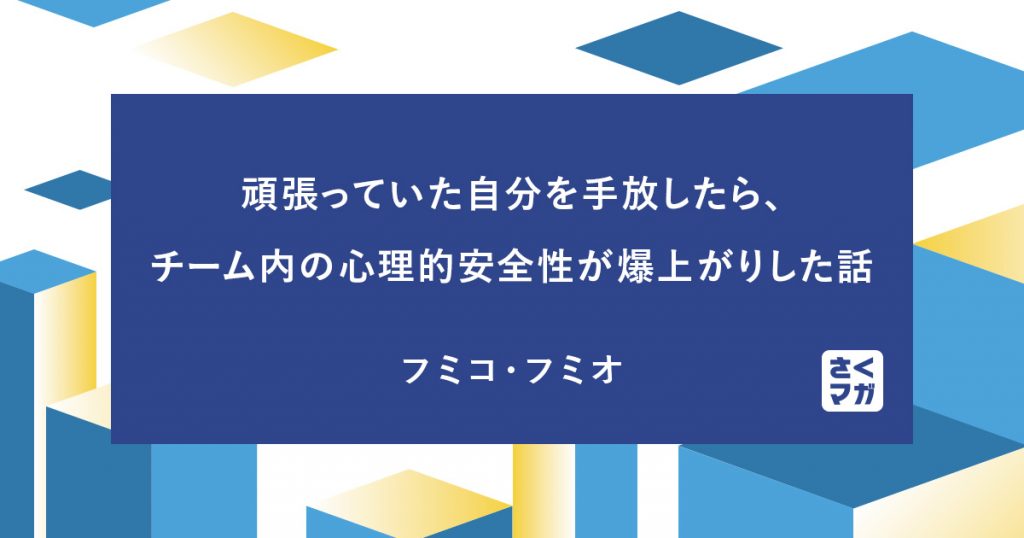

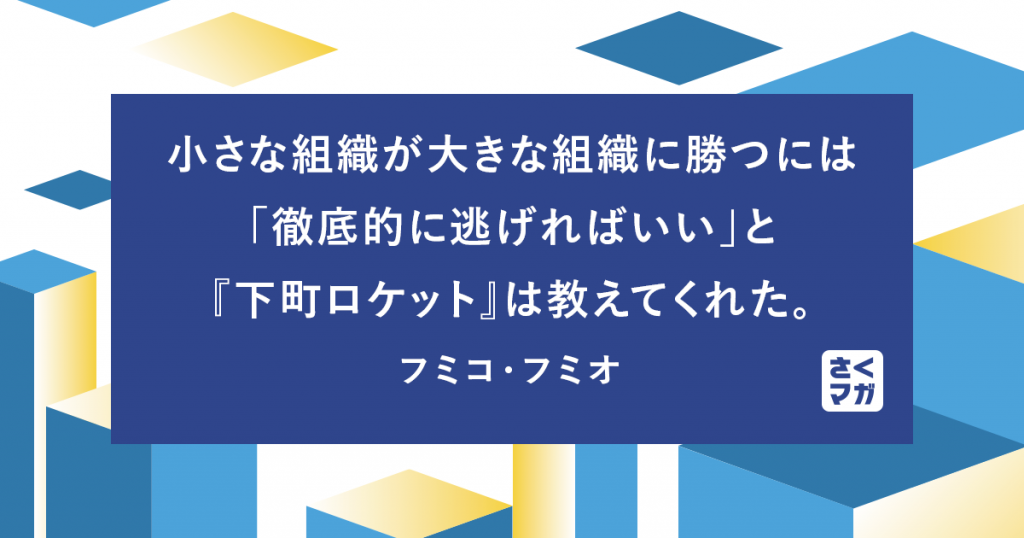
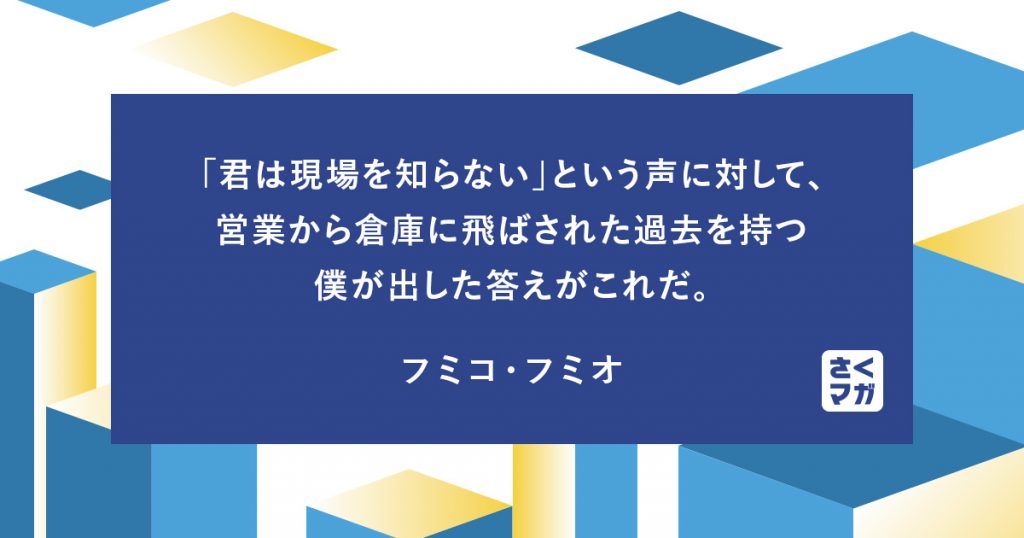
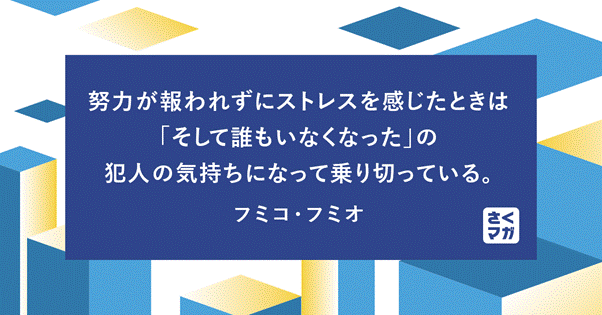
 特集
特集




