ビジネスパーソンに役立つコラムを読んでスキルアップ&隙間時間を有効活用
>>さくマガのメールマガジンに登録する
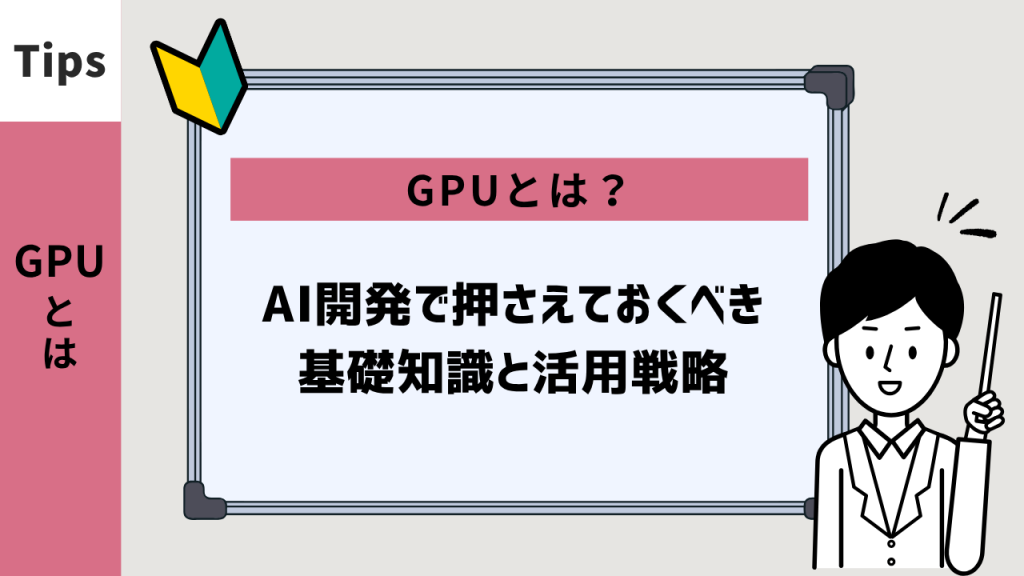
近年、ChatGPTをはじめとする生成AIの急速な普及にともない、AI開発での「GPU」の重要性がいっそう高まっています。AIプロジェクトの企画・推進者や、これからAI分野に取り組む初学者が、GPUについて知りたいことは多数あるでしょう。たとえば、GPUがなぜ不可欠なのか、どう選べばよいのか、効率的に活用するにはどうすればよいのかといった点が挙げられます。
本記事では、AI開発に関わる企画者や初学者の方に向けて、GPUの基礎知識から選定のポイント、クラウド活用方法、コスト管理まで実践的な観点でわかりやすく解説します。

さくらインターネットが提供している高火力シリーズ「PHY」「VRT」「DOK」を横断的に紹介する資料です。お客様の課題に合わせて最適なサービスを選んでいただけるよう、それぞれのサービスの特色の紹介や、比較表を掲載しています。
1.GPUとは?AI開発で注目される理由
AI開発におけるGPUの基礎知識とその重要性を、技術的背景から実際の活用分野まで整理して解説します。
1-1.GPUの定義とCPUとの違い
GPU(Graphics Processing Unit)は、コンピュータの画像処理を専門に担う演算装置です。CPU(Central Processing Unit)が複雑な処理を順次実行するのに対し、GPUは単純な計算を大量に並列で処理できるよう設計されています。
具体的には、CPUが数個〜数十個のコアを持つのに対し、GPUは数百〜数千個のコアを搭載しています。CPUは制御や複雑な演算に強い一方、GPUは行列計算など単純演算の大量並列処理で圧倒的な性能を発揮します。この特性こそがAI開発での決定的な強みです。
1-2.GPUがAI開発に使われるようになった背景
GPUがAIに活用されはじめた契機は、2012年に開催された画像認識コンテスト「ILSVRC」(ImageNet Large Scale Visual Recognition Challenge)での出来事です。トロント大学のジェフリー・ヒントン教授らのチームが、NVIDIA製GPUを用いたディープラーニング手法により、従来手法を大幅に上回る認識精度を達成しました。このモデルは「AlexNet」と呼ばれ、現在のAIブームの起点とされています。
それまでのAI研究ではCPUによる処理が主流でした。しかし、2012年の成功をきっかけに「GPUの並列処理能力がAI開発に革命をもたらす」ことが実証されたのです。以来、GPUメーカーはAI向け機能を積極的に強化し、現在では重要な技術基盤となっています。
1-3.AI処理におけるGPUの強みと活用分野
なぜGPUがAIに適しているのか
GPUはもともと、3Dグラフィックス処理を高速化する目的で開発された技術です。3Dグラフィックスでは、移動・回転・拡大縮小といった行列演算や、大量のピクセルに対する色計算やライティング処理など、同じ演算を大量のデータに対して並列に実行する必要があります。GPUは、こうした処理を効率化するよう設計されています。
ディープラーニングの分野でも、大量のデータに対して行列演算を繰り返し実行する必要があり、その処理パターンはGPUの特性と非常に相性が良く、GPUの性能を最大限に活用できます。
たとえば画像認識モデルの学習では、数万枚の画像データに対して畳み込み演算を並行して実行する必要があり、GPUの大規模な並列処理能力が大きな効果を発揮します。
この処理をCPUでおこなうと、順次処理となるため数日〜数週間かかることもありますが、GPUを用いれば同じ処理を数時間〜数日で完了させることが可能です。また、推論処理においても、リアルタイム応答が求められるWebサービスや画像解析システムではGPUの高速処理能力が不可欠です。
GPU活用が進む主要分野
- 画像認識:自動運転車の物体検出、医療画像診断、製造業での品質検査など。とくに動画解析やミリ秒単位の判定が求められる用途ではGPUなしでは実現困難です。
- 自然言語処理:ChatGPT、Gemini、ClaudeといったAIサービスに使われている大規模言語モデル(LLM)の学習や運用には、GPUが不可欠です。これらのサービスの背後では、膨大なGPU計算リソースが投入されています。1つのモデルを学習させるのに、数万時間分のGPU時間が必要となるケースも珍しくありません。
- 新興分野:音声認識・合成、動画生成、創薬支援など。従来は専門家の知識に依存していた領域でも、GPUを活用したAIシステムが実用化されています。
2.AI開発に適したGPUの選び方
AI開発におけるGPU選定では、処理の種類や用途を正しく理解することで、性能とコストの最適化が図れます。ここでは、学習と推論の違いから、具体的なGPUの選定基準までを解説します。
2-1.学習/推論に必要なGPU要件
AI開発には「学習(トレーニング)」と「推論(インファレンス)」という2つの処理段階があり、それぞれ求められるGPUの要件が大きく異なります。
学習段階の要件
学習段階では、大量のデータをもとにモデルのパラメータを最適化するため、広大なメモリ 空間と処理能力が必要です。学習プロセスでは、数時間〜数日間にわたって連続的に計算がおこなわれ、大きなバッチサイズでデータを処理することで効率が向上します。そのため、大容量の VRAMと高い演算性能を備えたGPUが求められ、一般的に最も高スペックなGPUを必要とする処理といえます。
推論段階の要件
推論段階では、構築済みモデルを用いて予測や判定をおこないます。学習段階ほどの高スペックは不要ですが、リアルタイム性が求められるWebサービスでは処理速度が重要です。また、複数ユーザーからの同時リクエストに対応する場合には、GPUの並列利用による負荷分散や、処理効率の最適化を考慮した設計が必要になります。
2-2.押さえておくべき基本指標
GPU選定時に重要な技術指標を理解していると、より的確な判断が可能です。
メモリ容量(VRAM)
GPU選定でもっとも重視すべき指標のひとつがメモリ容量(VRAM)です。メモリ容量が実行可能なAIモデルのサイズに影響するため、扱いたいモデルに応じた十分な容量を確保する必要があります。
処理性能(FLOPS)
GPUの処理性能については、一般的に浮動小数点演算性能(FLOPS)によって評価されます。ただし、演算フォーマット(FP32、FP16、INT8など)によって処理性能は 大きく異なるため、注意が必要です。最近のGPUは、AI処理に最適化されたTensor演算機能を備え、FP16やINT8での高速処理が可能です。企画者の立場では、「前世代に比べてどの程度高速化されているか」といった相対的な観点で比較すると実用的です。
消費電力
高性能GPUほど電力を多く消費するため、性能とのバランスを考慮した選定が求められます。クラウドGPUでは電力コストが利用料に含まれますが、自社運用の場合は電力・冷却のコスト負担も考慮する必要があります。
2-3.用途別の基本的なスペック目安
実際のプロジェクトでGPUを選定する際の参考として、主なAI用途別のスペック目安を紹介します。
画像認識用途
一般的な画像分類タスクであれば、8GB程度のメモリで対応可能ですが、4K動画のリアルタイム解析や医療画像処理などでは、16GB以上が目安となります。バッチ処理が中心で時間的余裕がある場合は、より多くのデータを一度に処理できるようメモリ容量を優先することで、コスト効率を高められます。
自然言語処理用途
数十億パラメータ規模のモデルでは16〜32GB、数千億パラメータの大規模モデルでは64GB以上、あるいは複数GPU構成が必要です。ただし、企業利用では事前学習済みモデルのファインチューニングや推論が中心であるため、比較的小規模なGPUでも十分対応可能なケースが多いです。
研究・実験用途
新しいアルゴリズムの検証やプロトタイピングでは、中程度のスペックからはじめ、必要に応じてスケールアップできる構成が理想です。予算制約がある研究機関では、共有利用を前提としたクラウドGPUの活用が効果的です。
2-4.クラウドGPUサービス選定時の基本的な比較ポイント
クラウドGPUサービスを選ぶ際は、性能や料金だけでなく、運用面の要素も含めて比較検討することが重要です。
GPUの種類と性能
まずは提供されているGPUの種類と性能を確認しましょう。主要なクラウドサービスでは複数のGPUオプションがあり、用途や予算に応じた柔軟な選定が可能です。最新世代のGPUは性能とコスト効率に優れている傾向がありますが、旧世代でも使用目的によっては十分なケースがあります。
料金体系
料金体系には、時間課金制、月額固定制、従量課金制などがあり、利用スタイルに合わせた選択が重要です。短期間の集中的利用には時間課金制、長期間の安定利用には月額固定制が適しています。利用計画を明確にしたうえで、最適な料金体系を選びましょう。
ネットワーク・サポート体制
大量のデータをクラウドに転送する場合、転送時間やデータ転送コストも考慮が必要です。また、日本国内での提供の有無、日本語でのサポート対応、セキュリティやコンプライアンス(例:SOC2、ISO27001など)への対応状況も確認しておくと安心です。
3.AI研究・開発を効率化するクラウドGPUの活用戦略
高性能GPUの導入・運用には多額の初期費用と専門知識が求められます。ここでは、それらの課題を解決する手段としてクラウドGPUを戦略的に活用する方法を紹介します。
3-1.クラウドGPU活用のメリットと導入効果
自社構築と比較しながら、クラウドGPUが選ばれる理由と期待される効果を説明します。
変動する計算需要への柔軟な対応
AI開発ではプロジェクトの段階によって計算リソースの必要量が大きく変動します。実験段階では小規模GPUで十分でも、本格学習では高性能GPUが数日単位で必要になる場合があります。クラウドGPUなら、都度必要な性能のGPUを利用でき、柔軟に対応可能です。
自社環境との比較
自社構築では、数百万円〜数千万円の初期投資が必要で、最大負荷を前提とした機器構成になるため、稼働率の低い期間でもコストが発生します。また、機器の陳腐化や運用ノウハウの確保も課題です。
クラウドGPUなら初期投資不要で、最新世代のGPUを必要なときに利用できます。短期プロジェクトや実験用途に適しており、段階的に自社環境へ移行するハイブリッド戦略にも有効です。
3-2.ハイブリッド構成の活用
データの性質や処理の特性に応じてオンプレミスとクラウドを使い分けるハイブリッド構成では、オンプレミスとクラウド両方のメリットを最大化できます。個人情報である顧客データや知的財産に関わる学習データは自社環境で処理し、大規模な計算が必要な実験や検証作業はクラウドGPUを活用するという使い分けが一般的です。
また、開発フェーズに応じた使い分けも効果的です。アルゴリズムの試行錯誤が中心となる初期開発段階ではクラウドの柔軟性を活用し、安定した本番運用が必要になった段階で自社環境に移行することで、開発効率とコスト効率を両立できます。平常時の処理は自社環境でおこない、繁忙期やピーク処理時のみクラウドで台数を増やすという運用も可能です。
ハイブリッド構成の運用では、データの一貫性管理とセキュリティポリシーの統一が重要な注意点です。複数環境間でのデータ同期やバックアップ戦略、アクセス制御の統合管理など、システム複雑化に伴う管理コスト増大を適切に見積もったうえで導入を検討しましょう。
4.AI開発でGPUコストを無駄にしないための基本的な考え方
GPUは高額なリソースであり、クラウドGPUでは使用時間に応じた課金となるため、効率的な利用計画と運用管理が重要です。
4-1.開発・検証・本番環境でのGPUリソース配分
GPUリソースの使い方は、開発・検証・本番という各フェーズで異なる要件に応じて最適化する必要があります。それぞれの段階に応じた適切な配分によって、パフォーマンスとコストの両立を実現できます。
開発環境の最適化
開発段階では、デバッグや試行錯誤が中心となるため、高スペックよりも起動・停止の柔軟性が重視されます。小規模なGPUを複数用意し、並行作業を促進する構成が理想的です。
検証・本番環境の設計
検証では、本番に近い条件でのテストが求められるため、同等またはやや控えめなスペックが適しています。一時的な利用にとどめ、オンデマンド方式で運用することでコストを抑えられます。本番環境では、サービス要件に応じたスケーリング設計がカギとなります。
4-2.チーム開発でのGPUリソース共有
複数人が関与するAI開発では、GPUリソースの共有が避けられません。効率的な運用を実現するには、競合の回避や運用ルールの整備が重要です。
リソース競合の回避
チームでGPUリソースを共有する場合、リソース競合によってプロジェクト全体の効率が低下する可能性があります。利用スケジュールや優先度設定を明確にし、重要度の高いタスクに優先的にリソースを割り当てて、実験的な作業は負荷の低い時間帯に実行するといった運用ルールを整備することが重要です。
自動化による効率化
リソースの長時間占有を防ぐため、最大利用時間の制限や自動停止機能の導入が有効です。クラウド環境ではオートスケーリングを活用し、必要な処理だけにリソースを割り当てる構成が効果的です。
4-3.AI開発プロジェクトでのコスト管理
限られた予算内でAI開発を成功させるには、GPU利用にかかるコストを継続的に可視化・最適化することが不可欠です。
利用状況の可視化
どの処理にどれだけのGPUが使われているかを定期的に可視化することで、リソースの無駄を把握しやすくなります。また、処理完了後の自動停止を設定しておくと、不要な課金を防げます。
予算管理と最適化
予算上限の設定やアラート機能を活用し、想定外の支出を防ぎましょう。開発段階ではコストを抑え、本番直前に高性能GPUを使うといった段階的なリソース活用も有効です。
また、スポットインスタンス(クラウド事業者の余剰リソースを安価で利用できるプラン)やリザーブドインスタンス(1年・3年といった長期間の利用を予約し割引を受けるプラン)といった料金プランを活用することで、継続的なコスト最適化が可能です。
まとめ
本記事では、AI開発におけるGPUの基礎知識から実践的な活用法まで、企画担当者や初学者が理解しておくべきポイントを解説しました。GPUはAI開発に不可欠な技術基盤であり、その選定と運用方法によって開発の効率や成果が大きく左右されます。
とくに重要なのは、プロジェクト要件に応じて、学習と推論の違いを正しく理解したうえで、コストと性能のバランスを考慮して適切なGPUを選ぶことです。クラウドGPUを活用することで、初期投資を抑えて最新の環境を柔軟に利用できます。また、クラウドとオンプレミスを組み合わせたハイブリッド運用も効果的です。
さくらインターネットの「高火力GPUシリーズ」では、AI開発に最適化されたGPUクラウドサービスを提供しています。従量課金制により無駄なコストを抑え、プロジェクトの規模に応じて柔軟に調整できる環境をご利用いただけます。AI開発でGPU活用をご検討の際は、ぜひ一度ご相談ください。専門スタッフが、プロジェクトに最適なソリューションをご提案します。

さくらインターネットが提供している高火力シリーズ「PHY」「VRT」「DOK」を横断的に紹介する資料です。お客様の課題に合わせて最適なサービスを選んでいただけるよう、それぞれのサービスの特色の紹介や、比較表を掲載しています。



 New
New
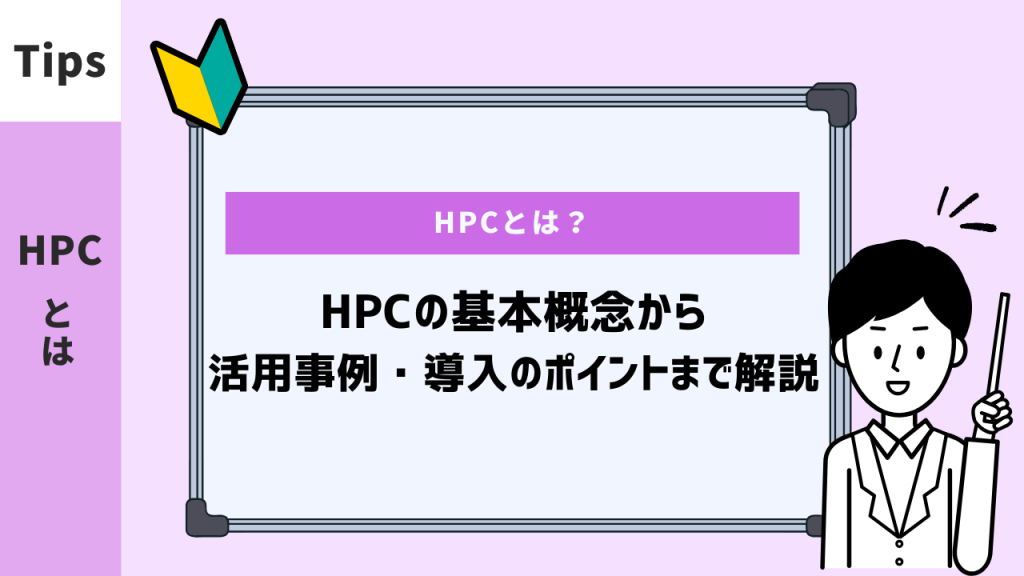 New
New
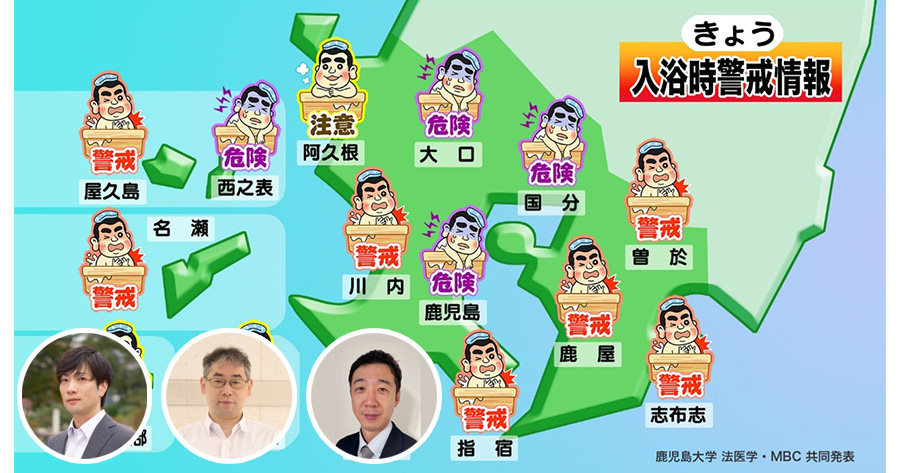 New
New

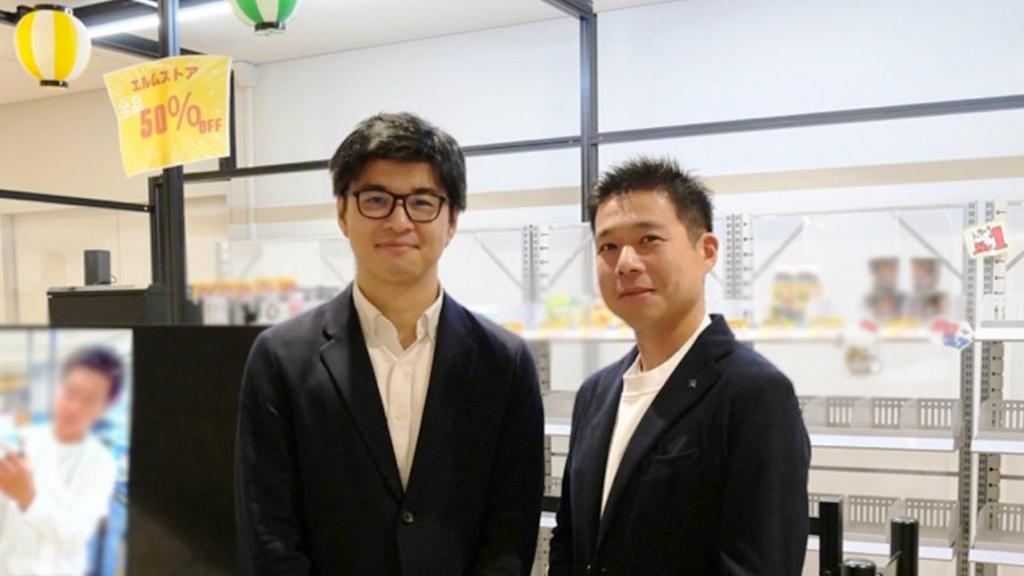
 特集
特集




