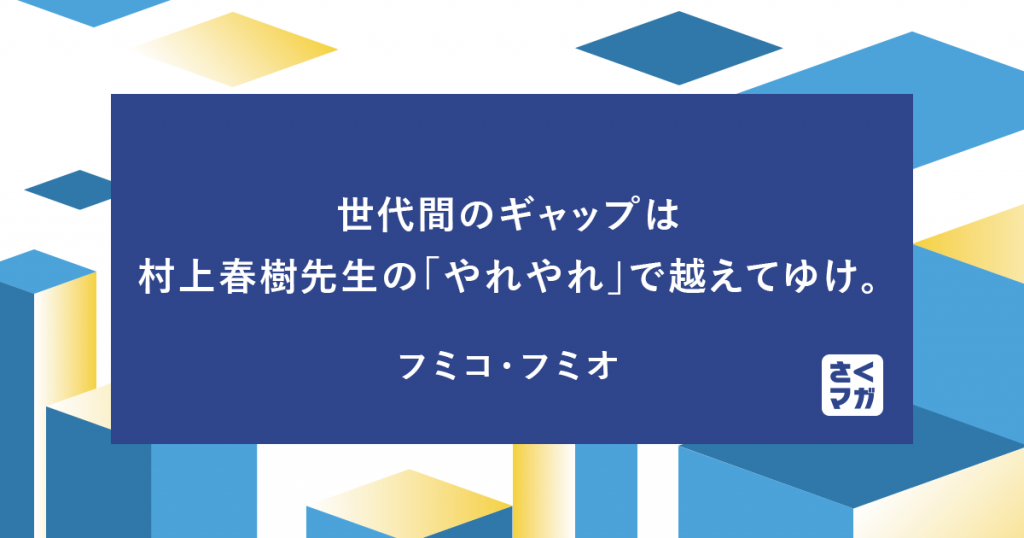
ビジネスパーソンに役立つコラムを読んでスキルアップ&隙間時間を有効活用
>>さくマガのメールマガジンに登録する
世代が気になる。
村上春樹先生はエッセイ集『職業としての小説家』(新潮文庫)のなかで「世代に優劣はない」と述べている。完全同意だ。同エッセイ内で先生は「世代には違いがあるだけ」とも言っている。まさに「世代の違い」が仕事を進めるうえで、障害になったり、トラブルのもとになったりするなどして問題になる。そのため、理屈では優劣はないとわかっていても世代を無視することはできないのである。
僕は1970年代前半生まれ、いわゆる「氷河期世代」「団塊ジュニア世代」だ。最近「見捨てられた」世代と言われているが、個人的には「見捨てられた」という認識はない。可もなく不可もなくといったところだ。ただ、同じ世代で苦しんでいる人たちを他人事とは思えない。そう思うのは、彼らが「違うルートを歩んできたもうひとりの自分」だからだ。僕がやってこられたのは、ごくごく平凡な多少の努力と我慢を除けば、運が良かっただけだ。ちょっと強い風に吹かれていたら僕も落ちていただろう。
世代が気になる人は多い。そのため、SNSやWebメディアで「Z世代」「氷河期世代」のような特定の世代を切り取ったトピックが話題になる。たまに炎上することもある。自分の属する世代だけでなく、ほかの世代がどういう考えをしているのか気になるのだ。先行きの見えない不安定な時代だ。同じ世代に共感したり、違う世代との相違を確認したりするなどして、世代にアイデンティティーを見出して安心を得ようとしているのかもしれない。
同世代とのコミュニケーションは楽。
自分と同じ世代に連帯感や興味を持つのは、「違うルートを歩んだもうひとりの自分」を彼らに見出すからだ。たとえば、スポーツ選手や芸能人のような有名人でも、自分と同年代の人物には「この人同じ年齢なのか。これから注目しよう」と親近感を持ったり応援したりする。活躍していると少しうれしくなる。逆に、対抗心や嫉妬心を抱くこともあるかもしれない。
実際、ほかの世代はよくわからない。通過してきた時代や空気感が違うからなのか、会話をしていてもギア比が違うように嚙み合わない。弾まない。同じ世代なら多くの言葉を要せずとも「あれだよあれ」みたいな感じで意思の疎通ができるが、ほかの世代との会話では「私たちのころはこれこれこんなことがあってですね」と前提と背景から細かく説明する必要があって、面倒くささが勝ってしまうのだ。
学生なら、だいたい同じ年代の人間が集まっているから世代の違いを感じることは少ない(飛び級の天才や留年生は除く)。だが、社会に出るとそうはいかない。会社や取引先にはあらゆる世代の人間が属して働いているからだ。同世代間の楽なコミュニケーションだけではクリアできない。
社会人になっても、新卒なら「同期」という同じ世代のグループに属することになる。中途入社であっても、同じ年代の人間とはコミュニケーションが取りやすいために近い関係になりがちだ。言葉を尽くして説明する必要がないから付き合いが楽だ。だいたい似たような経験をしてきているので会話のネタに困らない。それに比べるとほかの年代との付き合いは少々ハードルが高くなる。言葉を尽くして説明してもうまく伝わらない。こうして、「新人が何を言っているのかわからない」「上司が何を伝えたいのか、結局よくわからなかった」といった悲劇が起きてしまうのだ。
年代を超えてのコミュニケーションはストレス製造機。

同じ年代の人たちとだけストレスフリーにやっていけたら苦労はしないが、仕事ではそうはいかない。ストレスと面倒くささを覚えながら、いろいろな世代の人たちと付き合っていくことになる。しかし、人間は楽なほうへ流されるため、ともすると付き合いやすい人たちで仕事を進めていくようになる。最悪のケースは、特定の年代が組織内の実権を握り、そのグループ内の利益を最優先する状態に陥ることだろう。
現代の若者は、積極的に上の世代の話を聞くことを「かったるい」と感じるらしい。意見や助言を叱責ととらえる人もいるようだ。経験や実績を伝えようとすると「話長くなります?」「要点まとめてもらえますか」と話を遮られた経験が僕にもある。世代を超えて言葉を尽くして説明するという方法は、タイパが悪い方法とされている(らしい)。コミュニケーションを無理強いできない。ハラスメントになりかねないからだ。それに、上司の立場から若者の魂を動かそうと熱い話をして「それ仕事に直接関係ないですよね」と返されてショボーンな気分をこれ以上味わいたくない。
世代を超えて協力して仕事をしなければならないがコミュニケーションは難しくなるばかりだ。こういった面倒くささとストレスを感じるコミュニケーションは「これも仕事のうち」と割り切るしかなかった。これまでは。しかし、デジタルテクノロジーを活用すればこうした問題はクリアできそうだ。
生成AIなどのデジタルテクノロジーは世代間コミュニケーションの救世主だ。
仕事をするうえで世代を越えたコミュニケーションは不可欠だ。しかし面倒だ。タイパも悪い。強引な対話はハラスメントで訴えられる危険性もある。ストレスも大きい。同じ世代の小さいサークルでは、大きなプロジェクトをこなすことはできない。ほかの世代のニーズを的確に拾い上げることも難しくなる。仕事は行き詰まる。
生成AIなどのデジタルテクノロジーを活用すれば、そのようなストレスはかなり軽減されるようになるはずだ。生成AIに特定の世代の傾向をまとめてもらったり、データ分析させたりすれば、わざわざほかの世代の同僚と意見を交換する手間とストレスからは解放されるようになる。先輩社員がもったいぶって話そうとしない経験やノウハウも、AIにまとめてもらって体系的に整理しておけばいい。
仕事においてほかの世代との付き合いは不可避だが、仕事でストレスを抱えて命を縮めるのは本末転倒である。仕事とは生きるための手段だからだ。もちろん、デジタルテクノロジーがすべての世代間問題を解決できるわけでない。上司に対してプロジェクトの予算取りのための社内交渉などの業務は、秘書ロボが代行してくれる未来が到来するまでは我々がやるしかない。せめて今年中には、ノートパソコンの画面を見せて「社長、今回のプロジェクトの疑問点については直接AIにご質問ください」と言えるようなレベルに到達するまで世界のデジタル技術者には研究を頑張ってもらいたい。
効率化が進んだ世界は、「やれやれ」で失敗を流してあげよう。

デジタルテクノロジーによって、経験やノウハウを伝える、上司先輩からの助言は不要になる。経験やノウハウは、会社の財産としてデータとして蓄積していくことになり、属人的な要素は消滅する。上司や先輩の、思わせぶりな言葉から経験や技術を学ぶより、わかりやすい動画で学んだほうが効率的だ。お互い、ノーストレス。とてもよい。唯一の問題は上司や先輩という存在が軽くなることくらいだろう。
同時に若手が超えるべきハードルも上がる。若手ならではの経験不足や技術不足といった逃げ道はなくなるからだ。「動画マニュアルに全部あっただろ? 何で目を通していないの?」と詰められるようになる。テクノロジーに先人としての尊厳を奪われた上司や先輩たちはここぞとばかりに責めてくるはずだ。「俺たちの時代にはこのような便利なツールはなかった」「活用できなかったらただの技術の無駄にすぎない」と。若い世代は、デジタル技術を使いこなせない上の世代を「時代遅れの役立たず」と陰口を叩くようになる。
このように、人間対人間のコミュニケーションで発生していたストレスは、デジタルテクノロジーを介して違ったものになる。より厳しいものになる。そこで僕らは世代間にあるコミュニケーションの難しさが、緩衝材のようになっていたことに気づく。これまで「氷河期世代は陰気くさいよねー」「Z世代は何を考えているのかわからない」そういったやりとりで世代を悪者や逃げ道にしていたのだ。これからは、より直接的に能力や成果を相手に査定される。世代から解放されて実力を評価されるのだ。
しかし、逃げ道がないのは息苦しい。うまくいかなかったときは世代のせいにして本人の責任を薄めてあげることも必要になるだろう。正論で詰めすぎると相手の心を折ってしまうかもしれない。そのときは世代の出番だ。ゆとり世代だから、Z世代だから、と世代を悪者にして、「やれやれだ」と村上春樹流に肩をすくめて、失敗した本人の責任を軽く見てあげる。そういった隙をつくることもこれからは必要なのではないかと思う次第である。

執筆
フミコ・フミオ
大学卒業後、営業職として働き続けるサラリーマン。
食品会社の営業部長サンという表の顔とは別に、20世紀末よりネット上に「日記」を公開して以来約20年間ウェブに文章を吐き続けている裏の顔を持つ。
現在は、はてなブログEverything you’ve
ever Dreamedを主戦場に行き恥をさらす
Everything you've ever Dreamed : https://delete-all.hatenablog.com/
2021年12月にKADOKAWAより『神・文章術』を発売。
※『さくマガ』に掲載の記事内容・情報は執筆時点のものです。
- SHARE


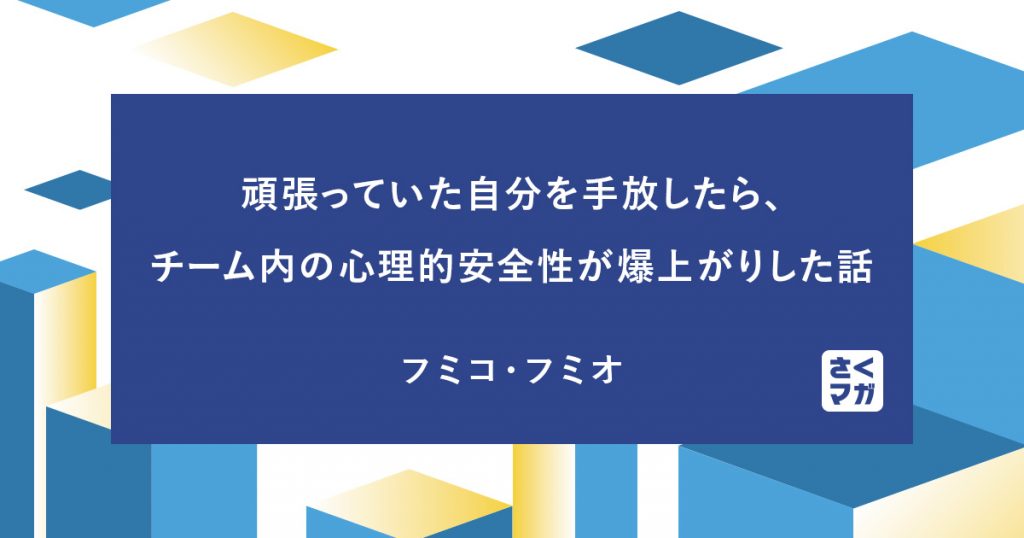

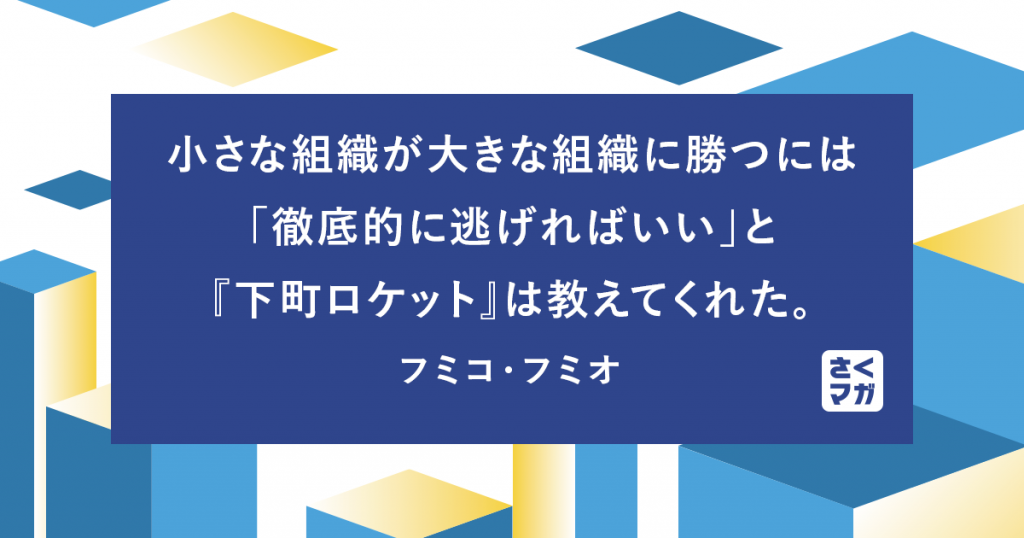
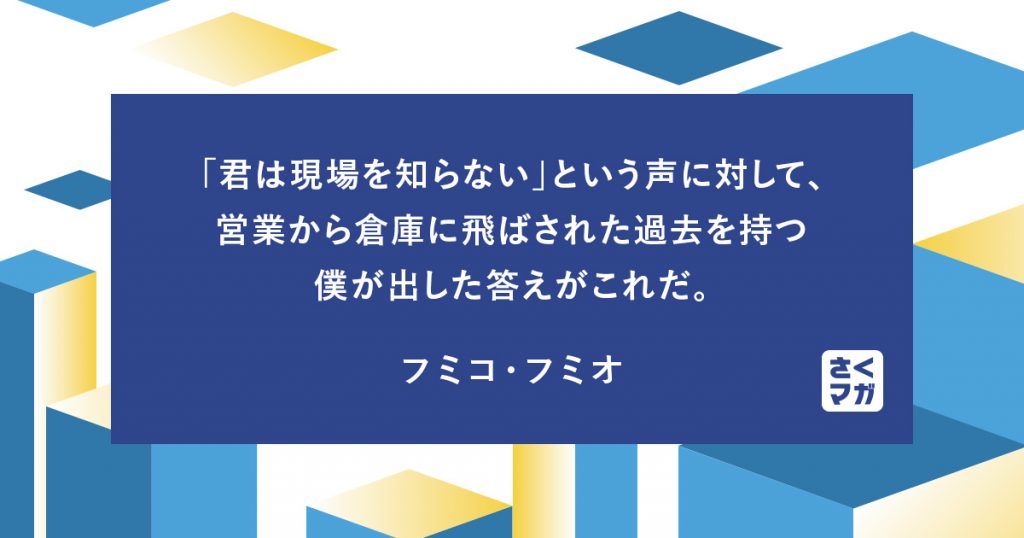
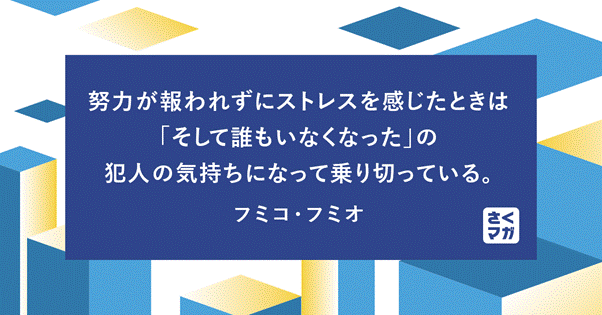
 特集
特集




