ビジネスパーソンに役立つコラムを読んでスキルアップ&隙間時間を有効活用
>>さくマガのメールマガジンに登録する
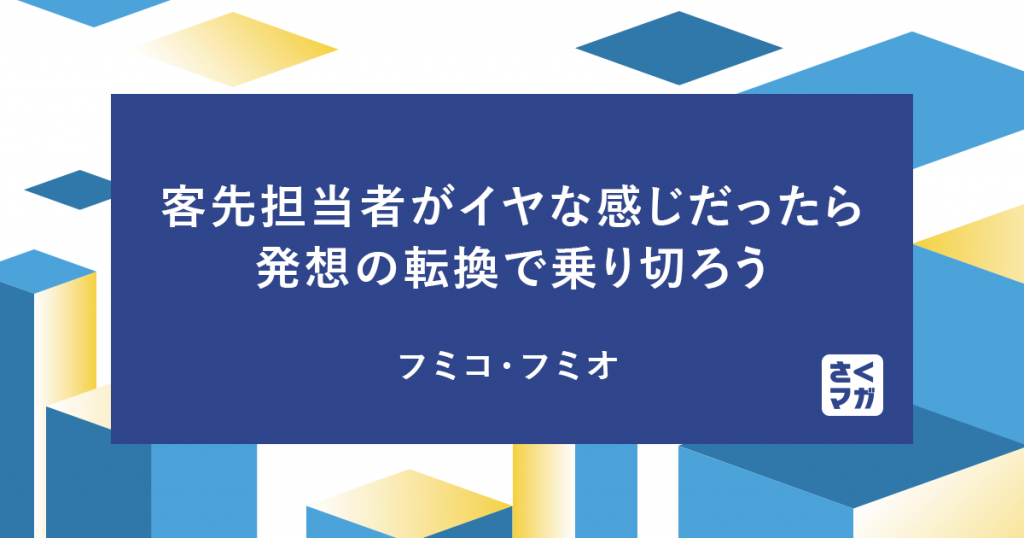
異動は必ずしもポジティブなものとはかぎらない。
早いもので今年も4月。季節は春だ。新卒入社、転職、異動等により新たな環境で仕事をはじめる人が多い季節である。勤務先に加えて取引先や関係会社の異動も集中する。「4月から御社を担当させていただくことになりました。営業五課のホニャララです」といったあいさつがあちこちで繰り広げられていることだろう。
異動には、フレッシュな新風を入れ、新たな気持ちで仕事に向き合えるようになる効果がある。しかしよいことばかりではない。なぜなら、よろしくない方向へ動く可能性もあるからだ。これまでいい感じに付き合えた担当者から新任に変わって、これまでどおりのやり方と雰囲気で仕事ができなくなった経験はないだろうか。
こちらがお金を支払う側で、取引業者の担当者がイヤな感じであれば、「ちょっと業務に支障が…」とやんわりクレームを入れて状況を改善できる。しかし、相手が大口取引先、クライアントの担当だったらそうはいかない。
「ご契約いただいて契約金もいただいているうえであえて申し上げますが、担当者さまとは意志疎通がうまくいかないので変えていただけませんか」
そんな言葉を口にしたら光ケーブルをつたってあなたの上司にクレームが入り「君には担当を外れてもらう」「これは査定に響くよ」と告げられ、あなたは悔恨の涙で枕を湿らせるのである。このようにイヤな客問題は働く人間共通のやっかいな問題なのである。
仕事マシンになってはいけない。
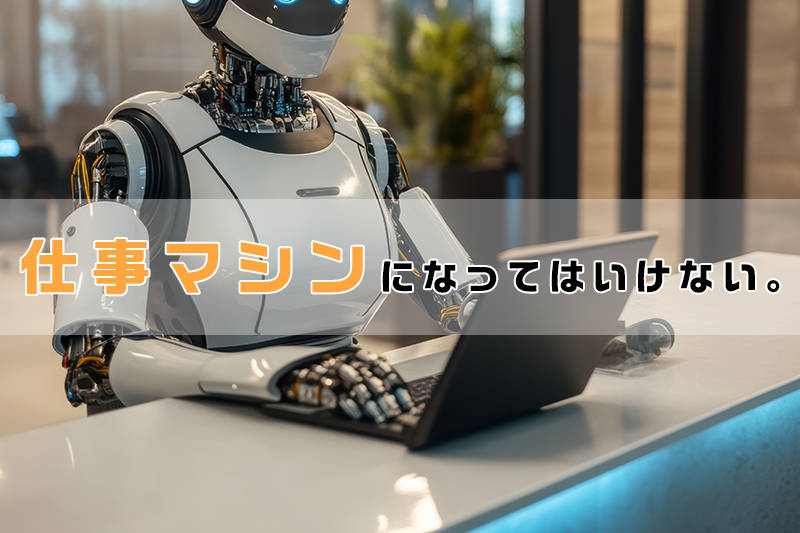
僕は、新規開発営業という仕事をしている。同僚の営業担当たちのなかには「この人苦手だ」と感じるセンサーが擦り切れた人がいる。センサーが擦り切れたから、長年、営業の仕事を続けてこられているようにも見える。なぜなら新規開発営業は、最初はあまりよい顔をされないからだ。
「いまは間に合っているけど、暇だから話だけは聞くよ」
「現在取引しているところより5割安ければ考えてもいい」
などと、プライベートでは子煩悩なパパっぽい顔面で非人間的な言葉を浴びせてくるイヤな人間が多いので、いちいち「この人イヤだな……」と感じているようでは仕事にならないのだ。
そのため、ベテラン営業担当になればなれほど、客先担当者にイヤな感じの人物が就いても、数秒後には落ち着きを取り戻し『羊たちの沈黙』のハンニバル・レクター博士のように抑揚の乏しい言い方で「いやあ。よろしくお願いします」とあいさつをするだけになるのだ。
第一印象の精度は低い。
このような昭和の仕事マシンになってはいけない。人間性を保ちつつ働いていくことが令和時代の働き方だ。イヤなお客にはどう対処すればいいのか、人それぞれ条件が異なるため、ケースバイケースで対応するほかない。これという特効薬はないのである。多くの人がイヤな客先担当者に悩んでいる現実こそ、特効薬がないことの証明だ。
ポイントは「仕事として割り切れるかどうか」になる。「人間は第一印象でほぼ決まる」という説があって、それはまあそのとおりではあるが、身も蓋もなさすぎである。プライベートなら第一印象で付き合う/付き合わないを決めればよい。積極的にイヤな人間を回避すべきだ。我慢がマネーにならないからだ。
しかし、仕事での付き合い、ましてや客先の担当者のイヤな感じを第一印象で忌避するのはすすめられない。少々乱暴な言い方になるが、イヤな相手と付き合うからお金になるのだ。仕事とは、人が「やりたくない」「手がかかる」「頼んだほうが楽」なことを引き受けるから、人がダルいと感じることを代理でおこなうからお金になるのである。つまり、イヤな相手と付き合うのは仕事の範疇になる。
このようなことを僕らは、理屈のうえではわかっている。それでも感情豊かな人間である僕らは、スパッと割り切れない。それで、第一印象で決めつけてしまう。しかし第一印象で客先担当者を忌避するとよろしくないのは先述のとおりである。そこで僕がご提案するのは「第一印象」期間の再設定だ。
最初に宣言しておきたいのは、第一印象はまったく全能ではないということである。ファーストコンタクトで正確な判定をするのは不可能だ。レディー・ガガが『ザ・フェイム』をリリースしたとき、僕はこれまでの経験と彼女から受けた第一印象からこれは売れないと判断したが、彼女はまたたく間にトップスターに登り詰めた。第一印象がいかに心もとないものなのかわかる好例だろう。なお、顔面の皮の厚い僕は「ガガは初っ端から売れると思ったよ。オーラがちがったもんねー」と言って過去を隠ぺいしている。これくらいの厚かましさがなければ社会の荒波は越えられない。
第一印象を「パッと見」で決めない。
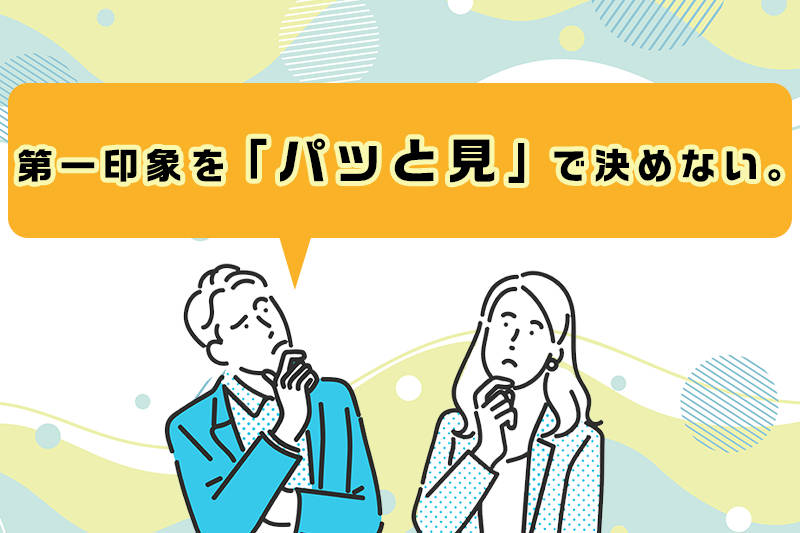
第一印象を決めるまで、初対面から3か月くらいのスパンを設定し、そのスパン内で相手を見極めることをおすすめしたい。3か月のうちにイヤな感じの客のイヤな部分もスルーできるようになるかもしれないし、僕も、ガガの人気も見極められたはずだ。
マンションの上に引っ越してきた人が、朝からドスドスひとり怪獣大行進をしている情景を想像してもらいたい。ちなみにこれは僕の実体験になる。うるさかった。イヤな感じがした。しかし、当時ジョン・レノンを愛聴していた僕は、マンションに国境線はないのさとイマジンの歌詞を思い浮かべ、文句を言いに行くのを控えた。何日か様子をみると、朝の決まった時間ごく短い間にドスドスやっていることに気が付いた。ドスドスのはじまりと終わりの時刻はつねにほぼ一定だった。僕はこのドスドスを朝の時計代わりにすることを思いついた。じつに便利だった。
こうして第一印象で耳障りだったドスドスの、イヤな感じは許容できるくらいにまで低減されたのである。こんなクソ体験でなくても、生前まったく売れなくて生活に困るレベルで困窮した画家が、晩年や死後評価されて大人気になることはときどき見聞きするエピソードである。このように人間の評価はあてにならない。ましてや評価対象のスパンが短いものはまったくあてにならないのだ。クソ退屈な画が数十年後に名画認定されるように。
とはいっても無理なものは無理である。
第一印象の評価対象の期間を延長したうえで、客のイヤな部分を仕事として割り切れるかどうかで判断する。要するに我慢できるかどうかである。何か月か付き合っているうちに自然と我慢できるようなものもあれば、どうにもならないものもある。たとえば、口癖はどれほどイヤなものであっても数か月で割り切れるようになる。20年くらい前に付き合いのあった担当者の口癖がイヤでしかたなかった。前後の文脈に関係なく、甲高い声で、会話の合間に「基本的な問題だよキミー」と口を挟んでくるのだ。
当初はそれがイヤで拒否反応から尻がかゆくなってしまうくらいであったが、数か月付き合ってみたら、その口癖を待ち構えている自分に気が付いた。イヤがスキに転換していたのだ。そのおかげで商談をまとめることができたのを覚えている。第一印象の判定期間の延長がスキを生み契約に結びついたのだ。
とはいっても、どうにもならないものはどうにもならない。数か月様子をみて、仕事と割り切れなければ、上司に相談してみよう。平成の世であれば、甘ったれたことを言うな、と一喝されるが、時代は変わった。従業員は守らなければならないものという意識が強くなった。それにクライアントとの関係が、イチ担当者の感じるイヤさが原因でこじれるようになれば上司の進退が怪しくなる。平均的な上司であれば、担当の交替等の対応が期待できる。
最初から上司に相談するのはおすすめできない。ファーストコンタクトでイヤだなと感じ即相談。精神衛生上は最高だ。だが、上司からみれば、「この部下は仕事に向いていないのでは?」「コミュニケーション能力に欠けるのでは?」と疑念をもたれてしまうからだ。
相手からイヤな人と思われているかもしれない。

人間関係は相互関係だ。僕らが客先の担当者にイヤだなと感じるのならば、同時に相手が僕らをイヤだなと感じている可能性もあるということ。もしかしたら、客先担当者も仕事だからとイヤイヤ付き合ってくれているかもしれない。それがちょっとイヤな態度にあらわれているのかもしれない。相手がそう考えているのではないかと疑いながら商談や面談に臨んでみてはどうだろう。
「相手が笑顔の裏で舌打ちをしているのかもしれない」「役職に忖度して付き合ってくれているがいち早くこの商談を終わらせたいと考えているかもしれない」「僕の加齢臭から一刻もはやく逃げ出したいと願っているかもしれない」
相手が僕に嫌々対応していると想定して仕事をしているのだ。この境地に到達すると、相手のイヤな部分が自分のイヤな部分で相殺される。お互いさまであり、第一印象などどうでもよくなるのである。
第一印象で相手を評価するのは一概に否定できない。ただその第一印象はそれほど正確なものではないことも知っておくべきだろう。なにかと即決がもてはやされる世の中だけど、それによって失っていることもあるかもしれないのである。いずれにせよ、無理しすぎはよろしくないので、自分の心と身体に正直になって自分が正しいと思う選択をしていけばいい。

執筆
フミコ・フミオ
大学卒業後、営業職として働き続けるサラリーマン。
食品会社の営業部長サンという表の顔とは別に、20世紀末よりネット上に「日記」を公開して以来約20年間ウェブに文章を吐き続けている裏の顔を持つ。
現在は、はてなブログEverything you’ve
ever Dreamedを主戦場に行き恥をさらす
Everything you've ever Dreamed : https://delete-all.hatenablog.com/
2021年12月にKADOKAWAより『神・文章術』を発売。
※『さくマガ』に掲載の記事内容・情報は執筆時点のものです。
- SHARE


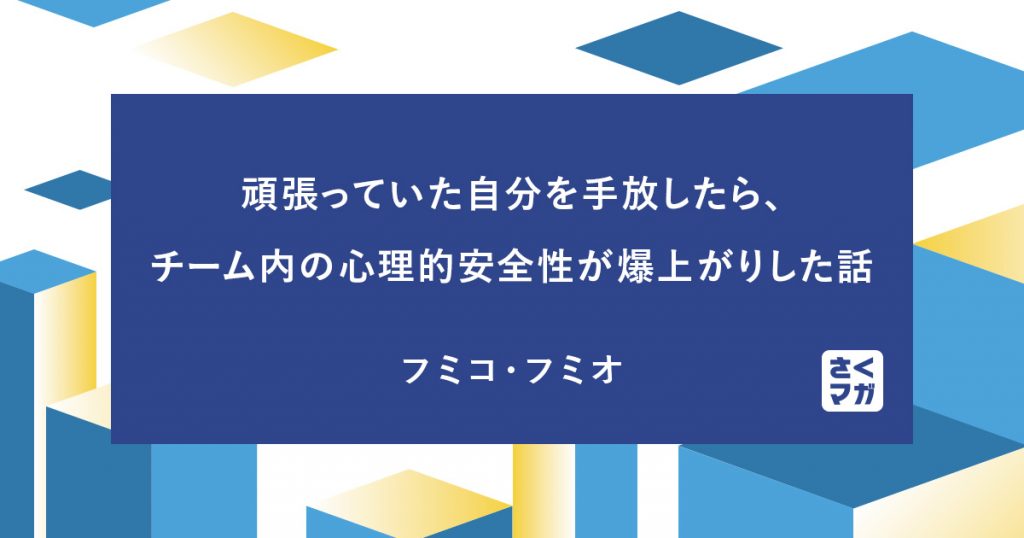

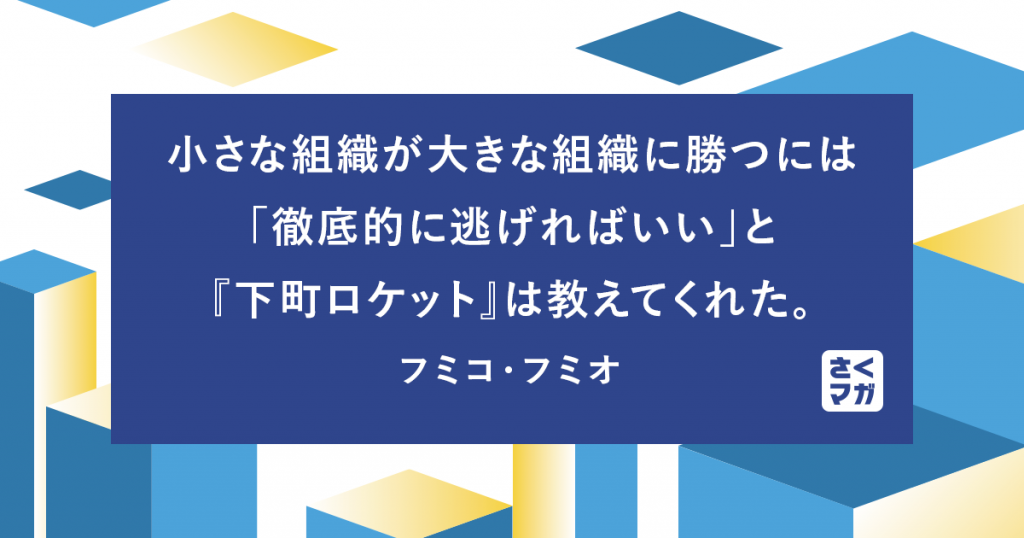
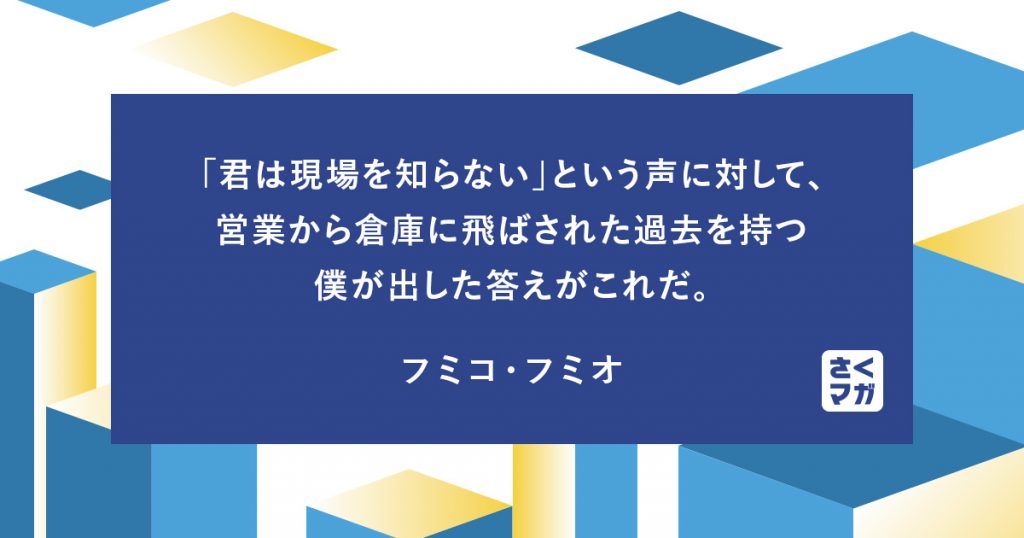
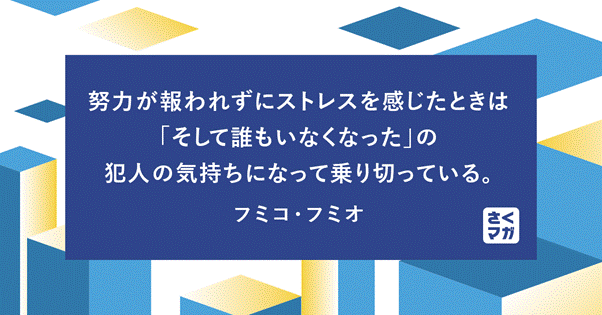
 特集
特集




