
ビジネスパーソンに役立つコラムを読んでスキルアップ&隙間時間を有効活用
>>さくマガのメールマガジンに登録する
ACジャパンのCMで信用と信頼を失うことの怖さを知る。
テレビで「なかやまきんに君」を見ない日はない。ヘビーローテーションだ。仕事中、食事中、ウォシュレット使用中、いついかなるときでも、なかやまきんに君の明るい声が響いている気がする。影響を受けやすい体質なので重苦しい空気の会議を打ち破るべく「パワー!」と叫んでしまうかもしれない。会社内での立場を失ったら、どうしてくれるのだろう。
このコラムを書いている2025年2月時点、地上波8チャンネルからほぼすべてのテレビコマーシャルが消え、代わりにACのコマーシャルが流されている。なかやまきんに君のCMもそのひとつ。僕自身は、地上波8チャンネルの愛好者ではない。特別な思い入れもない。お世話になっているのは、目が覚めそうなタイトルの朝の情報番組(そのなかの愛犬紹介コーナー)と日曜夕方の海産物の名前を登場人物に付けた長寿アニメとスーパーサイヤ人が活躍するアニメくらいだ。そんな僕の目にも、8チャンネルでACが大量オンエアしているように映っている。365日24時間体制で地上波8チャンネルを視聴している重度の8マニアが心配だ。
8チャンネルトップたちの10時間超に及んだ会見でも、スポンサー離れに歯止めをかけられなかった。信頼を失うということの怖さに他人事ながら震えている。
ビジネスパーソンに役立つコラムを読んでスキルアップ&隙間時間を有効活用
>>さくマガのメールマガジンに登録する
「失われた信頼」は回復しない。
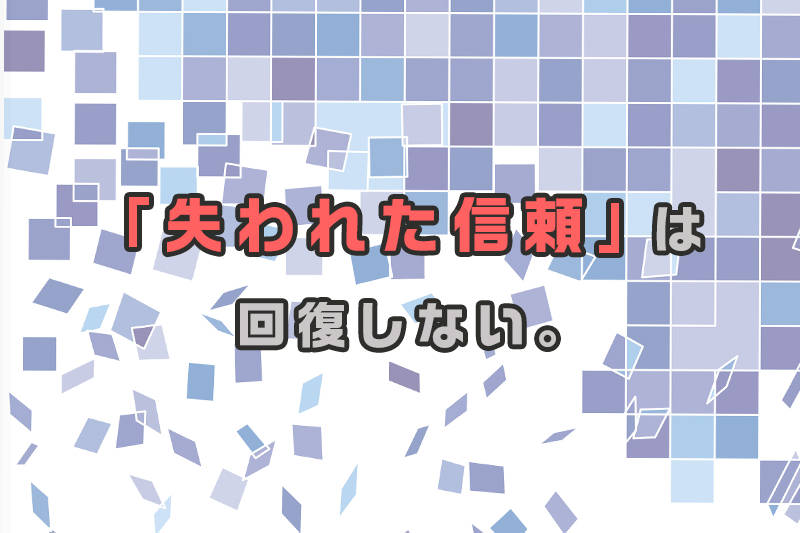
会見やインタビューで語られているのは「信頼回復」というキーワード。第三者機関を設けての社内調査、社内体制の刷新、ガバナンスやコンプライアンス体制の見直し。これらはすべて失った信頼を回復させるためのものだ。
しかし、今回のケースにかかわらず、「信頼回復に努める」「信用を取り戻す」というフレーズには違和感を覚えないだろうか。定型文のように、安易に使われていないだろうか。身も蓋もない言い方になってしまうけれども、失った信用と信頼が回復することはない。取り戻すこともできない。信用を失うような問題に対して対策を講じるのは当たり前。各対策によって築かれるのは、従来の信用と信頼とはまったく異なる新たな信用と信頼だ。いいかえれば、信用と信頼は僕らの命と同じで、一度死んだら終わりだということ。
僕は営業職だ。さいわい、勤務していた会社が信用や信頼を全面的に失うような事態にあったことはない。仮に今回のお台場のテレビ局のような事態になったら、信用信頼が回復されるまで営業活動はできなくなる。喫茶店で時間をつぶす最高の日々になるだろう。さらに、信頼が回復して活動再開がなされても、競合他社に契約を取られ、厳しい条件を突き付けられ、契約交渉が難航するなど仕事自体が変わるはずだ。
「信頼を回復できる」と考えるのはおごりである。
わかりやすくたとえると、「当社は明治時代に創業して100年以上食中毒を起こしたことはありません」と無事故アピールをしていたが、創業101年目に食中毒事故を起こしてしまったケース。まず、当然、「100年間NO食中毒」を売りにはできなくなる。既存の取引先からは「安全安心を選定理由に契約をしたのに」と嫌味を言われて契約見直し(値下げ)を迫られる。新規開発先からも「あーこないだ事故を起こした会社ねー」と足もとをみられる。元には戻れない。
もっとも、しっかりと対応策をおこなえば信用と信頼を回復できると信じていなければ、やっていられないというもの。だが、それは心構えにとどめておくべきだ。なぜなら、信用と信頼を失った側の言い分であって、信頼を寄せる側の言い分ではないからだ。本気で取り戻せる、回復できると考えているなら、ただのおごりだ。失ったら、新しい信用信頼を育てていくことしかできないのだ。
信用と信頼が一瞬で失われるのはレアケース
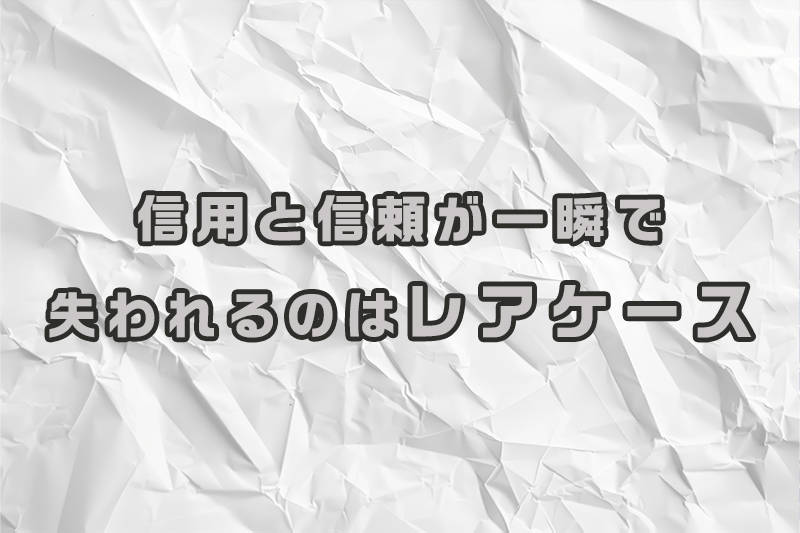
地上波8チャンネル級の大爆発ならば、どれほど強固な信用信頼関係を構築しても、一発ですっ飛んでしまう。「信用や信頼を築き上げるには長い時間と手間がかかるが、失うのは一瞬だ」という説教をする先輩や上司がみなさんの現在や過去において半径5メートルくらいにはいらっしゃるはずだ。仕事には慎重に取り組みなさい、という意味の教訓だ。
だが、こうした教訓で言われているように、信頼や信用が一瞬で失われるのはレアケースである。一瞬で失われてしまうような信頼や信頼は、もともと失われてしかるべき脆弱な関係なのだ。なぜなら、平均的な労力と通常の注意力をはらって仕事などに取り組んでいれば、一度の失策や失敗ですべてが無になる方がはるかに少ないからだ。
失敗しても信用と信頼をベースにしたリカバリー機能が働き、「次からはちゃんとやってよ」と注意を受ける程度で済むのだ。もちろん対応策や改善策は求められる。もし、一度の平均的なミスで信用信頼がゼロになるとしたら、それはもともと十分な信頼関係が構築されていないのである。
信頼の有無とはどういうことか。
一度のしくじりで信用と信頼は失われてしまう。それくらいの危機感をもって仕事にあたればよいのだ。仕事をやっていればわかるが、どれだけ注意をはらってまじめに取り組んでいても、ミスやしくじりは起こる。自分が原因ではない理由で、仕事や業務に支障や遅れが出るなど、働いていれば日常茶飯事である。たとえば業者からの納品が遅れれば、生産計画が遅れクライアントに迷惑をかけることになる。
そのとき、仕事ぶりが評価される。その納品遅れの前に丁寧な仕事をしてノーミスを何年間も継続していて、失敗への対応も完璧ならば、一度のしくじりで信用や信頼は損なわれることはないだろう。先述のリカバリー機能が働いて「次からはちゃんとやってよ」で済むのだ。
しかし、ここにいたるまで納品のルールを守らないなど、決定的な損失につながらない小さなミスをおかすなど雑な仕事をしていたら、納品遅れが決定打となって信用と信頼を失うだろう。つまり、信頼の有無とは、崖ギリギリに立っているか、崖から離れて立っているか、の違いなのだ。
崖のふちギリギリに立っている状態では軽く押されただけで転落するが、崖のふちから離れていれば少々強く押されても落ちないのだ。いいかえれば信用と信頼とは、この崖からどれだけの距離を取ることができるか、ということ。もっとも、バズーカ砲を打たれてしまったら崖から離れていても転落は不可避だけどね。このレベルになるとどうにもならない。
信用と信頼を失ったときの心構えはこれだ。
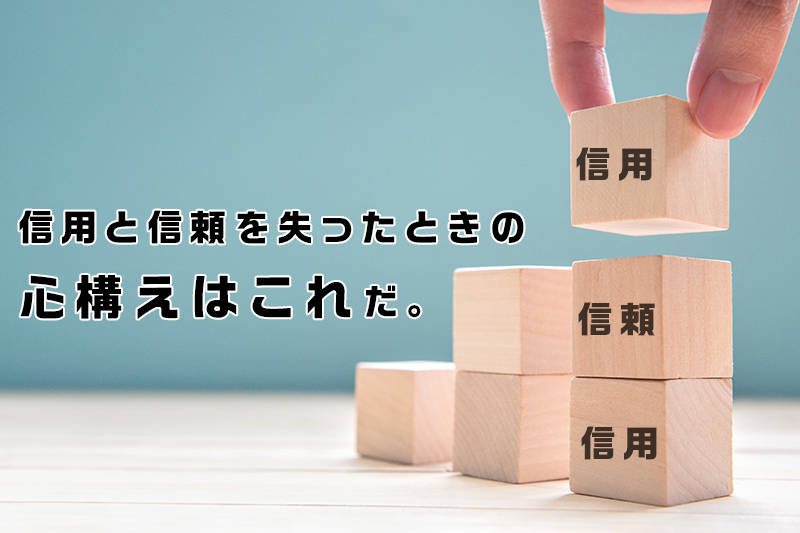
信用と信頼を得るためにはどうすればいいか、ゆとりのある計画を立てて丁寧にことに当たるといった、じつにつまらないことになるので割愛する。みなさんが普段やっていることを継続すればだいたい間違ってはいない。
では、信用と信頼を失ったときはどうすればよいのだろうか。謝罪と対応策はマストである。神妙な姿勢も必要だ。それでも信用と信頼は取り戻せない。それまでの信用と信頼は死んだものととらえて、まったく新しい信用と信頼を育てていくことになる。従来と同じような信用と信頼が回復できないとき、僕らに求められるのはある種の諦めと開き直りである。
創業以来100年間無事故無違反のウリにしていたメーカーが、軽い事故を起こしたら即市場から退場しなければならないのか。違うだろう。高い給料をもらっている経営陣には取引先への謝罪の旅に出てもらう一方で、やるべきことは「これから新たな100年の無事故無違反を続けていきます」と前に進んでいくことである。離れていく人を追わないことだ。チャンスがあればまたこちらを見てくれると信じて、新しい信用と信頼を築くような仕事をしていけばよい。
失った信用と信頼を回復させようとすると、どうしても従来の仕事のやり方にとらわれてしまう。失ったということは死んだということなので。生まれ変わりのチャンスだととらえればいい。僕は30年くらい営業職を続けているけれども、長く付き合いのあるクライアントは信用と信頼を失いかねない、いくつかの小さなしくじりを乗り越えてきたものばかりだと最近気づいた。失敗をカバーしているうちに自然と関係が強化されていた。信用や信頼を失わないように注意を払って仕事をしていれば、問題が起きたときに突然積み上げてきた信用と信頼を失う可能性は低くできる。
信用や信頼を失ったとしても、新たな信用や信頼を積み上げていくことで、新しいものが生み出せると考えれば、しんどいけれども、それほど悪いものではないように思えるのだ。
ビジネスパーソンに役立つコラムを読んでスキルアップ&隙間時間を有効活用
>>さくマガのメールマガジンに登録する

執筆
フミコ・フミオ
大学卒業後、営業職として働き続けるサラリーマン。
食品会社の営業部長サンという表の顔とは別に、20世紀末よりネット上に「日記」を公開して以来約20年間ウェブに文章を吐き続けている裏の顔を持つ。
現在は、はてなブログEverything you’ve
ever Dreamedを主戦場に行き恥をさらす
Everything you've ever Dreamed : https://delete-all.hatenablog.com/
2021年12月にKADOKAWAより『神・文章術』を発売。
※『さくマガ』に掲載の記事内容・情報は執筆時点のものです。
- SHARE



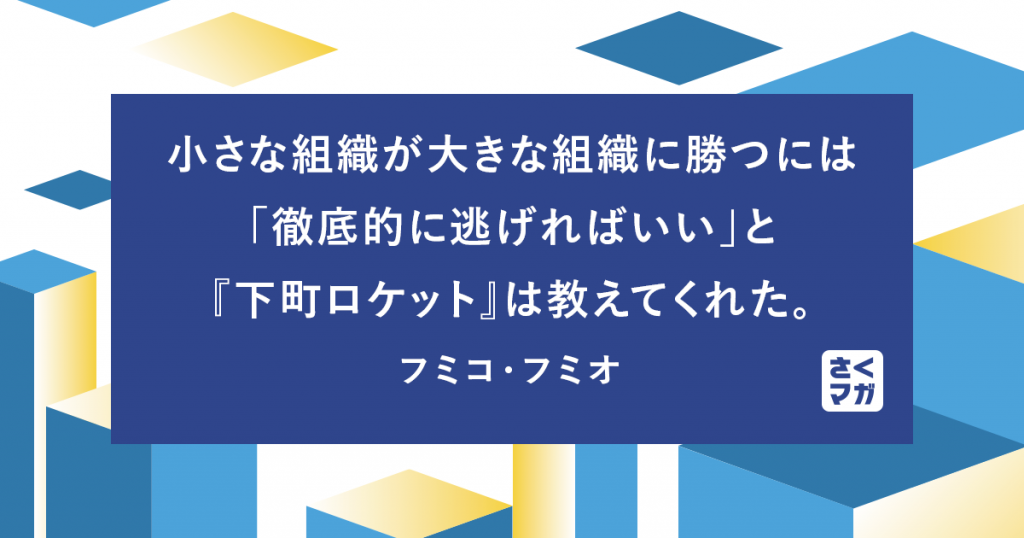
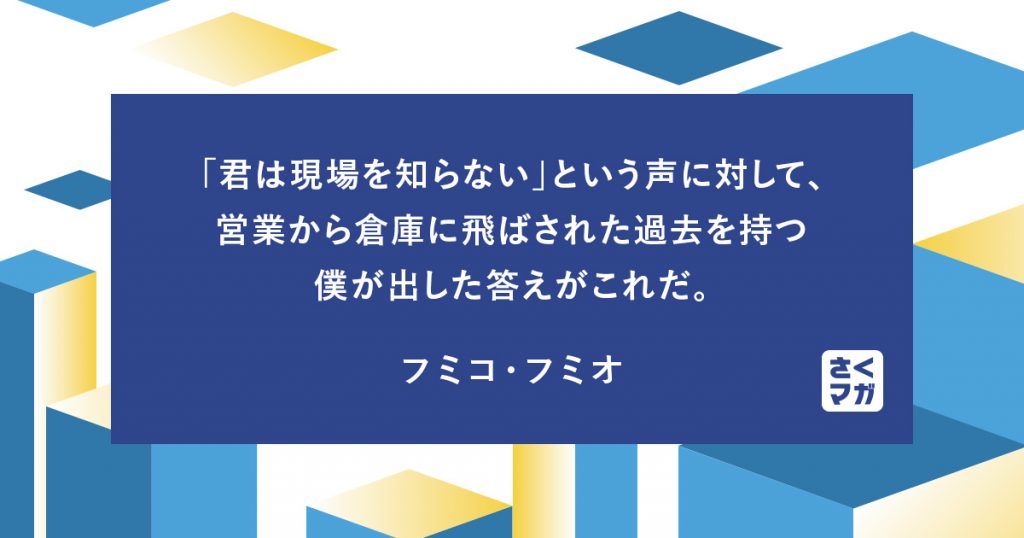
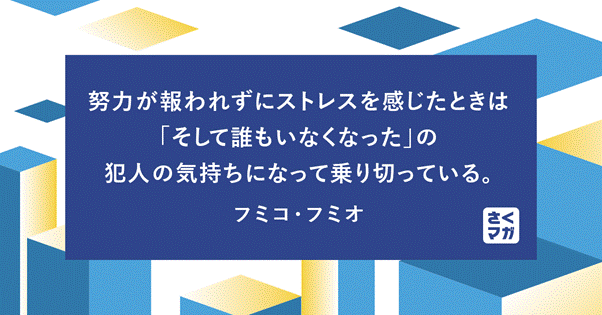
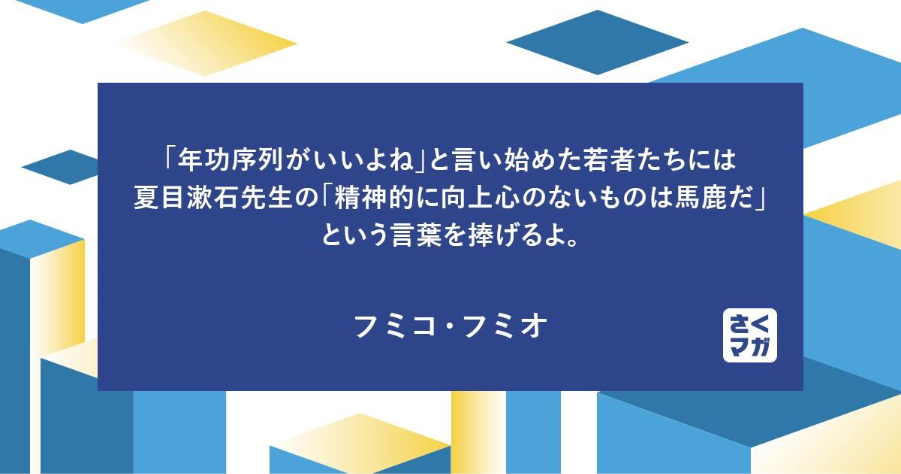
 特集
特集




