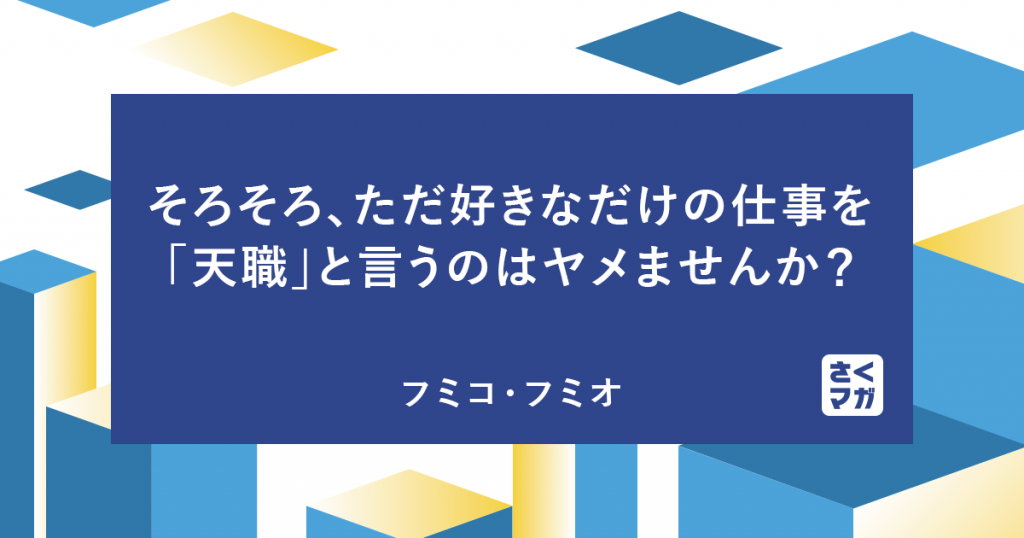
ビジネスパーソンに役立つコラムを読んでスキルアップ&隙間時間を有効活用
>>さくマガのメールマガジンに登録する
あなたの天職は本当に天職なのですか?
営業職として働き始めて今年で30年目。思えば遠くへ来たものであるが、地図に残るような大きな仕事も、NHK『プロフェショナル 仕事の流儀』やMBS/TBS系列『情熱大陸』に取りあげられるような活躍もしていない。だが、30年地味に働き続けた結果、ようやく平均年1、2回程度の頻度で「あなたは営業が天職ですね」と言われるようになった。うれしくない。はっきり言って心外である。最近、大人の精神性を身につけたので「ええ、そうですね」とやり過ごせるようになった。数年前なら「天職って何ですか? どこかの銘菓ですか?」「それ、私の可能性を限定していますよね」と面倒くさい反論をしていたはずだ。加齢にともなう心身の衰えで反論するエネルギーが枯渇したようである。
このように「天職」という言葉を僕らは日常的に使っている。「この仕事は私にとって天職だ」「いまは天職に就いているから転職は考えられない」というふうに。いま就いている職業や任されている仕事が楽しく、充実していて、本人が幸せならそれでいいが、「その程度の仕事が本当に天職なの?」と別の視点から検証してみようというのが、お節介かつ天邪鬼な今回のテーマである。
「天職」の意味を調べてみると、下記のように記されていた。
出典:『デジタル大辞泉』(小学館)
- 天から授かった職業。また、その人の天性に最も合った職業。
- 天子が国家を統治する職務。
- 遊女の等級の一。大夫の次の位。天神。
子どものころ、父に連れていかれたスナックで占い師に人相をチェックしてもらい「この子は天下人になる」と言われた実績のある僕個人としては「2. 天子が国家を云々」が気になるところではある。しかしながら、今回のテーマに沿っているのは「1. 天から授かった職業。また、その人の天性に最も合った職業」という意味の天職である。
好きな仕事は天職なのか問題

最近耳にする「天職」は、「当人の天性に最もあった職業」とはすこしズレているようだ。自分にとって「やりたい仕事」、自分が「やりたかった仕事」のような意味で使われている。ハードルが下がっている。数年前に見かけたYouTuberのキャッチコピー「好きなことで生きていく」のようなものだろうか(懐かしい)。
先日、一緒に働いている同僚が「営業は私の天職です」と清々しい顔面をして話していたので驚いてしまった。天職と考えるのは個人の自由であり、憲法によって思想の自由はガードされているため、「それを改めよ」なんて言うことはできないけれども、当該人物が確実にノルマを達成しているわけでもなく、仕事の進め方にも注意をしているような人物なので清々しく「天職」と言われるともやもやする。管理職の立場から客観的に見て営業が向いているようには思えないのだ。
当該人物にとっての営業が本来の意味の天職ならば、ノルマを何ごともない顔でクリアし、そのうえでプラスアルファの成果を積み上げているのではないだろうか。つまりこの場合、天職はせいぜい自分が好きな仕事という程度の意味で使われている。天職と言い切っているあたりに、危険なフレーバーを嗅ぎ取ってしまうけれども、ここは楽観的に希望があるととらえることにしている。つまり、現時点の力量はまだまだだけれども天職といえるレベルまで高められる可能性があると考えるのだ。
これは重要なポイントで、人間というものはある程度の将来像やイメージを持っていないと絶対にそこにはたどりつけないからだ。その点、当該人物は営業を天職と自称して前向きな姿勢でいることは期待できる。ただ、年齢が僕よりも年上の50代後半なので、天職と呼べるレベルに達するまで、それほど多くの時間が残されていないのが残念だ。現実は厳しい。とりあえず当面の目標を達成できるようになってほしい。
天職は自分で評価するものではないのでは?
「天職に就いている」「これが私の天職だ」と言っている人たちを貶すつもりは毛頭ない。「天職=好きな仕事、やりたい仕事というレベルなのだね、大袈裟ないい方だなー」と思うだけである。じつに微笑ましい。前向きに考えることは悪くない。ただ、あとで述べるように天職と決めつけることで「自分にはこの仕事しかない」と視野が狭くなってしまわないようにしたほうがよいのではないかとは思う。
結論っぽいことを言ってしまうと、天職か否かは自己評価するものではない。他人から、客観的に、評価されるものだ。「あの人は天職に就いている」というふうに。要するに、結果や実績のともなわない天職はありえないということ。好きな仕事に就いているという認識は重要であるが、本人の能力と資質がともなわなければ悲惨だ。最悪の場合、行動力に溢れるものの能力と適正のない、そのうえ天職と思っているから人の意見を受け入れず反省もしない劣悪仕事マンが爆誕するのである。
僕は約30年間会社員として働いてきた。新卒当初の数か月をのぞけば、ほぼ30年間を新規開発営業として従事している。そのなかで、何人か、十数人という人数の人が「営業をやりたい」「営業職が憧れでした」といって他部署から異動してくるのを見てきた。「営業が天職だと思っています」といっている人もひとりふたりいた記憶もある。彼らが口にしていた天職は「やりたい仕事」レベルの認識だったにちがいない。
仕事の華やかな部分だけを見ていると幻滅する。
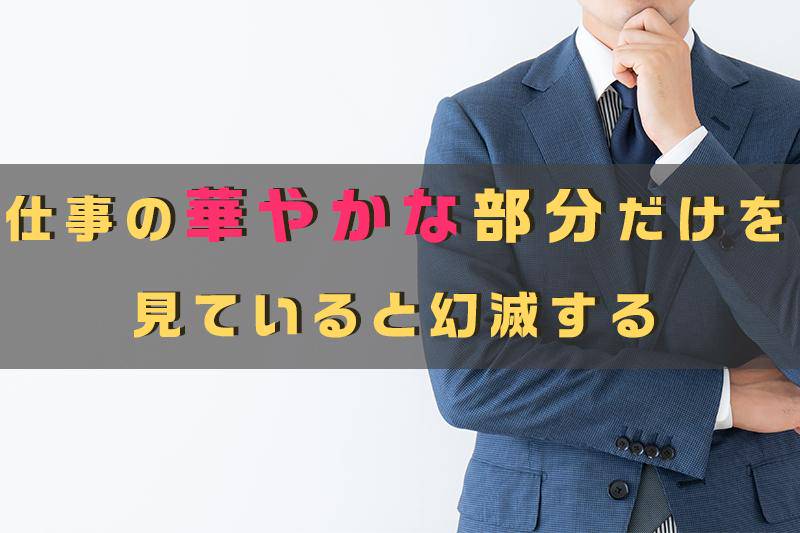
彼らは、営業という仕事について幻想を持っていて、その幻想に憧れていた。クライアントとの熱い商談。華やかなプレゼンテーション。お金を使った派手な接待。彼らはそういった営業の華やかな幻想(僕はそういう局面に遭遇したことがほとんどないからだ)に憧れて、営業職を志向していた。地味な現実に直面すると「こんなはずじゃなかった」と落胆するのは想像にかたくない。
なかでも「人と話すことが好き」を理由に営業を志望してきた人は100パーセントの確率でうまくいかなかった。理由は明確で、営業の仕事は話をすることではなく、話を聞くことだからだ。「話好き」は、むしろ、営業という仕事にとってマイナスになってしまうことのほうが多い。話をすることが話を聞くことより優先度が高くなってしまうため、相手のニーズを聞きもらしてしまうのだ。
営業は地味な仕事である。相手の話を聞きながら、わずかなヒントから相手自身が認識していない問題と需要をつかんでいき、それを提案に結びつけていく仕事だ。華やかな部分は体感で全体の3パーセントくらい。あとはひたすら相手とコンタクトを取り、話を聞く、地味オブ地味な仕事である。営業職の華やかなイメージは、ドラマや小説や映画といった創作物で描かれている「営業マン像」に起因していると思われる。
ひたすら話を聞いている営業マンは絵的に地味で、現代風にいえば「映えない」ため、伝えられる機会がない。だがそれが現実の営業職の姿である。営業に憧れを抱いて異動してきた人たちは、おそらく事前に抱いていた営業のイメージ(幻想)と現実とのギャップが大きかったために、うまくいかなかったのだろう。
30年続けた仕事を天職と思ったことはない。
天職に話をもどすと、僕は30年間続けてきた営業という仕事を天職と思ったことは一瞬もない。好きでもない。何年やっても、実績を積み重ねても、営業という仕事を1ミリも好きになれないでいる。新卒当時のひどい教育制度が営業嫌いを決定的にした。僕が新卒で入った当初は、教育プログラムはなく、上司や先輩がやっている背中を見て覚えろと言われただけ。仕事ができなければ叱責された。ひどい仕事だと認識した。絶対に好きになれないと思った。
ひたむきに営業という仕事に取り組んでみたが、どうしても好きになれそうもない。かといってほかにやれる仕事も見つからず、やりたい仕事もなかった(仕事自体が嫌いだった)。だから、自分なりに勝率と効率を両立させられる方法を作りあげていった。もし、営業という仕事が好きだったら「営業楽しー! いつまでもやっていたい!」とどっぷりとハマっていたはずだ。営業という仕事が嫌いだったからこそ、できるかぎり楽をして成果をあげようと考えて創意工夫したのだ。
その結果、30年間営業職を続けられている。これだけの年月を続けられてこられたのは、継続的に結果を出してきたからであり、営業という仕事に端から幻想を抱いていなかったため、何があっても幻滅することがなかったからだ。そして周囲からは「フミコさんは営業が天職ですね」「ほかの仕事をしている姿が想像できない」と評価されるようになった。僕自身、営業を天職だと思ったことがないというのに。皮肉な結果だ。
天職は自分で作りあげるもの。

天職というのは、自分で評価するものではなく、実績や成果によって周囲から「あなたにとってこの仕事が天職だ」と評価されることが第一条件である。そのうえでその仕事についてポジティブな気持ちで取り組んでいることが天職の要件になるのではないかと僕は考えている。僕はポジティブな気持ちで営業という仕事に取り組んでいないから天職に就いていることにはならない。
また、「自分は天職に就いている」「いまの仕事が天職だ」と考えることは危険だとさえ思う。視野と可能性を狭めて、他の可能性を考慮しなくなるからだ。現在の職業や仕事のほかに天職と言えるものがあるかもしれないではないか。それをざっくりと切り落としてしまうのは当人にとっても社会にとっても大きな損失だ。いまの自分がベストではなくベターくらいに控えめにとらえておいて、よりよい仕事や環境を見つけられるようにしておき、移っていけるようにしたほうがいい。なにより仕事や職業にこだわらないほうが気楽で自然な姿勢といえる。いろいろな分野にアンテナを張ってやりたいことを見つけていく柔軟性を持ったほうがよい。とくに若い人たちは。
結論から言えば、天職か否かは、まず、自分ではなく周囲から評価されることが第一になる。そして、天職と決めつけずに柔軟性を持ってポジティブな気持ちでいま従事している仕事に取り組んでいれば、結果や成果がついてきて周囲から天職と評価されるかもしれない。天職は、自分で決めるものではなく、自分で作りあげて周りから認められていく未来像にほかならない。

執筆
フミコ・フミオ
大学卒業後、営業職として働き続けるサラリーマン。
食品会社の営業部長サンという表の顔とは別に、20世紀末よりネット上に「日記」を公開して以来約20年間ウェブに文章を吐き続けている裏の顔を持つ。
現在は、はてなブログEverything you’ve
ever Dreamedを主戦場に行き恥をさらす
Everything you've ever Dreamed : https://delete-all.hatenablog.com/
2021年12月にKADOKAWAより『神・文章術』を発売。
※『さくマガ』に掲載の記事内容・情報は執筆時点のものです。
- SHARE



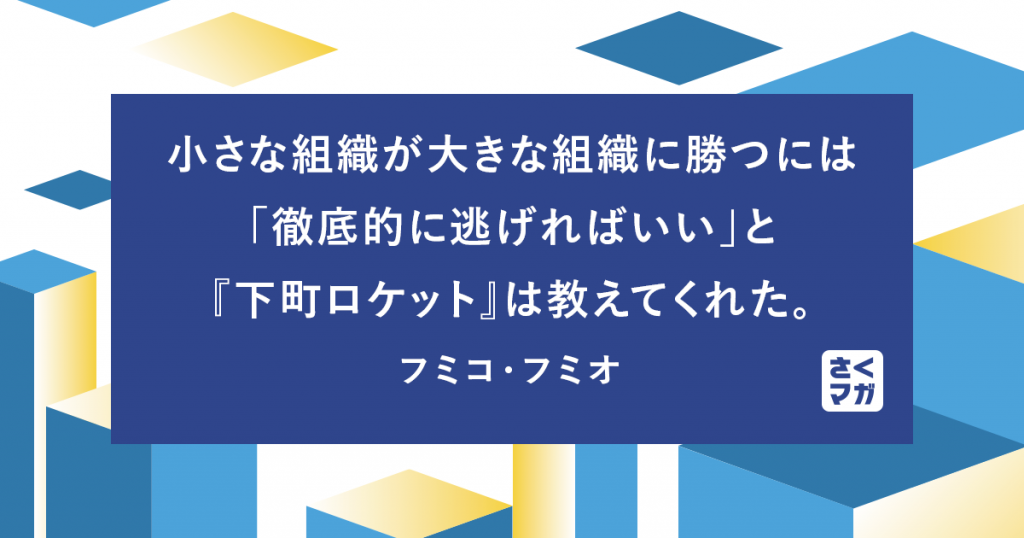
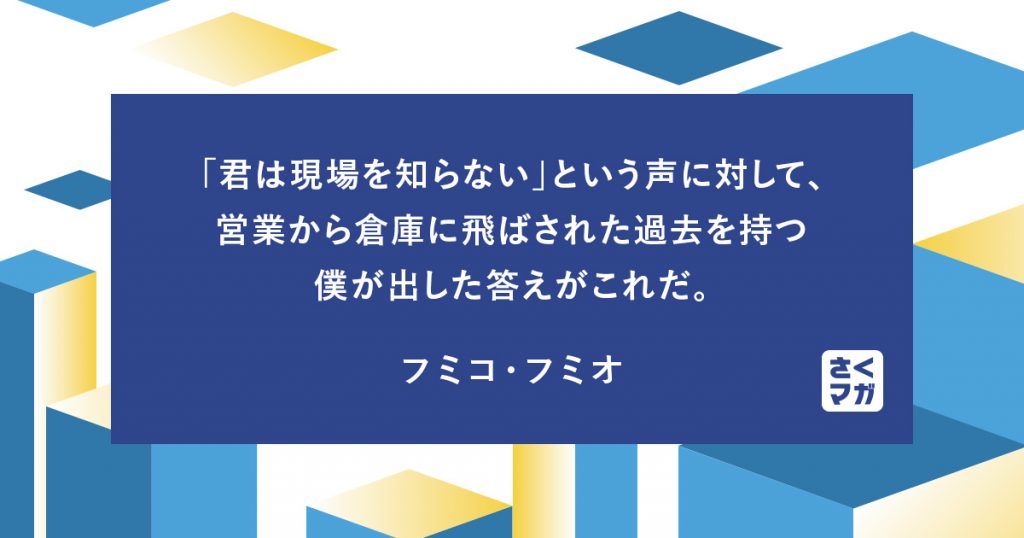
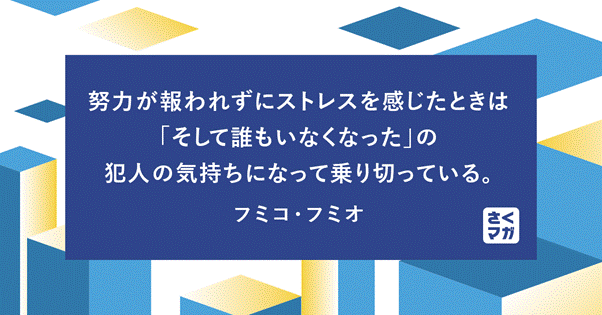
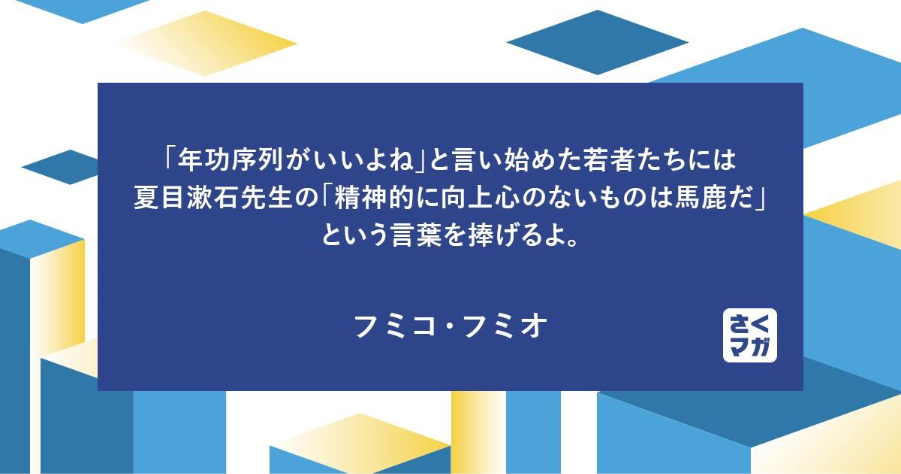
 特集
特集




