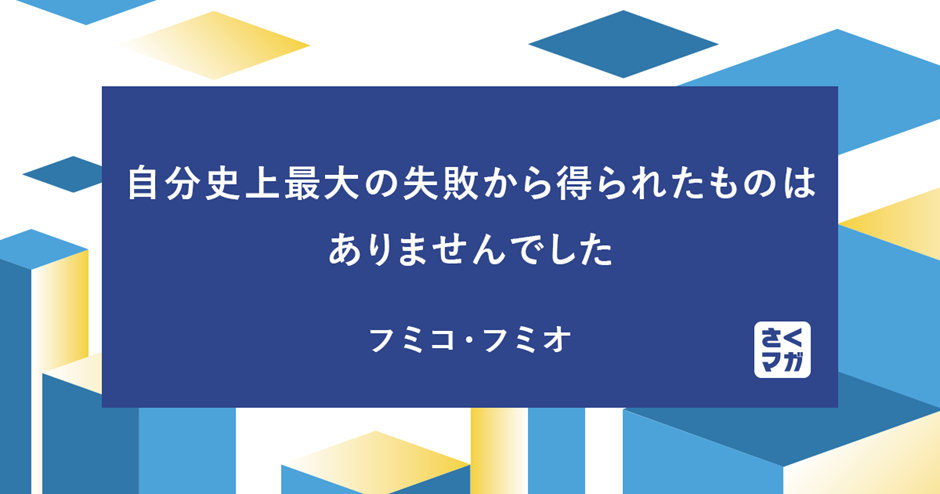
ビジネスパーソンに役立つコラムを読んでスキルアップ&隙間時間を有効活用
>>さくマガのメールマガジンに登録する
自分史上最大の失敗は取り戻せない。
人生最大の仕事上の失敗を忘れることができない。今のところ、その失敗を取り返すチャンスはなさそうなので、永遠に失敗のままになりそうだ。無念だ。20年以上前の話だ。僕は上司の嫌がらせで、とあるプロジェクトの末席に参加させられた。部署の垣根を越えたプロジェクトで、日本国内で使われていた中古鉄道車輛を海外へ輸出する仕事に取り組んでいた。僕が配属されたチームに任されていたのは、陸揚げ後の工程作成だった。現地代理店、現地業者、陸運と海運が関わるのでいろいろと厄介だったと記憶している。
とくに困ったのが現地代理店経由で紹介してもらった現地業者がたびたび音信不通になることだった。良くても反応が遅く忘れたころに「ヘイジャパニーズ、あの仕事はどうなっている?」という電話がかかってくる始末。その話をすると原稿用紙100枚くらいになってしまうので割愛するけれど、日本国内で仕事をするより、8割増の労力と苦労があった。事前調査で問題発生が予測できたので、逃亡、音信不通、業務怠慢等々うまくいかないことを前提に計画を二重三重に立てた。アクシデントやトラブルが起きても対応できるプランBをいくつも作成した(プランAXまであったかも)。フローチャートがどの経路をたどってもゴールにたどり着けるように計画した。
万全なはずだった。計画を実施する予定の2001年の秋にアメリカ同時多発テロ事件が起こった。プロジェクトはテロリストの根拠地のあるエリアを陸運で何百キロも通過するものだった。「安全が確保できない」という理由からトップダウンでプロジェクトは中断となった。当然だ。アメリカのトモダチです。命が危ない。
現地の工程作成は僕のグループが担当だったので責任を押し付けられた。その際の上司の言葉をいまも覚えている。「なぜアメリカを攻撃するテロリストの本拠地近くを通るルートにした?」である。アメリカ国防省や米軍でもつかめていなかったテロリストの情報を会社員が持っていると考えたのだろうか。当初の計画は中止せざるをえなくなった。
これが30年弱のサラリーマン人生で金額的にも規模的にももっとも大きな失敗である。なお、プロジェクト自体は2年後に再開された。復活した計画は、ほぼ僕の所属していたグループが作成したとおりだった。なお、僕自身は現地派遣につけられる危険手当が不当に低かったのでプロジェクトから外れさせてもらい、別の理由で退職してしまったのでその後プロジェクトがどうなったのかくわしくは知らない。
この人生最大の失敗から学んだ教訓を強いて挙げるなら、「どれだけ能力と労力をつくしても失敗するときは失敗する」である。「諦め」である。ポジティブな教訓はなかったと断言できる。「世界でビジネスをするならアメリカ軍以上の諜報能力が必須」を学びにしてもいいが、非現実的すぎるだろう?
ほぼすべての「想定外」は想定できる。

「失敗は成功の母」「失敗は成功の糧」と言われる。これは僕の経験と観測範囲では言い訳としか思えないケースがほとんどだった。たとえば「いやー協力会社さんがコケて納品が遅れます。想定外の事態でした」と報告して「これを糧に次は頑張ります」と決意するような人を何人も見てきたが、これは明らかに想定外ではない。納品遅れなんてあるあるです。つまり、想定することすらしなかっただけのこと。想定外とは想像を超えた部分で起きる事象である。
不思議なのはこういういい加減な仕事のやり方と言い訳が日本の会社では通用するのである。仕事なら、想定されるアクシデントを盛り込んで、プランをいくつか用意してしかるべきである。協力会社の納品遅れ、製造ラインの生産能力の未達など、いま、こうやって頭にぽんぽんと浮かぶような事態は想定内である。想定できたなら対応策を講じておけばいい。自分で思いつかなかったトラブルだけが、想定外のトラブルになる。経験を積むことによって想定外はほぼなくなっていくはずだ。
一時期「想定外」という言葉が流行って、いろいろな人が使っていたけれど、そのうち本当に想定外の事態がどれだけあったのか疑わしいものだ。想像すらしないのはただの怠慢である。任せられた仕事があったら、トラブルやアクシデントを想像して、それを盛り込んだ仕事をするようにしてもらいたい。最初は面倒くさいかもしれないが、トラブルを想定していくうちにその対策にも慣れてきて効率的に進められるようになる。「失敗は成功の母/糧」という言葉は、想定をしまくって抜けのない仕事をしてから言ってもらいたい。
失敗することのハードルが上がっている。おいそれと失敗ができない。若い世代は大変だ。大体のことはネットで調べてしまえば事前にわかってしまうので、まったく手も足も出ないということはないと周囲は考えるからだ。僕が新卒のころは、現代ほどネット上に情報がなかったので、まったくわからないまま仕事に取り組むことがままあった。そのため苦労することはあったが、周囲も「知識と経験がなくて戸惑う新人」を受け入れる雰囲気があった。
いまはどうだろう? いまの若い世代に対して「ネットで調べればすぐにわかるよ」と突き放してしまうことがあるのではないか。事前にネットで調べておくことが前提になってしまっている。たいていのことはネットでわかってしまうので、昔は許された「初歩的な知識不足」が許されなくなっているのは気の毒である。先ほどの想定外の話にもあったように、事前に準備をして想定外をなくしておくことが唯一の対策なので頑張ってもらいたい。
ネット時代の失敗の原因は力量の見積もりが甘いから

僕らはなぜ失敗をしてしまうのだろう。たしかに経験や知識不足は大きな要因だ。だが、ネットである程度は補填できる環境にある。まったく知識ゼロで仕事に当たるという事態は現代においてほぼないといっていい。それでも仕事をしていると、あるいは職場にいると、ありとあらゆる失敗が起きている。深刻な失敗もあれば、単純な準備不足の失敗もある。失敗のオンパレードだ。
不注意や不徹底が見積もりの甘さが原因だと思われる。自分自身と他者の能力や経験に対する見積もりが甘いのだ。「これくらいなら自分はできる」「あの会社ならこれくらいはやってくれる」僕らは仕事をしているうえでこういう見積もりを常にしている。失敗は見積もりの甘さに起因するのである。
である調で偉そうにいっている僕も、見積もりの甘い人間の1人だったのである。20代から30代にかけては自分の能力に対する見積もりが間違っていた。過信していたのだ。自分には能力や可能性が無限大にあると信じていたのである。痛すぎる。それゆえ勢いでうまくいくこともあったが、つまずきの方が多かった。最初に語った人生最大の失敗も、いま、振り返ってみれば過信があったといえる。「ここまで綿密な計画を立てたから万全だろう」という奢りがあった。テロ事件は予想できなかったが、過信と驕りから計画に融通性がなかった。ガチガチすぎた。そのため、事件勃発のあとの想定外の対応がうまくいかなかったのである(結果は変わらなかったかもしれないが)。
仕事においての見積もりや見通しに、「これくらいはできる」「やってくれるにちがいない」という過度な期待値を込めないようにすれば、失敗は少なくできる。体調が悪いときに奥様が優しくしてくれるだろうと期待して、いつもと変わらない態度に終始して落胆するのは、相手に対する見積もりに過度な期待値を込めているからなのである。
信じることと信じすぎることはちがう。
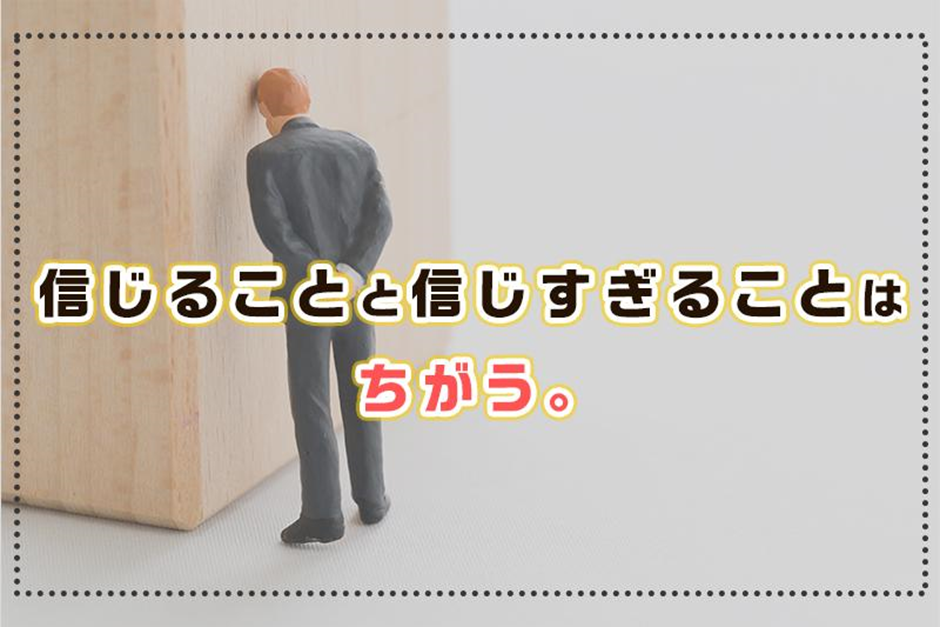
いまの世の中は相手を信じることを是としすぎなのだ。映画やドラマでもピンチに単独で対応しようとする主人公に、見守っている上司や同僚たちは「俺たちはあいつを信じる」という台詞を語らせている。信じることは大事だが、万能ではない。いや、むしろ無力だ。必要なのは、自分と相手の能力を正確に把握して「できることとできないことのラインを明確にすること」であり、その対応策である。協力会社の納品が遅れてしまうことを想定外ととらえるのは、協力会社の能力に対する見積もりに「これくらいはできる」という甘めの期待値が込められているからである。期待値を排除して見積もりをシビアにすれば、失敗をする確率は低くなるだろう。
誰だって失敗はしたくない。失敗したときは言い訳したくなる。それは誰でも同じである。だが、その失敗は本当に失敗なのか、ただの不注意や不徹底、想定していないこと等による当然の結果ではないか、と客観的に見てみるようにしてみよう。「失敗した」「よし反省しよう」「学びを得た」「次に活かそう」というサイクルがもてはやされているけれども、失敗そのものをよく見てみることをしないとおそらく同じことを繰り返すだけである。自分や相手の力量を、過度な期待値を込めずに見積もって仕事をする/任せる。事前に予想されるトラブルをピックアップして、それが起こったときのプランBを用意しておくこと。それでも失敗は起きてしまう。だが、そこまでやっていれば失敗の本質が見えてきて、初めて、本当の意味であとに役に立つ糧を得られるのではないかと僕は思うのである。

執筆
フミコ・フミオ
大学卒業後、営業職として働き続けるサラリーマン。
食品会社の営業部長サンという表の顔とは別に、20世紀末よりネット上に「日記」を公開して以来約20年間ウェブに文章を吐き続けている裏の顔を持つ。
現在は、はてなブログEverything you’ve
ever Dreamedを主戦場に行き恥をさらす
Everything you've ever Dreamed : https://delete-all.hatenablog.com/
2021年12月にKADOKAWAより『神・文章術』を発売。
※『さくマガ』に掲載の記事内容・情報は執筆時点のものです。
- SHARE


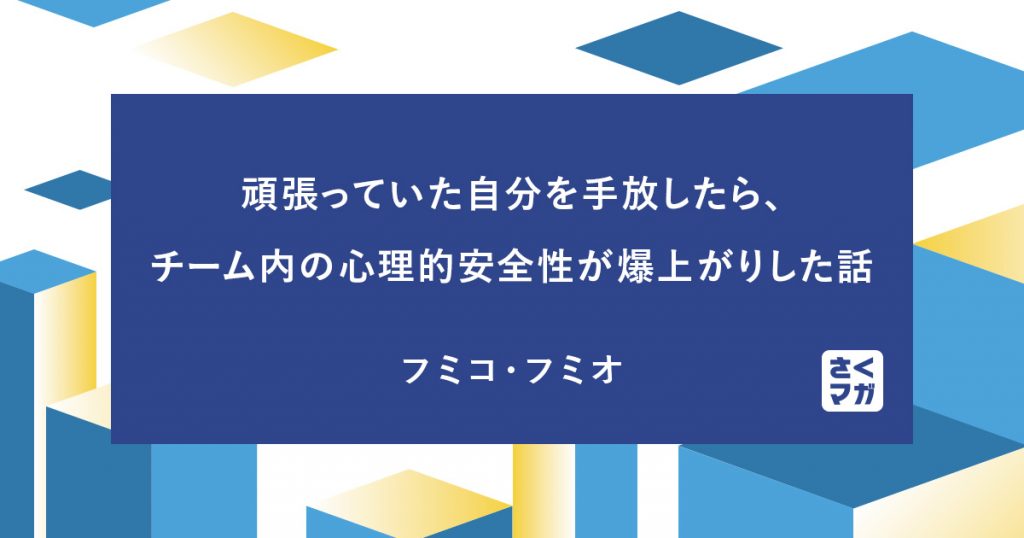

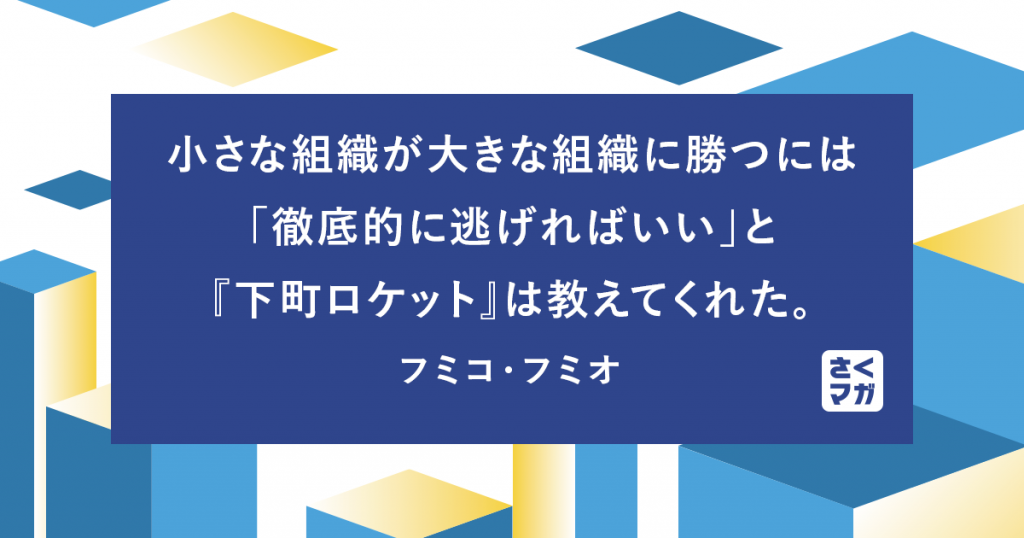
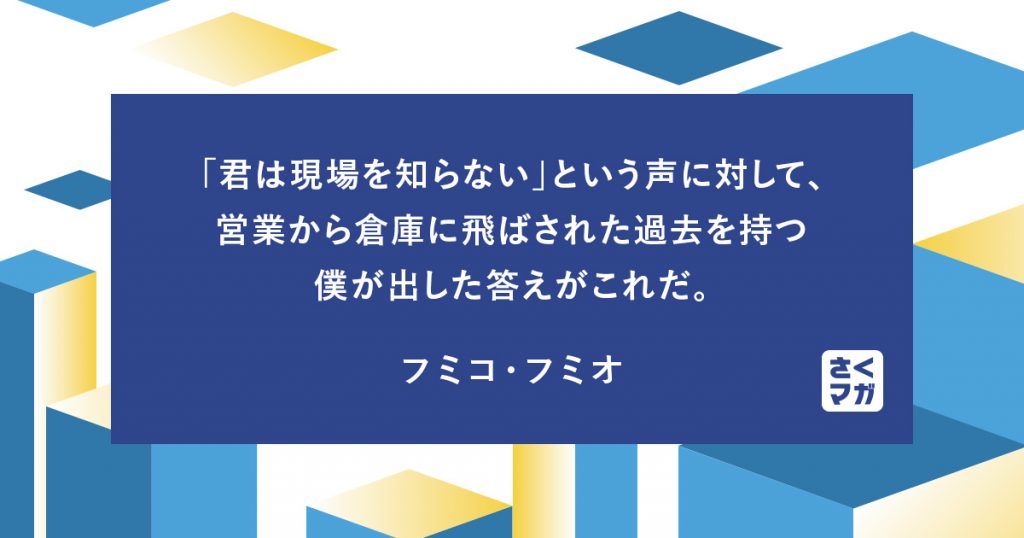
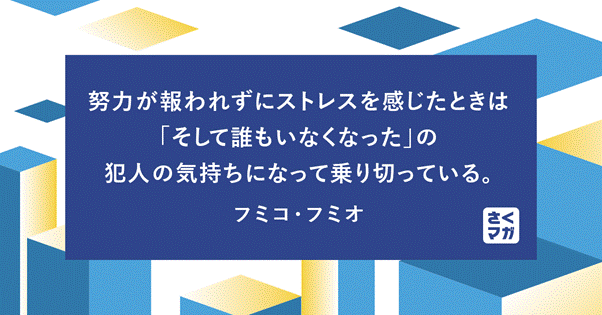
 特集
特集




