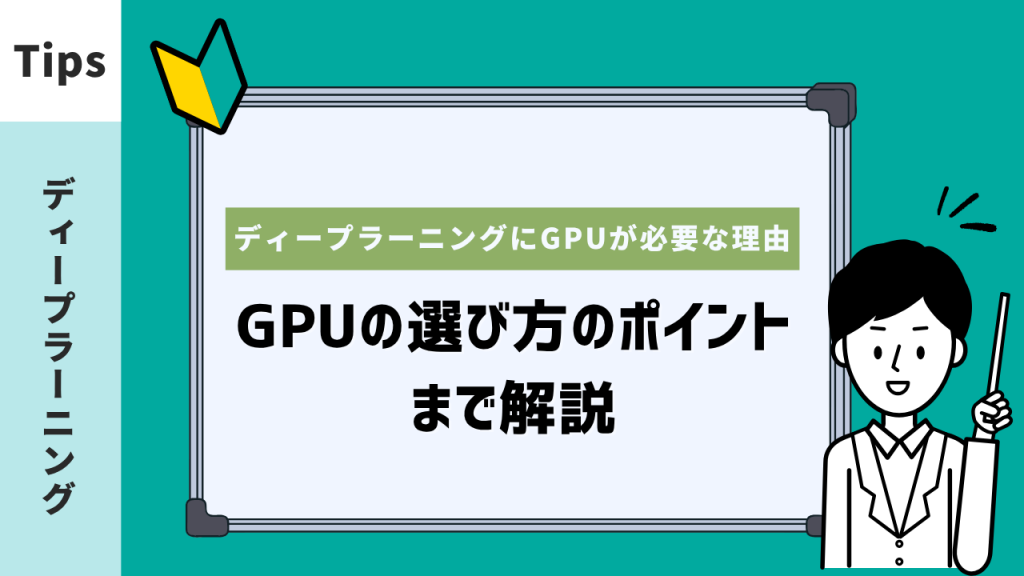
大規模なディープラーニングモデルの学習や推論をおこなう際、「CPUだけでは処理速度が遅い」「メモリ不足でモデルが動かない」といった課題に直面していませんか。
本記事では、GPUの基本概念からディープラーニングにGPUが求められる技術的理由、実務で役立つGPU選定の判断基準を解説します。限られた予算内で最適なGPU環境を構築したいAIエンジニア・データサイエンティストの方に向けて、実践的なガイダンスを提供します。

さくらインターネットが提供している高火力シリーズ「PHY」「VRT」「DOK」を横断的に紹介する資料です。お客様の課題に合わせて最適なサービスを選んでいただけるよう、それぞれのサービスの特色の紹介や、比較表を掲載しています。
GPUの基本とディープラーニングに必要な理由
現代のAI開発において、GPUは単なる選択肢ではなく必須のインフラとなっています。その理由を技術的な観点からくわしく見ていきましょう。
GPUとは
GPU(Graphics Processing Unit)は、もともと3Dグラフィックスの描画処理を高速化するために開発されました。ゲームや映像制作における画像処理では、画面上の数百万個のピクセルを同時に処理する必要があり、この並列処理に特化した設計が採用されています。
CPUが複雑な計算を順番に実行する「逐次処理」を得意とするのに対し、GPUは単純な計算を大量に同時実行する「並列処理」に最適化されているのが大きな違いです。この特性が、実はディープラーニングの計算処理と非常に相性が良いことが判明しました。
ディープラーニングの学習プロセスも、グラフィック処理と同様に大量の単純な計算(おもに行列演算)を並列実行することで成り立っています。この共通点により、2010年代以降、AI分野でのGPU活用が急速に普及することとなりました。
なぜGPUはディープラーニングに必要?
ディープラーニングでGPUが必要とされる理由は、ディープラーニングの計算の特性にあります。従来のCPU中心の処理では限界がある部分を、GPUが革新的に解決してくれるためです。
ここでは、技術的な観点から3つの主要な理由をくわしく解説していきます。
膨大な行列演算を並列処理で高速化できる
ディープラーニングの学習プロセスは、本質的に大規模な行列演算を中心とした計算の連続で構成されています。入力データと重みパラメータの掛け算といった行列演算や、大量のパラメータに対する同じ種類の演算処理が中心となるためです。
CPUは1つのタスクを順番に高速で処理する逐次処理を基本とします。一方、GPUは数千から数万のコアが同時に計算を実行する並列処理に特化しているのが特徴です。たとえば、1,000×1,000ピクセルの画像処理では、CPUが100万個の計算を順次実行するのに対し、GPUは同じ計算を数千のコアで並列実行するため、処理時間を大幅に短縮できます。
処理内容や規模にもよりますが、GPUを使うことで処理速度が10倍から100倍に改善される場合もあります。とくに、大量のデータを扱う深層学習では、この性能差が開発効率に直結するため、GPUの重要性は極めて高いといえるでしょう。
大容量のVRAMで大規模モデルに対応できる
現代のディープラーニングモデルは、数億から数兆のパラメータを持つ大規模なものが主流となっています。これらを効率的に学習・推論するには、十分なメモリ容量が不可欠です。
GPUに搭載されるVRAM(Video Random Access Memory)は、通常のシステムメモリより高速なデータ転送を実現します。バッチサイズ(一度に処理するデータ数)とメモリ使用量は密接に関係しており、バッチサイズが大きいほど学習の安定性と効率が向上するのが一般的です。
メモリ不足が発生すると、バッチサイズを小さくせざるを得ず、学習時間の延長や精度低下につながります。比較的小さな大規模言語モデル(LLM)であっても、推論だけでも10GB以上のVRAMが必要で、最新の大規模モデルでは40GB以上、学習時にはその2〜3倍のメモリが求められることが多いようです。そのため、VRAM容量は性能を左右する重要な要素となっています。
専用コアによるAI特化演算が可能
最新のGPUには、ディープラーニング専用に設計されたAI専用コアが搭載されています。これらのAI専用コアは従来の汎用コアとは異なり、AI特有の演算に最適化された専用回路です。
これらのAI専用コアは、FP16(半精度浮動小数点)や混合精度演算に対応しており、従来のFP32(単精度)と比較して計算速度を大幅に向上させることができます。混合精度演算では、メモリ使用量を約半分に削減しながら、精度の劣化を最小限に抑えることができます。これにより、同じハードウェアリソースでより大きなモデルを扱えるようになります。
最新アーキテクチャでは、前世代と比較してAI専用コアの性能が2〜3倍向上しており、AI開発の効率化に大きく貢献しているのが特長です。
ディープラーニング用GPU選択のポイント
適切なGPU選択には、技術仕様の理解から実際の調達方法まで、多面的な検討が必要となります。実務で成功するためのポイントを段階的に解説していきます。
性能を決める3つの技術要素
ディープラーニングの性能を左右する要素は、コア数、メモリ容量、計算精度の3つです。
コア数:汎用コアとAI専用コアの役割
汎用的な並列計算コアとAI専用コア、いずれについても搭載されている数を確認しましょう。汎用的な並列計算コアは数が多いほど基本的な処理能力が向上します。一方、AI専用コアはディープラーニング専用で、AI特有の行列演算を高速化する役割を果たしています。2025年現在の主流GPUでは、汎用コアが2,000〜10,000個、AI専用コアが数百個搭載されているのが一般的です。
メモリ容量:VRAMサイズと帯域幅
扱えるモデルサイズと処理効率に直結する要素です。VRAMサイズだけでなく、メモリ帯域幅も重要で、これが低いとGPUの処理能力を十分に活用できません。エッジAIでの限定的な推論処理では8GB程度、中規模モデルの学習では16GB〜24GB、大規模言語モデルの本格運用では40GB以上が目安となります。
計算精度:FP32/FP16/INT8対応
FP32、FP16、INT8などの対応状況を確認することも重要です。用途に応じて適切な精度を選択することで、メモリ効率と計算速度を最適化できるためです。
用途別の推奨スペック
用途に応じた適切なスペック選択が、コストパフォーマンスの最大化につながります。ここではスペック選択について用途別に解説します。
研究・実験用:コストパフォーマンス重視
小規模データセットでのプロトタイピングや手法検証が主目的の場合、8〜12GBのVRAMを搭載したミドルレンジGPUで十分対応が可能です。多様な実験を効率的におこなうため、極端な高性能よりも安定性とコストバランスを優先するとよいでしょう。
本格運用:安定性と拡張性重視
商用サービスでの推論処理や継続的なモデル改善をおこなう場合、16〜24GBのVRAMと高い処理能力が必要です。24時間稼働に耐える信頼性と、将来的な性能要求増加に対応できる拡張性も考慮する必要があります。
大規模モデル:ハイエンド仕様
数億パラメータを超えるモデルの学習や、リアルタイム推論が求められる用途では、32GB以上のVRAMと最新アーキテクチャのAI専用コアが必要です。これらの環境では、投資額は高くなりますが、開発スピードと品質の向上が期待できます。
調達方法の選択:オンプレミスとクラウドの比較
GPU環境の構築にあたっては、「自社でハードウェアを購入するか、それともクラウドサービスを利用するか」が重要な判断ポイントになります。プロジェクトの性格と組織の状況に応じて最適な選択肢は変わるため、それぞれの特徴を比較して適切に判断する必要があります。
オンプレミスのメリット・デメリット
おもなメリットは、初期投資後の低いランニングコストと完全なカスタマイズ性です。長期間継続的にGPUを使用する場合、減価償却を考慮すると経済的になり、セキュリティやデータ管理の観点でも優位性があります。
デメリットとして、高い初期投資(数百万円規模)、運用・保守コスト、技術更新への対応負担が挙げられます。さらに、最新GPUへの移行時には既存ハードウェアの処分と新規購入が必要です。
クラウドのメリット・デメリット
おもなメリットは、初期投資不要での利用開始、柔軟な拡張性、最新技術への即座のアクセスです。プロジェクトの進行に応じてリソースを増減でき、常に最新のGPUアーキテクチャを利用できる点が魅力です。
デメリットとして、長期継続利用時は従量課金のコストが累積する傾向があります(月額数十万円規模)。また、ネットワーク回線への依存、大容量データの転送コストも考慮すべき要素です。
選択のポイント
短期集中型や実験的なプロジェクトではクラウド、継続的な開発でも従量課金の柔軟性が求められる場合はクラウドが適しています。とくに時間単位での利用が可能で、必要な時に専有GPUリソースを確保できるサービスであれば、初期投資リスクを抑えながら高性能な環境を活用できるでしょう。
一方、大量データを継続的に扱い、長期間の専有利用が確実な場合はオンプレミスも有力な選択肢となります。ただし、GPU技術の進歩が早いため、数年後の陳腐化リスクも考慮する必要があります。コスト試算では、使用期間とリソース量を具体的に見積もり、総保有コスト(TCO)で比較することが重要です。
まとめ
ディープラーニングにおいてGPUが重要とされる理由は、もともとグラフィック処理に特化していたGPUの並列処理能力がAI処理と親和性が高く、VRAMの大容量化やAI専用コアの登場によりAI処理に必須のものとなったためです。適切なGPU選定にはこうした技術的背景の理解が重要です。
実務においては、コア数・メモリ容量・計算精度などの技術的な特性を理解し、目的に合ったスペックを見極めることが欠かせません。
また、GPUの調達方法を検討する際には、プロジェクトの性質や期間を考慮することが重要です。技術の進化が早く陳腐化リスクが高いGPU領域では、初期投資を抑えつつ常に最新スペックを利用できるクラウドGPUの活用が有効な選択肢として注目されています。
さくらインターネットの高火力 DOKは、時間単位の従量課金で専有GPUを利用でき、実験から本格運用まで柔軟に対応できるため、開発効率とコスト最適化を両立することが可能です。適切なGPU環境の構築により、ディープラーニングプロジェクトの成功確率を大幅に向上させることができるでしょう。GPU環境にお悩みのかたは、ぜひご相談ください。

さくらインターネットが提供している高火力シリーズ「PHY」「VRT」「DOK」を横断的に紹介する資料です。お客様の課題に合わせて最適なサービスを選んでいただけるよう、それぞれのサービスの特色の紹介や、比較表を掲載しています。



 New
New
 New
New

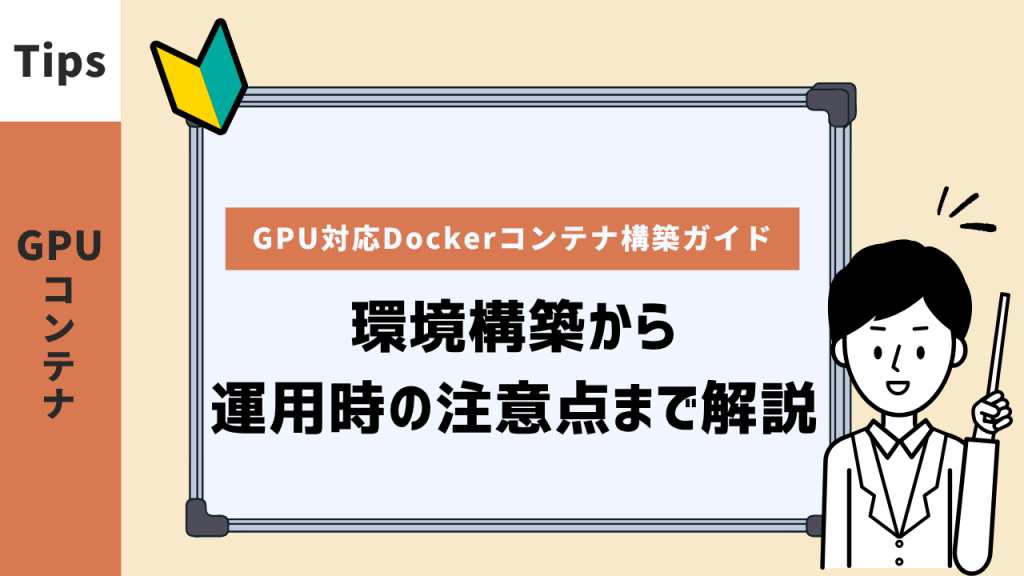
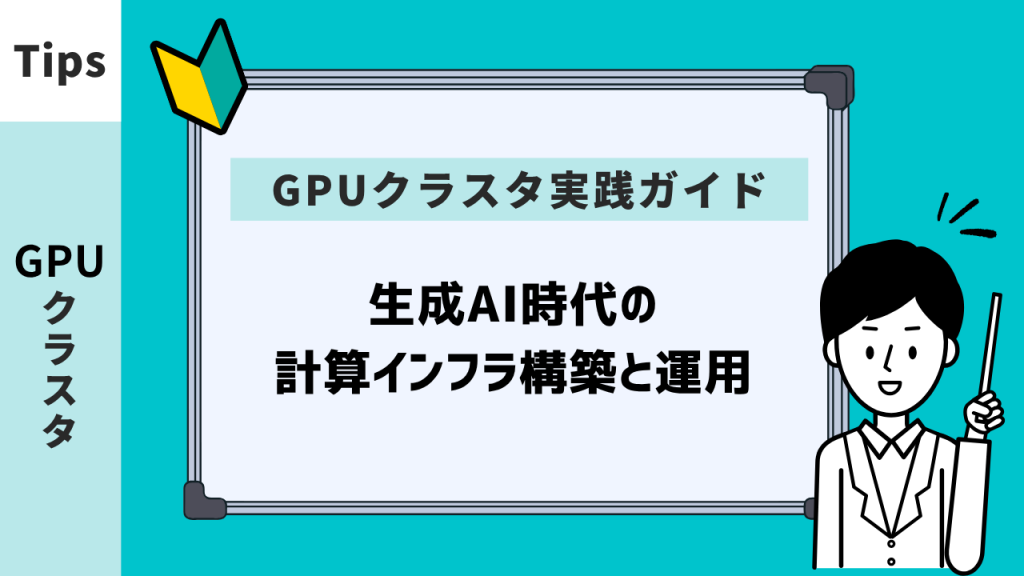
 特集
特集




