2023年10月1日、防衛生産基盤強化法が施行された。この法律は、日本の防衛生産・技術基盤を「我が国の防衛力そのもの」と位置づけ、その維持や強化策を講じて、装備品等の安定的な製造等をさらに推進するとともに、装備移転の円滑化を図ることを目指すものだ。国際的な情勢の変化や技術革新の進展に伴って防衛装備品のサプライチェーンは複雑化し、管理強化のためには民間製造業の協力やデジタル活用も不可欠になっている。本記事では、防衛生産基盤強化法の成立背景やサプライチェーンの課題、デジタル技術の活用などについて防衛装備庁 防衛技官 今村 健一氏(装備政策部 装備政策課 防衛生産基盤強化法室長)に聞いた。

今村 健一 氏 プロフィール
防衛装備庁 防衛技官(装備政策部 装備政策課 防衛生産基盤強化法室長)
2003年、防衛庁入庁。2016年から2018年まで防衛装備庁プロジェクト管理部事業監理官(航空機担当)で海上自衛隊練習機TC-90のフィリピンへの移転事業を担当。2018年から2021年まで同部事業監理官(情報・武器・車両担当)、事業監理官(宇宙・地上装備担当)で先任。2021年から同部事業監理官(誘導武器・統合装備担当)でスタンド・オフ・ミサイル事業のプロジェクト管理を担当。2024年9月から防衛装備庁装備政策部装備政策課防衛生産基盤強化法室長。
防衛生産基盤強化法成立の背景

「防衛生産基盤強化法は、2022年12月に政府が決定した『国家安全保障戦略』『国家防衛戦略』『防衛力整備計画』のいわゆる防衛三文書に基づいて成立した法律です。これらの文書では、防衛生産・技術基盤を取り巻く環境が厳しくなるなかで、優れた装備品の確保に必要不可欠な防衛生産・技術基盤を『我が国の防衛力そのもの』と位置づけ、抜本的な強化に取り組む、という方針が明確化されています」
防衛生産基盤強化法はこの方針に基づき、「装備品等の安定的な製造等の確保」などを実施するために、2023年6月に成立し、同年10月から施行されたものだ。
ここで安定的な調達を目指す「防衛装備品」とは何か。一般的には戦車や戦闘機など、特殊な専用品をイメージしがちだが、実際には多岐にわたる。
「車両や艦艇、航空機、その他自衛のために必要な防衛能力そのものを支えるものに加え、自衛隊が活動するために必要なあらゆる物品が『装備品等』に含まれます。身近なものでは、自衛官が派遣先で食べる食料品や日頃着用している制服も該当します」
たとえば災害支援で登場する装備品としては、輸送用のヘリコプターや水を確保するための浄水車両、孤立地域に物資を届けるために自衛官が利用する背のう(バックパック)などがある。災害時のテレビ報道でよく見られる炊き出し用の設備や入浴設備なども、もちろん「装備品等」に含まれる。これらの製造には、日本全国の多くの企業が関わっている。
「どのような装備品も、基本的に1社では作れません。たとえば1つの車両が完成するまでには、資源や部品の調達、製造加工はもちろん、輸送などの役務提供も含めると、民間を含む数万の企業が関わっている可能性があります。意外と気づいていないだけで、自分たちが防衛装備品の製造に関わっていた、というケースも十分に考えられます」
あらゆる装備品はサプライチェーンに支えられて自衛隊に届けられており、1つでも欠けると同じ製品の調達は困難になってしまう。それは民間の製品においても同様だが、そのなかでも防衛装備品に関しては、とくに以下のようなリスクを重視する必要があるという。
- 外国規制リスク:外国政府が資源の輸出を規制するなどして原材料等の日本への輸出が困難となる
- 事業撤退リスク:重要なサプライヤーが事業の継続が困難となって防衛事業から撤退する
- 外国資金リスク:外国の資本が防衛装備品の製造に影響力を行使し、防衛装備品の製造が安定的に進めにくくなる
- 懸念部品リスク・製造工程リスク:製造工程のなかで、悪意あるソフトウェアが混入する
「これらのリスクが顕在化すると、装備品等の安定的な製造などが困難になります。我が国の防衛力を支えるには各製造工程における具体的な課題を見つけ、それらを一つひとつ解決していく必要があります」
防衛生産基盤強化法の概要と狙い
防衛生産基盤強化法は、下図のような体制でこれらの課題に対応するものだ。

「基盤強化の措置」は大きく4つに分類され、それぞれ以下のような取り組みを通して、企業の課題やリスクの解決を目指す。
- サプライチェーン強靭化:国産化のための設備導入、国内調達のための設計変更、原材料などの備蓄、代替素材の研究開発などによって、外国からの部品や原材料の供給の停止に備える
- 製造工程効率化:新しい設備や先端技術の導入で自動化を進め、生産性を向上させることで、製造等の効率化や人手不足の問題による防衛産業からの撤退を抑止する
- サイバーセキュリティ強化:システム強化や人材育成を通して情報漏洩を抑制する
- 事業承継等:事業撤退する企業の設備移動や移転先企業のトレーニングなど、事業の承継に必要な経費に対して財政的な支援を提供する
今村氏によれば、これらの取り組みのなかで、とくに「生産量」と「品質」が防衛装備品ならではの課題になるという。
「たとえば自動車の部品メーカーでは、月間の生産数が数万から数十万に上ります。そのため『新規に投資して品質や生産量を上げ、コストを下げる』といった事業判断ができます。しかし防衛装備品はそれほどの大量生産を前提としておらず、さらに防衛装備品ならではの品質の高さも求められるため、民生品と同じような投資判断は困難です。そこで、基盤強化の措置のなかでこれらの取り組みに財政上の支援を実施します」
新規投資を促進するなかでも、IT・デジタル活用は製造効率化・生産性向上において重要な役割を果たすが、現場の作業実態を理解したうえで計画をしていく必要もある。
今村氏はこうした点を考慮しつつも情報システムの活用について「民間企業にとっても防衛装備庁にとっても進めていかなければならないもの」と強調する。
また、基盤強化の措置のなかで投資した設備は「20年、30年と使える状態であることが望ましい」と強調する。その中に組み込まれるシステムやソフトウェアにも同様の長期的なサポートが必要であるとし、国産の設備やシステムへの投資を「長期的な安定性を求めるうえで合理的」と述べた。

サプライチェーン調査をさくらインターネットが支援
防衛装備庁のIT活用として、さくらインターネットは「サプライチェーン調査」を支援している。サプライチェーン調査は、防衛装備品を直接納品するプライム企業およびそれを支えるサプライヤー企業群とサプライチェーン上の課題を明らかにするものだ。
さくらインターネットは2024年4月、防衛装備庁と「サプライチェーン調査に必要な役務の提供等」についての役務請負契約を締結し、調査の中では「さくらのクラウド」が使われている。
>>(ニュースリリース)さくらインターネット、防衛装備庁と約7.5億円の役務請負契約を締結
国内企業への期待、今後の展望
労働人口が減少するなかで、生産効率の向上は官民問わず喫緊の課題であり、デジタル化は必要不可欠な取り組みとなる。今村氏は「企業の皆さんの経験、知見、技術をさらに磨いていただき、それを製造企業の現場に投入して、生産性を向上していただきたい」と期待を込めて語る。
「みなさんのものづくりが、我が国の安全保障につながっています。各種製品を、しっかりと、速く、多く、これまでどおりの高品質で作っていただくためのお手伝いをするのが、我々の取り組みです」
今村氏によれば、2023年10月の法施行から1年半が経過し(取材時点)、サプライチェーン調査の実績は蓄積されつつある。「調査の手法もある程度確立し、データの蓄積も進んできました。リスクに対する支援のアプローチ方法も実例として積み上がりつつあります。これからが本番です」という。
製造技術は、事業撤退や承継の失敗などによって、一度失われると復活が難しくなる。技術を守り、サプライチェーンの脆弱性を補って、防衛装備品の供給網を途絶えさせないようにする取り組みは、国家の防衛力維持につながっている。
今村氏は「防衛生産・技術基盤の強化を通して、自衛隊がしっかりと機能できる環境を支えたい」と語り、我が国の防衛生産・技術基盤を担う事業者を支援する取り組みへの参加を呼び掛けている。


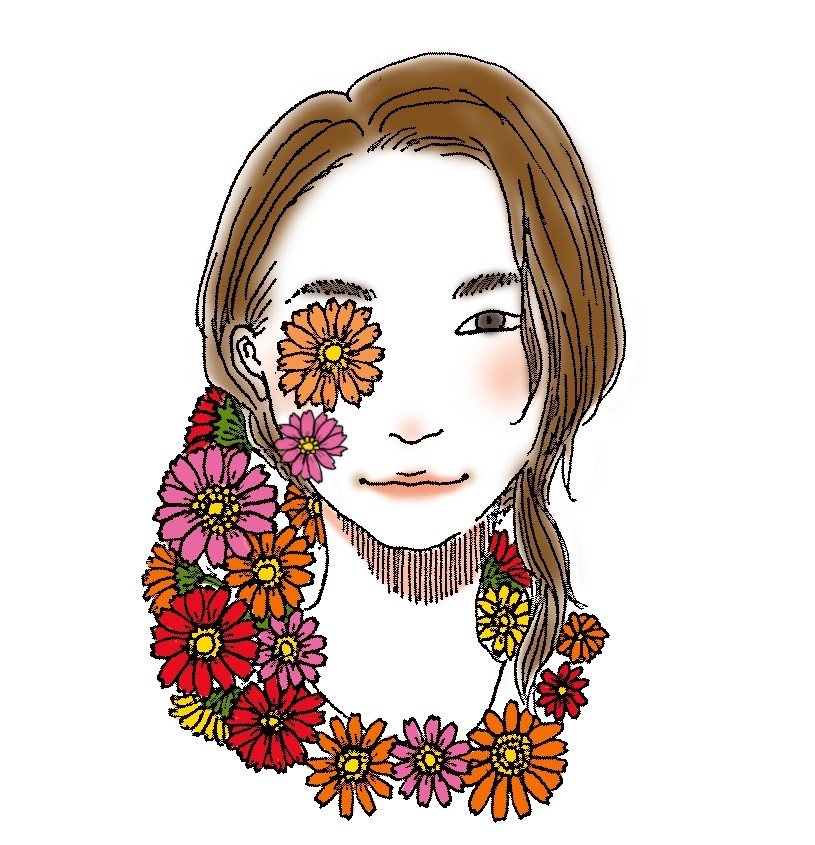
 New
New
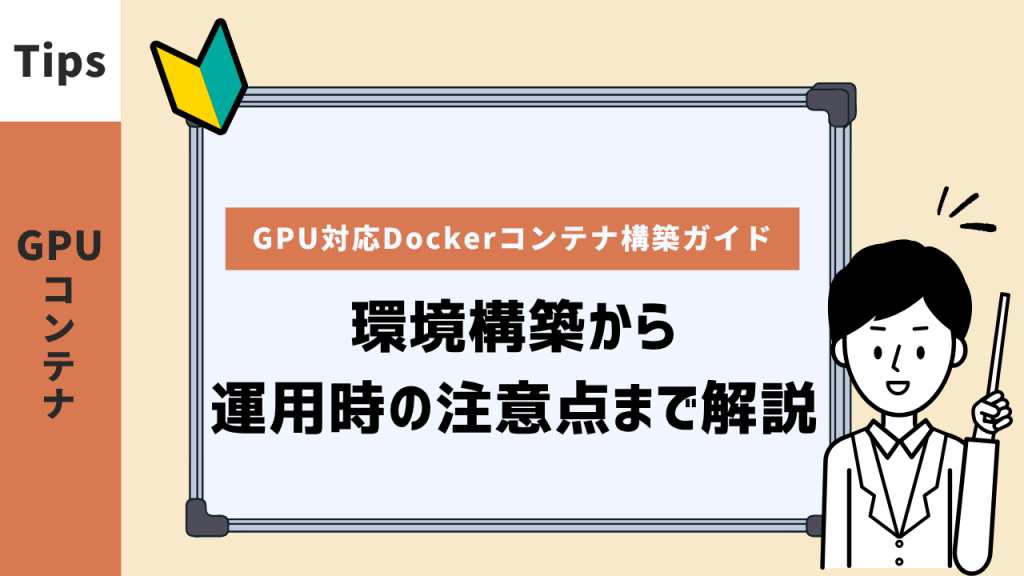 New
New
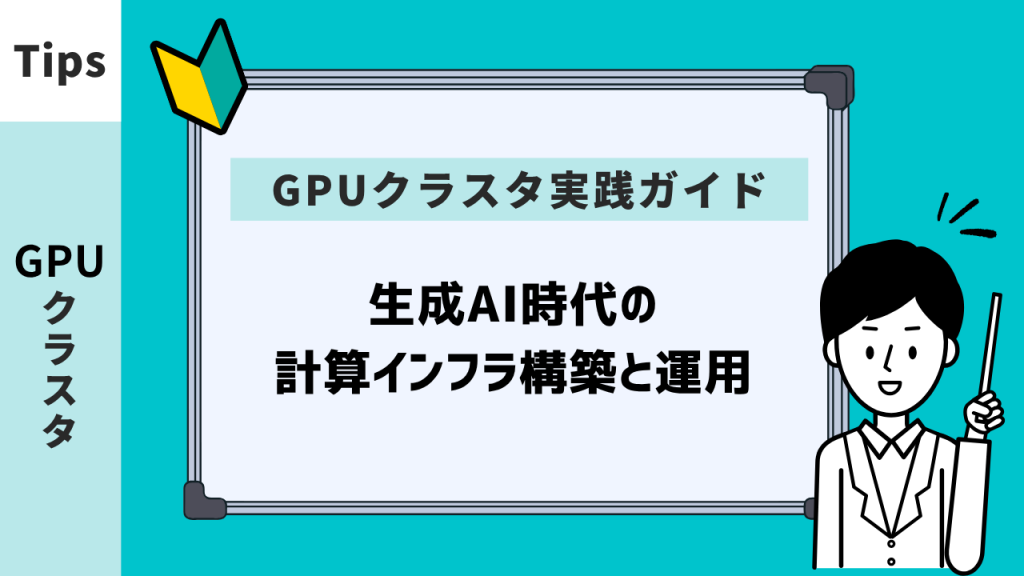

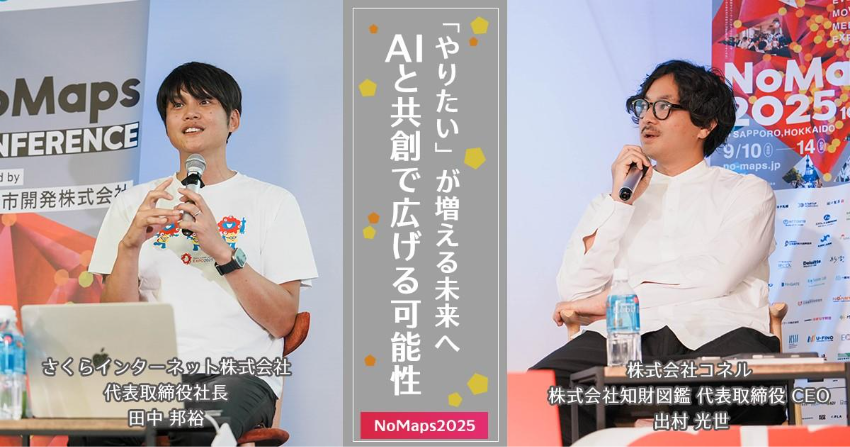
 特集
特集




