>>さくらインターネットの生成AI向けクラウドサービスとは?
空間を具体的にイメージするのは、そう簡単な話ではない。とくに住宅の購入時、間取り図だけを見て大きな買い物を決断をすることに、不安を感じる人は多いのではないだろうか。そうした際に役立つのが3Dパースだが、作成には専門的なスキルが必要であり、手間や時間もかかるため、依頼先によっては対応が難しい場合もある。
こうした課題に着目したのが、株式会社annviewだ。代表の植木拓さんは、間取り図をアップロードするだけで3Dパース作成ができる生成AIクラウドサービス「annview(アンビュー)」を開発。画像認識技術と生成AIを用いて間取り図から3Dパース画像を生成する技術は、特許も取得している。植木さんに、着想の背景や開発の苦労について聞いた。

植木 拓(うえき たく) プロフィール
東京工業大学卒業後、オーストラリア国立大学にてコンピュータサイエンスの修士号を取得。Web系ベンチャー企業でAIやXR技術を活用した新規事業開発に携わった後、不動産テックスタートアップにてR&DマネージャーとしてAIや3DCG分野の技術開発を主導。現在は株式会社annviewを創業し、画像認識技術と生成AIを組み合わせたサービスの開発・提供に取り組んでいる。
当事者としての体験が「annview」のアイディアに
3Dパースの作成にはCADを扱えるなど専門的なスキルを要する。そのため、「不動産会社やハウスメーカーの規模によっては、顧客である一般消費者に必ずしも提示できる状態にはない」と植木さんは指摘する。「annview」は、植木さん自身の消費者としての体験から開発された。
「家庭を持ち注文住宅の購入を検討した際、ハウスメーカーから提示されたのは間取り図のみ。その家が実際にどう見えるのかがイメージしづらかったんです。そんな状態で数千万円という高額な買い物をするのは、ハードルが高いなと思いました。周りに聞いてみても、3Dパースを見ずに買うかどうかを判断したという人が多かったんですよね。大手メーカーであれば3Dパースの提示が通常サービス内に含まれているのかもしれませんが、提供がない、あっても有償オプションという会社も少なくないことを知りました」
「annview」は、AIが間取り図をもとに壁やドア、窓、家具といった空間を構成する要素を自動で解析、抽出することで、3Dモデルを自動で構築。そこから部屋のテイストを画像で指定することで、リアルな3Dパース画像を出力することができる。画像認識技術と生成AIを用いて間取り図から3Dパース画像を生成する技術については、2025年6月に特許を取得済みだ。
目指しているのは「間取り図の3D化をもっと身近にし、誰にでも簡単に使えるようにして可視化のハードルを下げること」だという。
コンテナー型GPUクラウドサービス 高火力 DOK(ドック)
>>サービスの詳細を見る
会社員として働きながらコツコツ開発
植木さんは、東京工業大学を卒業したのち、オーストラリア国立大学に留学するなど、学生時代からAIの研究を重ねてきた。
「ここ数年で生成AIが伸びてきましたが、2017、18年ごろはAI、ディープラーニングが盛り上がってきたタイミングで、まだ世に出ていない新しい製品やサービスに携わりたいと感じ、渋谷にあるベンチャー企業に入社したんです。そこで、エンジニアとして新サービスの技術開発をしていました」
この企業で「なかなか自分が思うような仕事ができなかった」という植木さんは、不動産テックベンチャー企業に転職した。この会社で、部屋を写真から3Dに転換し、自由に歩き回れるリッチなオンライン内見体験を提供するサービスの技術開発を担当。この経験に加え、前述した自身の住宅購入時に感じた課題が、「annview」の着想につながった。
「調べてみたところ、間取り図を誰でも3D化できる、私が思い描いたようなサービスはまだ世にありませんでした。写真のようなクオリティで3D化するには、本来とても時間がかかります。私は3Dも触れるので、いかに“写真のような画像”を作るのが細かい作業であり、労力のかかるものなのかを理解していました。これがAIにより一瞬でできるようになれば、CADを使えない営業担当者でも、気軽に3Dパースを作成し、役立ててもらえるのではないかと思ったんですよね。テキストではなく、形そのものをAIにインプットする関連技術が出てきたときに、『この技術を応用できれば実現できる』と確信。先行者がいなかったことが挑戦の後押しになりました」
会社員勤めを続ける傍ら、夜間や週末の時間を使って、すべて植木さんひとりで開発を進めた。開発に要したのは、およそ1年弱。まだ一般的ではないAI技術のため、ゼロから作らなければならないところが多く、「正直、何度も投げ出しそうになった」と当時を振り返る。
「少しずつ精度が上がり、部屋の画像が出てくるのが見られるようになってきて、『悪くないな』と思えるようになりました。とはいえ、リリース後のいまもまだまだ改善の余地がある状態ではあります」
開発において最もこだわったのは、簡単に使用できることと、内装デザインのバリエーションを増やすことだった。類似サービスと比較して、「annview」はプロが作った間取り図をほとんど手間なくビジュアライズし、さらにさまざまなバリエーションで内装を可視化できる点が特徴だ。
特別な知識がなくても誰でも使えるように
植木さんが初めに期待していたユーザーは、ハウスメーカーだった。専門スキルがなくても、営業担当者が間取り図から3Dパースを作成し、住宅購入を検討する顧客に提示できるようにというねらいだ。しかし、顧客に見せるための画像となると、相当な精度やクオリティが求められ、100%の出来栄えでなければ導入に踏み切ってもらえないという。
「お使いいただいたハウスメーカーさんからは、ご期待の声を寄せていただきました。ただ、顧客に提示するものとして実用化するには、いまの精度では足りない。そのため、さらに精度を高めるべく取り組んでいるところです。AIによるテキスト生成と比べ、画像の生成はその後に人が手を加える難易度が高く、それでいて文章より瑕疵に気付きやすいという特徴があります。そのため、テキスト生成に比べて画像生成のほうがジャッジがシビアになりがちで、だからこそ高精度への期待値が高くなるのだと感じていますね」
もうひとつ、中古物件においてリフォーム後の予想図の可視化に活用できないかと植木さんは考えていたが、こちらは、いまの精度でもニーズにハマったという。
「社内で検討するフェーズにおいては、顧客向けほどのクオリティに至っていなくとも活用可能だということです。CADを扱えるスキルのない営業の方、企画の方だけであれこれリフォームのシミュレーションを試していただけているようですね。意外だったのは、間取り図が3Dになるだけで喜ばれる会社さんが多かったこと。大変ありがたいのですが、そこからさらにリアルな画像生成ができるのが『annview』の売りですので、そのあたりももっと活かしていただけるとうれしいですね」
「annview」は個人のユーザーにも提供しているが、そちらでのマネタイズは考えていないという。工務店やハウスメーカーの担当者とやり取りをする可能性のある個人のユーザーにサービスを知ってもらうことで、工務店、ハウスメーカーに利用してもらうきっかけにするという流れを期待している。
「特別な知識がなくても誰でも使えるサービスを目指し、とにかく使いやすいUI/UXにこだわって開発を進めてきました。新築物件だけではなく、リフォームの検討など、間取り図だけではイメージしづらいときに、誰でも簡単に3Dパースを作り、写真のようなリアルな画像で確認できる。『annview』のように一瞬でイメージを出せるサービスはまだほかにはないと自負しています。すでに一定の評価もいただいていますが、まだまだ伸びしろがありますので、今後もさらなる高みを目指していきたいですね」
さらなるクオリティ向上が目下の課題
今後について、まずは「簡単な編集機能を付与したい」と植木さんはいう。
「誤解されがちなのですが、AI生成は一発で理想通りのものを出力するというよりは、出したものに対し、AIへの指示(プロンプト)を工夫することで、より期待したものに近づけていくものなんですね。ただ、画像の場合は編集が難しいのがネックなため、誰でも簡単に編集できるようにすることで、より思い描いているものを作れるようにしたいと考えています。もちろん、長期的にはできるだけ少ない回数で、思い描いていたものを出力できる精度まで高めたい。でも、『いろいろ試すことで、いいものを作れるのが生成AIのおもしろさである』ということもお伝えしていきたいですね」
中長期的には、店舗やオフィスなど住宅以外のものにも領域を拡大。さらに、まだ建築されていない架空の建物を内見するといった、空間を歩き回れるアプリケーションを目指していきたいという。
その先については「明確に決まってはいない」という植木さん。ただ、画像生成AI技術の活用という軸はブレないと語る。
「この技術が好きなので、これからもその軸で何かができたらうれしいです。みなさんにも、ぜひ試してみていただきたいですね。ネットで見た画像を使って、自分の理想を具現化できるのが『annview』の新しさなので、1枚作ってみて終わりではなく、そこからいろいろいじりながら遊んでみてほしいです」
>>さくらインターネットの生成AI向けクラウドサービスとは?

執筆
卯岡 若菜
さいたま市在住フリーライター。企業HP掲載用の社員インタビュー記事、顧客事例インタビュー記事を始めとしたWEB用の記事制作を多く手掛ける。取材先はベンチャー・大企業・自治体や教育機関など多岐に渡る。温泉・サウナ・岩盤浴好き。
※『さくマガ』に掲載の記事内容・情報は執筆時点のものです。
- SHARE


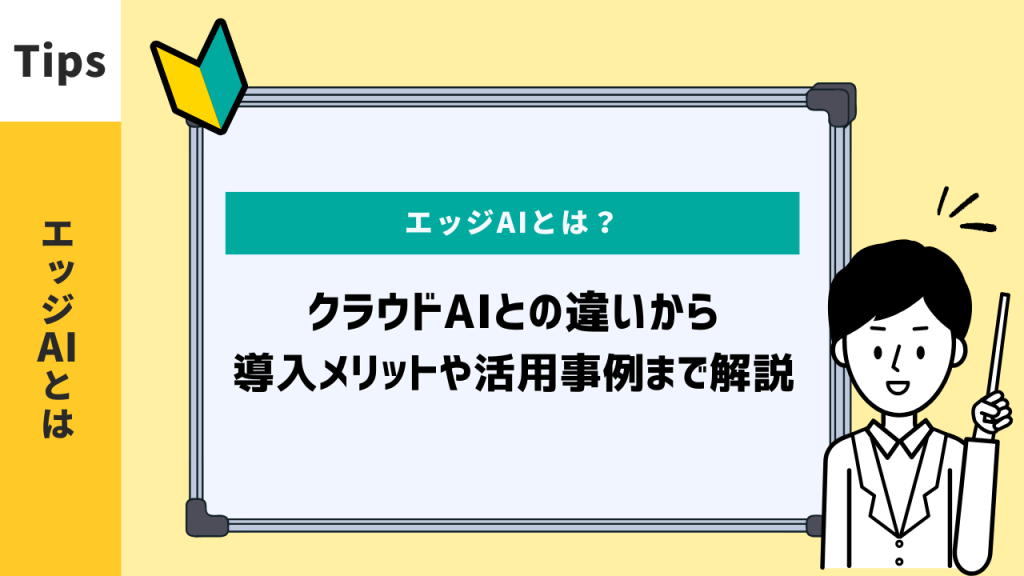

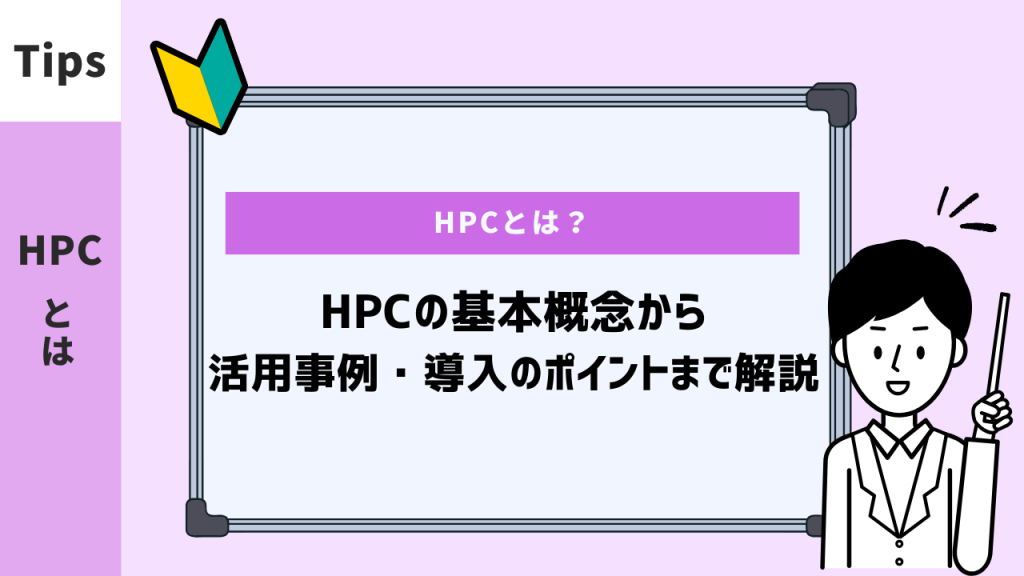
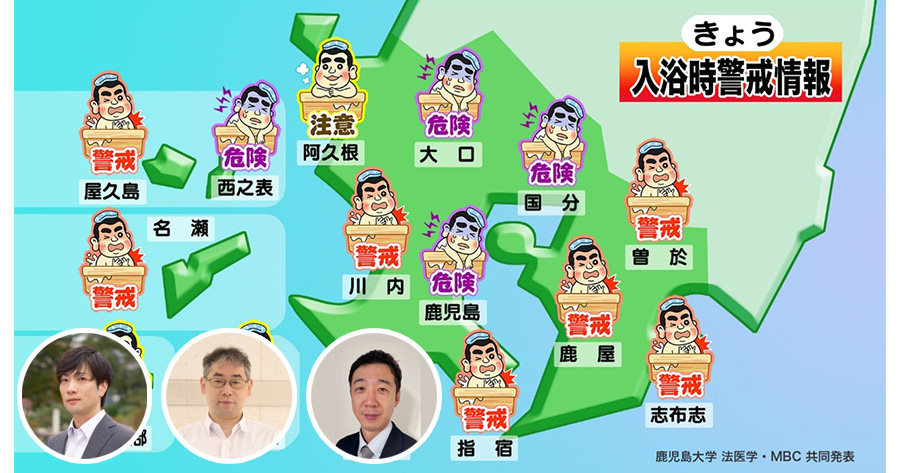

 特集
特集




