
「AI に仕事を奪われる!」
人工知能が進化するたび、巷で言われるこんな言葉。
近年、耳にタコができるほど聞かされてきたフレーズであり、それに対する異論反論もかなりの程度、テンプレ化しているように感じられる。
わざわざ自分のような底辺ライターが物申さずとも、世の中には AI、とくに直近で話題の ChatGPT に関する論説など、すでに飽和状態。
それでもあえてこのテーマを選んだのは、IT感度が高い方、はたまた意識 & スキル面で時代の先を行く方とは異なる視点の AI観を伝えたいと思ったからだ。
そんな筆者が AI 関連でいま考えていること。
それはたとえば、AI が仕事を奪うといわれて久しいが、ではどれほど技術が進歩すれば日本企業から「働かない人」が一掃されるのか? という疑問である。
また、教育への AI活用についても関心事の1つだ。筆者が若干携わっている語学や教育方面でいえば、学生の AI 利用を制限すべきとの論調があり、海外ではすでに対策が取られているところもあるという。
だがこれは、自分のようなひねくれた人間にとっては、「先生も使わない」という前提がなければフェアじゃないと感じてしまう。
少なくとも、筆者は仕事で AI 関連のサービスを利用している以上、同じ道を歩もうとしている若者に「使うな」とは言えないし、むしろ活用しなさいとすすめることもある。
……と、要するに以下は技術的な話は一切抜きで語る、体験ベースのごく私的な AI観。
おもに翻訳や言語学習、ライティングの現場からみる人工知能技術について、
「AI が働き方を、そして世界を変える!」
といった暑苦しさ抜きで、まったりと語ってみたい。
社会の仕組みの進歩は AI ほど速くない
AI がいまのように賢くなるはるか前、自分は都内の某出版社に勤めていた。
その経験を通じて痛感したのは、会社組織には多かれ少なかれ、スキルが陳腐化して無用と化している方が存在するということだ。
ちなみに当時の勤め先は社員200人程度と、吹けば飛ぶような規模である。
そんななかに、スキル不足が否めない先輩も多数いたわけだが、取引先の印刷会社や広告代理店といったいわゆる大手企業とて、よくよく観察すれば似たりよったり。
たとえば、特定のスキルを必要とされて入社した人がいたとして、数年後そのスキルが不要になってもまったく違う部署などに回されるだけでクビになることは少ない。結局、日本ではそう簡単に社員をクビにはできないのだ。
スキルどうこう以前に戦力外な方も、またしかりである。
つまり何が言いたいかといえば、「AI が仕事を奪う」といったところで、この手の人々がすぐさま駆逐されるとは到底思えないということだ。
目を閉じれば思い出す、かつて一緒に机を並べて働いた先輩方。
ZIPファイルの開き方がわからないと事あるごとに聞いてくる役員。
データ入稿にフロッピーはやめてと何度言われても使い続ける編集者。
編集職だったのに広告部に飛ばされ、連日直行直帰で半年ほど見かけないこともあった営業マン。
こういう人から、どうやって仕事を奪うのか。
そもそも彼らに仕事はあるのか―ー。
AI の進歩は速い一方、社会の変化は非常にゆるやか、というかそう簡単には変わらない。
他国はともかく、巷間で取りざたされるような AI失業が日本で大々的に起きるかというと、職種にもよるだろうが筆者はかなり懐疑的だ。
リスキニングなんてハナからやる気もないが、絶対に自分から辞めたりしない、そんな「働かない人」たちの粘り腰を舐めてはいけない。
よい悪いはともかくとして、スキルの陳腐化が即失業につながるとは限らないーーこれもまた、筆者が会社勤めで得た何の役にも立たない知見である。
技術ではなく人為が仕事を奪うこともある
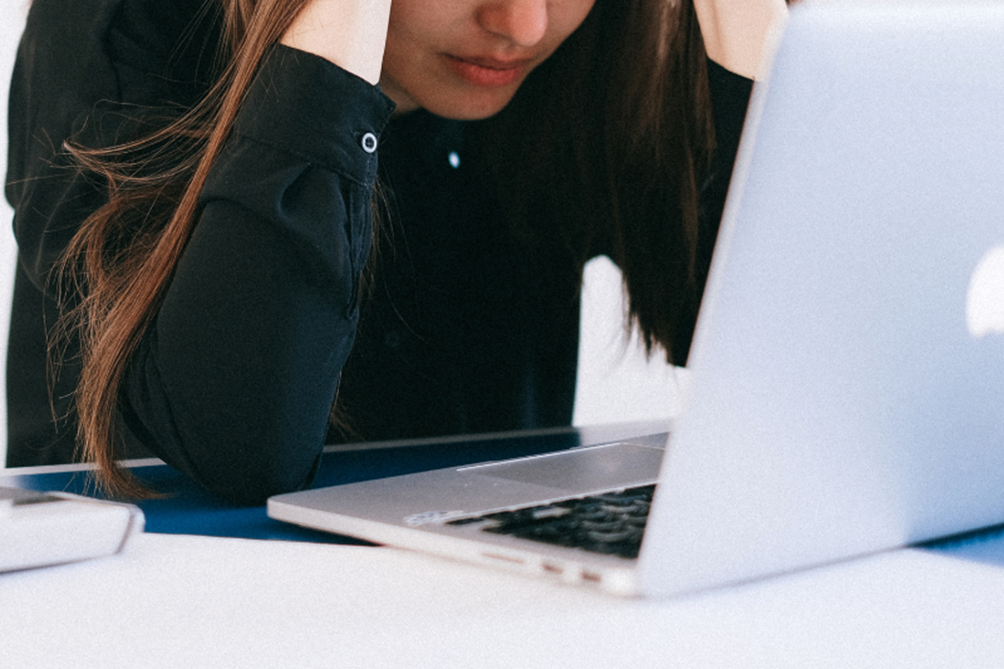
話題となって以降、筆者もぼちぼち利用している ChatGPT だが、個人的には機能を使いこなすことよりも解説動画を見るほうが楽しかった。
理系な話はさっぱりなので、チェックするのはおもに自分の仕事と関係のあるライティングや語学関連での応用例。
もっとも、「無限に SEO用の記事を書かせられる!」という動画を見れば、「そもそも AI に聞けば答えが出るレベルの記事なんて、今後要らなくなるのでは」と疑問の1つもぶつけたくなる。
つまるところ自分は根が素直ではないわけだが、それでも「AI が語学学習に与える影響は大きい」といった論調には、首肯させられる点も多かった。
というのも、筆者はたまたま現在、ピンチヒッターとして中国で日本語の授業を受け持っており、カリキュラム進行中に ChatGPT 流行の波が自分の住む中国にも及んだからだ。
学生たちも AI を使ってよしとするか、禁止すべきか。
ダメだというなら、どのような理由からか。
そんなことを考える必要性に迫られたのである。
ちなみに余談だが、AI が仕事を奪うという話でいえば、語学の先生も影響を受けてもおかしくない。
そもそも近年、語学学習アプリでかなり高性能なものが普及していたところに、現状文字入力とはいえ、ネイティブ並みの言葉を操るチャット相手がインターネット上に現れたわけだ。
そんな情勢に追い打ちをかける出来事が、昨年中国であった。政府の方針によって学習塾業界が根絶やし同然にされ、大勢の塾講師が失業したのだ。前述したクビになりにくい日本の例とは正反対である。
突然の学習塾規制。そのココロは、高騰する家計の教育費負担を減らすためだった。
学外授業を禁止すれば教育費負担を抑えられるだろうという直球ロジックなのだが、まさに AI の進歩もかなわない政策のスピード感。
むろん大混乱を招いたわけだが、技術革新ではなく人為により、これほど大量の人々が職を奪われることがあるのだなとしみじみ思ったものである。
AI が語学学習に与えるインパクト

さて、話を語学と AI に戻すと、両者が恐ろしいほどに相性抜群であることは、もう否定のしようがない。
何しろ、翻訳仕事を多々請け負ってきた筆者も、普通に AI 翻訳を便利に使っている。
むろん、AI 翻訳の文章をそのまま使ったりはしないが、ビシッと決まるいい訳文が思い浮かばないとき、おうかがいを立てる感覚で原文を放り投げてみる。
すると、毎回ではないけれどヒントが見つかったり、「それでいいじゃん」と思うような答えが返ってきたりするわけだ。
また、2か国語ならまだしも、資料として英文を読まなければいけない場合などは、そのときの忙しさにもよるが思い切り頼ることもある。
端的にいって、仕事でそのまま使える精度ではないとはいえ、筆者の場合はネット辞書と同じ感覚で利用するお手軽ツールになっている。
そこで話は冒頭に戻り、「自分が使っている以上、あなたたちは使用禁止ですとは言えないよね」というのが筆者の持論である。
そもそも筆者は講義の際、これからの翻訳は記憶と辞書だけでなく、IT を駆使してやるものだと教えている。
語学試験などではそうはいかないが、仕事で文章を扱う場合、母国語で何かを書くにしろ翻訳にしろ、リサーチは必須である。
たとえば、仕事で専門性の高い分野の翻訳を頼まれ、その方面にくわしくなかったとしよう。
その場合、翻訳と同等、もしくはそれ以上に調べ物に労力を費やすことになるが、精度の高い訳文を納品するためには絶対に必要な時間といえる。
こちらで長年翻訳に携わり、すでに引退したある方は、
「昔は辞書なんて職場に何冊もなくて、使いたいときは順番待ちになることもあった」
と言っていた。
それから急速に豊かになった中国では、1人1冊辞書を持てるようになり、やがて電子辞書が普及。
そして現在は誰でもインターネットにアクセスできる時代が到来し、IT は語学の現場においてあって当たり前のツールとなっている。
筆者は昨今話題の高性能な AI サービスも、このような延長線上にあるものだと考えている。
これほど便利なツールが、普及しないわけがない。
止めるだけ無駄、むしろそれらを学習や仕事に正しく活かす方法を考えるほうがよほど建設的だ。
むろん、初学者が AI を使って課題をこなしても、何の学習にもならない(AI への指示の出し方は学べるが)。
それでも使う学生がいたとしても、本人の選択だと考えるしかないのではないか。
別にこういった問題は AI に限らず、Wikipedia 丸写しの課題提出などはいままでもあった話。
よって、自分が受け持っている学生たちには、
「AI 結構、どしどし使いなさい。ただし、自分にとってメリットになると思えるならば」
と伝えている。
これが現時点での AI との付き合い方に関する、筆者なりのアドバイスである。



 New
New
 New
New
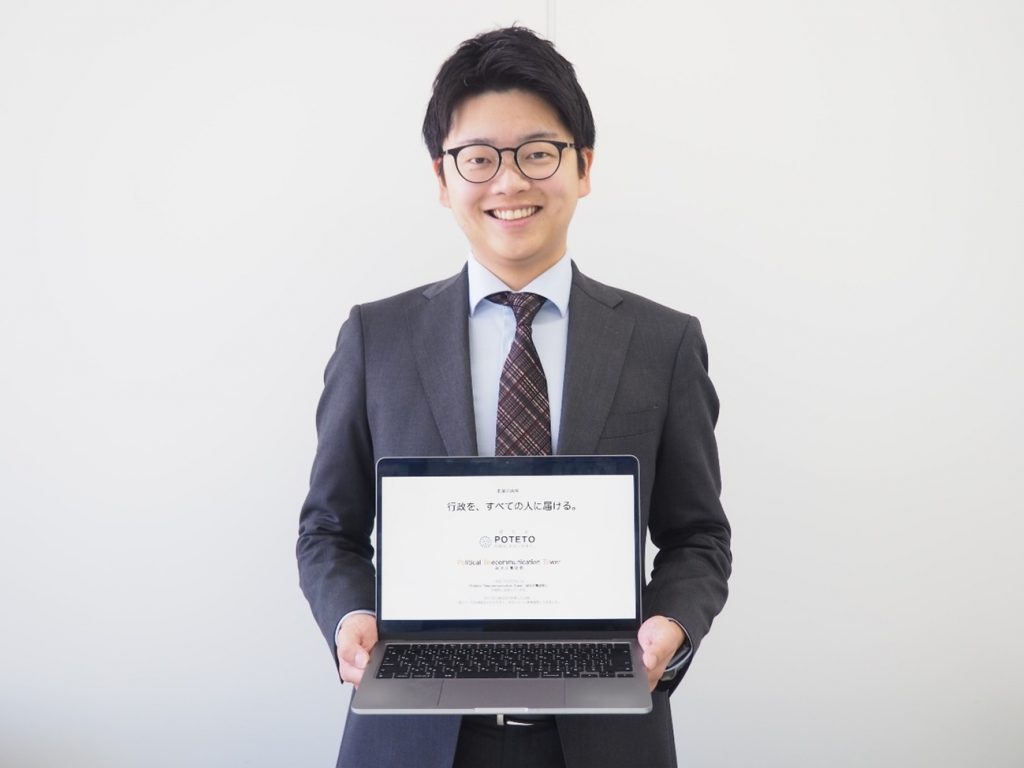
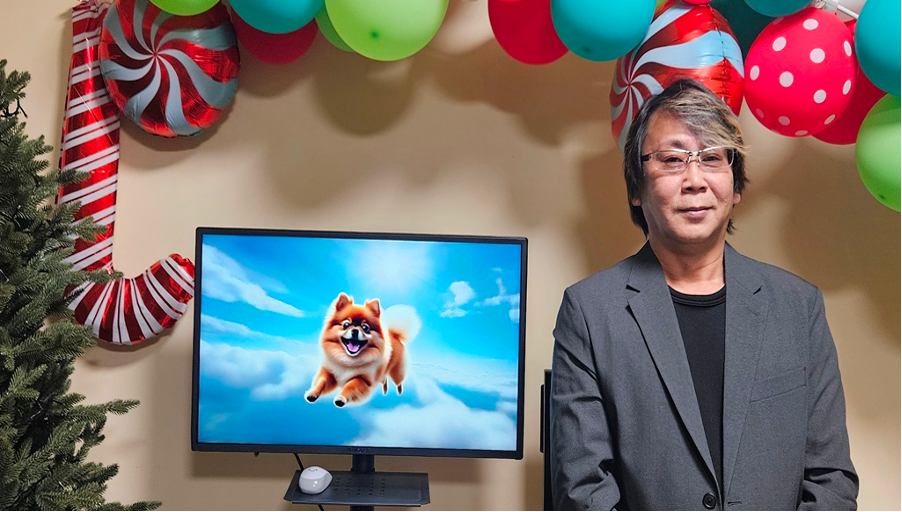
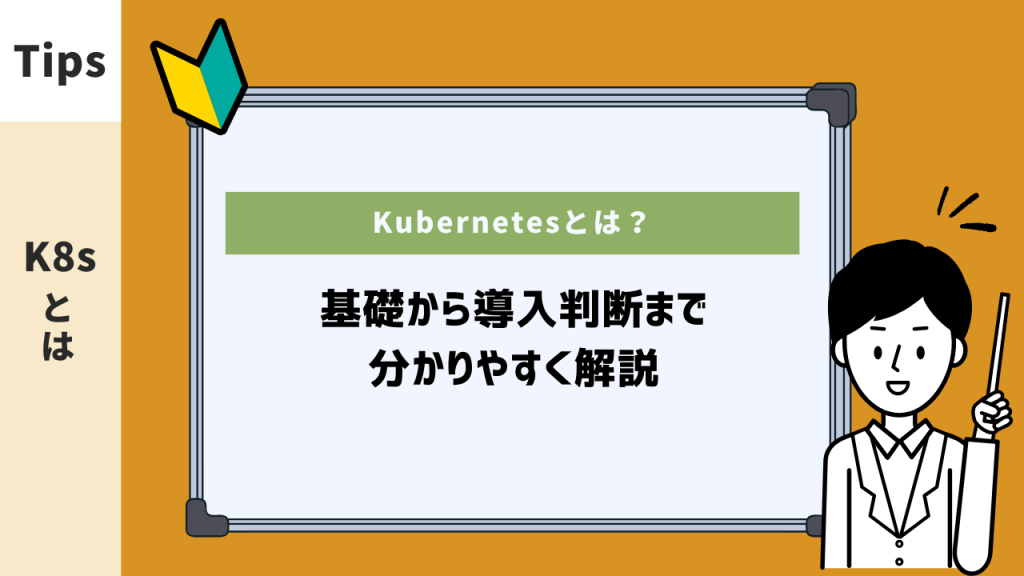
 特集
特集




