
私事だが、先日、実家で飼っているフレンチブルドッグの乙(おつ)が、とある手術を受けた。
異変に気付いたのは8月の終わり頃。乙の左手小指の外側に、プツっとしたイボのようなものが現れたのだ。
犬は高齢になると、このようなイボが発生しやすくなる。そこでしばらくの間、様子を見ることにした。
しかし、みるみるうちにイボは大きくなり、痛々しいほどぷっくりと育ってしまった。
「これはいけない!」と、すぐさま動物病院へ連れて行ったが、主治医の見立ては「そこまで悪いものではない」ということで、とりあえずは経過観察となった。
母が乙を連れて受診してくれたのだが、「こんなに痛々しいのに、経過観察で大丈夫なの?」と、やや不安を感じる私。
そこで、乙の症状をネット検索したところ、似たような症例がいくつも出てきた。しかもそのほとんどが、大事には至らず回復している様子。
疑ったわけではないが、やはり主治医の言う通り、もう少し経過を見守ることにした。
ところが、一か月が過ぎるとイボはますます巨大化し、もはや小指を超える大きさとなった。さらに、乙がイボを舐めることから出血もみられる。
さすがに今回は細胞を採取して、顕微鏡での検査を実施。だが細胞の形は崩れておらず、しっかりしているので「良性の腫瘍だろう」とのこと。
ステロイド剤も服用しているため、再び、経過観察となったのだ。
どうやらこの病気の特徴として、イボ(組織球腫という)は2〜3か月で退縮することが多く、これといった治療法がないらしい。
だが乙の場合、組織球腫があまりに大きく膨らんだため、さすがに切除しなければ生活に支障が出るレベルとなってしまったのだ。
後日、改めて主治医に相談したところ、
「部位が部位なので、小指ごと切断になるかもしれません」
と告げられ、私は驚きとともに絶望を感じた。
(いくら犬とはいえ、球腫を切除するのに指まで切り落とさなければならないの?!)
にわかに信じられない私は、とある友人に相談した。
愛猫が難病を発症し、いくつもの動物病院を駆け回った末に、命を救われた経験のある人物だ。
すると彼女は、意外な方法で”助け船”を出してくれたのである。
Instagram の威力

「猫ママたちのインスタ(Instagram)ネットワーク、すごいんだよ」
友人がこう切り出した。
「うちの子なんか病院を5軒もハシゴしたのに、なんの病気かわからなかった。それで泣く泣くインスタに、『助けてください』『どこか病院を教えてください』って投稿したら、すごくたくさんの情報が集まったんだよ」
その結果、彼女の愛猫は一命をとりとめたのだ。
一通り乙の症状や画像を確認すると、友人はすぐさま Instagram に投稿してくれた。
「友だちのワンちゃん、足の指に腫瘍ができて手術予定です」
「同じような症状で手術された方、経緯や病院を教えていただきたいです」
「情報提供、拡散いただけると嬉しいです」
すると1分も経たないうちに、何件かのリアクションがあった。
「少し遠いですが、〇〇県在住の猫ちゃんは骨肉腫で断脚手術を受けました。飼い主さんは全国を飛び回る仕事をしているので、何かいいアドバイスが聞けるかもしれません」
「愛猫の顎に腫瘍ができ、検査するも異常なし。しかし徐々に大きくなり出血することも。再び検査するも異常なしで、その後もどんどん大きくなる一方。絶対におかしいと訴え、ようやく切除手術をしてもらった結果、良性の細胞と急成長する悪性の細胞とが混在していました」
「動物病院を探しているとのこと、〇〇県ならばここがオススメです。うちの子が、肝リピドーシスになったのを助けてもらったので」
投稿の際に、私のアカウントをタグ付けしてくれたことで、見ず知らずの「猫ママフォロワー」たちから、次々とDM(ダイレクトメッセージ)が送られてくるのだ。
もちろん、友人のところへもたくさんの情報や励ましのメッセージが集まっている。
さらには、本職である獣医師からのコメントまでもが届いた。
夜中にもかかわらず親身になって相談に応じてくれるなど、リアルな繋がりだけではありえない、奇跡のコミュニケーションが実現したのである。
これらの出会いのおかげで、私は、乙の病気について正しく理解することができた。
さらに、組織球腫を切除するにあたって、「なぜ、小指を切断する必要があるのか」についても、納得することができた。
*
ちなみに、乙の病名をネット検索すると、動物病院のサイトやブログに辿り着ける。しかしそれは一方的な情報提供であり、乙に当てはまるかどうかは判断できない。
当然ながら、主治医でもなければ獣医師でもない素人が、勝手な判断をしてはならないことは承知している。
だが、セカンドオピニオンとまではいかなくとも、同じ病気を経験した飼い主たちの声が聞けるというのは、少なからずポジティブな気持ちになれるのも事実。
そして、このような双方向でのコミュニケーションを可能にした「Instagram の存在」は、単なる SNS を超えていると感じたのである。
余談だが、友人のフォロワー数は千人を超えている。しかし愛猫専用アカウントのため、彼女の顔や本名を知る者はいない。
さらに、フォロワー同士は「〇〇ちゃんのママ」というように、飼い猫の名前に「ママ」「パパ」をプラスした呼び名が採用されているため、個人が特定されることもないのだ。
こうした未知のやり取りに、私はいちいち戸惑った。
「ワンちゃんのママさん、応援しています!」
などと言われると、どこか照れくさい気持ちになる。
さらにお礼のメッセージでは、コロママさん(愛猫がコロ)、虎太郎ママさん(愛犬が虎太郎)といった具合に、ペットの名前+ママの表記で感謝を伝えなければならないわけで、これまた照れくさい。
それにしても、乙の病気がなければこのような出会いもやり取りも経験できなかったわけで、改めて猫ママたちのネットワークの凄さに脱帽である。
そして、猫好きの Instagram を「ニャンスタグラム」と呼ぶことも、併せて覚えておこう……。
ググるよりもインスタ?!

ニャンスタグラムの友人とは別に、Instagram で子供用の手作りグッズを販売しているシングルマザーの友人がいる。彼女いわく、
「最新の情報を知りたいなら、Instagram で検索するのが一番だよ」
とのこと。
たとえば、人気カフェの様子やリアルな評価が知りたいとき、その店を Instagram で検索することで、たくさんの画像やコメントを見ることができる。
言い換えると、店が用意した宣伝用の画像からは見えない「リアルなカフェ」を覗くことができるのだ。
投稿の多くは「美味しい」「映える」「オシャレ」といった表面的な評価だが、なかには独自目線で「他店のパンケーキとの比較」「ドッグランや授乳室など、近隣施設の情報」「店内の空気感」といった、その人ならではの感覚や情報を知ることができる。
要するに、意図的に作り上げられたキャラクターやコンセプトではなく、個々のリアルな声が聞けるからこそ、検索する側も Instagram を利用するのだろう。
*
子供用グッズの流行をチェックするために、友人は毎日 Instagram で情報収集をしている。
ネット検索よりもリアルタイムで、最新のトレンドを知ることができるからだ。
そして時にはフォロワー同士で情報交換をしたり、商品についてやり取りをしたりと、場所や時間にとらわれずスマホ一つで交流できる。忙しい子育てママにとってありがたいポイントだ。
もともとは画像や動画を共有する SNS としてスタートした Instagram だが、今ではその枠を超えて、現実社会の繋がりを超えた強い絆と、信憑性の高い検索エンジンとしての地位を確立している。
顔や名前を知らなくても、お互いが求める「共通の興味・関心」さえあれば、私たちは世界中と繋がり、お互いに影響し合うことができるのだ。
――これこそが、DX の真の姿なのではなかろうか。

執筆
URABE(ウラベ)
早稲田卒。学生時代は雀荘のアルバイトに精を出しすぎて留年。生業はライターと社労士。ブラジリアン柔術茶帯、クレー射撃元日本代表。
URABEを覗く時、URABEもまた、こちらを覗いている。
Instagram
※『さくマガ』に掲載の記事内容・情報は執筆時点のものです。
- SHARE


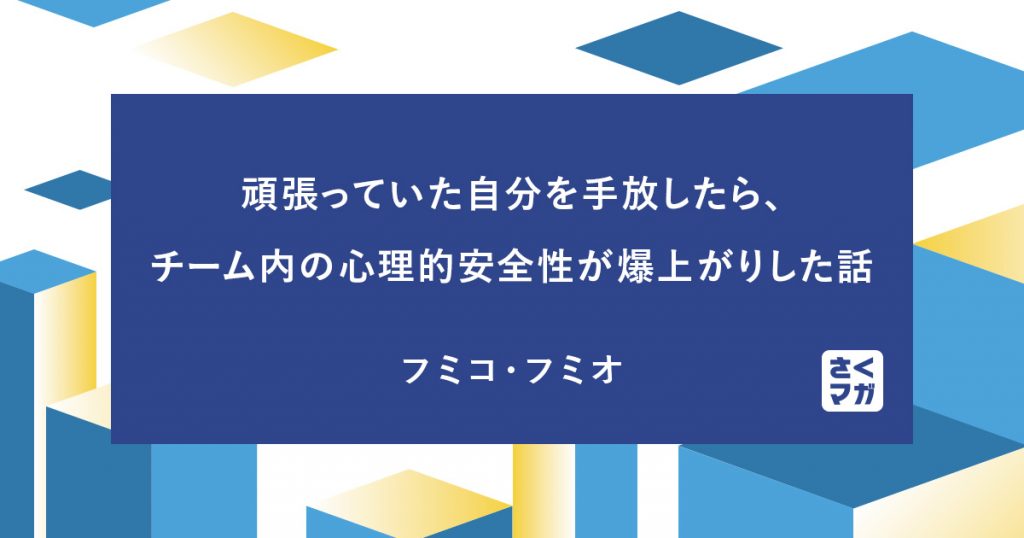

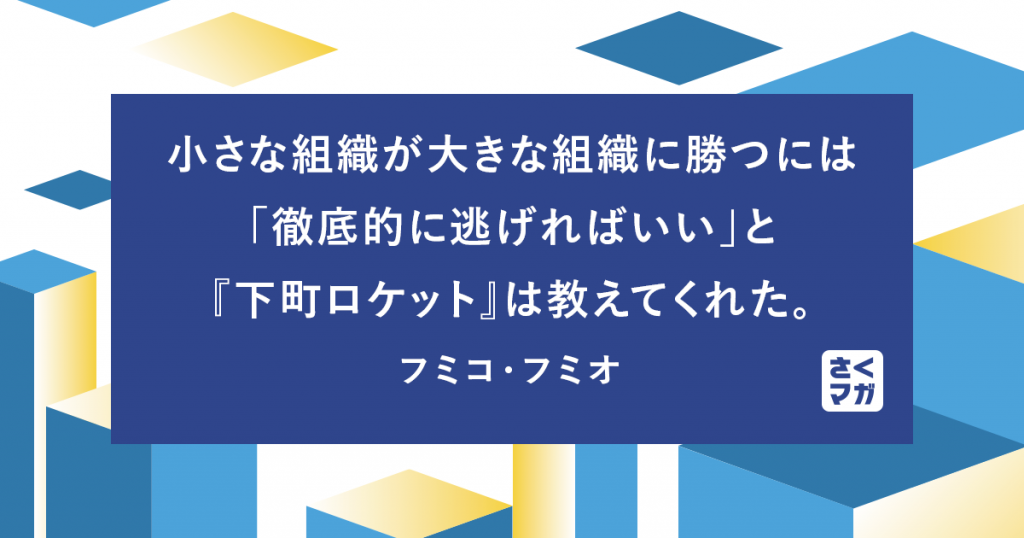
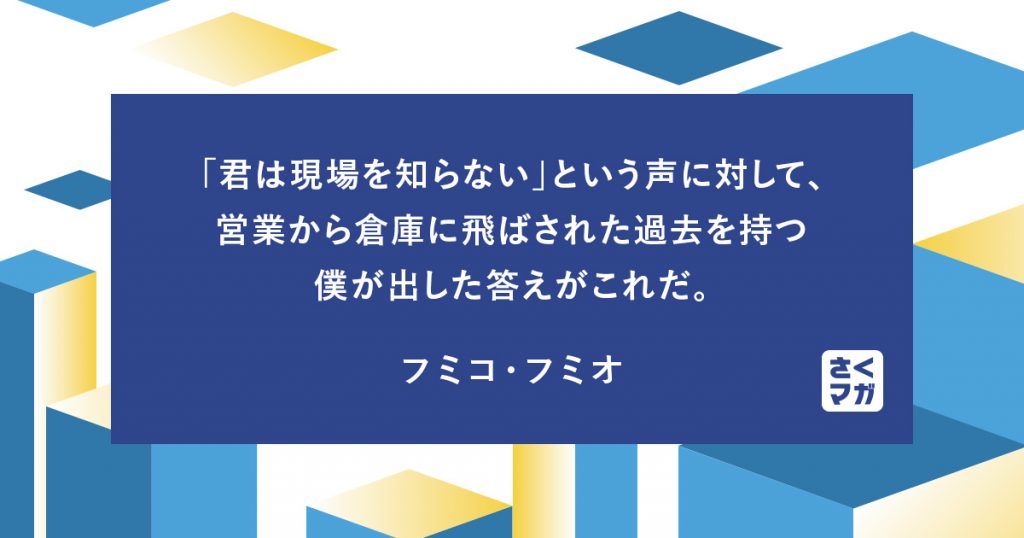
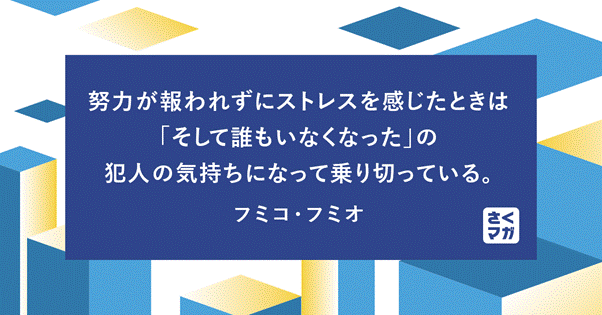
 特集
特集




