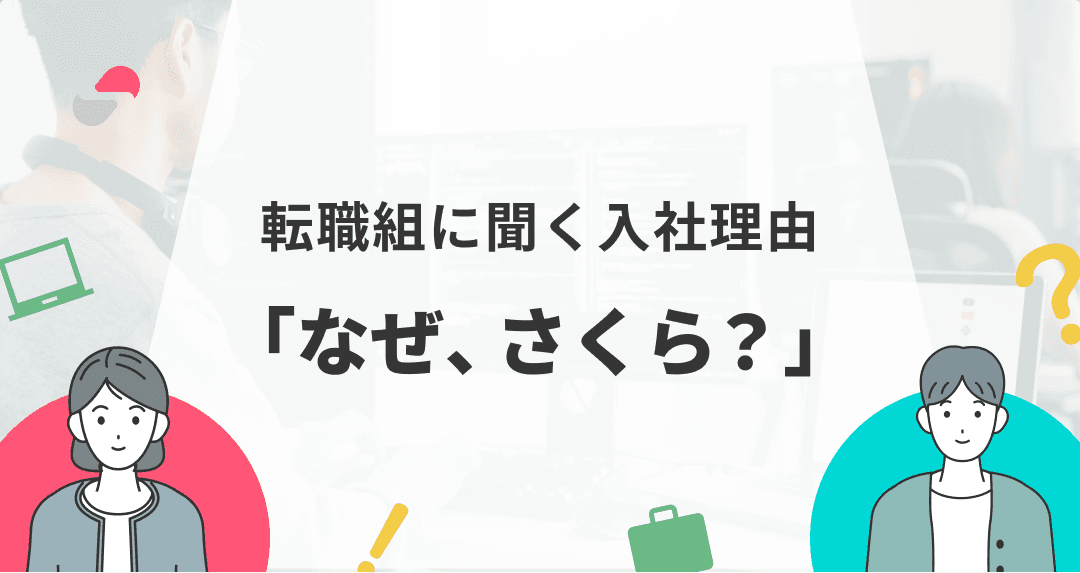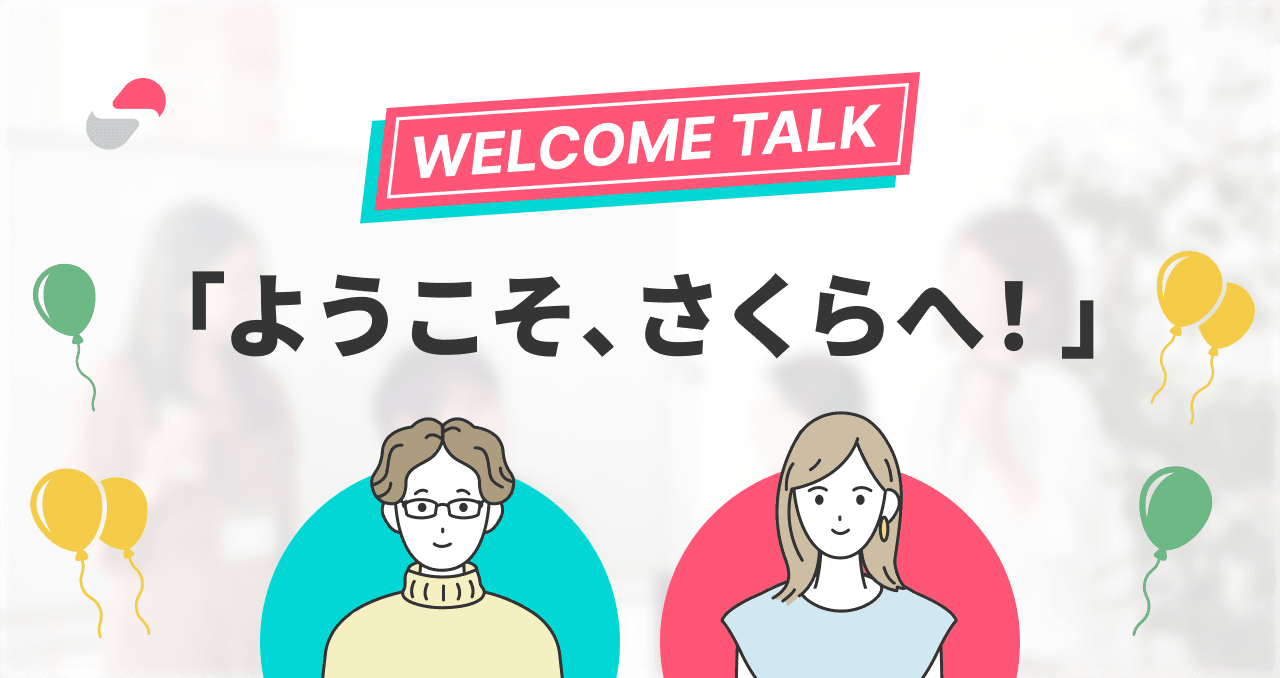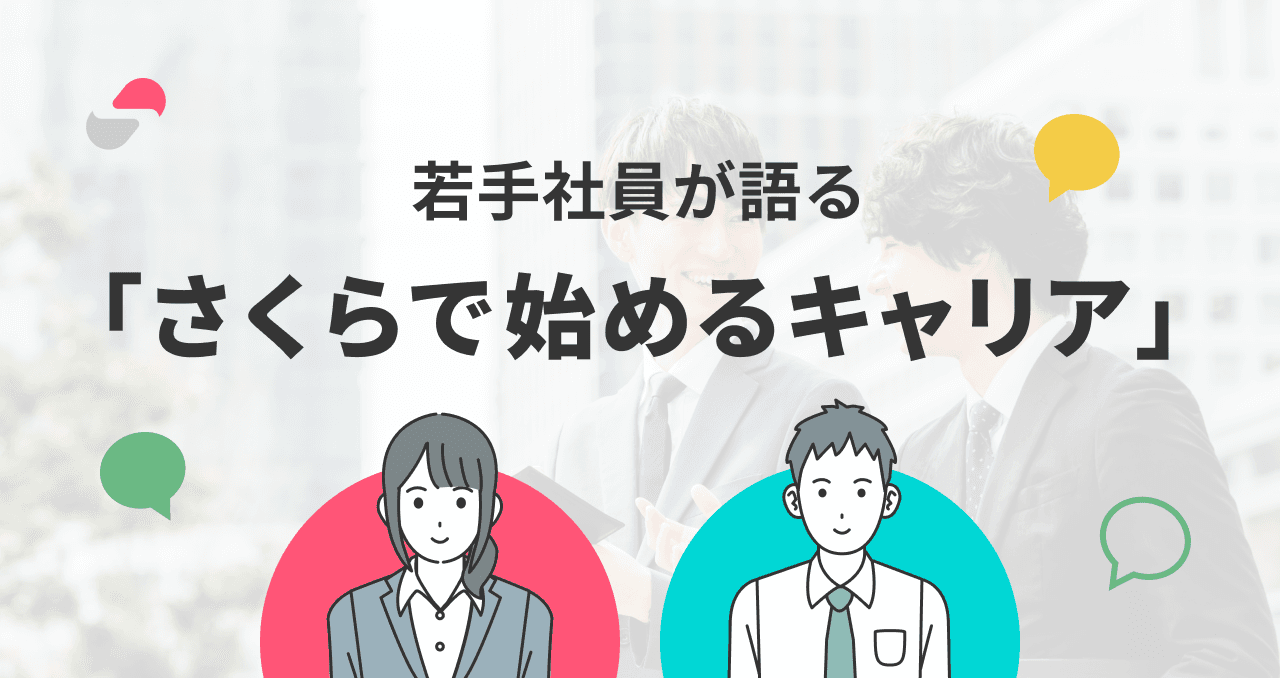ここ数年で市民権を得た言葉といえば、「コロナ」と「DX」だろう。
コロナはさておきDX(デジタルトランスフォーメーション)は、新たな価値の創出やこれからの社会のありかたを、デジタルによって実現する改革である。
文字にすると抽象的で難しい取り組みに聞こえるが、DXのための第一歩ともいえる「デジタル化」に着目すると分かりやすい。
まずは定義として、
「既存の紙のプロセスを自動化するなど、物質的な情報をデジタル形式に変換すること*1」
を、Digitization(デジタイゼーション)と呼んでいる。
さすがに最近では耳にしないが、かつては、デジタイゼーションこそがDXである、と息巻くアナログ世代の社長も多くみられた。
FAXを廃止してメールに切り替えたことで、
「わが社もついにDXが完了した!」
と、誇らしげに語る姿を思い出す。
そもそも、社会現象としてデジタル化が主流となったのは、いまから25年ほど前だろうか。インターネットの普及に伴い、携帯電話やパソコンなど、さまざまなデジタル商品が世に現れはじめた。
たとえば携帯電話には、スマホとガラケーの2種類が存在する。両方とも、通話機能のついたモバイル端末という点では同じだが、スマホはいわば小型パソコンなので、SNSやアプリの利用が可能。
対するガラケーは無線方式で通信をおこなうため、インターネット接続ができるとはいえ、時間がかかったりフルブラウザのために見にくかったりするので、ネットサーフィンには不向き。
しかしガラケー発売当初、「端末同士で通話やメッセージの送受信ができる」という画期的な機能により、ビジネスパーソンにとっては”持っているだけでステータス”だった。当時の携帯電話はビジネス向けに開発されたもので、学生たちが携帯するものではなかったのだ。
そして携帯電話が登場する以前、じつはもう1つの「モバイル端末」が存在していた。
ビジネスパーソンはもちろんのこと、学生も必携の歴史的IT機器――。そう、ポケットベルだ。
いまでこそポケベルを知らない世代が増えた。だが、デジタル時代到来前の1990年代、日本中の公衆電話で争奪戦をくり広げたデバイスといえば、ポケベル以外にないだろう。
そんな、いまは幻となったモバイル端末について、ちょっと笑える逸話とともに振り返ってみたい。
ポケベルをゲット
リモート授業がおこなわれる現代とは違い、私が中高生のころは、登校して友達と顔を合わせるのが当たり前だった。
さらに当時は、携帯電話もパソコンも普及していないため、家で電話をかける以外は対面でやり取りをするのが一般的。
そこへ突如、ポケットベルという四角いオモチャが登場した。
――ポケットベル、略してポケベル。
中学校時代、ポケベルの必要性は感じなかったが、おませな同級生が誰かからメッセージを受信する姿を見て、
「カッコいい!!」
と、思った記憶がある。
実際に彼女らが、どんな内容のやり取りをしていたのかというと、
「おはよう」
「なにしてる?」
「おやすみ」
この程度のことで、緊急性があるわけでも重要な用件でもない。ただ単に暇つぶしの延長で、メッセージを送り合っては楽しんでいたのだ。
そんな中、高校生になった私はとうとうポケベルを手にすることとなった。
ポケベルを持つということは、同時にテレホンカードを持つことでもある。
ポケベルはいわゆる「小型受信機」のため、メッセージを受け取ることしかできない。
その代わりに、電話機からメッセージを送るのだ。
文字の入力方法や通信の仕組みは割愛するが、当時、街中の公衆電話は女子高生によって占領されていた。
友人のヒトミなど、まさにお手本といえる女だった。綺麗なネイルを載せた細い指を、まるで蜘蛛の化け物のようにカタカタと動かしながら、瞬く間に文字を送信してしまう。
そんな彼女は、当時の女子高生の中でも断トツのスピードを誇っていた。
さらに、ヒトミのメッセージにはタイポ(タイプミス、誤字脱字)が見られない。あれだけの速度で数字を連打しているにもかかわらず、だ。
(恐るべし、女子高生のかがみ・・)
そんな畏怖の念を抱きながら、ヒトミから送られてきた超高速メッセージを見つめる。
(サーティーワンイコウ!アタラシイアイスデタ)

タイポこそが、人間に深みを与える
「ポケベルといえば女子高生」といわれるくらい、女子高に通う友人らのタイピング速度は驚異的であった。
街中の公衆電話には、さまざまな女子高の制服がずらりと並んでいる。どの生徒も左手で受話器を持ち、右手をフルに使って、もの凄い勢いでメッセージを入力していた。
黙々と打ち込むその姿は、戦いそのもの。
隣り合う公衆電話のブースに入り、テレホンカードを挿入したら試合開始。彼女たちの暗黙のルールで、「どれだけ速く、鮮やかに入力できるか」の勝負が始まるのだ。
その証拠に、ヒトミが公衆電話の前に立つと、周囲の女子高生らが一斉にヒトミの手元へと注目する。
それを当然のごとく承知しているヒトミは、顔色一つ変えず、猛スピードでカタカタとメッセージを打ち抜くのだ。
(カレシトケンカシタ!ミスドデマッテル)
こうしてミスドで落ち合った私は、延々とヒトミの彼氏の悪口を聞かされるのであった。
・・・だがこれは、無事にミスドで合流できたのだから結果オーライである。
中には「どこへ行ってしまったんだ?」と、ツッコミたくなるようなメッセージを送ってくる友人もいた。
「イマヘブン」
この一文が飛び込んできた時、私は呆然と立ち尽くした。
友人のサツキと待ち合わせをしていたが、約束の時間に遅れそうな彼女は、公衆電話から現在地を送ってきたのだ。「近くにいるから、もう少しで着くよ!」と伝えたいがために。
ところがどうだ、ヘブンとは。天国へ行ってしまったのか?!待ち合わせどころの話ではないじゃないか!
・・・なんていうのは冗談。彼女がどこにいるのかはわかっている。
これは「セブン」のタイポ。つまり、ここから近い距離にあるセブンイレブンの公衆電話から、メッセージを送信してきたのだ。
急いでいるという事情もあるだろうが、そうでなくてもサツキはタイポが多かった。
いまではあまり耳にしないが、当時、彼女が頻発していた言葉で「超ブルー」というものがある。憂鬱な気分、落ち込んでいる…このような場面で使うセリフである。
当人は決して明るい気持ちではないし、むしろ泣きたいくらいに落ち込んでいるはず。にもかかわらずサツキは、
「チョウベルー」
と、タイポをかましてくるのだ。
たかが一文字の誤り。ブがベになっただけのこと。されど、この間抜けな感じはいかがなものか。
まったくブルーな様子はうかがえないほど、ほのぼのとした雰囲気が漂う。
同様に、「わからない」と伝えたいサツキは、
「ワカンマイ」
と送ってくるので、「彼女に聞いても、決してわかることはないだろう」と、間接的にあきらめがつくのであった。
*
サツキのタイポは、ポケベルがスマホになった現代でも健在。ゆえに、これは性格的なものであることは間違いない。
とはいえあの当時、数字のボタンを睨みつけながら連打し、メッセージを作っていたわけで、一文字でも間違えればおかしな文章になること必至。
ましてや、入力後の文字の確認ができないとなれば、テレホンカード一回分を慎重に使おう、と考えるのが一般的だろう。
にもかかわらず、ヒトミが披露するタイピングのスピードと正確さは、
「ポケベル選手権があれば、優勝間違いなし!」
と称されるほどに神がかっていた。
これについては、サツキのタイポも相まって、心の底からウンウン頷けるのであった。
時代は変われど、思い出は永遠
古き良きポケベル時代を経て、ガラケーからスマホへと、モバイル端末の変遷は続く。
そしてこの先もまた、新たなモバイル端末が登場するだろう。
ポケベルは、
「電話機がなければメッセージを送れない」
という圧倒的な不便さに加えて、
「20文字程度しか作文できない」
という、低スペックの極み。
だが、そんな不便さをもってしても、ポケベルほど思い出に残る通信機器は、この先も現れないのではないか。
――ここは真冬の長野市。横殴りの雪が吹きつける、駅前の公衆電話。
手袋を外し、かじかむ手でボタンをカチカチと連打したあの時、私は誰に何を伝えたのだろうか。
送信者の手元には残らないメッセージ、それこそがポケベルの醍醐味だったのかもしれない。
*1:デジタル・トランスフォーメーションの定義 令和3年版情報通信白書/総務省

執筆
URABE(ウラベ)
早稲田卒。学生時代は雀荘のアルバイトに精を出しすぎて留年。生業はライターと社労士。ブラジリアン柔術茶帯、クレー射撃元日本代表。
URABEを覗く時、URABEもまた、こちらを覗いている。
Instagram
※『さくマガ』に掲載の記事内容・情報は執筆時点のものです。
- SHARE


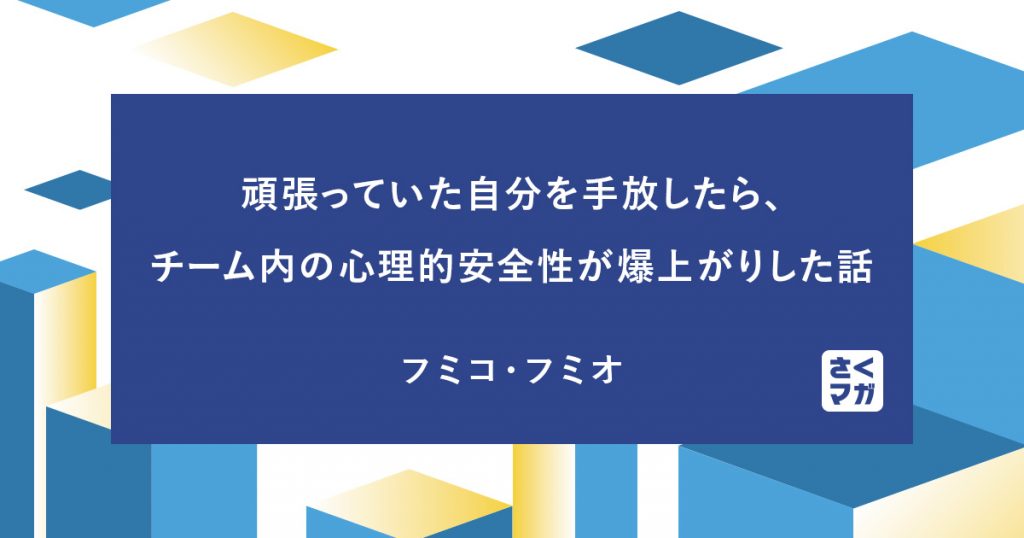

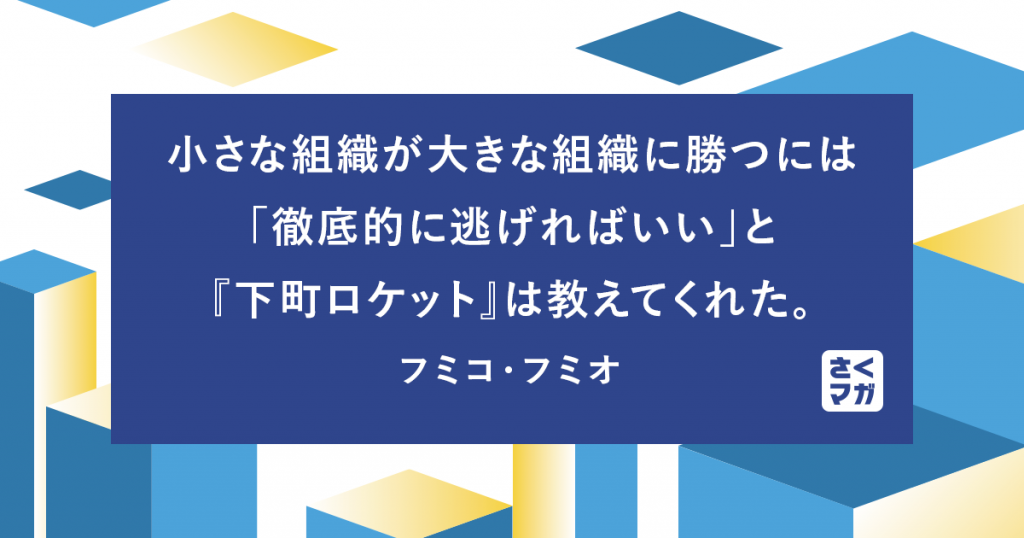
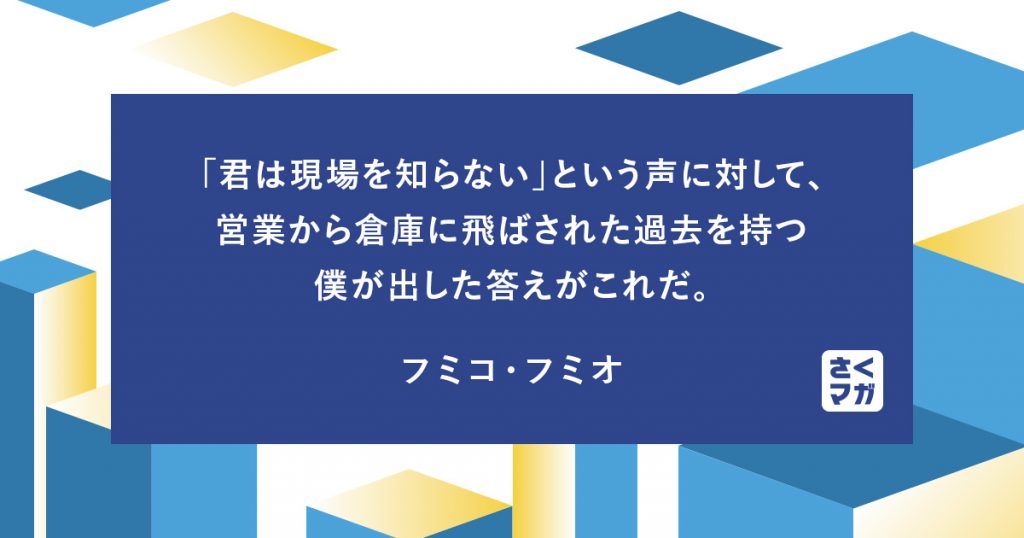
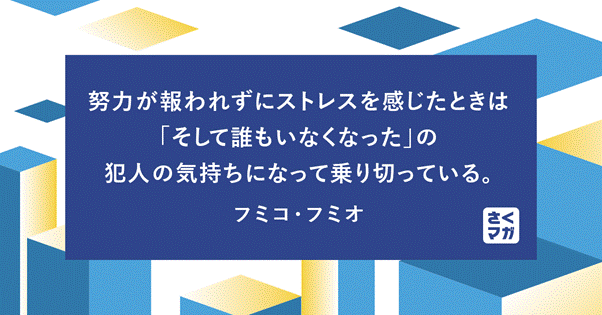
 特集
特集