
驕れる日本ブランド久しからず。メイドインジャパンなら中国市場で放っておいても売れた時代はとうに過ぎ去った。
いかに日本で知名度を誇るプロダクトであったとしても、今や現地企業が生み出す商品との激しい競争やPR合戦に晒されている。
そこで勝ち抜くためにはさまざまな取り組みが必要なわけだが、とりわけ肝となるのは中華ECでの展開やインフルエンサーを使った認知度アップと市場開拓。
ところが、すべての日系企業がこれらを上手に活用できているわけではない。
その要因は、現地子会社の不作為というよりは、本社側の中国に対する無理解。
はたまた「いいものを作っているのだから中国でも売れて当然」という間違った自信にある。
チャイナプラスワンや米中デカップリングにコロナ禍など、ことあるごとに「もう中国じゃない」と言われながらも、なんだかんだ巨大過ぎて手放せない中国市場。
その中で日本ブランドが生き残るため、日系企業はいかなる戦いを繰り広げるべきか?
変化の早い中華ECの世界で、どのようにしてSNSやITを絡めた商品認知を図るべきなのか?
今回は長年中国で事業を営み、日系企業ネットワークの表も裏も知り尽くす筆者の友人に話を聞くことにした。
なお、突っ込んだ話を語ってもらうため、以下匿名でのインタビューであることをあらかじめご了承いただきたい。
郷に入れば郷に従うよりほかになし

「日本製品はすでに中国市場で負けている。まずその認識が必要です」
そう語る友人はかつて「一人駐在」として裸一貫で中華の地に立ち、10年の時を経て社内の海外事業部門でトップの売上を叩き出す支社を育て上げた男である。
「日本ブランドの強みが完全になくなったわけではなく、たとえば口に入れるものはそれなりに比較優位があります。
安全性の面ではやはり日本製に一日の長があるということでしょうが、ほかのジャンルではメイドインジャパンの神通力が大なり小なり弱まっているのは確かです。
そもそも日本ってモノ作りを大事にしますよね。
でも、それが行き過ぎて商品開発が『聖域』になっちゃうと、中国市場ではダメなんです。
いくら技術があっていいものを作れても、それより格段に安くて品質もなかなかの国産品があれば、いまの中国の消費者はクレバーですから、そちらに流れてしまいます。
はっきり言ってしまうと、商品開発を日本でやって、現地のニーズを無視した製品を生み出し、それで俺たちはいいものを作っていると思っている会社は、ITの活用どうこう以前に一番ヤバいです」
中国支社からしてみれば、ピント外れな製品を本社に押し付けられたところで「それ、こっちでは売れませんから」という話に尽きる。
だが、日本企業においては一般的に本社の方が力関係で圧倒的に上。
子会社の諫言はどうしてもスルーされがちだ。
「じつは、中国のECというのはその気になればいくらでもデータが取れる世界でした。
というのも、今年の4月くらいまではアリババと提携していた会社のシステムを通じ、ECプラットフォームで扱われている商品の販売個数やアクセス数などあらゆるデータを見ることができたのです。
つまり何が売れているか、ニーズがどこにあるかは一目瞭然だったのですが、しっかりしたデータを踏まえて話しても日本側には通じないことが多い。
それでも本社の言う通りに新商品を投入して、やっぱり売れないとなると今度は犯人探しが始まり、『お前たちの売り方が悪い』と現地のせいにされがちです。
日本企業というのは失敗があったときに誰かのせいにしないと気がすまないし、自分で責任をかぶりたくないんですね」
現場のことは、現場にいる者が一番よくわかっている。
これほど単純明快な道理もないが、それが通らないのが日本本社と中国支社の関係というもの。
中国側がいまの市場に合った商品展開の提案をしても、日本側は往々にしてかつての成功体験を追いがちだ。
「これまでの日本ブランドの売り方というのは、まずインバウンドをきっかけに認知度が上がって、越境ECで火がついて、それから旗艦店を出して『京東』(中国の大手ECプラットフォーム)で売って……という基本パターンがありました。
でも、いまはコロナでインバウンドなんてないですし、PRならインフルエンサーやKOL(キーオピニオンリーダー)を使い、SNS戦略にカネをかけるといったふうに展開が変わってきています。そして、何よりも重要なのはライブコマースの活用です。
たとえば弊社の場合、微博(中国版ツイッターのようなもの)でフォロワー10万人程度のインフルエンサーなら予算は2000元(約4万円)、フォロワー200万〜300万人なら1万元(20万円)くらい。
最高ランクのKOLなら20万元〜30万元(約400万〜600万円)というのが大体の相場感です。
それも時期によって値段は変わり、大型のネットセール前だと忙しいから高くなったりと変動があります。
いずれにせよウチはKOLと直でやりとりをして交渉をしていて、予算もつけられているのですが、他社では『この人を起用します』と言って中国トップクラスのKOLの名前を本社に伝えたら、『誰それ?』なんて返事が返ってきたこともあるそうです」
終わりなき本社と中国支社との相克

筆者はくしくもこれと似たような話をほかの在中邦人から聞いたことがあり、その方いわく「日本でいうヒカキンみたいなものです」と本社の役員を説得して、わかったようなわからないような反応をされたとのことだった。
「なぜ宣伝広告でTVなどをすっ飛ばして最初に『ヒカキン』なのか」と、日本側からすれば理解不能なのかもしれず、それって日本のやり方と違うという違和感もあるのだろう。
前出の友人によれば、そのような本社と現地子会社との意識のズレは、ビジネスのあらゆる面で日常茶飯事に見られることだという。
「一例を挙げると、日本と中国ではホームページのデザインや商品パッケージに対する消費者の好みも違います。
ヘルスケア商品の場合、日本では洗練されたものが好まれますが、中国では多少ダサくてもとにかく効きそうな雰囲気を出したほうが正解だったりするんですね。
商習慣の違いでも同じことが言えて、こちらではコンビニなどで商品展開をする際に『棚代』がかかります。
置いてもらうのに敷金・礼金のようにお金をまず払うのですが、日本側からしたらなぜそんな予算が必要なんだという話になる。
実際には、日本でもコンビニや薬局でちょっとしたスペースを取るのだって営業力と実績、ブランド力が必要で、中国の『棚代』以上のコストがかかっているはずなのですが、そこは不思議と問われないんですね」
こういった認識のズレを埋めるために必要なのが、本社と現地の緊密なコミュニケーション。
ところが、現在は中国のコロナ対策により人の移動に制限があり、それすらもままならないという。
「オンライン会議は有用とはいえやはり限界もあって、Zoom会議が終わって回線を切ると、だいたい『本社の人はわかってないよな』みたいな話になります。
でもきっと、向こうも同じようなことを言っているんだろうなと思うんですよね。
逆に、そういうギャップがない企業というのは大体、本社が子会社の意見をしっかり聞き、裁量を与えているところです。
中国ビジネスで成功している会社ほど本社からの介入が少ないか、もしくは中国支社がそれをはねのけるだけのビジョンと発言力を持っているケースが多いように思います」
本社サイドとしては満足のいく売上を出していない海外子会社に対し、つい疑念を抱きがちなもの。
だからと言って、「現地に任せてはいられない」とばかりにムヤミに口を出すと、待っているのは悲劇であったりする。
「もちろん、何でもかんでも現場の声が正しいわけではないですし、中国のKOLを販促に使うにしたって、相手の言うことを全部丸呑みしていたらダメです。
たとえば、ライブコマースでKOLに商品販売を依頼するとき、向こうから『これだけ売るから商品を用意しておいてくれ』と自信満々に言われることがあります。
でも、KOLのフォロワー層によっては商品がマッチしないことも十分あり、言われた通りに生産したけれど半分しかさばけず赤字だった、なんていうことは結構起きるんですよ。
こちらとしてはそういうことを避けるためにフォロワーの分析からKOLの実力までつねにリサーチを欠かしませんし、可能な限り最適解を出しているつもりです。
それに対して本社側が現地をわかっていないコンサルを連れてきて、まったく見当外れの代案を出してきたりすると、正直言って『ふざけんな』とは思います。
そういうのが一番失敗の元なので、『耳を傾けるならまだ現地の人の意見』というのが私の考えです」
まとめると、日本と中国ではマーケットの性質からDXの進度に至るまで、明らかに差異がある。
それでもなお日本式のやり方を押し通すことは、好意的に見れば日系企業のプライドとも言えるが、筆者からすれば驕りに見える。
ECの世界に関して言えば、中国は日本の先を行っている。
むしろ中国のマーケットで得られた知見や学び、失敗を日本側にフィードバックすべきなのではとすら思うのである。
中国とはなんでもかんでも手放しに持ち上げていい国ではなく、底なしにダークな側面を持つことを承知の上で、自分はあえて言いたい。
日系企業よ、中国のEC世界を学びの場とすべし!

執筆
御堂筋あかり
スポーツ新聞記者、出版社勤務を経て現在は中国にて編集・ライターおよび翻訳業を営む。趣味は中国の戦跡巡り。
※『さくマガ』に掲載の記事内容・情報は執筆時点のものです。
- SHARE


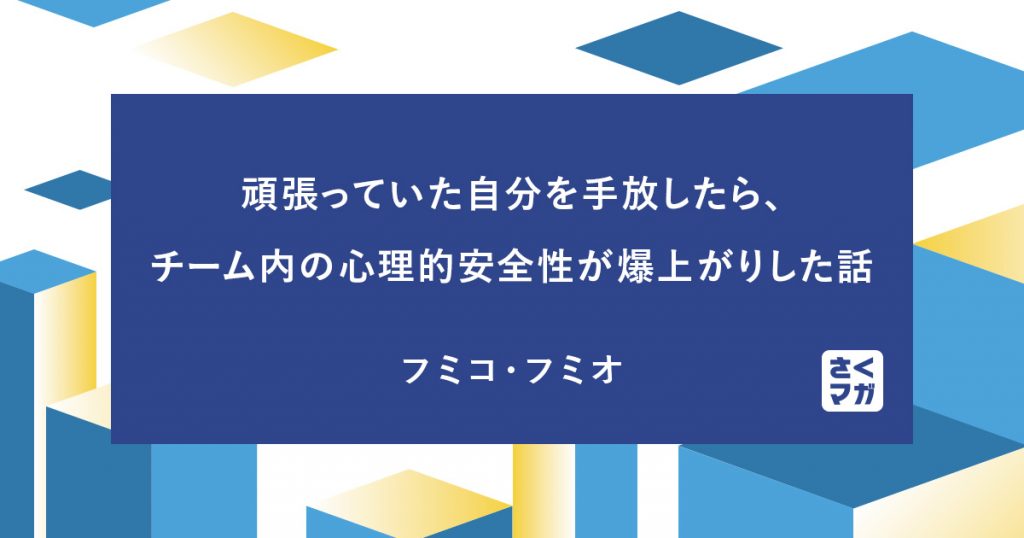

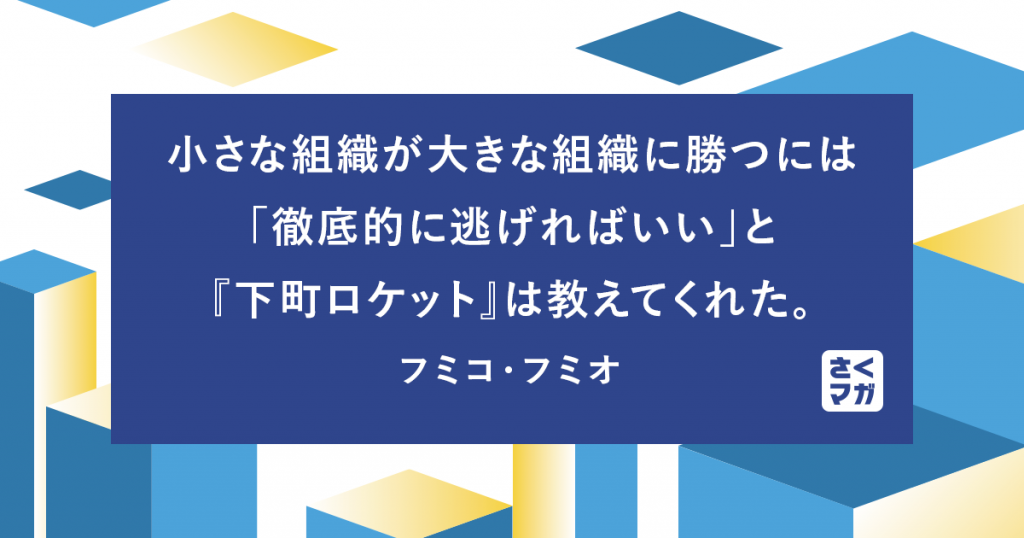
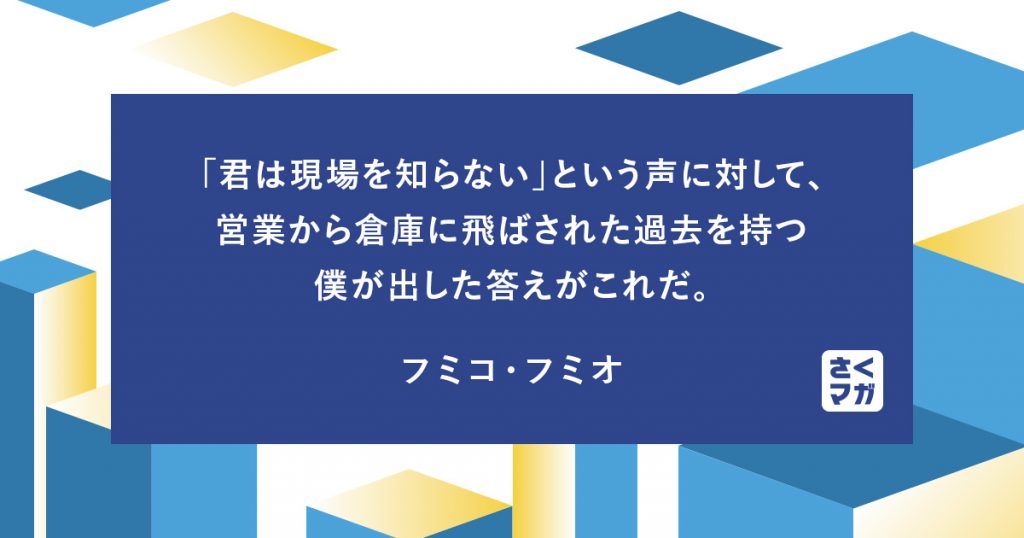
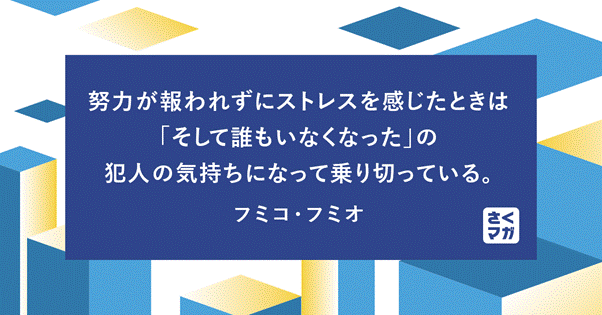
 特集
特集




