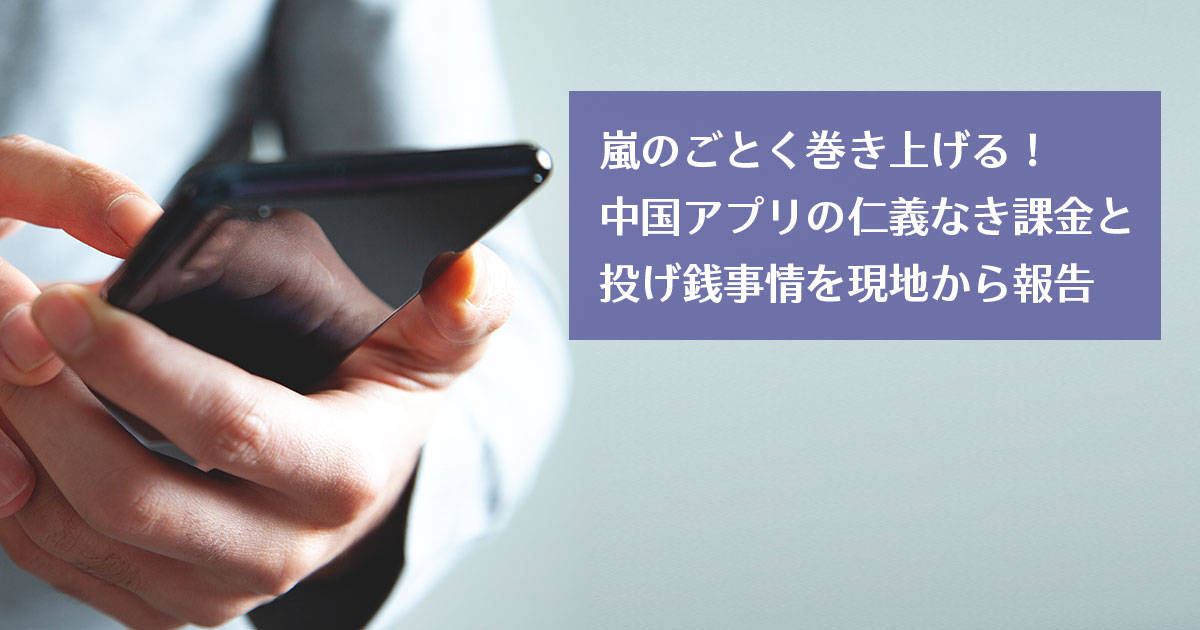
かつて日本のスマホゲーム業界で問題となったガチャシステムによる行き過ぎた課金。全く興味のない者からすればムダ使いとしか思えなくても、そこにはハマると抜け出せない面白みがある。
現在、日本では確率表示などさまざまな自主規制がおこなわれ、かつてほど射幸心を煽るものではなくなった。ところが、海の向こうの中国では今も課金と投げ銭、それに伴うトラブルが起きまくり。
これはいかがなものかと動き出した当局の指導を受けてもなお、一定の勢いを見せている。その要因は中国人の気質や国民性をしっかり押さえたシステムと、容赦なく金を巻き上げにくる運営側の姿勢にある。
今回は金と欲望が交差する中国の課金&投げ銭事情について、ほぼ毎日中華アプリでライブ配信をチェックしている筆者自身の体験と、中国のゲーム業界に詳しい方の話をうかがいつつ、分析を加えてみたい。
課金せずにはいられない! 中国の人々のメンタリティ
まず、最初に言っておこう。
自分は4年ほど前、中国の果てしなくどうでもいいスマホゲームで、日本円にして50万円ほど溶かしている。いま冷静に考えれば、1万円札で笹舟を大量に作ってその辺の側溝に流したような、無意味な行為。だからといって後悔があるかといえば、ちょっと違う。
当時どハマりした時のえもいわれぬ興奮はまだ記憶に残っており、タイムマシンで過去に帰って自分自身を諌めたとしても、きっと聞かない。それを分かっているので、後悔とかそういうのはなく、止められなかった浪費であったと認識している。こんなことを思わず言いたくなるほどに、中国系のスマホゲームは課金へのモチベーションを煽るのが上手い。
かつてある人が「騙されるのもある限度を超えると、快感に変わる」という明言を吐いたことがある。課金や投げ銭は当然ながら納得の上での金銭のやり取りであり、騙しでは決してない。しかし、あまりにも手際がよく、考え尽くされた課金や投げ銭勧誘の手口というものは、キッチリとカタにはめられていながらも、何かすがすがしいものすら感じてしまうのだ。
中国は今や世界最大のゲーム市場

では、なぜ中国ではこのような課金システムが生まれたのか。日中のゲーム事業に従事した経験を持つIT専門家の飯島剛氏に話を聞いた。
「まず、中国というのは今や世界最大のゲーム市場です。昔は中国人がゲームに金を払うわけがないと思われていたのが、中国、アメリカ、日本の順で3強となっているんですね。コンシューマーゲームやPCゲームもそれなりに人気ですが、マネタイズの中心はアプリの課金。そこになぜお金が流れ込むかというと、スマホゲームには時間や手間暇をショートカットするために課金させる作りになっている側面があるんです。
もちろん毎日少しずつだったらお金を払わなくても遊べますが、何しろこの国の金持ちはケタ違いの額を持っていますから。スマホゲームをリリースしたら、いきなり一晩で2000万円課金する人が実際に現れる世界です。そうすれば当然、他の人より有利になるのは当たり前ですが、日本人の感覚だと『そんな遊び方して面白いか?』と思いますよね。
でも、こちらの人はとにかく他者の上に立ちたい、勝ちたいという気持ちが強い。アプリの運営側もそれを分かっていて、ランキングなどで煽りに煽るんです。いわば、課金システムを構築するに当たり、中国人の国民性をよく理解して作っているということです」
中国のゲーム企業はグローバル展開を前提に製品を作っている
付け足すならば、中国の人々は基本、気が短い。毎日コツコツと遊ぶようなタイプもいるにはいるが、大体は熱くなったら我を忘れがち。そういった気質を理解した上で、計算され尽くした内容となっているのだとしたら、課金の沼にどっぷり浸かる人が出てくるのもうなずける。
「中国は人口が多く、娯楽も多くないためエンターテイメントの需要があり、スマホゲームは何だかんだ言っても人気です。しかし近年、中国のゲーム企業は国内で規制が強まるに従い*1、海外市場をより指向するようになっています。
私自身、上海でゲーム開発に携わっていた際、中国で作ったゲームを日本側に納品したり、また中国市場向けのものでもイラストは日本のクリエイターに発注したりとさまざまな業務をハンドリングしていました。
そこで感じたのは、中国のゲーム企業は世界を見ていて、グローバル展開を前提に製品を作っているということ。かつて日本はゲーム大国でしたが、中国製のゲームが存在感をより強めていく展開は、十分にありうることだと思っています」(飯島氏)
中国式の課金ゲームが日本を席巻する日は近い? いや、すでにその事態は進行しているのかも……?
金にシビアな中国人が投げ銭にハマる謎
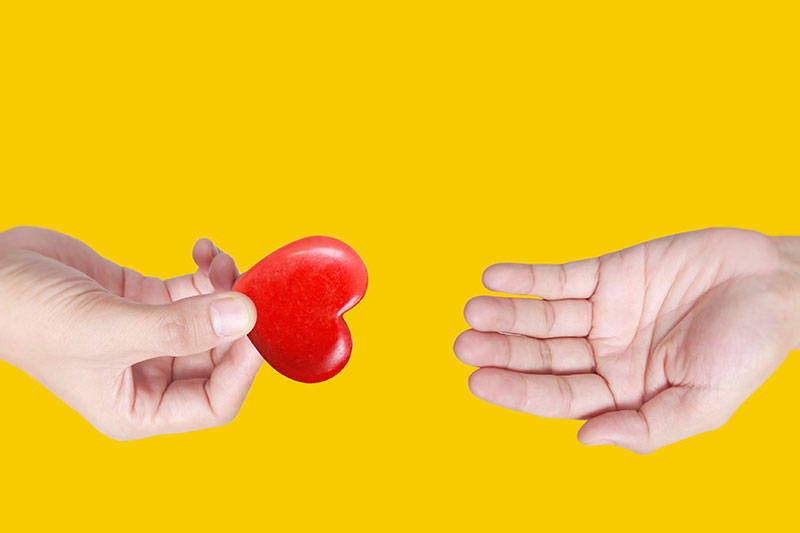
日本でもおなじみ「TikTok」(中国では「抖音」という)、地方在住の利用者が多めで洗練されていないところがむしろ魅力の「快手」。
他にもライブ配信のプラットフォームは多々あるが、ややこしすぎるので上記2つに絞って話すと、それらのアプリを開いて見られるのは、しゃべり、踊り、時には配信中にメシを食ったりしつつ、映像を垂れ流すあまたの配信者たち。
見ている側は気に入った配信者に投げ銭できる仕組みとなっており、課金してコインを買って、そのコインで「礼物」(贈り物)を購入。高いものほどスマホゲームのガチャのごとくビジュアル効果が派手であり、贈った分はプラットフォーマーに一部抜かれるが、配信者の稼ぎとなる……極めて単純化しているものの大体こういった仕組みである。
例えばここに、とある地方都市の工場で働いている娘さんがいるとしよう。安月給で真面目に働いていたところ、ある日たまたまライブ配信で自分と同じ年頃の子がミニTに短パンで踊っているのを発見。
そこでコアなフォロワーが99元(およそ2000円)の「礼物」プレゼント10連打、踊っている子は大喜びなどという場面を目撃してしまったとしたら?翌日の仕事をばっくれてライブ配信者を始めても何ら不思議ではないし、自分だって同じ境遇ならばおそらくスマホの前で踊っている。
もちろんいきなりデビューしたところで、全員が投げ銭で食っていけるはずもなく、そこにはやはり創意工夫と努力が必要。ただしルックスやトークスキルなど持って生まれた要素がかなり大きく、もっと言えば運もある。自分でビジネスをやっている知人・友人がSNSマーケティングのためにTikTokを研究する中、筆者は泥臭くて垢抜けず、わけの分からない配信者多めの「快手」をひたすらチェックしてきた。
ランキングから見るカオスな世界

このアプリのライブ配信にはランキングがあり、各省(自治区・直轄市)、はたまた都市ごとのリアルタイム順位に加え、中国全土ベスト100も表示される。素人オーディション風のものからトークチャンネル、街角レポートに絶叫カラオケ、さらにはビジュアル勝負の配信者……。
ジャンルがあまりに豊富すぎていちいち解説できないが、ランキング順に見ていくと上の前歯が数本しかない司会者や亀仙人みたいなおっさん、金を託したらその場でいなくなりそうな怪しい投資指南者などが、ぶっちぎりの美男美女より人民の注目を集めていることもザラにあるなど、端的に言ってカオスな世界だ。
フォロワーから投げ銭を搾り取るための「手口」は、人それぞれ。ただ、共通する法則としては、やはり見ている者を上手く誘導し、ファンとしての地位を競わせる。面白いものを見せたからその対価をよこせと言うよりは、「支える者」としての自尊心をくすぐる方が中国人の心に刺さりやすいのである。
日本ではアイドルの世界でCDやチェキ購入といったシステムがあるが、中国人はそんなまどろっこしいことはせず、「推す」ならキッチリ現金を送りつける。この場合、現ナマを投じているファンは当然、スマホの向こうにいる配信者に好意を持っている。だが、それと同時に「こんなに推してる俺、どうよ」という自己愛にも浸っていると見ていい。
投げ銭で与えられる「称号」
ちなみに投げ銭を続けていると、レベルアップもあれば称号までも与えられる。ライブ配信中、とんでもなくハイレベルで「至尊保護」なんていう称号の持ち主が入ってくると注目が集まるわけで、それも自意識をくすぐる。
傍から見れば「カモ登場」としか思えないのだが、ハマっている本人にそういう自覚はおそらく希薄。極論すれば、自分が気持ちよくなるためにムダ金……ではなく投げ銭を払っていると言っても過言ではないと筆者は思う。
感情的になりやすく、勝ちたい欲がやたらと強くて、自分のことが何より大好き。そんな中国人の性質を熟知し、気持ちよく金を払わせられる者は、ライブ配信で成功しやすいということだろう。
なお、さすがにこの状況は異常と当局も判断したのか、最近は規制がかけられるようになった。*2
「日本では業界団体などがおおごとになる前に自主規制をするのが普通ですが、中国は上から言われて初めて動きます。稼げる時に稼げ、行ける所まで行ってしまえというメンタリティーがあり、それも中国の課金や投げ銭の爆発的なブームにつながったと思います」(飯島氏)
いわば、金を巻き上げる側が焼き畑農業的というか、持続可能な形で稼ごうという意識が薄いのが中国なのである。
IT関連に限らず、中国企業は世界を視野に入れて事業をおこなっている今、そのビジネスモデルが日本に波及してくる可能性はますます強まっている。
ぜひ日本の皆さまにおかれては、中国式の強欲商売を冷静に見つめ、警戒しつつも参考になる部分はキッチリ観察するというクレバーな姿勢を持っていただきたいものである。
*1:東洋経済オンライン「中国政府が未成年のゲーム『週3時間』制限の衝撃」
*2:電ファミニコゲーマー「中国国内の配信プラットフォームで未成年の「投げ銭」利用が禁止に。送金と受け取りのいずれも保護者の許可なく行うことを政府が制限、夜10時以降の視聴も不可となる」

執筆
御堂筋あかり
スポーツ新聞記者、出版社勤務を経て現在は中国にて編集・ライターおよび翻訳業を営む。趣味は中国の戦跡巡り。
※『さくマガ』に掲載の記事内容・情報は執筆時点のものです。
- SHARE


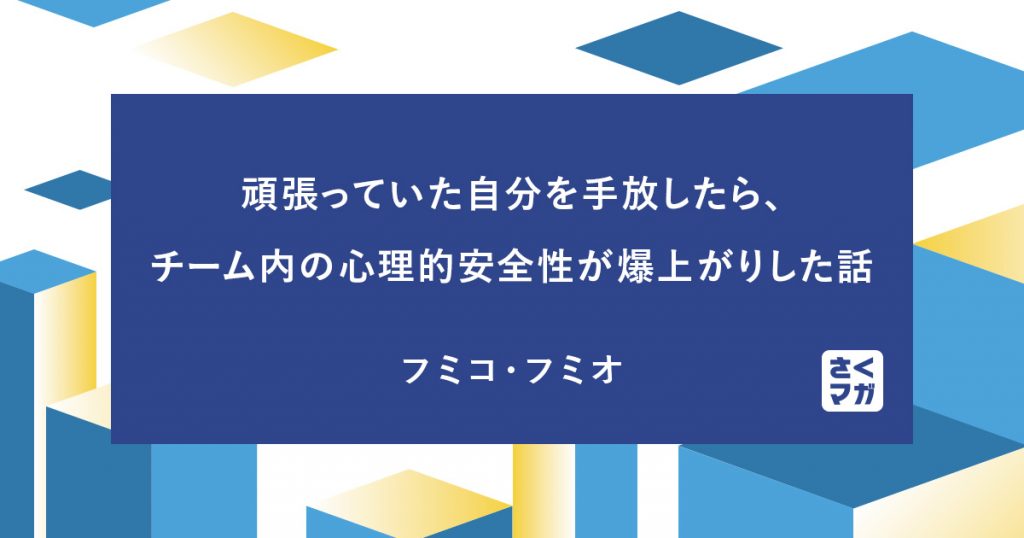

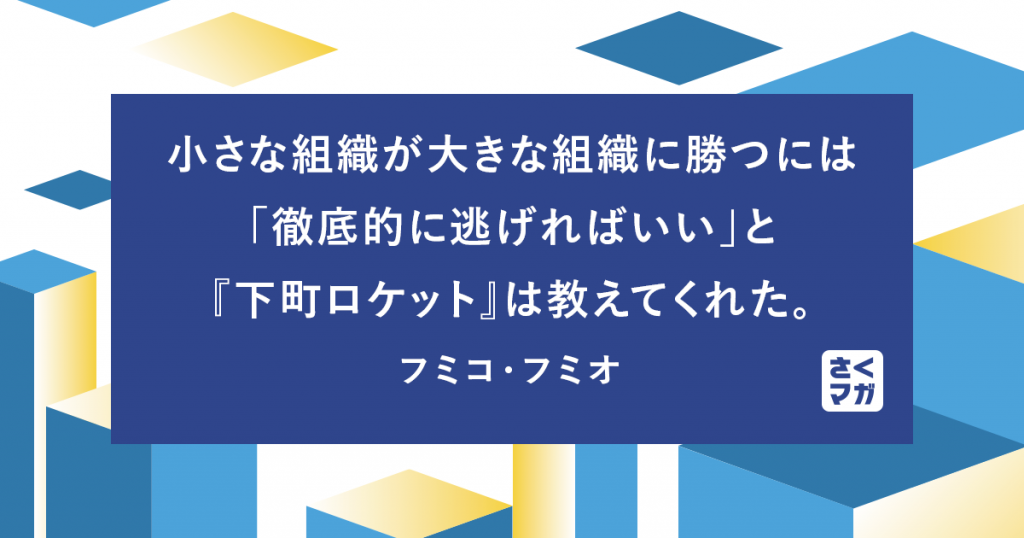
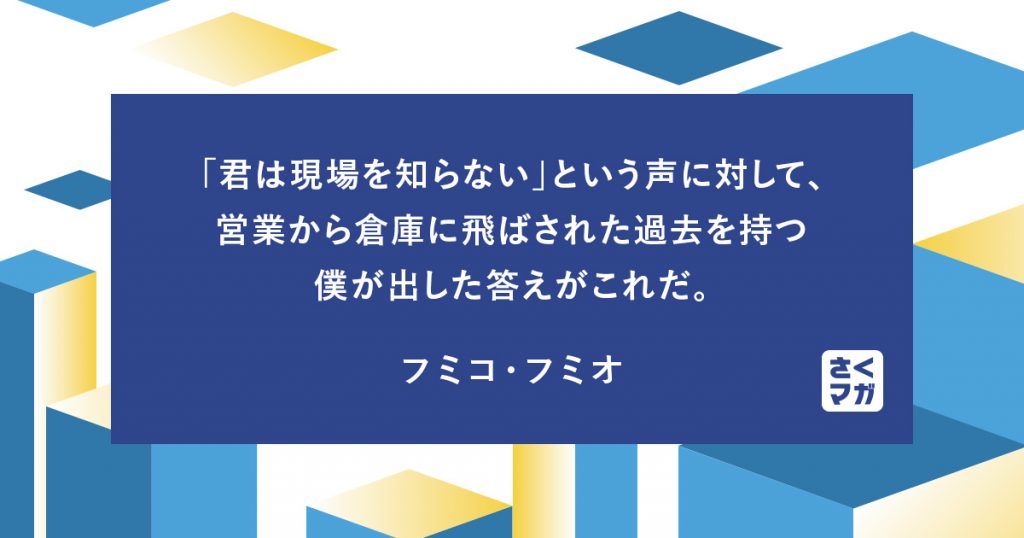
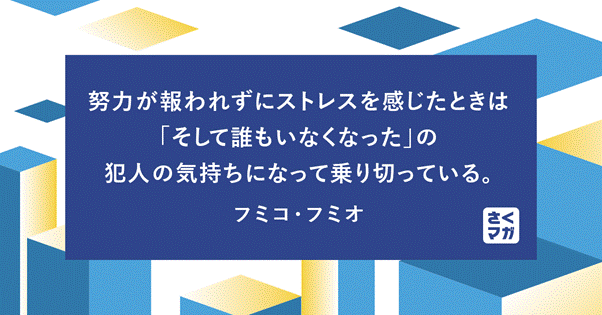
 特集
特集




