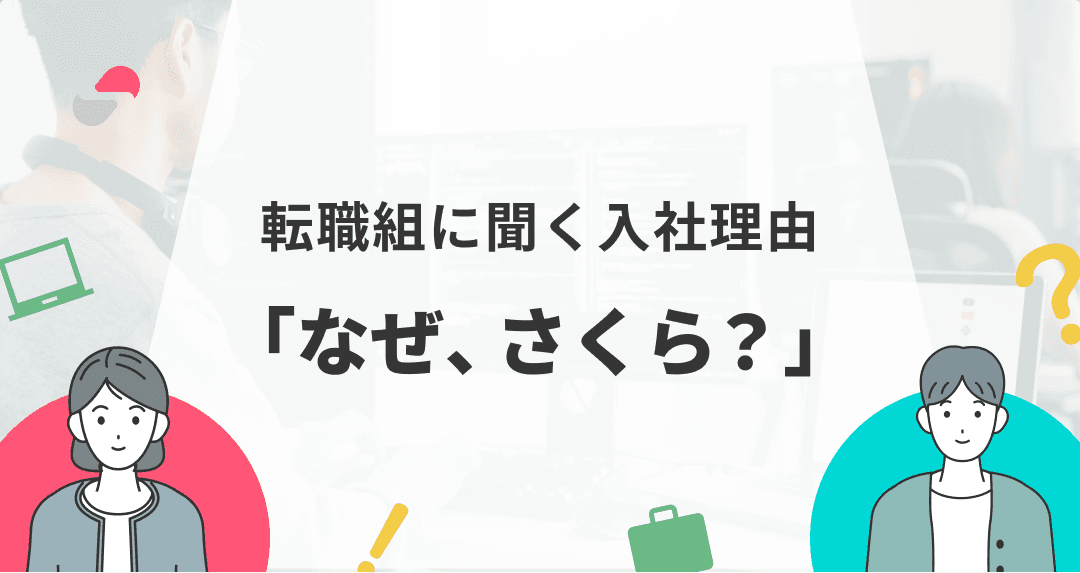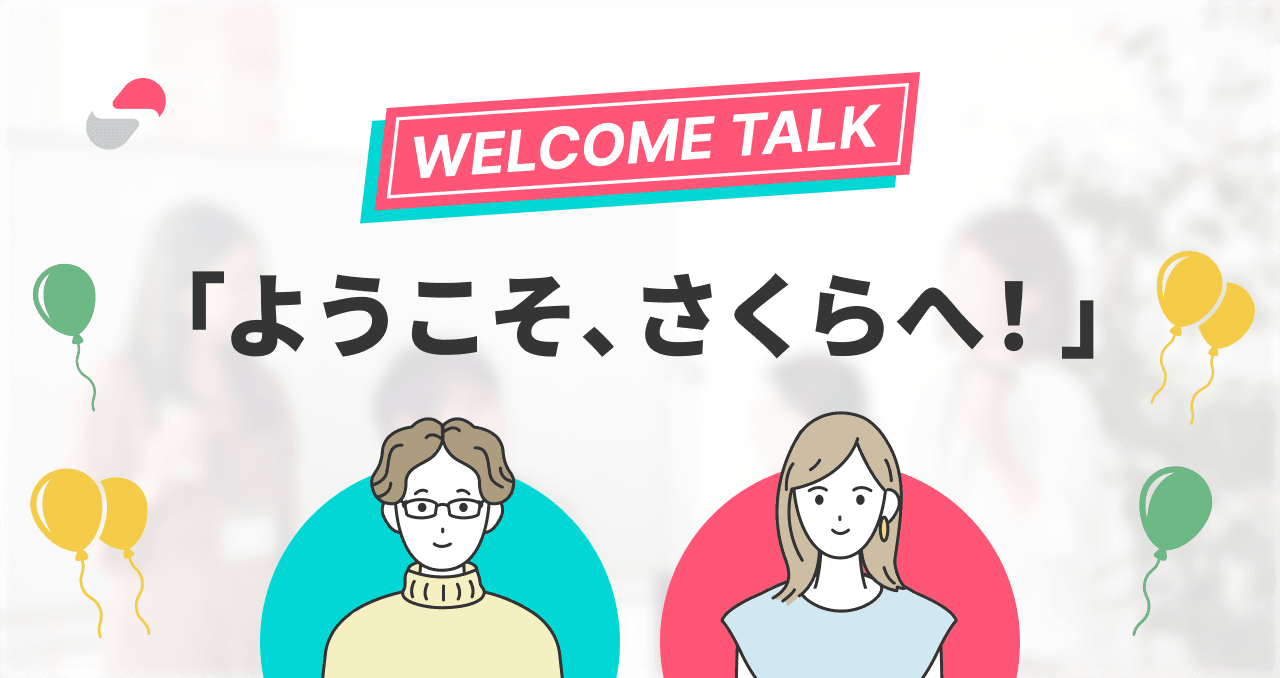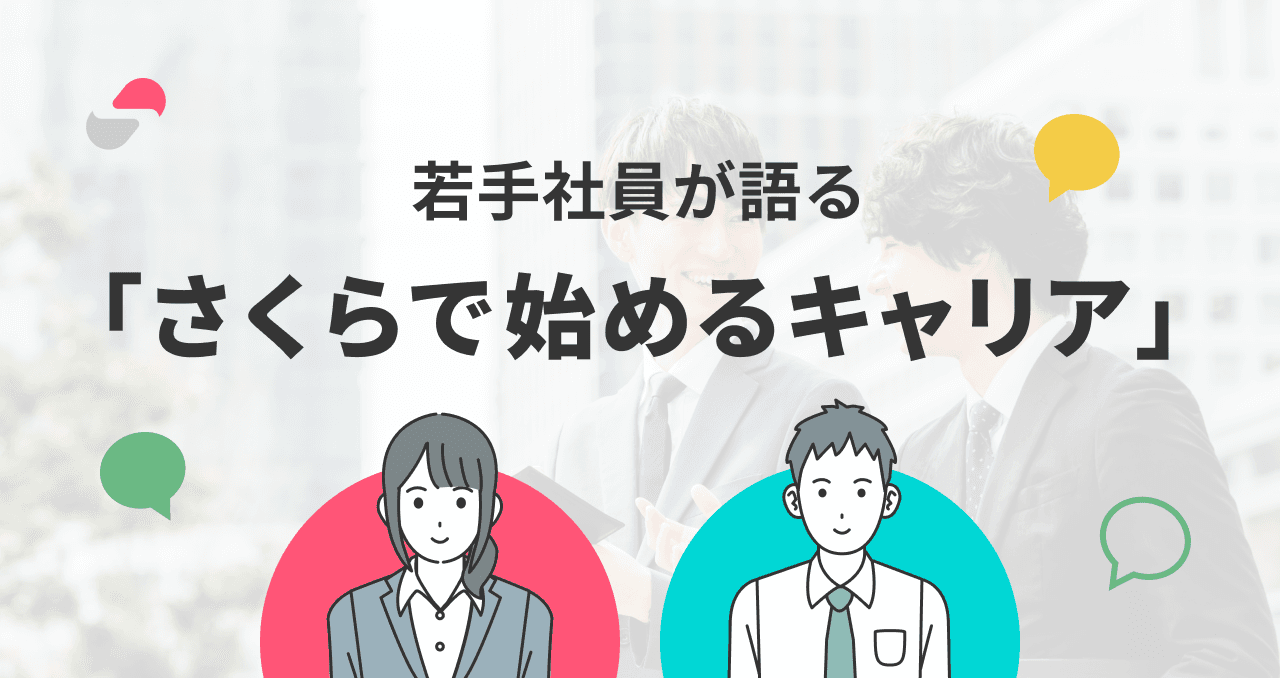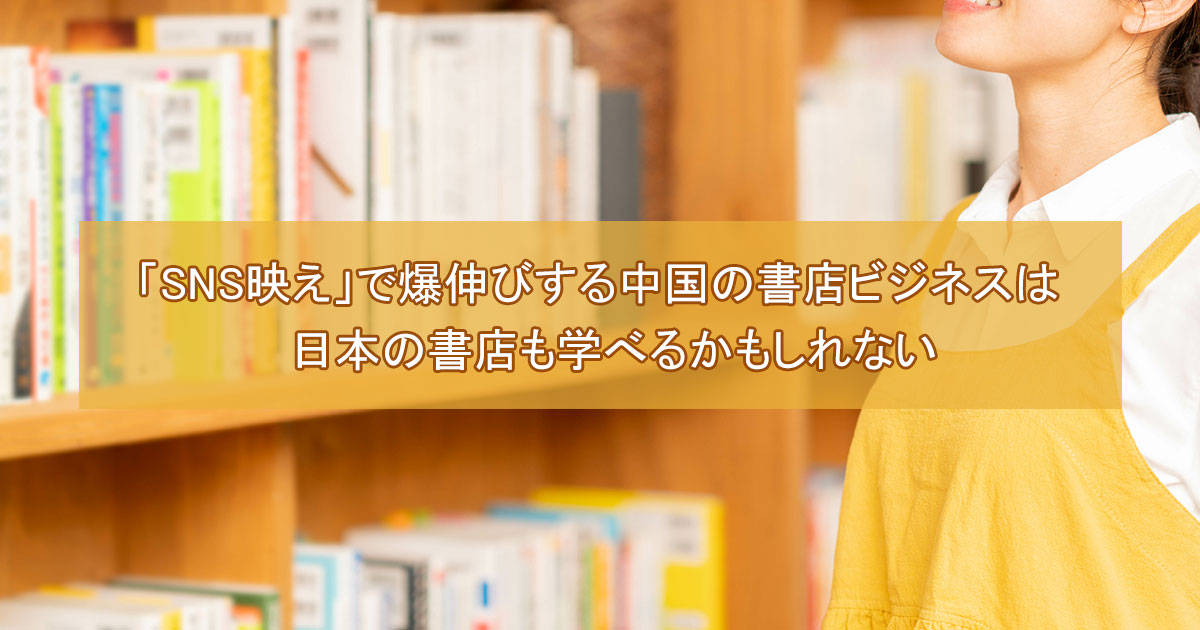
コンテンツ産業が大きくさま変わりする中、書店ビジネスは時代の曲がり角を迎えている。電子書籍の普及により、今や人々は本棚を持ち歩いているかのごとく、どこにいようが自分の蔵書を楽しめる環境が整いつつある。
そして将来、サブスクのさらなる発展は本を所有するという概念すら過去のものとし、誰もが図書館に常時アクセスできるに等しい全く新たな読書体験をもたらす――。
紙への思い入れや印刷された本のメリットに重きを置く方からは反論もあるだろうが、あらゆる文字情報の電子化への移行は必然というのが筆者の見立てである。
書店業界のこれから
さて、来たるべきそのような時代に「紙の本を売るお店」、つまり書店がどれほど生き残れるかといえば、かなり厳しいと想像される。と言うよりも、尖った個性を持つ一部の店や体力のある大型店などの例外を除くと、日本の書店業界は既に危機的なレベルにある。
よく言われる数字としては、ここ20年で店舗数が半分になったというもの*1。筆者は日本の某出版社に勤めていた頃、営業とひんぱんに書店回りをしていたが、その経験から言うとお店側とて何もしていないわけではない。コンセプト特化や著者を招いてのイベントによる集客など、あらゆる手立てを尽くした上で、それでもなお縮小を余儀なくされているのが現状なのである。
さて、そのような苦境にある日本の書店ビジネスとは対照的に、お隣の中国ではリアル店舗を構える書店が気勢を上げている。2019年の中国全土における書店数としては約16万店というデータがあり、ソースが中華系ニュースなのである程度割り引いて考えなければならないが、それでも圧倒的な数字であることに変わりはない*2。
中国では電子書籍がまだまだこれからという事情もあるものの、むろん理由はほかにもある*3。
中でも筆者が大きいと考えるのは「SNS映え」を意識したお店作り。それは一体どのような狙いなのか。また日本が学ぶべき点はあるのかといった視点から、ここでは中国の書店ビジネスについて語ってみたい。
自撮り好きの中国人が集まるインパクト系の大型書店

中国の書店といえば、かつては「新華書店」という全国チェーンが代名詞だった。中国各地にありながら品揃えは金太郎飴のごとく同じであり、店に入ると一番目立つ場所に党と政府関係の書籍が並べてある。
当然、いつ行っても客はそう多くなく、店員からもやる気はあまり感じられない。それでも絶対につぶれないのは国営だからで、要は採算を考えなくていい本屋というわけだ。
今回語るのはこういった古いタイプのものではなく、近年増えているやたらと派手な大型店。その多くはショッピングモールや商業エリアにあり、日本の書店からすれば考えられないほどの床面積を使い、書籍だけでなく雑貨なども売り、たいがいはカフェ併設となっている。とにかくスペースが有り余っているのかアート展示や観葉植物展などの催しも盛んで、店内に図書館併設という謎の本屋もあるほど。
そして最大の特徴は、書店そのものがとにかく「映える」ことだ。
本を陳列して売るという本来の目的から逸脱し、見た目で度肝を抜くためとしか思えないような内装の書店も珍しくなく、そういう場所にはSNS用の写真を撮るために多くの若者が訪れる。中国では撮影スポットのことを「打卡点」(ダーカーディェン)と言う。
SNS大好き、自撮り(というか自分自身)はもっと大好きという中国の人々にとって、休日の街歩きや旅行などで「打卡点」巡りは外せない。その需要に狙いを定めているせいか、中国では次々と珍妙な大型書店が生まれているのである。
採算が取れている理由
しかし、ここでひとつ疑問が出てくる。
だだっ広いスペースを使い、新規投資をして書店を立ち上げているのだから、いくら客が集まっても本が売れなければ経営的に厳しいのでは? これはもっともな話で、実際のところ見込み外れで閉店に追い込まれる大型書店もなくはない。しかし、それ以上に多くの書店で採算が取れているのには理由がある。
ひとつはショッピングモールや商業エリア全体の集客効果を考えて、テナント代がかなり割り引かれるケースが多いことだ。日系百貨店の中国法人でフロアのテナント管理を担当している知人の話では、日系デパートではそれほどでもないが、中華系などは「書店は客寄せパンダ」と捉えて大胆な賃料を提示することもあるのだとか。
そしてもうひとつは、本の売り上げに頼り切らないビジネスモデルである。書店にカフェを併設する試みは日本にもあるが、中国の場合は割り切り度合いが全く違う。まず、店によるとはいえ、売り物の本をカフェで立ち読みならぬ座り読みをされようが、「困ります」などと野暮なことを言ったりしない。本に比べて粗利の大きい飲み物で稼げればそれでよしとする潔さがそこにはある。
さらに言えば、中国では書店員にお金をかけない。日本における大型書店の店員さんといえば、下手すれば編集者よりも多くの本を読む人々で、面白い本を知り尽くしているカリスマ書店員すら存在する。それに対して中国の書店では、書籍売り場もカフェの方も、場合によってはファストフードの店員より給料が安い(大都市の書店員でおおよそ4000元=約8万円)*4。
SNS映えで集客を狙い、売り上げは書籍だけに頼らず、ランニングコストを抑える――。さまざまなコンテンツ産業が限られたパイを取り合う中、本来「紙の本」を商品とする中国の書店は、このようなビジネスモデルによって健闘を見せているのである。
言論の自由がない国で栄える書店ビジネスに学べること
では、中国で本屋が増えているからといって、出版産業が栄えているかといえば、そうとばかりも言えないのが現状だ。政府は読書習慣を広げるためにハッパをかけているものの、2021年における成人中国人の年平均読書量は4.76冊と、決して多くない*5。
そもそも、中国では本を発行するに当たって当局の検閲があるため、何でも好きなものを読めるという環境にない。読書にかける時間があるなら、TikTokなどの動画シェアアプリでショートムービーでも見ていたほうが面白いし、お金もかからないというのが多くの若者の本音だろう。
しかし、そんな風潮の中でも読書の楽しみを世に広めるべく、しかもお上におもねらず頑張っている本屋とて、中国には存在する。中国の最高学府・清華大学のほど近く、北京の知識人に愛される知の聖地「万聖書店」。神保町の古書店顔負けといった感じで書籍が並ぶ店内は、SNS映えとは全く無縁の世界でありながら、生粋の本好きたちで常に賑わっている。
当然ここでは入り口そばに党や政府関連の書籍が山積みなどということはない。それどころか店内の一番目立たないところに置かれており、しかも「どういうわけか」1冊だけ、毛沢東がらみの本がフェミニズムコーナーに間借りするかのごとく陳列されている。
おすすめ書籍コーナーで無言の批判
さらに特筆すべきは、店内のおすすめ書籍コーナー。
筆者はここ3年間ほどたびたび店を訪れているが、この棚の品揃えはどんな新刊が出ようが、絶対に変わらない。並べられているのは『1984』をはじめとするジョージ・オーウェル全集、そしてナチスドイツに関する専門書。勘のいい方ならすでにお気づきだろう。
この書店はささやかな抵抗ではあるものの、書籍の陳列方法によって当局に無言の批判を加えているのである。むろん、このような信念の下で経営されている書店は例外中の例外。国営書店は別にして、やはり町中で見かけるのはSNS映えする大型店やカフェ併設の民営チェーン店だ。
鉄の情報情報が敷かれたディストピアの国における事象であり、決して手放しで賞賛すべきことではないと理解しつつも、それでもあえて言いたい。
この国の書店には、間違いなく人がいる。
たとえ写真を撮るのが目的の人や、クーラー目当てにカフェで粘っている人などが含まれるにしても、間違いなく日本よりも書店に活気があるのだ。

筆者はやがて大半の人々が電子書籍に移行する未来を予測しつつも、ふと入った書店でたまたま手にとった一冊との出会いという喜びもまた、理解しているつもりである。ぜひ日本の街の本屋さんには、まだまだ頑張ってもらいたい。
できれば筆者の薄っぺらい未来予測など覆すほど、我が国の書店文化をより豊かなものにしていってほしい。そのために中国の書店から学べる点があるかどうか、自分は書店経営も書店員も経験がないため分からない。
だが、ビジネス全般に言えることとして、中国の人々の柔軟な思考とあくなき探究心は、鑑とすべきものがある――筆者はそう信じている。
*1:Yahooニュース「『街の書店が消えてゆく』…書店をめぐる状況は今、とても深刻だ」
*2:AFPBB News「増え続ける中国の書店 『史上最多』となった理由は」※記事は「東方新報」からの提供
*3:HON.jp「中国電子出版事情――巨大な市場規模、だが電子書籍ビジネスはこれから」

執筆
御堂筋あかり
スポーツ新聞記者、出版社勤務を経て現在は中国にて編集・ライターおよび翻訳業を営む。趣味は中国の戦跡巡り。
※『さくマガ』に掲載の記事内容・情報は執筆時点のものです。
- SHARE


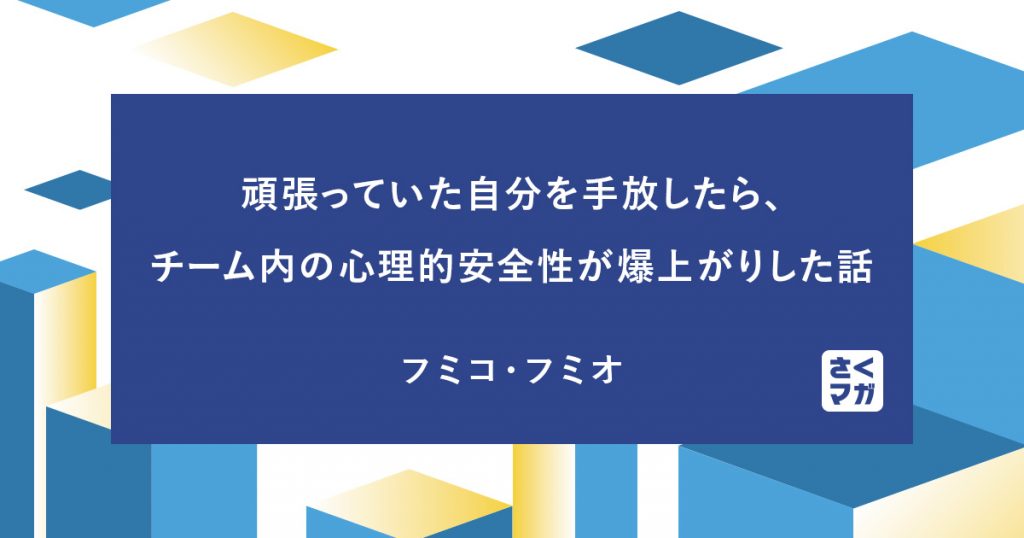

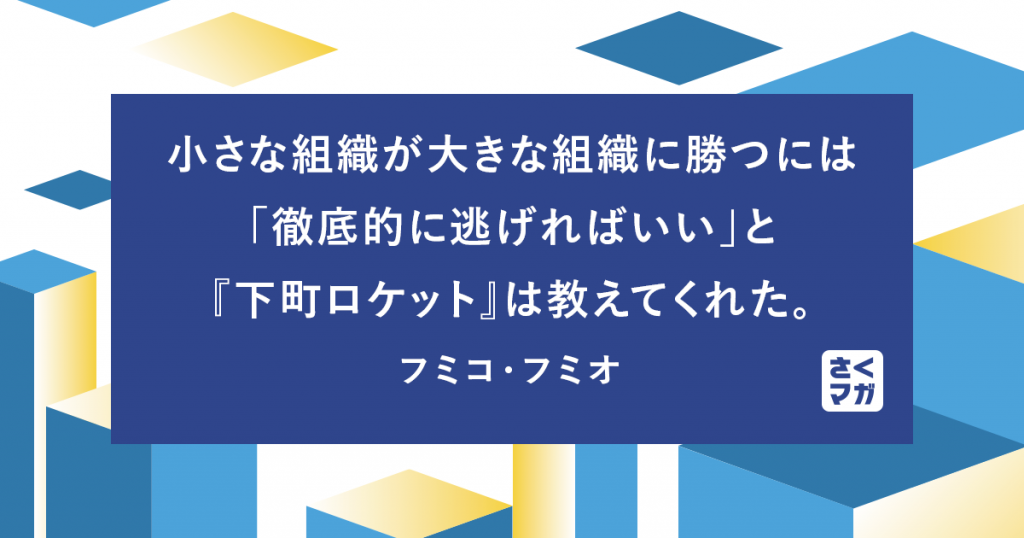
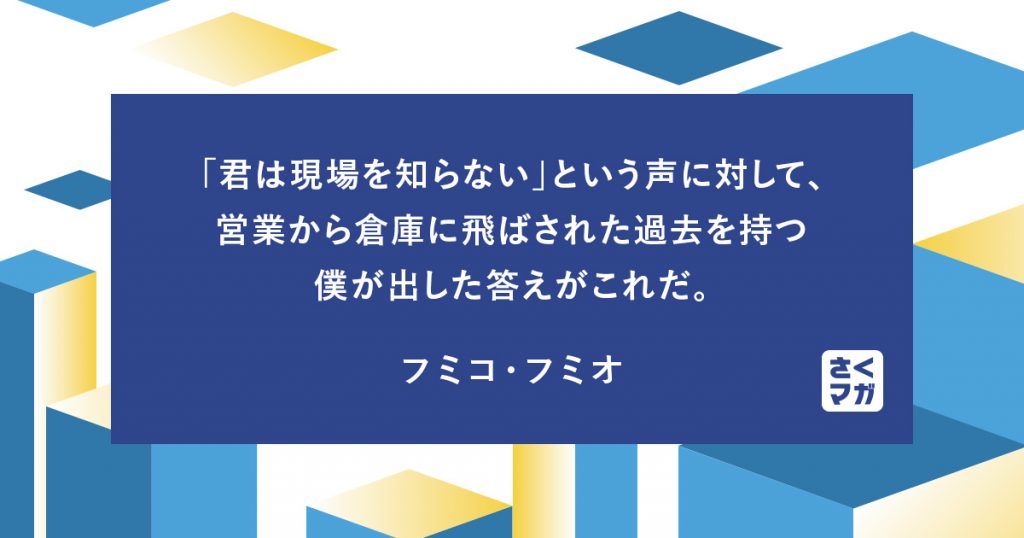
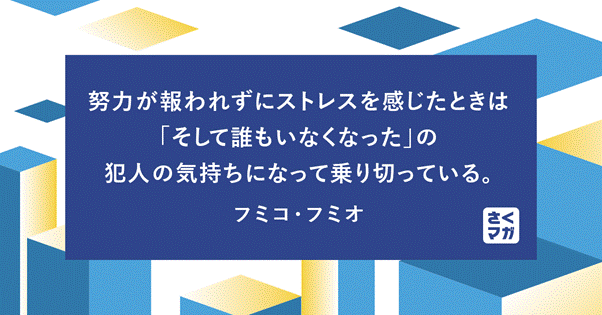
 特集
特集