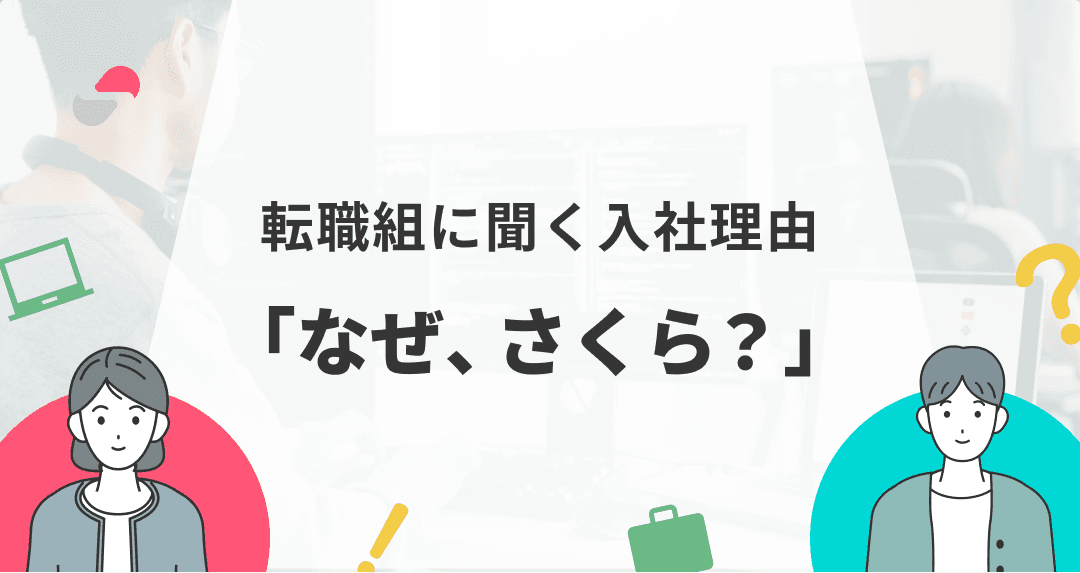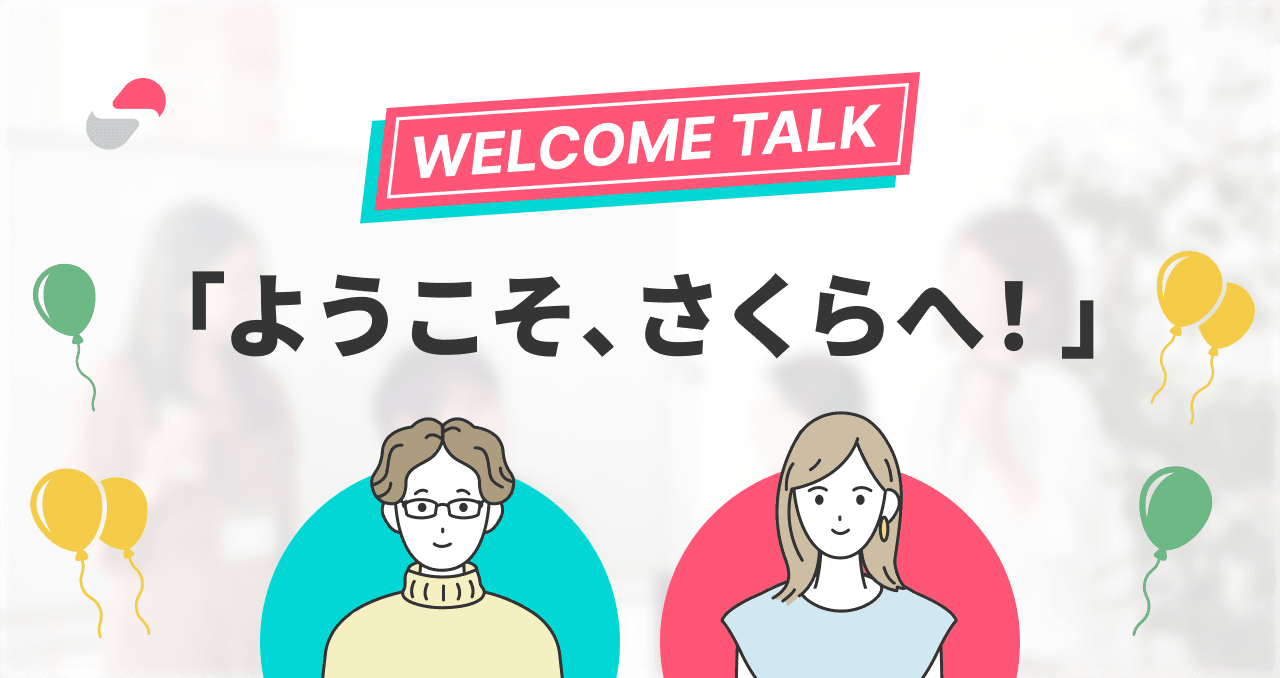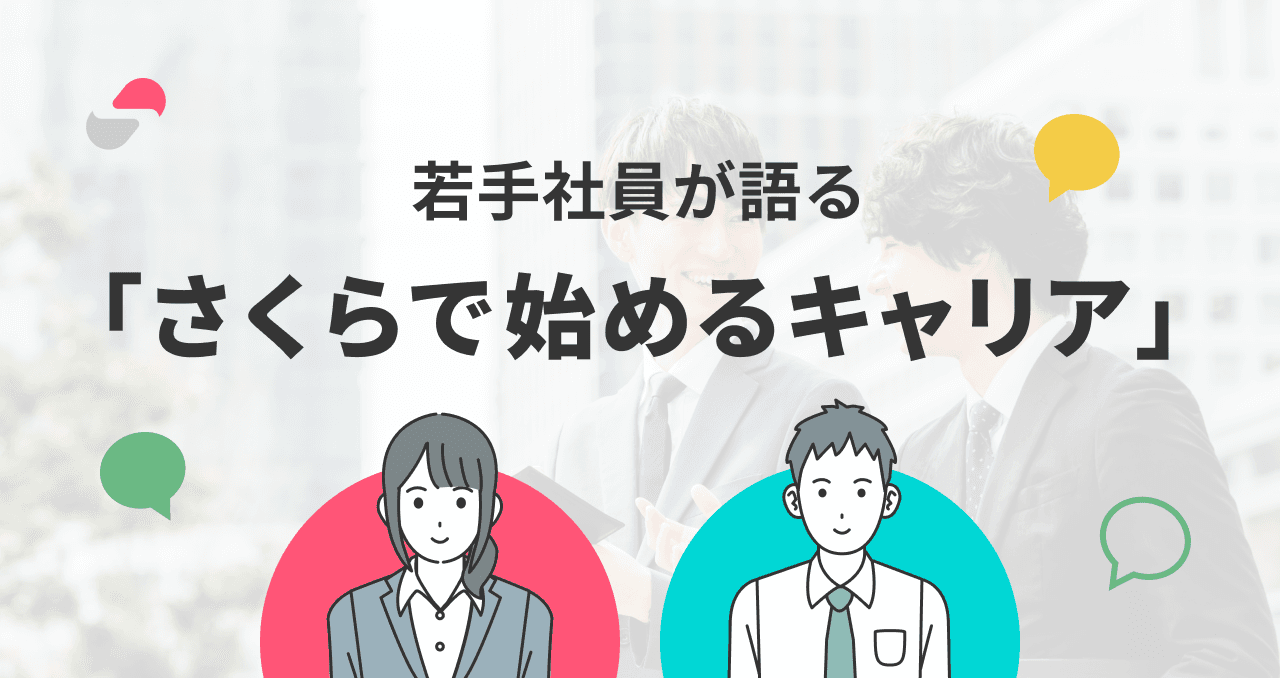10時50分、キスしにきてよ

アラームが鳴る。パソコンに備え付けられたチープなスピーカーが規則的な電子音を鳴らしていた。
「10時50分だ!」
跳ねるように体を起こし、即座にパソコンに向かう。投げ出されたマンガ本がバサリと音を立てるのが聞こえた。
「接続っと」
そう呟いてマウスをクリックする。カチッというクリック音が部屋に響き渡った。
ほどなくしてディスプレイの上部に置かれた小さなモデムが大音量で電子音を鳴らしはじめた。ガーガーとなにやらノイズめいた音を奏でる。規則的なんだか不規則なんだかわからないリズムで、その音はどこか儀式めいたものに思えた。
「やあ、今日はちょっと遅れた?」
モデムの儀式も終わり、インターネットに接続すると、独特の通知音が鳴り響いた。メッセージを受信したことを知らせるものだ。
「あ、うん、ちょっと手間取った。重くなってきたのかな」
カタカタとキーボードを打ち込み即座に返信する。メッセージの相手は「ナナ」というハンドルネームを名乗っていた。地元の人が集まる掲示板で知り合い、インスタントメッセージのIDを交換した相手だ。初めてできたネットの友達で、もう3か月もこうしてやりとりしている。
僕はこのナナにネット友人以上の感情を抱いて意識していた。このネットの世界には若い女性が少ないという事情もあり特段意識していた部分もあるかもしれないが、反応や言葉が妙にかわいいのだ。彼女のIDの文字列を眺めるだけでドキドキする自分がいた。
ただ、ネットでしか知らない相手に心の底からの好意を向けるのもおかしい気がして、それ以上、踏み込めないでいた。むしろ、踏み込もうという考え自体がなかった。こうしてネットだけで繋がってるほうが心地よい気がした。
「そろそろ30円以上を覚悟するときがきたのかも」
「そうかもね」
僕らは10時50分にネットに接続すると示し合わせ、実行していた。その時間には大きな意味があった。それもこれも全て「テレホーダイ」というサービスのためのものだ。
パソコンをインターネットに接続するには、アクセスポイントと呼ばれる場所に電話をかける必要があった。いわゆるダイヤルアップ接続というやつだ。そうなると当然のことながら、そのアクセスポイントまでの電話代がかかってしまうわけだ。
これはネットサーフィンをしている間かかり続け、例えば同じ市内なら通話した時と同じ3分10円ほどの通話代がかかる。ちょっとネットに夢中、なんてことになったら翌月の電話代が大変なことになってしまう状況だ。
「テレホーダイはありがたいけど、こう繋がりにくくなるとね」
ナナのメッセージが表示された。
ネットに繋ぐと電話代がかかる。長いこと繋ぐと膨大になる。それを解決するために登場したのが「テレホーダイ」と呼ばれるサービスだ。
これは、徐々に増えつつあったネットユーザーに向けてNTTが満を持して投入したサービスだった。早い話、月額定額制の通話プランだ。あらかじめ登録した先であれば同じ市内なら月々1800円でかけ放題というもので、とにかく大変ありがたいものだった。
この登録先にプロバイダのアクセスポイントを選んでおけば、別途プロバイダ代はかかるものの、通話料に関しては定額で繋ぎ放題になるわけだ。
ただし、24時間いつでもというわけではなく、利用者の少ない夜間、午後11時から翌朝の午前8時まで限定のサービスだった。そう、たった9時間のシンデレラタイム。この間だけ時間を気にすることなくネットを回遊できる。それは夢のようなサービスだった。
午後11時、シンデレラタイムが到来すると多くの人がたちまちインターネット戦士と変身し、颯爽と電子の海にダイブしていったのだ。もちろん、まるで運命で決められていたかのように、多くの人があっという間に昼夜が逆転、当たり前に廃人が量産されていくこととなった。
「それだけネットを繋ぐ人が増えたってことでしょ」
ナナに返信する。
徐々にインターネット人口が増えつつあるのを感じていた。同時にテレホーダイの認知度も上がっていき、それに比例してアクセスポイントに繋がりにくくなったのだ。おそらく、同じ市内に住む同じプロバイダのインターネット戦士が11時になるのを待って大挙して繋いでいるのだろう。
いくら接続ボタンを押しても、ツーツーと話し中の音声がモデム越しに聞こえることが増えてきたのだ。そうなると、誰かが切断するまで待つ必要があった。下手したら0時を回るくらいまで繋がらない、なんてこともあった。
「だったら、ちょっと早めに繋いじゃおうよ」
そう提案したのはナナだった。テレホタイムに人が殺到するから、ちょっと早めに繋いじゃおう。そんな単純なものだ。この戦法をとるとテレホーダイが適用されるテレホタイムまで通話料がかかってしまうが、そんなもの3分10円くらいだ。繋がらなくてイライラするくらいなら10円払った方がいい。僕たちは10時57分に繋ぐようになった。
作戦の効果は絶大だった。あれだけ苦労したのが嘘みたいに簡単に繋がるようになったのだ。
「別世界みたい(笑)」
「もっとはやく気付くべきだった(爆)」
顔は見えないけど、たぶん、僕らは笑い合っていた。
この10時57分作戦も最初こそは順調だったが、繋がらなくてイライラするのはみんな同じのようで、早めに繋いでおくことが一般的になりつつあった。そう、ユーザー全体が徐々に接続を早める方向にシフトしていき、10時57分でも繋がりにくくなってきたのだ。
そうなると、さらに早めに繋がなければならない。ただし、あまりに早く繋いではけっこうな電話代がかかってしまいテレホーダイの意味がなくなる。かといって遅すぎると回線が塞がってしまい手遅れとなる。このあたりのちょうどいいバランスの探り合いが続いた。
僕らが出した答えは「10時50分」だ。このくらいが混み具合と電話代のバランスが最も良い時間帯だった。50分に接続ボタンを押し、モデムの儀式が終わって繋がると51分くらいになる。そこからテレホタイムまで9分、だいたい30円くらいの電話代だ。微々たるものかもしれないが30日間続くとしたら月に900円だ。これ以上かかるとちょっと厳しくなってくる。
「もうしばらく10時50分のままでいようよ。まだいけるよ」
「そうだね」
月額900円以上は痛い、そんな理由ももちろんあったが、なんだかこの「10時50分」という響きが気に入っていた。テレホタイムの10分前、その微妙なバランスが僕とナナの関係のようで心地よかったのだ。これが40分台になると途端に壊れてしまうような気がしたのだ。いいや、40分台に踏み込むことが、僕らの関係性すらも踏み込ませてしまうような気がしたのだ。はやい話、勇気がなかった。
「じゃ、またあとでね」
そう言葉を交わし、気ままにネットサーフィンを楽しむ。趣味のホームページを見たり、行きつけの掲示板をチェックしたり、ナナ以外のネット友達とも簡単にメッセージを交わす。最近になって一気に増えた友人たちだ。そこにはテレホタイムの世界の交友関係がうっすらと形成されつつあった。
「俺は生涯、テレホタイムに生きる! テレホタイムこそが我が人生、残りはおまけ」
そう豪語するのは極度のネットジャンキー、カワイさんだ。社会人らしいが、テレホタイムの間、ずっと精力的に活動している。主にゲーム関連の掲示板に出入りしているって言っていた。何の仕事をしているかは知らない。
「おばあちゃんにパソコン買ってもらいました」
ことあるごとにおばあちゃんに買ってもらったPC-98を自慢するフロッグマン。その言動からも年下だと思われる。それでも明るくて面白いやつだ。
「恋人ができてもずっとネットやっていると思う」
自称、ネットナンパ師の「混沌の戦士」さんは、いつもネットで知り合った女とお泊りデート、と自慢していた。仕事はしておらず、株の配当で暮らしているらしい。ただ、毎日テレホタイムにネットサーフィンしているので、なにをどうやって連日のお泊りデートを達成しているのか疑問だった。
テレホタイムのこの平原には、現実世界では出会えないような人々がいた。愉快で、変わった面白い人が溢れていた。それは現実での不甲斐なさを忘れさせてくれるような頼もしさがあった。
楽しい面々との会話は恐ろしい速さで時間を経過させていった。気が付くと、窓の外が白々と明るくなってきた、なんて日常茶飯事だった。
「あ、そろそろだね」
「じゃあおやすみ」
「また明日」
「10時50分に」
ナナといつものお決まりの挨拶を交わし、切断する。テレホタイムの終了。朝日が昇ると同時に僕らにとっての夜がきていた。ただただずっと、なにをするでもないこんな日々を生きていた。そう、テレホタイムの住人、僕らはそれ以外の何者でもなかった。永遠とも思える世界がそこにあったのだ。
———————————————
ある日のことだった。いつものようにネットサーフィンに興じているとナナからメッセージが届いた。もう午前4時を回った頃だ。
「ねえ、好きな人、いる?」
それは意外なものだった。キーボードを打つ手が止まった。いままでこんな恋愛的な会話を交わしたことなんてなかった。それが突然、抉るように核心に迫ってきたからだ。何かが急に動き出したような気がした。何かが踏み込んできた気がした。
どう返信するのが正解なのか分からず、キーボードを叩いては消し、叩いては消しを繰り返していると、追撃のようにメッセージが着弾した。
「ねえ、いちど会ってみない?」
その言葉はなんだか恐ろしいものだった。なんというか、ネットの向こうにいる人が本当に実在するんだっていう奇妙な生々しさがあった。
「ナナに、会う……?」
現実感が湧かなかった。そりゃあ、会ってみたい。でも、もしナナにあってお互いに気にいって付き合うことになって、結婚することになったらどうするんだろう。披露宴で二人のなれそめがインターネットで知り合ってなんて言ったら親戚たちはなんて思うだろうか。いいや、そういうのは上手に司会の人が誤魔化してくれるか。
「テレホタイムこそ俺の人生!」
悩んでいるとネットジャンキーカワイさんがメッセージを送ってきた。この人はいつもタイミングが悪い。邪魔だ。それはもうわかったから。無視する。
問題はナナへの返答だ。
同じアクセスポイントに繋ぐ人物であることはわかっている。つまり、同じ市内に住んでいるわけだ。会うこと自体は簡単だろうと思う。でも、なんだかやはり実際に会うことを考えると、ネットの世界が現実に侵食してきたみたいで妙に怖かった。
「どうして?」
そう答えると、今度はナナのメッセージが止まった。打ち込んでは消してと繰り返しているのかもしれない。しばらくして、軽快な電子音と共にメッセージが表示された。
「10時50分だから」
その言葉の意味は分からなかった。もう時計の針は4時を回っている。10時50分なんかじゃない。どう返していいのか分からずにマゴマゴしていると、それを察したのか、追加のメッセージが届いた。
「自分にとっての10時50分が今だからかな。だから今。11時じゃもう繋がらない」
説明されてなお、全く分からなかった。
「うーん」
正直にそう返信する。
僕たちは10時50分にインターネットに繋いでいる。それは11時になると回線が塞がって繋がらなくなるからだ。それと同じ気持ち? どういうことだろう。悩んでいると、今度は長めのメッセージが届いた。
「ちょっと変わっているのかな。むかしから本当に心の底から好きになるともう何も言えないし、何もできなくなっちゃうんだ。それが自分にとっての11時。そうなる前に、10時50分に気持ちを伝えちゃおうって。いつもやってることと同じだよね」
それはなんだか自分が持つ感覚に近い気がした。10時50分という時間に対する考え方、11時からの距離、それらが妙に納得できるものだった。同時に、おそらく僕もナナのことが好きなんだろうと思った。それこそ会ったことない相手だ、確定的なものではなく10時50分くらいの感覚で好きなのかもしれない。
「え、それって……」
「もう、言わせないで」
ここから一気にやり取りのスピードが早まった。
「会うの? 会わないの?」
「会います、会います!」
「じゃあ、10時50分にスーパーヤスデの駐車場で! 遅れないでね!」
「え? 夜に会うの?」
「だって今から寝るでしょ? それならいつもどおり、10時50分でいいじゃん」
「たしかに」
あれよあれよという間に会う約束を交わしてしまった。まだ気持ちの整理がついていないのにだ。気が付くと、そろそろ太陽が昇り始める時間になっていた。カーテンの隙間から侵入してくる朝陽が妙に力強いものに見えた。
「じゃあおやすみ」
「また明日」
「10時50分に」
いつもの挨拶を交わす。でも、その言葉の意味はこれまでとは全く別なものになっていた。
「10時50分、ナナに、会う?」
まだ現実感が湧かない。ナナが実在していて、明日にはそのナナに会う、そして10時50分くらいの感覚でこちらに好意を抱いている。いったい何が起きているのか分からなかった。
「もう寝るでしょ」
朝が来て、いつものように寝るでしょってナナは言ったけど、寝られるわけがない。すっかりと昇りきった太陽をギラギラとした眼で眺めていた。会う、会うだけで終わるのだろうか。もしかしたらキスとかするのかもしれない。ますます眠れなくなった。
ナナのことを思い出していた。
「いきなりは無理だけど地元で遊んだりできる人募集、かわいい女の子がいいな」って掲示板で募集をかけていたんだ。ナナっていうかわいい名前に惹かれてこちらは「かわいい女の子」じゃないのにメールを送ったんだった。どうせネットの世界に女の子は少ない。だから男でも大丈夫だと思ったんだ。
「ねえ、ナナって本名?」
狙い通りだったのかナナからの返信はすぐにやってきた。メッセージを交わすようになってすぐにそう聞いたことがある。かわいい名前だと思ったからだ。
「うーん、本名じゃないけど、まあ本名からとった名前だよ。さすがに本名そのままは怖い」
「同じだ」
このやり取りで一気に親近感を覚えたんだった。さすがにインターネットで本名を名乗るのは怖い、けれども本名に近い名前をハンドルネームにする。10時50分のこともそうだけど、僕とナナは妙に感覚や感じ方が近いように思えた。
「ナナに会うのか」
すっかり高くなり、すでに朝日ではなくなった太陽とともに、いつの間にか眠りについていた。
———————————————
どっぷりと日が暮れていた。
スーパーヤスデの駐車場はもちろん誰もいなかった。スーパー自体はとっくに閉店している。真っ暗闇の中に妙にポップは「スーパーヤスデ」の看板が佇んでいた。
真っ暗な駐車場にポツリと街灯が灯り、規則正しく並ぶ白線を照らしている。隅っこにはちょっとした休憩所があって汚い灰皿と簡易的な椅子が置かれていた。
「10時50分だ」
約束の時間だ。心臓の鼓動が最高潮に達するのを感じた。
腕時計を睨みつける。いつもならパソコンの前で接続ボタンを押している時間だ。でも、ここにはパソコンもなければ、モデム音も聞こえない。インターネットなんて存在しない。整然と並ぶ駐車スペースと街灯があるだけだ。
「騙されたかな」
小さく呟く。時計の針が10時51分になりそうな瞬間だった。ヘッドライトを灯して大きな車が勢いよく駐車場へと侵入してきた。車はそのまま、駐車スペースを無視して突っ切るようにこちらに向かってくる。ヘッドライトが眩しく、右手で視界を遮った。
「ナナだ」
普通に考えて、この時間にこの駐車場にやってくる車はいない。間違いなくナナだ。
パワフルで大きな車で、イメージしていたナナの車とは程遠かった。車は回り込むようにして停車し、運転席側の窓がゆっくり開いていくのが見えた。まだ目が慣れないのか、その人影の正体はよくわからない。別人かとも思ったが、問いかけてみる。
「すいません、ナナさんですか?」
運転席の人影はゆっくりと頷いた。そして、思いもよらない言葉を口にする。
「騙されちゃったかな? てっきり女の子だと思ったんだけど」
男の声だ。やっと目が慣れてきて姿が見えた。男だ。それもまあまあ年上に思える男の姿がそこにあった。そして、男は少しひきつった笑いを見せていた。
「いや、こちらも女の子だと……、なんかすいません」
二人の間に流れる時間が止まるのを感じた。聞こえるのは車のエンジン音と、カーステレオから流れるTRFだけだった。
しばらくした後、運転席の男が大きく笑った。
「あー、もしかして名前で!? すいません、七尾といいます。七尾からとってナナです。もしかして君も?」
「はい、真田といいます」
それを受けて男はさらに大きく笑った。
「だからサナか。てっきりかわいい女の子だと思ったのに」
「なんかすいません」
「いや、こっちもだからお互い様だよ」
僕らは慣れないネットのやり取り、良く知らない相手とのやり取りということで、極度に丁寧な言葉でコミュニケーションをとっていた。だから、お互いの性別を勘違いしていた。
ネットが現実に侵食していた。でも、それは思っていたものとは大きく違っていた。
ナナの野太い笑い声と車のエンジン音、TRFの音楽がスーパーヤスデの駐車場に響き渡っていた。
———————————————
「10時50分だ」
いつものようにネットに接続する。少しだけ接続に手間取ってしまったがいつものように接続できた。けれども、オンラインになってもナナは話しかけてこない。ステータス上はオンラインになっているので、彼女も、いいや、彼も変わらずネットには繋いでいるようだ。ただ、昨日のことがあって気まずいのか、話しかけてこない。こちらも気まずいので話しかけられない。
ナナが話しかけてきたのは、かなり後になってから、もう日も昇ろうかという時間になってからだった。
「昨日のことなんだけど……」
「うん」
「まあ、お互い勘違いしてったことで、許してほしいんだ」
許すもなにも、最初に「女の子募集」を無視したこちらが悪いことだけは確かだ。ただ、現実の人間関係なら性別を勘違いするなんてほとんどありえないが、ネットのみの関係性ゆえに起こった勘違いだ。それはなんだか新しく、次世代に生きているように感じた。
「できればこれからも仲良くしてほしい。君とは友人として仲良くなれそうなんだ」
「もちろんです。お願いします。ナナさん」
すぐに返事をする。なんだか嬉しかった。それから、付け加えるようにしてさらにメッセージを送る。
「友人として本当に仲良くなるちょっと手前ってことですよね」
「そう、私にとっての10時50分。よろしくね、サナちゃん」
「はい、よろしくおねがいします」
「じゃあ、おやすみなさい」
「また明日」
「10時50分に」
「はい」
窓の外を見ると、すっかりと朝日が昇っていた。カーテンの隙間からはいってくる太陽の光は、なんだか力強いものだった。
四人の容疑者
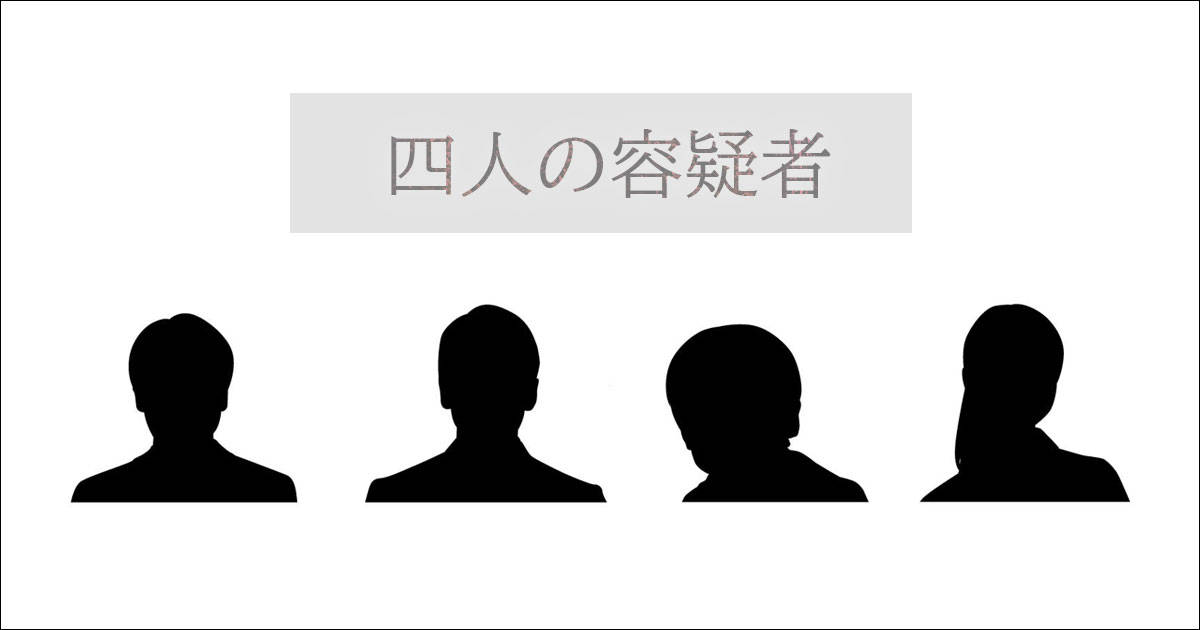
容疑者は四人だ。
この四人の中に、必ず「愚者の楽園」が存在する。それはもう、予感だとか疑惑ではなく歴然たる事実として確信していた。
世の中にはやっていいことと悪いことがある。そして、これは確実に後者に属するだろう。やってはいけないことだ。正義だとかそういった大きなことを言うつもりはないけれども、これは人として許されない行為だろう。
夜、11時00分、パソコンを起動する。PC-98のハードディスクがうなりをあげた。
友達なんていなかった。あのつまらない地獄のような学校には友達と呼べるものは存在していなかった。あえて言うならこのパソコンだけが友達だろう。学習机に燦然と輝くPC-98。モデム内蔵のいかしたヤツだ。
プログラミングの勉強をする、これからはITの時代って説得しておばあちゃんに買ってもらったものだ。もちろん、プログラミングの勉強なんかするわけがない。
ちょっと本を読んでみたけどチンプンカンプンだったし、自分には必要ないものに思えた。ただ、プログラミングの勉強こそはできなかったけど、このパソコンは僕に「居場所」というものを作ってくれた。
もう一度、11時を超えたのを確認して接続ボタンを押す。まるで大ごとのように内蔵モデムが音を奏でた。
「あーやだやだ、インターネットなんてなければよかったのに。おばあちゃんもこんなもの買い与えて!」
母の言葉が思い出される。母はそう言って顔をしかめて見せた。渋る彼女をなんとか説得し、なんとかテレホーダイの申し込みをすることになったが、また金がかかることが面白くないらしい。
先月のことだった、市内の電話だからいいかと調子に乗ってPC-98を駆り、昼も夜も関係なく好き放題にインターネットに繋ぎまくっていたら電話代がシャレにならないことになっていた。とても電話代とは思えない金額だ。母は請求書を見て悲鳴をあげ、納得できないとNTTに殴り込みをかけた。
「ほら、申し込む電話番号をかきな!」
その殴り込みをかけたNTTにはなかなか手練れの猛獣使いがいるようで、母はたしなめられ、意気消沈して帰ってきた。そこで勧められたのが「テレホーダイ」というサービスだ。夜11時以降なら指定した電話番号にかけ放題になるという画期的なサービスだ。
しっかりと確認しながら申込用紙にアクセスポイントの電話番号を記入する。記入して気が付く。もう一つ枠が空いていた。
「任意の電話番号を2つまで指定できる」
申し込み用紙にはそう書かれていた。
「そう言われても指定する場所ないなあ、友達いないし」
いくら考えてもアクセスポイント以外の電話番号が思い浮かばない。別にテレホーダイはインターネット接続専用のサービスというわけではない。ここに市内の普通の電話番号を指定しても夜11時以降は話し放題になる。もしかしたら恋人なんかが長電話するときに使っているかもしれない。
これが社交的なやつだったら友人とか、決してかけることはないけど憧れのあの子の番号とか、そういったものを指定するかもしれないが、あいにく、それらには全く縁がなかった。
迷いに迷い、それでも空欄のまま出すのはもったいないと思い、特にかけることはないだろうけど、自宅以外で唯一覚えている電話番号であるお婆ちゃんの家の電話番号を記入しておいた。
「あんた、学校にもちゃんと行くんだよ! お婆ちゃんも心配してたわよ! それにパソコン買ってもらったお礼の電話はしたの?」
母は乱暴にテレホーダイの申込書を受け取りながら怒りを顕わにした。こちらも慣れたもので、このような母親の怒りも適当に受け流すことができる。
残念ながら、テレホーダイを申し込んだ時点でそれらは逆方向に走り出している。あっという間に昼夜は逆転するだろうし、ネットの世界にどっぷりになるだろう。つまり、輪をかけて不登校になることは分かりきっている。自明の理だ。
けれども、それは口にしないでおいた。まあ、お婆ちゃんへのお礼の電話は機会を見てすればいい。それでも昼夜逆転したら難しいかもしれない。なにせ老人は極度の朝型人間だ。これから夜型になるこちらとは完全にすれ違うだろう。まあ、そのうちやればいい。
接続ボタンを押す。うなりをあげていたモデムだったが、あっという間に意気消沈してしまった。
ツーツーツー。
話し中の音声がパソコンから響き渡る。何度やりなおしても繋がることはなく、やっと繋がったのは0時を回って日付が変わろうかという時だった。
「お、今日からテレホデビュー?」
接続してすぐ、目ざとくメッセージを送ってきたのが「愚者の楽園」を名乗る男だった。PC-98のメモリを増設するときによく分からなくて技術系の掲示板に相談したら親切に色々と教えてくれた人だ。それをきっかけに仲良くしてもらうようになった。
IT系の企業で働くエンジニア、25歳と年上で頼りがいがある。最近ではパソコンだけでなく不登校のことだとか、友達がいないだとか、母と関係が悪いだとか、そういった相談にも乗ってもらっている。
「まいりましたよ、全然つながらなくて」
「あはははは、人増えて来たもんね、ちょっと早めに繋ぐといいよ、電話代ちょっとかかるけど」
「それやると母が怒り狂うんですよ」
「はははははは」
彼は兄貴みたいな存在だった。そのアドバイスには優しさがあって、学校なんて無理に行かなくてもいいよと言ってくれる人だった。ネット上の友人なのでその姿形は分からないが、間違いなく尊敬できる人、のはずだった。そう、あの瞬間までは。
僕は、いま、この「愚者の楽園」に対して一つの疑惑を持っている。
あれは、体育祭のことを相談した時だった。担任に言われて嫌々やっている感を丸出しにした3名のクラスメイトが、夕方になると家までやってきて学校に来るように説得しにくるのだ。せめて体育祭に参加しよう、クラス一丸にならないと意味がないと自分勝手な理屈を振りかざしてくるのだ。それが嫌で嫌で、どうしたら来ないようにできるか「愚者の楽園」に相談した。
彼の提案は、画期的なものだった。
「そんなに嫌なら体育祭に行くと言えばいい、そうしたらもう誘いに来ないよ。それで当日に行かなければいいだけの話」
月並みに「居留守を使えだとか」「学校に行けばいい」「クラス一丸となって」とアドバイスする人はたくさんいたけど、「行くと言って行かなければいい」なんて助言してくれたのは彼だけだった。
「だいたい、運動が苦手なヤツを体育祭に誘うなんてどうかしている。失礼な奴らだ」
彼はそう付け加えた。確かにそうで、この意見には同意しかないが、妙な違和感を覚えた。
「あれ? 確かに俺、運動は苦手だけど、それ教えたことあるっけ?」
不登校ながらもネット上では不甲斐ない部分を見せたくなかったので、運動が苦手だなんて誰にも教えていないはずだった。むしろ、ちょっと得意な感じを装っていたはずだ。それなのに「愚者の楽園」は真実を知っている。
もちろん、不登校で部屋にこもっているイメージとして運動が苦手そうに思われるかもしれないし、もしかしたら何かの拍子に伝えてしまったのかもしれない。けれども、なんだか妙な違和感があったのだ。
その疑惑が確信に変わったのは、テレホーダイを導入してしばらくたった日のことだった。いつものように11時になるのを待ってインターネットに接続するが、接続できたのは11時40分くらいだった。接続してすぐにメッセージが届いた。それは「愚者の楽園」からではなく、別のネット友達からだった。
内容は実にくだらないもので、「サナ」と名乗っていた女の子が、実際には女の子ではなく、単に「真田」という名前の男の子だったというものだ。実際に会いに行った人が真実を知ってしまったらしい。
「サナ」とは何度か会話を交わしたことがあるが、その内容から男であろうことは分かっていた。名前から連想して勝手に盛り上がっていただけで、「サナ」自身には騙す意図なんてなかったんだと思う。
「勝手に女性だと思って盛り上がって失望するなんて自分勝手じゃん」
その後、愚痴っぽく「愚者の楽園」にこぼした。すると彼はこう返してきたのだ。
「なんだかずいぶんと怒っているね。確かに女子っぽい名前で勝手に間違われたりするとイライラするよね。気持ちは分かるけど落ち着いて」
確かに、妙ないら立ちを覚えるのは、僕の本名が「かおる」だからだ。名前だけ見られて女の子と勘違いされることも多いし、それをバカにされることも多かった。それが不登校の原因の一つでもある。ただ、愚者の楽園がそれを知っているような反応なのだ。絶対に伝えるはずのない本名に関する悩みを、なぜ「愚者の楽園」が知っているのか。
「もしかして、知っているやつなのでは?」
彼はあまりにこちらの情報を知りすぎている。たぶん、お互いに存在を知っている人間が正体だ。そうでなくては説明できないことが多すぎる。
そうなると最も怪しいのが、他人に言われて嫌々感を隠そうともせずに誘いにくる3人のクラスメイト、もしくは担任だ。それくらいしか可能性がない。この4人のうちの誰かが「愚者の楽園」で間違いがないだろう。
今日はそれをハッキリさせる必要がある。こうなってくると皆が一斉にネットに繋ぐテレホタイムは好都合だ。なにせ、知人が全員、オンラインになっているわけで「愚者の楽園」の動きを補足しやすい。
しかも、ネットに繋げているということはアクセスポイントに電話をかけているということだ。つまり、接続中に容疑者の家に電話をかけ、話し中であった場合はそいつが「愚者の楽園」である可能性が高い。そう、こうやって調べていくしかない。
一番怪しいのは、やはり担任だろう。彼はなんとかしてこちらの不登校を解消しようとする熱血漢だった。世間的には良い教師なのかもしれないが、こちらとしては面倒くさい教師でしかない。
その彼が、なんとかして不登校を解消しようと、ネット上の友人を演じている可能性がある。仲良くなって頼りがいがある関係を築き、遠回しに学校に行くようにアドバイスするつもりだろう。表では正当な手段で学校に誘い、それを裏で否定して信頼させる。なんとも卑怯なやつだ。
「愚者の楽園」のオンラインを確認し、こちらの接続を切る。電話をかけるにはこちらの回線も使うからだ。すぐにクラス名簿を見て、家の電話から担任の家に電話する。
「プルルルルルルルル」
呼び出し音が鳴った。つまり、担任はインターネットに接続中ではないということなのだろう。すぐに電話を切った。どうせこちらがかけたことなんて分かりっこない。これで担任は容疑者から外れた。
もう一度、接続して「愚者の楽園」がオンラインであることを確認する。
次に怪しいのは、クラスメイトの山川だろう。彼は学級委員をやっている優等生で、委員長として誘いに来ているに過ぎない。彼は本気でこちらを心配しているわけではなく、自分の役職に課せられた義務を果たしているに過ぎない。そこまで本気で学校に来て欲しいと思っているわけではない。
ただ、クソ真面目な山川のことだ。妙な正義感に燃えてネットでも学校に行くように外堀を埋めるつもりなのかもしれない。よくよく考えるとクラスが一丸となるために体育祭に来いというが、委員長としては、いきなりこんな不登校マンが来たって統率が取れなくて困るはずだ。
だから行くと言って行かなければいい、と裏からアドバイスした可能性がある。また、このようにネットを使えそうなクラスメイトと考えるとコイツが最も可能性が高い。
山川の家に電話する。呼び出し音が鳴った。こいつもシロだ。
そうなると、吉岡、こいつが一番怪しくなる。山川と同じく、家まで誘いにくるクラスメイトだが、そもそもこいつが誘いに来ることが理解できない。嫌がらせに近い言動でこちらを不登校に追い込んだ張本人みたいなものだ。
おそらく贖罪だとか、そういった感情でもないだろう。単純に面白がっているのだ。おそらくネットで「愚者の楽園」を名乗って心の支えとなり、どこかでそれを暴露してバカにするつもりだろう。もっとも悪質だ。もしこいつが「愚者の楽園」だったとしたら、怒りを抑えられる自信がない。
もう一度、接続して「愚者の楽園」のオンラインを確認する。それからすぐに切断して吉岡の家に電話する。呼び出し音が鳴った。
そうなると、残った一人、橋本が「愚者の楽園」ということになる。橋本は優等生タイプの女子で、どこか地味だが、黒縁メガネの奥に隠されたクリクリとした瞳が魅力的な人だ。
「そうか、橋本が愚者の楽園か。もしかして、俺のこと本当に心配しているのかな」
それはなんだか悪い気はしなかった。もちろん、正体を隠してネットから近づいてきたことは決して褒められたことではない。ただ、僕を想っての行動だとしたらそれを責めることはできない。彼女なりに最善の策を考えてのことだろう。
もう一度ネットに接続し「愚者の楽園」がオンラインであることを確認する。すぐに切断して橋本に電話をしようとしたその時だった。
「さっきからオンラインになったりオフラインになったりしているけどどうしたの? ネットの調子悪い?」
それは「愚者の楽園」からだった。さっきから接続したり切断したりしてステータスが動きまくっているのを不思議に思ったようだ。相変わらず、橋本はこちらのことをよく見ている。
「うん、ちょっとネットの調子が悪いみたい」
すぐに返事をする。
「そっか、てっきりキャッチホンかと思った(笑)、キャッチホンに加入していると電話かかってきただけでネットの接続が切れちゃうもんね」
「キャッチホン!?」
それは話し中でも、電話がかかってきたよと教えてくれるサービスだった。別料金を払ってそのサービスに加入しておけば、話し中にはならないというやつだ。それがネット接続と重なると、電話がかかってくるだけで接続が切れるという現象を引き起こしていた。
「その場合さ、電話かけた方はどうなるの?」
「そりゃ、呼び出し音が鳴った状態でしょ」
なんてことだろうか。ということは「愚者の楽園」がキャッチホンサービスに入っていた場合、呼び出し音が鳴る。同時に接続は切れるが、こちらも接続を切っているのでそれを確認はできない。こちらが確認する前に接続してしまえば変わらずオンラインだ。つまり、これまで呼び出し音が鳴った3人、いずれも「愚者の楽園」である可能性が消えない。
もうどうしたらいいのか分からなかった。呼び出し音作戦では容疑者を特定することができない。どうにか相手がキャッチホンを使っているか判定できる方法はないか、技術系の掲示板を覗いてみることにした。あの「愚者の楽園」と出会った掲示板だ。
いろいろ書き込みを漁ったが、相手がキャッチホンなのか調べる方法はなさそうだった。こちらが2回線持っていればいけそうだったが、もう1回線増設するとか、これ以上の出費を母が許すはずがない。
ふと思い立って、ログを遡り、過去の書き込みを読んでみた。PC-98のメモリを増設したくて質問し、「同じ容量のメモリを2枚刺して増設する」みたいな解答を「愚者の楽園」からもらった出会いの書き込みだ。
その書き込みを見ているとあることに気が付いた。「愚者の楽園」の名前がリンクになっているのだ。この掲示板は、書き込む際にメールアドレスを入力すると、名前にリンクする形でメールアドレスが表示される。
入力しなくても書き込みできるので入れない人がほとんどだし、ちょっとした遊び心で変なアドレスを入力している人もいた。ただ、「愚者の楽園」は本物っぽい、プロバイダのアドレスを律儀に入力していた。
「このアドレスで検索したら何かわかるんじゃ?」
検索エンジンであるYahoo! JAPANは、厳選して登録されたサイトしか表示されなかったのでinfoseekで検索した。すると、いくつかの書き込みがひっかかった。
「不登校に悩む男の子をどうやって元気づけるか悩んでいます」
「そうですね、居場所を与えてあげるのもいいかもですね」
「パソコンを与えてみようと思います。頼まれていたので」
「PC-98ってやつがゲームができていいんですね」
「孫がメモリの増設をしたいと言っています。PC-98です。注意点はありますか?」
「そうですね、彼の母親にそれとなくテレホーダイを教えておきます」
「体育祭に誘いに来るクラスメイトが心の重荷になっているようです」
「なるほど、そういう考え方もあるんですね。そう伝えておきます」
「こちらの問題なのか、ネットをしているとよく接続が切れます。なるほど、キャッチホンのせいなのですね。原因が分かればいいです。キャッチホンは解約しません。孫から電話がかかってくるかもしれないので」
そこには「愚者の楽園」のメールアドレスを律儀に入力して質問する人と、それにこたえる人のコミュニティができあがっていた。
「そうですね。無理に学校に行く必要ないかもですね。孫の居場所を作ってあげられるように私ももっと勉強します。いつもみなさんありがとうございます」
どこまでも続くと思われる大量の書き込みを、ずっと読んでいた。ずっと。
そして、僕はネットを切断した。
—————————————–
電話をかける。呼び出し音が鳴った。
「もしもし、婆ちゃん、うん、夜遅くにごめん。でも起きてたでしょ?」
「うん、なんとなくね」
「うん、ありがと。パソコンありがと。あと、いろいろありがと」
「うん、大丈夫だよ」
「電話代? 大丈夫。夜11時以降はかけ放題だからさ」
PC-98のモニタは、縦横無尽にパイプが伸びるスクリーンセイバーを表示していた。
テレホみたいな恋をした

ままならない人生に、ままならない恋愛、そんな中で彼女は救いだったのかもしれない。
途中に立ち寄ったコンビニでMISIAの「everything」が流れていた。店を出るとナギサは缶コーヒーを優しく握りしめながら白い息を吐きだし、笑いながら言った。
「なんかさMISIAの曲っていい曲じゃない?」
「だね」
車に乗り込む。ナギサはおまけのようにチョコンと助手席に座った。隣にナギサがいる。それはなんだか不思議な感覚だった。
「さあて、夜景でも見に行くぜ」
どこかギクシャクした雰囲気をごまかすように少しだけ芝居がかったように声を張り上げた。
「ゴーゴー! 灰が峰!」
同じように少し芝居がかったノリを見せるナギサ。無邪気に笑い右拳を突き出す仕草が本当にかわいいと思った。
僕とナギサは数時間前に初めて会った。山奥に佇む空港の到着ゲートではじめてお互いの姿を確認した。もちろん、それまで全く知らない仲だったというわけではなく、それどころか僕たちは恋人関係にあった。実際に出会ったことがないのにだ。
変に思うかもしれないが、インターネットも広く普及した昨今の事情を考えると、そう珍しいことでもなかった。ネットで出会い、付き合い、結婚する、そんな話も特別なエピソードではなくなりつつあった。
「テレホーダイってさ、私たち遠距離恋愛カップルのためにあるサービスだよね」
ナギサはことあるごとにそう言っていた。そう、僕とナギサは住む場所が遠かった。遠距離恋愛だったのだ。それこそ飛行機の距離で、会ったこともない僕たちは付き合っていた。
そのような距離にあるので電話で会話しようと思ったら遠距離通話になる。途方もない電話代だ。けれども、ネットを使えばボイスチャットだってできるし、メッセージのやり取りもできる。そして、テレホーダイを使えば夜11時以降ならネット接続の通話代も定額となる。まさに遠距離恋愛の救世主といえるだろう。
FM放送を流すカーラジオからはSPEEDの曲が流れ、それに続くようにしてCMが始まった。
「時代はブロードバンドへ! Yahoo!BBなら高速接続! 常時接続!」
どうやら祝日の番組枠を買い取って特別番組を放送しているらしく、しきりに「ブロードバンド」「新しいネットの時代!」と連呼していた。
「なんかすごいよね。都会の駅前とかでは無料でモデム配ったりしているんだって。でもね、工事に来てもらわないといけないんだけど、その工事がなかなかこなくて、接続できなくて、開通までの業者との戦いを記録したホームページがあってさ、その内容が面白くて」
ナギサは饒舌に語った。その内容と勢いはいかにもネットの住人といった趣だ。
「ブロードバンドかあ、ADSL接続だっけ? これがこれからの主流になるのかな」
「そうかもね、だって、ずっと繋がっているんでしょ。すごくない? テレホーダイより便利だよね」
一時期はテレホタイムなんていって夢中になっていた時期もあった。11時になるのを待って狂ったように接続し、女性にモテまくっているとか株の配当で暮らしているとか、そういう嘘の設定で楽しんでいたこともあった。
混沌の戦士とかやばいハンドルネームを名乗っていた時期もあったように思う。それでもあの時、少し仲良くやり取りしていたハンドルネーム「愚者の楽園」よりはまともなものだと思う。なんだよ「愚者の楽園」って。
ただ、そんなものでも何年も続けると飽きてくる。夜型の生活もきつくなってくる。仕事も始め、繋ぐことも少なくなってきた。あの時、まわりにいた仲間だって次第に疎遠になっていった。あの時のあの場所は、明確な終わりではなく、グラデーションのようにゆっくりと遠ざかっていった。
11時を狙って繋ぐようなことは少なくなった。特に必要がなくなったからだ。気が向いたらサッと繋いで情報をチェックして切る。時間帯は気にしない。どっぷりとやることなんてなくなってしまい、そこまで電話代も気にならなくなった。それでも、テレホーダイの契約を残していたのは、そこまで深い理由なんてなく「なんとなく」だった。
ただ、ナギサと出会い、付き合うようになって、また真剣にテレホーダイに向きあうようになった。なにせ、遠距離恋愛の救世主だ。ブランクがあったことが嘘のように、11時を狙って繋ぎまくる日々がまた、始まった。
「ブロードバンドってやつになったらずっとやり取りできるわけかあ」
常にネットにつながっている常時接続ともなれば、これまでのように11時を狙う必要がなくなる。それは遠距離恋愛の僕たちにとってとても心強いものだった。いつでもナギサの声が聴け、姿を見ることができるのだ。
「そっかあ、そうなったらテレホーダイ、終わっちゃうんだね」
「まあ、ブロードバンドのほうが便利だもんなあ」
夜景スポットへと進む車は、賑やかな国道を離れ、いつの間にか山道に入っていた。ふと、ナギサが口にした。
「ねえ、テレホーダイの”テレ”ってなんだかわかる?」
ルームミラーを確認しながら答える。
「え、テレフォンの意味じゃないの? テレフォンし放題、だからテレホーダイでしょ」
ナギサはその答えを言い終わる前にさらに質問をかぶせてきた。
「じゃあ、そのテレフォンの”テレ”は?」
「うーん」
考え込む姿がよほど面白かったのか、ナギサはクスリと笑った。
「テレはね「離れた」って意味らしいよ。テレパシーとかもそうだけど、離れて何かするときにつく言葉みたい」
「へえ」
ナギサの雑学講座はまだまだ続く。
「だからね、将来的には離れて家で仕事することが増えてきて”テレワーク”なんて言葉が流行るかもしれないよ」
「えー、仕事が? ないない。仕事はやっぱり会社でしょ。ネットじゃ遅すぎて仕事にならないよ。さぼり放題になっちゃうし、パソコンもネットも重いしね」
「そうかなあ。わかんないよー」
ナギサはまた無邪気に笑い、続けた。
「だからね、テレホーダイって”離れ放題”って意味だと思うんだ。だから遠距離恋愛のためだって言っていたのはそういう意味。これがあるから、ずっと離れていても恋愛ができる。コミュニケーションが取れるから、離れていても恋愛ができる。会わなくても大丈夫、そう思わない?」
「うーん」
少しだけを首をひねる。
ナギサの言うこともわかるが、こちらとしてはこうやって実際に会いたいものだ。だって付き合っているんだもの。今回のことだって、渋るナギサを説得し、飛行機のチケットをとってあげて強引に会うことに漕ぎつけたのだ。「離れ放題」といわれるとなんだか寂しくなってしまう。
「でも、やっぱ実勢に会う機会を増やしたいじゃん」
「うーん」
今度は、ナギサが首をひねって見せた。その反応はなんだか寂しさを感じるものだった。もしかして、実際に会ってみて想像と違ったのかな、幻滅したかなと思ったが、ナギサの笑顔をみているとそうは思えなかった。たぶん幻滅はされていないはず。
車はゆっくりと勾配のある道を上り始めていた。
「それでね、ずいぶん前に、それこそテレホになってちょっとしたくらいかな、足しげく通っていた掲示板に「愚者の楽園」ってちょっとどうかと思うハンドルネームのやつがいたんだけど、明らかに結構なご年配な感じだったのに、数年したら突然に若い感じになっちゃって、中身が変わったのか、みたいに騒然となったことがあったのよ」
「そっかあ、そうだよね。ネットのなかと現実の人格ってやっぱり別だから、中身が入れ替わることもできるよね」
往年のネット話が盛り上がる。ときおりすれ違う対向車のヘッドライトに照らされるナギサの横顔をチラリとみる。その笑顔はやはり眩しかった。
それはなんだか新鮮な感覚で、ネット上のナギサのことが好きで付き合っているのだけど、こうして隣にいる実際のナギサも好きで、間違いなく同じ人間なのだけど、なんだか二人の女性を好きでいるような感覚に近かった。
「さあ、ついた。ここからの夜景が最高なんだよ」
灰が峰は上のほうまで登ってしまうより、中腹あたりから見える夜景のほうが綺麗だった。なんでもない場所に車を停め、外に出て夜景を見下ろす。
「綺麗……」
より冷たくなって空気はナギサの吐息をより白く可視化してくれた。ナギサの瞳の中にもごく小さい夜景があって、それが妙に儚げであり、綺麗でもあった。
「あ、あのさ、その、なんだ、良かったらなんだけど、付き合ってほしい」
夜景を背に告白する。とんでもなくベタベタな告白だ。そして、奇妙なことになってしまった。なにせ僕たちは付き合っている。恋人関係だ。それなのにまた告白してしまったのだ。
「うーん、その返事、待ってもらっていい?」
ナギサはそう言って笑った。
これまた奇妙なことになってしまった。何度もいうが、僕たちはたとえネット上といえども恋人関係にあった。それなのに改めて告白してしまい、改めて返事を待つことになってしまった。
山を降り、市内のビジネスホテルへナギサを送り届け、その日は終わった。次の日は、一緒にお好み焼きを食べたり観光したりしたのち、山奥の空港まで送っていた。荷物検査のゲートで、一度も振り返ることなく進んでいったナギサの後ろ姿が、妙に印象的だった。なんだか、そのまま消えてしまいそうな儚さと寂しさが同居していた。
—————————————————
すれ違いが続いた。
お互いに仕事が忙しくなったこともあり、テレホタイムにネットに接続しても連絡が取れないことが続いた。もちろん、相手がオンラインでなくともメッセージを残すことはできるが、その返事が次の日に届いていないことも多くなった。
かつていたテレホタイムの仲間たちがフェードアウトするように離れていったように、ゆっくりと、ぼんやりしていたら気づかないくらいの速度でナギサが離れつつあるように感じた。あの日の返事も聞けないままだった。
ついつい大量のメッセージを送ってしまいそうになるが、グッとこらえる。そんなことをしては逆効果だ。
「もしかして、テレホーダイだからダメなんじゃないか?」
テレホーダイ、時間限定のネット接続、それだから二人はすれ違うのだろう、こちらが常時接続に切り替えればその勢いでナギサも常時接続に切り替えるだろう。そうすればいつでも連絡を取れる。すれ違うこともない。
「切り替える時期かなあ」
気が付くと、NTTでテレホーダイ廃止の手続きをし、ADSL接続の申し込みをしていた。ADSL開通までの戦い! みたいな誰かが公開していたホームページを読んで少し怖がっていたが、そんなこともなく、あれよあれよと工事日が決まり、開通となった。あの骨肉の争いはなんだったんだと思うほどあっさりとした開通だった。
「これ、もう繋がっているんですか?」
「繋がっていますよ」
工事の人は笑顔で答えた。
ブラウザをダブルクリックする。カチカチっとマウスの音がして、すぐにYahoo!が表示された。
「おお」
そこには接続ボタンも、モデムの儀式もない。速度だって別世界だった。もちろん、時間も制限されない。それは自由という翼だったのかもしれない。
「へへっ、今日からADSLに切り替えたぜ。もう時間を気にしなくていいよ」
オフライン表示だったナギサにメッセージを送る。時間は夜の7時、テレホタイムなんて関係ない時間だ。
テレホタイムを待っても、夜が深い時間になっても、ナギサからの返事はなかった。それどころか次の日も返事はなかった。変わらず、オフライン表示のナギサのIDを眺めるだけだった。
皮肉なことに、ADSL接続にし、常時接続にしたことによって言い訳を失ってしまったのだ。テレホーダイだからすれ違っているという言い訳を失い、常時接続ゆえに返信がないという事実を常に意識しなければならなくなってしまった。
常時接続はとにかく便利で、自由で、理想の楽園かのように考えていたが、思ったほどではなかった。むしろ、苦しさが増したような気がした。
ナギサから返事があったのはその次の日のことだった。常時接続である自分にはもはや関係ないが、テレホタイムに入ってすぐのことだった。
「ごめんね。忙しくて時間とれなくて。そっかあ、テレホーダイやめたんだ」
「うん、もういつでも連絡取れるよ。ナギサもADSLにすればいいよ。あのホームページみたいなことはなくて簡単に開設までいけたよ」
すぐに返事を送る。しかし、返事はかえってこず、ナギサのID表示はオンラインのまま、ピクリとも動かなった。
「うーん、わたしはいいや。テレホーダイのままで」
15分ほどして、そんな返事が届いた。
「いやいや、不便だよ。やってみたらわかるよ。ADSLの便利さやばいから!」
また、返信に時間がかかった。30分ほどして届く。
「やっぱり私は自分の良心に嘘はつけないから伝えるね。たぶん、わたしテレホーダイじゃないと付き合えないんだと思う。ごめんね。だから別れたい」
よく意味が分からなかった。ただ、別れたいということだけが生々しく伝わってきた。とりあえず、すぐに返信を打ち込む。
「え?どういうこと? 別れるってこと俺がテレホーダイやめたから別れるってこと?」
今度はすぐに返事があった。
「ううん、そういうことじゃない。いや、そういうことなのかな。なんていうのかな。わたしね、たぶん遠距離恋愛じゃないとダメなんだと思うの」
ナギサの説明はこうだった。彼女はとても寂しがり屋で嫉妬深い性格だ。そんな性格だから近場で常に会える恋人が合っていると思ったが、そうではないらしい。近くにいる恋人でいつでも会えるからこそ、会いえない時間が不安になるらしい。
連絡がない時間が不安になるらしい。遠距離恋愛だからそうそう会えない、すれ違う、そう納得させないと歯止めがきかなくなってしまう。だから遠距離恋愛じゃないとダメだと言った。
「それと同じでね、テレホーダイくらい制約があって、すれ違いもあって、不便だと、納得できるんだけど、これがいつでも連絡取れるとなると、連絡取れないことに別の理由が必要になるでしょ。別な人を好きになったかもしれない。私のことに飽きたかもしれない。あの時の言葉で嫌われちゃったかもしれない。それを考えはじめたら気が狂いそうになる。不便だからすれ違っているって納得するほうがずっといい」
遠距離恋愛は切なく悲しく、辛いものだと思い込んでいた。誰もが遠距離恋愛を避け、近場で恋をしたいと望むと思い込んでいた。けれども、ナギサにとっては遠距離恋愛こそが心地よい恋愛形態だったらしい。
「だからね、わたしにとってテレホーダイは本当に離れ放題のサービスなの。離れていて、ほどよく納得できるためのサービス。でもそれも終わっちゃったんだね」
すぐに返信をする。
「大丈夫。それならそれでいいから。ADSLも解約してもう一度テレホーダイに戻すからさ。ダメかな?」
すがるようにしてメッセージを送る。
「実際に会ってみて幻滅したわけじゃないよ。すごく楽しかったし、お好み焼きもおいしかった。夜景も綺麗だった。告白もうれしかった。たぶん、現実の私だったらOKしていたと思う。でも、会いに行ったのはネットの私だから。テレホみたいな恋をしたい私だから、ちょっと望みは叶えてあげられないなって思った」
もう何も打てなくなっていた。キーボードの前で固まってしまった。なんて言葉を送っていいのか、送るべきなのかわからなくなっていた。
「たぶん私はね、会えなくて不便な人がいいんだと思う。一年に一度くらい、「会ってみない?」ってメッセージ送って、それでも会わないような、会えないような、そんな人が理想かも。ごめんね、変な女で」
返事を持たず、すぐに次のメッセージが飛んでくる。
「ADSLおめでとうブロードバンドだね。それじゃあ、元気でね」
そう言い残して、彼女はオフライン表示となった。そのまま二度とオンライン表示になることがないであろう彼女のIDを、常時接続で見続けるのだなあとなんとなく感じた。それはやはり残酷なことだと思う。
「わかった。いろいろとありがとう。元気でね」
メッセージを送る。たぶんきっと読まれることはないのだろうメッセージを送った。
————————————
ブラウザを立ち上げる。
「はは、時間を気にする必要なく、常に繋がっているや。速度も速い」
テレホーダイ時代には考えられない速度でYahoo!のトップページが表示される。けれども、それだけだった。その先に進むものがなかった。
ブロードバンド、ADSL、常時接続となり、便利になった。それはいままで柵に囲まれた中で行動していたところで、突如として柵を取り払われたようなものだ。自由だ、どこに行ってもいい、便利だ。けれども、それは同時に「柵の中」という居場所を失ったことを意味するのかもしれない。
もしかしたら、テレホタイムという居場所を失ったのかもしれない。
「何も見るものねえな」
ブラウザを閉じる。それでもパソコンはインターネットに繋がったままだった。彼女のIDもあいかわらずオフライン表示のままだった。
囚われの令和テレホーダイ

5月23日。4月初旬から続いていた緊急事態宣言がそろそろ解除されるという機運の高まりを受けて、長かったテレワーク勤務が終わった。
久々に出勤した店舗はどこか異世界のように感じられた。少し肌寒い事務室、片隅に段ボールが積み上げられ、真ん中に簡易的な机と安っぽい椅子が2つ。見慣れた光景だったはずなのに、それはあまりに殺風景に思えた。
「久々の出勤だっていうのに気が重いよ」
通りがかった同僚と軽口を交わす。確かに、この後にいきなり扱いにくい問題を解決しなくてはならなかった。思えば、自分より年上の部下という存在に戸惑いがあったのかもしれない。普通に業務をこなす上では特に気にもしなかったが、これが注意だとか説教だとか、そういうものが必要になってくると途端にやりにくくなってしまう。
コンコン。
小気味良くドアがノックされる。ドアの中央上部に据え付けられた摺りガラスの小窓には、中年男性と思わしきシルエットが浮かぶ。
「どうぞ」
その言葉を受けて男が部屋へと入ってきた。マスク姿だが、何日間も使いまわしているようで、そのマスクは果たして機能を果たせるのか心配になるほどヨレヨレになっていた。
「どうぞかけてください。あ、ちょっとソーシャルディスタンスで離れましょうか」
「はい」
すっかりと世界は変わった。この小さな机で膝を突き合わせてなんてできない世の中になってしまったのだ。お互いに椅子を机から遠ざけて腰掛ける。男は落ち着かない様子だ。
「本日、河合さんに来ていただいた理由はわかりますか?」
落ち着いて話し始める。男は首を傾げて考え込む素振りを見せた。
「遅刻のことでしょうか」
「確かに遅刻も問題です。売り場からの苦情もきています。でもそれは今に始まったことではないですよね」
「じゃあなんでしょう?」
政府の緊急事態宣言発出を受け、我が店舗も時短営業を余儀なくされた。それにより、緊急のシフト変更が何度もおこなわれ、おまけに正社員はほとんどがテレワーク、そういった状況にあって仕方なく、パート従業員間でシフトの連絡をおこなわせることとなった。通常ならありえないことだが、非常事態宣言下で一刻を争う、ということで仕方がなかった。
「急激なシフト変更、我々正社員はテレワークとやりにくい中でよく店を回していただきました。それには感謝申し上げます。ただ、そのシフト変更の連絡のことで河合さんに苦情がきているんです」
「苦情?」
河合はそんなこと考えもしなかったといった驚いた表情を見せた。
「岡田さんにシフト変更の連絡をしましたよね? LINE通話で」
緊急事態ということで従業員間の連絡はLINEが推奨されており、IDの交換を行っていた。ただ、多くの従業員はメッセージでやり取りしていたが、河合は頑なに通話で連絡してきたようなのだ。その点は岡田さん以外からもいくつか苦情があがっていた。
「ああ、あのババアか。まあ、どうにもこのスマホで文字を打つって慣れなくてね。パソコンなら得意なんだけど」
河合は悪びれることなく言った。
「まあ、通話したこと自体は問題ではありません。いくつか苦情は来ていますが、そこは本質ではありません。こちらもメッセージでとは指定しませんでしたからね。問題はその時間です。どうして真夜中に連絡したんですか?」
パートの岡田さんからは「常識では考えられないような真夜中に通話がかかってくる、気持ち悪い」というもので、けっこうな剣幕だったようだ。
「まあ、次の日のシフトだからね。真夜中でも伝えないといけないわけで」
河合はさも正当性があるかのように反論する。
「いや、それでも夜の7時にはシフトが判明していますよね。すぐに伝えればいいじゃないですか。どうしてわざわざ真夜中に伝えるのかってことです」
その言葉に、河合は黙り込んでしまった。その頭の大きさにしては小さく縮みすぎたマスクでも表情を覆い隠すには十分だった。いま、河合がどんな感情を抱いているのか全く読み取れなかった。
沈黙が続く。
「なにか答えてもらえませんか?」
発言を促すが、河合は答えない。その表情もわからない。相手と対話しているのに相手のことが何もわからない、なんだかこの感覚は久しく忘れていたものに思えた。
「まったく、ネットの相手じゃあるまいし」
つい口にしてしまった。いまや「ネット」と「現実」を区切るような時代じゃない。日常とネットは近づき、融合している。だから「ネットの相手」という言葉が時代錯誤であることは理解している。けれども、この感覚は確実に古い時代に経験したあれに似ているのだ。
「え、主任、そういう感じですか?」
河合はこの言葉に食いついた。
「もしかして、ネットとか古い人ですか?」
「まあ、学生時代にちょっとやったくらいですよ」
河合は敏感に反応し始めた。なんにせよ、この切り口で会話を進められれば会話してもらえる。黙り込まれるよりはましだ。そこから徐々に言い聞かせていけばいいかと、このまま話に乗ることにした。
河合は饒舌だった。やれダイヤルアップ接続がどうとか、テレホーダイがどうとか。そこにはたくさんのネット友達がいて楽しい日々だった、みたいに話し続けた。まるで自分の人生の黄金期といわんばかりの語り口だった。
「テレホーダイかあ、僕もやっていましたね」
マスクの下に隠された河合の素顔が明らかに笑顔になったのが分かった。
「おお、主任もそうとうなツウじゃないですか! あれは画期的なサービスでしたね」
こんなに喋る人だったのか。急に人が変わったみたいになってしまった。
「11時になったら重くなるからちょっと早めに繋いだりして」
「ああ、やっていましたね」
インターネット回顧話が延々と続くかと思われたが、さすがに話しすぎたと感じたのか、河合は黙り、少し呼吸を整える仕草を見せた。そして、なにかを決意するように大きく息を吸い込んで切り出した。
それは何らかの宣言に近かった。
「おれ、いまだにテレホーダイに囚われているんですよ」
ただ、よく意味が分からない言葉だった。
「え、囚われる? どういう意味ですか? もしかして今でもテレホーダイをやっているって意味ですか?」
率直な疑問点をぶつけてしまったが、河合はそれを否定するように首を横に振った。
「さすがに今はやっていません。それにほら、いまはスマホでもなんでも使っていつでもネットできるじゃないですか。そんな時代にダイヤルアップ接続でテレホーダイってナンセンスですよ」
「いや、でもさっき囚われているって言ったじゃないですか」
その言葉を受けて、河合は待っていましたとばかりにまた饒舌に説明し始めた。
「学校って、学校に行くと当たり前に友達がいるんですよね。友達と言わないまでも学校に行けば知っている顔があって、知っている先生がいて、それが当たり前のように次の日も続く。誰も、明日から会えなくなるなんて思わない。それと同じことがテレホーダイにもあったんです。繋げば知っている人がいた」
「それはなんとなくわかります」
経験したことがあるからわかる。テレホーダイは11時から限定のサービスだ。皆が揃ってその時間に繋ぐことである種のコミュニティが形成されている感じがあった。
「学校の場合は、その当たり前が卒業によって終わります。あ、もう明日から当たり前が当たり前じゃなくなるんだ、そう思うはずです。でも、テレホーダイは違った。気づいたらみんないなくなって、その終わりを意識する前に誰もいなくなってしまったんです」
「それでテレホーダイに取りに残されちゃったってことですか?」
その言葉に河合は首を横に振った。
「私の好きな人、いいや尊敬する人かな、まあ、その人もネットで出会った人で実際には会ったことはないんですけど、その人の言葉でね、“自分の良心には嘘はつけない”ってのがあるんです」
「自分の良心?」
「ずっとテレホタイムに生息していると、昼夜が逆転するんですけど、そのテレホタイムの世界が全てみたいになっちゃうんですよ。こんな楽しい世界はない。俺はもうずっとテレホタイムに生きる。常々、そう周りに宣言していまして」
そういえば当時はけっこうそういう人がいたような気がする。昼間は何やっているんだこの人っていう正体不明な人が随分といたものだ。
「その日の宣言をずっと守っているわけですか?」
その問いに、河合は手に握りしめたスマホを凝視しながら答えた。
「でも、もうダイヤルアップなんて時代じゃない。スマホだってあるし、家の回線もADSLになって光ファイバーになりましたよ。テレホーダイに生きたくても生きられない。だからね、せめて意識だけでもテレホーダイに生きようと」
そこまで言われてハッとする。
「だから連絡が夜11時だったんですか?」
「はい。もう、ずっと、ネットは夜11時以降しかやりません。メールもLINEもネットサーフィンも、アマゾンの注文も、ネットフリックスだって11時以降のテレホタイムにしかやりません。この時代にもテレホタイムの世界に生きているんです。まあ、意味なんてないんですけどね」
「だから岡田さんへのLINE通話も……」
「はい、あれ、ネットなんで。11時前はやりません」
河合は少しだけ誇らしげだった。この令和の時代にテレホーダイに取り残された男。それは衝撃的な告白だった。
「あの日、ずっとテレホタイムに生きるって宣言しました。それを実行しているだけです。それが私の良心です」
「あの日の宣言を守っているだけ、と」
問いかけに河合は深く頷いた。
衝撃の告白だった。
ただ、この告白には少しだけ違和感があった。この河合という男、パートを統括する立場からずっと見てきたが、そこまで律義な男ではないのだ。
当時、ずっとテレホにいるわ、なんて宣言するやつはたくさんいた。けれども、ブロードバンドが広がればそちらに移り、光ファイバーが一般的になればそちらを導入している。便利なほうに流れるのが当たり前だ。
もちろん、本当に律義な人がいて、どんな便利なものが流行っても俺はここにいる! なんてこともある。いまだに大昔に流行ったネットゲームをやっている人だっている。ただ、この河合という男、そこまで律義ではないように思う。
「律義にその時の宣言を守っているわけですか?」
もう一度、問いかける。
本当なら、岡田からの苦情を伝え、そういった行為をやめさせるためだけの面談だった。ただ、ここまできたら同じテレホタイムに生きたこの男を救いたい。テレホタイムという呪縛から解き放ちたい。そんな気持ちが生まれていた。そう、おそらくこの男はテレホタイムという幻想に縛られているのだ。
河合は押し黙っていた。おそらく何か別の感情があることを隠している。そんな振る舞いだ。
「言ってください」
さらに言葉をかける。河合は両手を額にあて、考え込むそぶりを見せた。
「おなじテレホタイムに生きたものとして、あなたをテレホーダイの呪縛から救いたいんです」
いつの間にか語気が荒くなっていた。
河合は深いため息をつき、吐き出すように呟いた。
「正当化、なんでしょうね。不甲斐ない自分の正当化、それにテレホーダイを使っていたのだと思います」
マスクの下に隠されたその表情は、なにか覚悟したものに思えた。そしてゆっくりと切り出す。
「主任、今日は何の日だかわかりますか?」
「いやわからない」
特に祝日とかではないと思うが、すぐにスマホを取り出して調べると「キスの日」と表示された。日本映画で初めてキスシーンが登場した「はたちの青春」の封切り日を由来とするらしい。
「キスの日ってでるね」
「そう、あの日もキスの日でした。徐々にテレホタイムに人が減りつつあった年だったと思います。その時、私は一人の女性に夢中でした」
河合は、徐々に活気が減りつつあったテレホタイムにあっても積極的に多くの人と交流していたようだ。その中で一人の女性と出会うこととなった。「アゲインズ」というハンドルネームを名乗る女性だ。
「はじめてでしたね。ネットでね。嘘をついたんです。自分をよく見せようと思って、当時は無職でしたし、今と変わらず太っていたんですけど。バリバリの商社マンで、モデル並みのルックスの写真を拾ってきましてね、昼間は忙しいからテレホタイムくらいしかネットできないから睡眠時間を削ってやっているってね。ショートスリーパーだから2時間しか寝ないって嘘ついていました。やりたい放題でしたね」
どうせ会うことなんかないからとそうやって彼女とやり取りしていると、本当に心の底から彼女のことが好きになってしまったようだ。
「ただまあ、それでもいいかなって。しょせんはネットの世界でのことですし。あの時まではそう思っていました。そう、あの時までは」
河合は遠い目をしていた。
「オッス!」
まるでテレホタイムになるのを待っていたかのようにアゲインズからメッセージが届いた。
「いやー、仕事が忙しくてさ。俺がいないと回らないし大変だよ。会議の連続だしさ」
本当は仕事なんてしていないくせに、それっぽくアピールしておく。それにはテレホタイムはうってつけだった。いつものように続く軽口。こうしてテレホタイムにやり取りする相手は彼女だけになってしまった。
「それにしても人減ったね」
「減ったね」
テレホタイムは閑散としつつあった。ブロードバンドが導入され、常時接続のサービスを導入する人が増えたことが原因だろう。
「ねえ、今日が何の日だか知ってる?」
他愛もない会話が続く中で、突如として彼女が切り出してきた。
「いや、わかんない(笑)。なんかあったっけ? 国民の祝日?←オイッ」
検索するのも面倒で、そう返事をした。
「今日ね、キスの日なんだって」
モニターに表示された「キス」という文字に一瞬、ドキリとした。
「へえ、キスの日なんだ。仕事忙しくてわからなかったわ」
意味不明な返事をしていることからわかるように、確実に動揺していた。そしてこの動揺は彼女から届く追撃のメッセージで最高潮を迎える。
「ねえ、今から会ってみない?」
思わずパソコンの前で叫んでしまった。それだけ衝撃的なセリフだった。同時に複数の考えが頭の中を巡る。それをわかっているのか、彼女の追撃が続いた。
「会ってみよう」
「会ってみたいな」
今日の彼女は何かが違う。こちらに何か恨みでもあるのかと思いたくなるほどメッセージごとにこちらを絶叫させた。
「キスの日だもん、キスしにきてよ」
もう絶叫はなかった。意味不明に立ち上がり、なぜか意味不明にうがいをしにいってしまった。
彼女とキス……?
話していてわかる。彼女は魅力的な女性だ。そんな彼女が誘ってくれている。この誘いに乗らない男がいるだろうか。いや、いない。いくしかない。そこに葛藤はなかった。
早速、身支度を整えるために履き古したジーパンを探し始めたところで、ふと気が付いた。電源の落ちたテレビのブラウン管に自分の姿が映っていた。
「誰が会うっていうんだ?」
彼女に伝えているこちらの特徴は、モデル体型でイケメンでバリバリの商社マンで、それでもってショートスリーパーだ。そんなやつ、どこにも実在しない。いったい誰が彼女に会いに行くというのだろうか。
「ごめん、会えないかな」
涙を流しながらキーボードを打った。
「ありゃりゃ、ダメだったかな? 私は会いたかったんだけどなー」
こちらだって会いたい。けれどもいろいろな意味で会わせる顔がないのだ。
「仕事が忙しいかな? だったら今日じゃなくてもいいよ」
「ちょっとでもいいから会いたいな」
架空の自分をよほど好いてくれているのか、彼女の提案が続いた。その一つひとつが真綿で首を絞めるように心の奥底をギュッと締め付けた。
「ちがうんだ。俺、ずっとテレホの世界にいるって決めるから。だから現実に出ていくことはしないんだ」
彼女が悪いんじゃない。彼女に魅力がないんじゃない。こちらの都合なんだと告げる。
「ずっと?」
「そう、ずっと」
「そっかあ、それがキミの良心なんだね。わかった」
長いことネットをやっていてこれほど悲しいことはなかった。悔しいことはなかった。苦しかった。それでも彼女の提案は続いた。
「でもさ、もしさ、テレホの世界から出る決意ができたら連絡してよ。こっちからもときどきメールしてもいいかな? うん、そうだ、年に1回、キスの日にきくよ、忘れないでね」
「うんわかった」
そう返事をしながら決意をした。彼女のためにも自分はテレホーダイの世界に居続ける。テレホーダイが終わろうとも、ほかに便利なサービスが出ようとも、だれも使わなくなろうとも、心の中でテレホーダイに居続ける。それは彼女への義理立てなのかもしれない。嘘をついたことへの贖罪なのかもしれない。でも、必ず守るべきことだと思った。
「そういう事情があって、ずっと一人でテレホーダイをやり続けているんです」
長い河合の話が終わった。ふと、壁に掛けられた時計を見ると、偶然にも長針がパキンと動く瞬間だった。
「その後もずっとキスの日に彼女からメールがきているんですか? もしかしたら今日もキスの日ですけど、くるんですか?」
河合は首を横に振った。
「いいえ、ここ数年はきていませんね。さすがに。それまではまだ出る気はないってテレホタイムに返信していたんですけど」
数年前まではきていた。もしかしてそこまでずっと待っていたけど、さすがに待てなくなってしまったのだろうか。「ずっと」という言葉が妙に残酷なものに思えた。
「差し出がましいようですが、僕から思ったことを言わせてもらってもよいでしょうか」
その言葉に河合は小さく頷いた。
「まず、この令和の時代に一人でテレホーダイを貫いているという部分ですが、河合さんはそれを良心だとか、律義に宣言を守っているだとか、彼女のためだとか、そういう表現をされますけど、それっておかしくないですか?」
河合は少しだけ首を傾げた。構わず続ける。
「単に、彼女についた嘘がばれるのが怖かっただけですよね。話が違うじゃないかと怒られ、なじられたくなかっただけですよね。それのどこが良心なんですか。どこが律義なんですか。単に怖がっているだけで、それでいてずっと自分と彼女を欺いているだけじゃないですか。テレホーダイのせいにして、勝手にテレホーダイを続けているだけじゃないですか」
「いや、それは……」
「僕もそうだったからわかります。当時、みんなテレホーダイのせいにしていました。廃人になるだとか、昼夜逆転だとか、不登校になっただとか。ぜんぶテレホーダイのせいにしていた。でも、みんなどこかで折り合いをつけてその世界から出てきたんです。どこかで自分のせいだって気づいたんですよ。いまだにテレホーダイのせいにしてウジウジしているのはあなただけですよ」
河合は押し黙ってしまった。
「いい加減に……」
そこまで口にした瞬間だった。小さな机の上に置かれた河合のスマホが振動した。メールの着信を告げるものだった。
「メールですよ。もしかして彼女からじゃないんですか?」
毎年、キスの日にメールを送ってくる彼女。ここ数年はなかったようだが、久々に送ってきた可能性が高い。
「たぶんそうだと思います。ほかにメールがくるようなこともほとんどないですし、キスの日ですし」
スマホは机の上に伏せられている。画面は見えない。
「確認しないんですか?」
河合は首を横に振った。
「メールを見るのもネットですから、夜11時以降じゃないとしません」
その言葉にカッとなり、強く机を叩いてしまった。
「いい加減にしろ。なんでもかんでもテレホのせいにしてるんじゃねえ! 怖がってるだけだろ!」
「もうテレホは終わったんだ! 目を覚ませ!」
「ちゃんと彼女に謝るんだ! すべて打ち明けて、罵倒されてもいい! そこからがスタートだろうか!」
「人と人が分かりあうのにテレホなんて関係ねえんだよ! 出て来いよ、いい加減に!」
「これ以上、彼女を欺くな!」
語気を強める。河合は今までの腑抜けた表情と違い、睨みつけるように視線でこちらを射抜いた。
「テレホは今日で終わり! ちゃんと向き合うんだ! 彼女に謝れ! 河合!」
河合はこちらを睨みつけながらゆっくりとスマホに手を伸ばした。ゆっくりと裏返し、画面を確認する。それは、河合がテレホーダイの呪縛から解かれた瞬間だった。
「それでいい。もうあなたのテレホは終わりました」
河合は何かから解き放たれたかのように、憑き物がおちたように、スマホの画面を見つめていた。
きっと彼女からだ。また彼女が「キスしにきてよ」と送ってきたのだろう。そう思った。
「彼女からでしたか?」
優しく問いかける。
「岡田さんからでした」
真夜中にLINEを送ったことに対して正式に謝罪を求めるメールが岡田さんから届いていた。なかなかの剣幕だとわかる文面だった。
強烈な沈黙が居座っていた。屈強な沈黙が居座っていた。
「ま、まあ、それはそれでちゃんと謝罪しておいてください。もう大丈夫ですよね、テレホは終わったんですから」
「はい。すぐに謝罪のメールを打ちます」
「じゃ、失礼します」
河合が深々と頭を下げる。
「はい、もう大丈夫ですよね」
「はい」
去り際、河合がこちらを振り返って付け加えた。
「そうそう、主任、さっきテレホーダイが終わったみたいに言いましたけど、実はまだ、サービスとしては存在しているんですよ。ちゃんとNTTのサービスの中にあるんです。終わっていないんです」
マスクの下の河合の表情は、不敵に笑っているように思えた。
「そ、そうですか」
河合の背中を見送り、深く息を吐きだす。
スマホを取り出し、メッセージを送る。
「お久しぶりです。お互い忙しくて困りますよね。どうですか七尾さん、たまには飲みませんか?」
すぐに返事がきた。
「お、真田君、元気してた? 飲むのはいいけどさあ、いまはお店やってないでしょ、夜の街は自粛とかで」
「じゃあ、リモート飲み会やりましょう」
「いいね」
「何時にしますか?」
「じゃあ、10時50分でどうかな」
「いいですね」
「10時50分に」
「はい」
ふと見た時計の長針がまたカチリと動く瞬間を目にした。
あとがき
テレホーダイがサービスを開始した1995年の2年後、1997年に出されたロックバンド「シーナ&ロケッツ」の楽曲に「インターネット・キス」というものがあります。この曲になぞらえるわけではないですが、思えば当時のインターネットは「キス」のようなものだったのかもしれません。
甘美であって、どこかワクワクして、それでいて儀式めいていて挨拶的でもあり、祝福のようでもある。親愛的な側面もあったのかもしれません。テレホタイムに繋がった瞬間はまるでインターネットからキスされたかのようでした。
当時のテレホーダイとそのなかで広がっていた世界は、僕らインターネットの子どもたちの礎を築いたといっても過言ではありません。
いまや「インターネット」と世界をくくる時代ではないでしょう。これらは僕らの日常に当たり前のように存在します。当時のインターネットは儀式を伴う異世界転生のようなものでしたが、もはや召喚の必要はなくなり、異世界がこちら側にやってきたボーダレスの時代となったのでしょう。
サッカーは手を使えないから面白い。制限があるからこそ、多くの人を魅了する足技が発達し、その不自由さに立ち向かってゴールを目指すから、プレイしても、観戦しても面白いわけです。
ただ、単純にボールを運んでゴールに運ぶだけなら手を使ったり、タクシーを使った方がずいぶんと効率的なわけですが、それらを不便に制限するからこそ、ドラマやストーリーが生まれるわけです。
テレホーダイのあの当時も、いまから考えるとずいぶんと制限があったように思います。夜中しかできない、重くてまともに繋がらない、やりとりしている相手はよくわからない怪しい人、画像のダウンロードに30分かかる、数え上げればきりがありません。
けれども、僕らは精いっぱい、その制限の中で工夫して楽しんでいました。10時50分に繋いでいたのも、そんな工夫の一つでした。そして、当時の僕らは、それが制限だと思わず、とんでもない自由の大平原だと感動していたのです。
インターネットが日常と融和した現代、僕らはその便利さを享受していますが、これからさらに発展した先の世界から思い返すと、ずいぶんと制限のある中で楽しんでやがったんだな、と思い返されるのかもしれません。
これからも、これまでも、そしていまも、僕らは制限を楽しむべきです。
奇しくも、この世界は別の軸で予想外に不便なこととなってしまいました。きっと制限だらけでうんざりするでしょう。けれども、それを嘆くのではなく、そこで生じる工夫やイノベーションを楽しむべきなのかもしれません。
テレホーダイとは、そんなことを感じさせてくれるサービスでした。
おそらく利用者はかなり少なくなっていると思いますが、今なお続くテレホーダイというサービス。もしかしたら今でも、僕らがひょっこり迷い込んでくるのを、親愛をもって待っているのかもしれません。
10時50分、キスしにきてよ、と。
おわり
≫ インターネットを支える。さくらインターネット お役立ち資料ダウンロードページ




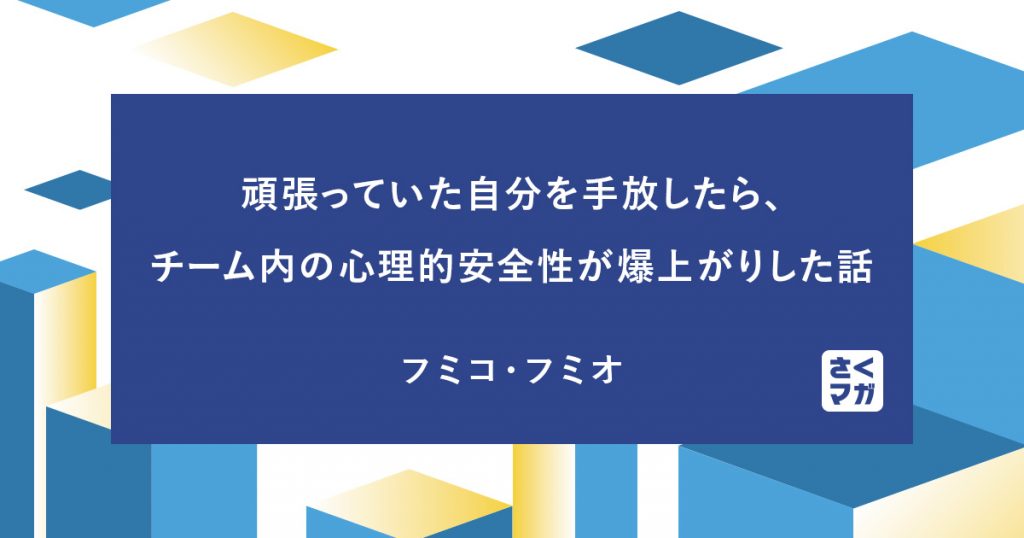

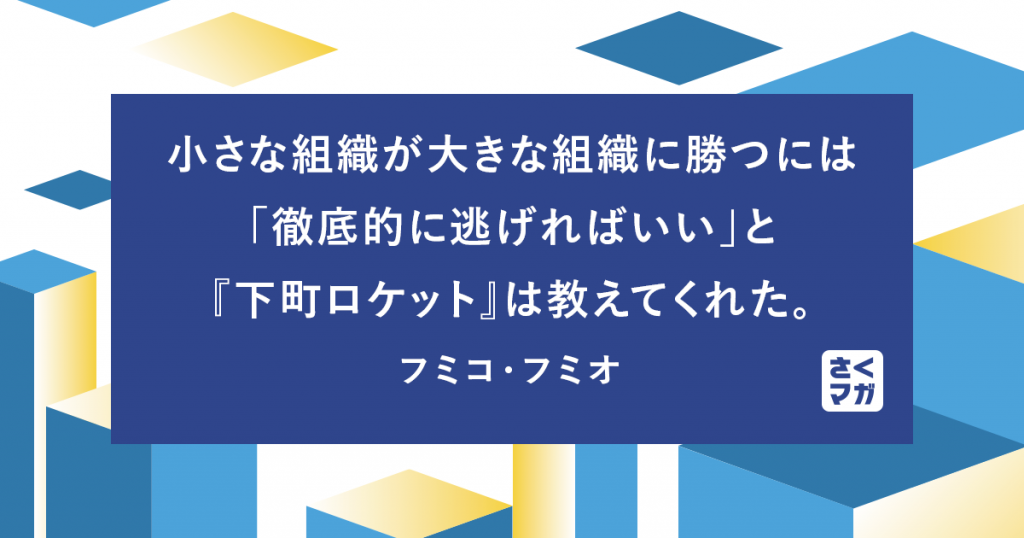
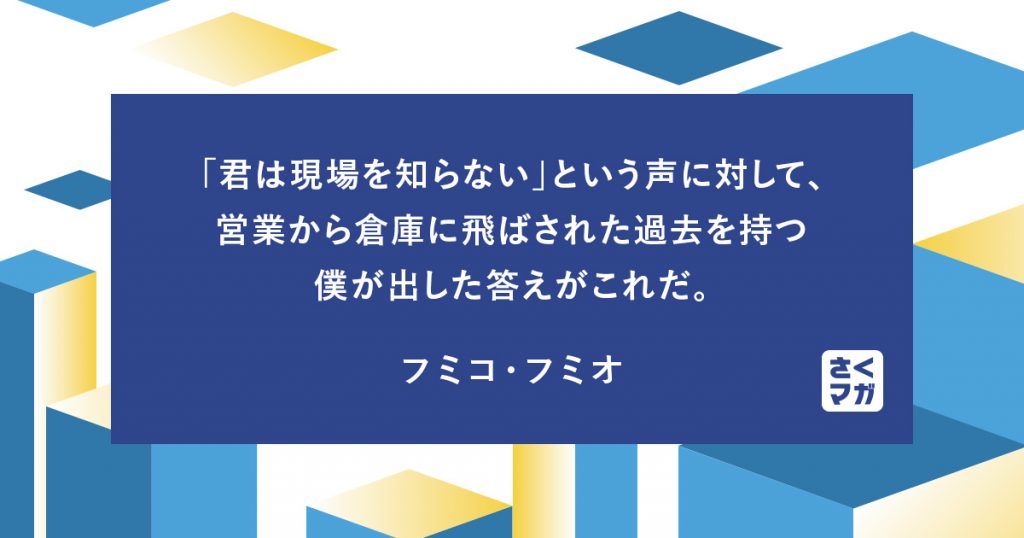
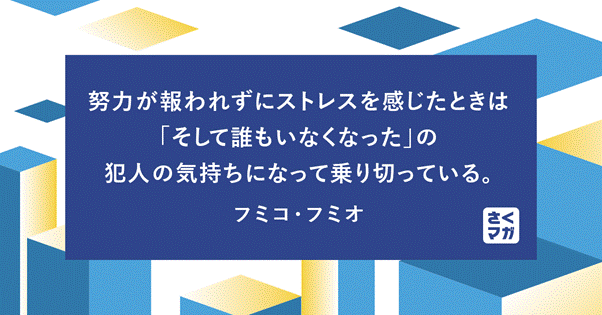
 特集
特集